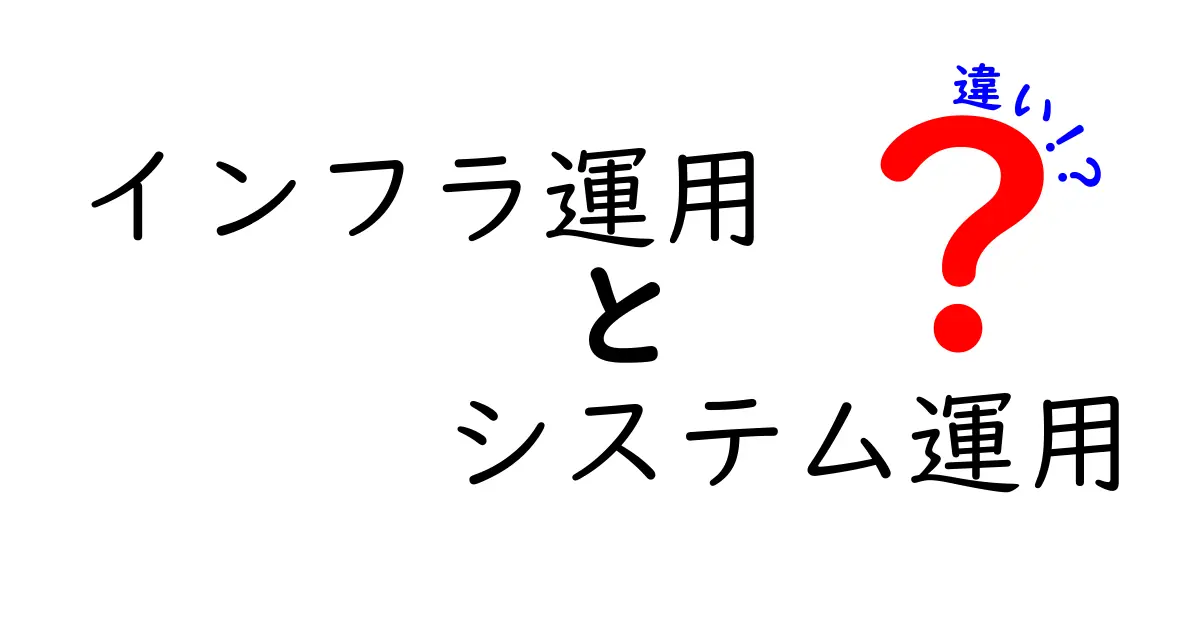

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:インフラ運用とシステム運用の基本概念
インフラ運用とシステム運用は、似ているようで目的や対象が異なる仕事です。「インフラ運用」は基盤となる設備やネットワークの安定運用を担い、「システム運用」はアプリケーションが正しく動くようにサポートする役割です。具体的には、サーバーやネットワーク機器の監視・保守・容量管理・障害対応といった日々の運用を指します。インフラ運用は物理的・仮想的な構成要素、ネットワークトポロジー、OSやミドルウェアの設定を含みます。一方、システム運用はアプリケーションのデプロイ、設定管理、ログ分析、リリースの品質保証、ユーザーからの問い合わせ対応までを含みます。現場では、これら二つの領域が重なる場面が多く、効率的な運用を目指すには両方の視点を持つことが重要です。
たとえば、Webサイトを運用する企業では、障害が起きた時の切り分けや、 変更手順の標準化、監視アラートの適切な閾値設定、バックアップの整備などが挙げられます。これらは単に機器を直すだけでなく、システム全体の信頼性を高め、利用者体験を守るための重要な作業です。
この入門部では、まず「何を運用するのか」を整理し、次に「どう動かすのか」という実務の感覚をつかむことを目指します。
具体的な違いのポイント
インフラ運用とシステム運用の違いを理解するには、実務上のポイントを丁寧に分解するのが効果的です。対象のスコープが第一の差で、インフラ運用は「基盤となる機器・環境そのもの」を対象にします。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、仮想化やクラウドの設定、OS・ミドルウェアの基本動作などが含まれ、ここだけを安定させれば多くのアプリは動作しますが、アプリの挙動そのものは別の運用領域の課題になることも多いです。これに対してシステム運用は「アプリケーションが正しく動く状態を保つ」ことを最優先にします。設定ファイルの管理、デプロイ手順、ログの収集・分析、エラーの原因追及、パフォーマンスの最適化、リリース管理、ユーザー対応といった活動が中心です。
つまり、インフラ運用は土台づくり、システム運用は機能の安定と改善という二つの役割が並行して走っている状態です。現場ではこの二つを別々に見ると穴が空くことがあるため、協調と連携が最も大切なポイントになります。
実務での役割と職種の違い
現場では、インフラ運用とシステム運用の担い手は異なることが多いですが、実際には複数の職種が関与します。インフラ運用担当者はネットワークの設計・監視・容量管理・バックアップ戦略・災害復旧計画などを中心に担当します。クラウドサービスの活用や自動化ツールの導入、障害発生時のエスカレーション対応などを日常の業務として行います。
一方、システム運用担当者はアプリケーションのデプロイ作業、環境の構築・設定の標準化、アプリの稼働監視、ログの傾向分析、パフォーマンスのボトルネック解消、リリースの品質保証といった業務を担います。最近は、双方の境界が曖昧になる場面が増えており、DevOps的な考え方のもと、共通の自動化基盤を使って協力するケースが多く見られます。
この変化は組織の成熟度にも影響します。自動化と監視の統合、運用ドキュメントの整備、SLAやSLOの設定と共有、定常的な見直し会議などを通じ、ミスを減らし、迅速な対応を実現します。
最終的には、チーム全体で運用知識を共有する文化が生まれ、誰でも標準手順に従って対応できる状態が望ましいです。
表で見る比較
以下の表は、インフラ運用とシステム運用の主要な違いを一目で把握するための比較表です。細かな差異は組織やプロジェクトごとに異なりますが、全体像を掴むのに役立ちます。
ポイントを押さえておくと、教育・新人育成・評価の際にも伝えやすいです。
まとめと実務のヒント
この違いを理解すると、運用の改善ポイントが見つけやすくなります。まずは現状の監視指標を見直し、不可欠な閾値を設定します。次に、標準手順の文書化とデプロイ手順の自動化を進めると、人為的ミスを減らせます。最後に、コミュニケーションと共有の文化を育て、異なる担当者同士が協力して「何をどう改善するか」を定期的に話し合う場を設けると、組織全体の信頼性が高まります。
友人と雑談風に、監視の話を深掘りします。私「監視って、ただアラートが鳴るかどうかだけじゃないんだよね」。友人「え、どういうこと?」私「監視には3つのレイヤーがある。まず基礎的な生存確認、次にパフォーマンスの傾向分析、そして不可欠な変更が起きた場合の自動対応だ。たとえば夜中にCPUが高いとき、ただ叱るだけでなく、原因を探し、再起動だけでなく設定の改善まで踏み込む。さらに人手が足りないときには自動化が救世主になる。結局、監視は“異常を伝えるだけ”ではなく、“予測と予防”を可能にする道具で、運用の品質を大きく押し上げるんだよ。
前の記事: « システム運用と保守の違いを徹底解説!現場で役立つ説明と実務のコツ





















