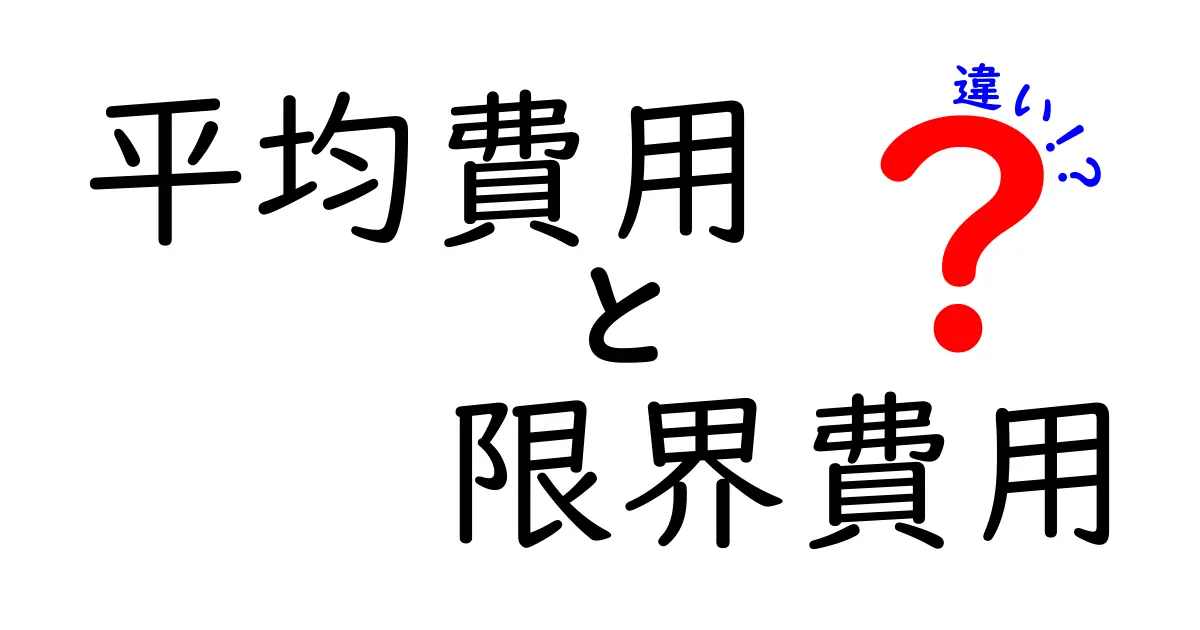

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
平均費用と限界費用の違いを理解するための基礎
まずは言葉の意味を整理します。総費用TCは「その商品を作るのにかかった全てのお金」です。これには、工場の家賃や機械の減価償却など、数量が増えても同じ金額がかかる 固定費と、生産量が増えると増える 変動費 が含まれます。総費用は TC = FC + VC という形で表せます。次に 平均費用ACです。ACは「1個あたりの費用」を示し、式は AC = TC / q となります。ここで q は生産量、つまり作った商品の個数です。ACの見方を簡単に言うと、1つあたりの費用がどう変わるかの目安です。
固定費が大きく影響する初期の段階では、1個あたりの費用が高くなることが多いですが、生産数を増やすと固定費の影響が薄まり、ACは下がりやすくなることが多いです。ところが、変動費の増え方が急になるとACは再び上がることもあります。こうした性質を理解することは、学校の課題だけでなく、実際のビジネスの意思決定にも役立ちます。
ここでのポイントを整理します。
・ACは総費用を生産量で割った数値で、1つあたりの平均コストを教えてくれます。
・固定費はqが大きくなるほど1個あたりの影響が小さくなる。
・変動費の伸び方次第でACは下がり続けるのか、それとも上がるのかが決まる。
・実務では、価格を決めるとき「1単位を作るのにいくらか」が大切な指標になります。
さらに分かりやすく整理すると、
・固定費の影響が大きいときはACが高くなる、
・大量生産で固定費の割合が小さくなるとACは下がりやすい、
・変動費が急に増えるとACは上昇する。この3つのポイントを覚えておくと、価格設定や生産計画を立てるときに役立ちます。
実務で使われる基本的な式と考え方
実務では、ACとMCの関係を使って最適な生産量を探します。ACはTCをqで割ったもの、MCは追加の1単位を作るときの追加費用と言い換えられます。以下のような基本的な考え方があります。
1) 生産量を増やしてもACが下がるときは、生産を増やすほど効率が上がる可能性がある。
2) MCが価格より低いときは、追加生産は利益を増やす方向に働く。
3) MCが価格を超えるときは、追加生産はコストを押し上げ、利益を減らす。
このような考え方は、学校の課題だけでなく、実際のビジネスでの意思決定にも直結します。
実例で見る違い
ここでは、固定費を100、変動費を1単位あたり50と仮定して、総費用 TC = 100 + 50q、平均費用 AC = TC/q、限界費用 MC = ΔTC/Δq を使って計算してみます。これにより、ACとMCがどのように変化するかが見やすくなります。以下の表は、数量 q が1から5のときの値を示しています。表を見ながら、ACが下がるタイミングとMCの高さがどう関係するかを実感してください。
この表から読み取れるのは、ACが下がっているときは生産を増やしても損にはならない可能性が高いという点です。MCが一定であれば、価格がそのMCより高い場合には追加生産が利益を押し上げ、低い場合には控えたほうがよいと判断できます。現実のビジネスでは、MCと価格、時にはMRを比較して最適な生産量を決めることがよく行われます。さらに、長期的にはMCが変動することもあり、在庫や需要の変化に応じて最適解は変わります。
友達と学校帰りにカフェで話していたとき、平均費用と限界費用の話題になりました。友達は『1個増えるときのコストってどう変わるの?』と尋ねてきたので、私は写真のようなイメージで説明しました。まず固定費は見た目には大きな数字でも、量を増やすと1個あたりの値が小さくなる“スケールメリット”の話。次に限界費用は“次の1個を作るために追加でいくらかかるか”を教えてくれる指標だと伝えました。最後に、そのMCと市場の価格を比べると、どれくらい生産を増やすべきかの判断ができる、という結論に落としました。以上を友達と軽い雑談の形で共感しながら深掘りするのが、経済の基本的な考え方を身につけるコツだと感じました。
前の記事: « 3C分析とSTP分析の違いを徹底解説|初心者にもわかる比較ガイド





















