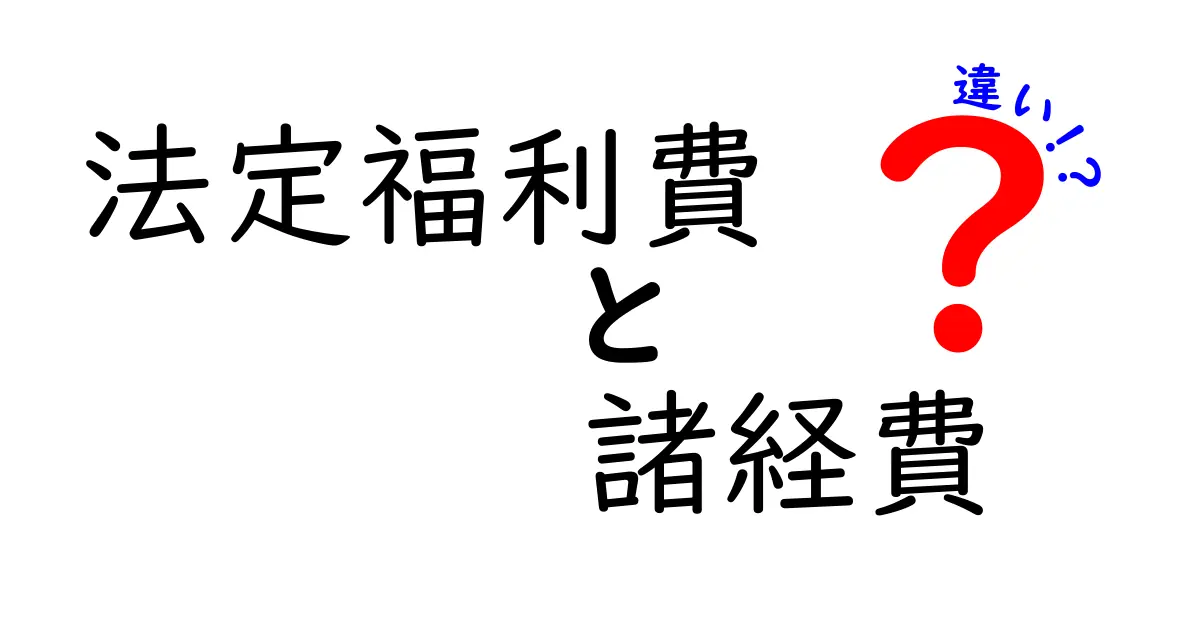

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
会社の会計や経理の話を聞くと、「法定福利費」や「諸経費」という言葉が出てくることがあります。
特に、これから社会に出る人や、会社の仕組みを知りたい人にとっては、何がどう違うのか気になりますよね。
この記事では、この二つの言葉の違いや意味をわかりやすく解説します。
中学生の皆さんにも理解しやすいように、やさしい表現でお伝えしていきます。
法定福利費とは何か?
法定福利費とは、会社が従業員(社員やアルバイトの人たち)に支払うお金のうち、法律で決まっている社会保険や労働保険などの費用のことを言います。
これには、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などが含まれ、これらは会社と従業員が半分ずつ負担する仕組みになっています。
会社は、社員の給料に上乗せしてこれらの保険料を支払う必要があり、この部分が「法定福利費」として計上されます。
中学校の家庭科や社会の授業で、保険や年金の話を聞いたことがあるかもしれませんが、法定福利費は会社が社会のルールに従って払う義務のある費用です。
諸経費とは何か?
諸経費具体的には、交通費、通信費、事務用品の購入費、接待費、光熱費など、仕事をする上で直接関係する多くの費用が含まれます。
つまり、会社の日常的な活動にかかる経費であり、必ず支払わなければいけないものもありますが、法定福利費のように法律で支払いが定められているわけではありません。
会社の経理担当者は、これらの費用を管理し、いくら使ったのかを記録しています。
簡単に言うと、諸経費は「会社が仕事をするために使ういろいろなお金」のことです。
法定福利費と諸経費の違い
ここで、法定福利費と諸経費の違いをまとめてみます。
| ポイント | 法定福利費 | 諸経費 |
|---|---|---|
| 意味 | 法律で定められている社会保険などの会社負担費用 | 会社が事業のために使うさまざまな経費 |
| 内容 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など | 交通費、通信費、接待費、光熱費、事務用品費など |
| 法律の義務 | あり(必ず支払う必要がある) | なし(会社の必要に応じて支払う) |
| 会計上の扱い | 人件費に付随する費用として計上される | 費用全般に分類される |
このように、法定福利費は「社員に関わる法律で決まっている費用」であり、諸経費は「会社が普段の仕事をするために使ういろいろなお金」という違いがあります。
まとめ
法定福利費も諸経費も、どちらも会社の大切な費用ですが、
法定福利費は法律で支払いが義務付けられている社会保険の負担分、
諸経費は会社が仕事を行う際に必要になる、さまざまな支出という点で違いがあります。
会社の会計や経理を理解する時に、この二つの違いをきちんと知っておくと役立ちます。
今回の記事が、少しでも皆さんの学びの助けになれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「法定福利費」という言葉を聞くと、堅苦しく感じるかもしれませんが、実は会社と社会が従業員を大切にするための仕組みの一つです。例えば、健康保険や年金の一部を会社が負担することで、社員は安心して働けます。つまり、法定福利費は会社が社会のルールを守って社員をサポートする大切なお金。会計の中でも「義務的に払う費用」なので、会社の財政状態を見るときにも注目されることがあります。こんな背景を知ると、経理や社会保険が身近に感じられるかもしれませんね。
次の記事: 労働保険料と雇用保険料の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















