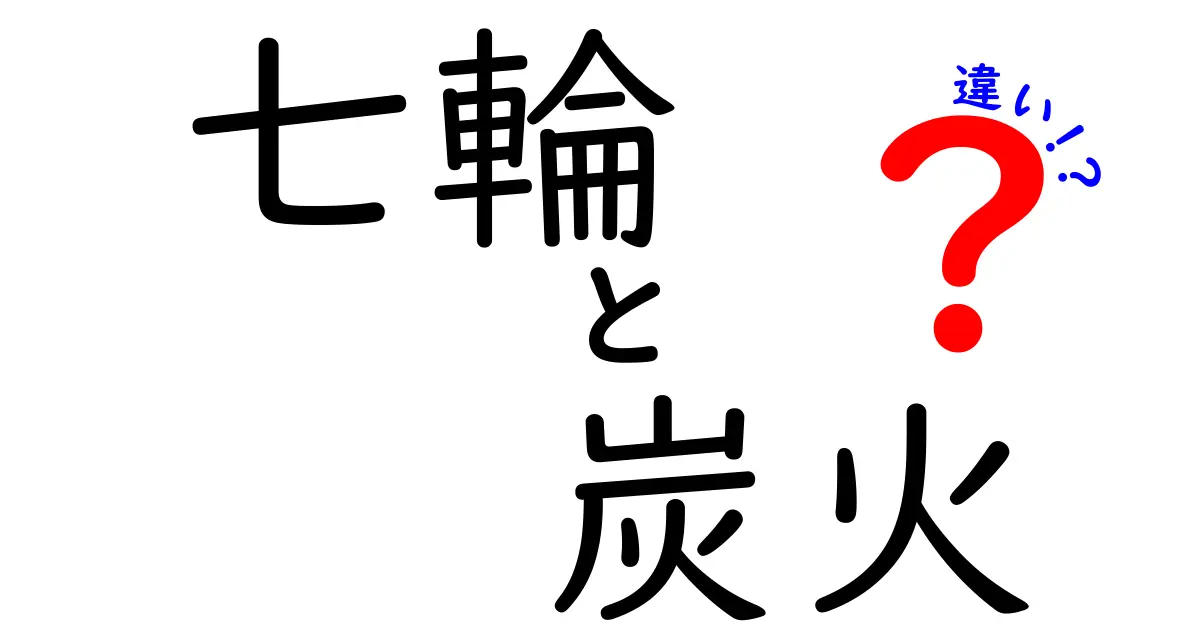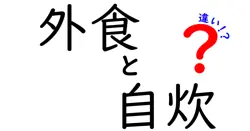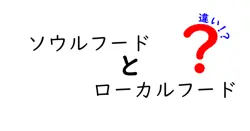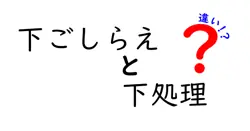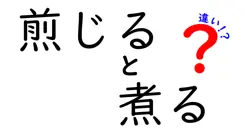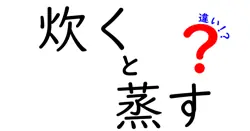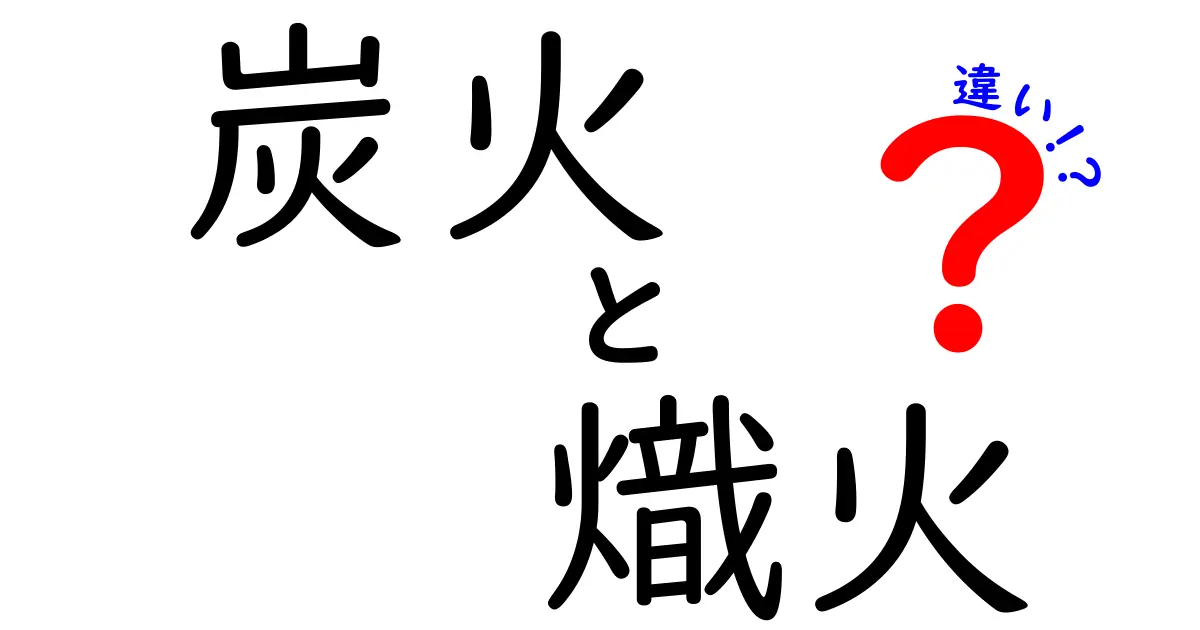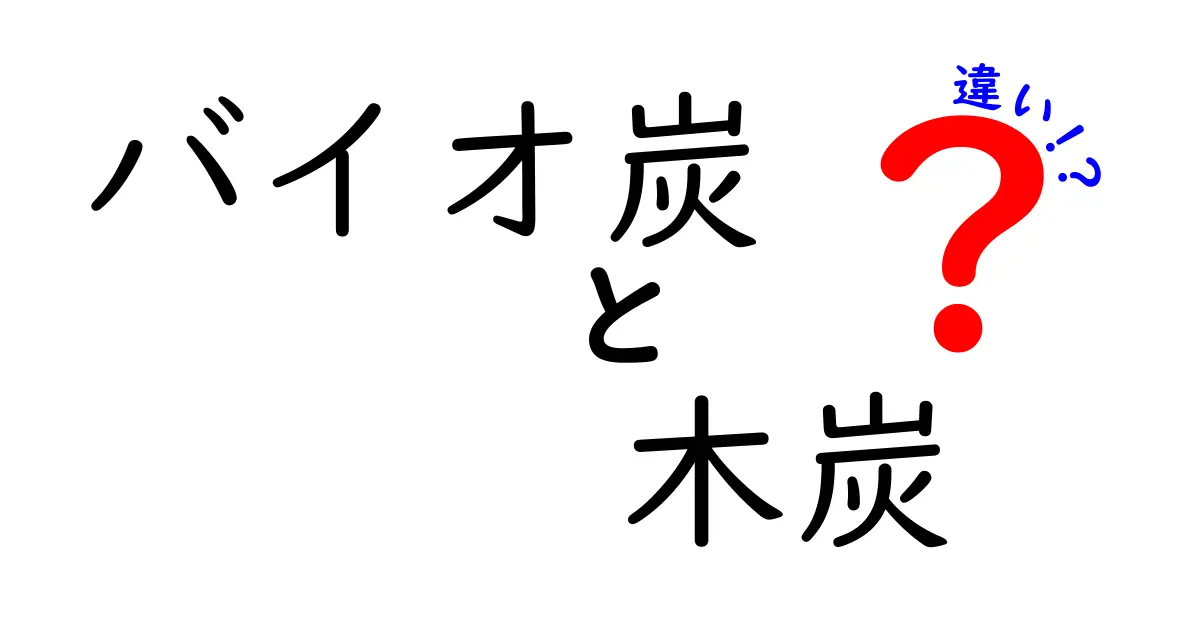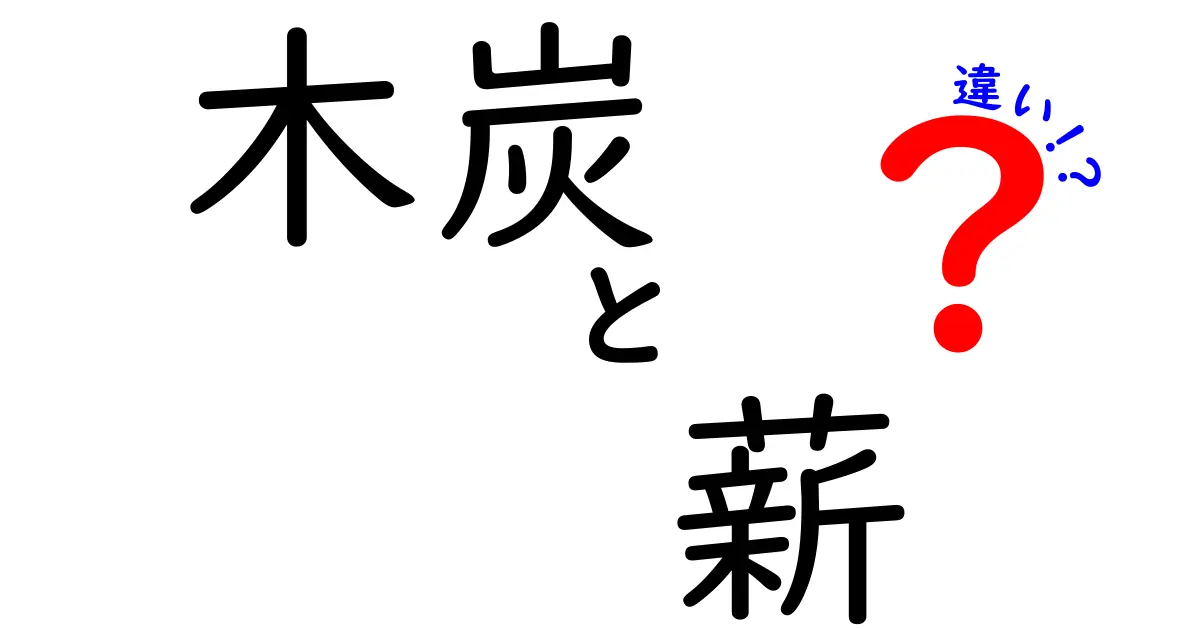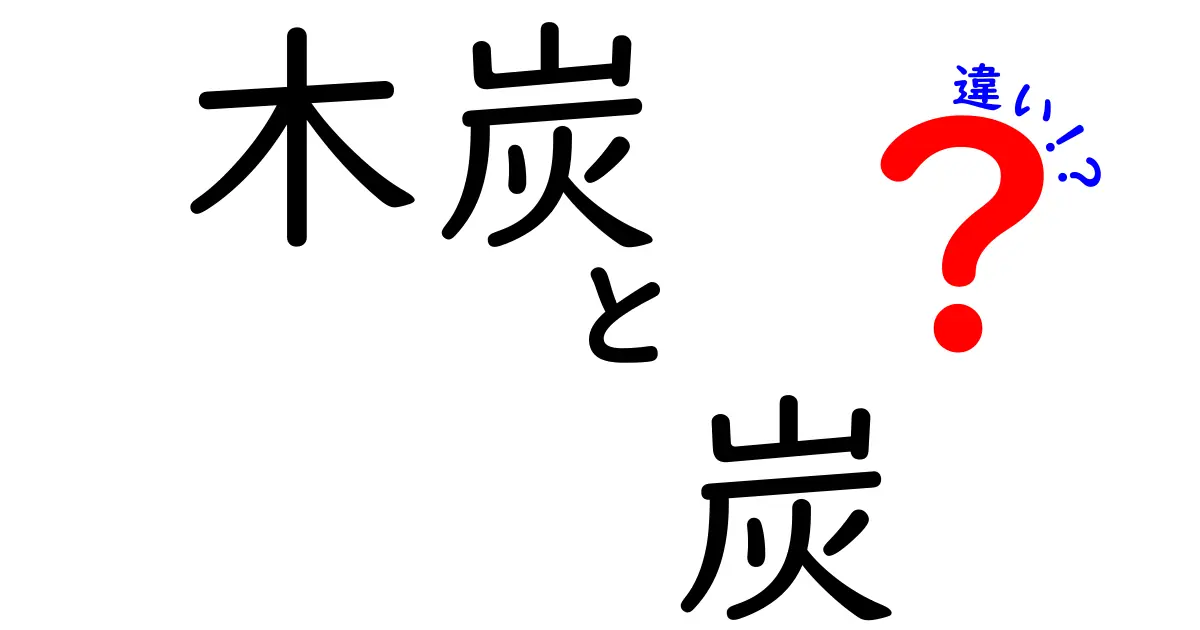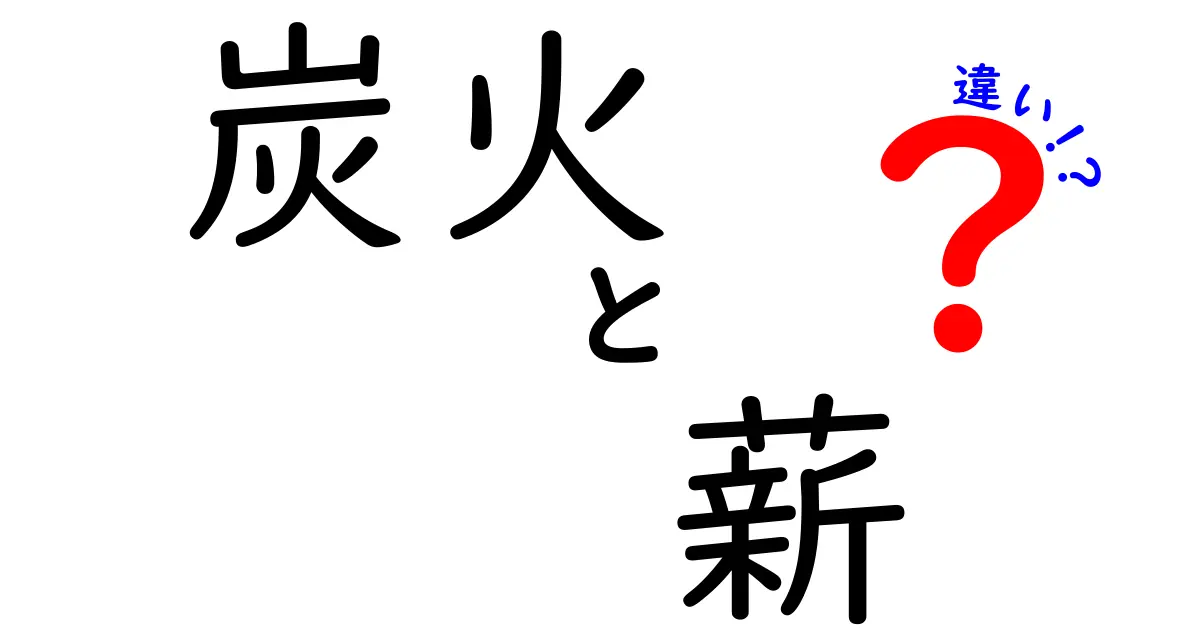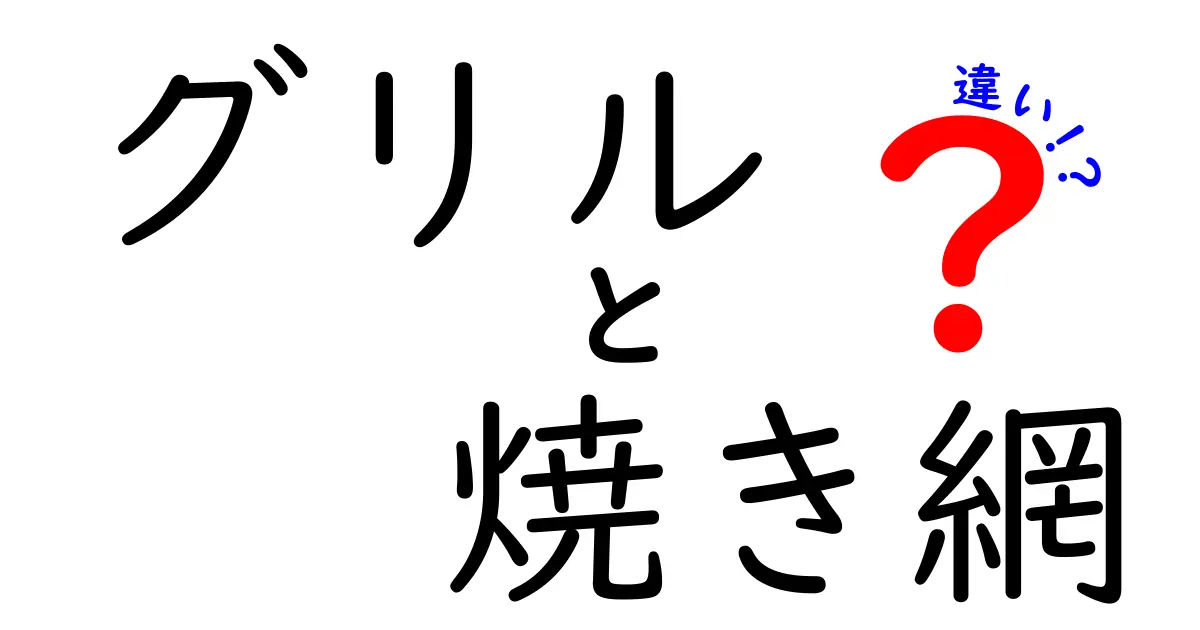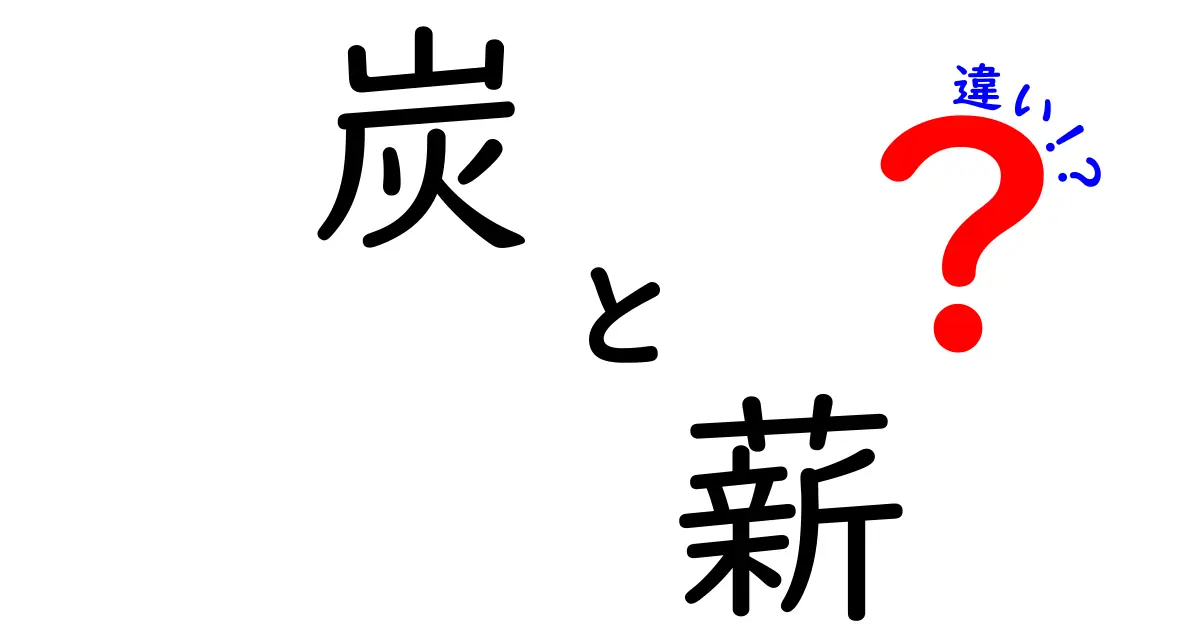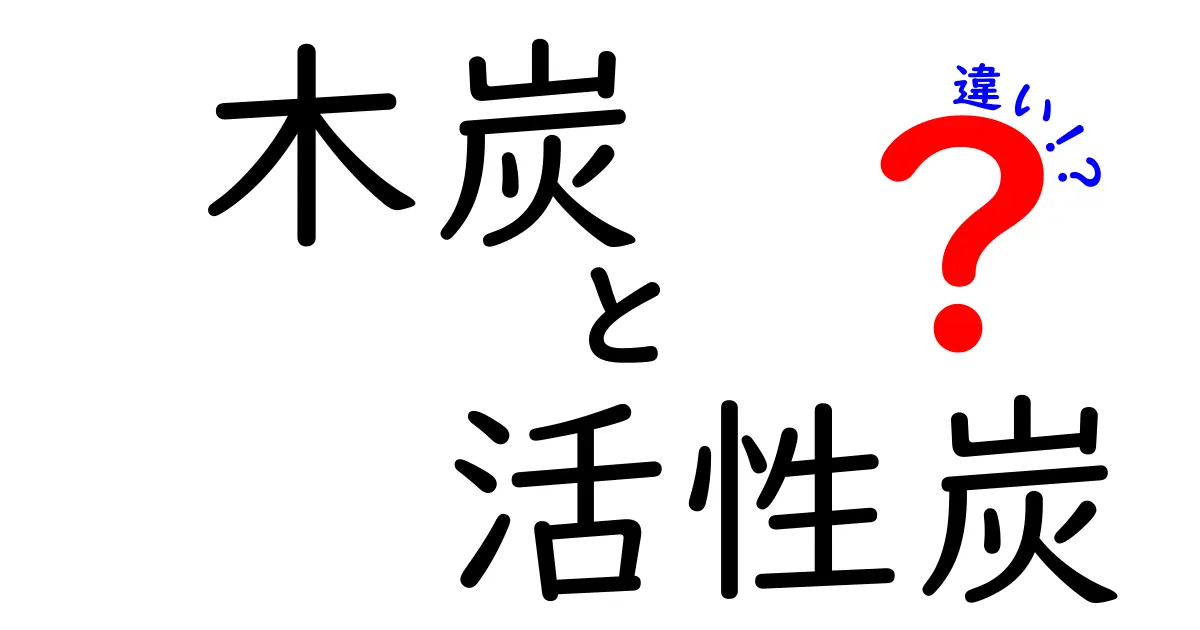

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
木炭と活性炭の違いを徹底解説:名前の由来から実生活まで
木炭と活性炭の違いを知ると、家庭での選択だけでなく、授業での理解も深まります。木炭は木を熱で酸素を少なくする条件で分解して作る「炭」です。これに対して活性炭はその炭を加工して“表面に無数の小さな穴”を作り出したもので、物質を吸着する力が高くなっています。つまり、木炭は燃料や香りづけ、土壌改良など幅広い用途を持つ普通の炭で、活性炭は清浄化や脱臭、浄水・空気清浄の目的に特化したオーダーメイド炭といえるのです。木炭と活性炭は名前が似ていますが、作り方・性質・使い道・安全性が大きく異なる点をまず押さえておくと混乱を避けられます。
以下では、それぞれの特徴をわかりやすく整理し、日常生活での実用例も交えながら解説します。
木炭とは何か
木炭は木材を高温で炭化させることで作られます。燃焼を起こしやすくするために酸素を制限した環境(少ない酸素)で長時間加熱すると、木材に含まれる有機物が分解され、炭素の結晶が網目状に残ります。こうしてできた木炭は多孔質ですが、活性炭ほどの細かな孔は多くはありません。木炭の主な用途は燃料(BBQの焚きつけや家庭用ストーブの燃料)や調理の香りづけ、あるいは土壌改良の材料としても使われることがあります。木炭には灰分が混じることがあり、燃焼後の灰は堆肥の成分として再利用されることもあります。木炭は安価で手に入りやすく、材料の原料指定をしなくても作られ、家庭での実験にも適しています。ただし、活性炭ほど吸着力は高くなく、におい・色・水の透明度を大きく改善する力は弱い点には注意が必要です。
活性炭とは何か
活性炭は木炭などをさらに加工して、表面に非常に多くの微細な孔を作り出した「高表面積の炭」です。作り方には大きく分けて物理的活性化と化学的活性化があります。物理的活性化は高温と蒸気や二酸化炭素を使って孔を広げ、化学的活性化は酸や塩基性の薬剤で材料を処理して孔を生成します。こうした加工により、活性炭の比表面積は数百から千数十平方メートル毎グラムにも達し、非常に多くの物質を吸着できる力を持ちます。主な用途は水道水・飲料水・空気の浄化、脱臭、食品添加物のろ過、医療現場の消臭・脱色など多岐にわたります。使用上の注意としては、活性炭は有機物を広く吸着するため、取り扱い時には粉じんに注意し、再利用は適切な処理が必要です。
また、活性炭は塗料や香料、医薬品など一部の成分を過剰に吸着してしまう場合があり、用途に応じて適切なグレードを選ぶことが重要です。
木炭と活性炭の違いの要点
この見出し以下では、原料・作り方・表面積・用途・安全性・再利用の観点で、木炭と活性炭の違いを要点として整理します。木炭は木材を原料にして炭化させたもので、表面積は活性炭と比べると小さく、吸着力は限定的です。主な用途は燃料・調理・土壌改良など、日用品としての利用が中心です。活性炭は炭素の多孔構造を加工して作られるため、表面積が非常に大きく、吸着力が高いのが特徴です。水・空気・匂い・色素など、さまざまな不純物を取り除く能力があり、日常生活の多くの場面で活躍します。安全性の側面では、適切に使用すれば一般的には安全ですが、粉じんには注意が必要で、特に子どもやアレルギー体質の人は吸い込みを避ける工夫が求められます。再利用については、木炭は有機物を吸着していることが多いため、再炭化や焼却の際の環境負荷を検討する必要があります。
このように、両者は似た名前を持ちますが、作り方と機能が大きく異なることを頭に入れておくと、生活の中で正しく選べます。
表でひとめでわかる比較
放課後、友人と活性炭の話をしていて、私は『活性炭は表面に無数の穴がある小さな sponge のようなものだ。空気や水の中の臭い・汚れを‘吸い込んでくれる’ので、浄化には不可欠なんだよ』と説明しました。友人は『じゃあ木炭はどう違うの?』と聞いてきて、私は『木炭は主に燃料として使われることが多く、吸着力は活性炭ほど高くない。だから料理の香りづけや土の改良には向くけれど、浄化を任せるには物足りない場合が多いんだ』と答えました。そこから、身近な例として家庭用フィルターや deodorizer の違い、選ぶ時のポイントを二人でリスト化しました。こうした“小さな孔の力”が、実は私たちの生活を支える大きな役割を果たしていると実感しました。活性炭の魅力は、日常のほんの些細な場面でこそ光るという気づきが得られたので、これからも身の回りの素材に注目していきたいと思います。
前の記事: « 七輪と炭火の違いを徹底解説:料理の味を左右するポイントとは