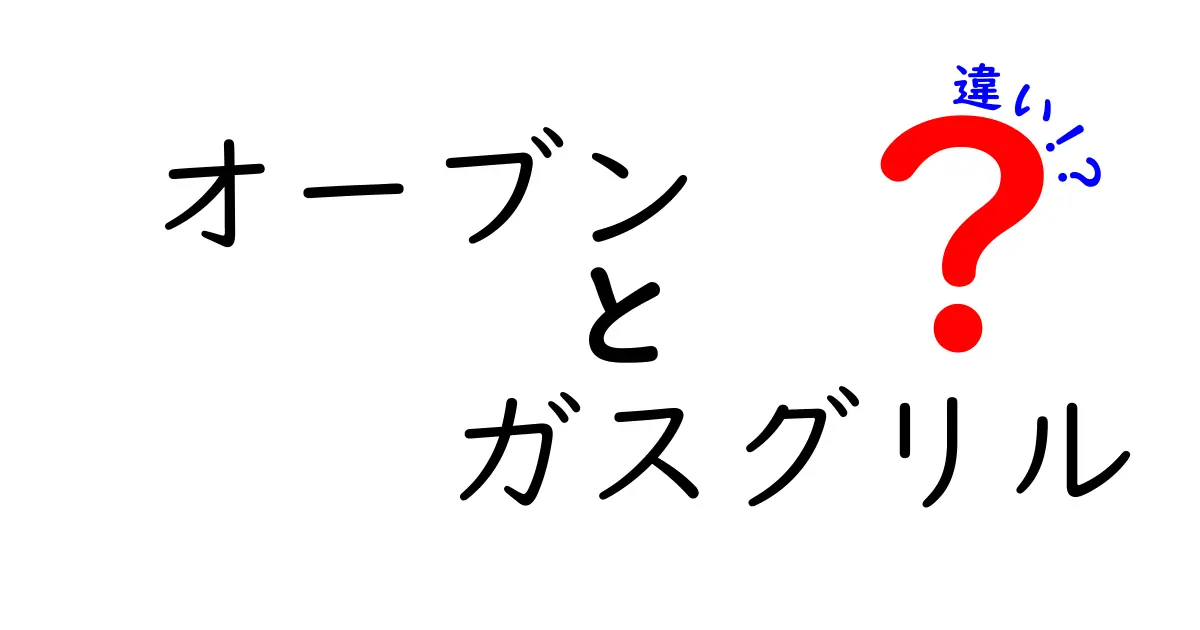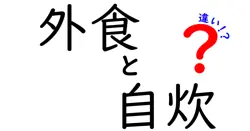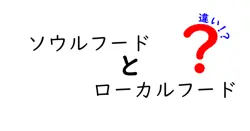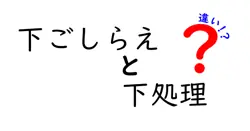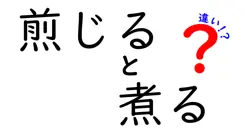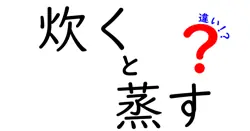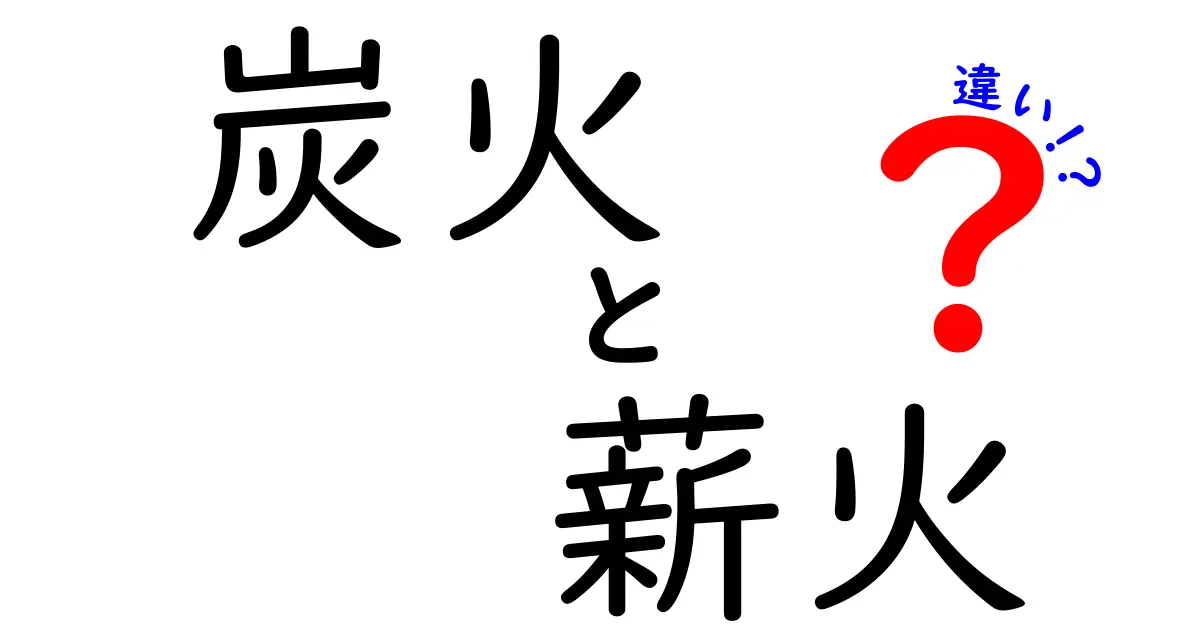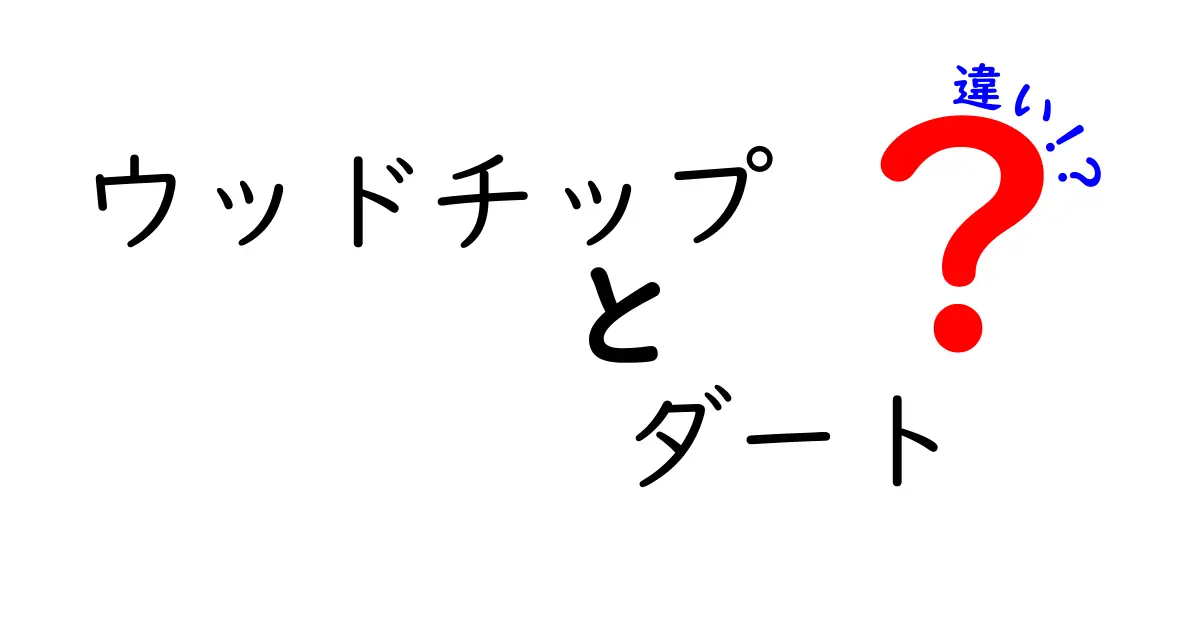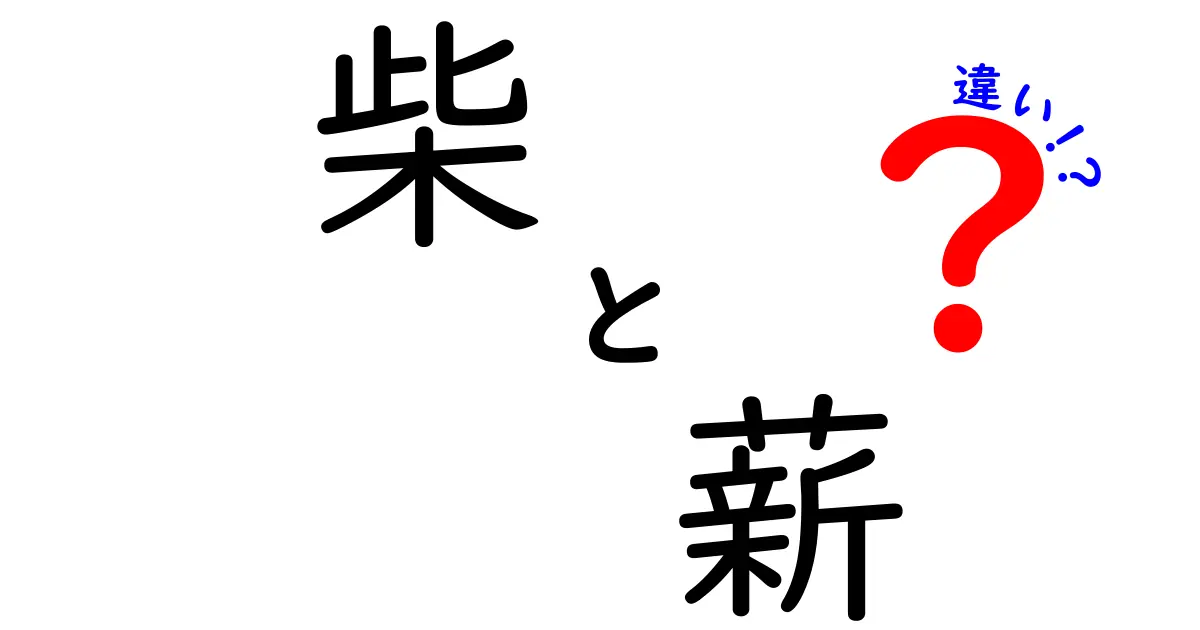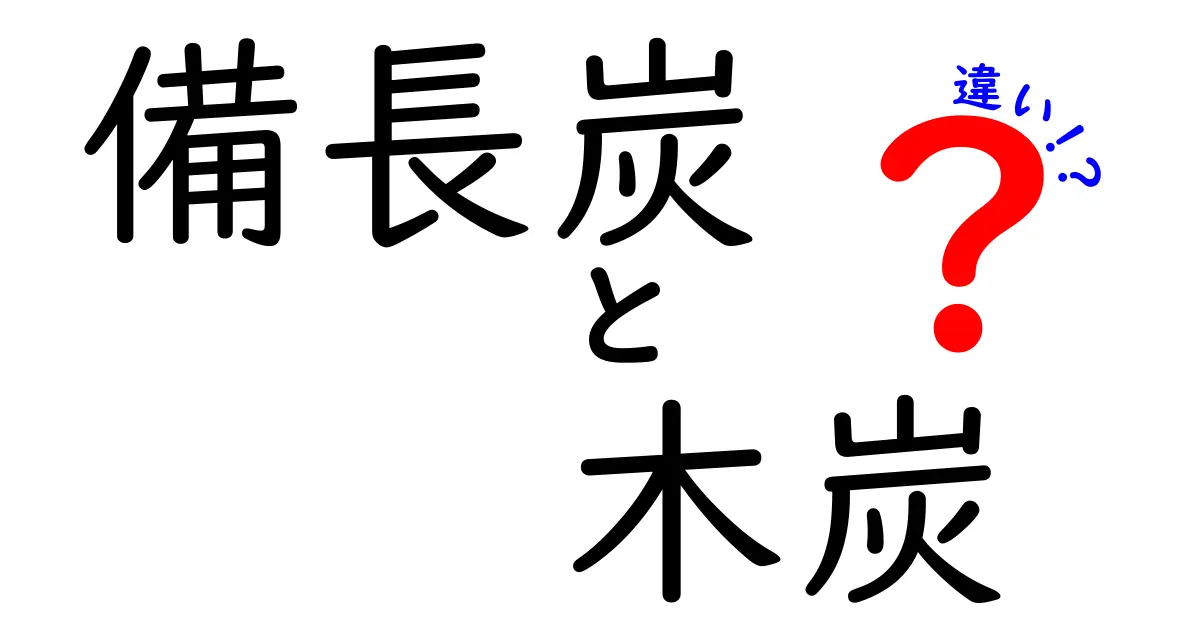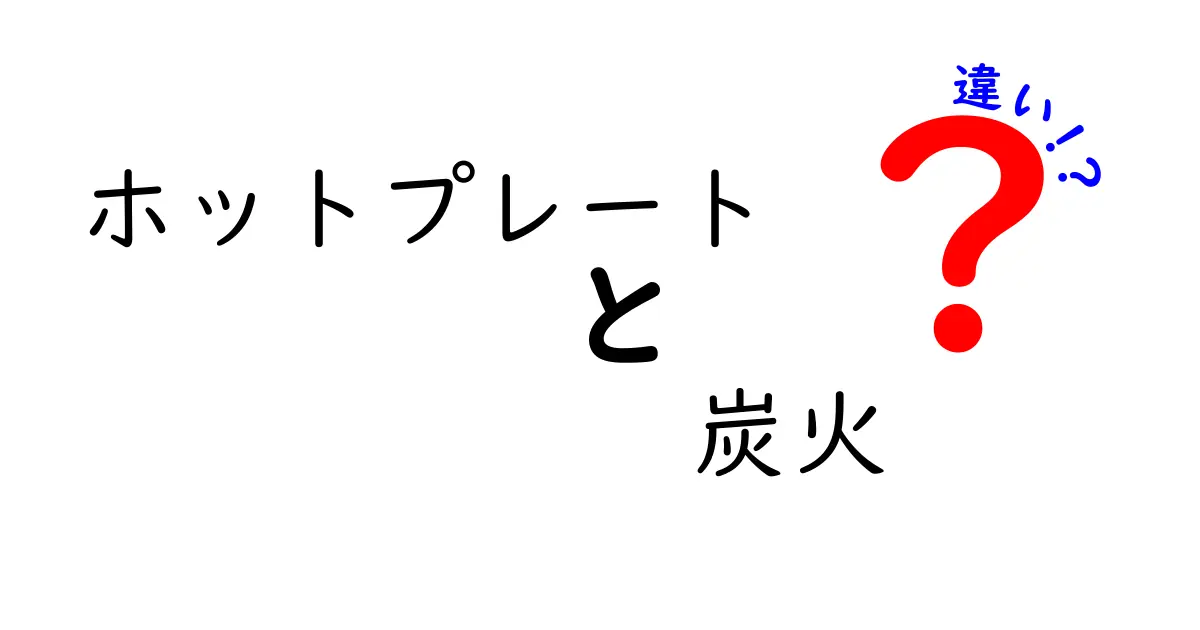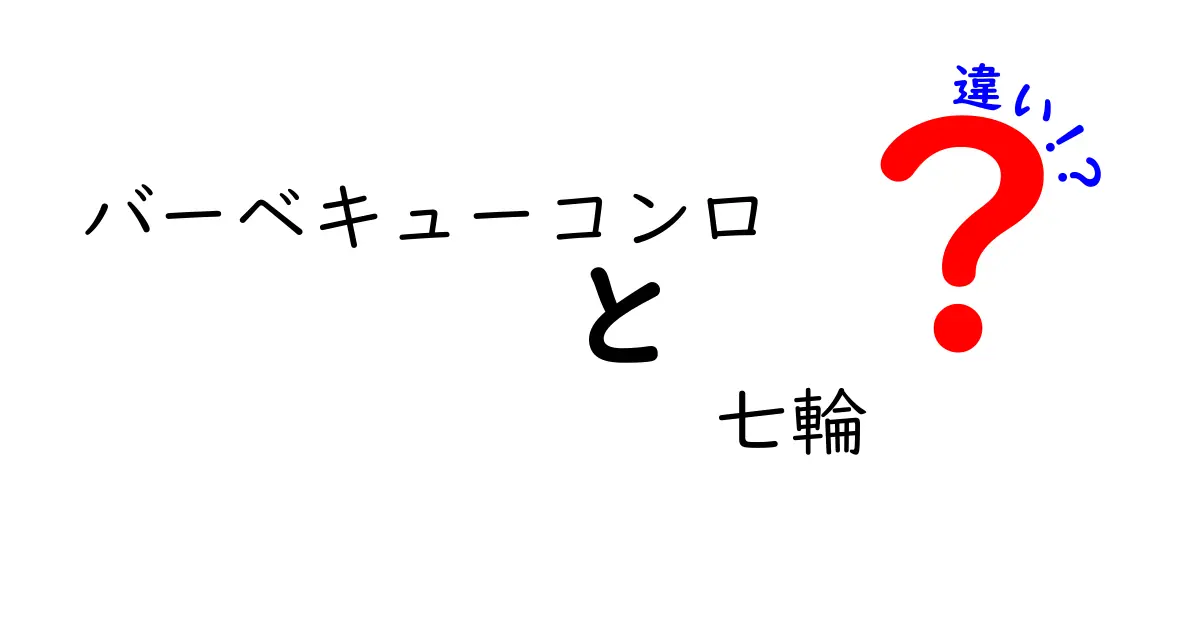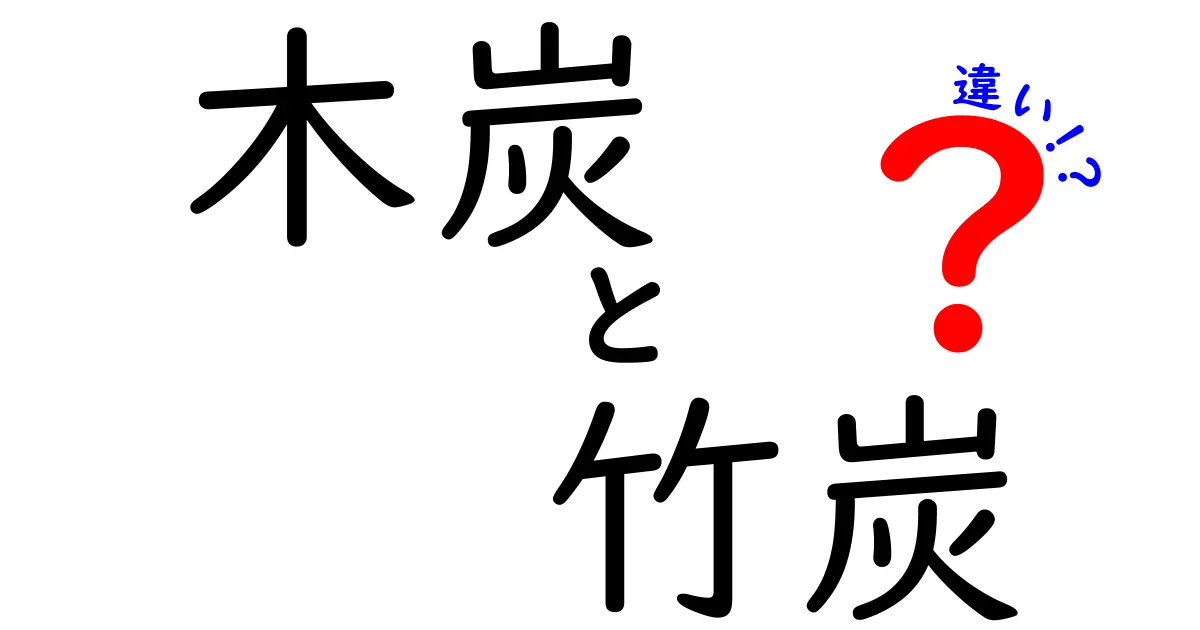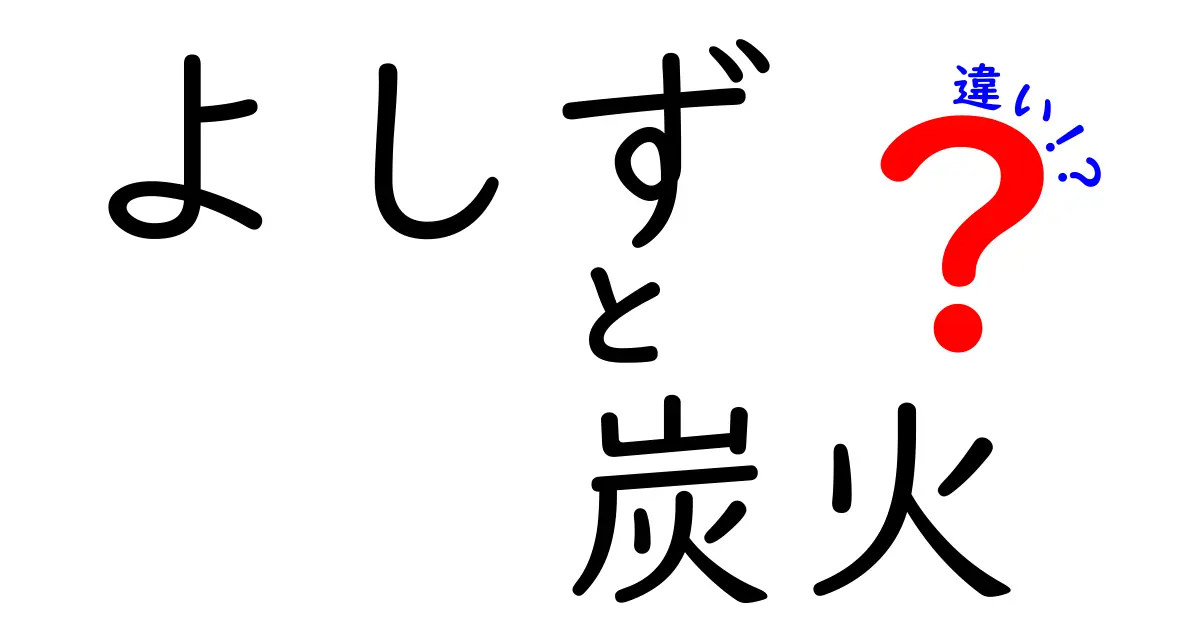

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
夏の庭やベランダで日陰を作る道具には、よしずと呼ばれる昔ながらの万能アイテムがあります。よしずは竹や葦を編んで作られ、太陽の光をやさしく遮りつつ風を通します。そのため、強い直射日光を受けても体感温度を下げ、涼しさを保つ効果があります。また、遮光だけでなく目隠しや見た目の雰囲気づくりにも使われ、和風の景観とよく合います。対して炭火は、太陽光を遮るわけではなく、熱と光を直接生み出す源です。炭火を使う場所は、料理や暖房、雰囲気づくりなどの目的が主で、温かい色の炎と独特の香りが特徴的です。これらは同じ屋外での活動を支える道具ですが、まったく別の役割を果たします。よしずは涼しさと陰を作る道具、炭火は熱と光を作る源。頭の中でこの違いをはっきり分けると、夏のアウトドア計画がずっと上手くいきます。
本記事では、なぜこの二つがセットで登場するのかを、実用的な観点で整理します。例えば、日が強い午後にはよしずを立てて陰を作り、涼しく過ごす工夫をします。一方で、夕方に向けては炭火を使いたい場面—焼き物を楽しむときや暖をとるとき—には炎の取り扱いに注意を払いながら、風向きと周囲の安全を確保します。よしずは建具としても使える発想の幅が広く、場所を移動させやすいのが利点です。炭火は燃焼させることで生まれる熱量に依存するので、風が強い日には炎が揺れて危険になることがあります。こうした性質の違いを理解しておくことで、無駄な労力を減らし、天候や状況に合わせて道具を使い分けられるようになります。
よしずと炭火の特徴と使い分け
よしずの特徴として、第一に自然素材でできており、透湿性が高く風を通す点が挙げられます。これにより、室内の湿度を保ちつつ直射日光だけを弱くしてくれるため、涼しさを感じやすくなります。次に設置の柔軟性です。よしずは軽量で設置場所を自由に変えられるタイプが多く、ベランダの長さや庭のレイアウトに合わせて調整しやすい点が魅力です。さらに耐久性とメンテナンスも重要で、雨風にさらされると劣化が早まることがあるため、雨の日の避難場所や収納方法を考える必要があります。こうした点を踏まえれば、よしずは夏の陰を作る“道具”として、日常的な使い方に適しています。
反対に炭火の特徴は、第一に高い熱量と雰囲気です。炎の色や匂いは夏のアウトドアで特別な体験を作り出し、焼き物や暖房など実用的な用途に強い力を発揮します。次に安全性と風向きの影響です。風が強い日は炎が煽られやすく、周囲の炎症性物質に注意を払う必要があります。また、煙や匂いが苦手な人がいることを忘れず、換気の確保や場所選びをきちんと行うことが大切です。炭火は温度管理が難しいこともあるため、初めて使うときは小さな範囲で実験するのがおすすめです。
よしずは陰を作ることが得意で、直射日光の影響を緩和する一方、炭火は熱や光を作る力が強く、料理や暖房、雰囲気づくりに役立ちます。用途を分けて使うのが基本ですが、組み合わせて使う場面もあります。例えば、軒下やテラスのよしずの陰の下で炭火を使い、涼しさと暖かさを同時に演出するなど、工夫次第で一年中楽しむことが可能です。安全第一の原則を忘れず、周囲の素材との距離や換気、子ども・ペットの安全対策を徹底しましょう。
用途別の使い分けのコツをまとめると、日中の暑さ対策にはよしず、夜の雰囲気づくりや料理には炭火という分担が基本です。これを念頭に置けば、夏のイベントや日常の屋外活動を、より快適で楽しいものにできます。
最後に、設置場所に応じてよしずと炭火の位置関係を見直すのを習慣にすると、風向きや日照の変化にも柔軟に対応できます。
よしずの話題を深掘りする小ネタです。先日、友達と外で勉強していると、日差しが強くてノートが反射して見づらい。そこで私が選んだのがよしず。陰を作るだけでなく、風を適度に通して涼しさを保つ工夫がすごい。よしずの影は太陽の位置で形が変わるので、時間とともに影の動きを観察するのも楽しい。暑い午後にはよしずを少しだけ動かして影を移動させると、机の上の光の反射が改善され、集中力が戻ってくる。この小ネタでは、よしずがどうやって私たちの生活を助けてくれるのか、日陰の作り方や風の取り回し、材質の選び方まで、雑談形式で深掘りします。