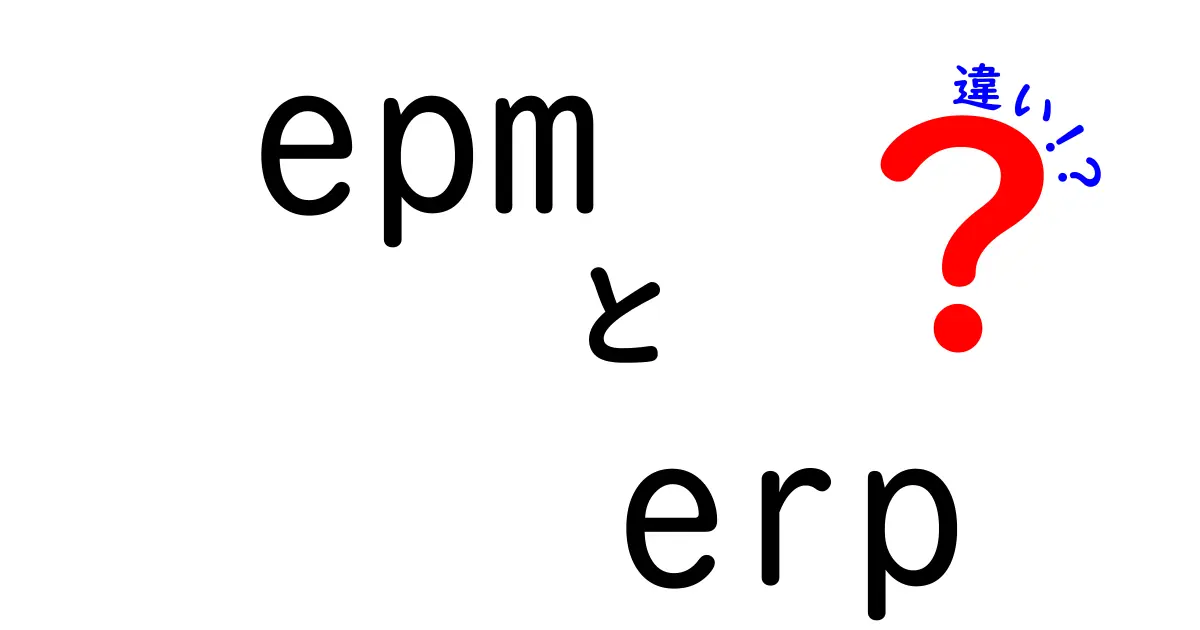

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
epmとerpの違いを理解するための基礎ガイド
こんにちは。今日はepmとerpの違いについて、分かりやすく解説します。エンジニア用語っぽく聞こえるかもしれませんが、実は中学生にも理解できる考え方です。epmは企業の“パフォーマンスを高める仕組み”として、現場の動きや作業の流れを可視化し、問題を早く見つけて解決するための道具です。
ERPは企業の資源を横断的に管理する大きな仕組みで、買い物、在庫、製造、会計、人事などのデータを一つのデータベースに集約して、企業全体の運営を安定させる土台となります。
この2つは似ているようで役割が違い、導入を検討する際には「何を達成したいのか」を最初に決めることが大切です。
この基本ポイントをしっかり押さえておくと、具体的な製品を選ぶときの判断材料が増えます。以下のポイントを覚えておくと、どちらを選ぶべきかの判断がしやすくなります。
1. 目的の違い:epmは現場の実行と成果の可視化、erpは企業全体の資源統合を目指します。
2. 対象の範囲:epmは部門・プロジェクトのパフォーマンスを追跡します。
3. 導入の規模とコスト:epmは比較的小規模~中規模の導入が多く、erpは大企業や複雑な業務を抱える企業での導入が中心になることが多いです。
4. データの性質:epmは現場データのタイムリー性を重視し、erpは取引データの正確性・整合性を重視します。
5. 成果の測り方:epmはKPIの達成状況や作業効率、リスク低減などを評価、erpは財務諸表や原価計算などの定量指標を中心に評価します。
このように違いを並べて見ると、epmは“使い方の設計図”に近く、erpは“データの設計図”に近いと捉えると理解しやすいです。
epmとerpの役割の違いと現場での使い分け
epmは現場の運用を支える道具で、進捗の見える化、タスクの割り当て、リスクの検知、KPIのダッシュボード作成などが主な機能です。現場の人が「今何をすべきか」「次の一手は何か」を理解できるようにするのが目的で、意思決定を早くする効果があります。
ERPは購買・在庫・生産・受発注・会計・人事などのデータを統合し、部門を跨ぐ情報の齟齬を減らして財務的な信頼性を高めます。つまりepmは“運用の筋肉”を鍛え、erpは“体全体を支える骨格”のような役割です。
導入の際には、まず自社の現状の課題とゴールを具体的な数値で整理し、どの指標を改善したいのかを明確にすることが大切です。次に、現場の運用とデータの品質を同時に整える計画を立てると成功しやすいです。
最後に、両システムをどう連携させるかが鍵になります。適切な連携設計によって、現場の作業指示と財務データが一致し、予算の使い道がすぐに見えるようになります。
友人の雑談風です。店で勉強会をしていたとき、Aさんがepmとerpを学校の運営で例えて話してくれました。ERPは学校の財務、購買、出欠、成績といった“学校という資源の全体像”を一つの箱に集約する大きな仕組み。EPmはその箱の中で、各部活や委員会の進捗を日々監視する“進捗ノート”のような存在です。つまりERPは全体の骨格、EPMは現場の動きを支える筋肉。二つを適切に連携させると、予算がどう使われ、現場がどう進んでいるのかが、教室の黒板にもリアルタイムで映し出される感覚になります。こんな話をしていると、難しく見える言葉も身近に感じられます。





















