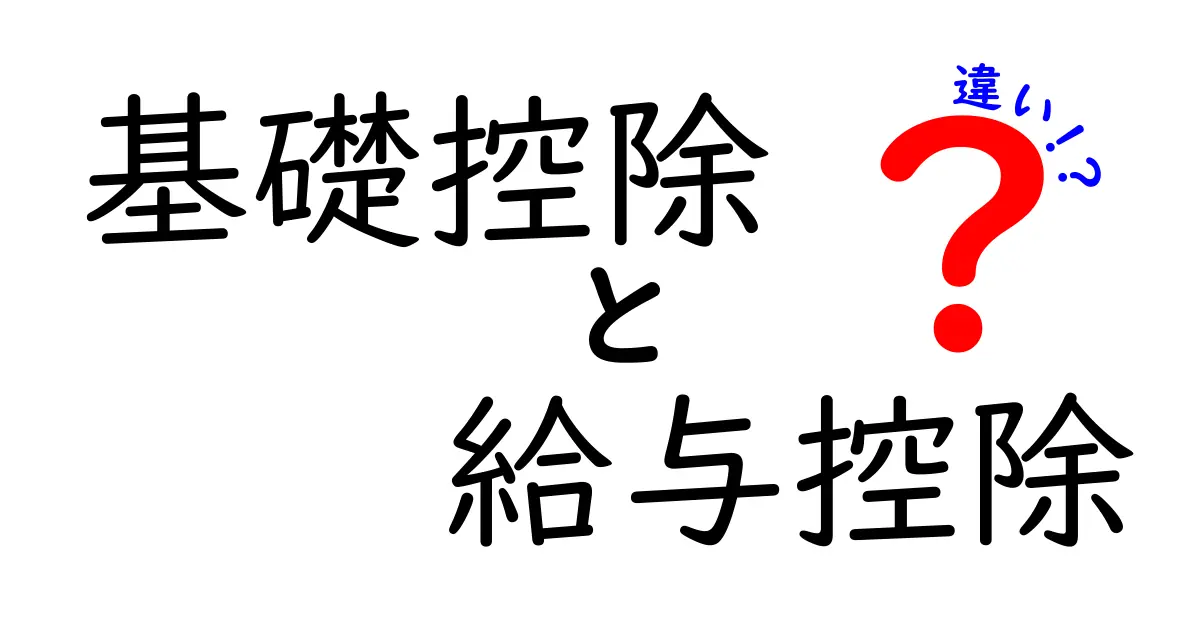

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基礎控除と給与控除って何?
税金の計算でよく出てくる言葉に「基礎控除」と「給与控除」があります。控除とは、税金を計算するときに収入から差し引ける金額のこと。つまり、税金がかかる対象となる収入を減らすしくみです。
この二つは似ていますが意味も仕組みも違うので、混同しやすいのが特徴です。
ここでは、中学生でもわかるように、基礎控除と給与控除の違いについて、詳しくやさしい言葉で説明します。
基礎控除とは?
基礎控除は、すべての人が受けられる税金の控除です。
簡単に言うと、税金を計算する時に、一定の金額を無条件で収入から引いてもよいというものです。これにより、誰でもその分だけ税金が減ることになります。
2020年(令和2年)から基礎控除の額が見直されました。現在は一律48万円で、
例えば、年収が100万円の人でも48万円は税金がかからない計算になります。
この控除は、給料をもらっている人だけでなく、自営業者などすべての納税者に適用されます。
つまり、「基礎控除」は税金計算の土台のようなもので、誰でも一律もらえるお得な控除です。
給与控除とは?
給与控除は、給料をもらっている人にだけ使われる特別な控除です。
会社などからもらった給料から、一定の金額を差し引いて税金の計算をするための仕組みです。
どうして給与控除があるかというと、給料収入には仕事にかかる様々な費用や必要経費があるからです。例えば、通勤費用や仕事で使う道具代などです。
給与控除は年収の額によって段階的に金額が決まっていて、
例えば、年収が100万円から180万円の人は給与控除が55万円、300万円の人なら100万円近くになります。
これは、収入が増えるほど控除の額も増える仕組みなので、給料の税金が直接はねあがらないように国が調整しています。
給与控除があるのは「給料をもらって働く人」に特別な配慮として設けられている控除と理解してください。
基礎控除と給与控除の違いを比較表で理解しよう
このように基礎控除は家計の基礎的な負担を減らす役割、給与控除は働いて得た給料の特別な経費を考慮しているところに違いがあります。
まとめ:知っておくと得する基礎控除と給与控除の違い
以上のように、基礎控除は誰でも受けられる一律の控除で、
一方で給与控除は給料をもらっている人だけが対象の、年収に応じて変わる控除です。
これらを正しく理解することで、税金計算の仕組みがわかりやすくなり、自分の税負担を減らすために必要な知識になります。
会社で働いている人やこれから働きたい中学生のみなさんも、この違いを覚えておいて税金の話を聞くときに役立ててみてくださいね。
「給与控除」って、実は会社からもらう給料の中に含まれている本当の「儲け」じゃない部分をまず差し引くっていう仕組みなんだよね。例えば、通勤にかかる費用や仕事の道具代など、仕事をする上で必要なお金を国が考えて、給料から自動的に控除しているんだ。これによって、給料が高くなっても税金が急に増えるリスクを和らげているってわけ。つまり、給与控除は働く人にやさしい税の配慮なんだよね。こういう控除があるからこそ、みんな安心して働けるとも言えるんだ。
次の記事: 「交通費支給」と「通勤手当」の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















