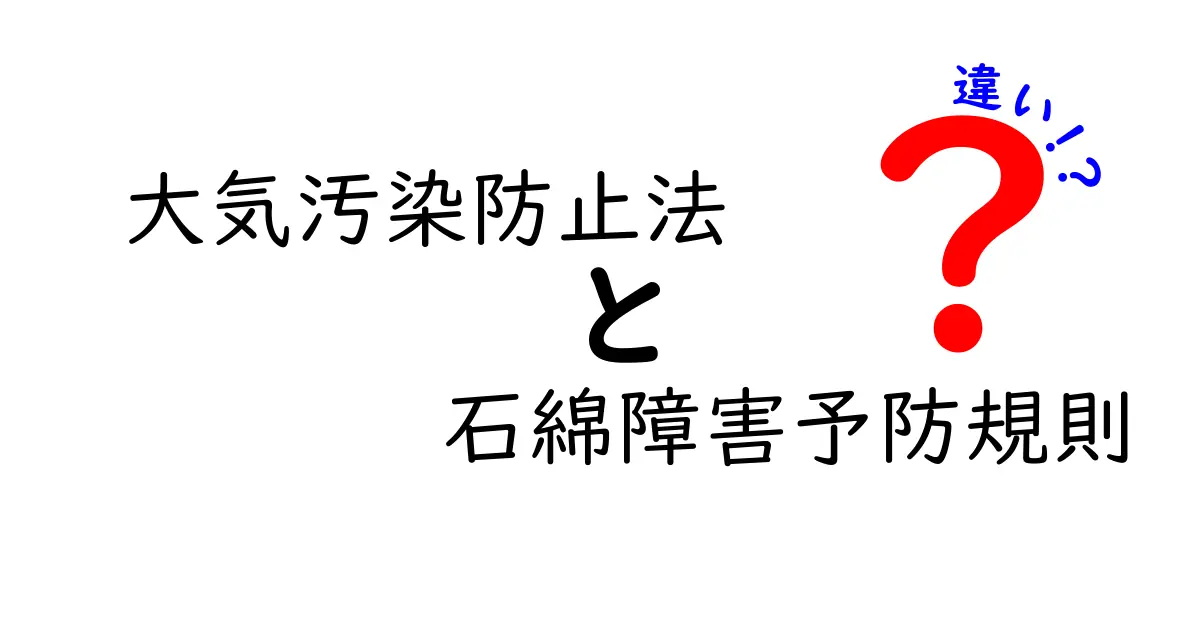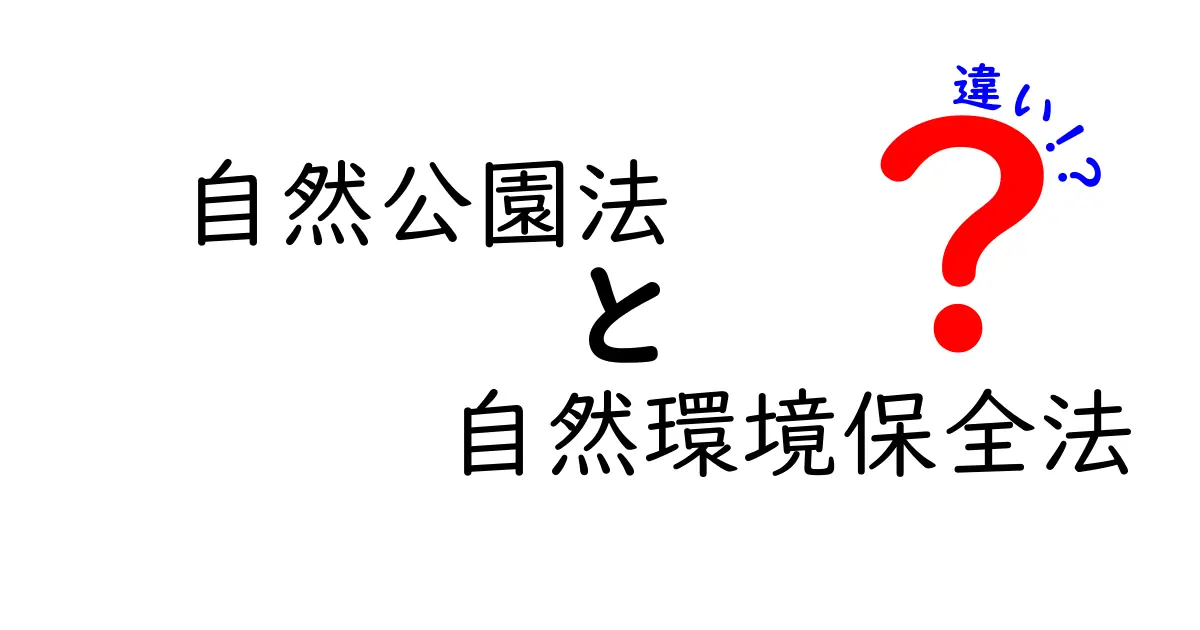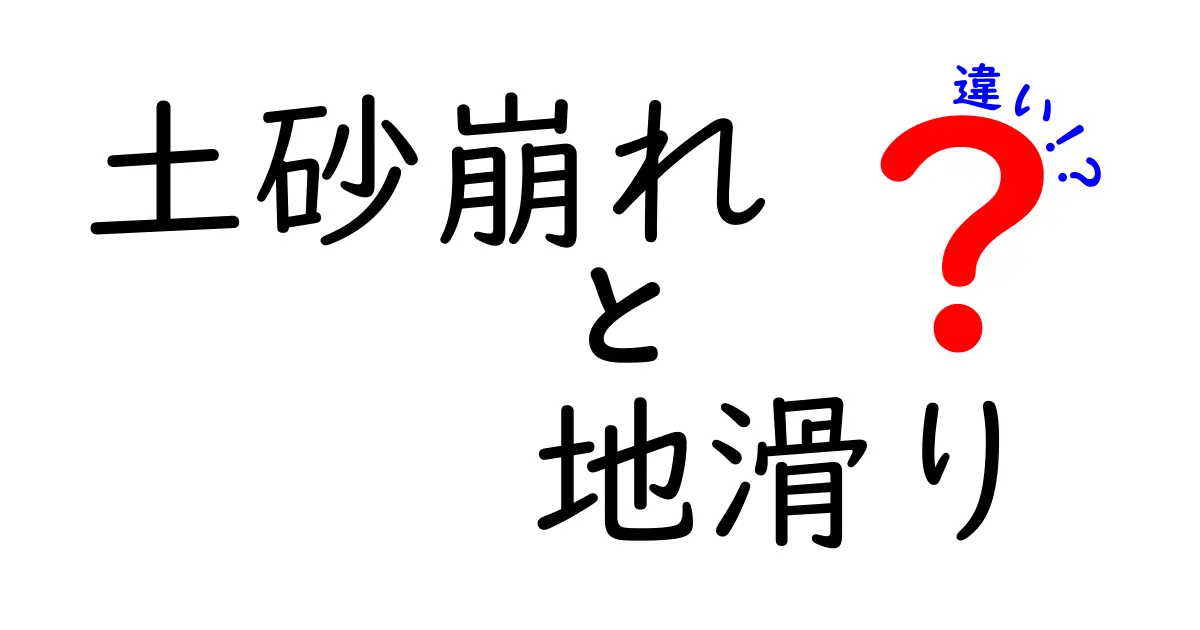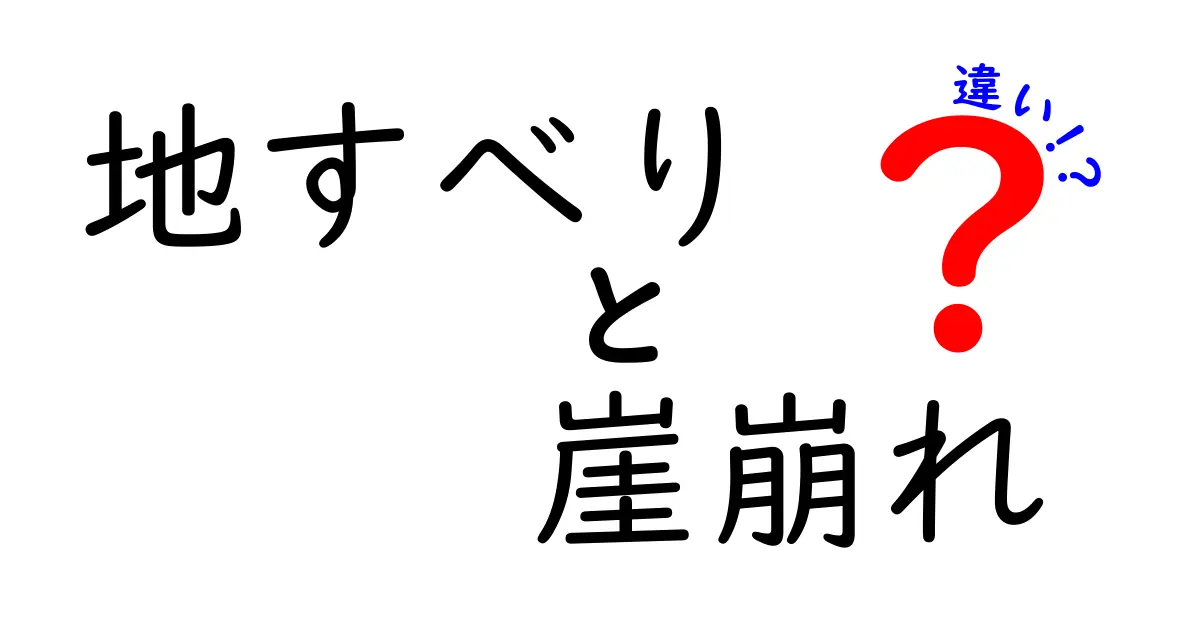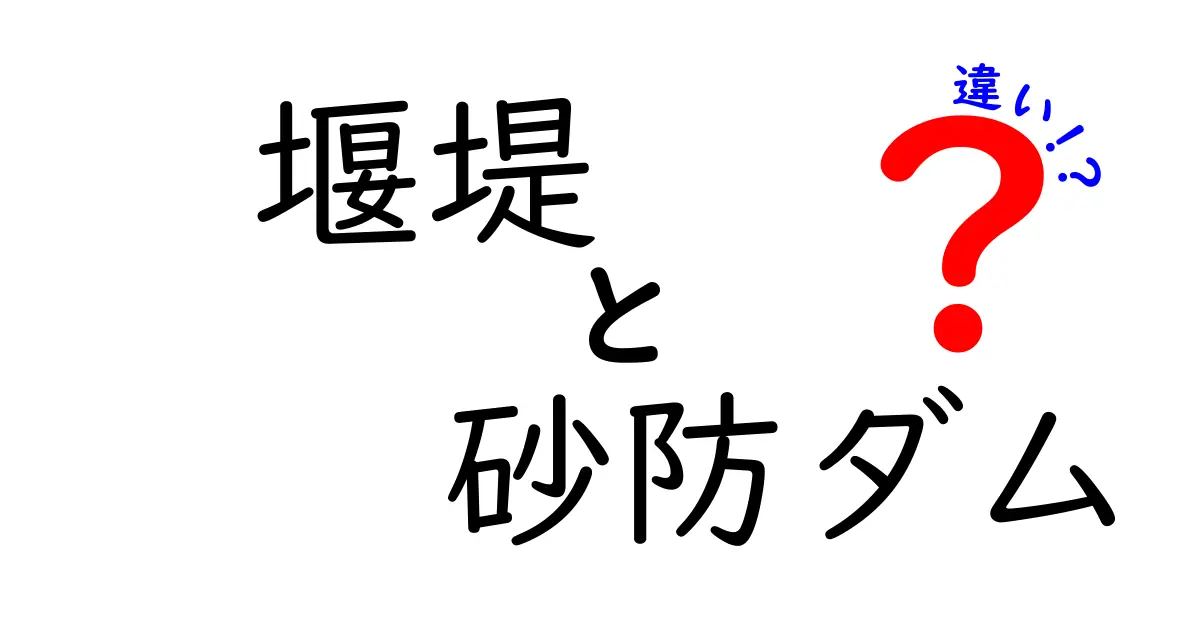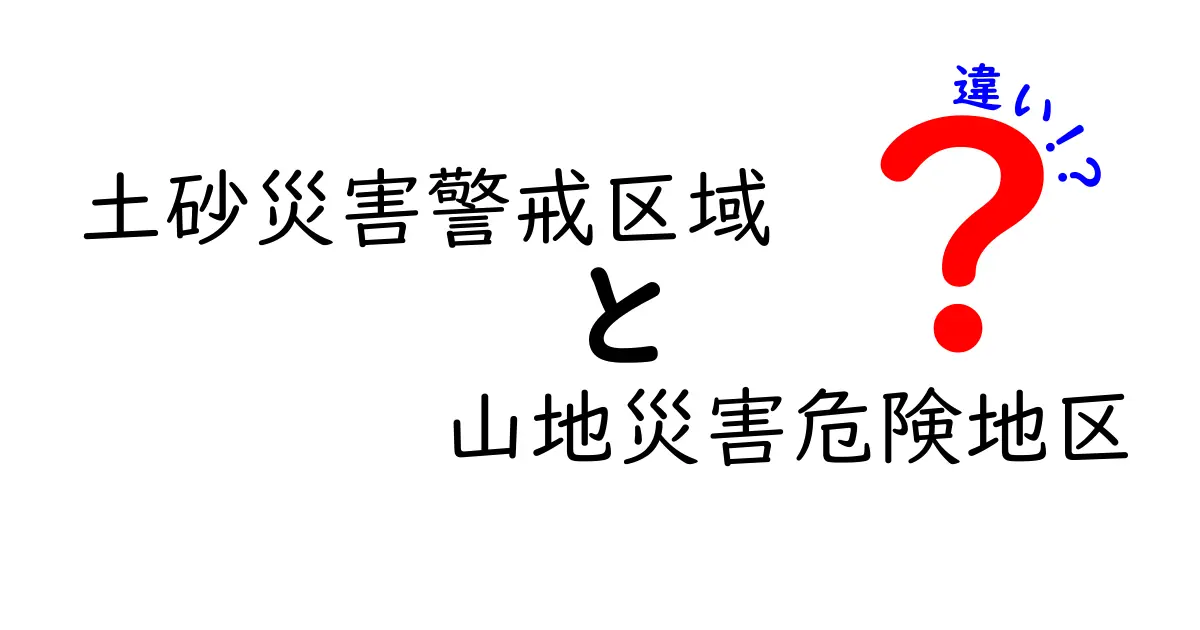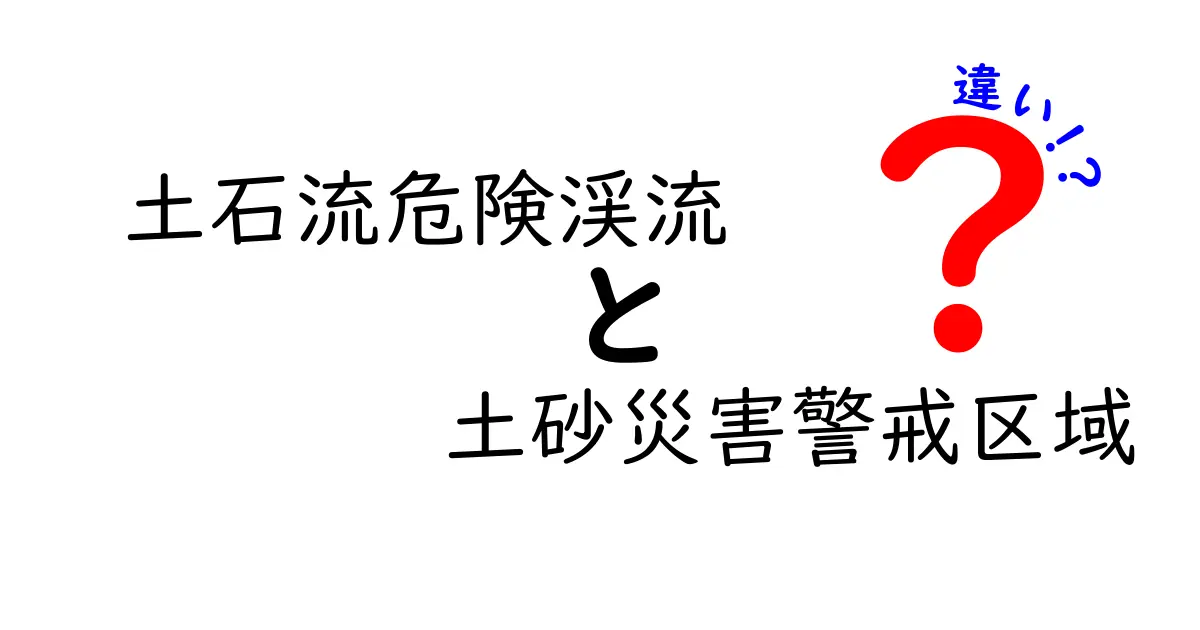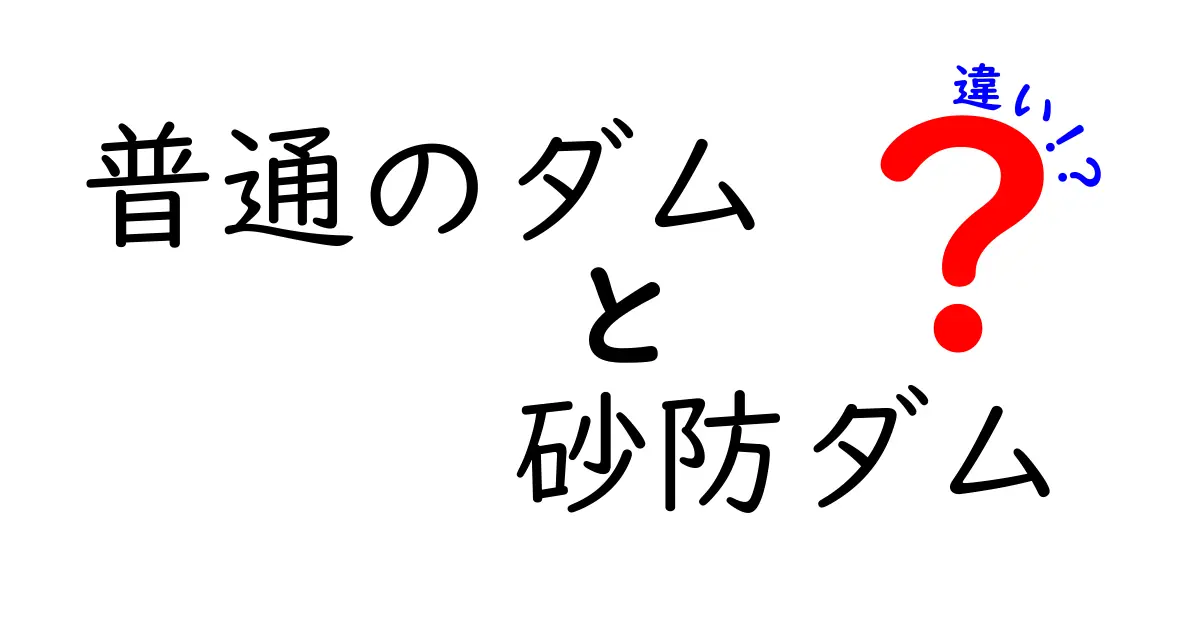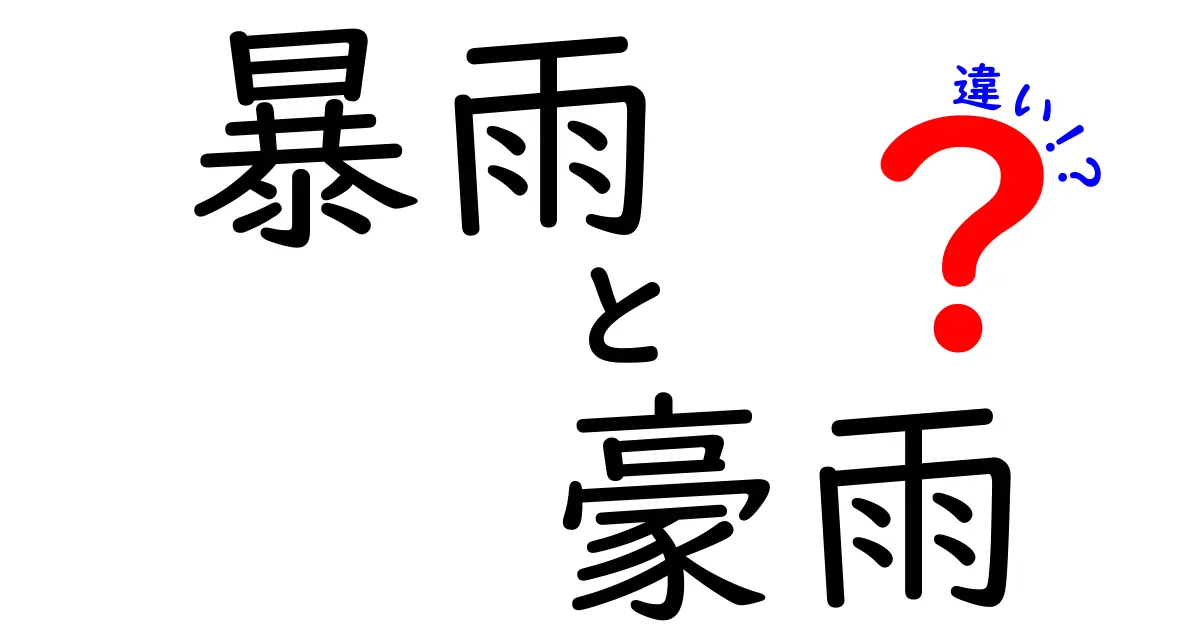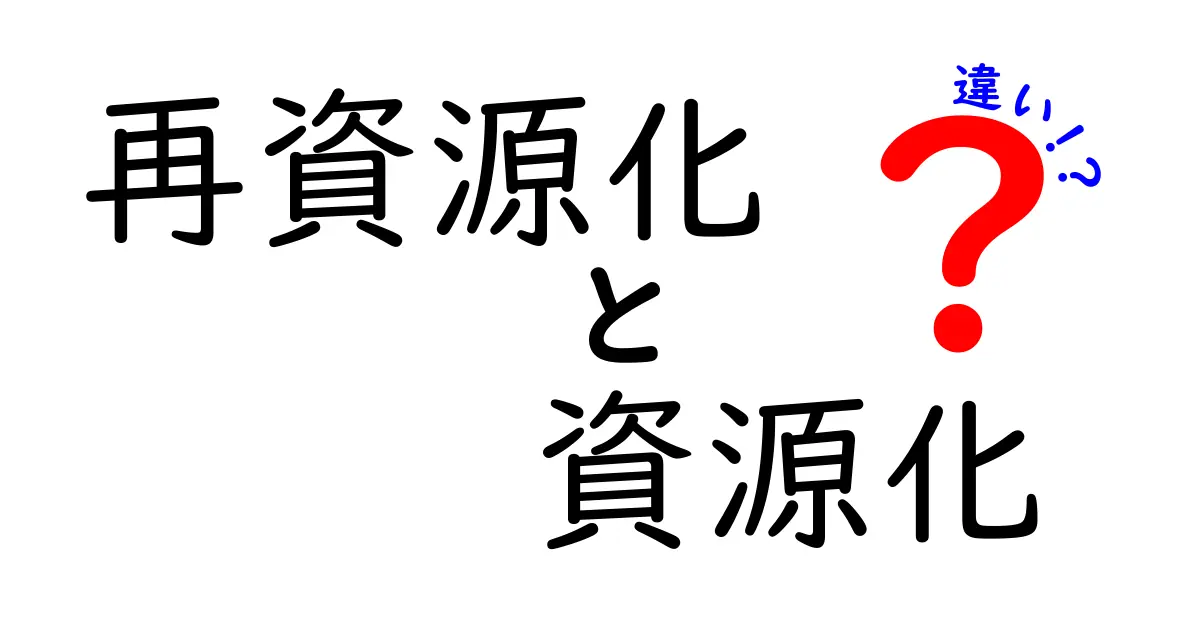

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
再資源化と資源化とは何か?基本の意味を理解しよう
私たちが普段使っている商品や資源は、使い終わった後にどうなるのでしょうか?
ここで登場するのが「再資源化」と「資源化」という言葉です。どちらもリサイクルや環境保護に関わる大切な言葉ですが、意味は少し違います。
簡単に言うと、「資源化」とは廃棄物から何かを作りだしてもう一度資源として使うことを指し、
「再資源化」は、特に一度使用された資源を再び同じ種類の資源として再利用することを強調しています。
たとえば、ペットボトルを集めて新たなプラスチック製品に作り変えることは資源化ですが、そのペットボトルがまたペットボトルとして再生される場合は再資源化と言えるわけです。
このように、リサイクルの過程での役割が微妙に違うため、きちんと区別して理解する必要があります。
実際の違いを具体的に比較!再資源化と資源化の特徴
では、もっと詳しく両者の違いを見てみましょう。
下の表で比較すると分かりやすいです。
リサイクルとしての価値が高い
エネルギー回収も含む
このように資源化はもっと広い意味で使われるため、再資源化は資源化の一部と考えられることもあります。
また、再資源化は製品の形や用途をできるだけ変えないで戻すことが特徴であり、それによって資源の無駄を少なくしています。
なぜ再資源化が重要なのか?地球環境と私たちの未来
リサイクルや資源の再利用は環境を守るために欠かせません。
特に再資源化は、資源の質を高く保ちながら無駄なく繰り返し使うことができるため、地球に優しい行動といえます。
地球の資源は限られているため、同じ資源を何度も使える再資源化は重要です。また、ゴミの量を減らすことにもつながります。
私たち一人ひとりが再資源化について理解を深め、資源を無駄にしない生活を心がけることは、未来の地球を守ることにつながっています。
例えば、ペットボトルはただ捨てるのではなく、分別してリサイクルに出すことが大切ですね。
「再資源化」という言葉はよく聞きますが、実はそれが特に『同じ種類の資源に戻すこと』を指しているのは面白いポイントです。たとえば、ペットボトルをリサイクルするとき、ペットボトルからペットボトルへと再生されることで、再資源化と言います。これは資源の価値や質をできるだけ保つことが目的で、ただ燃やしてエネルギーにする資源化とは違うんですよね。こうした違いを知ると、環境保護の取り組みももっと身近に感じられるかもしれません。みんなもぜひ分別リサイクルに注意してみてくださいね!
前の記事: « 振動規制法と騒音規制法の違いとは?わかりやすく解説します!