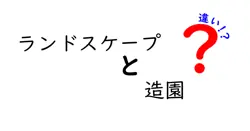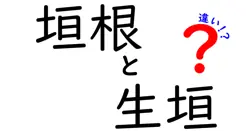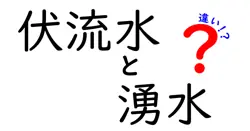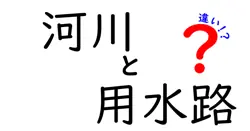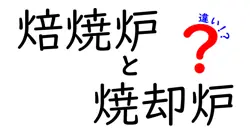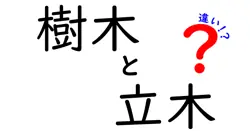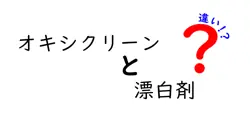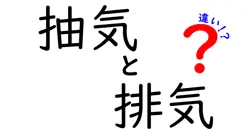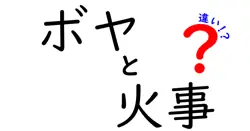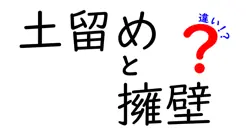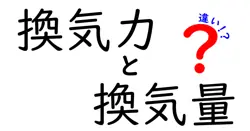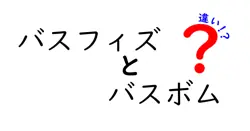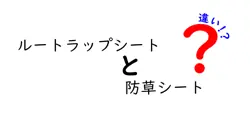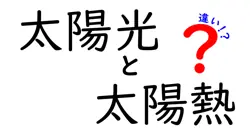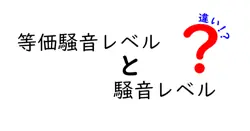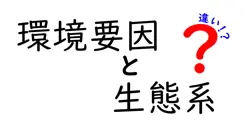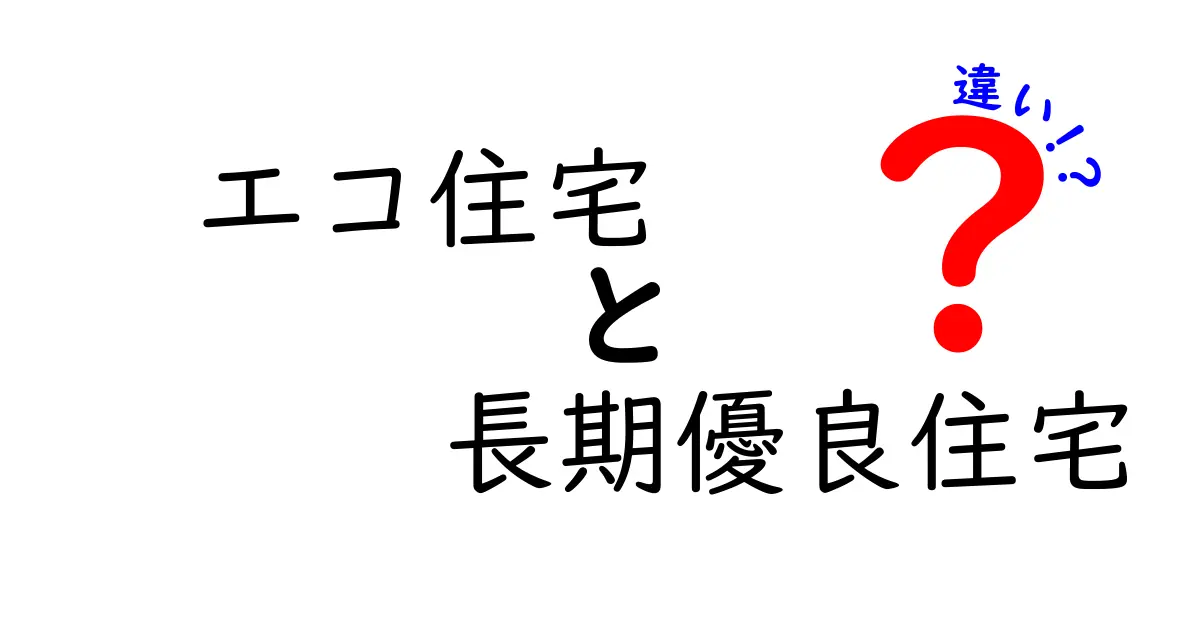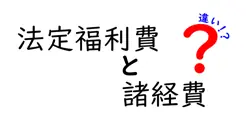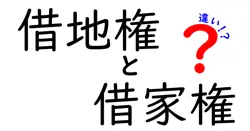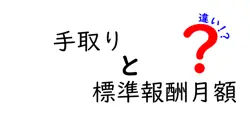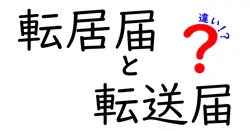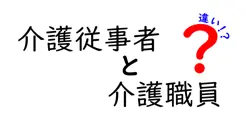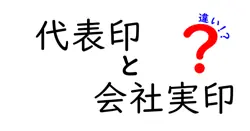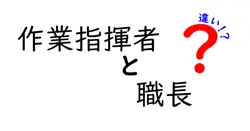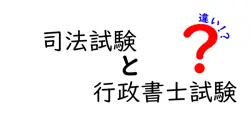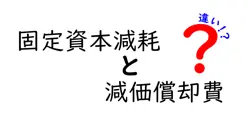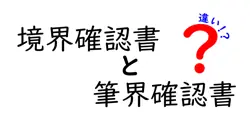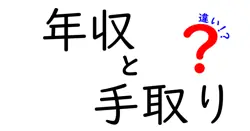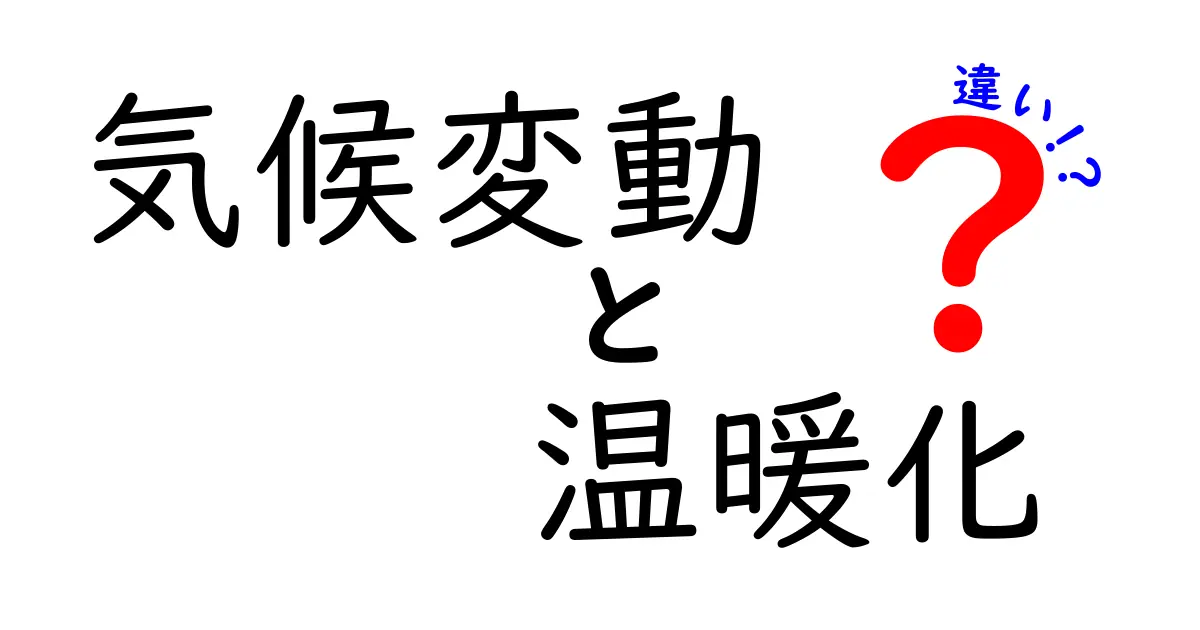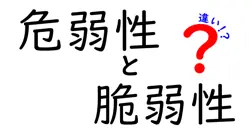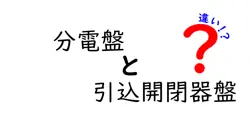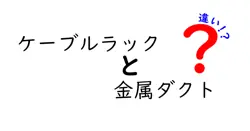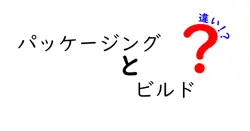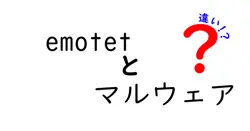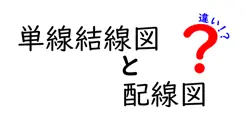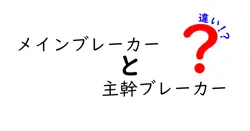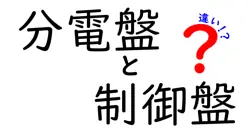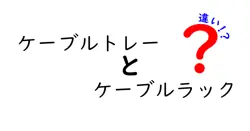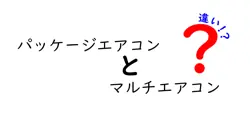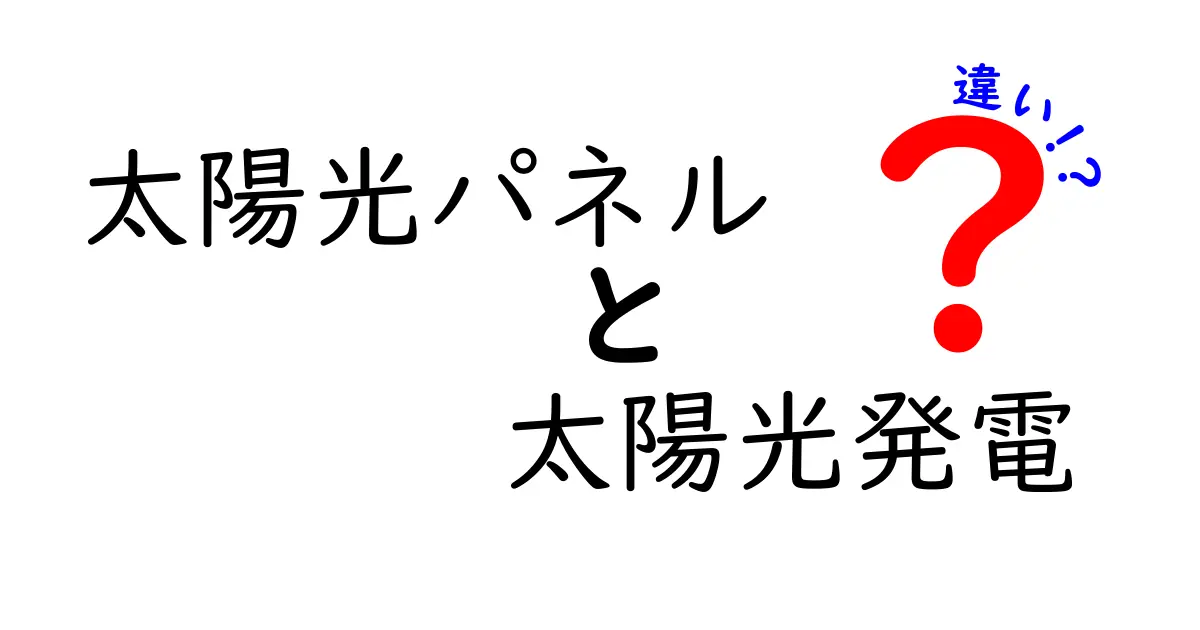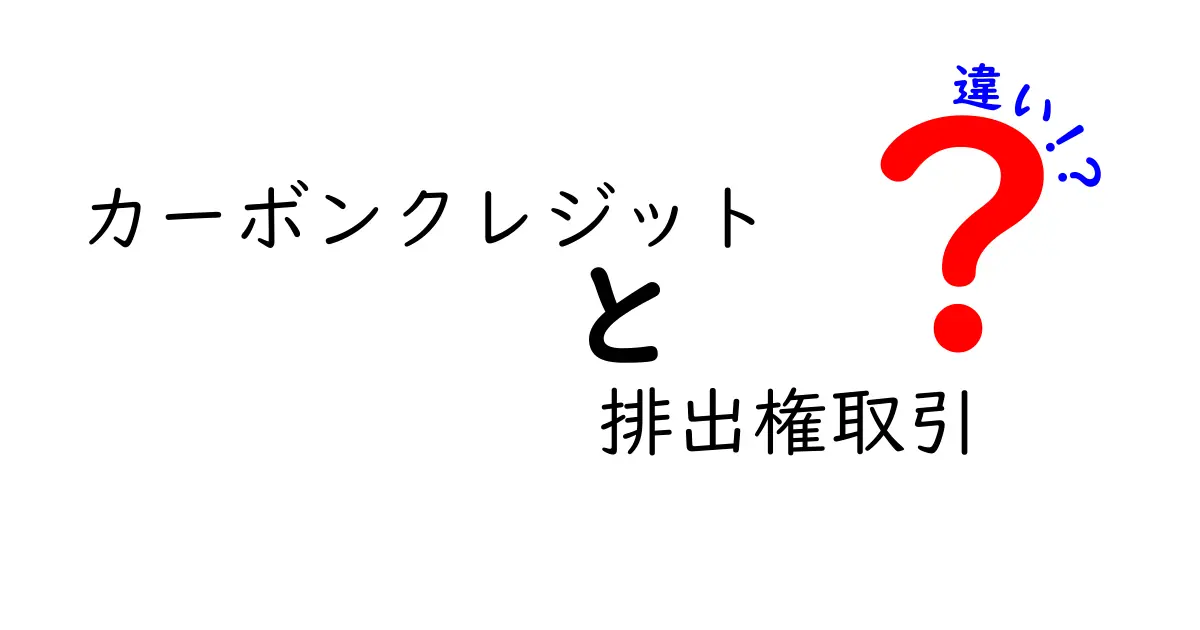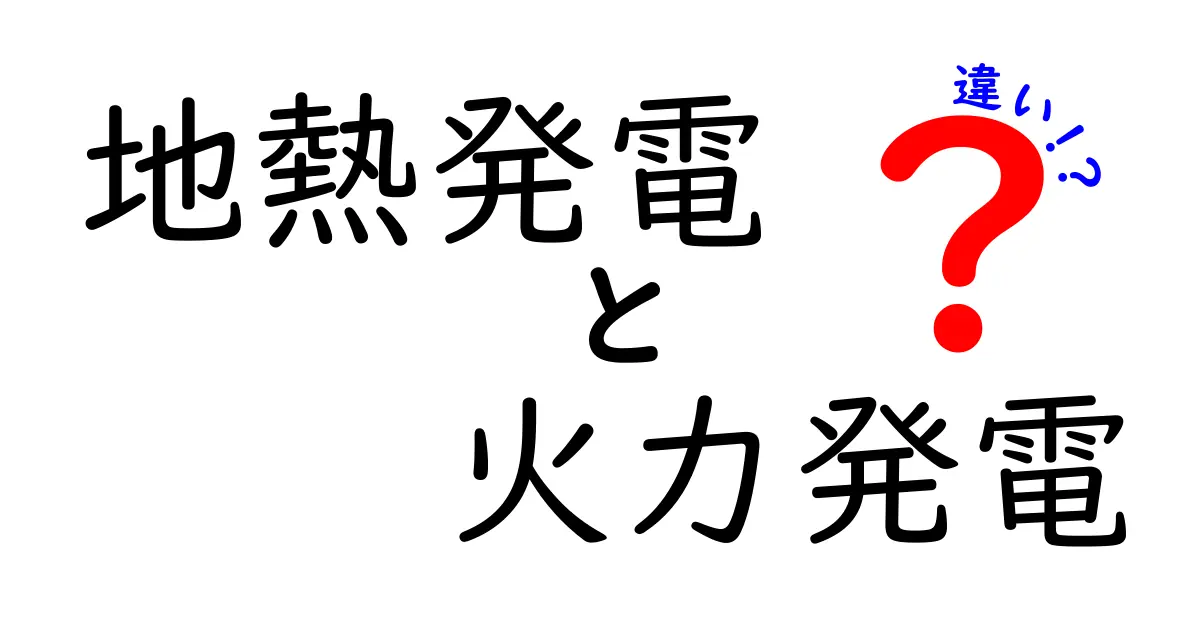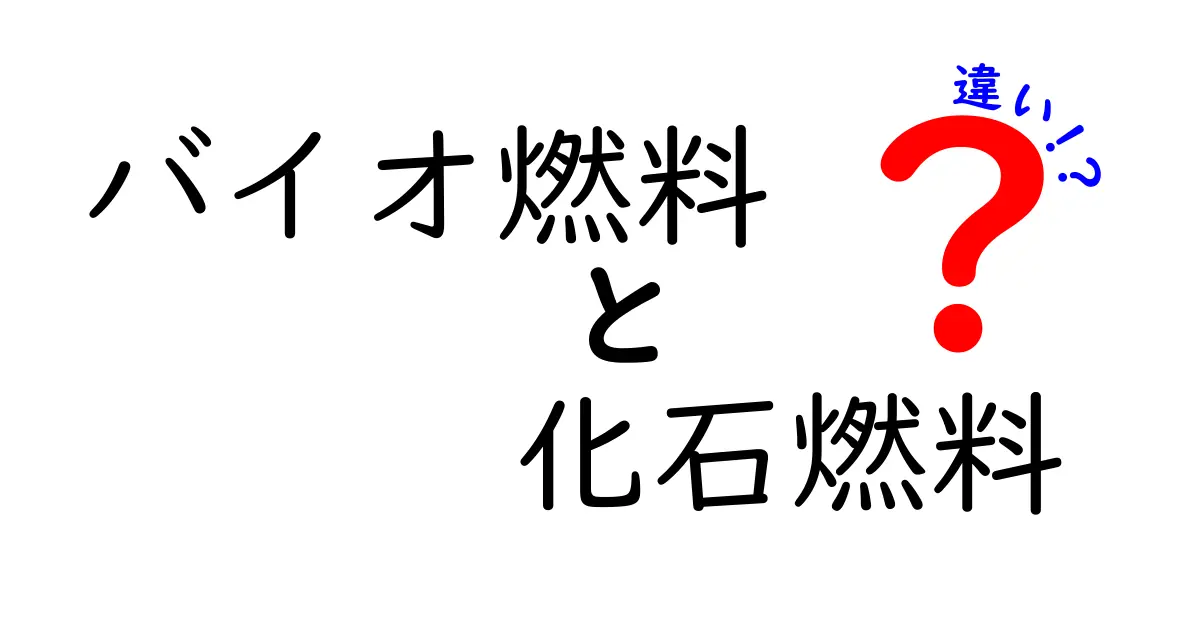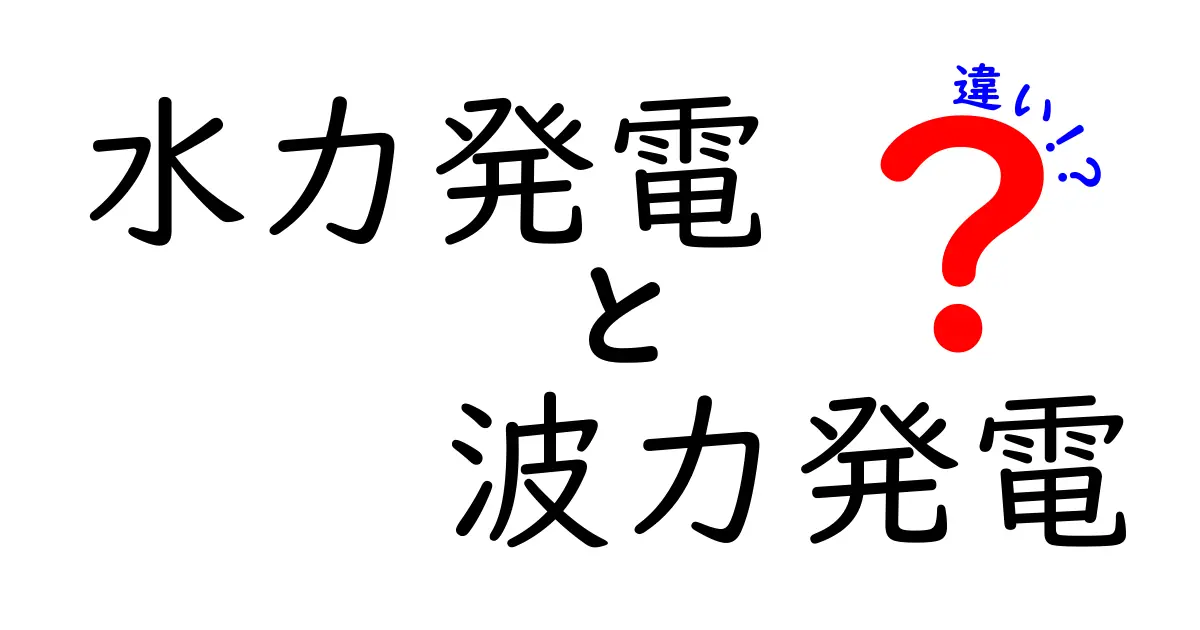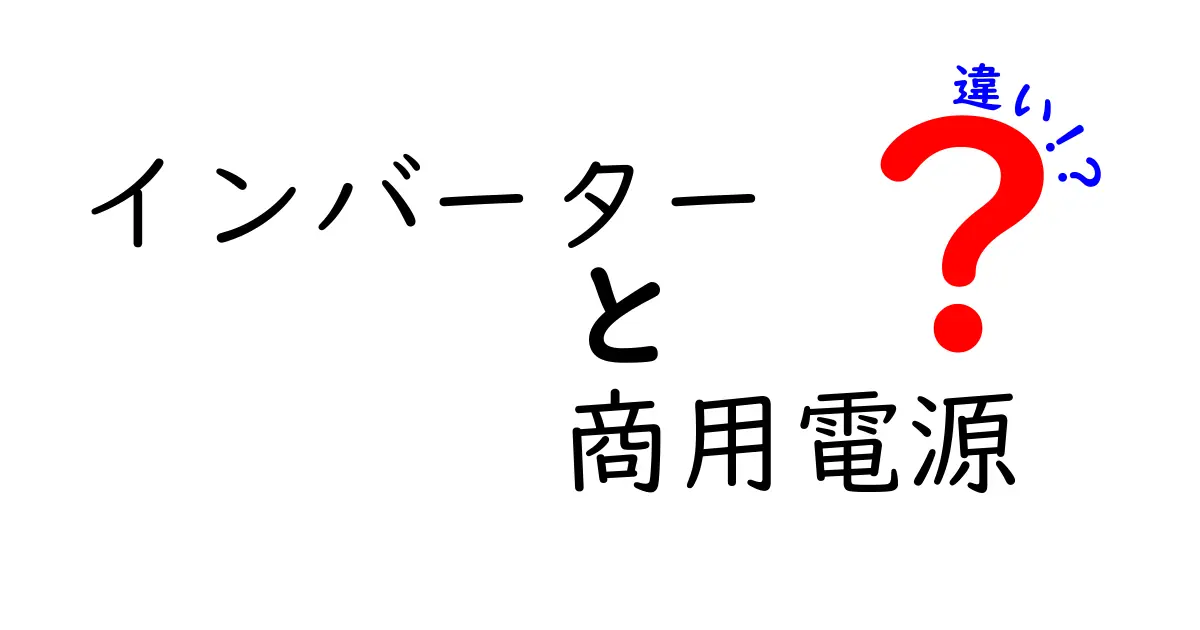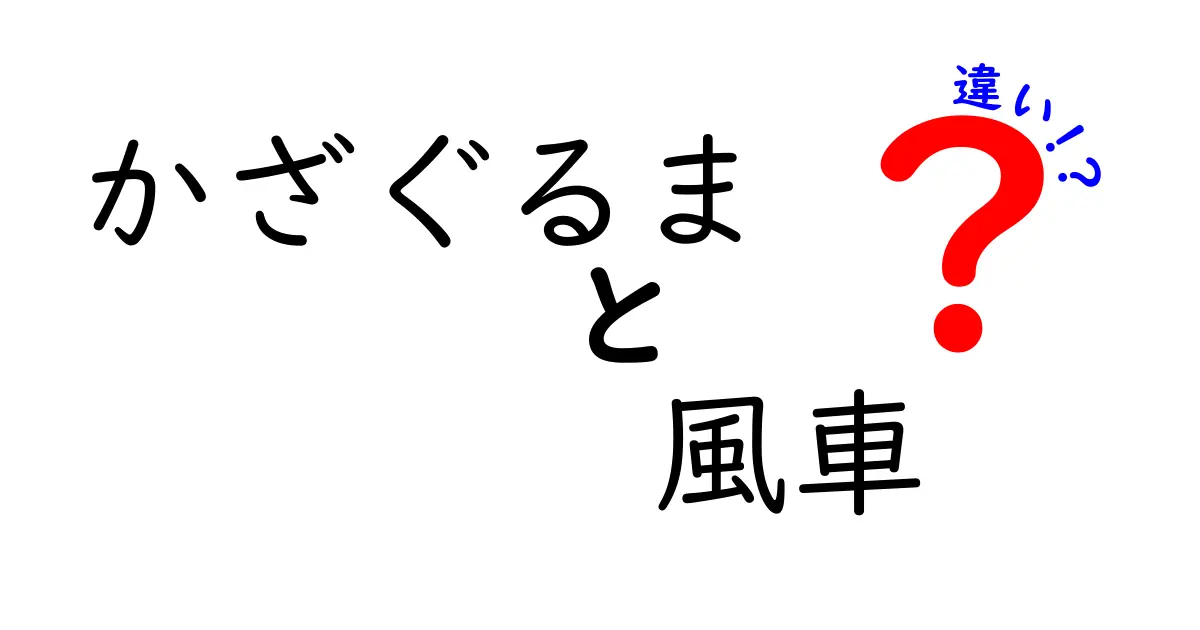
かざぐるまと風車は何が違う?基本の違いを知ろう
まずはじめに、かざぐるまと風車という言葉は、一見似ているようで実は違うものを指しています。
かざぐるまは子どもが遊ぶおもちゃで、風を受けてくるくる回る小さな装置のことを言います。
一方、風車は風の力を利用して動力や電気を生み出す機械の総称です。
この二つは見た目も用途もかなり異なり、混同して使われがちですが、それぞれの役割も異なります。
かざぐるまは主に飾りや玩具として使われ、風車はエネルギーを作るための道具という点が大きな違いです。
かざぐるまは軽くて小さいため、風がふけば簡単に回りますが、風車は大きくて強風を受けて回るようにできています。
ここからは、それぞれの特徴や種類、しくみ、使われる場面について詳しく見ていきましょう。
かざぐるまの特徴と構造について詳しく解説
かざぐるまは、風を受けると回転する小型のおもちゃで、昔から子どもたちに親しまれてきました。
一般的には、軽いプラスチックや紙でできた羽根(はね)が軸の周りについています。
風を受けると羽根が回転し、その動きが楽しくて目を引きます。
かざぐるまの特徴は、その簡単な構造と遊びやすさにあります。
たとえば、羽根の枚数や形状によって回りやすさや回転の速さが変わります。
また、色や柄が鮮やかなことが多く、子どもたちに人気です。
かざぐるまは動力を生むための機械ではなく、主に遊びや装飾を目的としたものです。
風の強さや方向によって回転速度が変わるのも魅力の一つです。
さらに、かざぐるまは風の方向を知る風向計としても使われることがあります。
ただし、これはあくまで簡易的なもので、正確な観測には向きません。
風車の種類と役割、仕組みを詳しく解説
風車は自然の風の力を利用して動力を生み出す機械で、その種類は大きく分けて「伝統的風車」と「現代的風車(風力発電用風車)」があります。
伝統的な風車は粉を挽いたり、水をくみ上げたりするために使われてきました。
対して現代の風力発電用風車は、風のエネルギーを電気に変換することを目的としています。
風車の基本的な仕組みは、羽根が風を受けて回転し、その回転力を軸を通じてモーターや機械に伝えることです。
羽根の形状は空気力学に基づいて設計されており、風を効率よく受け止めることで回転を最大化します。
風車は自然エネルギーの有効活用として注目されており、環境にやさしい電力供給手段の一つです。
風の強さや安定度が発電効率に大きく影響します。
また、風車の大きさや羽根の枚数は用途や設置場所によって異なります。
例えば、風力発電所に設置される風車は数十メートル以上の高さがあり、大型の羽根が力強く回ります。
かざぐるまと風車の違い一覧表
| 項目 | かざぐるま | 風車 |
|---|---|---|
| 主な用途 | 遊び・装飾・風向計 | 動力生産・電気発電 |
| 大きさ | 小型(数センチ〜数十センチ) | 大型(数メートル〜数十メートル) |
| 素材 | プラスチック・紙・軽い素材 | 金属・強化プラスチック・木材 |
| 回転原理 | 風の力で羽根が自由に回転 | 空力設計された羽根で効率よく回転 |
| 目的 | 風の動きを楽しむ | 動力や電気を作る |
風車の羽根の形は、ただ丸いだけではありません。実は、風を効率よく受けて回るために、飛行機の翼と似た形『翼型』をしています。これにより、風の力を最大限に活かして回転させることができるんです。かざぐるまは遊びの道具で羽根もシンプルな形が多いですが、風車の羽根形状は科学の結晶と言えますね。
次の記事: PCUとインバーターの違いとは?初心者でもわかる基本解説! »