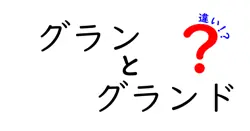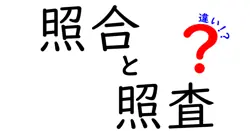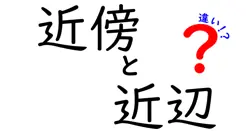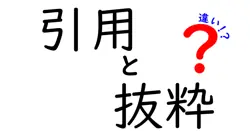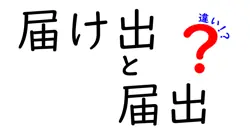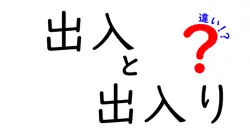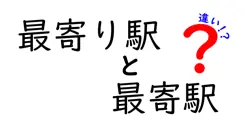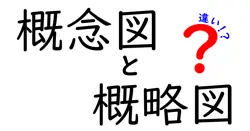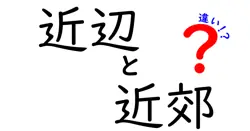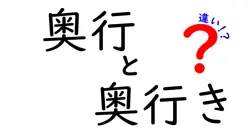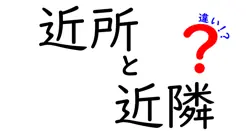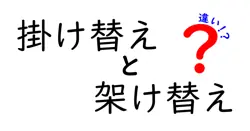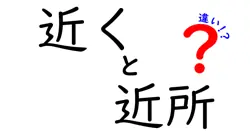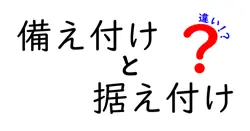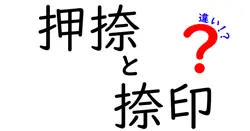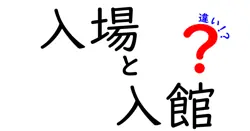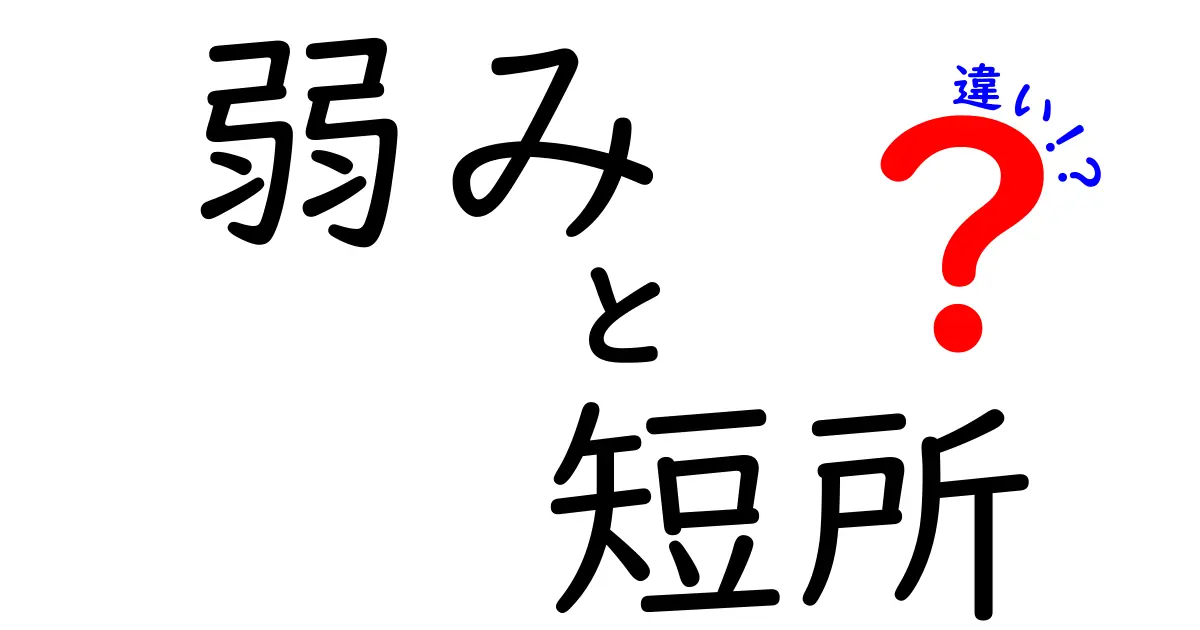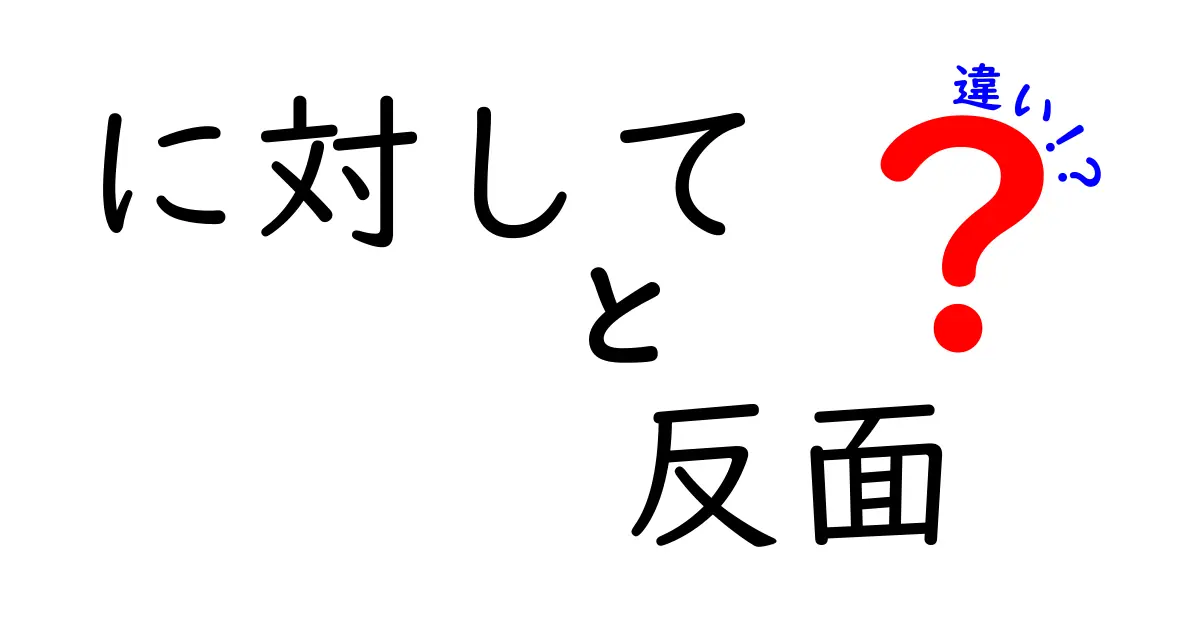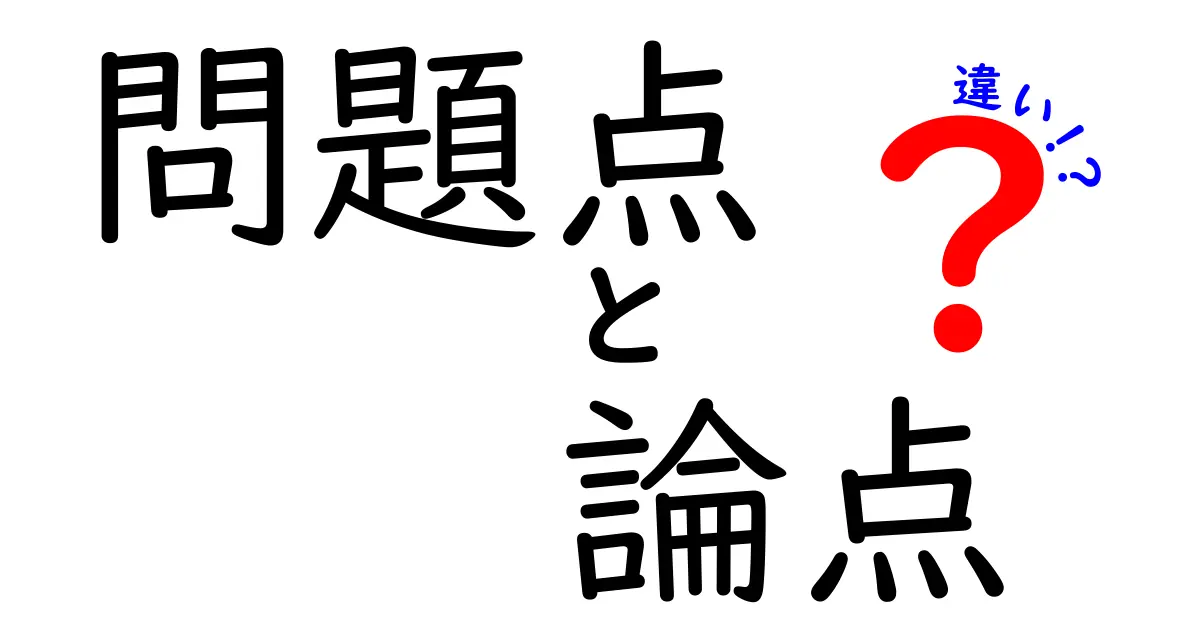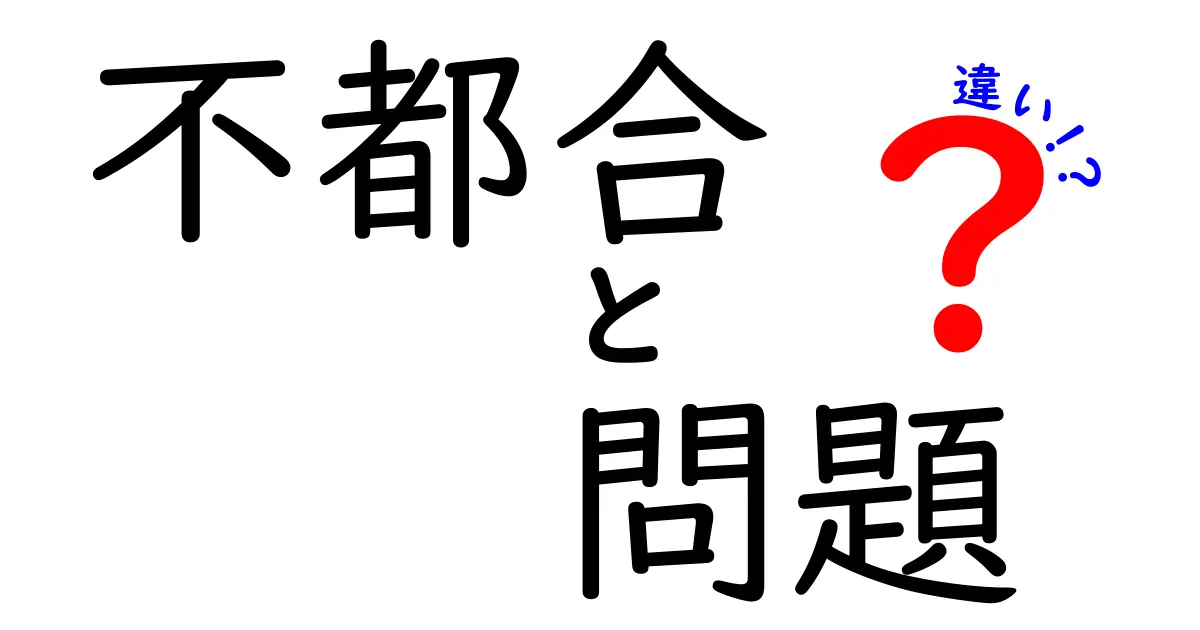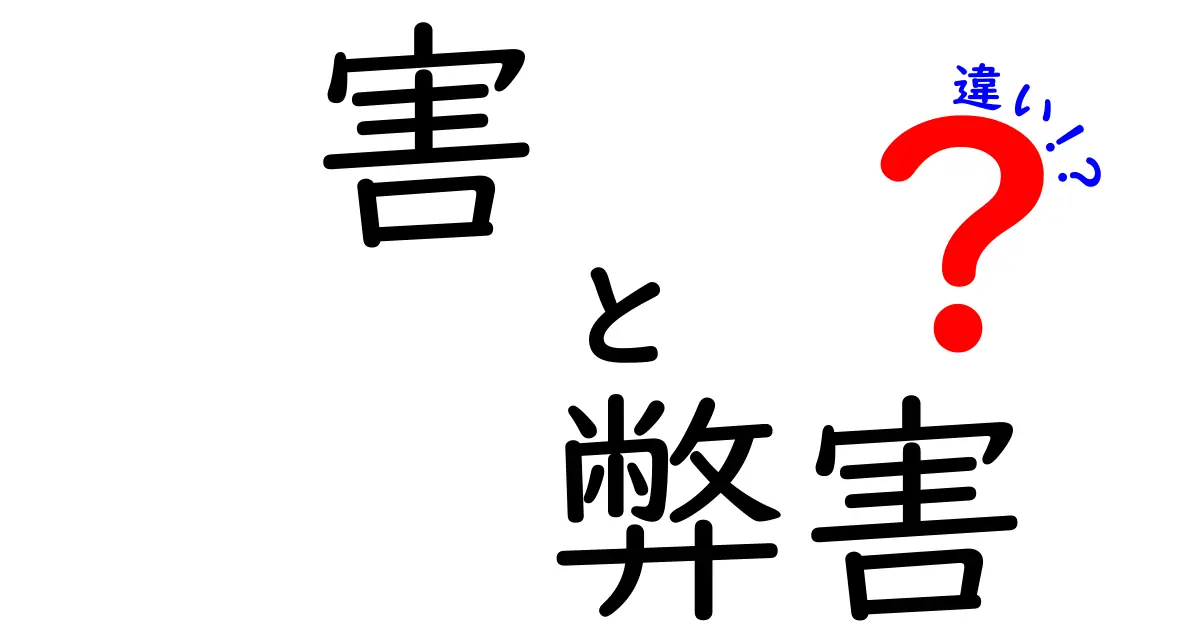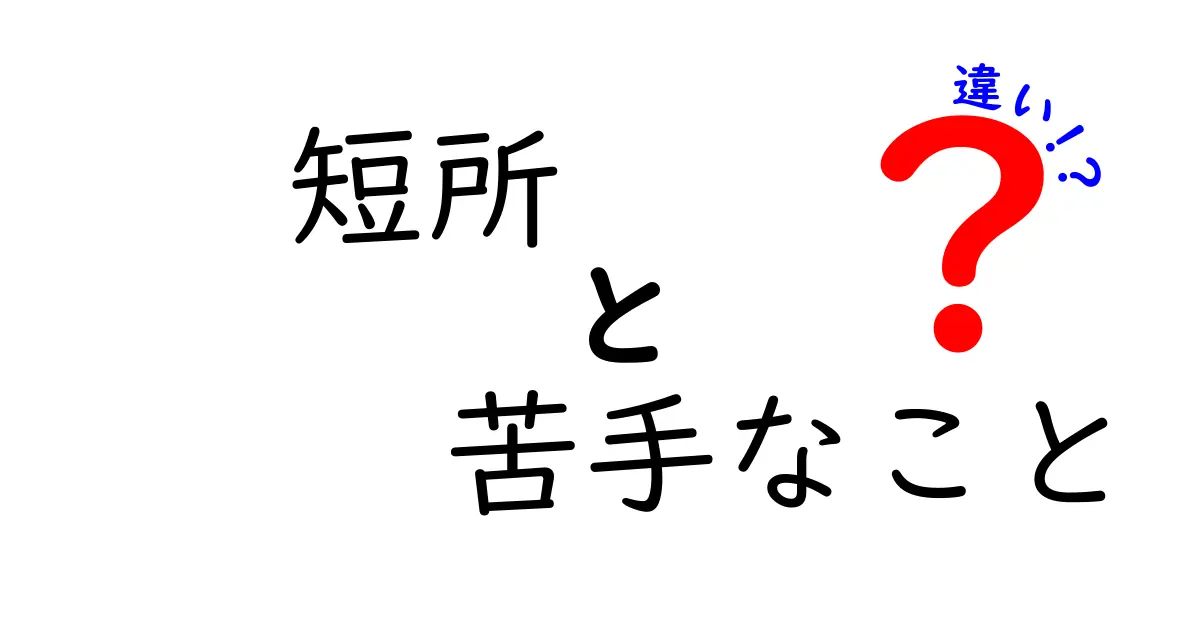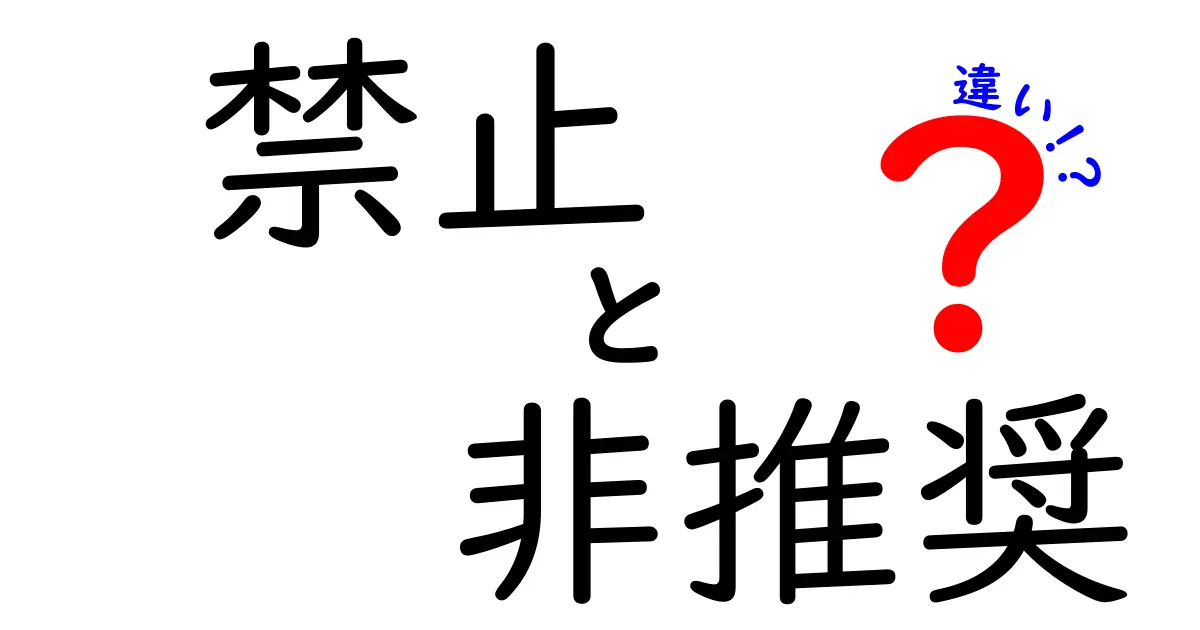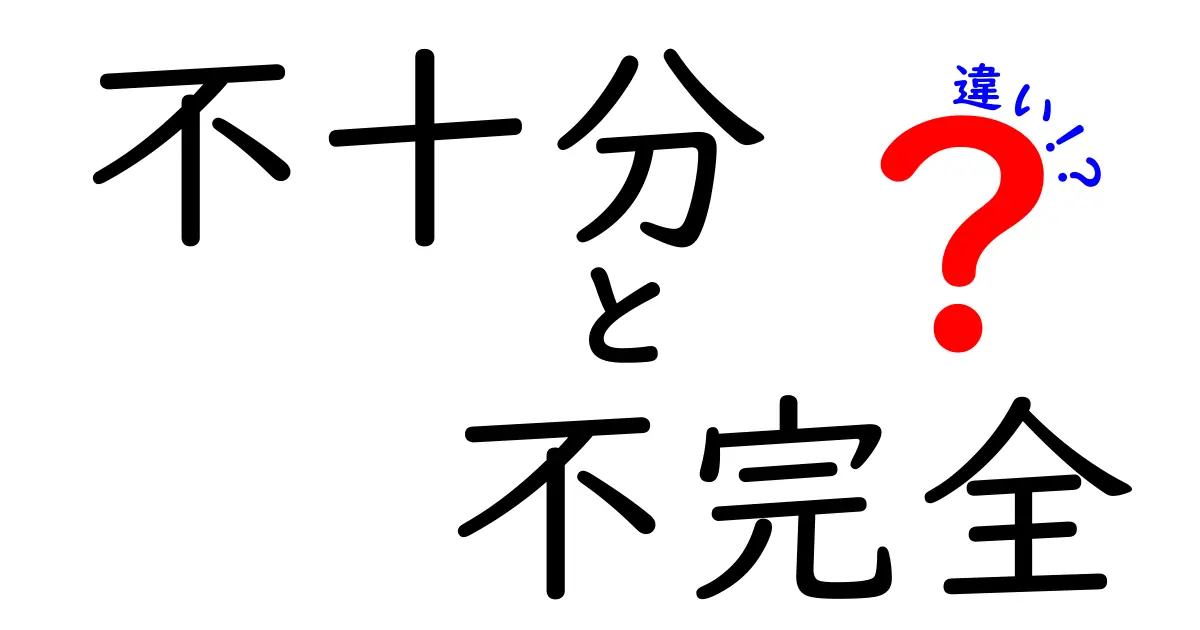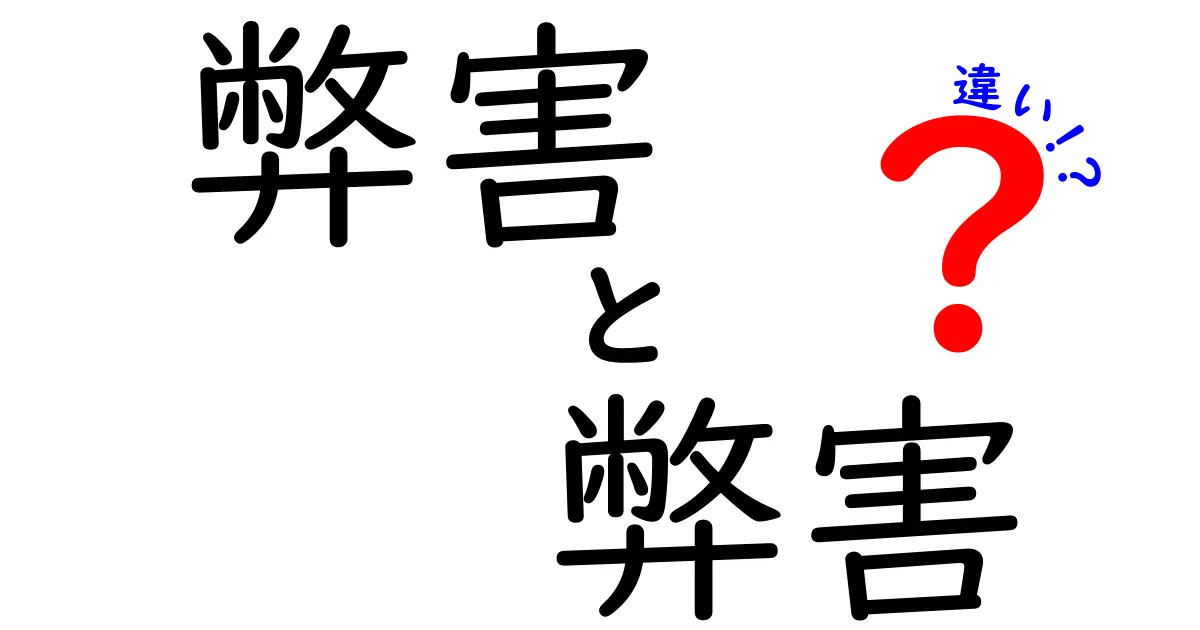
弊害と害悪の違いとは?基本的な意味を理解しよう
「弊害(へいがい)」と「害悪(がいあく)」は、どちらも悪い影響を示す言葉ですが、使われる場面やニュアンスが少し異なります。まずはそれぞれの基本的な意味を見てみましょう。
「弊害」とは、ある物事や仕組みがもたらす思わぬ悪い影響や問題のことを指します。たとえば、新しい便利な技術が普及した結果、その技術の使用によって発生する悪影響も「弊害」と言います。
一方、「害悪」は文字通り、「害(害)+悪(悪)」と書き、直接的かつ重大な悪い影響や被害の意味を持ちます。たとえば、有害な物質や悪意のある行為を指して使われることが多いです。
このように、「弊害」は副次的に起こる問題、「害悪」は悪そのものや大きな害と覚えておくとわかりやすいです。
弊害と害悪の使い分け:具体例で確認しよう
ここでは「弊害」と「害悪」の違いをよりはっきり理解できるよう、いくつかの具体例を挙げます。
- 弊害の例
インターネットの普及によって便利になった反面、長時間の利用が目に悪影響を及ぼすことがある。これが「インターネット利用の弊害」と言えます。 - 害悪の例
有害な廃棄物を不法投棄することは環境への「害悪」となる行為です。こちらははっきりと悪いものとして扱われます。
このように、弊害は新しい発展や行動の中で出てくる副次的な悪影響を指し、害悪は元から悪いとされるものや重大な悪影響を指すのが特徴です。
また、会話や文章内での使い方も異なります。
「この政策にはいくつかの弊害があるため注意した方がいい」
→政策の中に予期せぬ問題が出てくるニュアンス。
「あの人物の行動は害悪そのものだ」
→主体が悪であることを強調しているニュアンス。
この違いを押さえておくと、伝えたい意味を正確に表現できます。
弊害・害悪のニュアンスを表で比較
ここで「弊害」と「害悪」の違いを簡潔にまとめた表を作成しました。
| 項目 | 弊害 | 害悪 |
|---|---|---|
| 意味 | 新しいことや制度から生じる副次的な悪影響 | はっきりとした悪い影響や被害 |
| 使われ方 | 主に物事の問題点や副作用を指す | 悪意や害を強調するときに使う |
| ニュアンス | 問題の原因は必ずしも悪意ではない | 害や悪意が根本にある |
| 例 | 政策の弊害、技術の弊害 | 環境への害悪、有害物質 |
この表を参考に、使い分けのポイントをイメージしてみてください。
弊害は「悪い結果が出る可能性」を示し、害悪は「悪いもの自体」を指すイメージです。
まとめ:正しい意味を理解し自然な使い分けを目指そう
「弊害」と「害悪」は似ている言葉ですが、意味・ニュアンス・使い方に違いがあります。
弊害は「新しいものや制度の良い部分の裏にある問題点や副作用」を表し、害悪は「悪そのものや強く悪影響を与える存在」を指します。
日常会話や文章で間違った使い方をすると、意味が伝わりにくくなることがあります。
したがって、「弊害」は新たなものの予期せぬ悪影響に注目するときに使い、「害悪」は明らかな悪や害を強調したい時に使うというポイントを押さえておきましょう。
これで「弊害」と「害悪」の違いを正しく理解し、適切に使い分けることができます。
ぜひ日々の言葉遣いで活用してくださいね。
「弊害」という言葉、よく考えると面白いですよね。普段は便利なものや制度に付随して起こる悪影響を指しますが、それが必ずしも悪意によって生まれるわけではないことがポイントです。たとえばスマホは生活をとても便利にしましたが、長時間使いすぎると集中力の低下など弊害が出ますよね。つまり、弊害は良いものの裏側に潜む“気をつけたい問題”なんです。だからこそ、弊害を見つけて対策することが未来をよりよくするために大切です。
前の記事: « 「弱み」と「短所」の違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: 「不完全」と「未完全」の違いとは?わかりやすく徹底解説! »