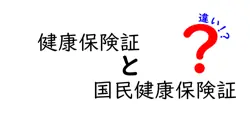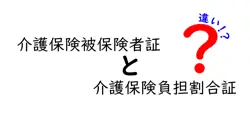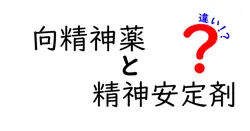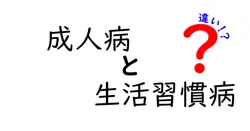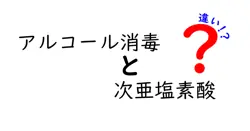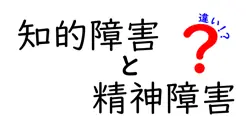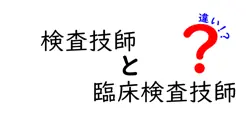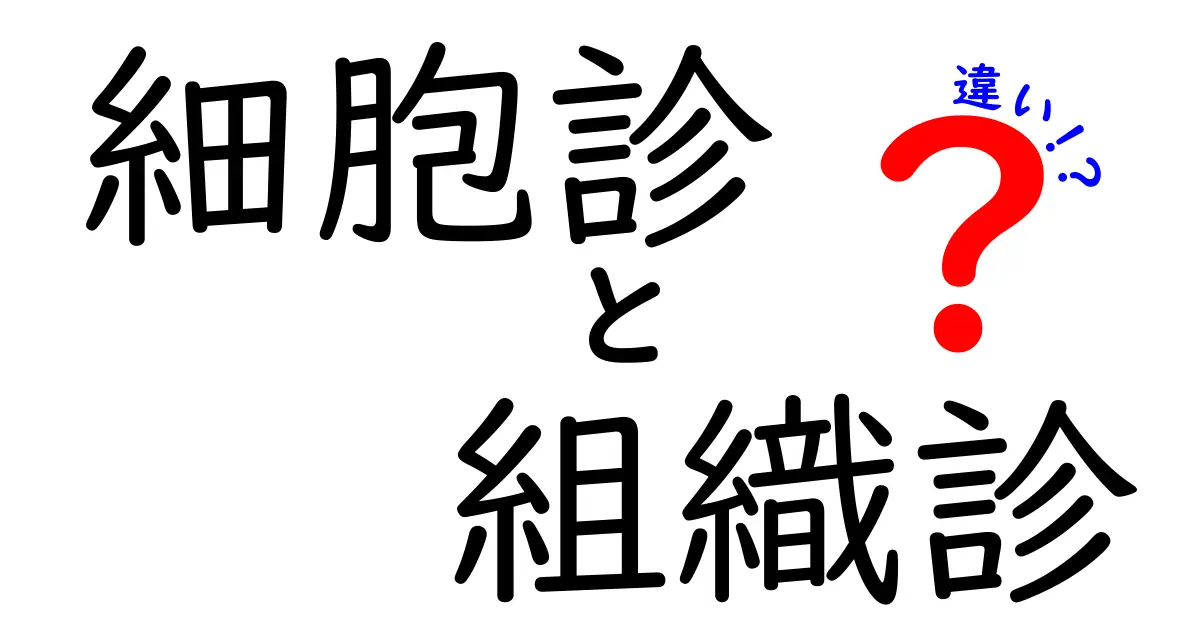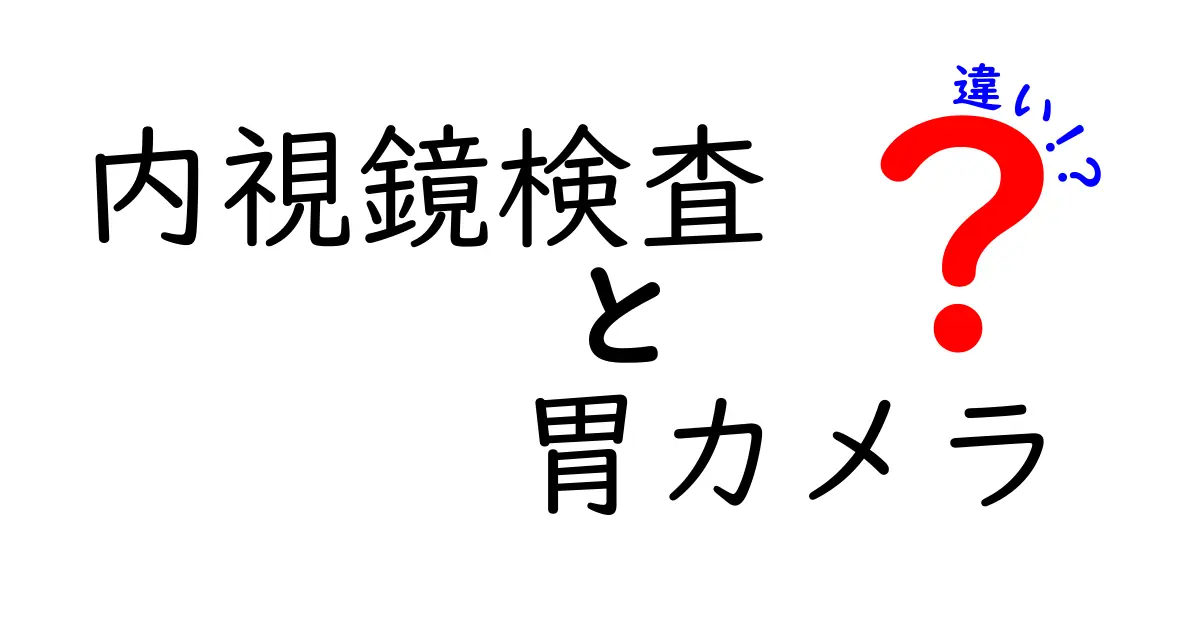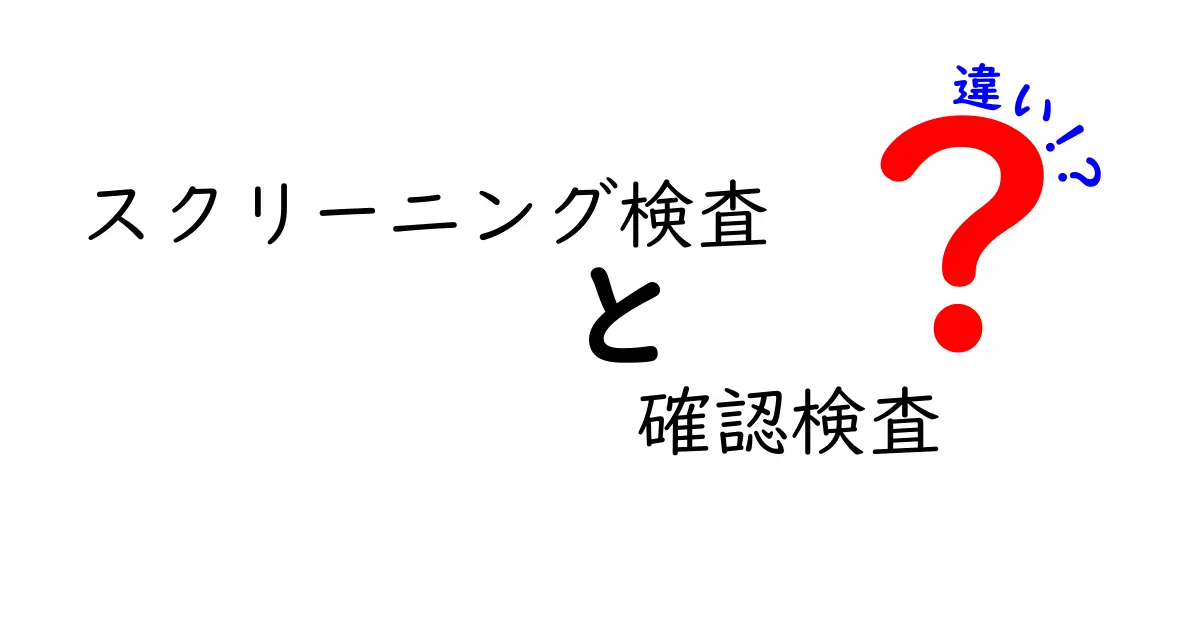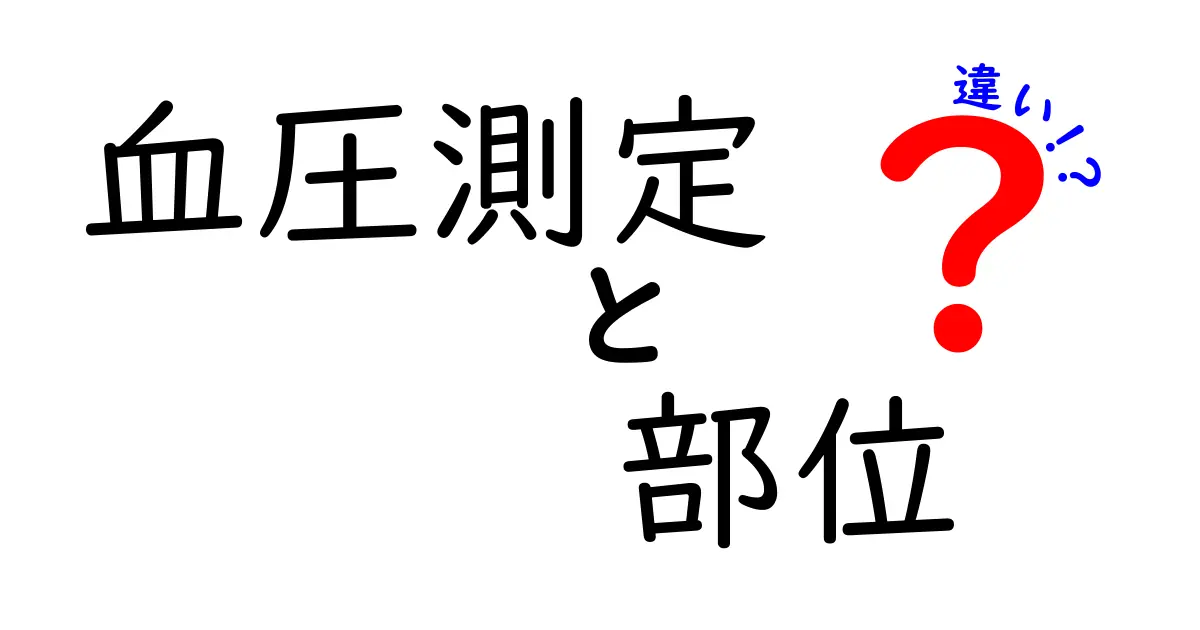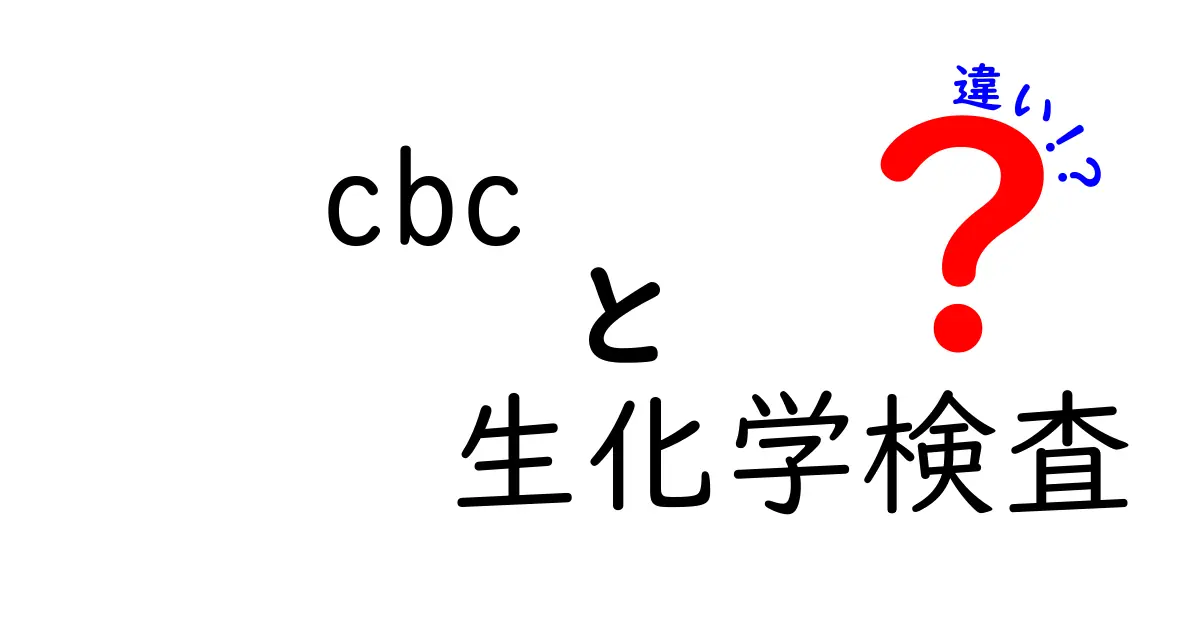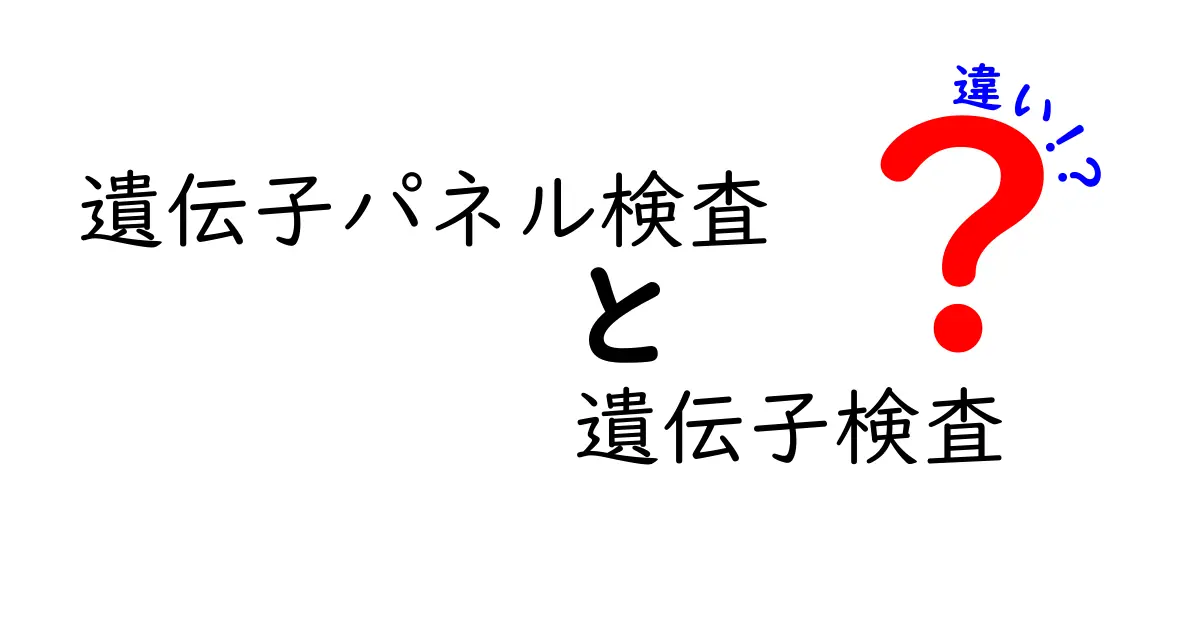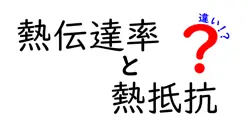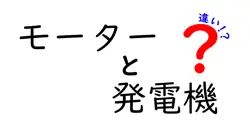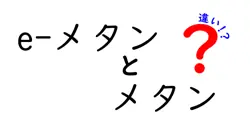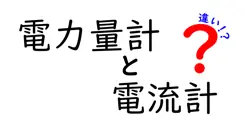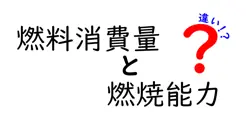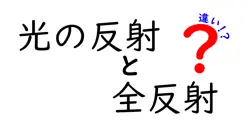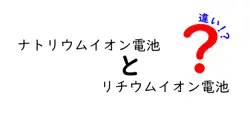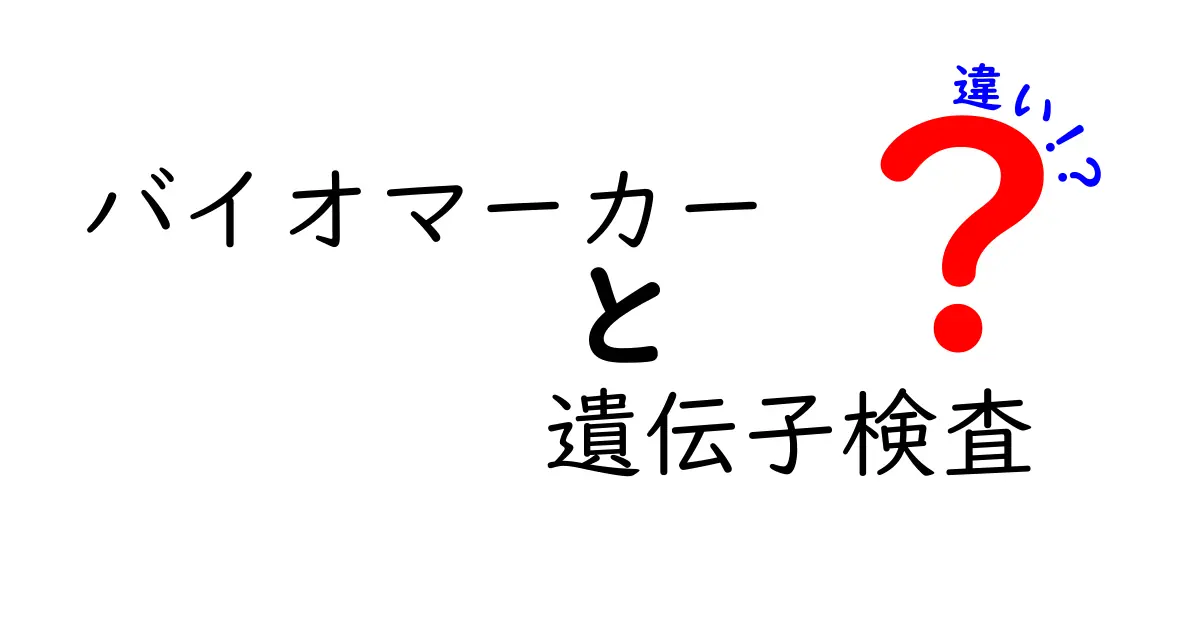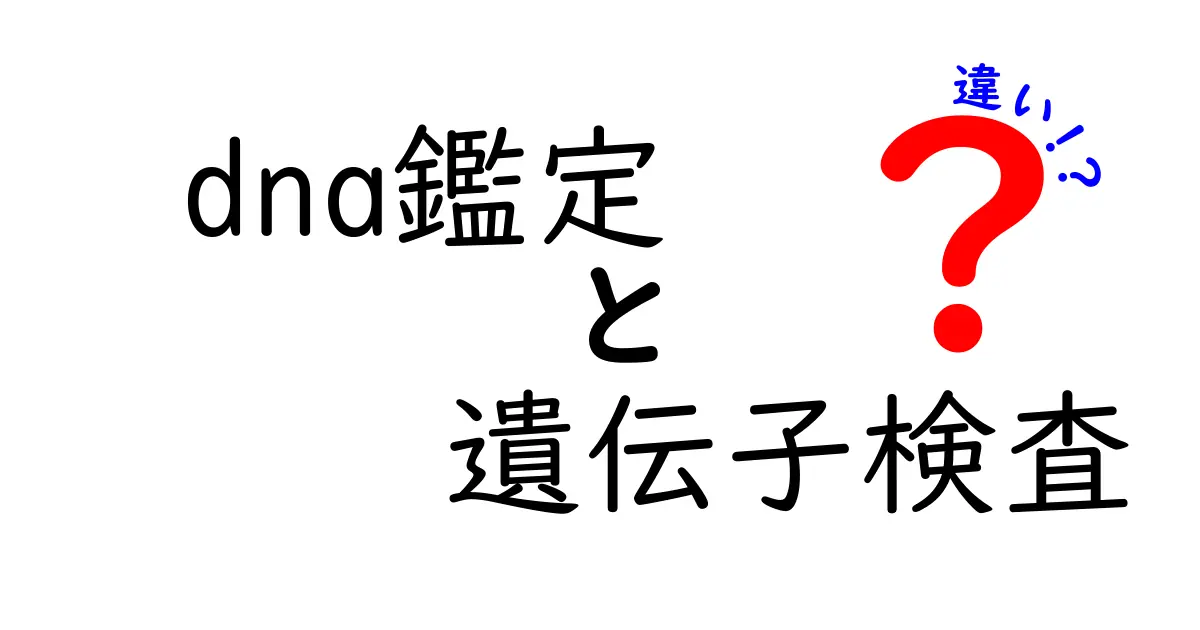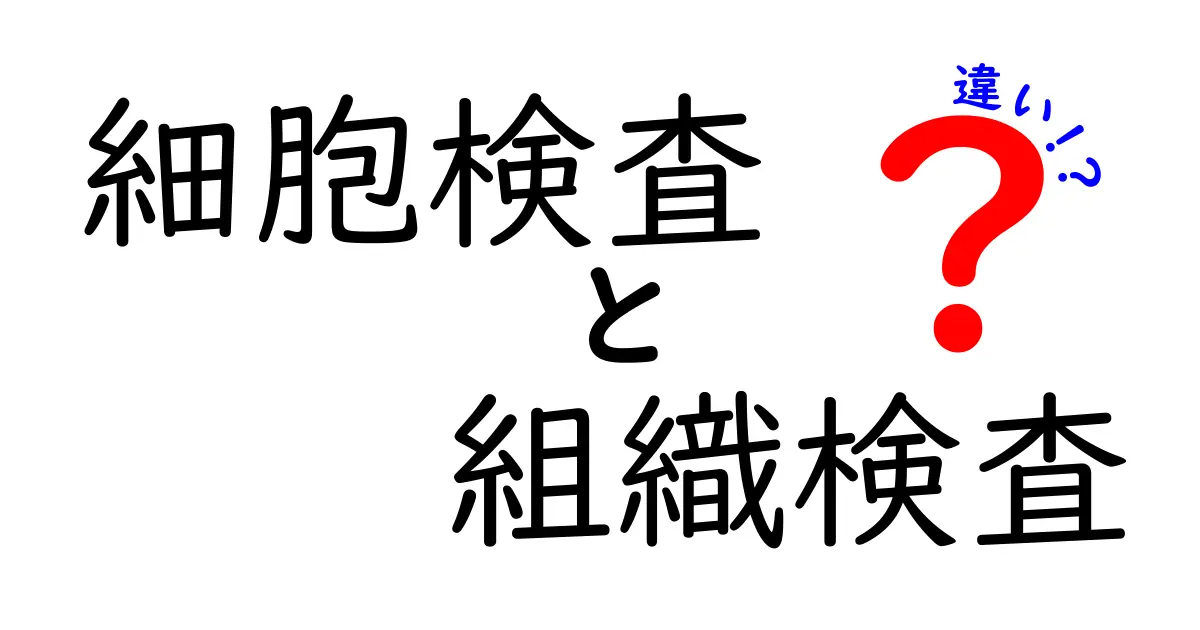
細胞検査と組織検査とは?基本の違いを理解しよう
病気の診断に使われる検査には、細胞検査と組織検査という主な種類があります。これらは見た目が似ているように思えても、検査の取り扱い方や検査結果の使い方に違いがあります。
まず、細胞検査とは、体の表面や体内の分泌物、例えば液体や擦り取った細胞を顕微鏡で調べる方法です。細胞単位での異常を調べることができ、非侵襲的で体への負担が少ないのが特徴です。
一方、組織検査は、病変部分の一部や全体の組織を採取し、細胞が集まった組織単位で詳しく調べます。細胞同士のつながりや組織の構造までわかるため、より精密な診断に向いていますが、検査には組織を取るための手術や生検が必要になることが多いです。
このように、細胞検査は細胞単体の異常を、組織検査は組織の形や成り立ちも含めて調べる違いがあります。
細胞検査と組織検査のメリット・デメリット比較
次に、細胞検査と組織検査、それぞれのメリットとデメリットを具体的に見てみましょう。以下の表をご覧ください。
| 検査 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 細胞検査 | - 体への負担が軽い - 短時間で結果が出る場合が多い - 簡単に検査できる部位が多い | - 組織の構造はわからない - がんの広がりや深さの診断は難しい - 偽陰性(見逃し)のリスクがある |
| 組織検査 | - 組織の形や細胞のまとまりを詳しく調べられる - がんの種類や進行度を詳細に診断できる - 正確な治療方針の決定に役立つ | - 侵襲的で痛みや出血のリスクがある - 検査に時間や手間がかかる場合がある - 患者の負担が比較的大きい |
| 項目 | 細胞診 | 組織診 |
| 検査対象 | 単細胞(細胞のみ) | 組織(細胞の集合) |
| 採取方法 | 擦過・吸引・洗浄 | 組織の一部を切除 |
| 痛みや負担 | 少ない | やや強い |
| 検査時間 | 短い | 長いことが多い |
| 診断の詳細度 | やや限定的 | 詳しい |
| 主な使用場所 | 子宮頸がん検査、喉などの表面部 | がんの確定診断、深い組織の検査 |
まとめ:どちらの検査が良い?
細胞診と組織診は、目的や状態に応じて使い分ける検査方法です。
細胞診は簡単で負担が少なく、初期のがんや炎症を調べるためによく使われます。
組織診は、細胞診で異常が見つかったときや、より正確な診断が必要なときに活用されます。
どちらの検査も、体の中の病気を見つけるために大切な役割を持っています。
検査を恐れず、医師のアドバイスに従って正しい検査を受けることが健康管理には重要です。
細胞診では、体の中から細胞をくり返し取り出す方法が特徴的です。たとえば、喉や子宮の表面から擦って細胞を集めますが、実はこの作業はとても繊細で、採取の仕方で検査結果に差が出ることもあるんです。細胞診は簡単そうに見えて、検査技師の腕もかなり重要なんですね。ちょっとした作業の違いが、病気の見逃しを防ぐカギになるなんて驚きですよね。