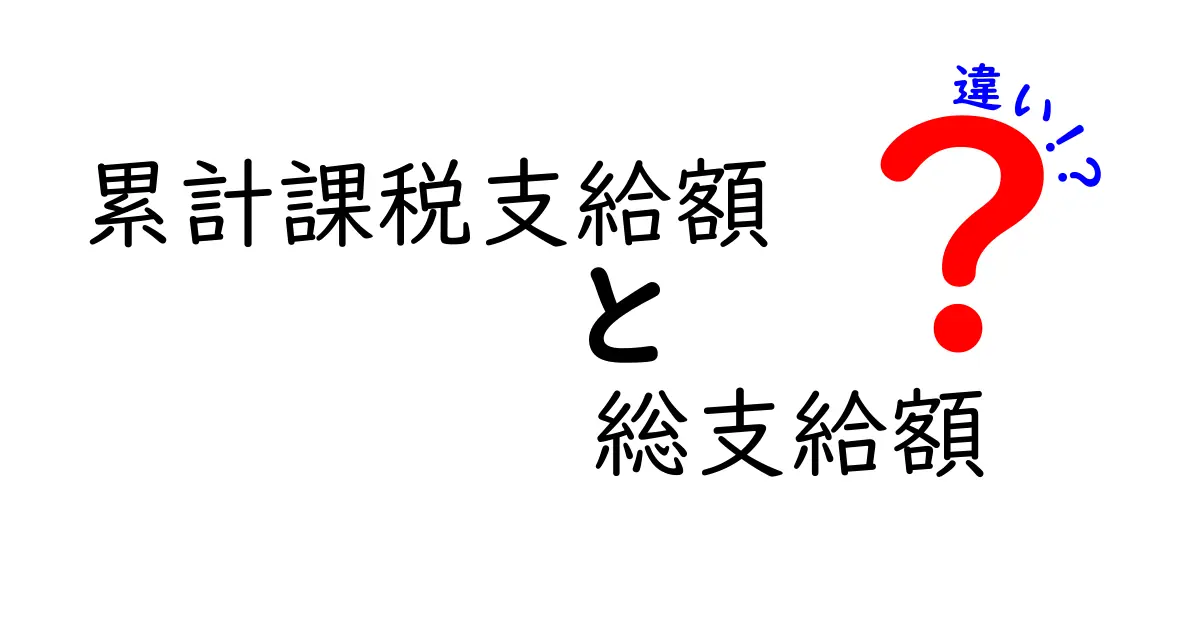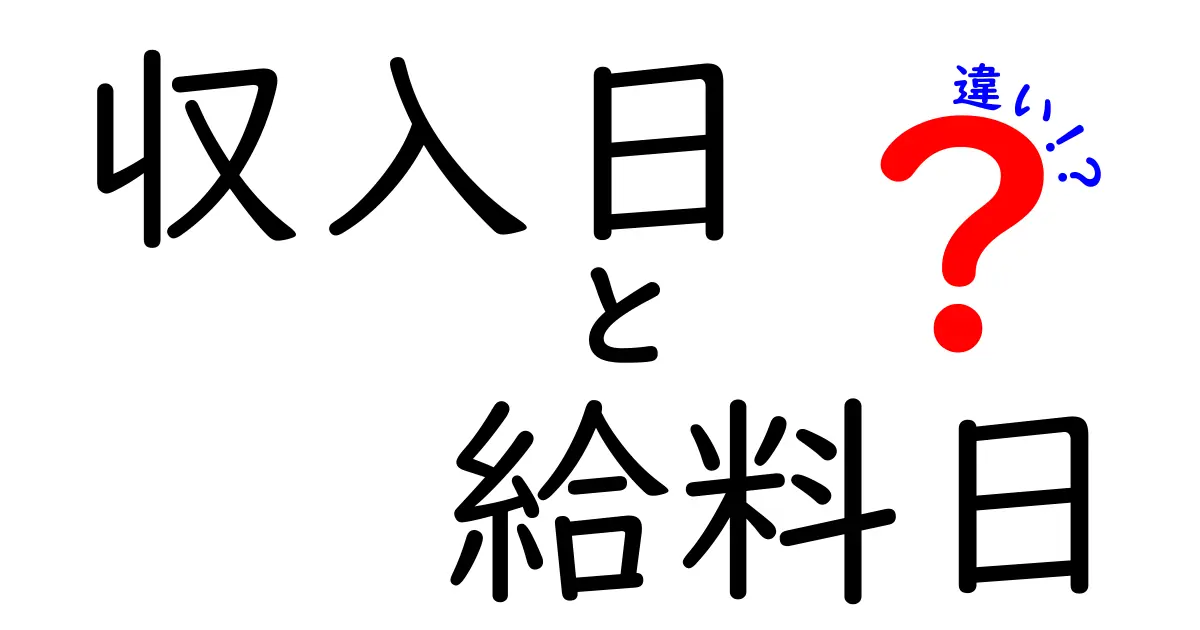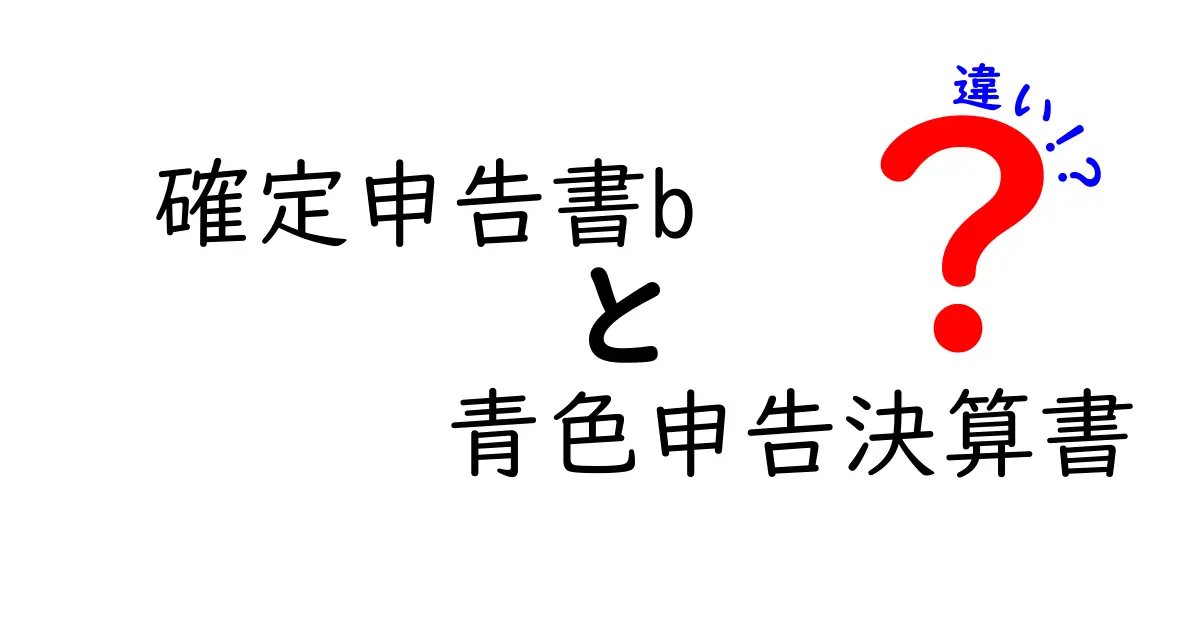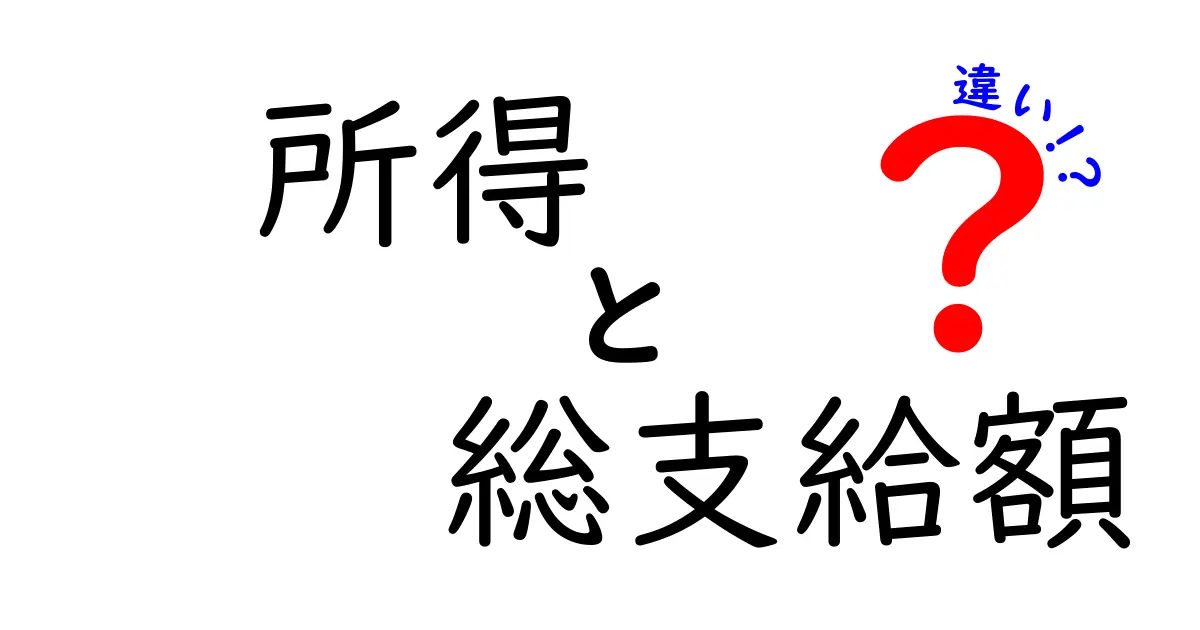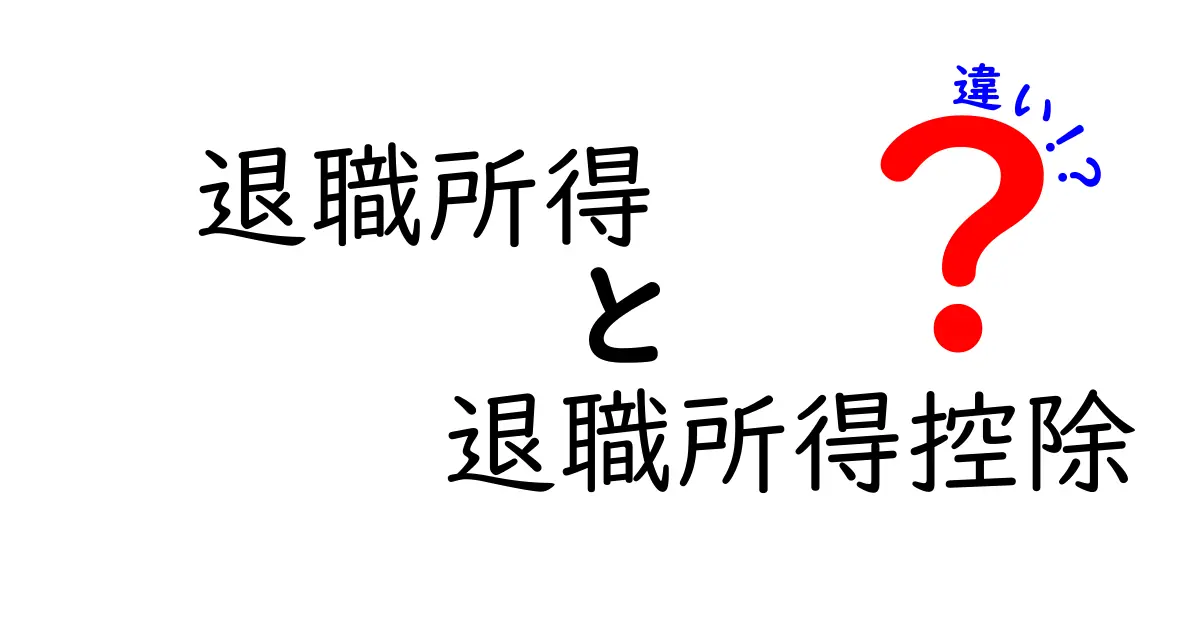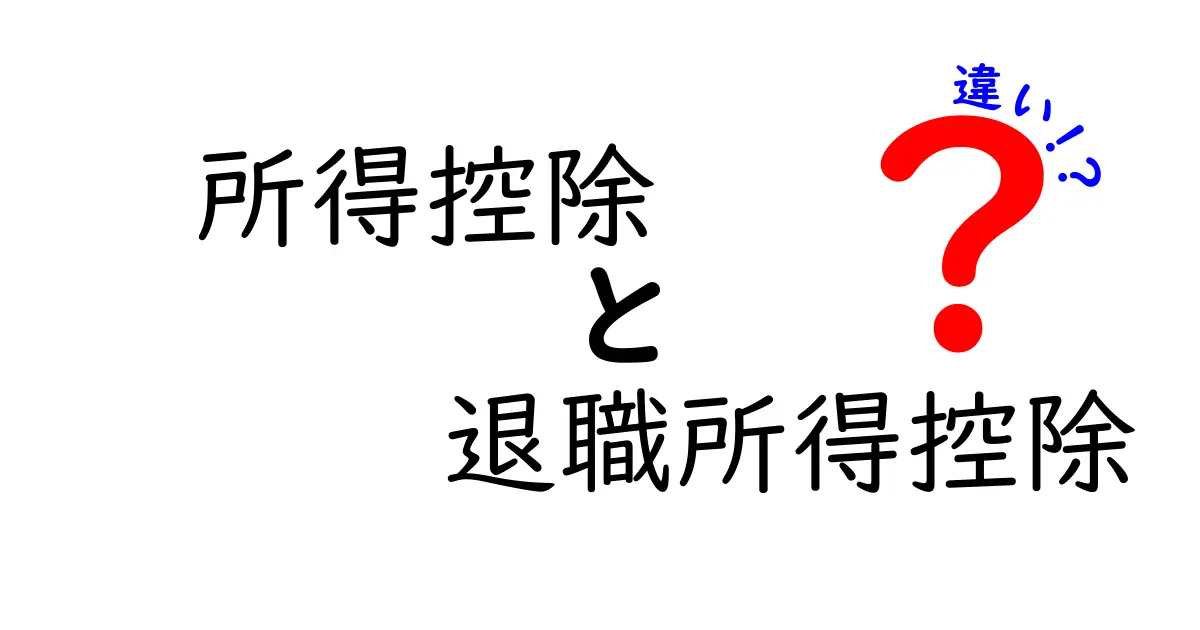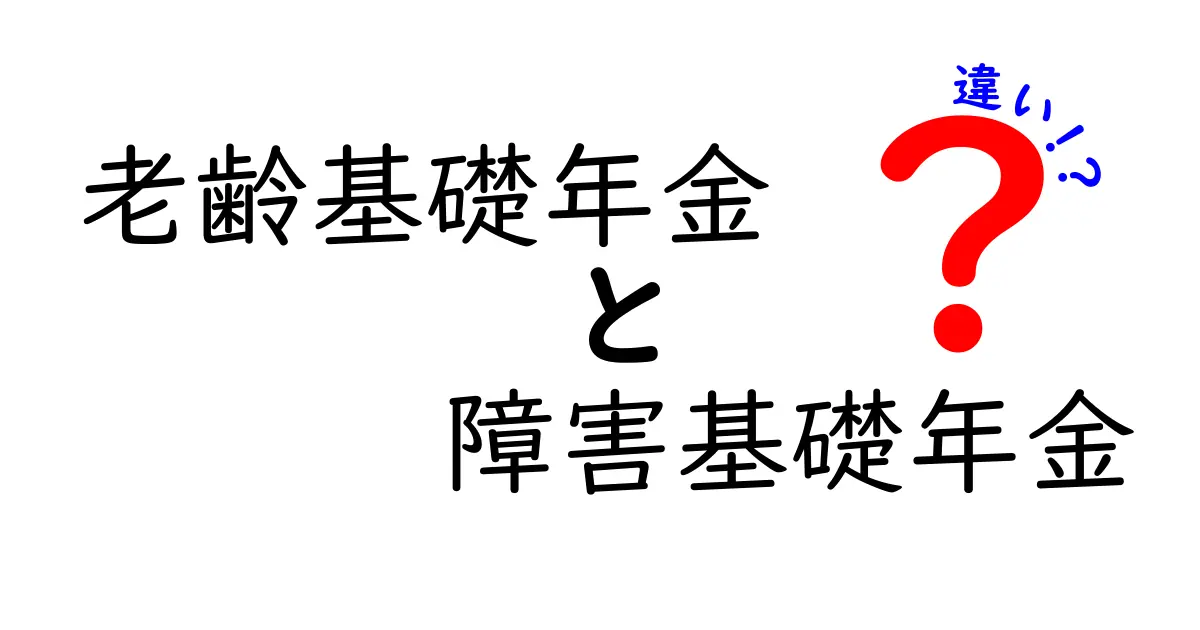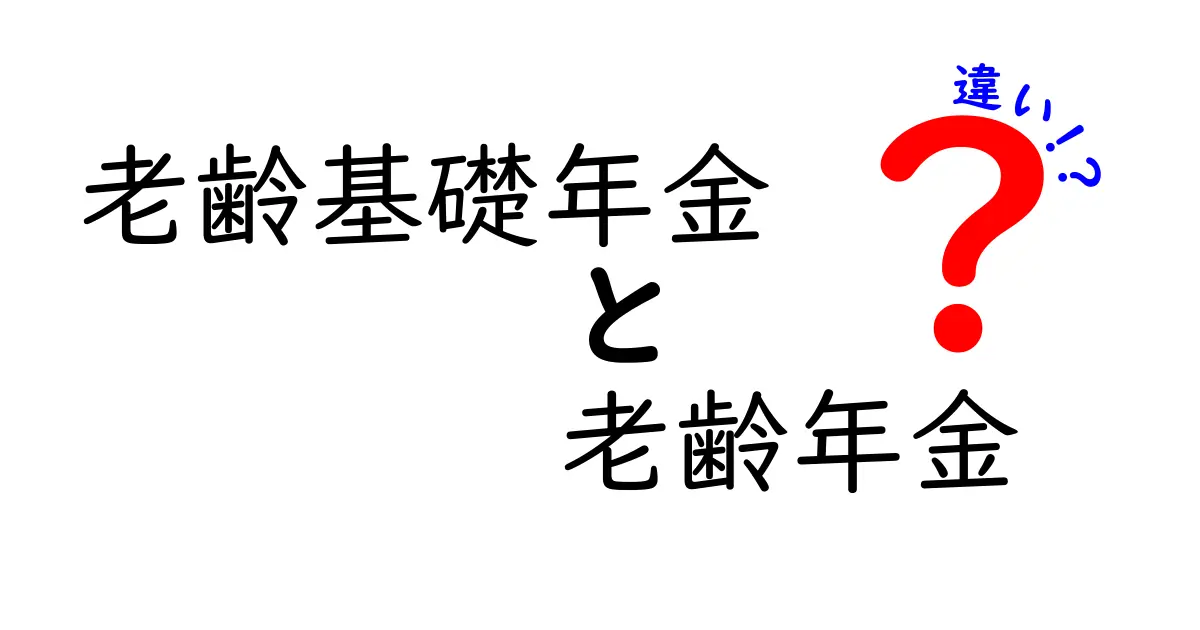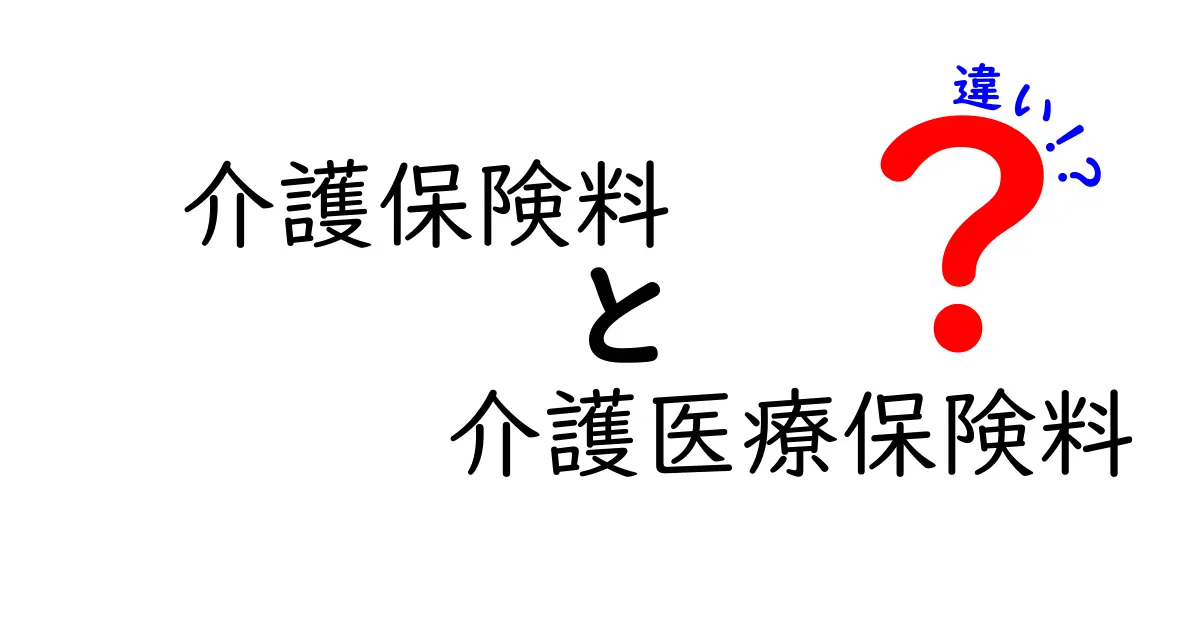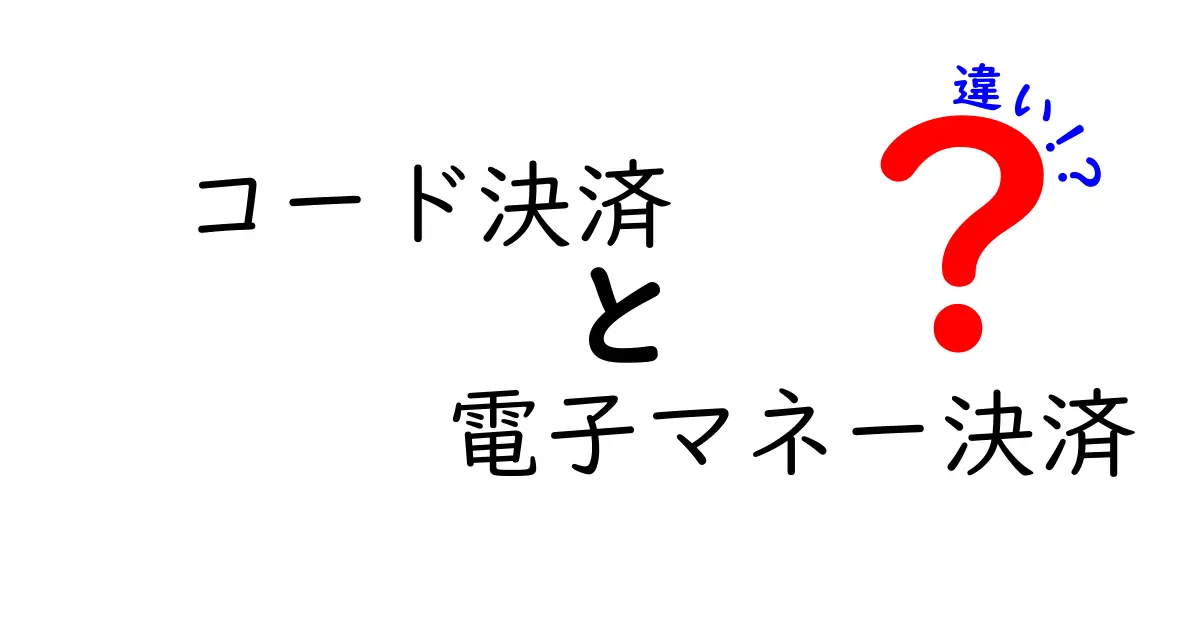

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コード決済と電子マネー決済の違いを理解する
コード決済はスマホのアプリに表示されるQRコードやバーコードを読み取って決済を完了するしくみです。店側には読み取り機があり、客が自分のアプリのコードを提示するだけで支払いが進みます。現金を使わずに会計を済ませられる点が大きな魅力です。特に若い世代にはポイント還元や期間限定のクーポンがつくケースが多く、買い物の楽しさが広がります。通信環境が必要な場合が多いので、ネットワークの安定性やアプリのアップデート状況を日頃から確認しておくと失敗が減ります。
一方、電子マネー決済は蓄えたお金を使うタイプです。あらかじめチャージをしておくと、支払い時にはその残高から自動的に引き落とされます。カード型やスマホのウォレットアプリを使い、店舗の端末にかざすだけで決済完了です。残高を管理できる点が特徴で、どれくらい使ったかを月ごとに見える化しやすく、使いすぎを防ぎやすいというメリットがあります。ただし、チャージを忘れると購入できなくなることもあるので、日ごろの予算管理を意識すると良いです。
コード決済と電子マネー決済の違いを整理すると、根本のポイントは決済の仕組みと残高の扱いです。コード決済はアプリ内のコードを読み取って資金を動かす仕組みで、現金の代わりとして使いやすい反面、通信状態やアカウントの安全性に左右されやすいという特徴があります。電子マネー決済はあらかじめチャージした金額を使うため、予算のコントロールがしやすい一方で、残高ゼロの状態では買い物を続けることができません。どちらもセキュリティ対策は重要で、スマホのロックとアプリの通知設定を有効にすることが基本です。
日常での使い分け方と注意点
日常の買い物では使い分けのコツを押さえるとストレスなく支払いが進みます。短時間で決済したいときはコード決済が便利です。会計のレジでスマホのコードをサッと読み取ってもらえば現金を出す手間がありません。反対に長時間の外出で予算をきっちり管理したい場合やポイント還元の条件が複雑なときは電子マネー決済を選ぶと良い場合があります。
また、セキュリティ面の注意点も覚えておきましょう。コード決済はアプリのアカウントが狙われると被害が広がることがあるため、パスワード管理や二段階認証、端末の紛失時の停止手続きが不可欠です。電子マネーはカード紛失時の停止機能やロック機能を有効にしておくと安心です。店舗での読み取り方の違いやカード式とスマホ式の違いを理解しておくとトラブルを避けやすくなります。
友達とカフェでコード決済と電子マネー決済の話をしていた時の会話です。A はコード決済の速さを絶賛しますが、通信トラブルが起きたらすぐに使えなくなる点を心配します。B は電子マネーのチャージ残高で財布を管理できる点を評価しますが、チャージを忘れずに済むように計画が必要だと言います。私は二人の意見を聞きながら、使い分けは場面次第だと気づきました。結局は日常で自分が最もストレスなく支払いを完了できる方法を選ぶのが一番だと感じます。