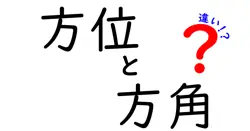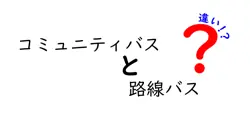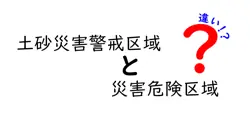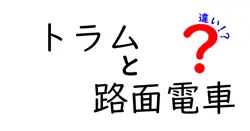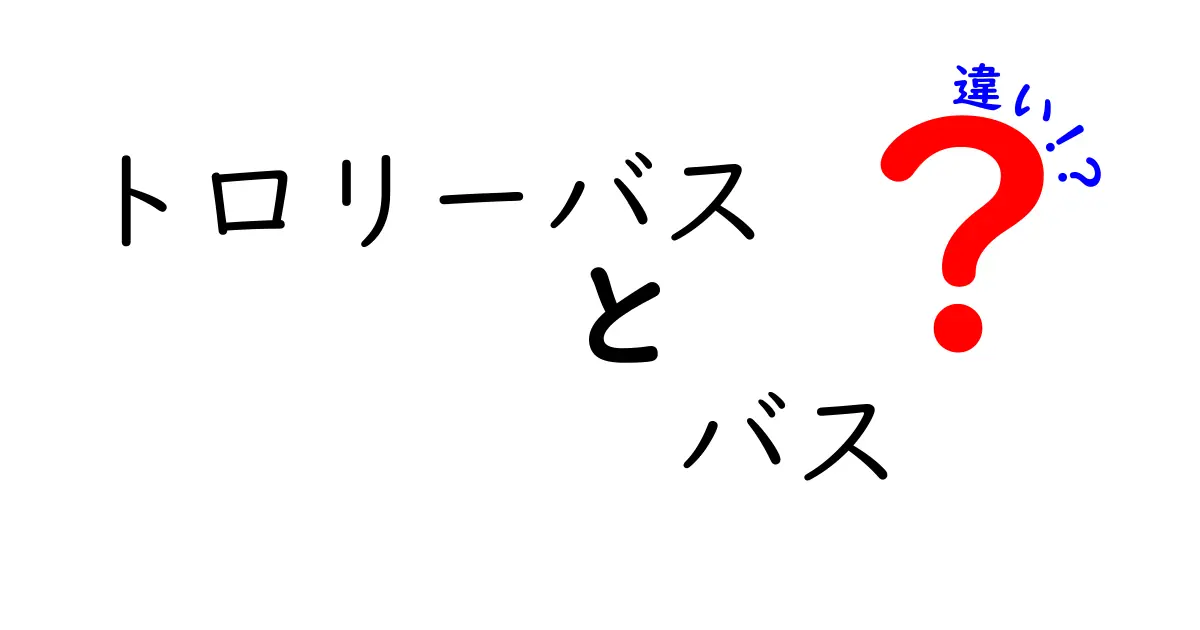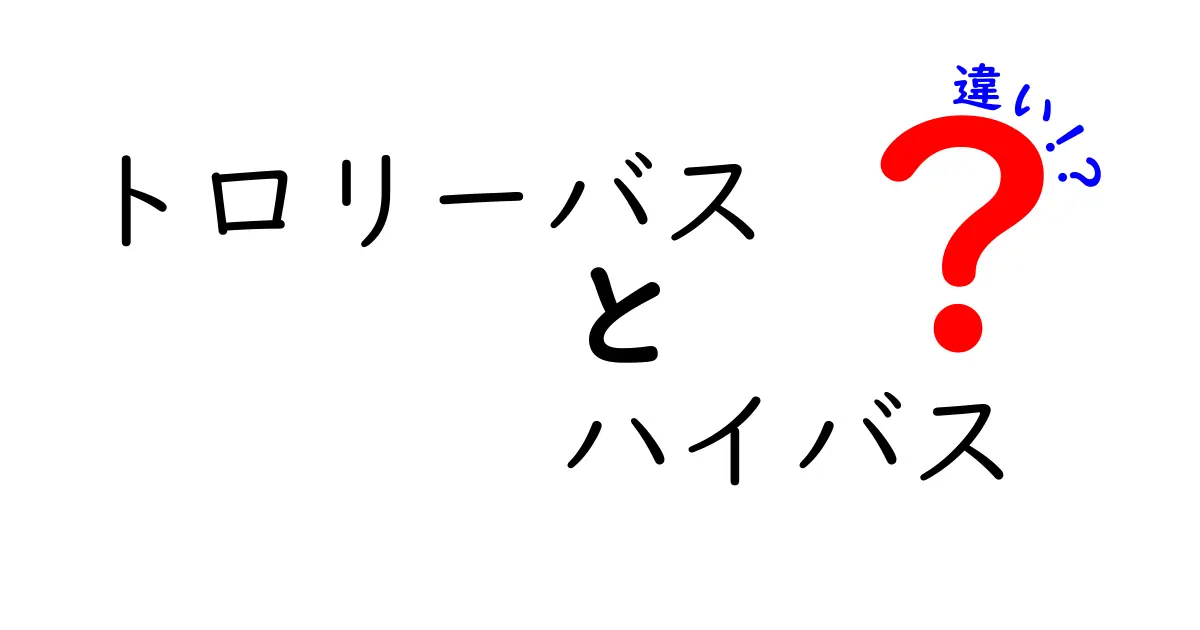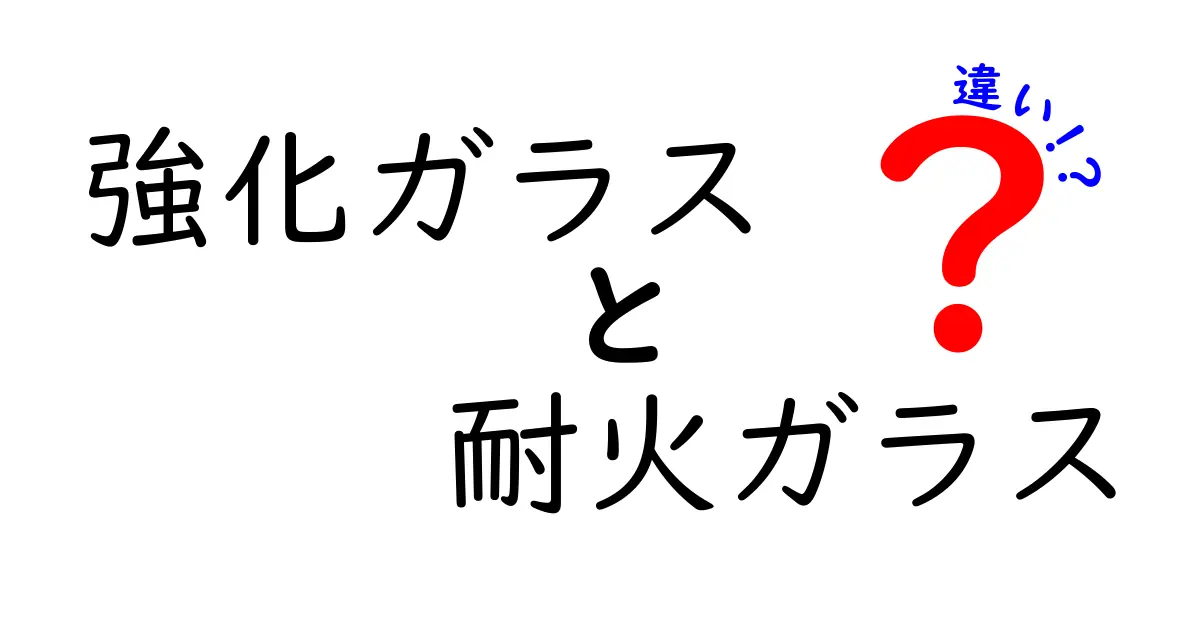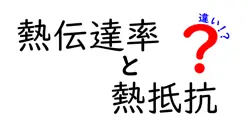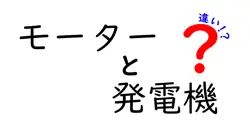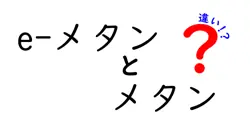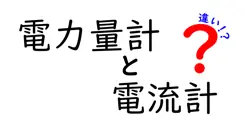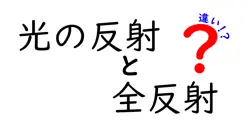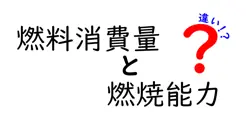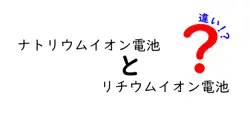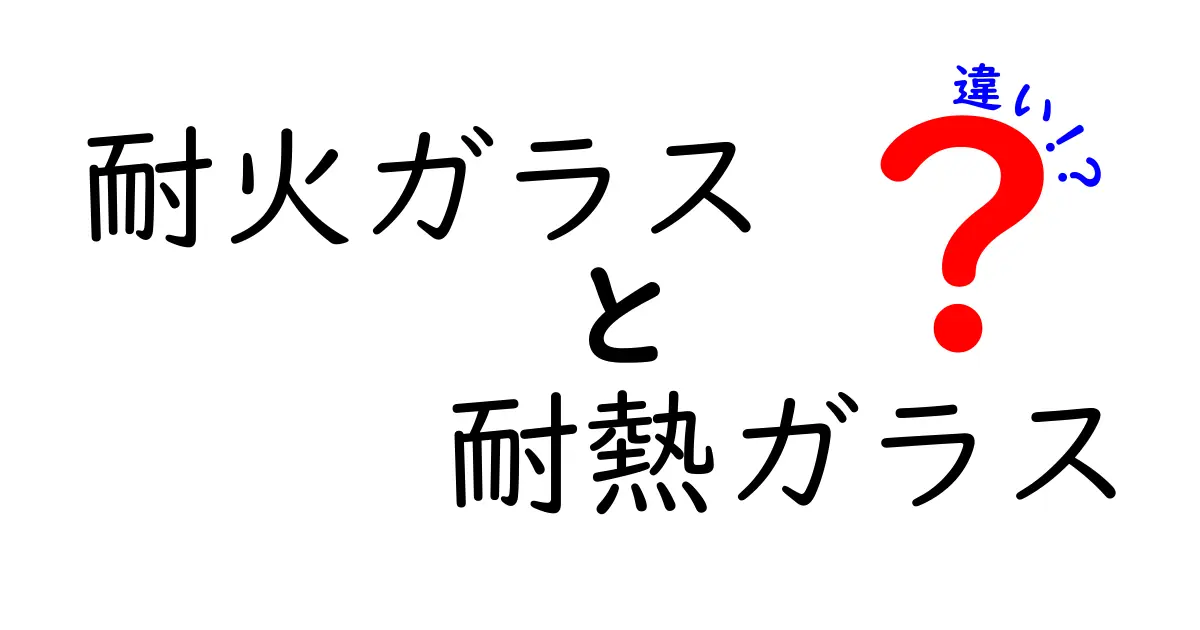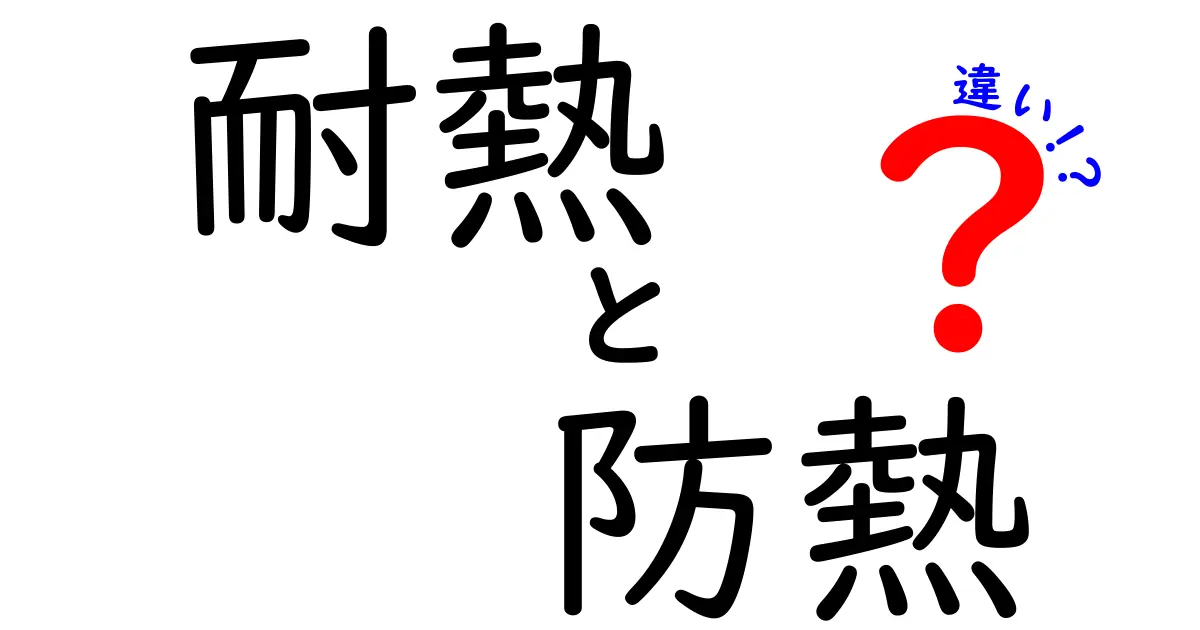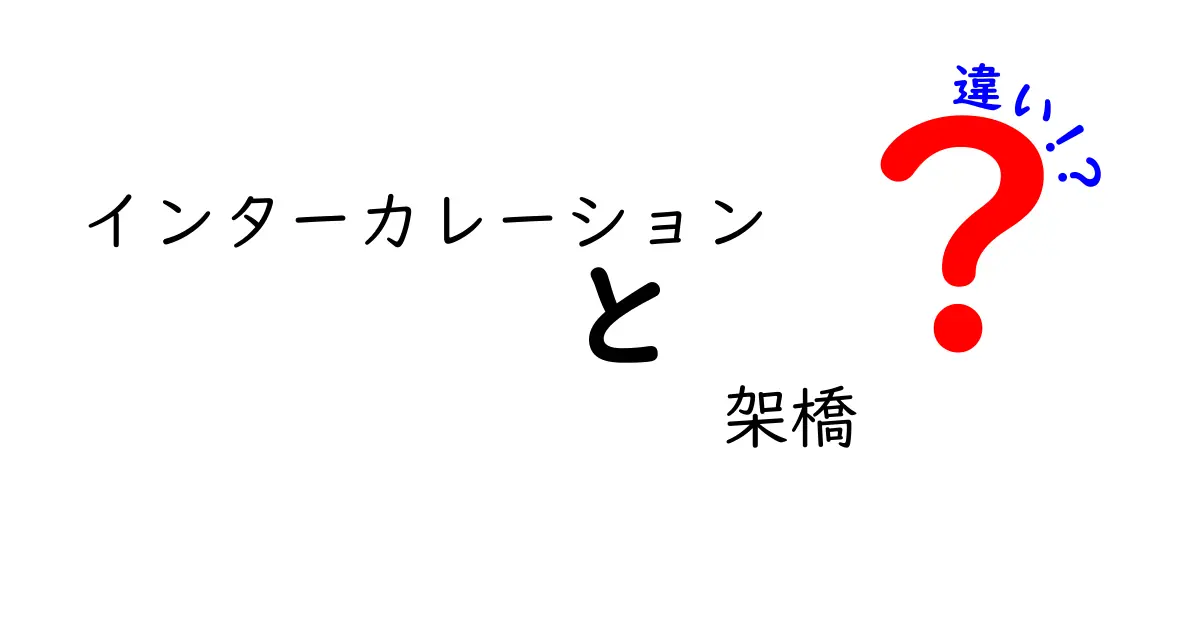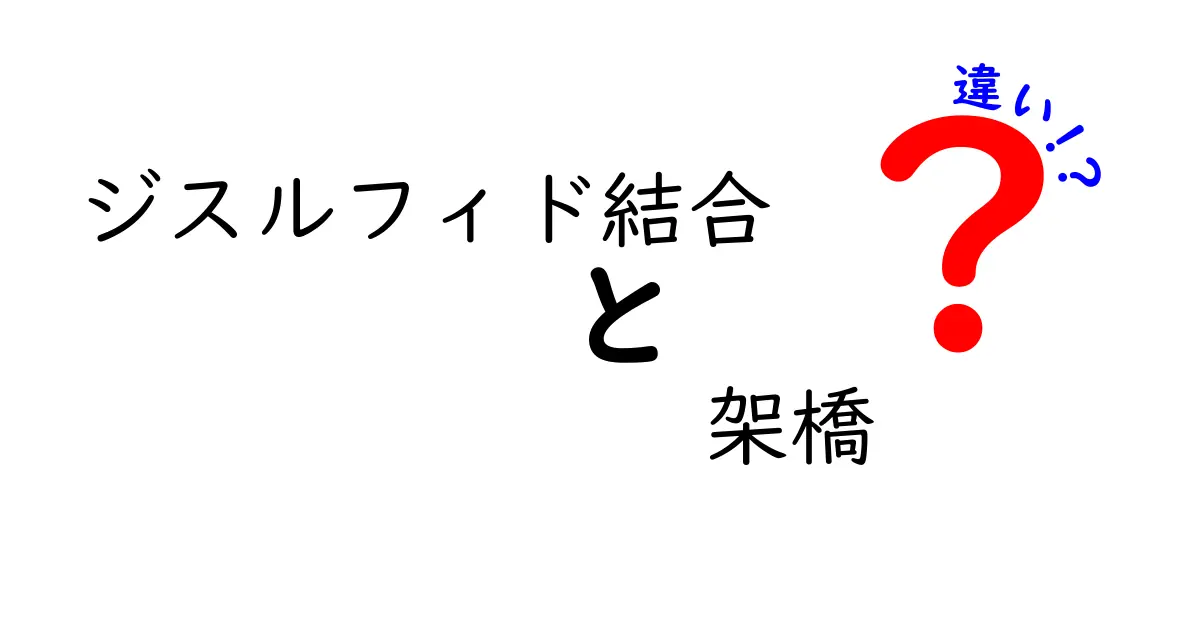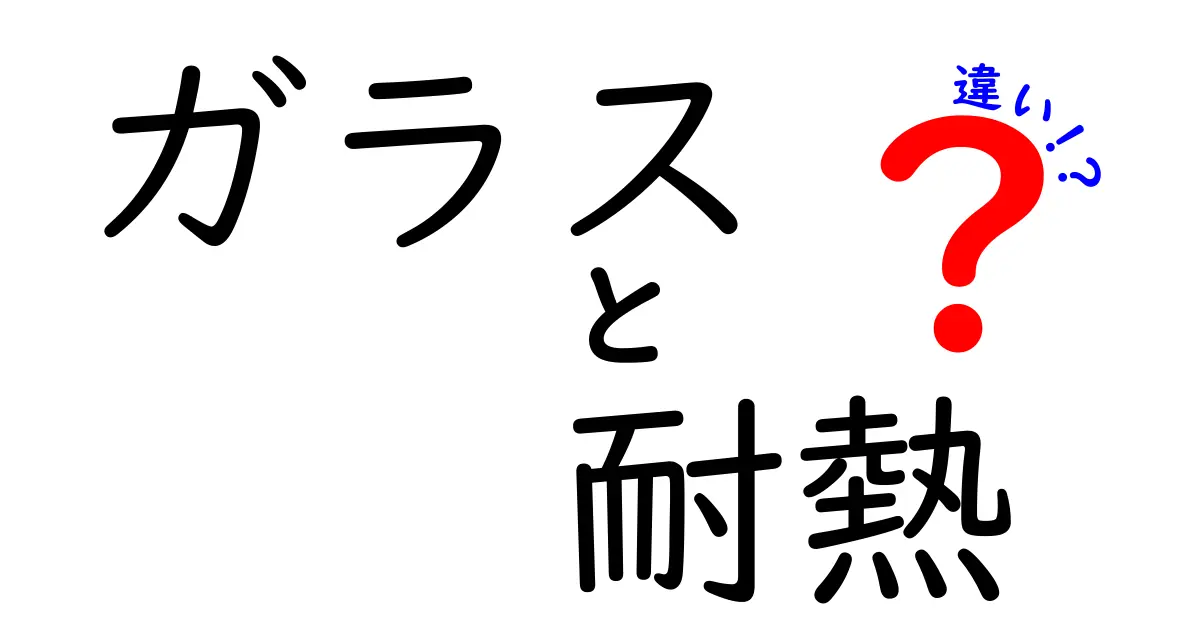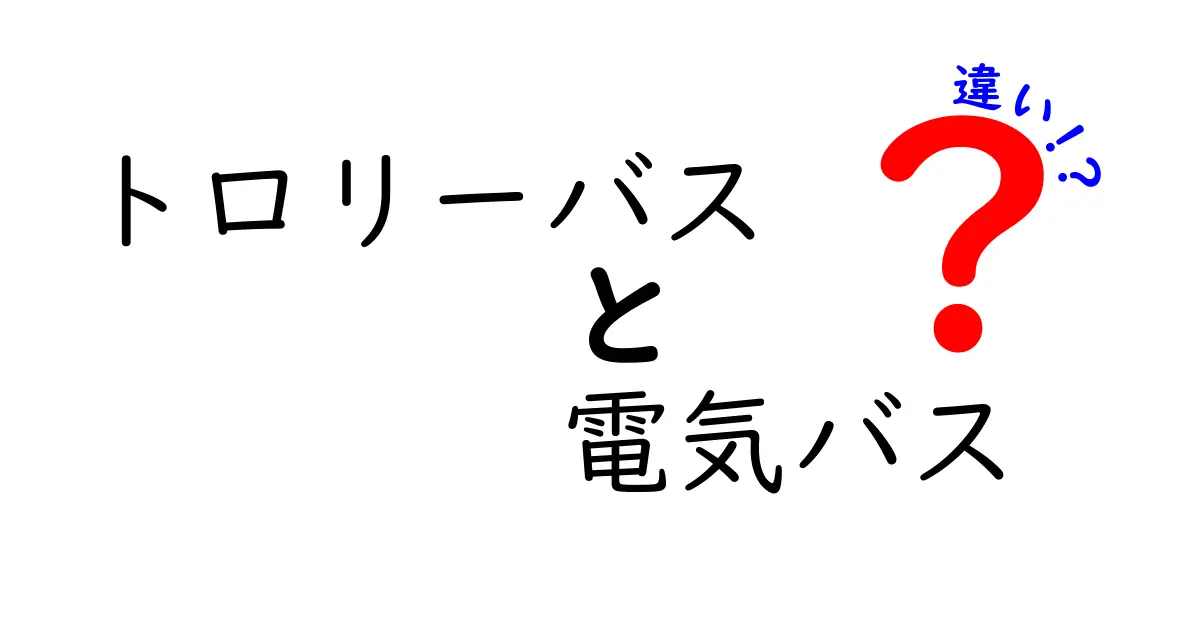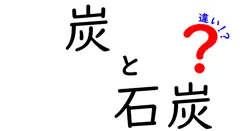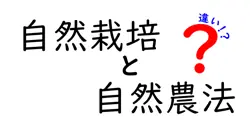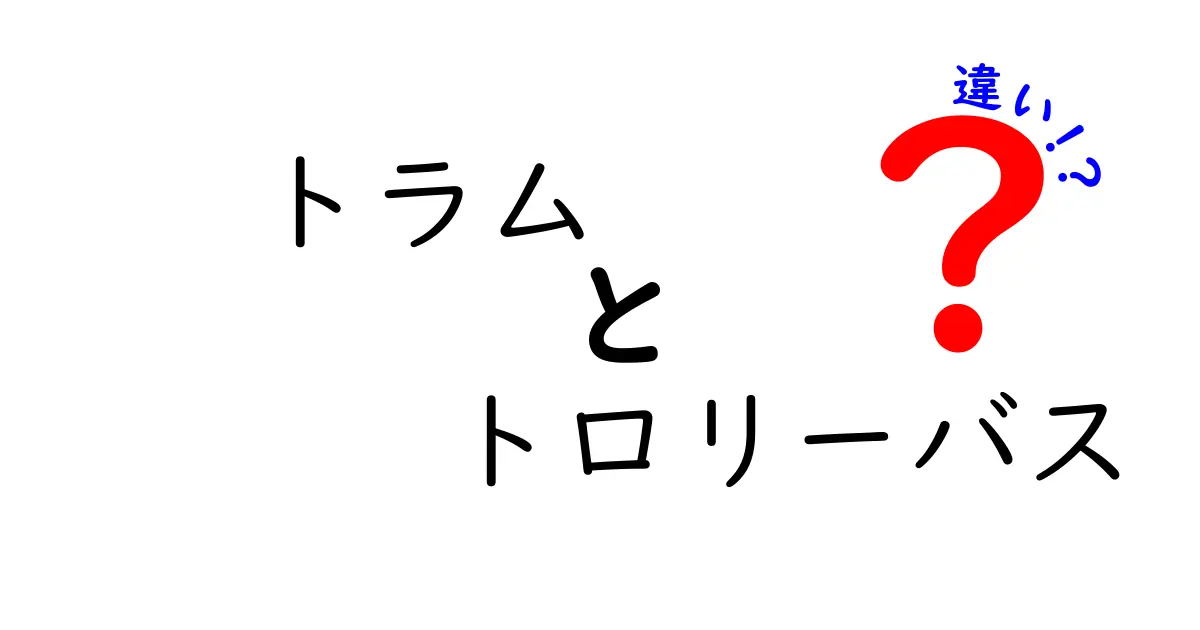
トラムとトロリーバスの基本的な違いとは?
トラムとトロリーバスは、どちらも電気を使って走る公共交通の乗り物ですが、走る場所や仕組みに大きな違いがあります。
まず、トラムは線路の上を走る電車の一種で、市街地や観光地などの道路に敷かれたレール(線路)に沿って動きます。車輪はレールの上を走り、電気は線路とは別に架空の電線から取り入れて走ります。
一方、トロリーバスはゴムタイヤで道路の上を走る電気バスの一種です。線路が無いので自由度が高いですが、道路の上に設置された電線から電気を供給されて走ります。
つまり、大きな違いは「線路の有無」と「走行方式」と言えます。
走行の仕組みと電気の取り入れ方
トラムはレールの上を車輪で走るため、普段見る線路の上にいます。車体に付いているパンタグラフやトロリー棒が架線に接触し、電気を受け取ってモーターを動かします。
トロリーバスも同じように架線から電気を取りますが、車体には2本のトロリーポールがあり、架線から2本のケーブルを使って電気を受けます。これは通常の電車やトラムとは違い、電気の流れ路が必要なためです。
レールを使用するトラムに対して、トロリーバスは道路を利用し電線だけが必要な点が大きな違いです。
見た目や運行範囲の違いと利用される場所
見た目の違いは意外とわかりやすく、トラムは電車のように長い編成になっていることも多く、線路に沿って決まったルートを走ります。定期的に駅停車し、多くの乗客を運びます。観光都市や市街地の主要路線でよく見られます。
一方でトロリーバスは見た目は普通のバスですが、屋根にトロリーポールが2本立っています。道路を自由に曲がりながら走ることができるため、路面バスの代替として使われることが多いです。峠道や坂道の多い地域で環境に優しい交通手段として導入される場合もあります。
つまり、トラムは固定された線路を走る交通手段、トロリーバスは架線式の電気バスで道路上を走る交通手段という違いがあります。
トラムとトロリーバスの比較表
| 項目 | トラム | トロリーバス |
|---|---|---|
| 走行方式 | レールの上を車輪で走る | 道路の上をタイヤで走る |
| 電気の取り入れ方 | パンタグラフやトロリー棒で架線から電気を受ける | 2本のトロリーポールで架線から電気を受ける(直流電気回路) |
| 走行場所 | 線路の上(専用軌道または路面軌道) | 道路の上(バス路線に近い) |
| 見た目の特徴 | 長く連結された車両、多くは車体が低床式 | バスに似ており屋根にトロリーポール2本がある |
| 運用の特徴 | 定められた線路を走り、観光路線や市街地輸送に活用 | 道路を自由に走行可。公共交通や環境配慮のために利用 |
まとめ
トラムとトロリーバスはどちらも電気で走る環境に優しい乗り物ですが、トラムは線路の上を走る電車の仲間で、トロリーバスは道路を走る電気バスの一種です。
見た目や走る場所、電気の取り入れ方も異なるため、興味がある方は実際に街中で見比べてみるのも面白いでしょう。
これらは地域ごとに特徴的な交通システムとして活躍していますので、ぜひ違いを知って賢く公共交通を利用してください。
トロリーバスの「トロリー」とは、英語の "trolley"(トロリー)から来ています。「トロリー」とは元々はワゴンやカートを意味し、転じて電線から電気を取るための棒や装置を指すようになりました。トロリーバスではこの「トロリーポール」という棒が屋根に2本付いていて、空中の電線から電気を受けています。面白いのは、同じ電気を使う乗り物でも、トラムはパンタグラフを使うことが多いのですが、トロリーバスはトロリーポールを使うという違いがあること。これが名前の由来にもなっているんですね。中学生でも、電気の受け方が乗り物の名前に影響していると知ると、ちょっと面白く感じるかもしれません!
前の記事: « トロリーバスと通常のバスの違いとは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: 【耐熱と難燃】その違いを徹底解説!知っておきたい基礎知識 »