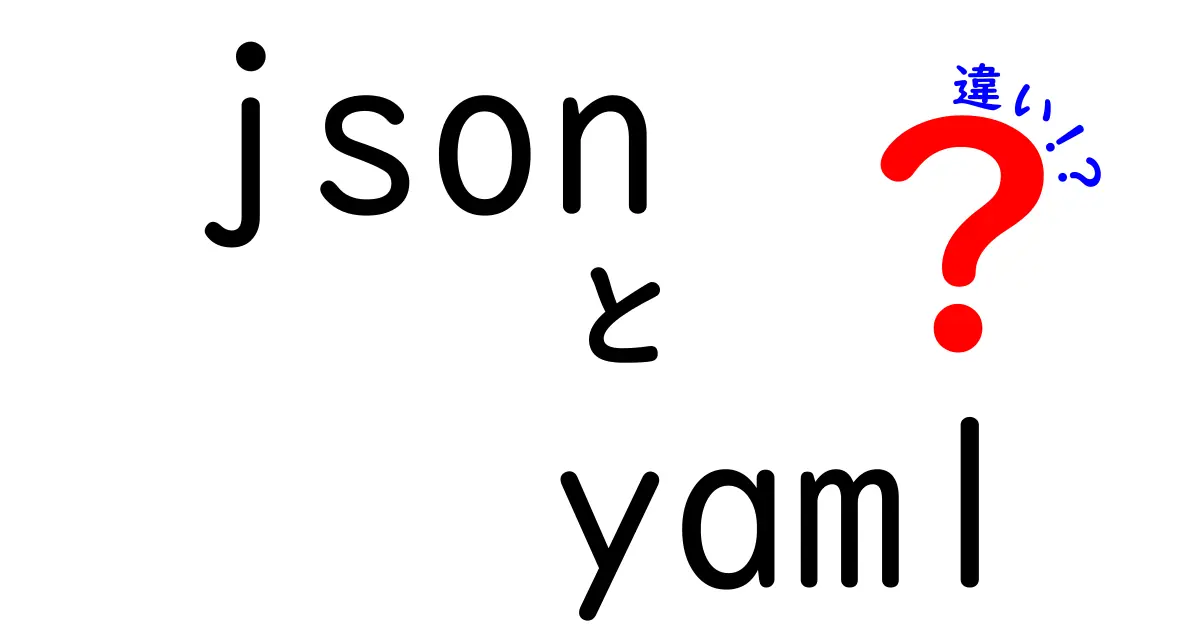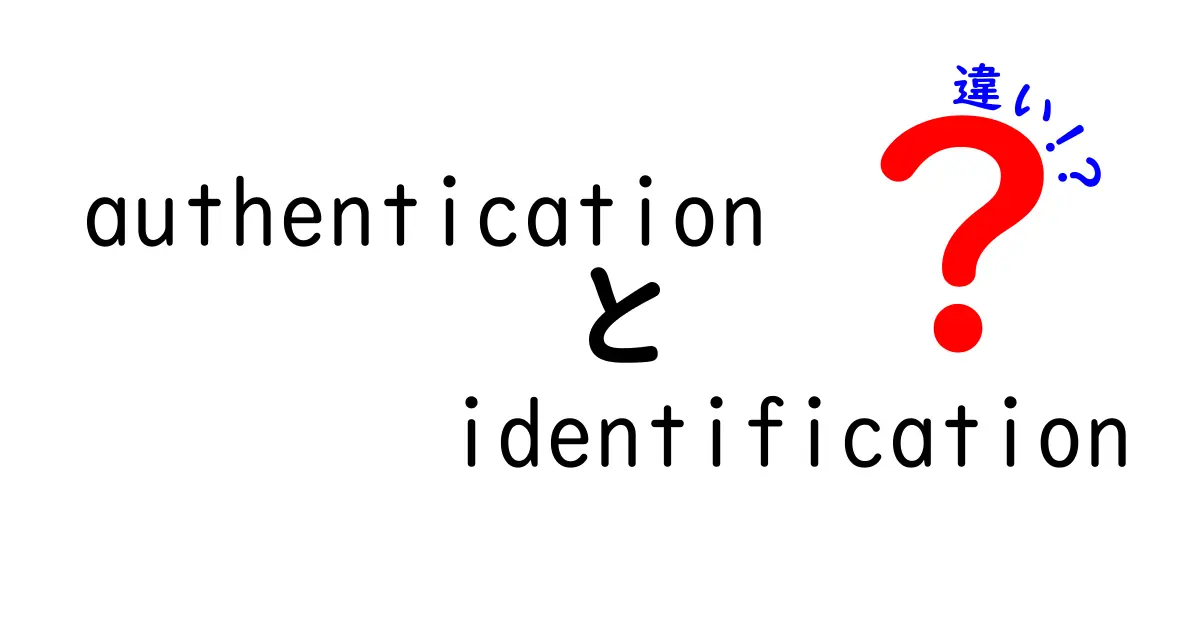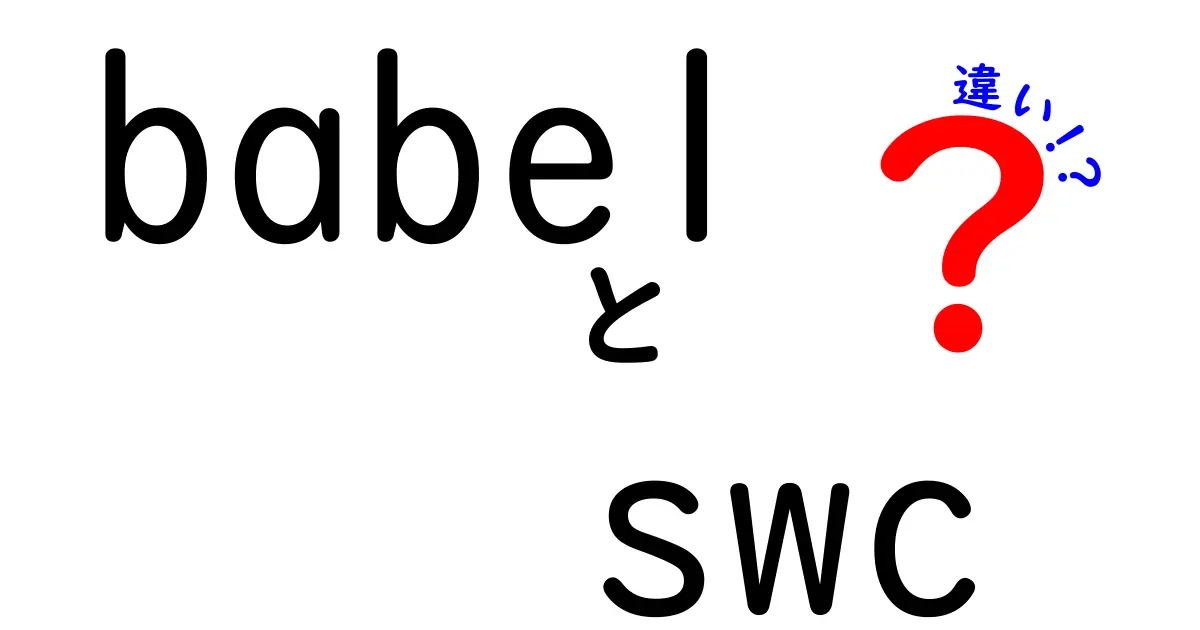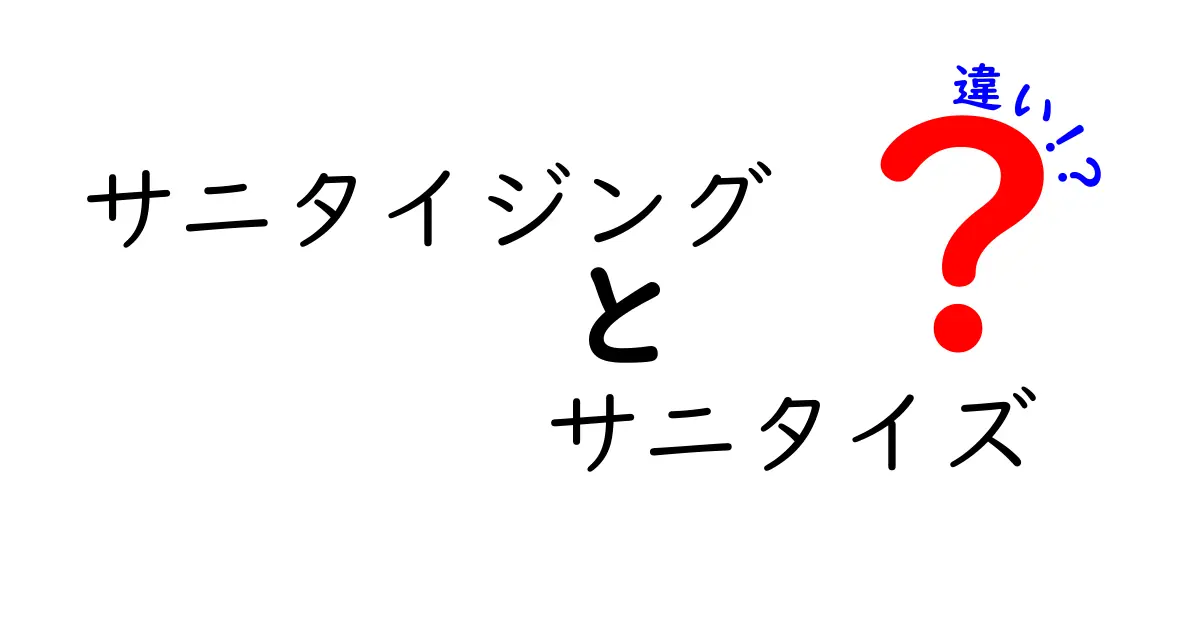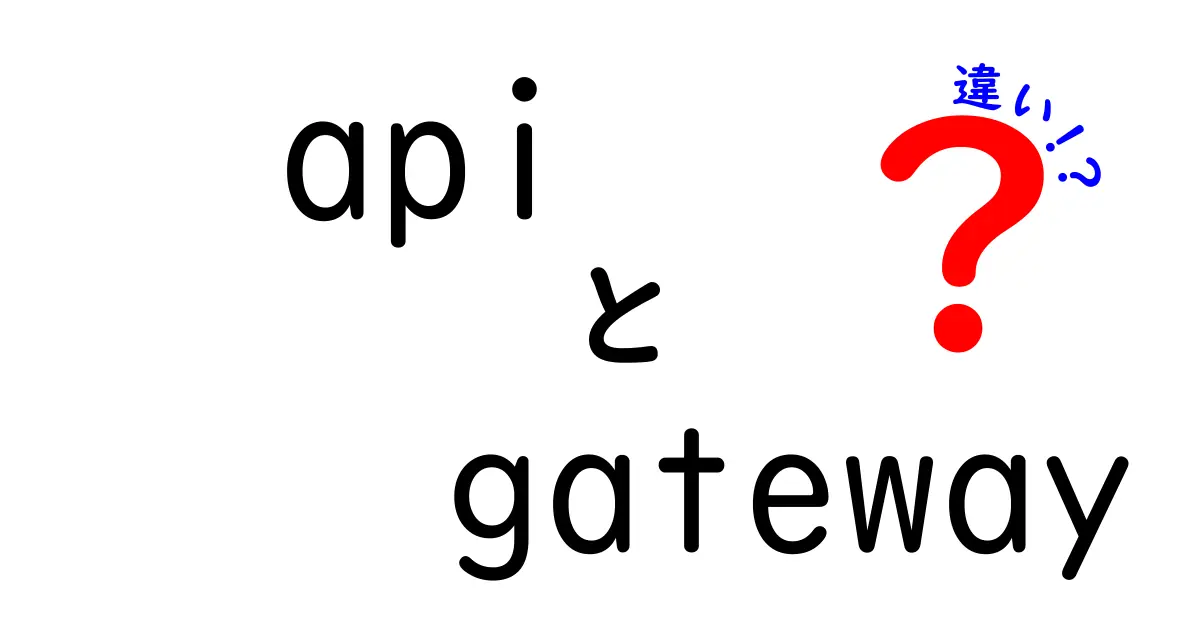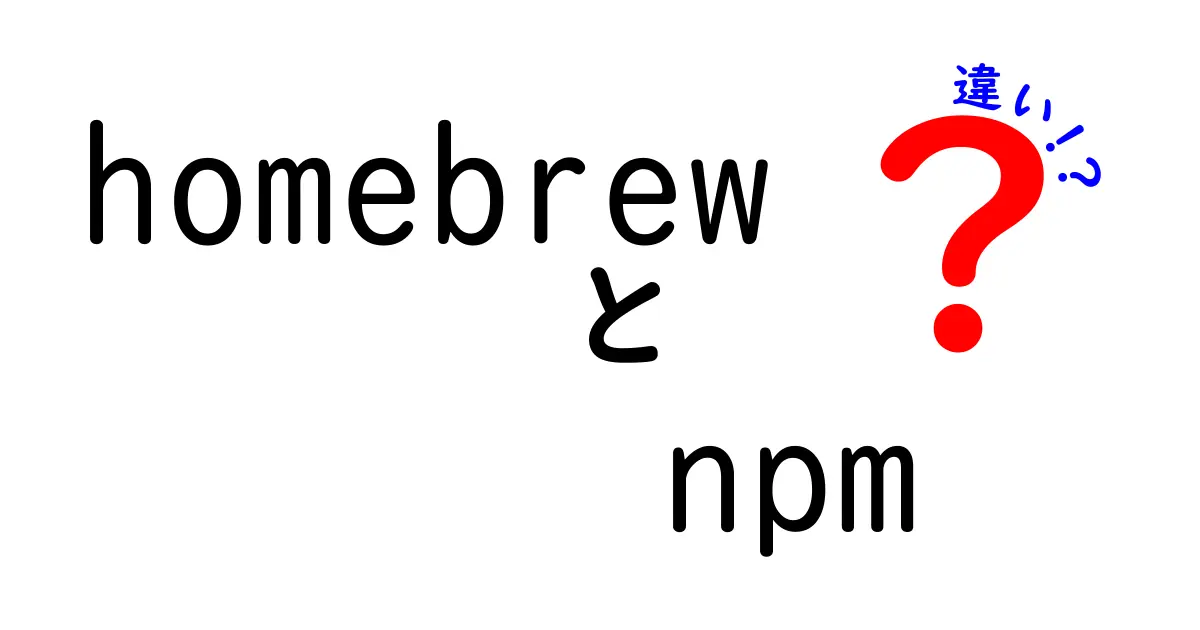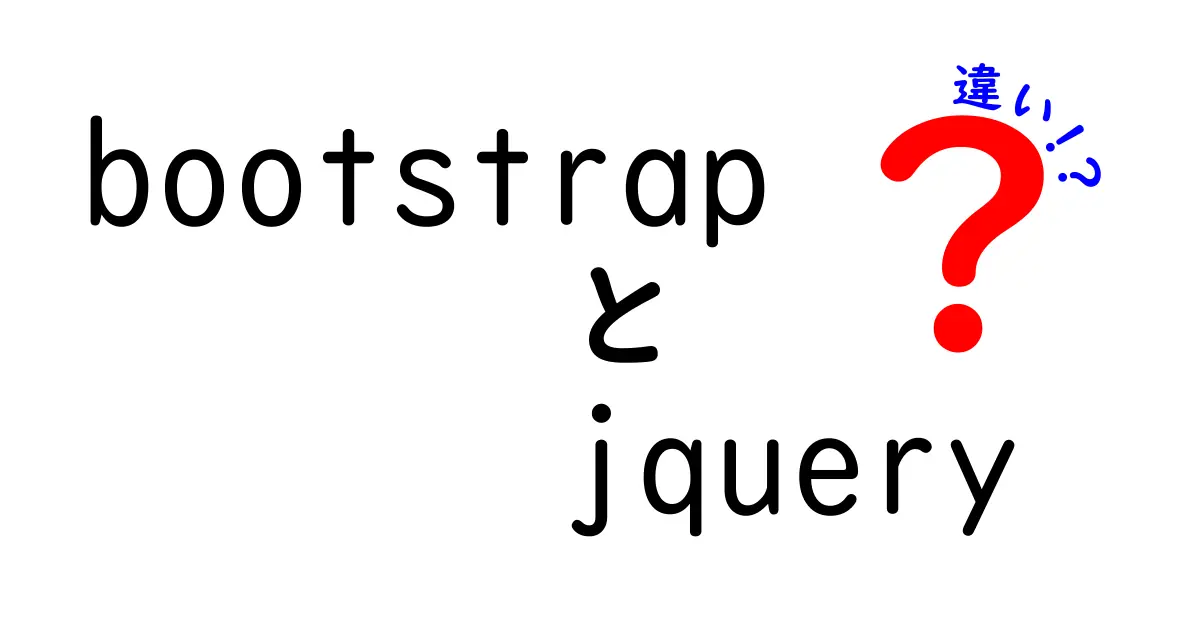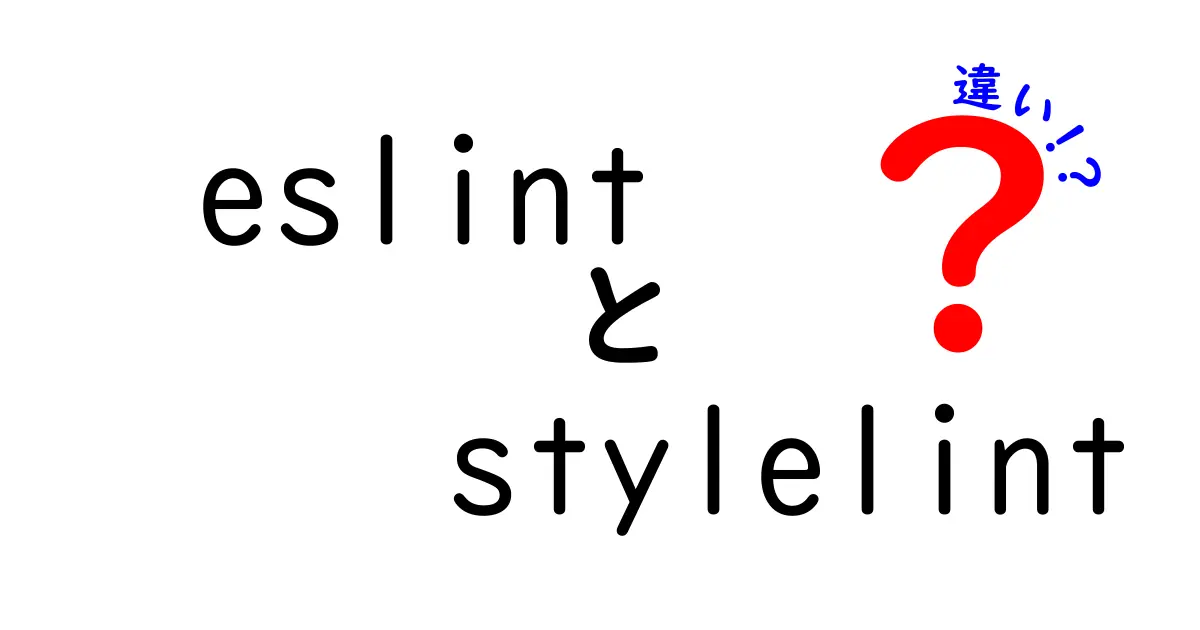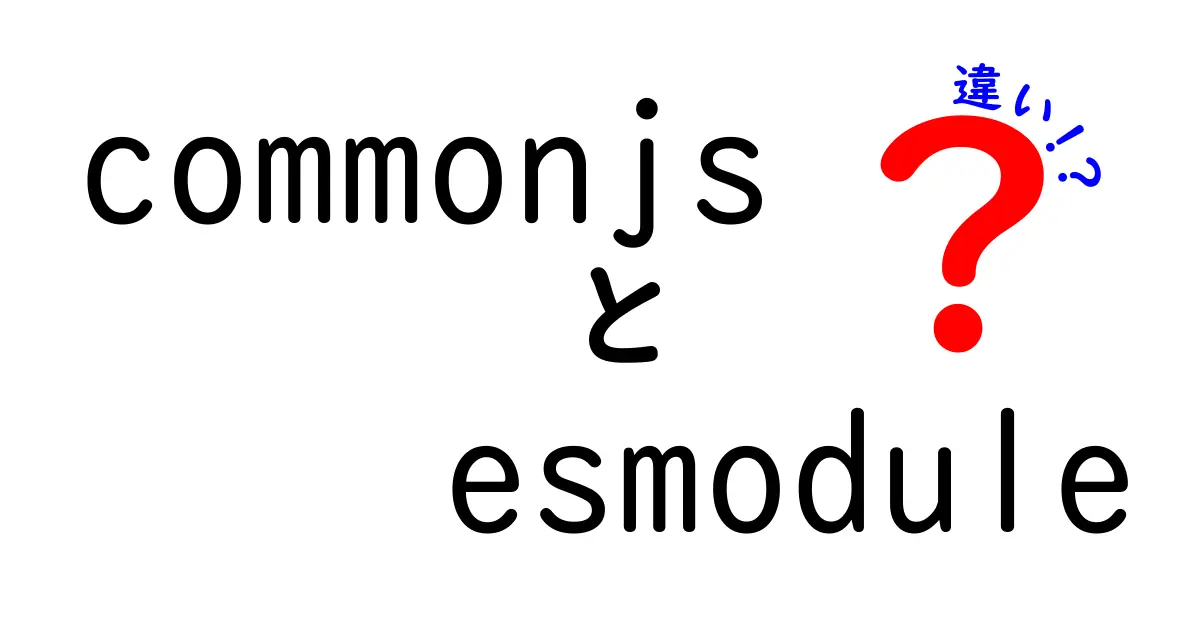

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
commonjs esmodule 違いを徹底解剖!このブログでは、なぜCommonJSとESModuleが別のものとして設計されたのかを、プログラミング初心者の中学生にも伝わるよう、用語の意味から実際のコードの書き方、互換性を跨ぐ注意点まで、丁寧に噛み砕いて解説します。ブラウザとサーバーの違い、ビルドツールの役割、動的読み込みの扱い、そして今後のECMAScriptの動向まで、具体的な例と比喩を使って順番に理解できる構成です。
この章では、まず大事な「何が違うのか」を見極める土台を作ります。CommonJSはNode.jsの昔からの標準で、同期的な読み込みを前提としています。つまりファイルを読み込む時点で必要な分を全部揃えてから処理を進める設計です。代表的な書き方は const mod = require('./foo') のような形と、module.exports か exports を使って外部に機能を公開します。対してESModuleは現代の標準で、静的な読み込みを前提とする設計です。importと export を使い、ビルド時に最適化をかけやすく、ブラウザでも動作します。
この違いは、実際のコードの見た目だけでなく、実行タイミングや ツールの挙動、将来的な互換性にも影響します。
今から詳しく見ていきましょう。
長い見出しで探る基礎の本質を説明する章一つ目の長い見出し
ここでは、両方のモジュールが「どのように読み込まれ、どのようにエクスポートされるのか」という基本的な仕組みを、日常生活の例えを使って説明します。
例えば、CommonJSは「家の中の部屋を順番に開けるように、必要な部屋だけを一つずつ開けていく」イメージです。必要なステップが直列で進むため、途中で止まると後続の処理も止まります。これは、requireが実行されるまで次の処理を進められないという特徴に由来します。
一方、ESModuleは「地図を見ながら、先に全ての部屋の扉の位置を読み取っておく」ような感覚です。静的解析が可能なので、実行前に必要な分を特定でき、ブラウザ側の最適化にも強いのです。
このような性質の違いが、実際の開発の使い勝手やビルドの挙動に現れます。
長い見出しで探る実務の違いを理解する章二つ目の長い見出し
次に、実務での使い分けを見ていきます。CommonJSはサーバーサイドの環境で依然として根強く使われています。理由は、長い間の互換性と大量の既存モジュールが require ベースで動作しているからです。実務での注意点として、非同期読み込みが必要になる場面での扱いが難しく、動的なimportを使うケースが限定的です。対照的にESModuleは新規プロジェクトで推奨されることが多く、importと export で構成されるコードは読みやすく、ツールチェインとの相性も良いです。
ただし、古い環境を跨ぐ時には互換性の問題が生じることがあります。例えば、ブラウザで「ESModuleをそのまま使えるか」という点や、Node.jsの設定でtype: 'module'の扱いをどうするか、などが挙げられます。
この章の要点は「使い分けの判断基準を持つこと」と「互換性の検討を怠らないこと」です。
長い見出しで探る未来志向の選択肢と学習のヒントの章三つ目の長い見出し
将来を見据えた学習のヒントをまとめます。
新しいプロジェクトではESModuleを選ぶのが無難です。理由は、標準化が進み、ツールチェーンのサポートが広いからです。互換性を確保するためには、既存のCommonJSモジュールをESModuleと併用する「互換レイヤー」を用意する方法があります。例えば、import側でrequireを使うケースを避け、export defaultと名前付きエクスポートを使い分ける練習をすると良いでしょう。最後に、学習者としての心構えとして、コードを読む時間を多く取り、公式ドキュメントと実際の挙動を自分の手で確かめる癖をつけることが大切です。
この小ネタは、ESModuleを深掘りする雑談風の解説です。私たちは友達とおしゃべりするように、モジュールの読み込み順やデフォルトエクスポート、名前付きエクスポートの意味をゆっくり語ります。ここでは、なぜ互換性の壁が生まれるのか、なぜブラウザではesmoduleが標準化されたのか、そして新しい機能が登場しても古いコードが動くようにする工夫を、身近な例と一緒に考えます。
次の記事: npmとnvmの違いを徹底解説!初心者でも迷わない使い分けのコツ »