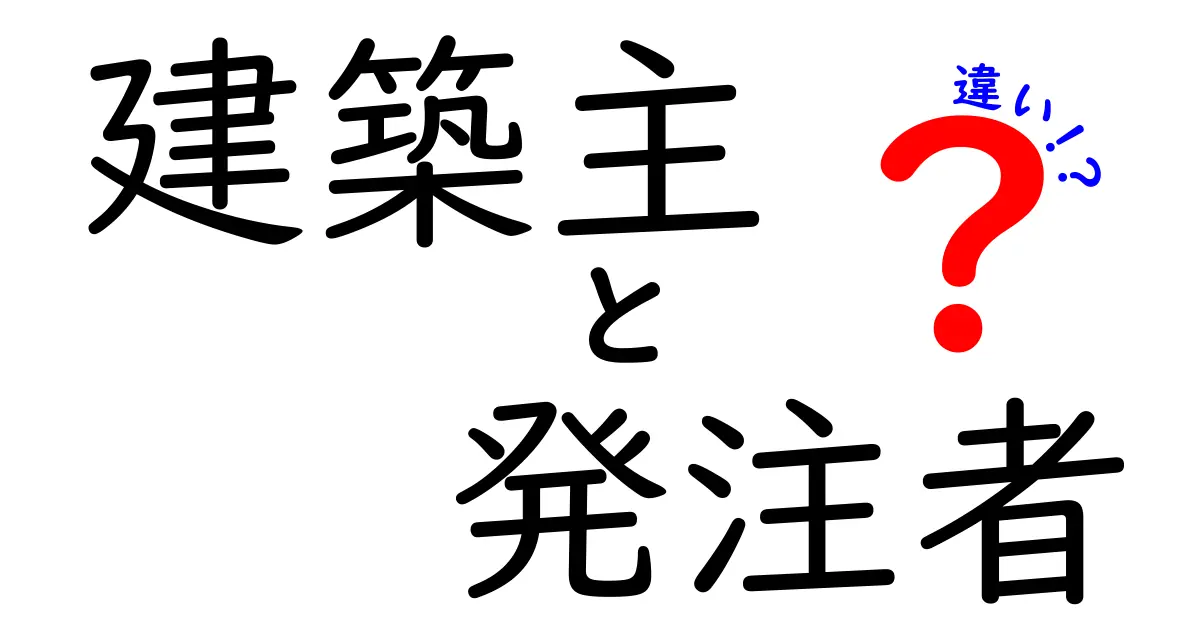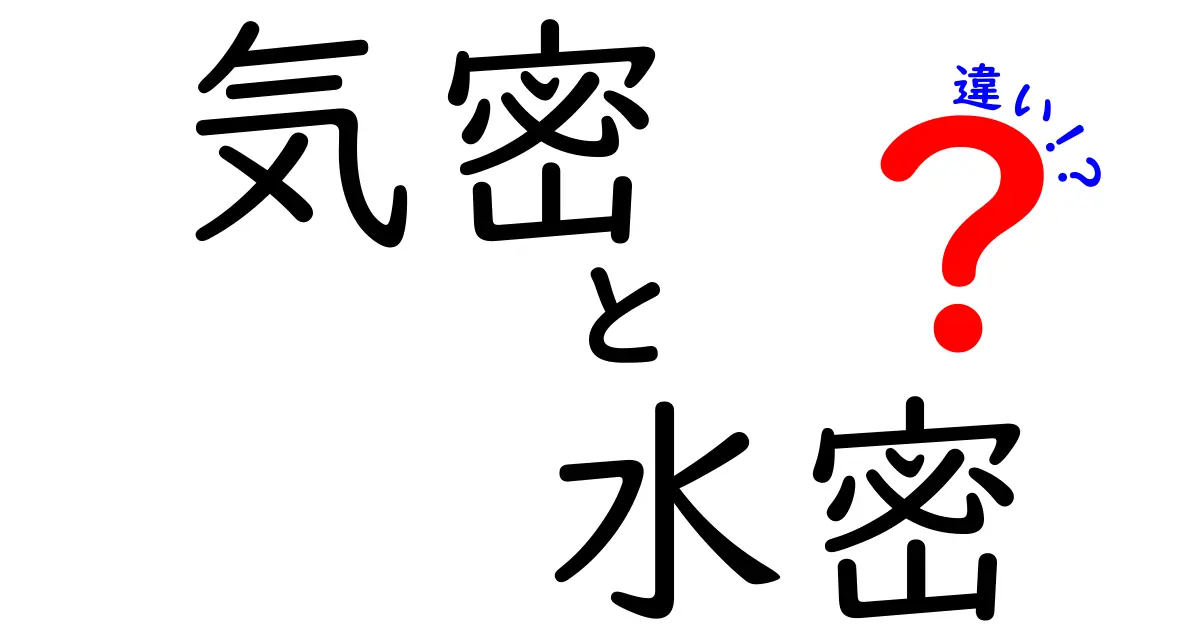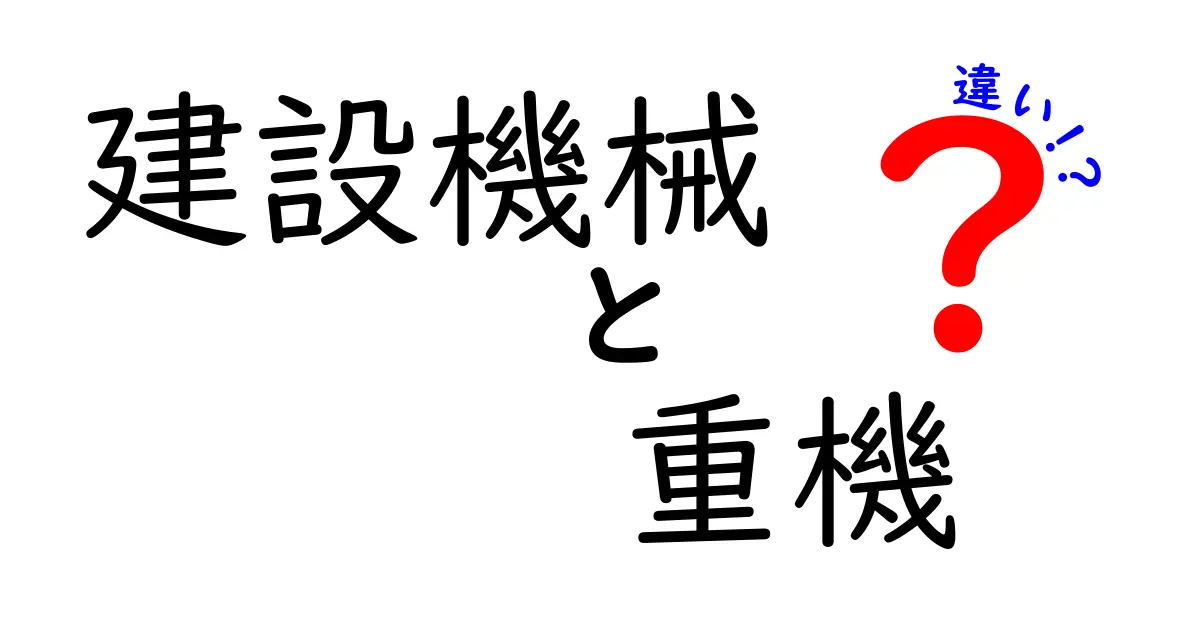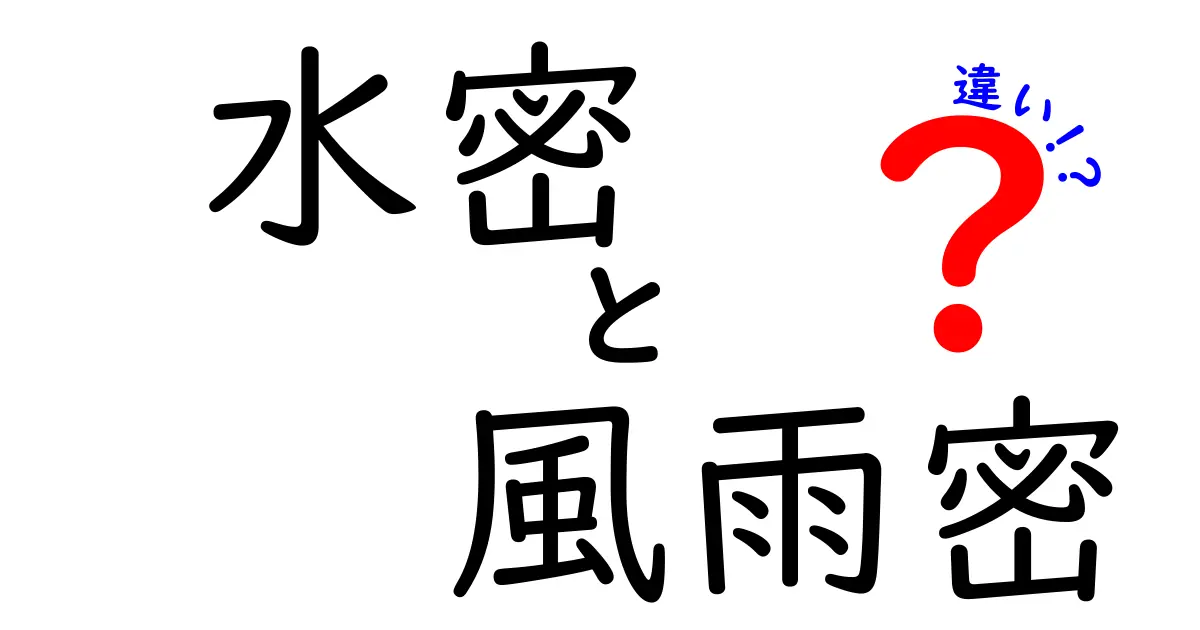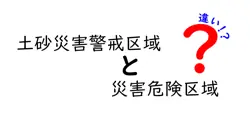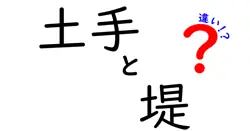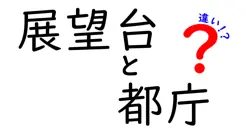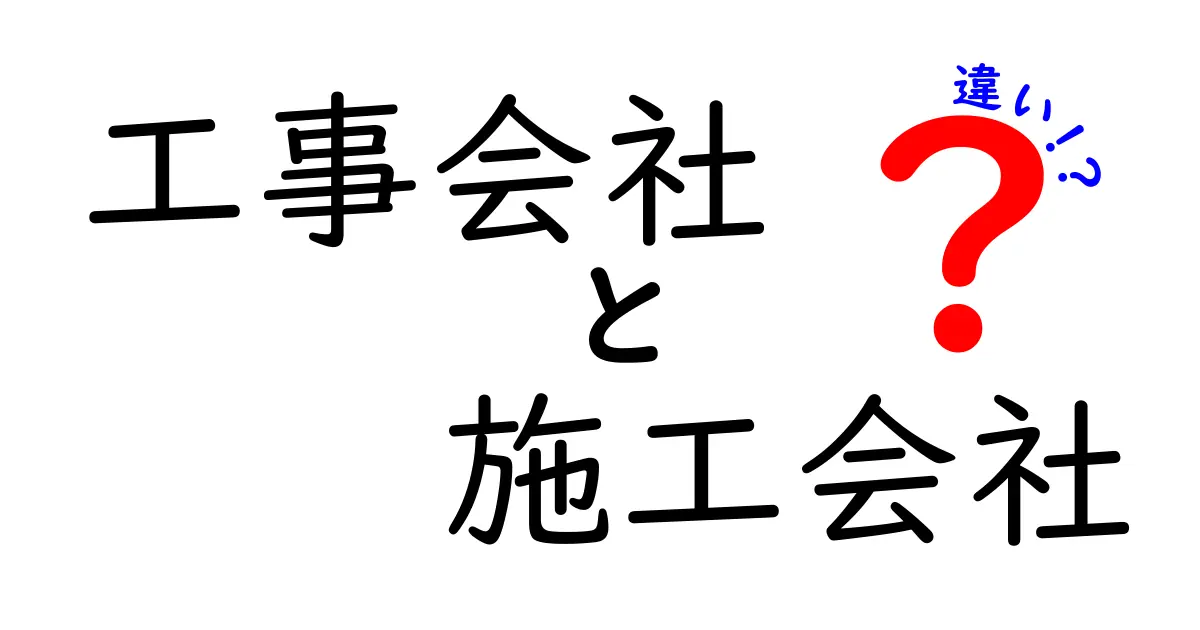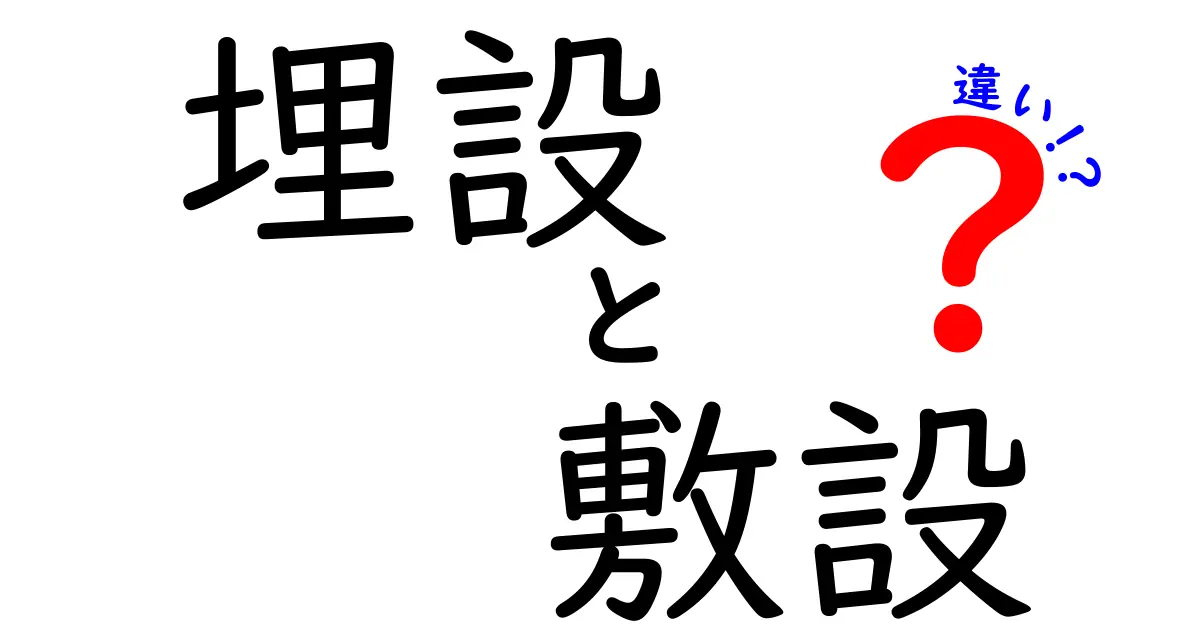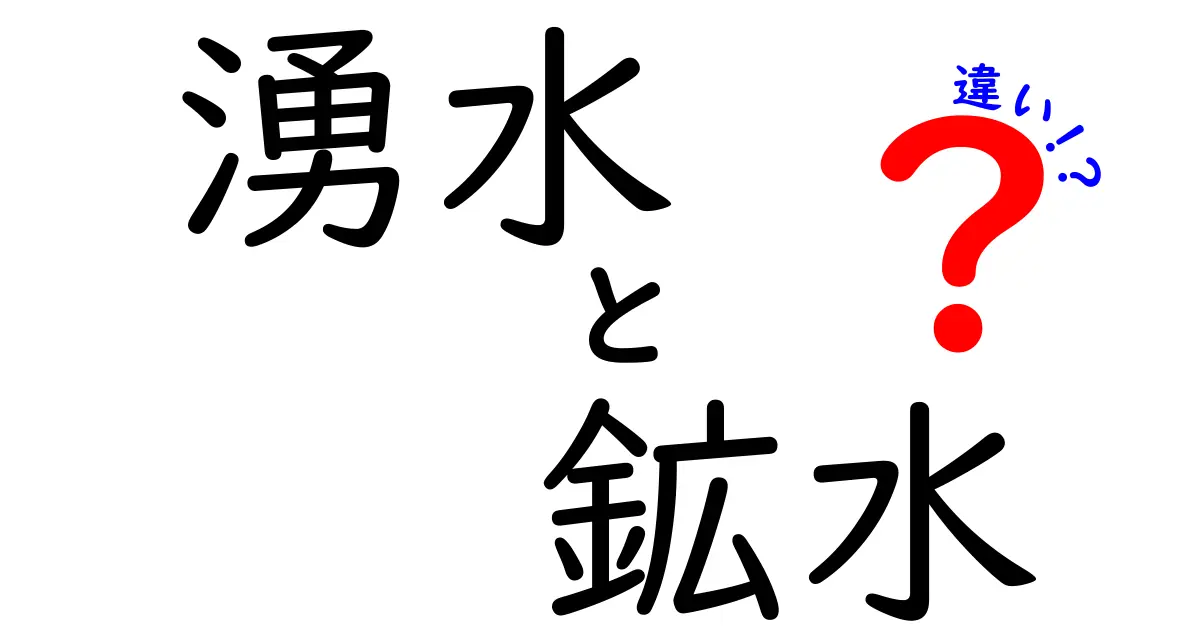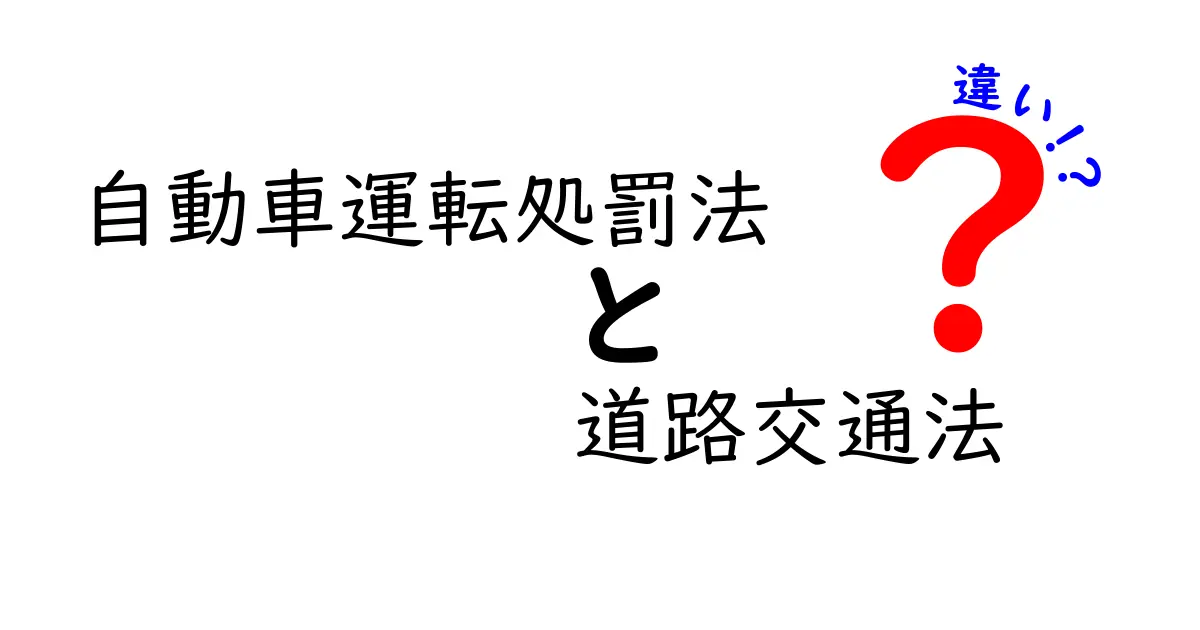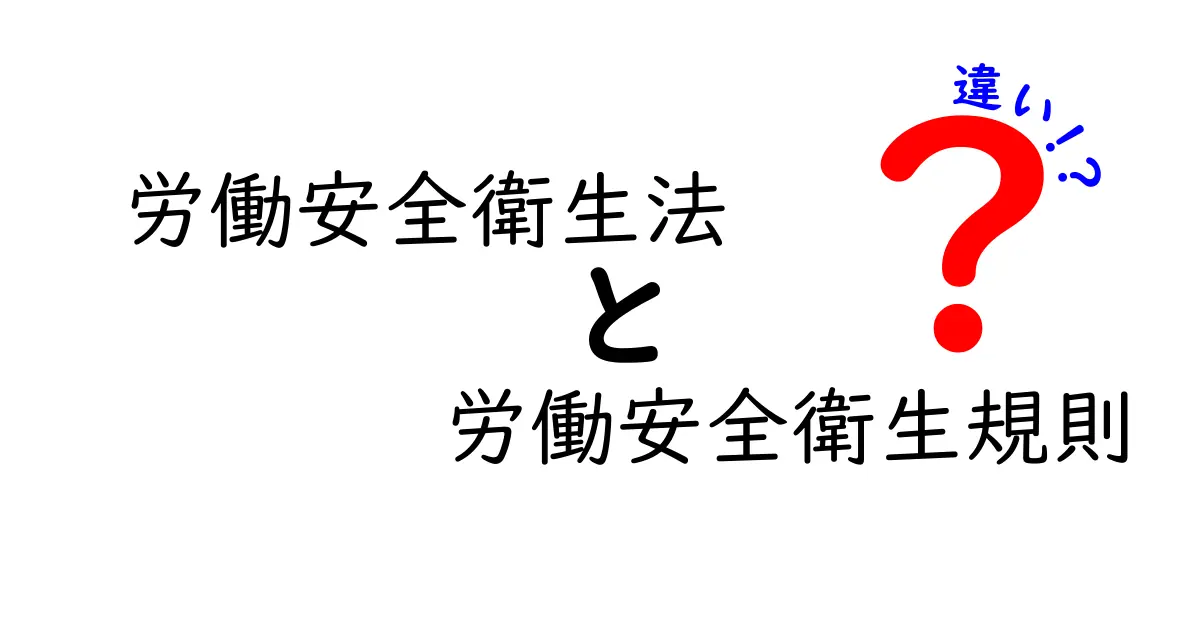

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
労働安全衛生法と労働安全衛生規則の基本的な違いとは?
働く人の安全と健康を守るために、日本では労働安全衛生法と労働安全衛生規則という法律が定められています。この2つは似ている名前ですが、役割は少し違います。
まず労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための基本的なルールを決めた法律です。国会で作られた法律なので、全ての働く場所に共通して適用されます。例えば、働く環境を安全にしたり、健康診断を行うことが義務付けられていたりします。
一方で労働安全衛生規則は、労働安全衛生法を実際に守るための詳しい決まりが書かれています。規則は厚生労働大臣が作る命令で、現場で具体的にどう安全管理をすればよいか細かく定めています。たとえば、機械の安全装置をどのように設置するか、どんな保護具を使うかなどの細かい基準が決められています。
このように、法律は「基本ルール」、規則は「そのルールを守るための具体的な方法」と言えます。
わかりやすく言うと、法律が「安全に働きましょう」と全体の目標を示し、規則が「こうやって安全にしましょうよ」とやり方を示しているのです。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則の違いを表でまとめてみよう
言葉だけだとわかりにくいので、代表的なポイントを表にまとめてみました。
| 項目 | 労働安全衛生法 | 労働安全衛生規則 |
|---|---|---|
| 種類 | 法律(国会で制定) | 省令(厚生労働大臣が制定) |
| 内容 | 労働者の安全と健康に関する基本ルール | 基本ルールを守るための具体的な方法や基準 |
| 対象 | 全ての事業所や労働者 | 全ての事業所や労働者 |
| 例 | 安全衛生管理者の設置義務、定期健康診断の実施 | 安全装置の設置方法、保護具の種類・使い方 |
こうして比べると、法律は大まかなルールで、規則はその実践的な細かい内容であることがよくわかります。どちらも労働環境を安全に保つためには欠かせない役割を果たしています。
なぜ労働安全衛生法と労働安全衛生規則を分けているの?
どうして法律と規則を別々に作っているのか、不思議に思う人も多いでしょう。
それは、法律は国会で決めるため時間がかかるのに対し、規則は少し柔軟に改訂できるからです。
働く環境や技術は日々変わるので、規則の方で最新の機械に合わせた安全基準をすぐに定めたり修正したりできます。法律だけだと変化に対応しにくいのです。
また法律は基本ルールだけを示し、規則で実際の現場の状況に応じた対応を決めているため、分けておくことでわかりやすく、柔軟な管理が可能になっています。
このように両者をうまく使い分けることで、安全で健康に働ける職場が作られているのです。
「労働安全衛生規則」って普段は法律ほど注目されないけど、実は安全を守るとても細かいルールがギッシリ詰まっているんです。例えば、新しい機械が導入された時、それに合わせて安全装置の設置方法をすぐに細かく決められるのは規則のおかげ。規則が柔軟に変わることで、現場の安全が実際に守られているんですよ。法律だけじゃなくて、この規則の存在が現場の安全のヒーローなんですね!
前の記事: « 建築主と発注者の違いって何?初めてでもわかるシンプル解説
次の記事: 現場代理人と職長の違いとは?役割や責任をわかりやすく解説! »