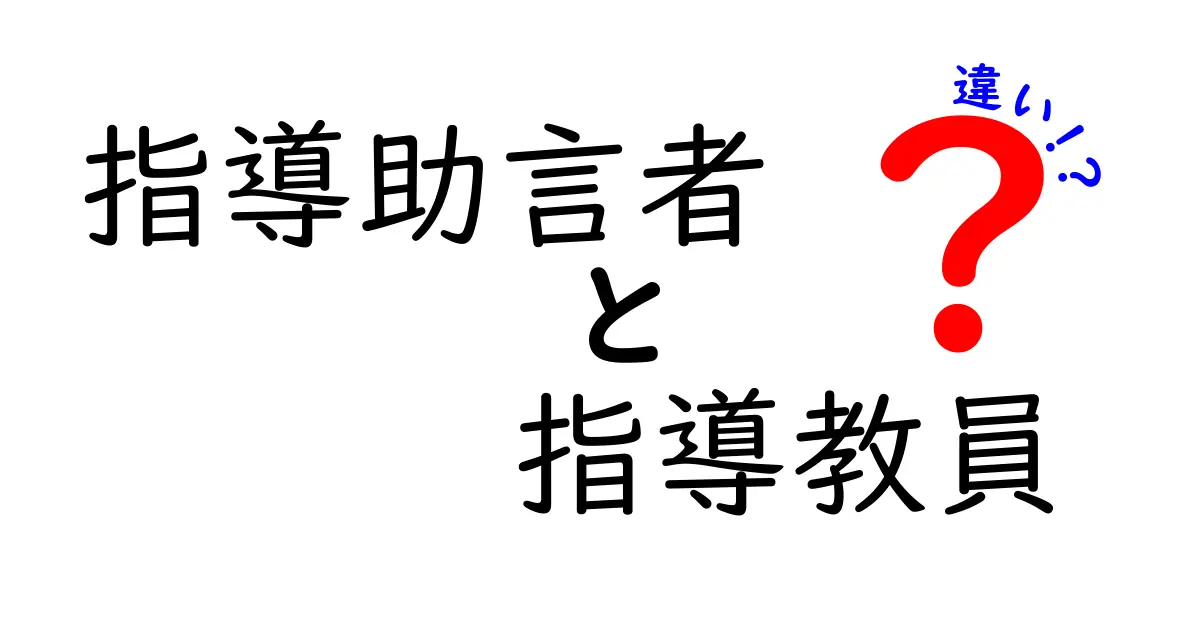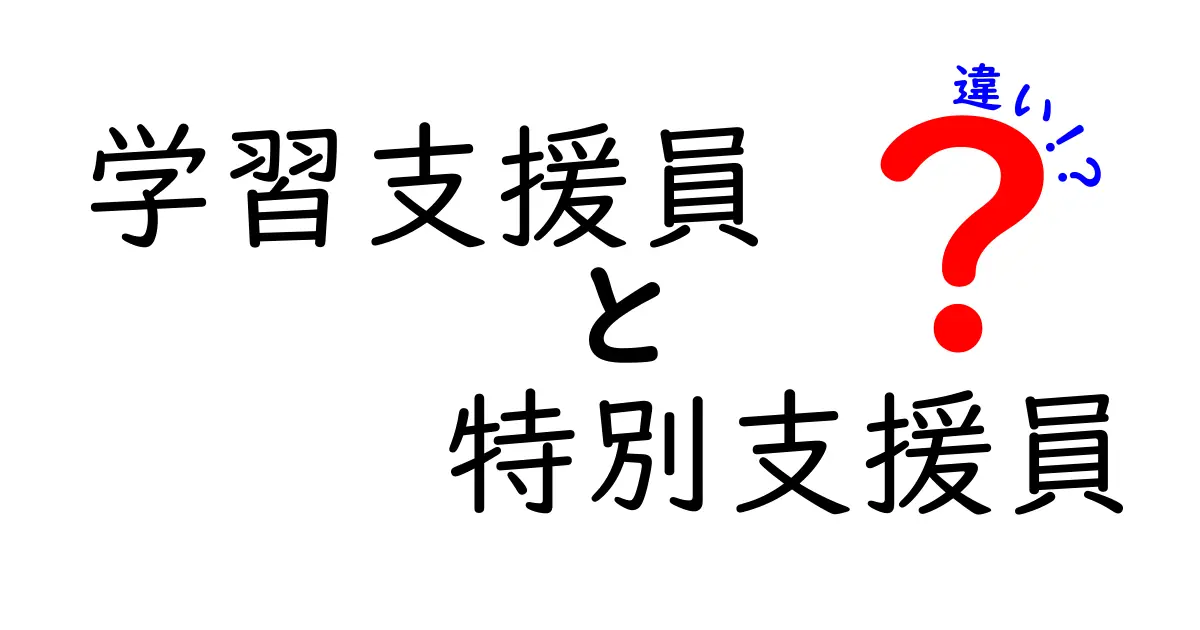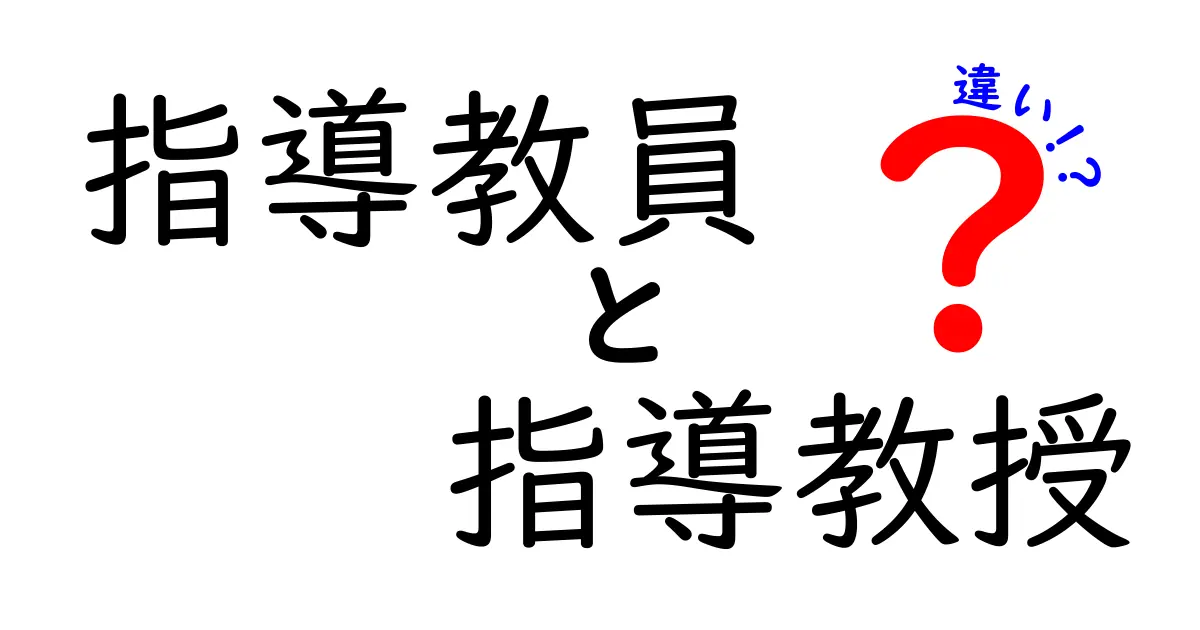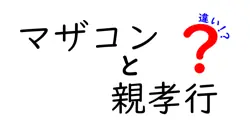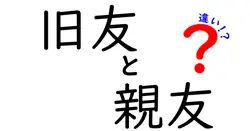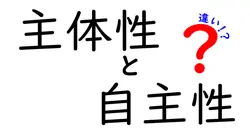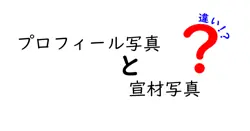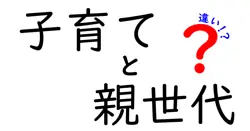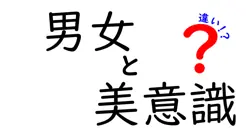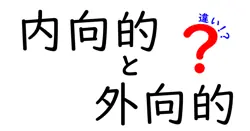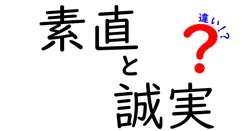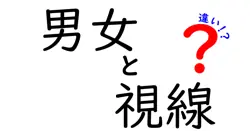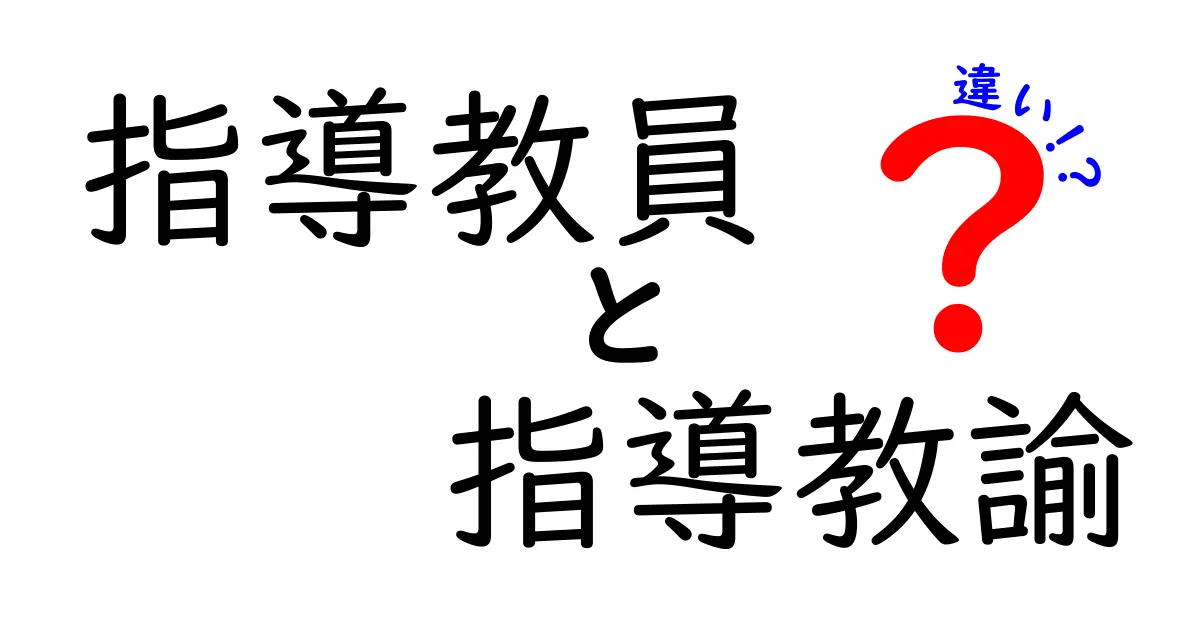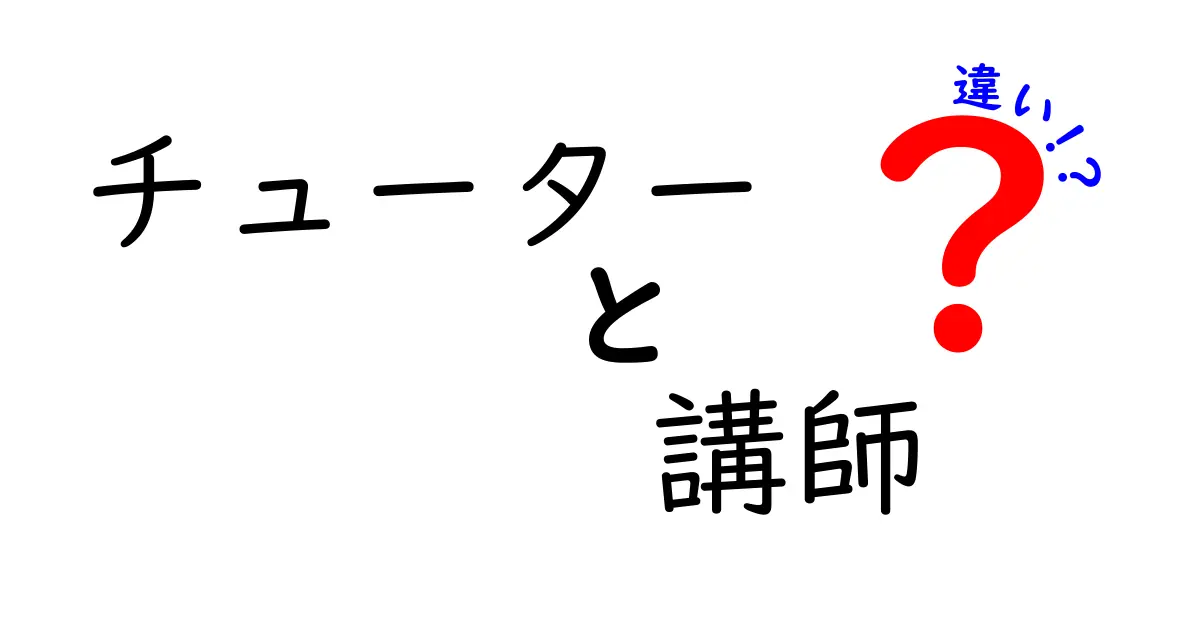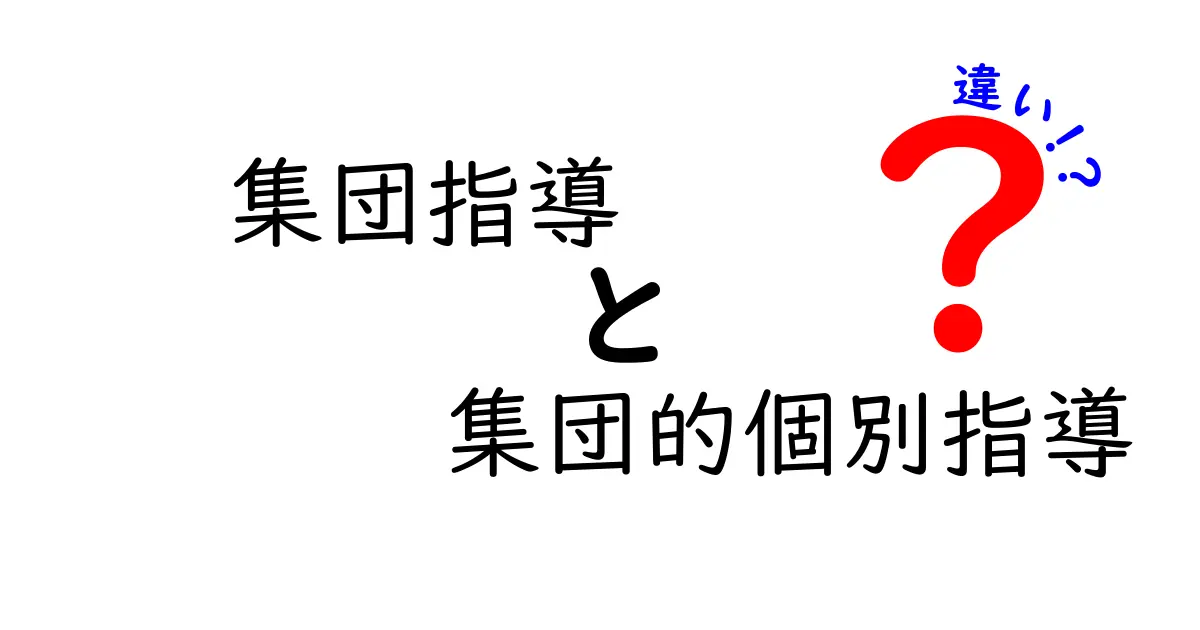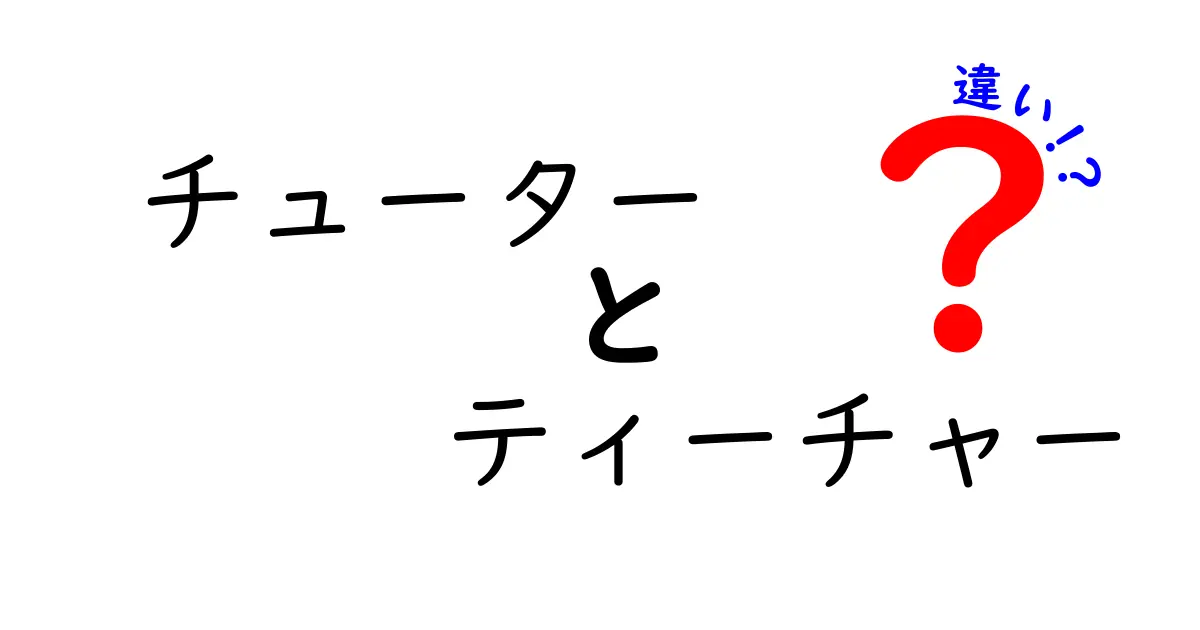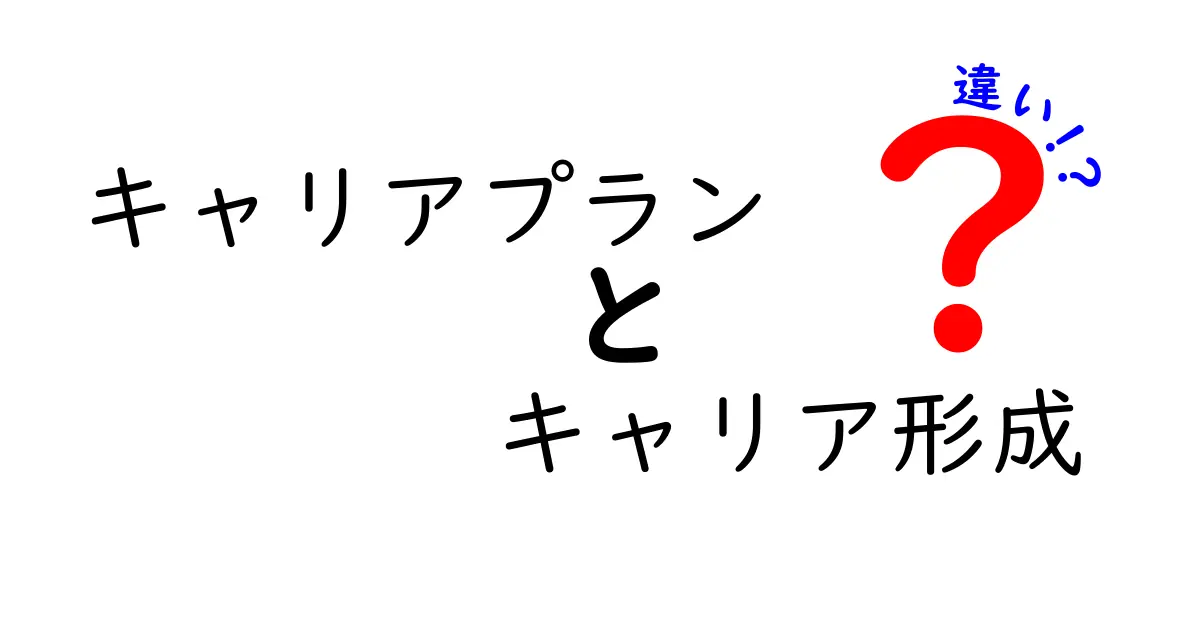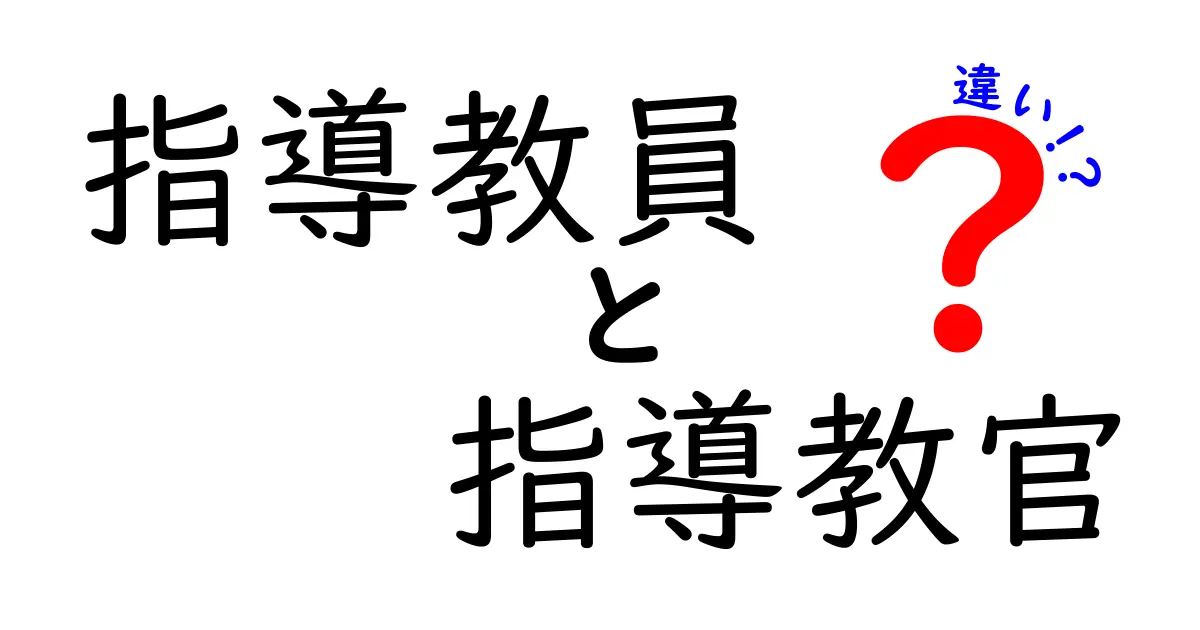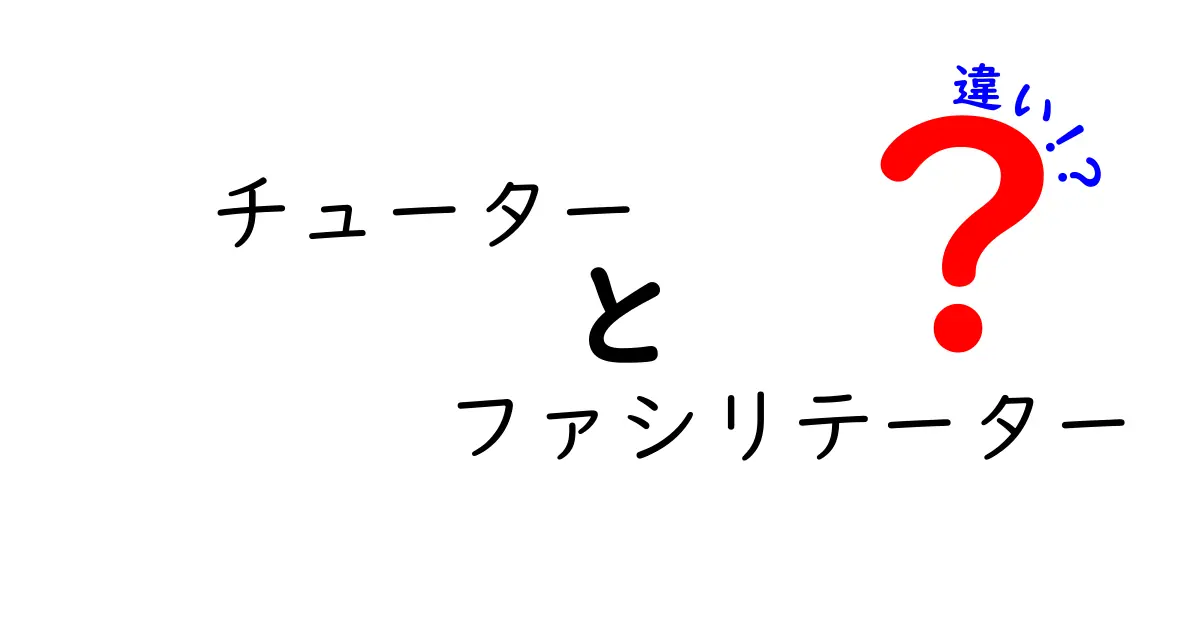

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
チューターとファシリテーターの違いを徹底解説!役割・場面・効果を中学生にもわかる言葉で解説
チューターとファシリテーターは、学習や仕事の場で似ている響きを持ちますが、役割や目的が大きく異なります。チューターは個人に焦点を当て、理解を深めるために難しい概念を分解して伝える役割を担います。一方でファシリテーターは集団全体の学びを動かす役割を担い、参加者が自分の頭で考え、意見を出し合い、結論へと導くための環境づくりをします。
この違いを具体的な場面で見ると、たとえば数学の宿題を進める時には「チューター」が必要な場面が多いです。反対に、クラスプロジェクトで複数の意見をまとめ、全員の参画を促す場面では「ファシリテーター」が活躍します。
以下では、さらに詳しく両者の特徴、場面、身につく力、そして授業設計での使い分け方を解説します。ここで何が大事かというと、目的に応じた適切な役割選択です。
チューターとは何か
チューターは個別の指導を提供する専門家か経験者で、学生の理解度に合わせて進め方を決めます。難しい概念を分解して順序立てて説明し、例題を順に解く練習をさせ、間違いをただ指摘するのではなく、どうして間違えたのかを一緒に考えます。宿題の取り組み方、学習計画の作り方、苦手分野の克服の道筋を具体的に示すのが得意です。
このような指導を受けると、個人のペースや理解度に合わせて進むことができ、短時間で効果的に成績を伸ばすことが期待できます。
ただしチューターは「教える人」という役割が強い分、授業の流れを作る力や学習の自立を促す工夫が不足しがちな場面もあります。
要は、個別最適化と反復練習を重視する役割だと覚えておくと分かりやすいです。
ファシリテーターとは何か
ファシリテーターは、集団の学びや意思決定を円滑に進める人のことです。内容を一方的に伝えるのではなく、参加者が自分の意見を安全に出せる場を作り、質問を投げかけ、相手の考えを言語化する手助けをします。目的は“成果を出すための共同作業”を可能にすることです。
具体的には、話を長く独占する人を抑制し、意見が出揃うよう促す、時間配分を管理する、話の要点を要約して整理する、反対意見にも配慮して全員の納得感を高める、などの技術があります。
ファシリテーターは「教える」より「引き出す」役割が中心です。だからこそ、参加者全員の発言機会を均等にすることが重要なスキルになります。
違いを実生活でどう使い分けるか
具体的な場面での使い分け方を考えてみましょう。例えば学校の補習や個別サポートでは、理解が遅れている科目の内容を一人ひとり丁寧に解く「チューター」が適しています。生徒が自分のペースで学習を進められるよう、適切な例題と演習を用意して、つまずきポイントを正しく把握させます。一方、クラス全体で課題に取り組む際や新しいアイデアを出し合う場では「ファシリテーター」が活躍します。全員の意見を引き出し、矛盾を整理し、共通理解を作るのが役割です。
このように場面に応じて役割を使い分けると、学習の効果が高まり、グループの協働力も向上します。次の表は、主な違いをまとめたものです。要素 チューター ファシリテーター 主な目的 個別の理解を深める 集団の学びを促進する 進行の主役 生徒の理解を中心に指導 場の雰囲気と議論の進行を管理 主な場面 個別補習・家庭学習支援 グループワーク・会議・ワークショップ
最後に重要な点は、場面に応じて適切な役割を選び、必要なら両方の役割を組み合わせることです。例えば、授業の中で小グループの作業を進める時には、ファシリテーターが全体の進行を取り仕切りつつ、特定の生徒にはチューターが個別サポートを提供する形が理想的です。これにより、知識の習得と協働のスキル両方を同時に育てられます。
koneta: 友だちとグループ学習をするとき、ファシリテーター役の人がいると会話の流れがとても滑らかになるんだ。話題を整理してくれる人がいると、誰かが一人でしゃべり続けるのを防げるし、全員が発言する機会を持てる。私も授業以外の課題でファシリテーターをやってみて、話を止めずにまとめるコツを学んだ。小さな工夫だけで、集まりの成果は大きく変わるんだよ。