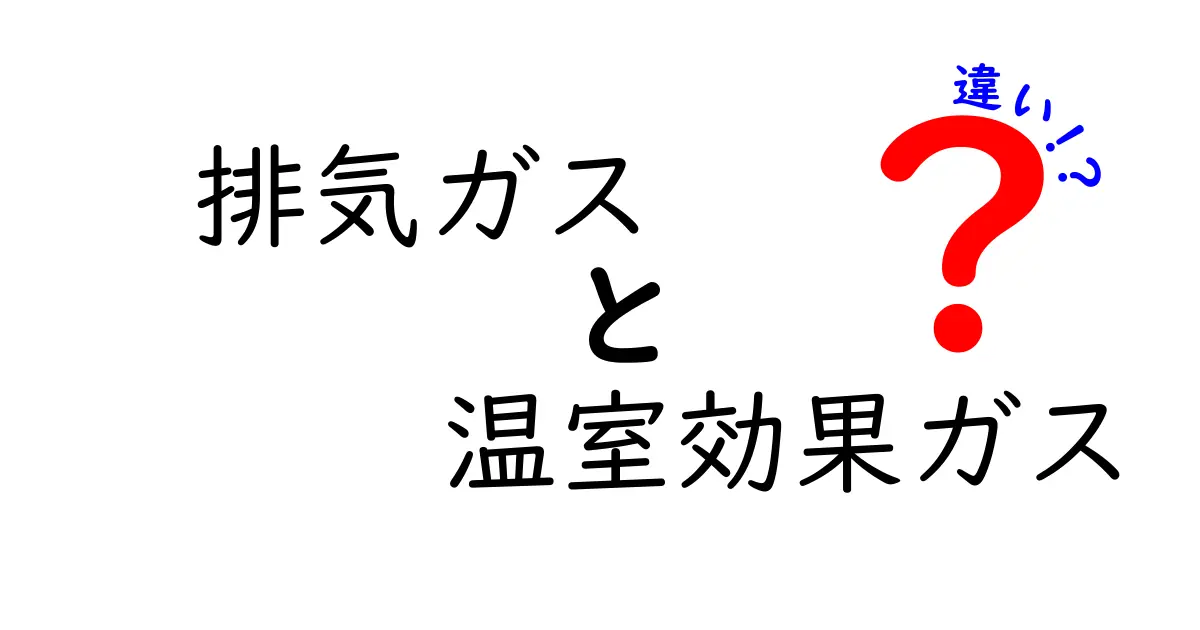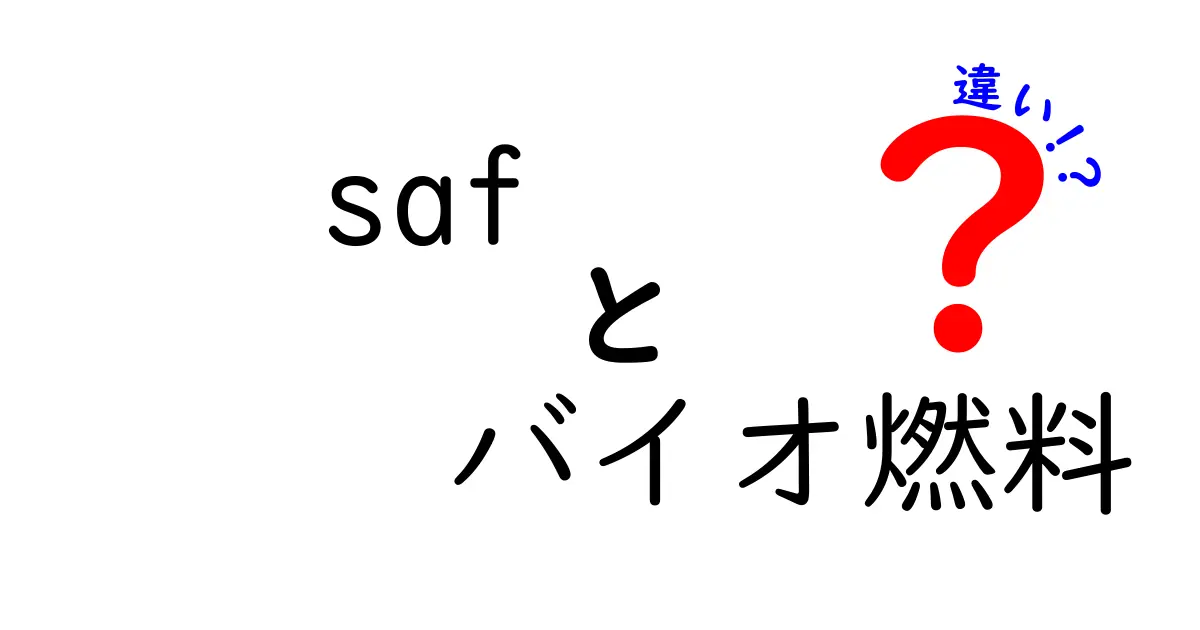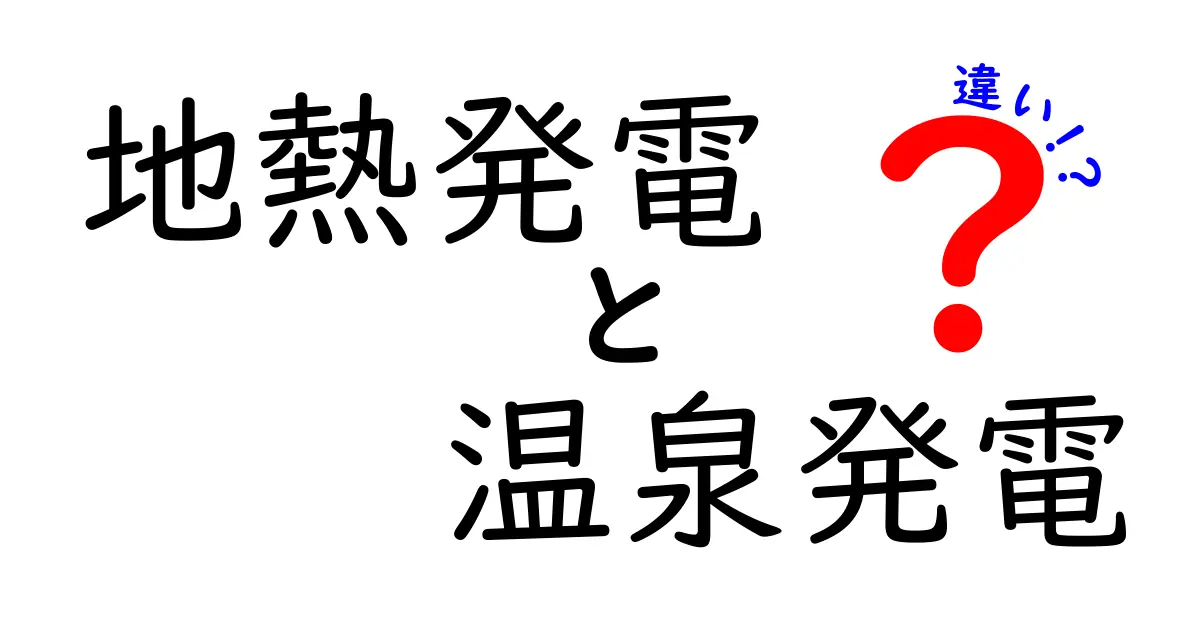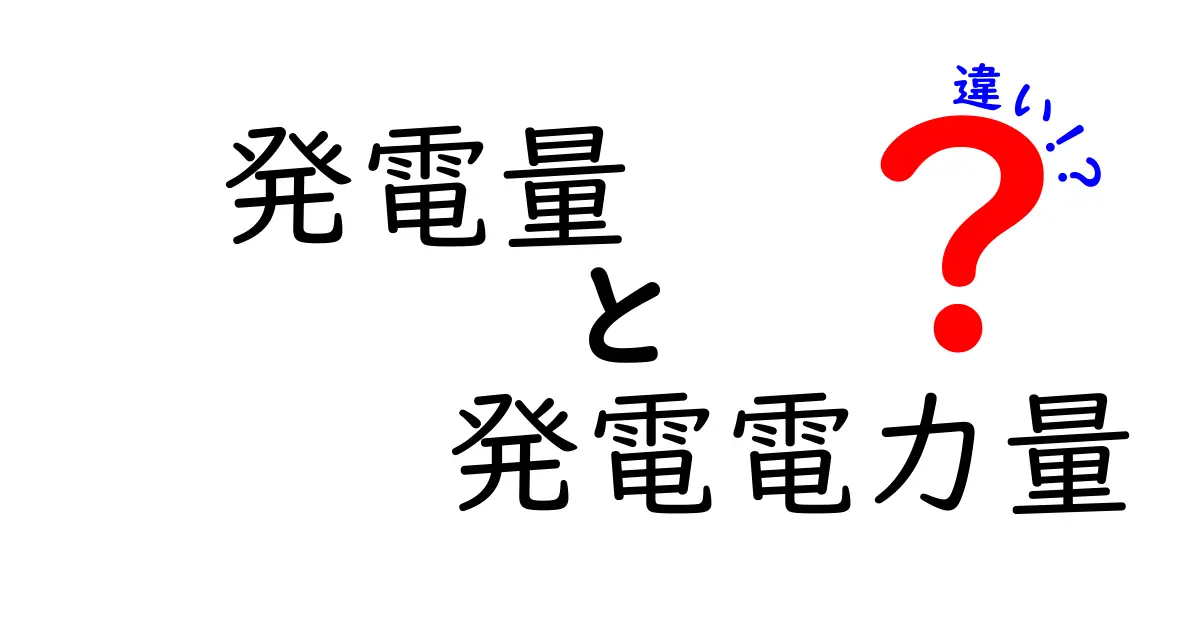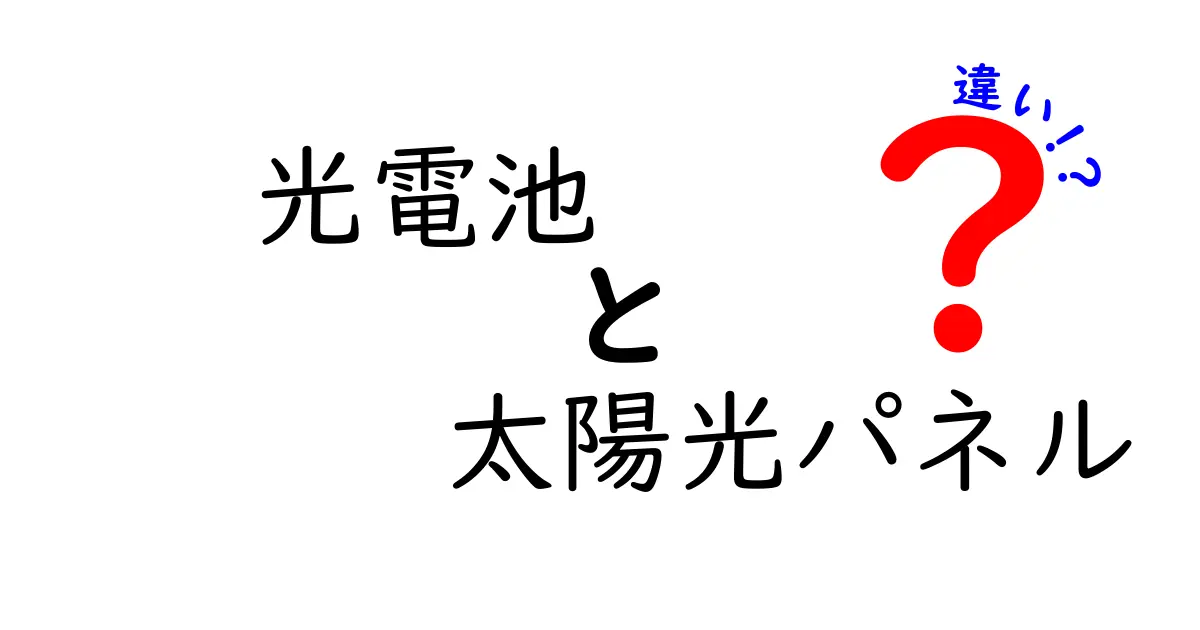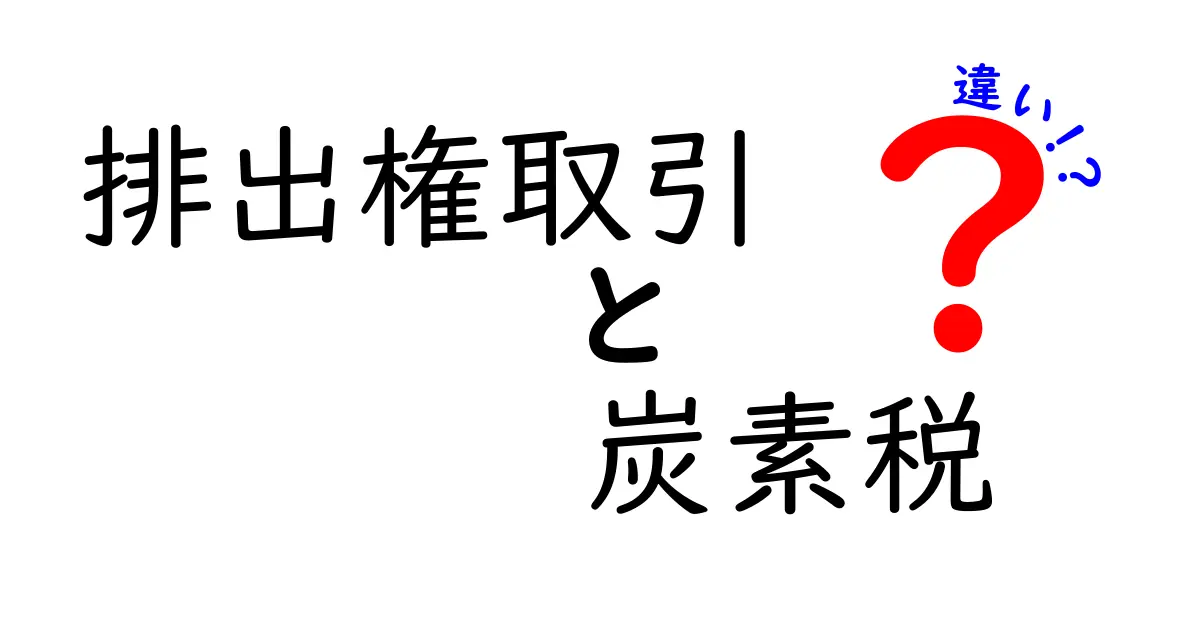

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
排出権取引と炭素税の基本的な違いとは?
環境問題への対策の中でよく耳にする排出権取引と炭素税。どちらも温室効果ガスの排出を減らすための方法ですが、そのしくみや目的には違いがあります。
排出権取引は、企業などに一定の温室効果ガス排出枠(排出権)を割り当て、それを超えて排出した分は他の企業から排出権を購入しなければならないシステムです。逆に排出量が少なければ排出権を売ることもできます。
一方、炭素税は二酸化炭素の排出量に応じて税金をかける方法。排出した分だけ費用が発生するため、企業はできるだけ排出量を減らそうと努力するインセンティブが生まれます。
このように、排出権取引は排出量に上限を設けて市場で売買する制度で、炭素税は排出量に対して直接お金の負担を求める仕組みという点で大きく異なります。
どちらも環境対策ですが、アプローチ方法が違うのがポイントです。
排出権取引と炭素税のメリット・デメリットを比較
環境保護のための政策としてどちらも有効ですが、それぞれメリットとデメリットがあります。
| 排出権取引 | 炭素税 | |||
|---|---|---|---|---|
| メリット | ・排出量の総量をコントロールしやすい ・市場の取引で効率的な削減が可能 ・排出権の価格変動が企業の省エネ投資を促す | ・税率が明確で予測しやすい ・徴収がシンプルで運用が容易 ・税収を他の環境施策に活用できる | ||
| デメリット | ・排出権の適正価格の設定が難しい ・取引市場の仕組みが複雑 ・不正取引のリスクがある | ・税率が低すぎると効果が薄い ・企業負担が増えすぎる恐れがある ・低所得者への配慮が必要 |
| 項目 | 排気ガス | 温室効果ガス |
|---|---|---|
| 定義 | 車や工場などから排出されるガスの総称 | 地球温暖化に影響を与える特定のガス |
| 主な成分 | CO2、一酸化炭素、窒素酸化物など様々 | CO2、CH4、N2O、フロン類など |
| 主な影響 | 大気汚染や健康被害 | 地球温暖化・気候変動 |
| 排出源 | 交通機関や工場、発電所など | 人間活動全般(燃料燃焼、農業、工業製品など) |
まとめ
まとめると、排気ガスは車や工場など特定の場所から出るガスのことをいい、さまざまな有害物質を含んでいます。
一方、温室効果ガスは地球の温度を適度に保つために重要ですが、人間の活動で増えすぎると地球温暖化の原因になる特定の気体を指します。
排気ガスの中に温室効果ガスが含まれている場合も多くあるため、排気ガスの排出削減は温暖化対策ともつながっています。
今後は、排気ガスを減らすと同時に温室効果ガスの増加を防ぐ活動がより一層必要とされています。
温室効果ガスの中でも特に二酸化炭素(CO2)はよく知られていますが、意外とメタン(CH4)というガスも強力な温室効果ガスであることはあまり知られていません。メタンは牛のげっぷや湿地帯からも出ていて、CO2の約25倍も温室効果が強いと言われています。だから、地球温暖化対策では温室効果ガス全体を考えることが大切なんですね。
自然の人気記事
新着記事
自然の関連記事
再エネ証書と非化石証書の違いをわかりやすく解説!環境に優しいエネルギーの証明書とは?
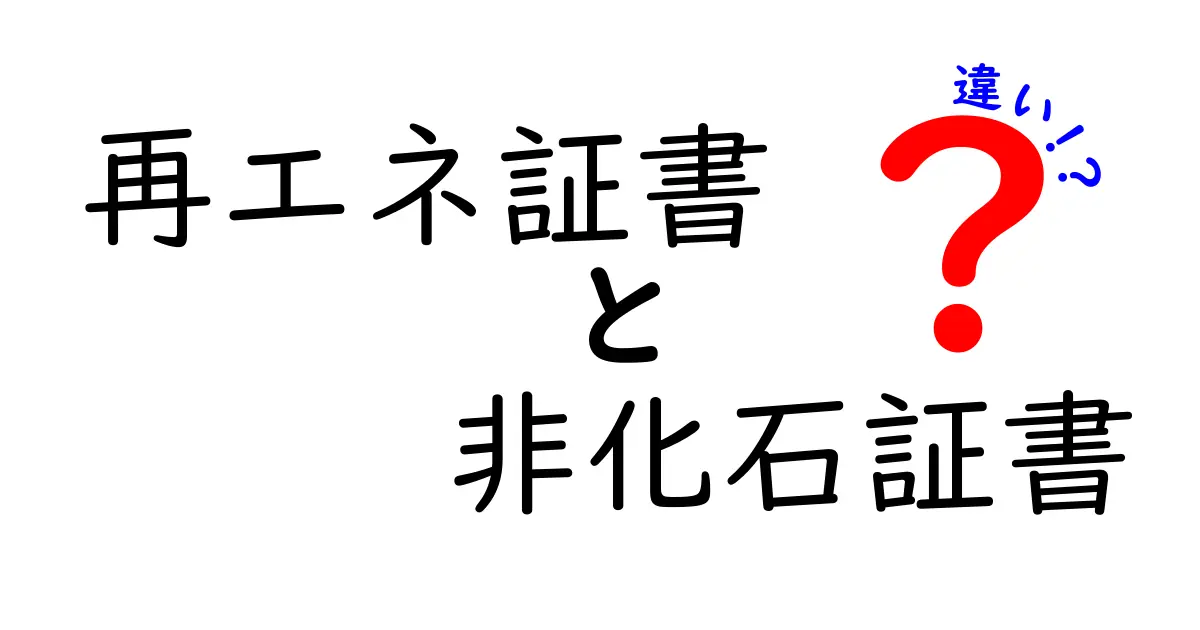

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
再エネ証書と非化石証書とは何か?
私たちの生活で使う電気の中には、地球環境にやさしいエネルギーから作られたものもあります。再エネ証書と非化石証書は、その環境に配慮した電気の証明書です。どちらも「環境に良い電気を使っていますよ」ということを証明するものですが、目的や対象が少し違うんです。
「再エネ証書」は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーから作られた電気に発行されます。いわば、自然の力で生み出されたクリーンな電気を使ったことの証明です。
一方、「非化石証書」は、再生可能エネルギーだけでなく、原子力なども含む化石燃料を使わない電気に対して発行されます。つまり、石炭や石油のような環境に負担をかける燃料を使わない電気全般の証明書ということになります。
この2つの証書は共通点もありますが、それぞれ役割や対象が違うため、混同しないように理解することが大切です。
再エネ証書と非化石証書の違いを表で比較
| 証書の種類 | 対象の電気 | 発行目的 | 具体例 | 利用分野 |
|---|---|---|---|---|
| 再エネ証書 | 太陽光、風力、水力、バイオマスなど再生可能エネルギー由来 | 再生可能エネルギーの普及促進 | 太陽光で作った電気の証明 | 企業や家庭の環境負荷軽減アピール |
| 非化石証書 | 再生可能エネルギー+原子力など非化石燃料由来 | 化石燃料依存の削減とCO2排出削減の促進 | 原子力発電や太陽光の電気の証明 | 電力小売業者の義務達成や環境政策対応 |
なぜ再エネ証書と非化石証書が必要なの?
私たちが毎日使う電気は、石炭や石油の発電所でも作られています。これらはCO2を大量に出してしまい、地球温暖化の原因となっています。そこで、環境にやさしい電気を増やすために、電気の使った量だけクリーンな電気を使っていることを証明する仕組みが必要になりました。
再エネ証書は、特に自然の力で発電した電気を増やしていくために使われます。企業や家庭がこの証書を購入することで、再エネの利用が広がりやすくなります。
非化石証書は、より広い範囲で石炭や石油の利用を減らすことを目的に発行されています。法律で電力会社に利用が義務づけられていることが多く、全体的なCO2排出削減に役立っています。
このように、両者は異なる役割で私たちの環境にやさしい生活を支えるために重要な存在なのです。
まとめ:再エネ証書と非化石証書の違いを正しく理解しよう
再エネ証書は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーに限定した証明書。
非化石証書は、再生可能エネルギーに加え原子力などの非化石燃料由来も含めた証明書で、より広い範囲の化石燃料使用ゼロを目指す取り組みです。
両者を理解することで、どのように環境にやさしい電気が社会で使われているのかがわかります。
ぜひ、電気を選ぶときや環境問題について考えるときに、この違いを参考にしてみてください。
環境に優しい社会づくりは一人ひとりの行動から始まります。再エネ証書や非化石証書は、その大きな助けとなる仕組みです。
再エネ証書の中で面白いのは、バイオマス発電です。木や植物を材料にしてエネルギーを作るこの方法は、使う材料がまた育つので、環境に優しいとされています。でも、実はバイオマスにも色々あって、その燃やし方や原料の選び方によって環境への影響が変わるんです。たとえば、木を切りすぎると逆に森が減ってしまうことも。だから、再エネ証書を考えるときには、こうした細かい部分も知っておくといいですよね。環境にいいって言っても、ちゃんとバランスを考えることが大事なんです。
次の記事: 排気ガスと温室効果ガスの違いとは?わかりやすく解説! »
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
「マイクロ水力発電」と「水力発電」の違いとは?初心者にもわかりやすく解説!
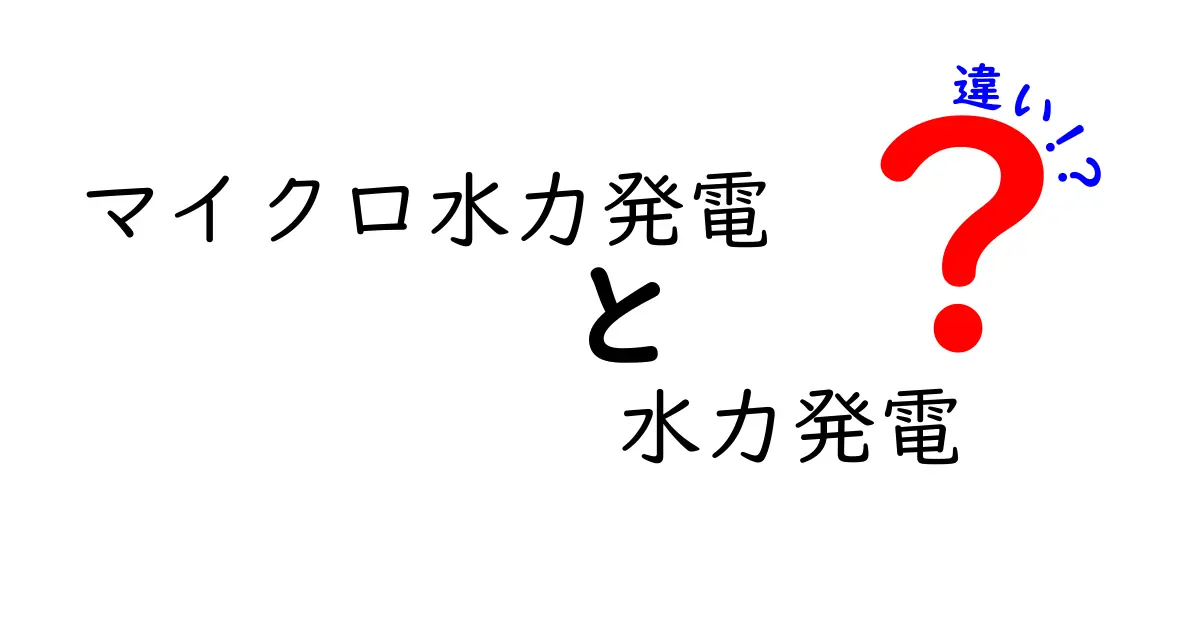

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
マイクロ水力発電と水力発電、基本的な違いとは?
まずはマイクロ水力発電と水力発電の違いを理解するために、それぞれの特徴を押さえましょう。
水力発電は川やダムなどの水の流れを使って発電する方法で、日本でも多くの発電所が存在します。大型の水力発電所は非常に大きな施設で、たくさんの電気を作り出せますが、建設には莫大な費用や時間がかかります。
一方、マイクロ水力発電は、小規模な水の流れを利用した発電です。小さな川や農業用水路などで導入しやすく、発電量は少ないですが設置や維持のコストも低く、環境への影響も小さいのが特徴です。
つまり、マイクロ水力発電は規模が小さく、設置場所も限定されにくいのがポイントです。
マイクロ水力発電の特徴とメリット
マイクロ水力発電は、一般的に出力が100kW以下の小さな電力を作り出す装置を指します。大型の水力発電に比べて、設備が小さく、村や農家単位での利用が可能です。
また、設置の自由度が高いため、自然環境を大きく変えることなく、川の流れの一部だけを利用して発電できます。
メリットとしては、再生可能なエネルギーでCO2排出が少ないこと、電力が自給自足できること、また停電時のバックアップ電源にもなりやすいことが挙げられます。
さらに、設置費用が比較的安いため、地域のエネルギー自立を目指す際に注目されています。
大型水力発電の特徴と役割
大型の水力発電は、ダムを利用して大量の水を貯めて、その水の勢いで大きなタービンを回し、大量の電気を作り出します。
特徴としては、非常に高い発電能力と安定した電力供給が可能なことです。日本全国の電力網を支える重要な発電方法のひとつです。
ただし、ダム建設には多くの時間とお金、そして周囲の生態系や住民生活への影響が指摘されています。
それに比べてマイクロ水力発電は自然破壊が少なく、限定された地域や施設の電源確保に向いています。
マイクロ水力発電と大型水力発電の違いを表で比較
| 項目 | マイクロ水力発電 | 大型水力発電 |
|---|---|---|
| 発電規模 | 100kW以下の小規模 | 数MWから数千MWの大規模 |
| 設置場所 | 小さな川や水路で可能 | 大規模な川やダムに限定 |
| 環境影響 | 少ない | 自然環境に大きな影響あり |
| 設備費用 | 比較的安価 | 数十億円以上かかることも |
| 発電安定性 | 流量変化に影響されやすい | 安定的に大量発電可能 |
まとめ
マイクロ水力発電と水力発電は、規模や設置場所、発電量、環境への影響などで大きく異なります。
マイクロ水力発電は小規模で環境に優しい再生可能エネルギーとして、地域や小さなコミュニティのエネルギー自給に役立ちます。
一方、大型水力発電は国全体の電力を支える重要な役割を持ちながら、環境への影響やコスト面で検討が必要です。
どちらも地球に優しい発電方法ですが、使い分けが大切だといえるでしょう。
マイクロ水力発電の面白いところは、小さな水の流れでも電気が生まれる点です。たとえば、田んぼの用水路など、思わぬ場所に適したポテンシャルがあることがあるんですよ。
実際には流水の速度や量が重要で、たった数百ワットでも節電に役立つケースも多いです。
また、地域の人たちが自分たちで電力を作ることでエネルギーの自立につながり、環境意識の向上にも貢献しているんですね。小さな発電所が意外と身近にある未来が楽しみです。
自然の人気記事
新着記事
自然の関連記事
【初心者向け】FIT証書と非化石証書の違いとは?仕組みや目的をわかりやすく解説!
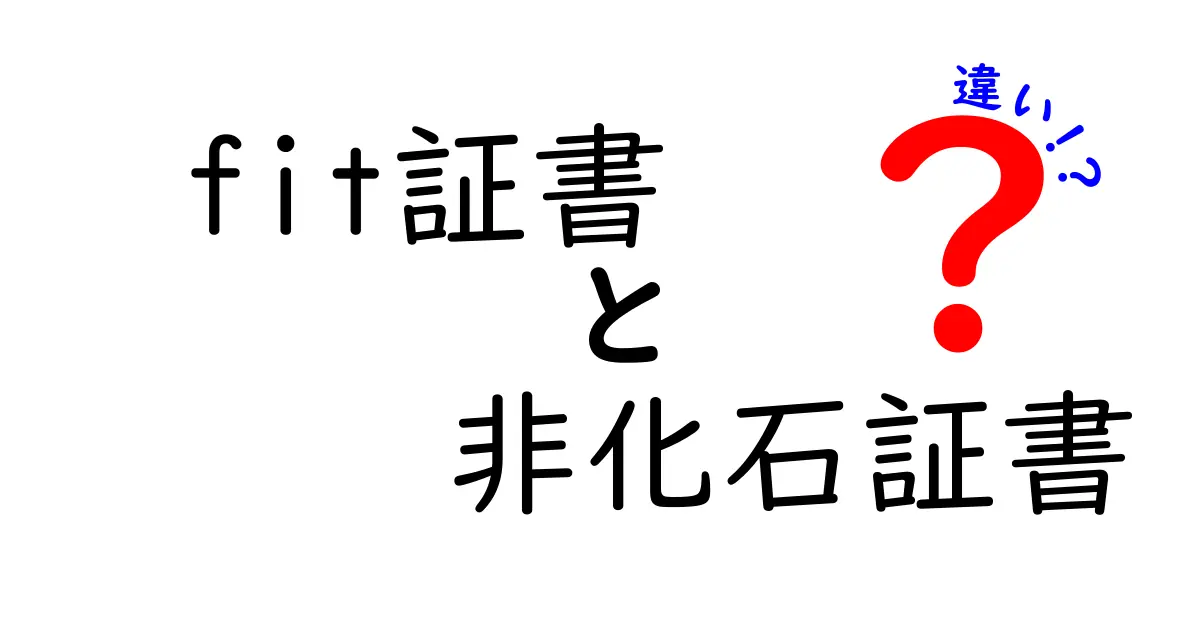

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
FIT証書と非化石証書の基本とは?
日本のエネルギー政策でよく聞く
FIT証書(フィット証書)と
非化石証書ですが、名前は似ていても実は違うものです。
まずはそれぞれが何を指しているのかを
簡単に説明します。
FIT証書は、再生可能エネルギーの普及を目的として、日本政府が定めた「固定価格買取制度(FIT)」に基づき、太陽光や風力などで発電された電気に対して発行される証書です。これを持つことで、発電事業者は売電収入以外に証書の売却で追加の収入を得ることができます。
一方、非化石証書は、火力などの化石燃料を使わない発電で生まれた電気を証明するための証書です。つまり、環境にやさしい再生可能エネルギーだけでなく、原子力や水力発電なども含めた化石燃料を使っていない電力であることを示すものなのです。
このように、FIT証書は主に再生可能エネルギーの証明であり、非化石証書は化石燃料を使わない(非化石)電力全般の証明と覚えておくと分かりやすいでしょう。
FIT証書と非化石証書の仕組みの違い
では、具体的にFIT証書と非化石証書はどうやって作られ、使われているのでしょうか。
まずFIT証書ですが、これは電気を作った発電事業者が電力会社に電気を売った時に発行されます。日本では再生可能エネルギーの導入を促すために、政府が決めた一定期間・固定価格で買い取る制度があり、それに参加した発電事業者が対象です。
FIT証書は売られたり買われたりして、市場で取引されることもあり、これにより発電者は経済的なインセンティブを得て再エネを増やすことができる仕組みです。
一方、非化石証書は主に電力会社が国に対して非化石電源の利用量を報告し、これを証明するために発行されます。また、この証書は電気の供給者が、どれだけ環境に優しい電気を供給しているかをアピールする手段にもなります。
両者は似た役割を果たしつつも、発行条件や使い方に違いがあります。FIT証書はあくまで再生可能エネルギー発電の支援を目的としていますが、非化石証書は環境負荷の少ない電気の利用証明を広くカバーしています。
FIT証書と非化石証書の違いを表で比較!
| 項目 | FIT証書 | 非化石証書 |
|---|---|---|
| 対象電源 | 再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス等) | 再生可能エネルギー+原子力+水力など非化石電源全般 |
| 発行主体 | 発電事業者が電力会社に売電した際に発行 | 国が非化石電源利用を証明するために発行 |
| 目的 | 再生可能エネルギーの普及促進と発電者支援 | 非化石電源の利用証明と環境価値の提供 |
| 取引形態 | 市場で売買可能 | 供給実績に応じて電力会社が活用 |
| 活用例 | 発電事業者の追加収益、企業の環境認証 | 電力の環境価値アピール、CO2排出削減証明 |
まとめ:それぞれの証書の特徴を理解して活用しよう
FIT証書と非化石証書は、どちらも環境に優しい電気の価値を証明するための仕組みです。
しかし、FIT証書は主に再生可能エネルギーの発電者を支援し、その普及を促すために使われます。
一方で、非化石証書は化石燃料を使わない電気の利用を証明して、企業や電力会社が環境負荷低減をアピールする役割があります。
私たち消費者や企業がこれらの仕組みをよく理解することで、より環境に配慮した電気の利用や政策への関心が高まります。
環境問題に対して一歩を踏み出すためには、普段使う電気がどうやって作られているのか、どんな証明があるのか知ることも大切ですね。
これからも再生可能エネルギーや非化石電源の利用が広がり、持続可能な社会づくりに貢献していくことを期待しましょう。
FIT証書って聞くと、ただの『証書』と思いがちですが、実はこれが再生可能エネルギー発電の経済的な裏付けになっているんです。
つまり、例えば太陽光で電気を作った人が、それを売るだけじゃなくて、このFIT証書を売ってもう一つ収入を得られる仕組みなんですね。
これ、なんだか昔の切手収集みたいに取引されていて、証書を通じて環境保護に参加できるって考えると面白くないですか?
証書があるからこそ、再生可能エネルギーの利用が増えて、地球に優しい未来への足がかりになっているんですよ。
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
小水力発電と水力発電の違いとは?初心者でも分かる仕組みと特徴をやさしく解説!
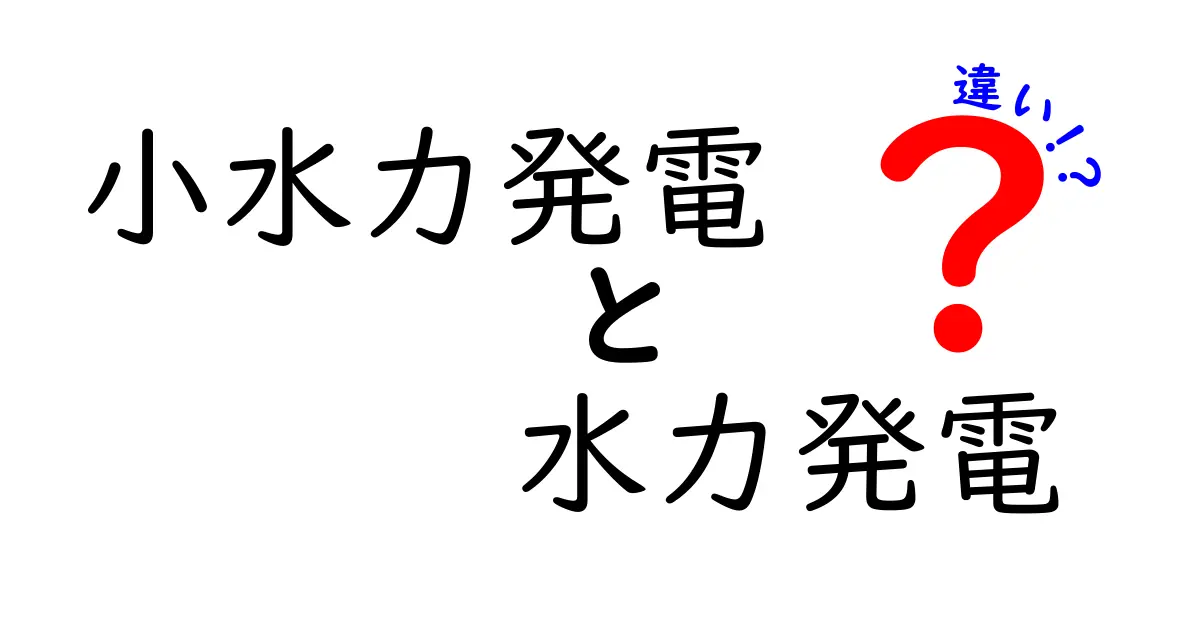

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
小水力発電と水力発電の基本的な違い
まずは小水力発電と水力発電の違いを理解するために、それぞれが何を指しているのかを知りましょう。
水力発電は、川やダムの水の力を使って電気を作る方法の一つです。川の流れや落差を利用して、水のエネルギーをタービンに伝え、それが回ることで発電機が動いて電気が生まれます。
一方、小水力発電はこの水力発電の中でも、比較的小さな規模で行われる発電方法を指します。具体的には、出力が数百キロワット以下の発電施設を言い、ダムを大きく作ったり、大規模な設備がいらず、自然の川の流れを活用しやすい特徴があります。
つまり、水力発電は大きな電力を生み出すのに対し、小水力発電は小規模で地域に適した発電方法と覚えると分かりやすいです。
技術的な仕組みと設置環境の違い
小水力発電と水力発電は、基本的な仕組みは似ていますが、設置環境や使われる技術に違いがあります。
大規模な水力発電ではダムの建設が必要となり、巨大な水の貯め池を作って放水させることで大きな落差を生み出します。それによって、強い水流が生じ、多くの電気を生み出せるのです。
小水力発電は渓流や小川などの自然の流れを利用するため、ダムを作る必要がありません。そのため環境への影響も少なく、地域の水資源を有効活用する手段として注目されています。また、設備は比較的簡単で小さく、設置や管理コストも抑えられますが、その分発電可能な電力量は限定的です。
まとめると、大規模は人工的なダムや設備、小規模は自然の流れを活かし手軽に設置できる技術ということです。
小水力発電と水力発電のメリット・デメリット比較表
まとめ:どちらが適しているのか?
小水力発電は自然の力を活かし、地域の特色や環境を損なわずに発電できる方法として増えています。特に電力需要が少ない場所や、自然環境の保護が重視される地域では非常に効果的です。一方で、より大きな電力量を安定して供給したい場合は、ダムを利用した大規模水力発電が適しています。
今後、日本を含む多くの国が再生可能エネルギーの導入を推進する中で、小水力発電は環境に優しく、地域に根ざしたエネルギー源として注目されているのです。
ぜひ、この違いを理解し、私たちの生活にどう役立つのかを考えてみてください。
小水力発電に使われるタービンにはいろいろな種類がありますが、中でも「クロスフロータービン」というタイプは、小川の自然な流れを効率よく電気に変えることができるんです。これは水がタービンを横切るように流れる仕組みで、環境への影響も最小限に抑えられます。小規模でも賢く自然エネルギーを活用できる秘密の一つですね!
前の記事: « SAFとバイオ燃料の違いとは?未来のエコ燃料をわかりやすく解説!