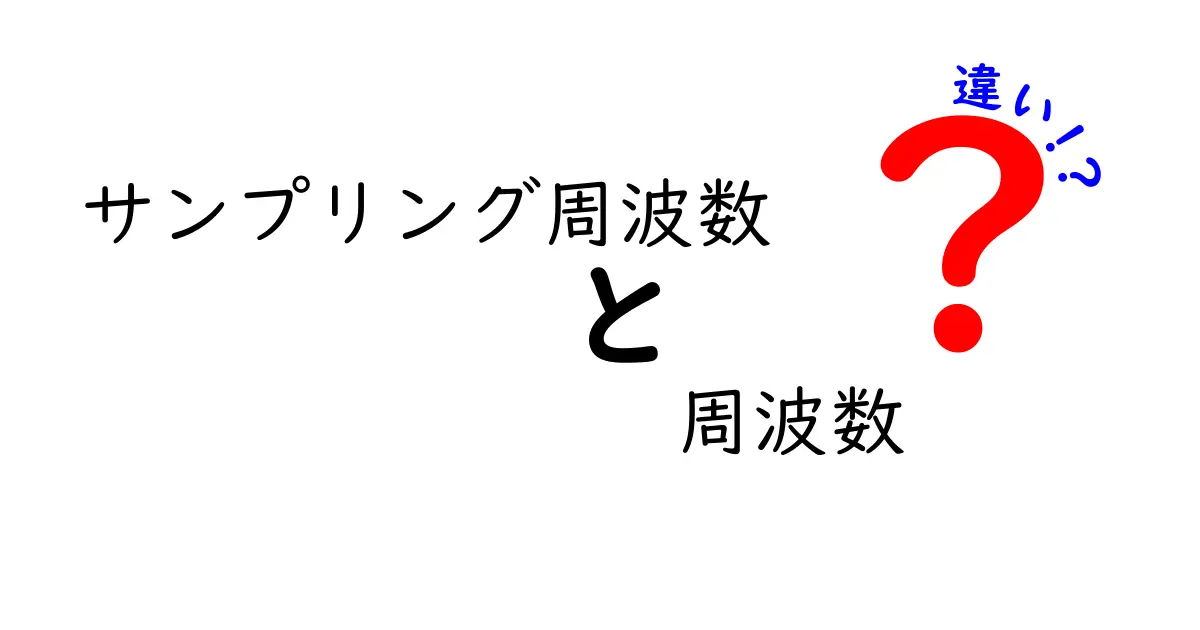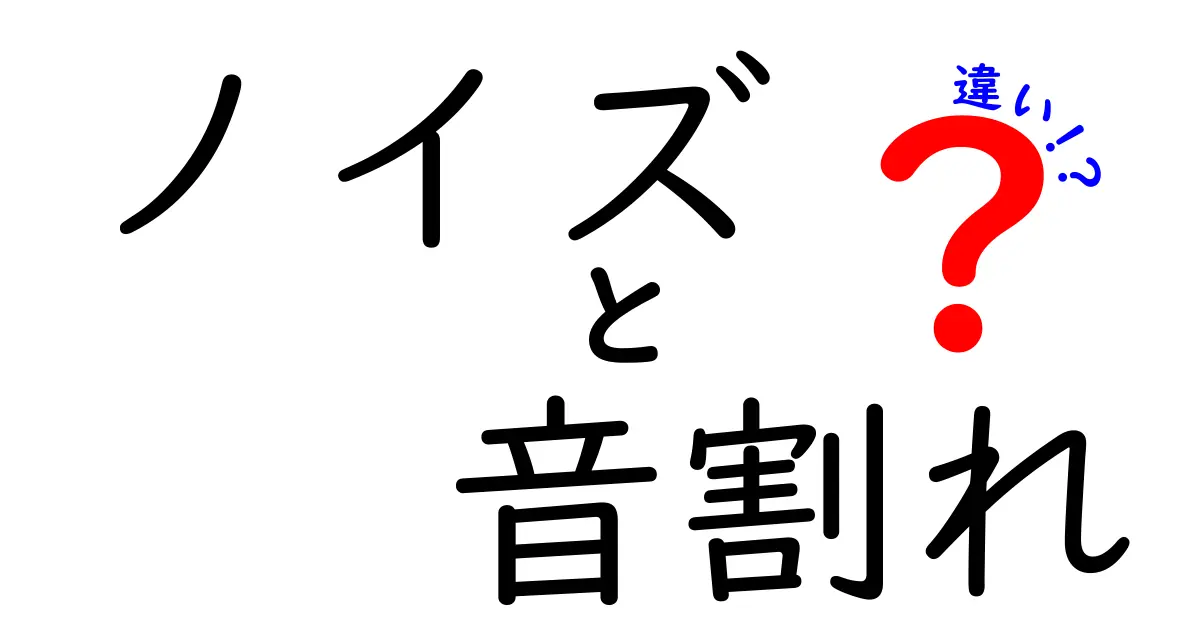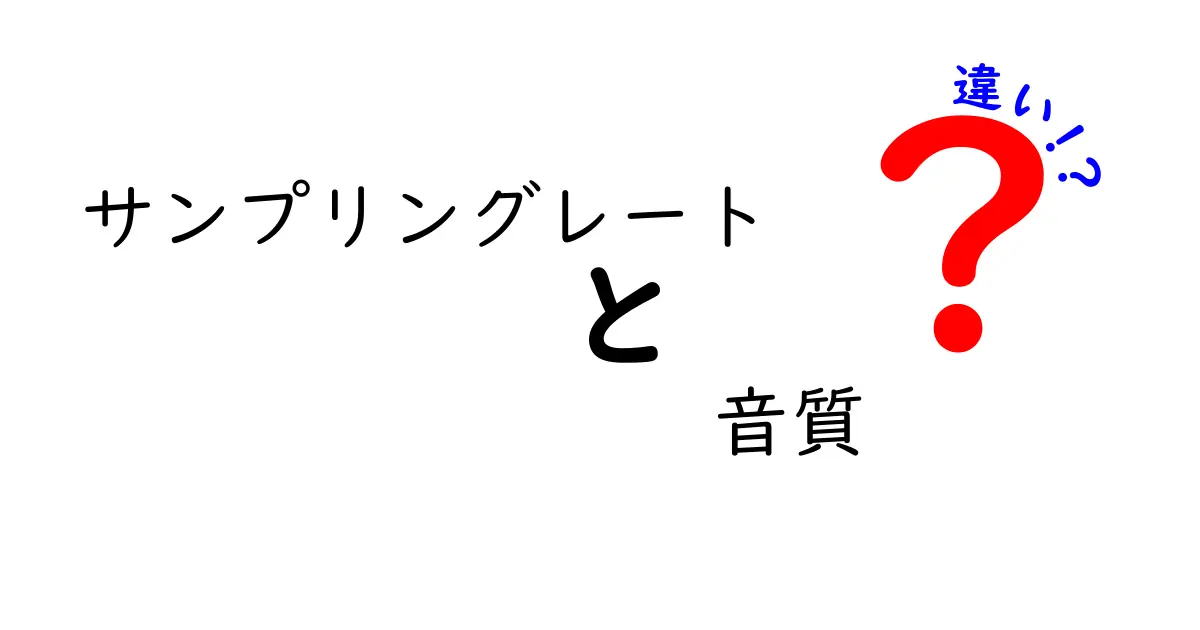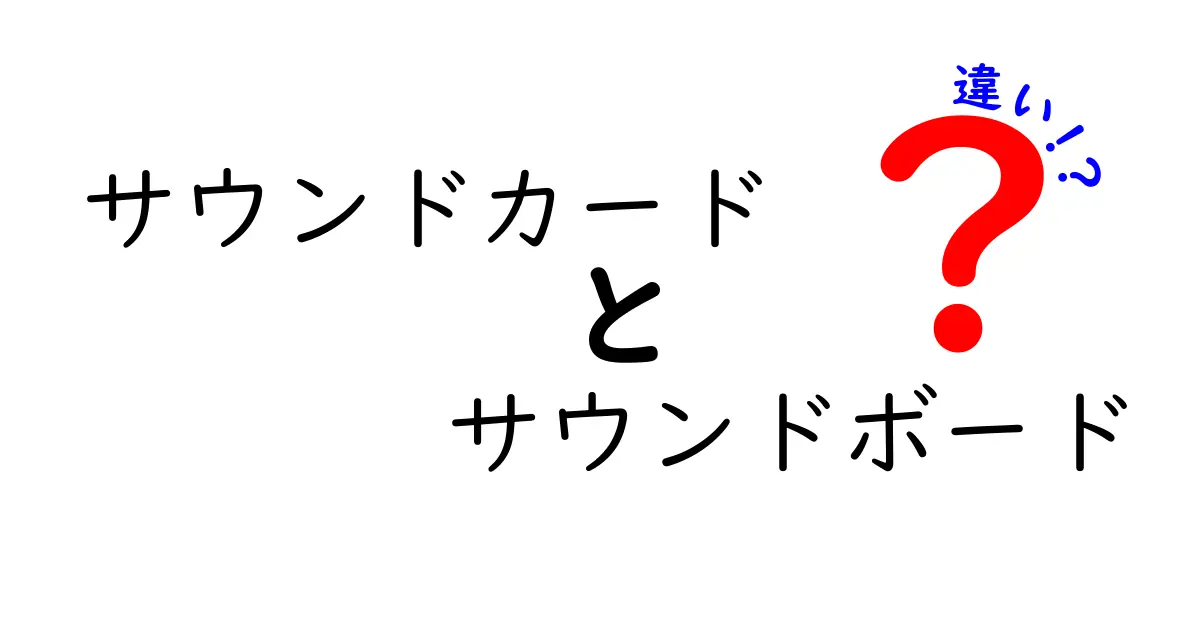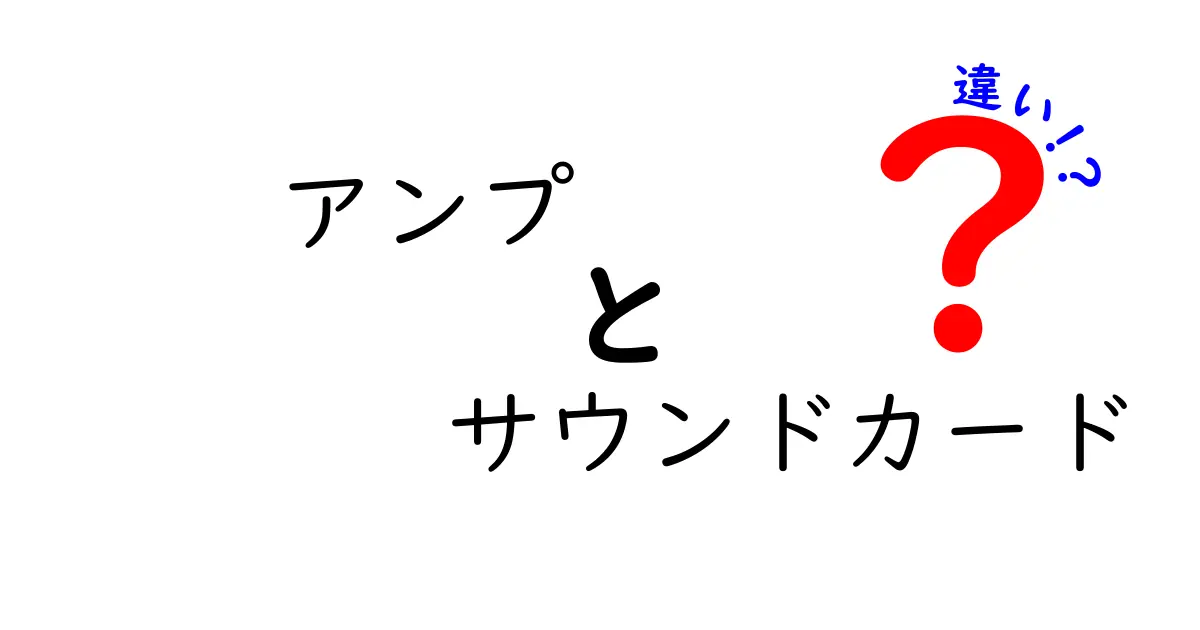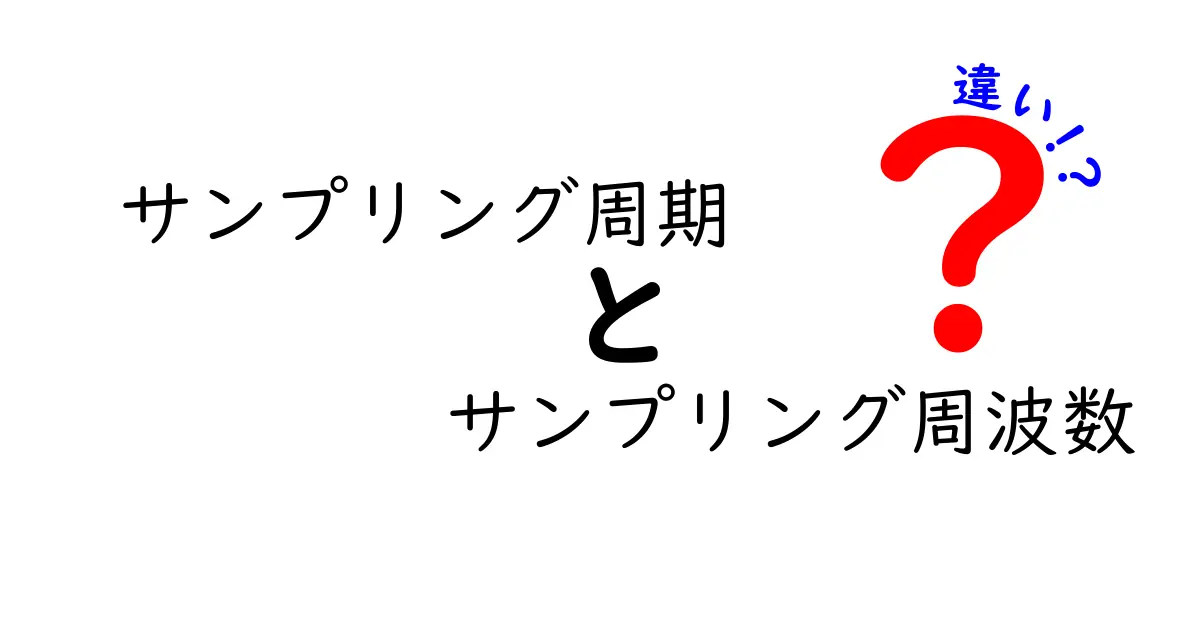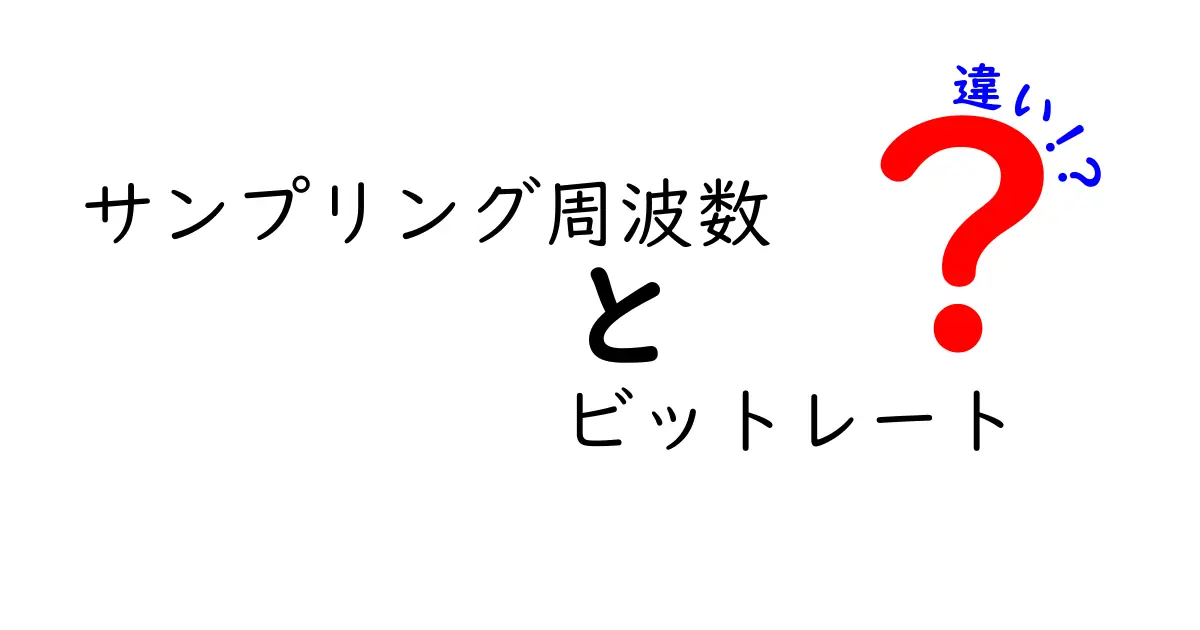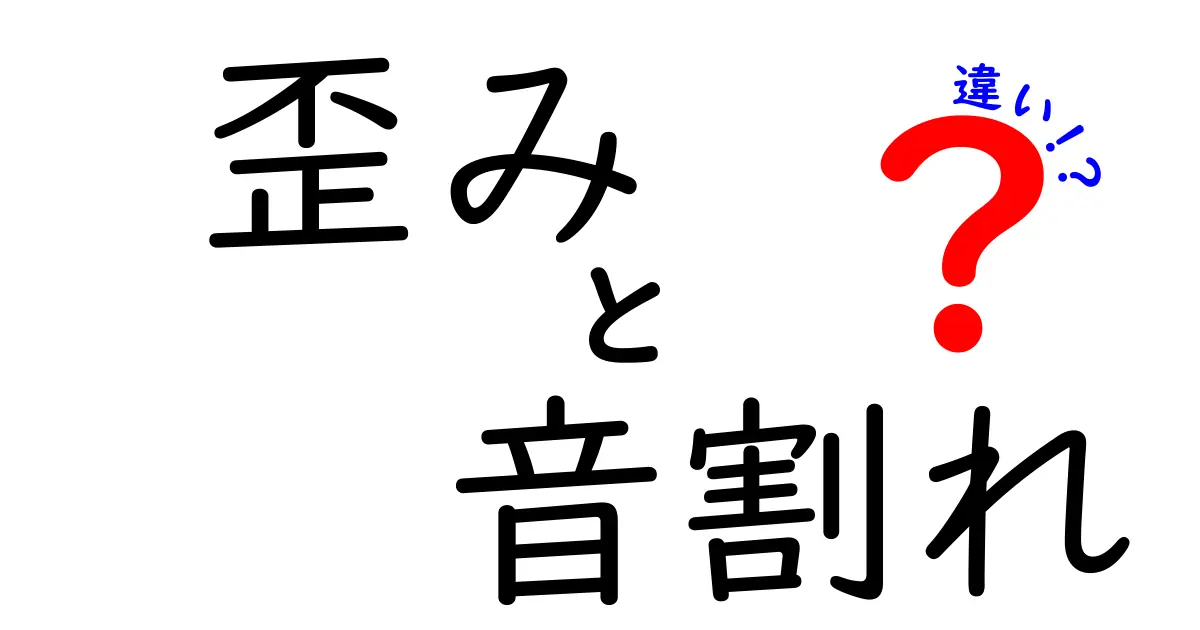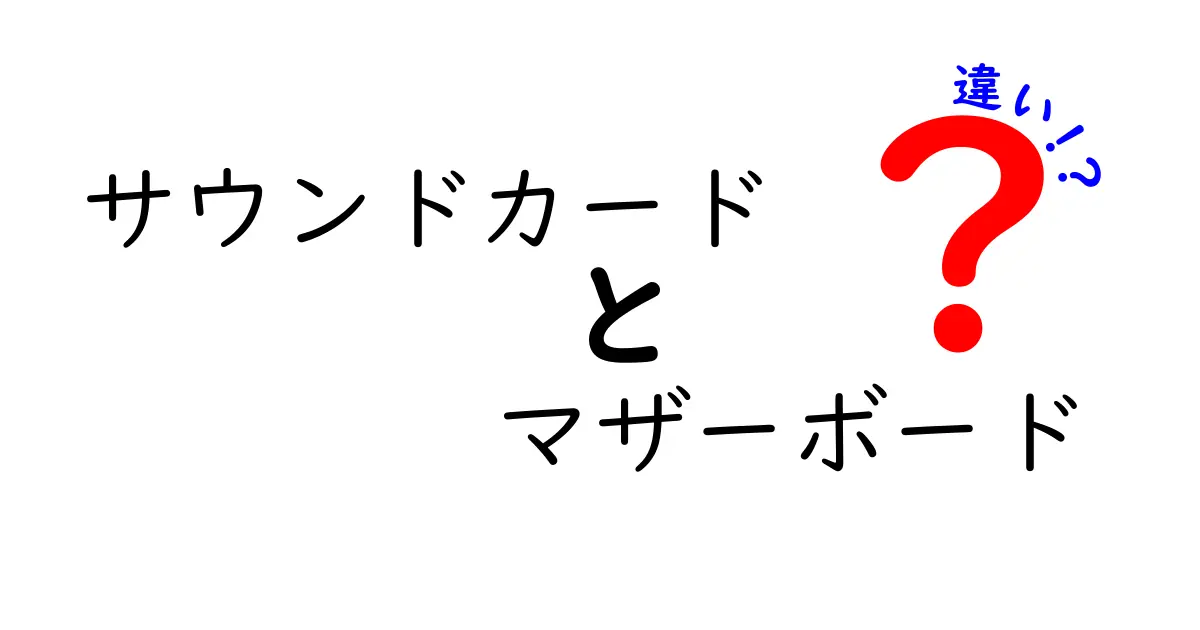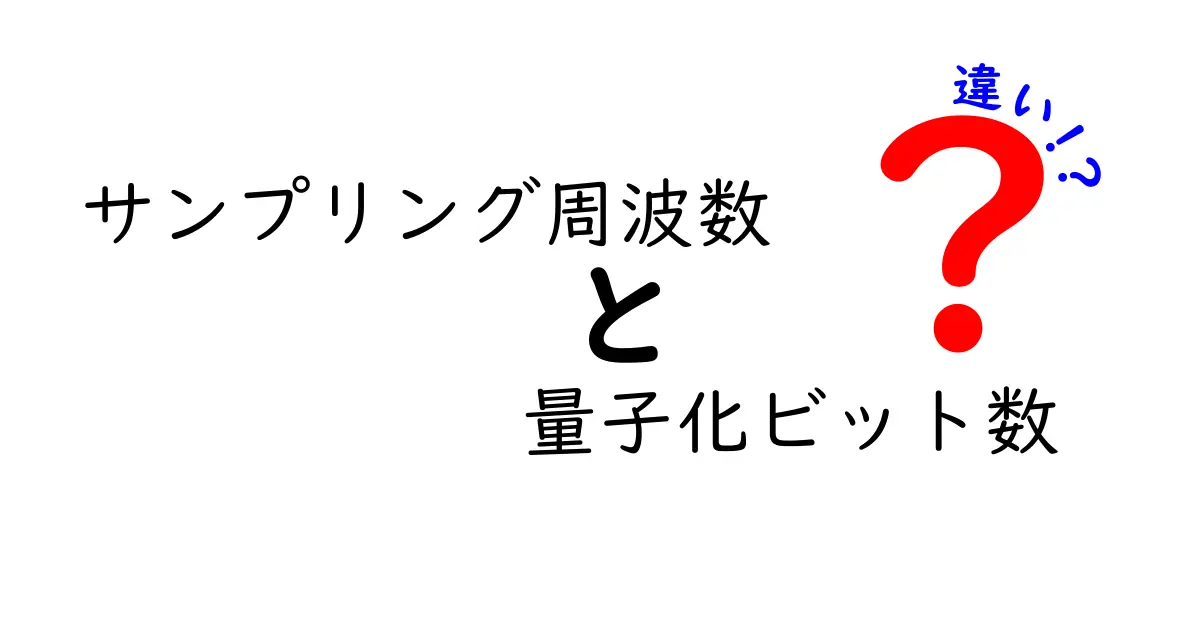

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サンプリング周波数と量子化ビット数の違いを理解するための徹底ガイド:音をデジタル化する仕組みを紐解くとき、私たちは日常生活で耳にしている音楽や録音の背後にある「数字の世界」を知ることになります。ここでは、周波数とビット深度がどう音質に影響するのか、どんな場面でどちらを重視すべきかを、難しくならないように具体例や比喩を使いながら丁寧に解説します。デジタル音響の基礎を学ぶ人にとっては、サンプリング周波数が高いほど高音の再現が良くなると感じるかもしれませんが、それだけではなくフィルタリングの影響やデータ量の増加も同時に考える必要があります。量子化ビット数も同じく、音の細かなニュアンスやノイズのレベルを決定します。
最初に、サンプリング周波数とは何かを、耳で聞こえる音の世界と結びつけて説明します。音は連続した現象ですが、デジタル機械は秒間に何回その音を切り取って記録するかを決めます。例えば、44,100回/秒で切り取ると、人間の聴覚で感じられる約20kHzの範囲を適切に再現できる近い値になります。ここで重要なのは、サンプリング周波数が高いほど高音がよりはっきりする一方、データ量が増えるという現実です。すなわち、周波数が高いと音の「解像度」が上がり、ノイズの影響も変化します。
次に、量子化ビット数とは何かを見ていきます。音の大きさをどう数字で表すかの尺度で、ビット数が多いほど音の細かな差が再現でき、ダイナミックレンジ(音の強さの幅)が広がります。例として、16ビットは約96dBのダイナミックレンジを実現します。24ビットは約144dB程度まで広がり、静かな場面での微妙なニュアンスを拾いやすくなります。もちろん、量子化ビット数が増えるとデータ量も増えます。ここで重要なのは、私たちが実際に聴く環境や機材によって「どの程度の深さが必要か」が変わるという点です。
また、サンプリング周波数と量子化ビット数の組み合わせがデータ量に与える影響を理解することも重要です。例えば、モノラルの音声で44.1kHz/16-bitの場合とステレオの音源で同じ設定、あるいは48kHz/24-bitのような高品質設定を比較すると、1秒あたりのデータ量が違うことがわかります。表を使うと視覚的にも理解しやすいので、以下の表を見てみましょう。
結論として、サンプリング周波数と量子化ビット数は、それぞれ音の再現性とデータ量のトレードオフをつくる要素です。CD品質は44.1kHz/16-bit、制作現場では48kHz/24-bitなどがよく使われますが、用途に応じて選ぶのが賢い方法です。
友達と音楽の話をしていて、サンプリング周波数の話題が出たとき、実は周波数って言葉が出ても音楽の『細かさ』は数字だけで決まるわけではないんだと思います。サンプリング周波数が高いほど耳に届く微妙な音の揺れまで拾えるように感じますが、実際には会話のテンポや聴く環境、再生機器の特性も大きく影響します。だから、私たちは「高ければいい」という単純な話ではなく、どんな場面で何を重視するべきかを、データ量との関係も考えながら考えると面白い、という結論に落ち着くことが多いのです。