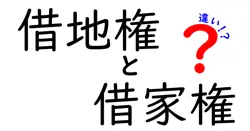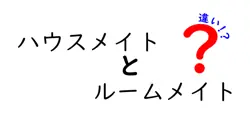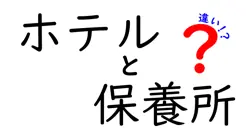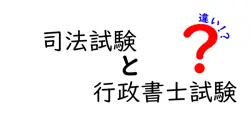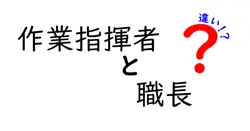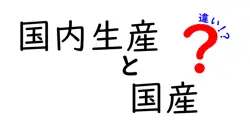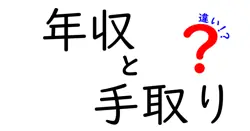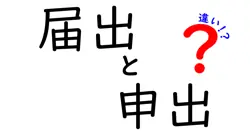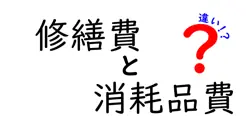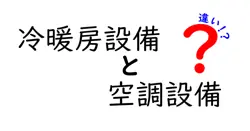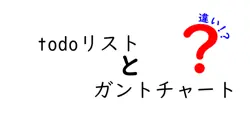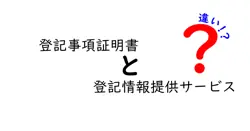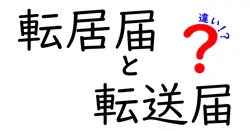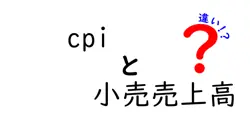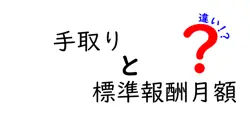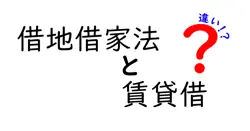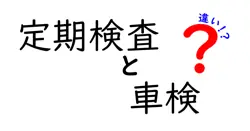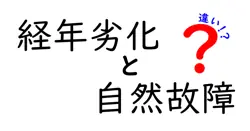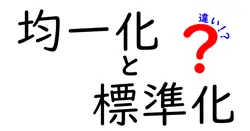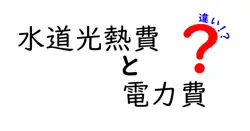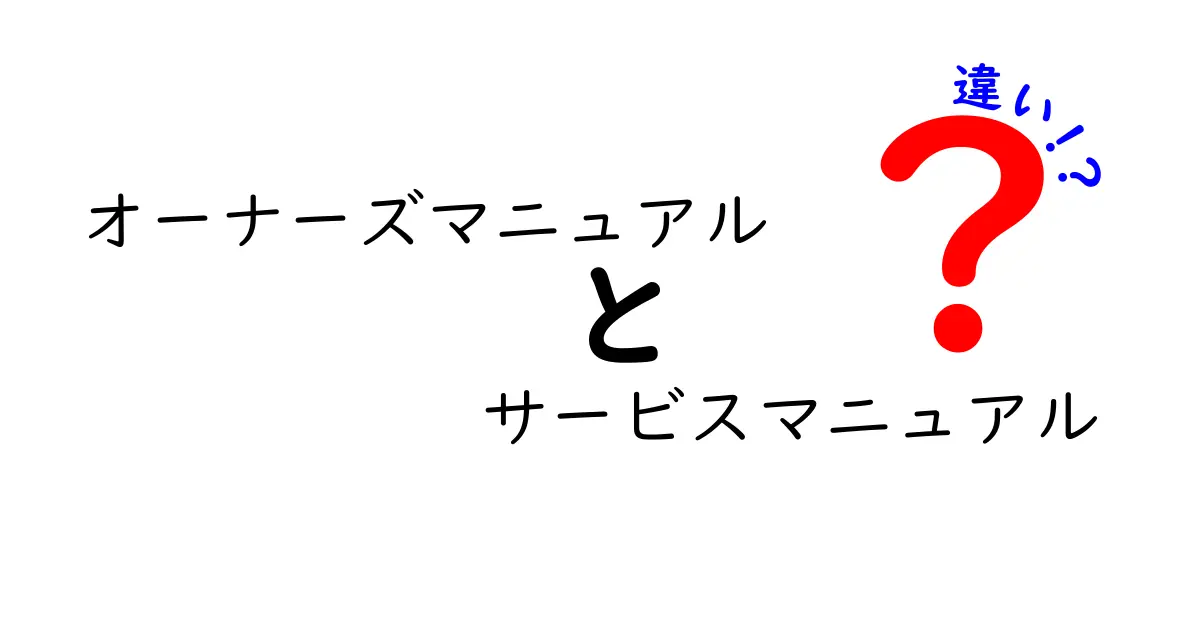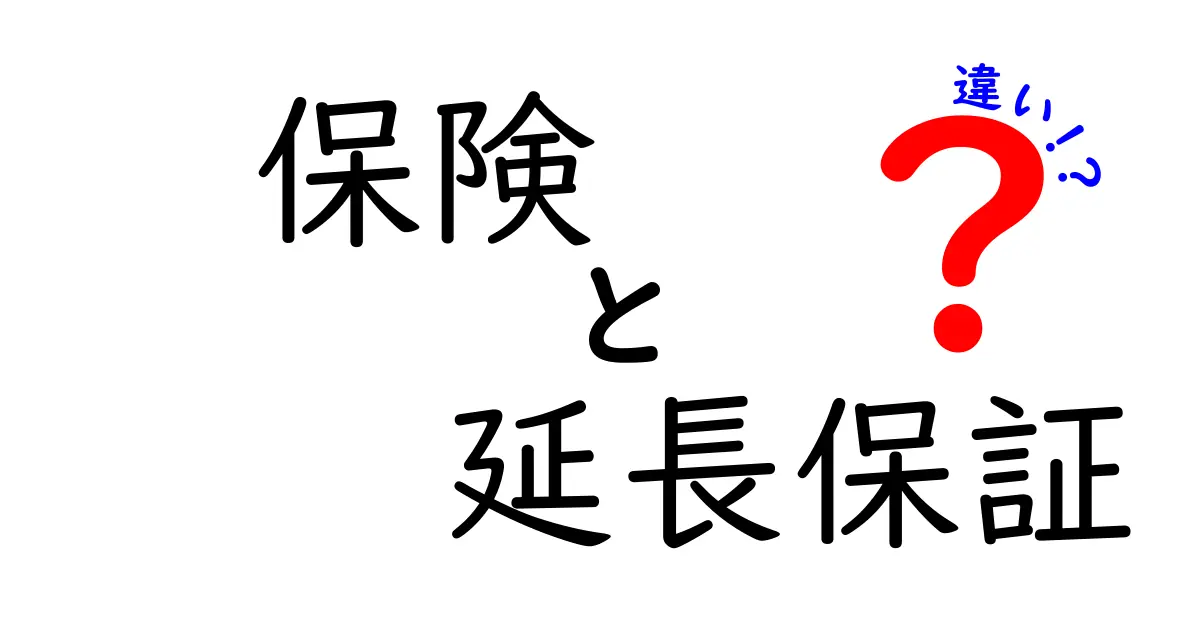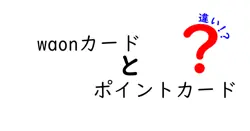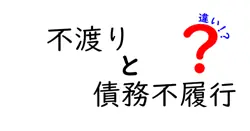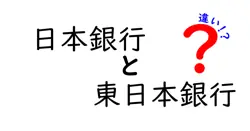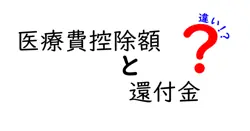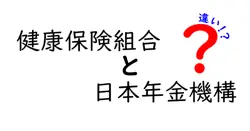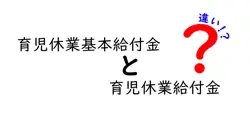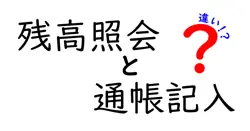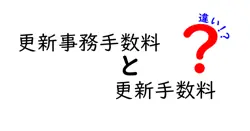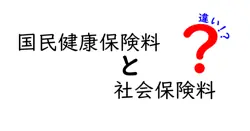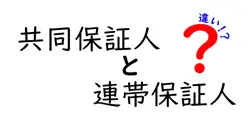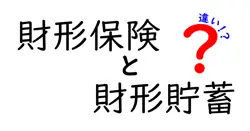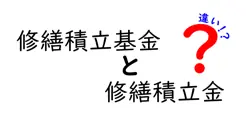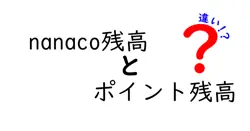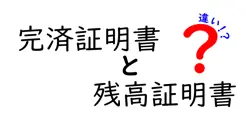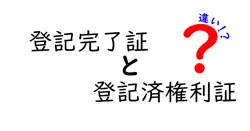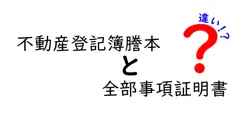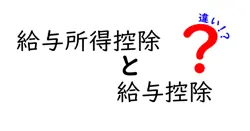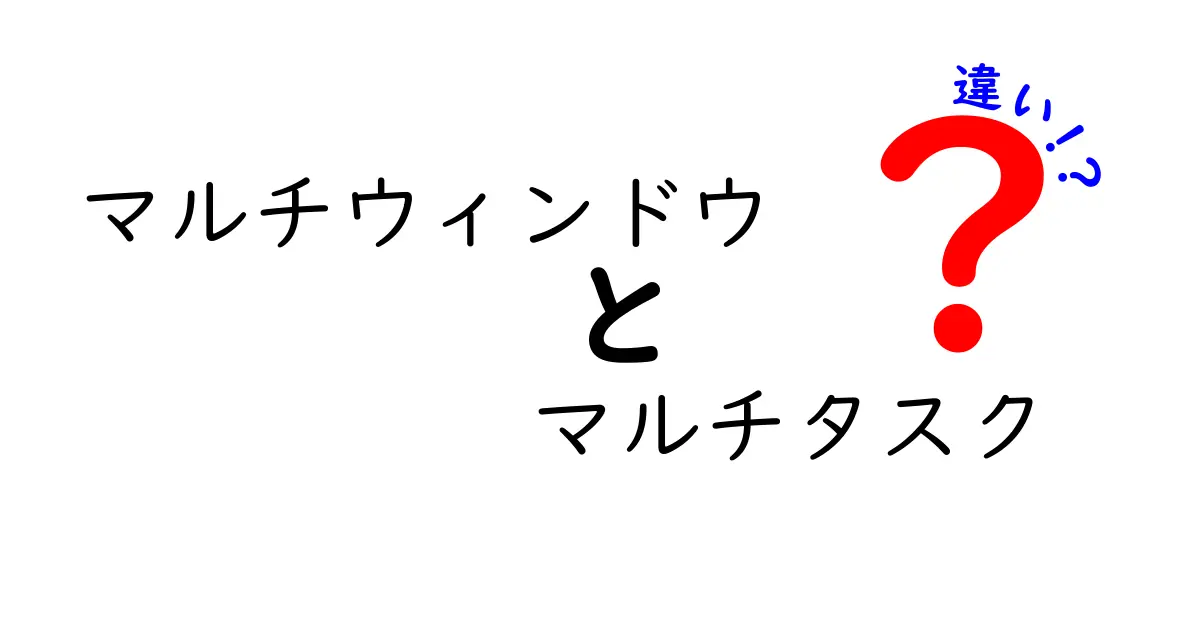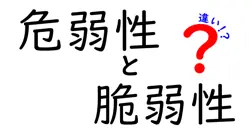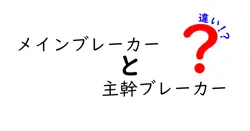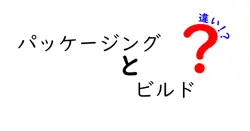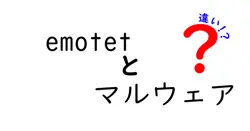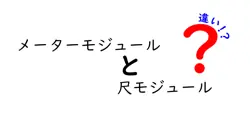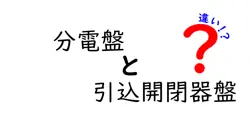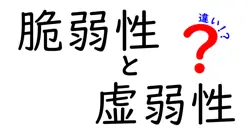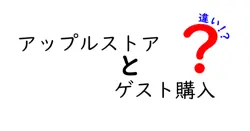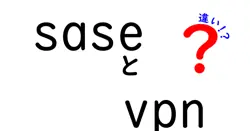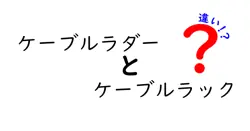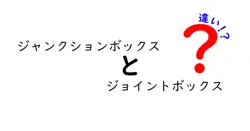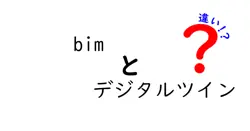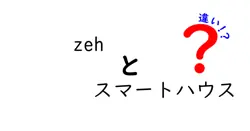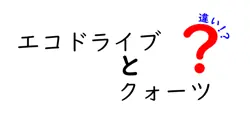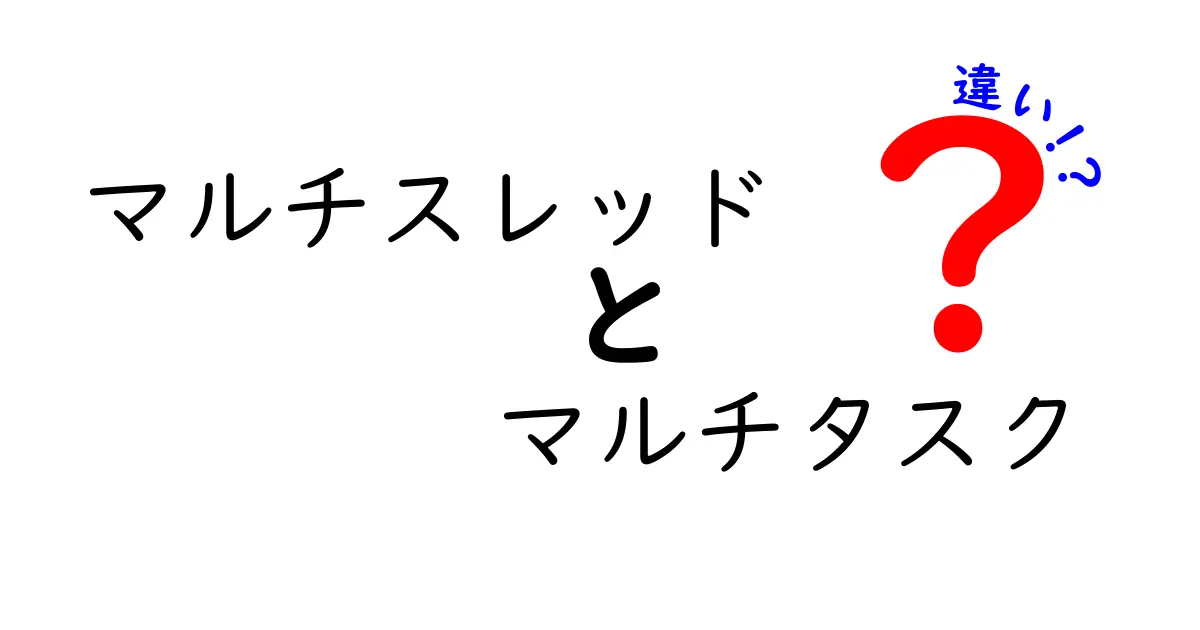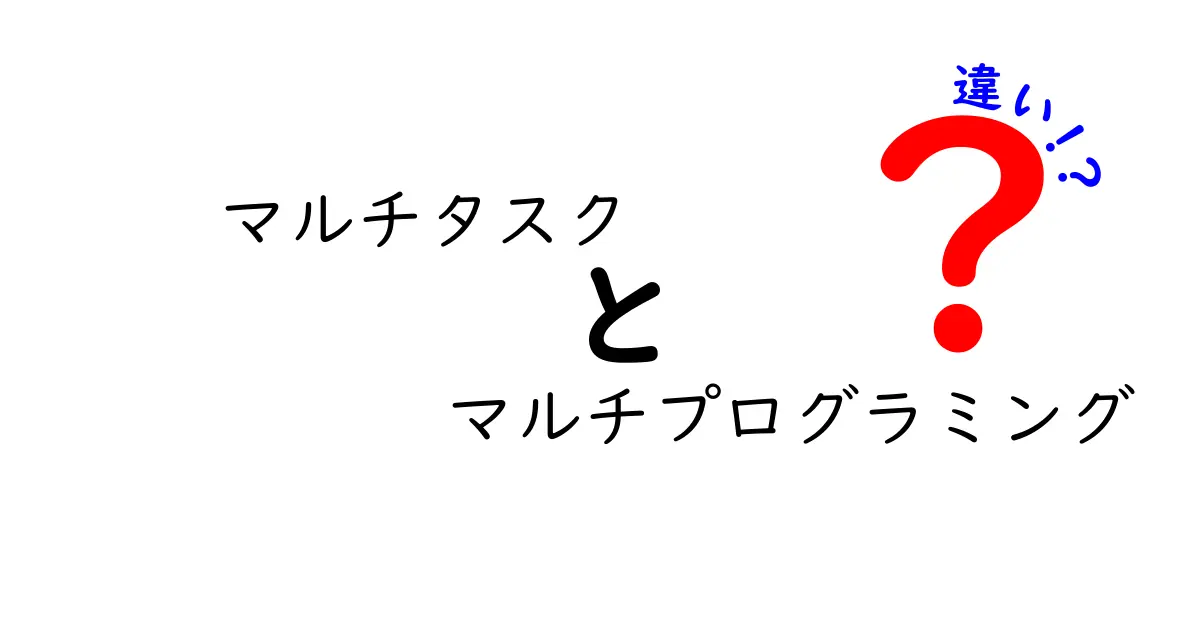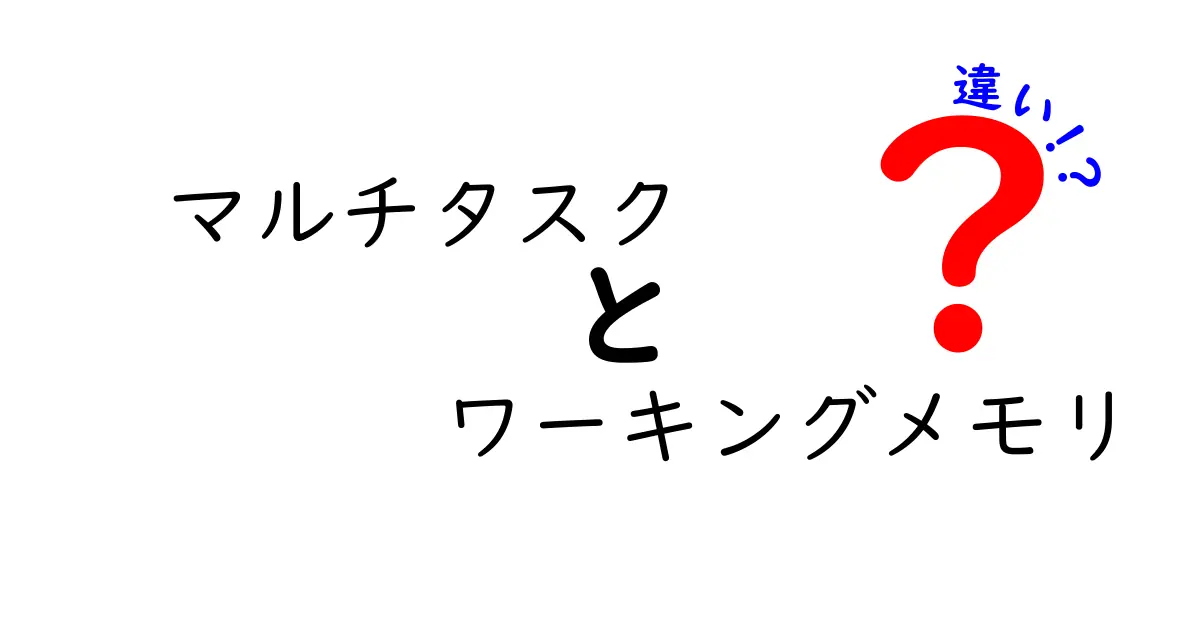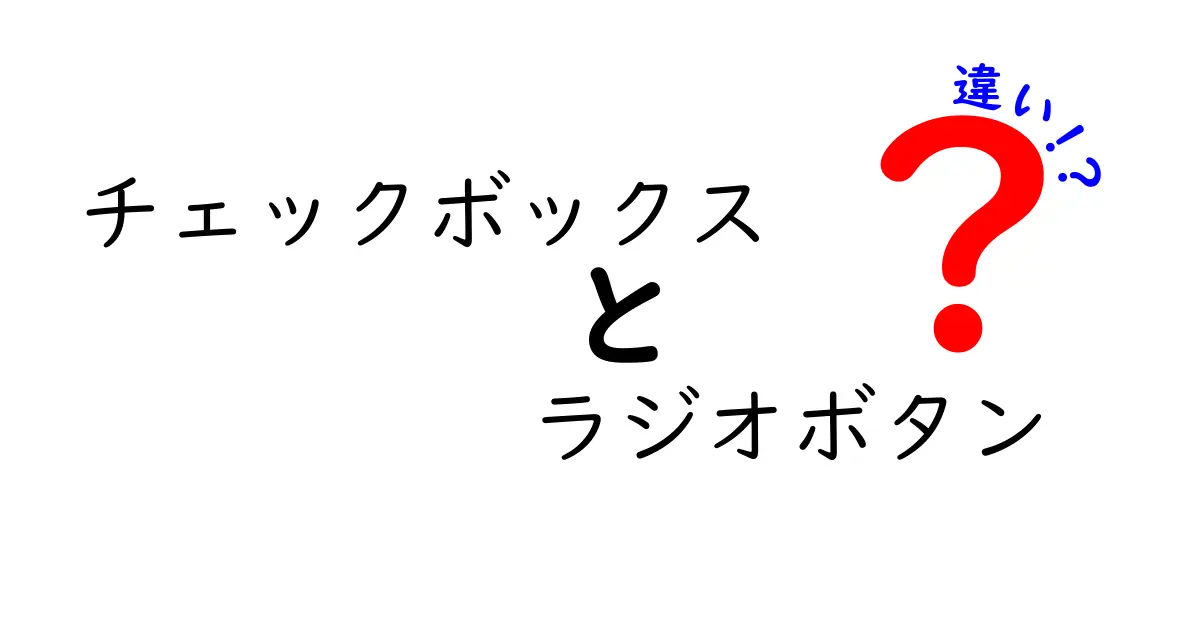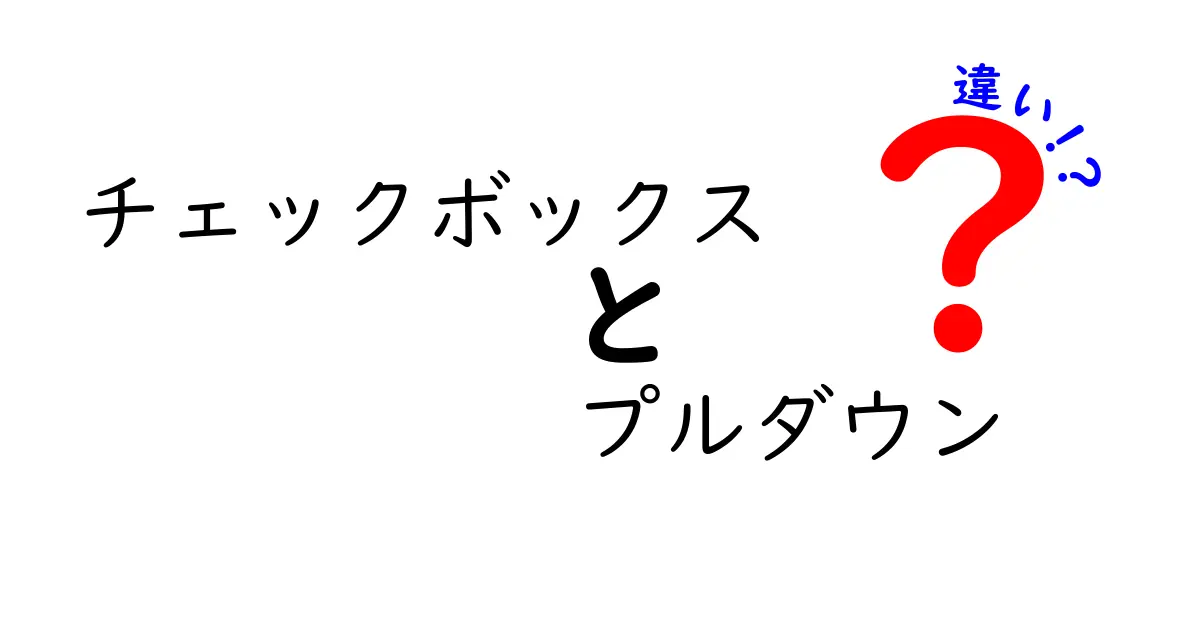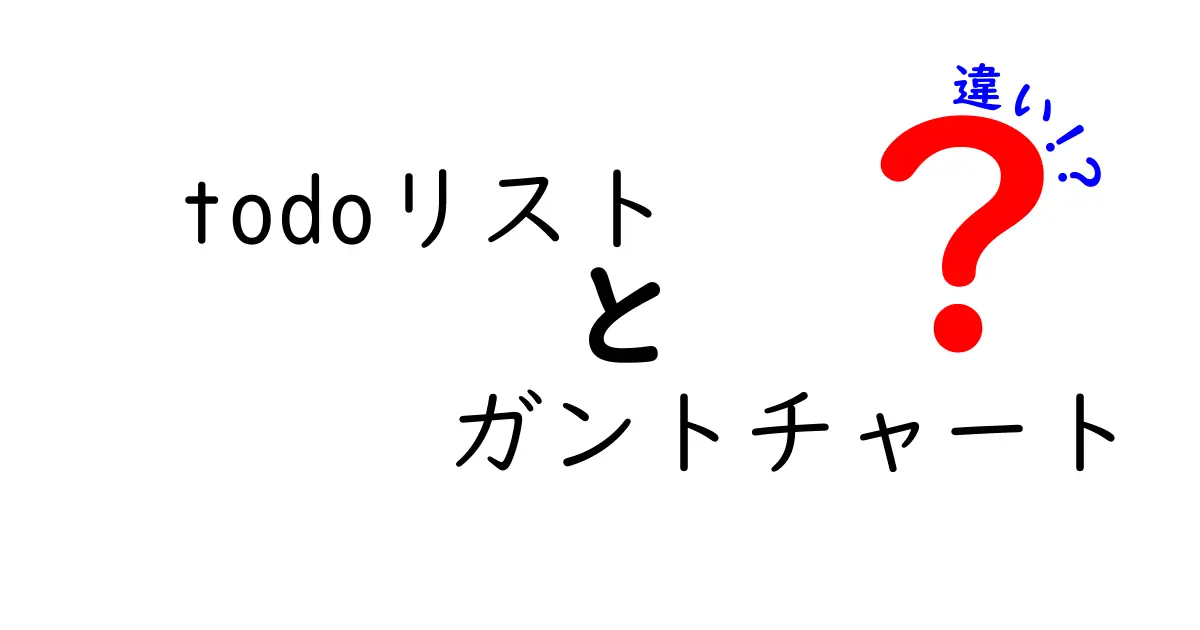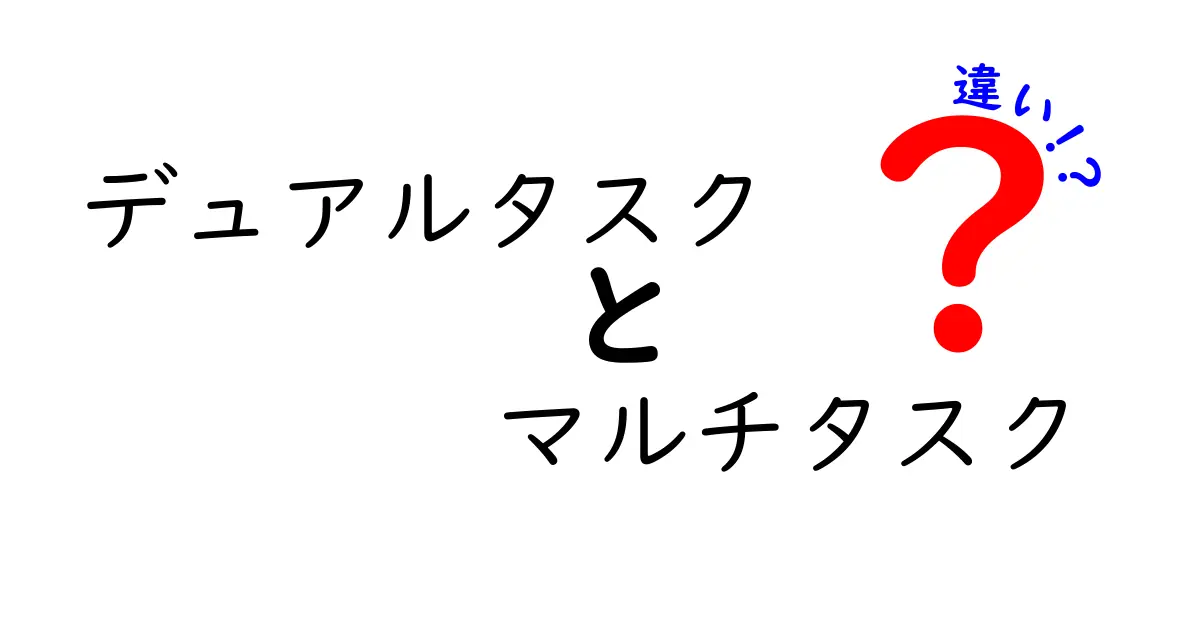
デュアルタスクとマルチタスクの基本的な違いとは?
日常生活や仕事の中で「同時に複数のことを進める」というシーンはよくあります。この時に使われる言葉にデュアルタスクとマルチタスクがあります。どちらも複数の作業をこなすことを指しますが、実は意味や使い方が少し違います。
デュアルタスクとは、2つの異なるタスクを同時に行うことに集中する状態です。例えば、音楽を聴きながら簡単な計算問題を解くといった行為がこれに当たります。
一方でマルチタスクは、2つ以上の作業を切り替えながら短時間で処理していくことを指し、複数のタスクを効率よく並行処理するイメージです。
このようにデュアルタスクは2つのタスクに集中して処理するのに対し、マルチタスクは数多くのタスクを素早く切り替えながら処理する違いがあります。
学校や職場で学習や作業を効率よく進めるためには、この違いを理解することが大切です。
デュアルタスクとマルチタスクの特徴とメリット・デメリット
どちらも複数の作業を同時に進める手法ですが、それぞれ特徴やメリット、デメリットがあります。
デュアルタスクの特徴は、主に2つのタスクに同時集中することです。例えば、スマホで音楽を聴きながら読書をすることが挙げられます。
強みは、慣れると2つのタスクの処理がスムーズになることですが、2つ以上の集中力が必要なタスクは難しいという点がデメリットです。
マルチタスクは複数の作業を時間を区切りながら切り替えて行います。例えば、メールの返信をしながらテレビを見る、または会議の準備と報告書作成を交互に行うことです。
メリットは、時間を効率よく使い多くのタスクをこなせる点ですが、度重なる切り替えで集中力が途切れ生産性が落ちるリスクもあるのがデメリットです。
以下の表で詳細をまとめます。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| デュアルタスク | 2つの作業に同時集中 | 集中して効率アップ可能 | 2つ以上の複雑なタスクは難しい |
| マルチタスク | 複数の作業を切り替えながら処理 | 多くのタスクを短時間で消化可能 | 切り替えによる集中力低下の可能性 |
仕事や勉強で活かすためのポイントと注意点
仕事や勉強でデュアルタスクとマルチタスクを上手に使い分けることで、効率を上げることができます。
まず、集中が必要な複雑な作業や学習はデュアルタスクで取り組みましょう。例えば、数学の問題を解きながら同時に説明を聞くなど、2つに集中することが効果的です。
一方、メールのチェックや簡単な作業の合間に違うタスクをこなす場合は、マルチタスクが役に立ちます。
しかし、マルチタスクは繰り返すと頭が混乱しやすく、作業ミスや集中力の低下につながります。
特に大切な仕事や難しい課題は、マルチタスクで無理にこなそうとせず、一つずつ丁寧に処理する方が結果的に効率が良い場合もあります。
まとめると、デュアルタスクは同時に2つを集中、マルチタスクは多くの作業を素早く切り替えるという性質を理解して、適切な場面で使い分けることがポイントです。
今回は『デュアルタスク』について、ちょっと深掘りしましょう。普段、「何かをしながら別のことをする」ってありますよね。でもデュアルタスクは特に2つのタスクに同時集中すること。例えば、音楽を聴きながら簡単な計算をするのがそうです。でも意外と脳は完全に2つに集中できるわけじゃなく、実は素早く切り替えているだけという説もあるんです。だから『同時にやってるつもりでも実は交互に処理している』って考えると面白いですよね。脳の仕組みを知ると、日常の作業効率もアップしそうです!
次の記事: 反省点と課題の違いは?意味や使い方をわかりやすく解説! »