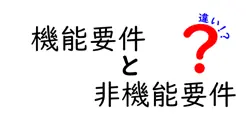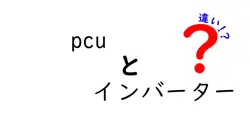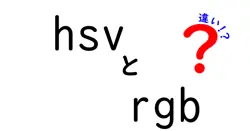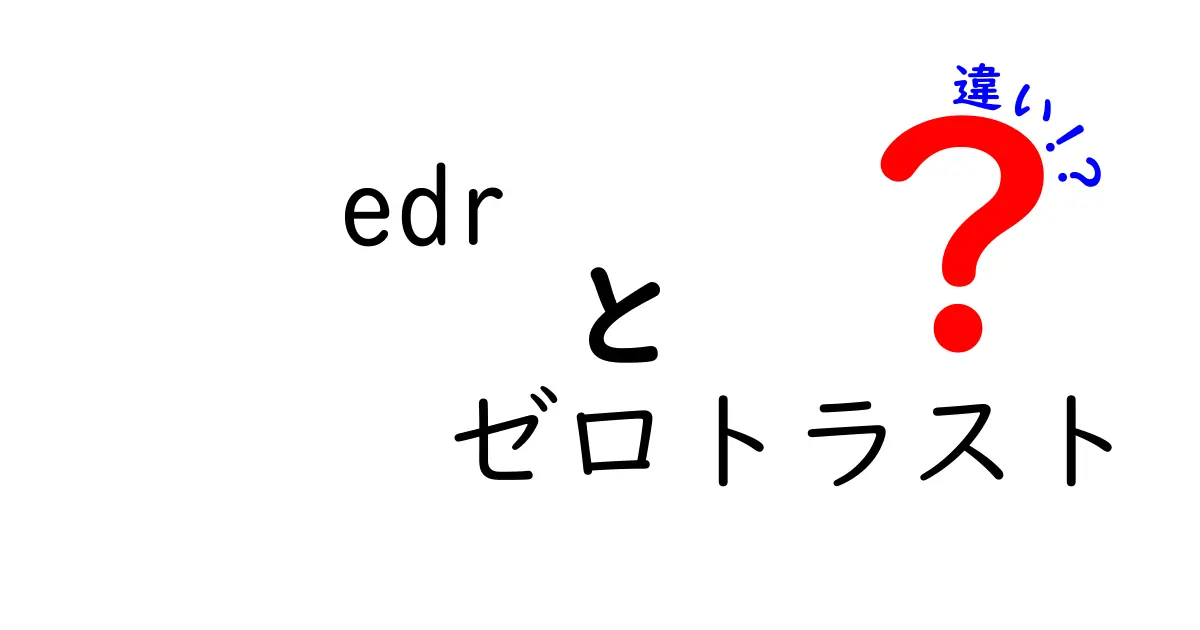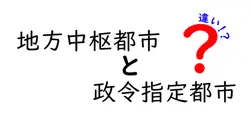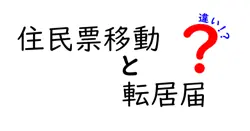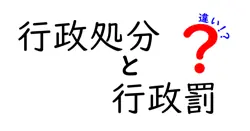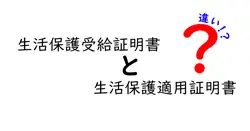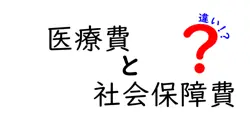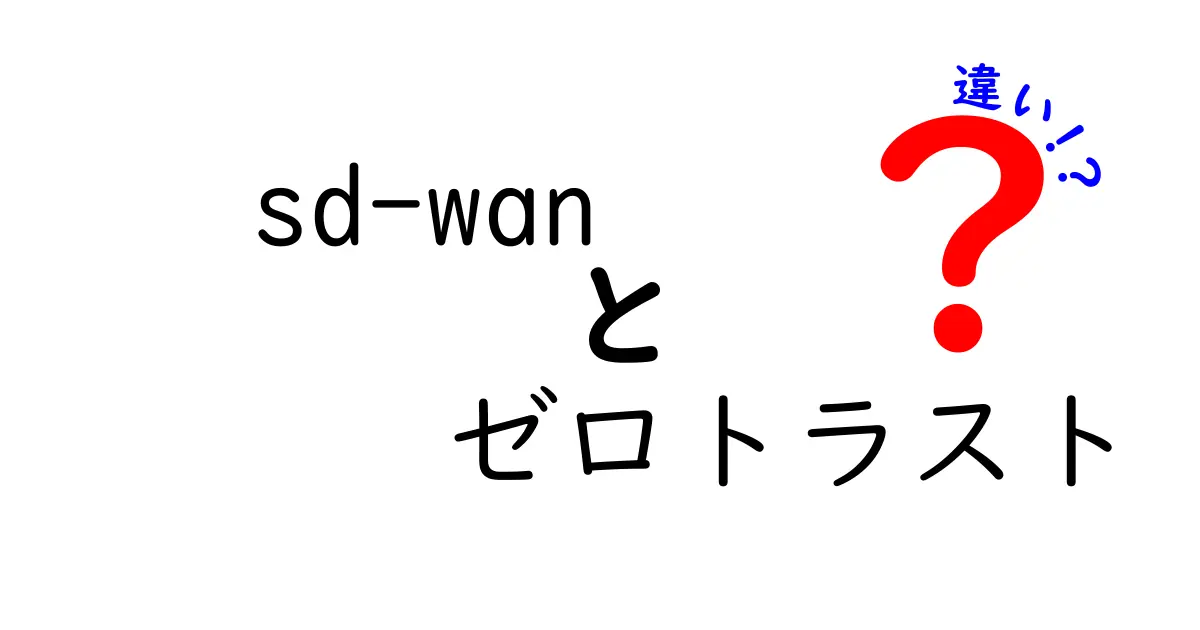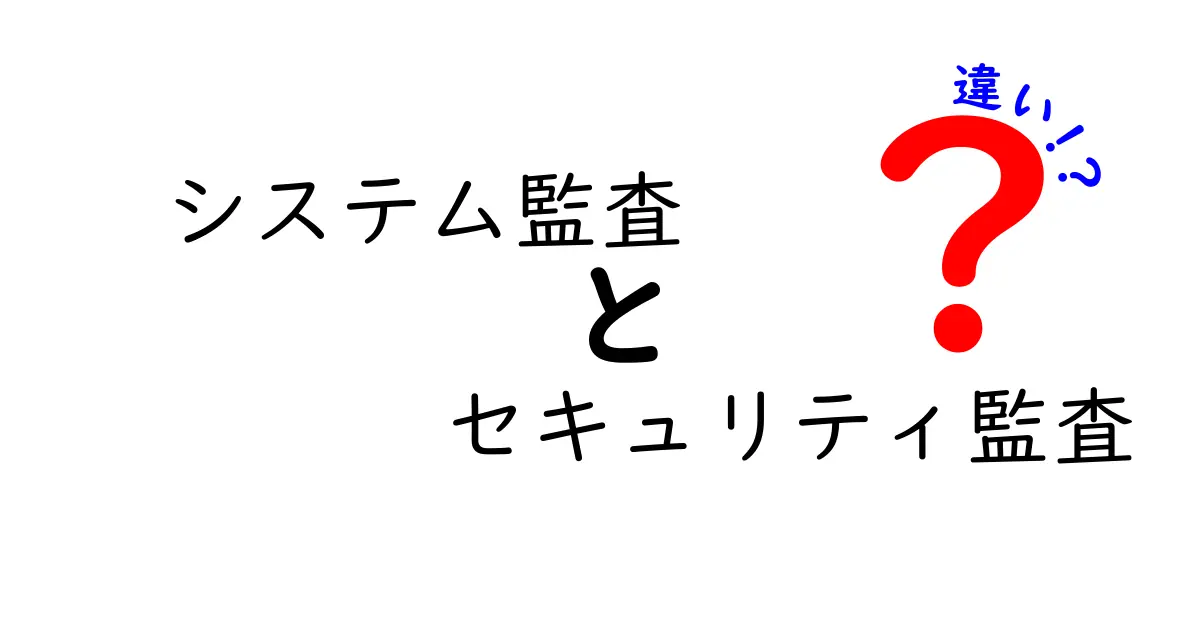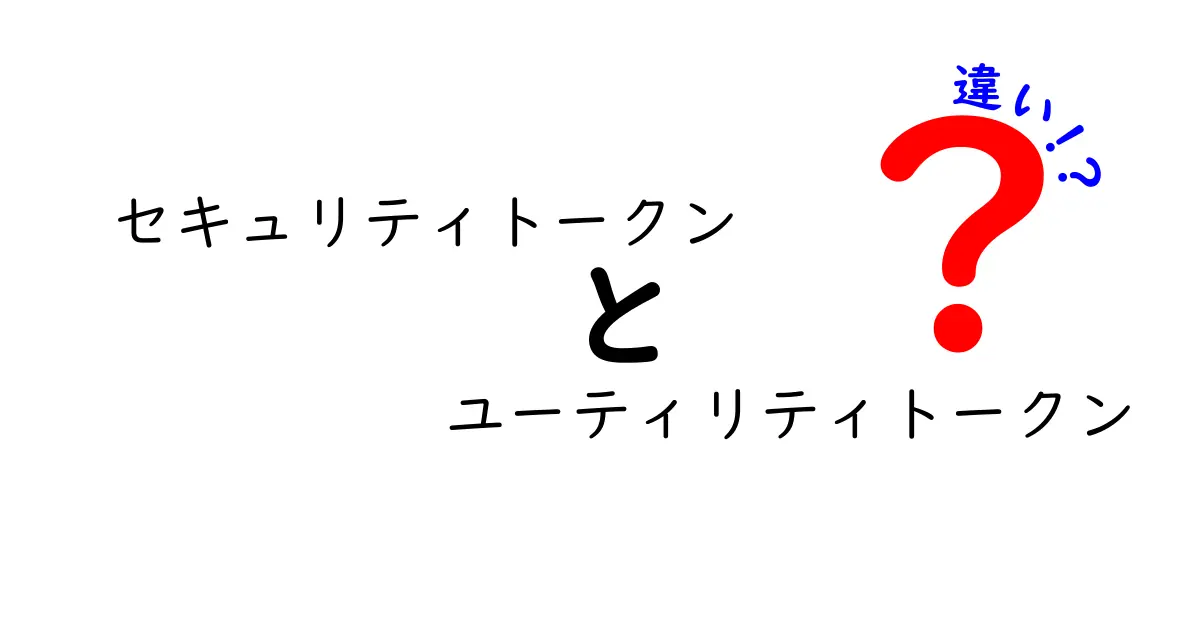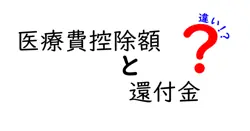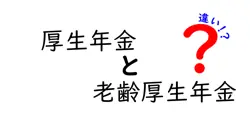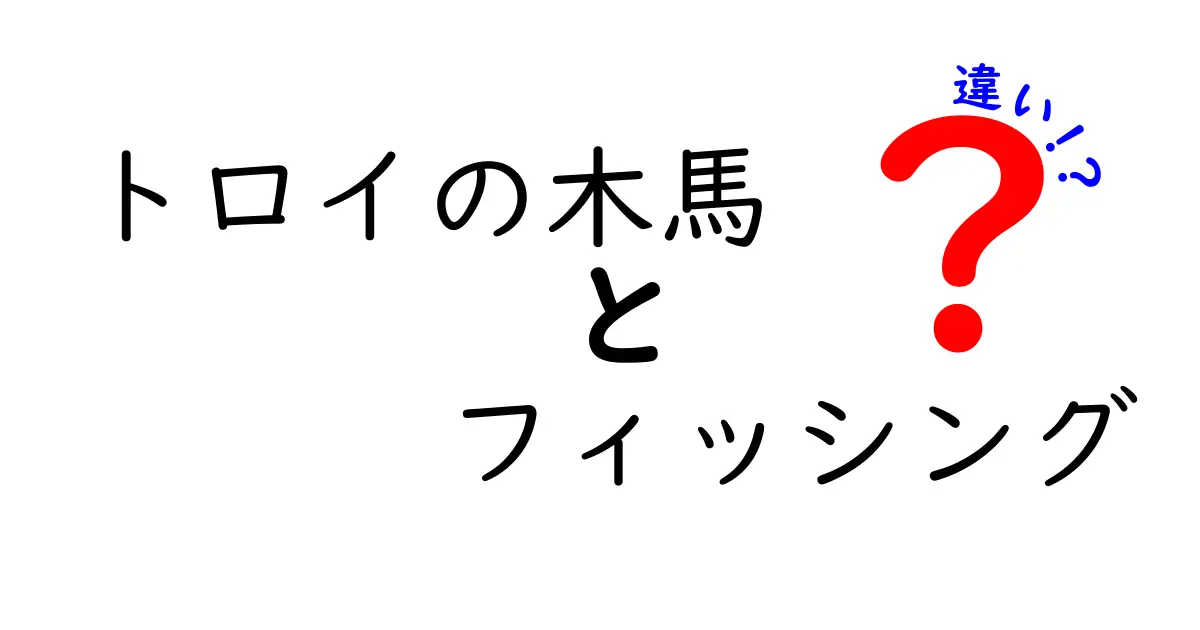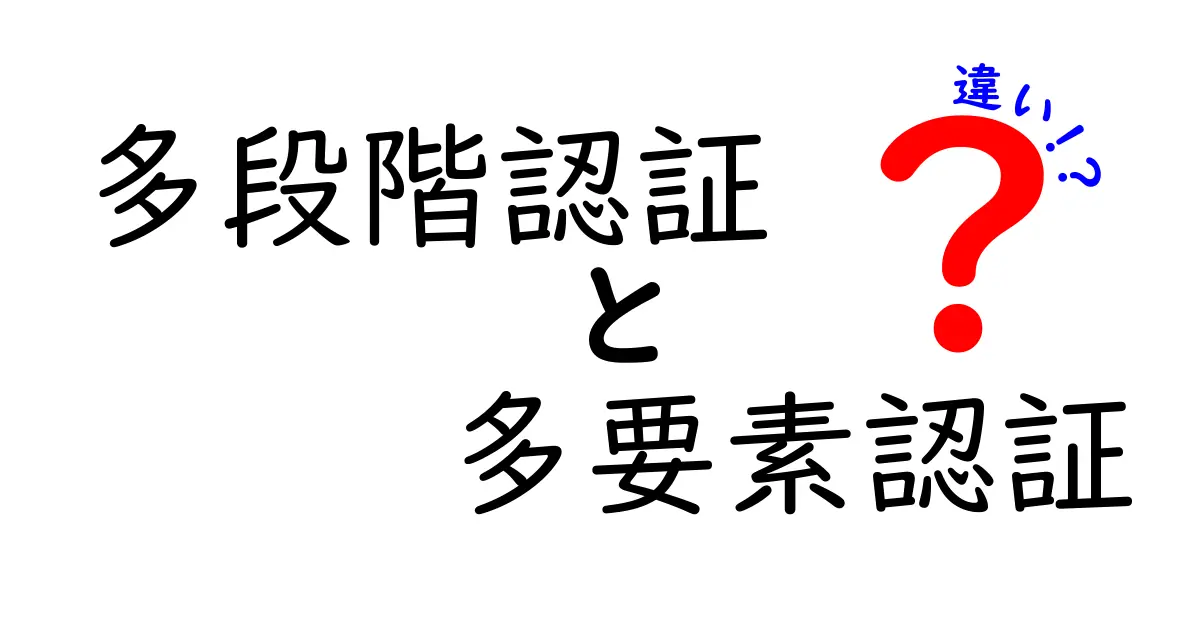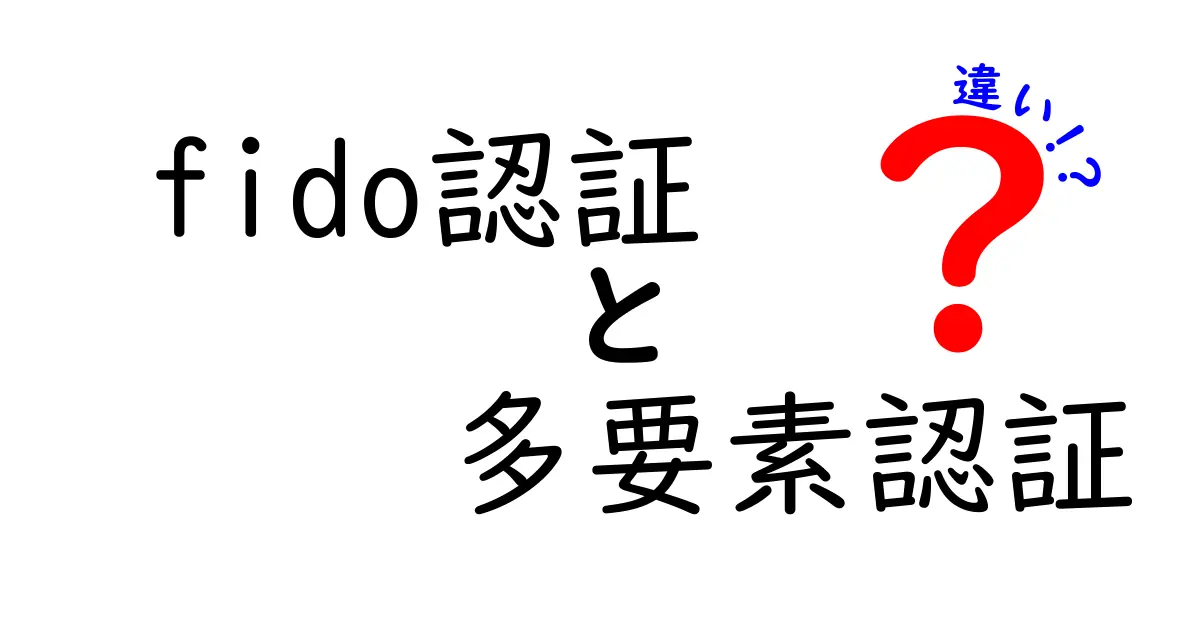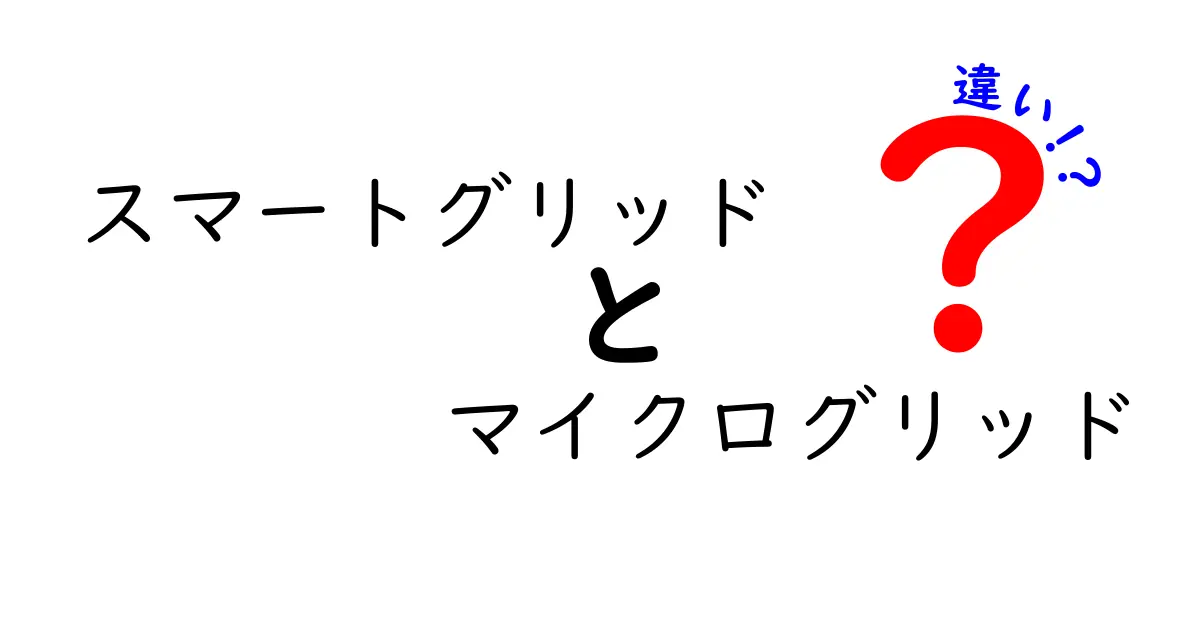
スマートグリッドとは何か?その特徴をわかりやすく説明します
スマートグリッドとは、最新の情報通信技術を使って電気の送配電を効率的に管理する新しい電力システムのことです。従来の電力網は一方的に電気が送られるだけでしたが、スマートグリッドは電気の需要と供給をリアルタイムで調整し、無駄なく電気を届けることができます。
例えば、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは天候によって電気の量が変わりますが、スマートグリッドならこうした変動も瞬時に対応してバランスをとることが可能です。
また、消費者も自分の電気の使い方をスマホなどで見ながら節電できるため、経済的で環境にも優しい仕組みとなっています。
まとめると、スマートグリッドは情報技術と電力網の融合で、効率的で持続可能な電力提供を目指す仕組みなのです。
マイクログリッドの基本とは?スマートグリッドとの違いを理解しよう
一方、マイクログリッドとは、限られた地域や施設内で独立して電力を供給・管理できる小規模な電力網のことを指します。
通常の電力網は大きなエリアをカバーしますが、マイクログリッドは工場、学校、住宅地などの限定された範囲内で自律的に電気の供給・制御を行います。
特徴としては、通常の電力網から切り離しても電力供給が可能な「アイランド運転」ができることです。つまり、災害などで大きな電力網が使えなくても、マイクログリッド内では電気が使い続けられます。
また、太陽光や蓄電池を組み合わせていることが多く、地域のエネルギー自給や環境負荷の軽減に役立ちます。スマートグリッドは広い地域全体の効率化を目指すのに対し、マイクログリッドは局所的に電力の安定供給と独立運用を実現する点が大きな違いです。
スマートグリッドとマイクログリッドの違いを表で比較!それぞれの特徴を整理
両者の違いをわかりやすくまとめるために、以下の表をご覧ください。
| 項目 | スマートグリッド | マイクログリッド |
|---|---|---|
| 規模 | 広範囲(地域・都市単位) | 小規模(限定された地域や施設) |
| 運営形態 | 集中と分散のハイブリッド | 自律的な独立運転が可能 |
| 目的 | 電力の効率化と最適化 | 安定供給とエネルギーの自立 |
| 特徴 | 情報通信技術によるリアルタイム制御 再生可能エネルギーの活用 | 災害時も独立して稼働可能 地産地消のエネルギー利用 |
| 項目 | EDR | ゼロトラスト |
|---|---|---|
| 目的 | 端末内の異常検知と対応 | アクセスや通信の厳格な検証・制御 |
| 主な機能 | マルウェア検知、行動監視、自動対応 | アイデンティティ認証、多要素認証、アクセス制御 |
| 導入対象 | PCやスマホ、タブレット等の端末 | ネットワーク全体、クラウド、ユーザーアクセス |
| セキュリティアプローチ | 攻撃の検知と対応(リアクティブ) | 信頼性ゼロからの厳格認証(プロアクティブ) |
なぜ両方を組み合わせるのが効果的か?
EDRとゼロトラストは補完関係にあります。
ゼロトラストの厳しいアクセス制御で不正侵入のリスクを下げつつ、もし侵入があってもEDRが端末内の異変を見つけて被害拡大を防ぎます。
例えば、ゼロトラストで多要素認証を行い強固にユーザーの本人確認をしても、攻撃者がそれを突破した場合でもEDRが端末上の怪しい動きを早期に発見します。
これにより組織全体のセキュリティが強化され、被害リスクを減らせます。単独で使うよりも、セットでの導入がおすすめです。
まとめ
EDRはエンドポイントの攻撃検知と対応に特化したツールで、ゼロトラストはアクセスを厳しく検証し信頼性をゼロから築く考え方です。
それぞれ得意分野が異なり、お互いに補い合う関係にあるため、両方を取り入れることでより安全なセキュリティ環境を実現できます。
現代のサイバー攻撃は高度化しているので、EDRとゼロトラストの違いを理解し、適切に活用することが重要です。
この記事で基本の違いがわかったら、ぜひ担当者や専門家と相談して最適なセキュリティ対策を検討してみてください。
EDRと聞くと「端末の見張り役」というイメージがありますが、実はEDRは単なる守りではありません。攻撃の痕跡を細かく分析して、今後の防御を強化する“探偵”のような役割も持っています。だから攻撃があった後の対応も早く、被害拡大を防ぎやすいんです。ゼロトラストは入る前の門番、EDRは入ってからの警察、そんなイメージで覚えるとわかりやすいですよね。今のセキュリティはこの両方が必要不可欠なんです。
前の記事: « SDGsとカーボンニュートラルの違いとは?わかりやすく解説!
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
SDGsとカーボンニュートラルの違いとは?わかりやすく解説!
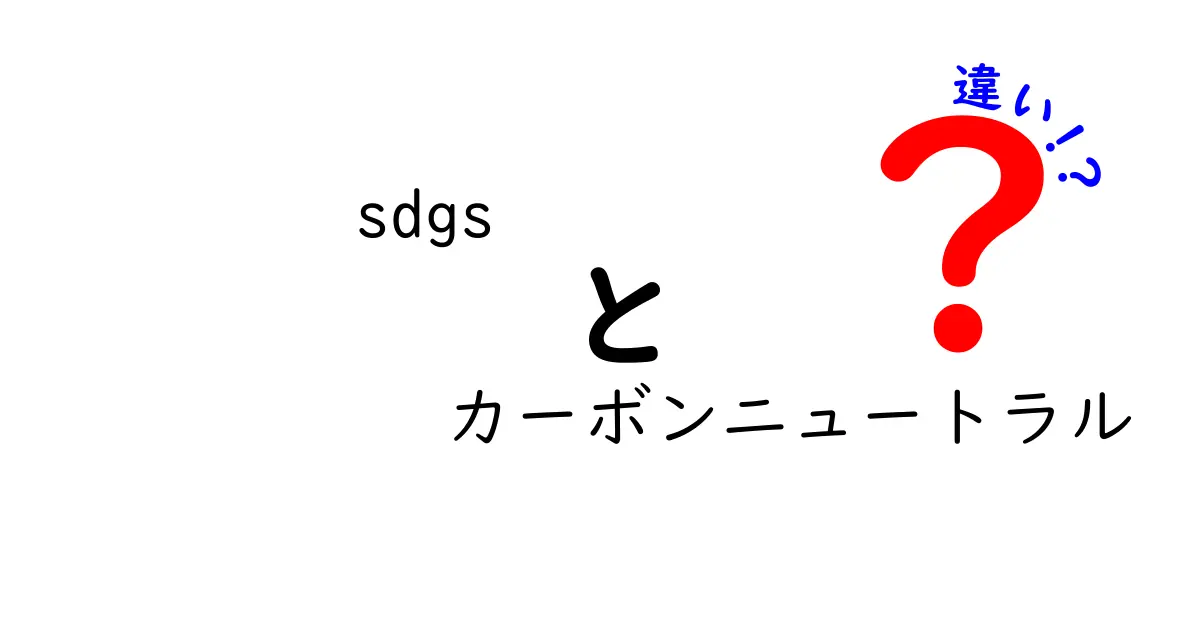
SDGsとは何か?
最近よく耳にする「SDGs(エスディージーズ)」ですが、これは「持続可能な開発目標」という意味です。持続可能とは、環境や社会、経済が将来にわたって続いていくことを指します。SDGsは、国連が2015年に決めた世界中が目指すべき17の目標で、貧困をなくしたり、教育を広げたり、環境を守ったりすることが含まれます。
SDGsは幅広い分野をカバーしていて、例えば「誰もが学校に行けるようにする」「安全な水をみんなに届ける」「ジェンダーの平等を実現する」など社会問題の解決を目指しています。
つまり、SDGsは「世界がみんなで協力して、より良い未来にするための大きな計画」と覚えておくとわかりやすいです。
カーボンニュートラルとは何か?
一方、カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出を実質ゼロにすることを意味します。私たちが車を走らせたり工場が動いたりすると、CO2(二酸化炭素)が空気中に排出されます。これは地球温暖化の主な原因の一つです。
カーボンニュートラルを目指すためには、CO2の排出を減らすだけでなく、植林や技術でCO2を取り除くことも含まれます。電気自動車や再生可能エネルギー(太陽光や風力など)を使うことも一つの方法です。
つまり、カーボンニュートラルは「地球の温度をこれ以上上げないようにするためのCO2対策」と言えます。
SDGsとカーボンニュートラルの違い
ここまででわかった通り、SDGsは世界の幅広い課題を解決するための目標群で、
カーボンニュートラルはその中の環境問題、特に気候変動対策にフォーカスした具体的な取り組みです。
下記の表でその違いをまとめます。
つまり、SDGsは「みんなで目指す大きな目標のセット」で、カーボンニュートラルはそのなかの「環境問題を特に解決する目標の一つ」と考えるとイメージしやすいです。
これからの社会では、SDGsのほかにカーボンニュートラルを意識して生活や仕事をすることが大切ですね。
カーボンニュートラルという言葉、最近よく聞くけれど、実は環境問題だけでなく経済や社会にも大きな影響を与えるんです。例えば、再生可能エネルギーを使うと電気代が下がる可能性もありますし、環境に優しい技術が新しい仕事を生むことも。だからカーボンニュートラルは単なる環境対策以上に、未来の暮らしや経済の形を変える大きなチャレンジなんですよ。
みんなが少しずつ意識して生活することが、とても大事ですね!
次の記事: EDRとゼロトラストの違いとは?初心者にもわかりやすく徹底解説! »