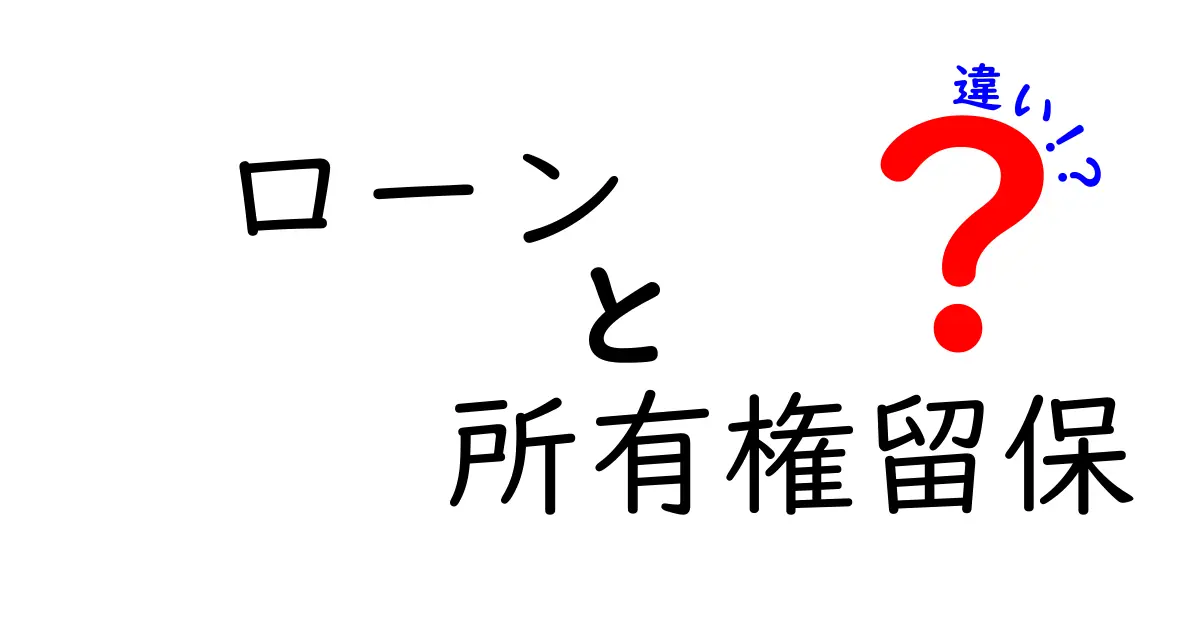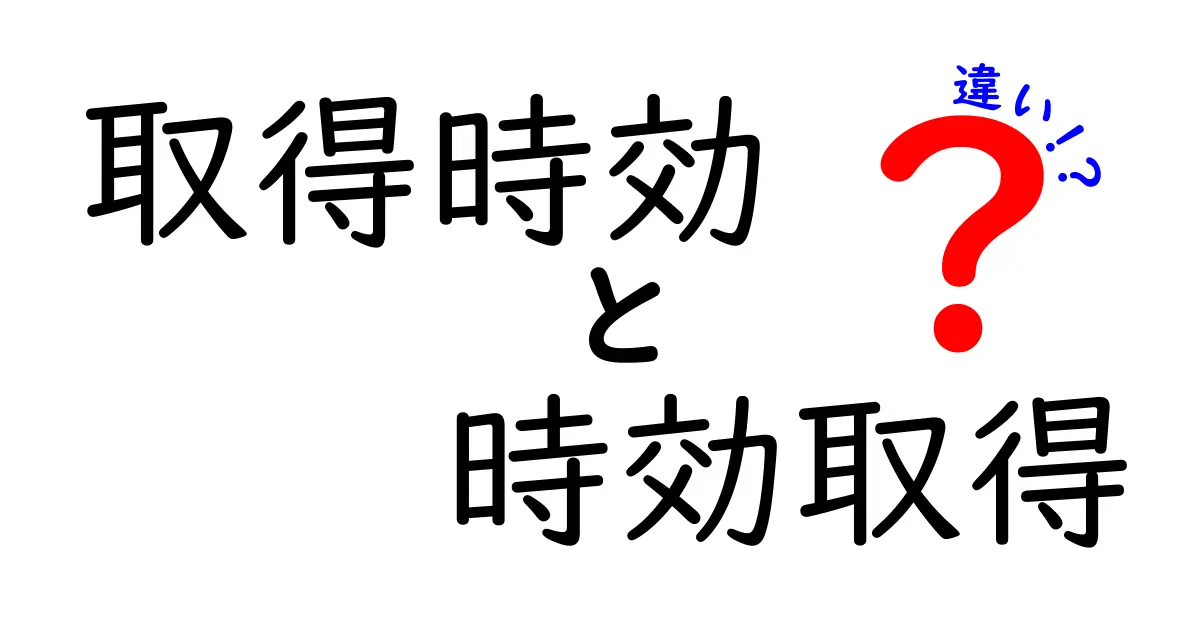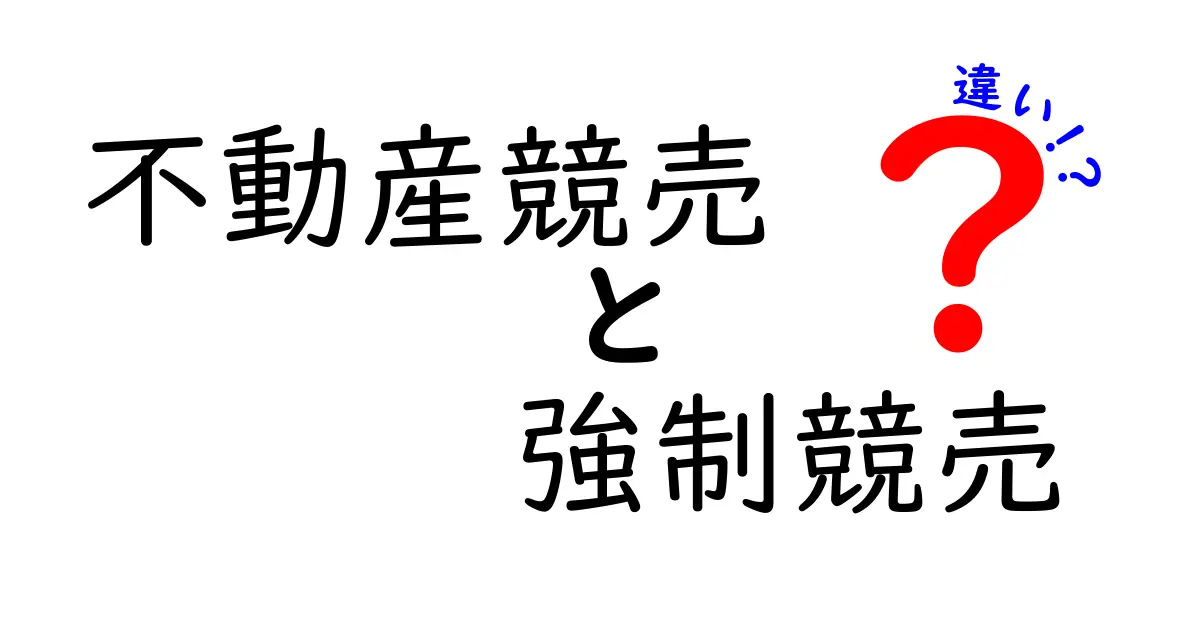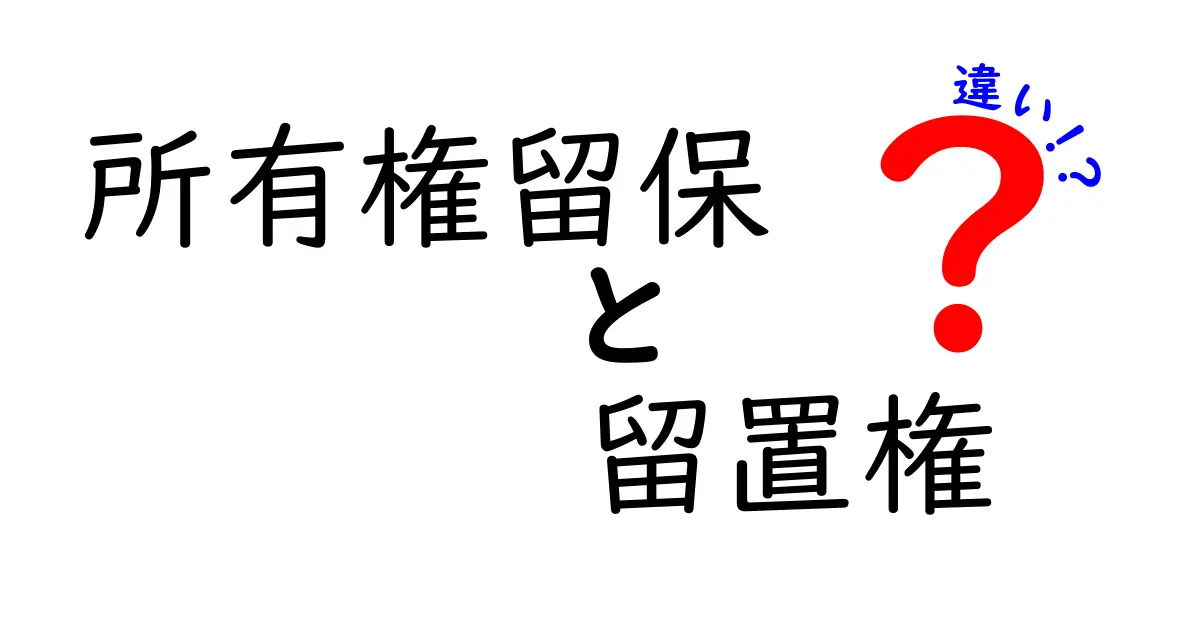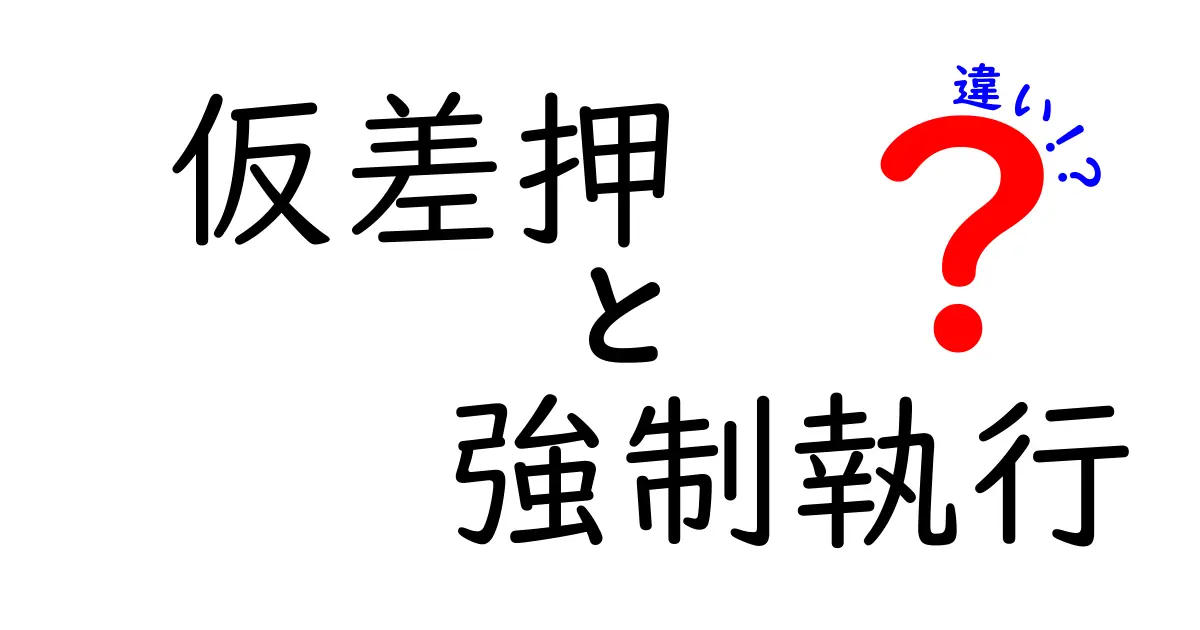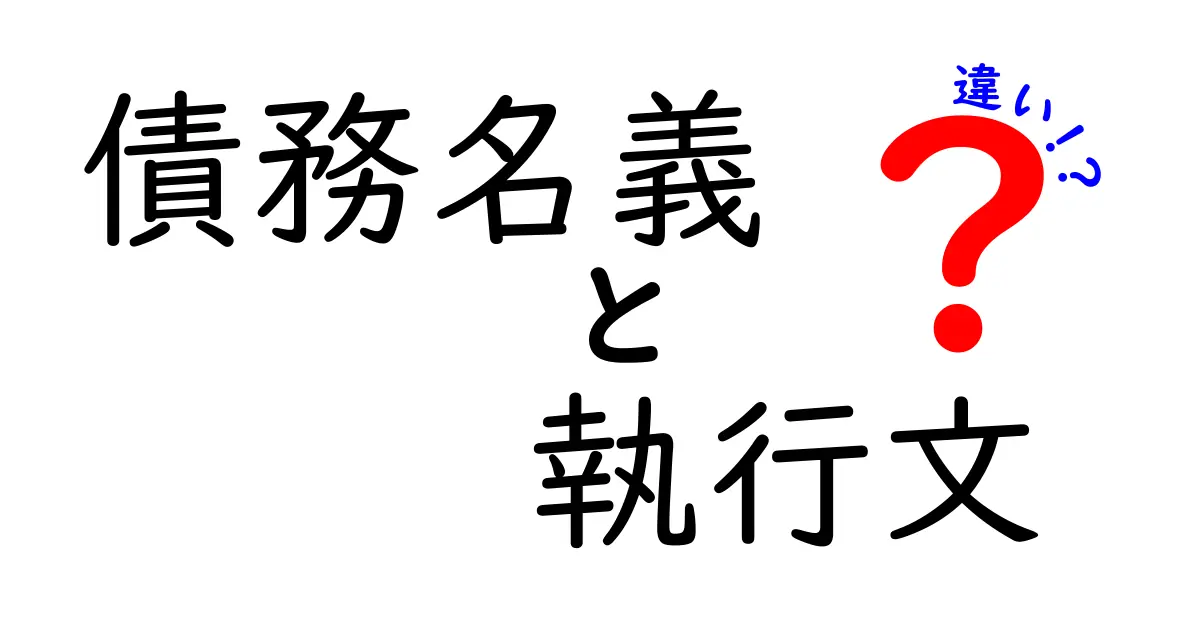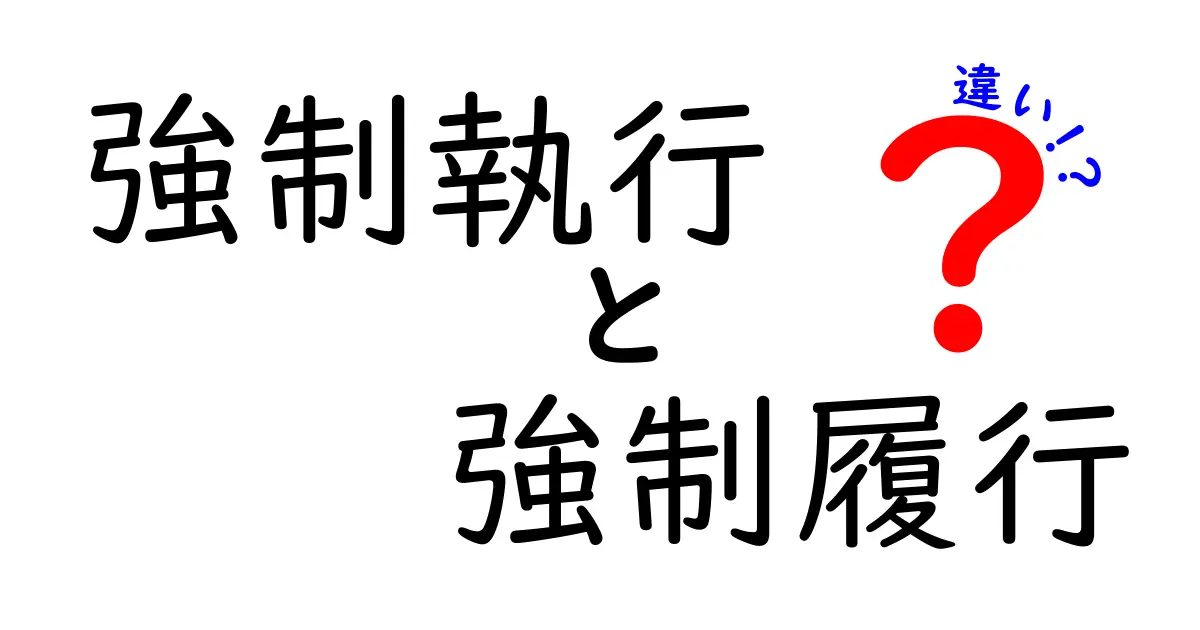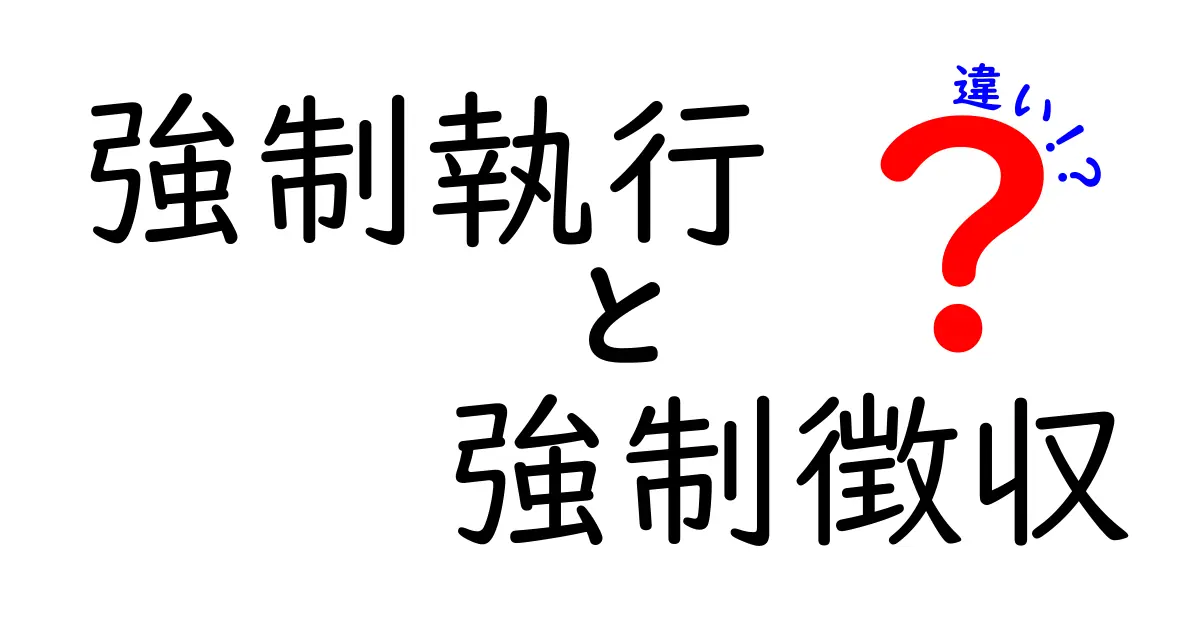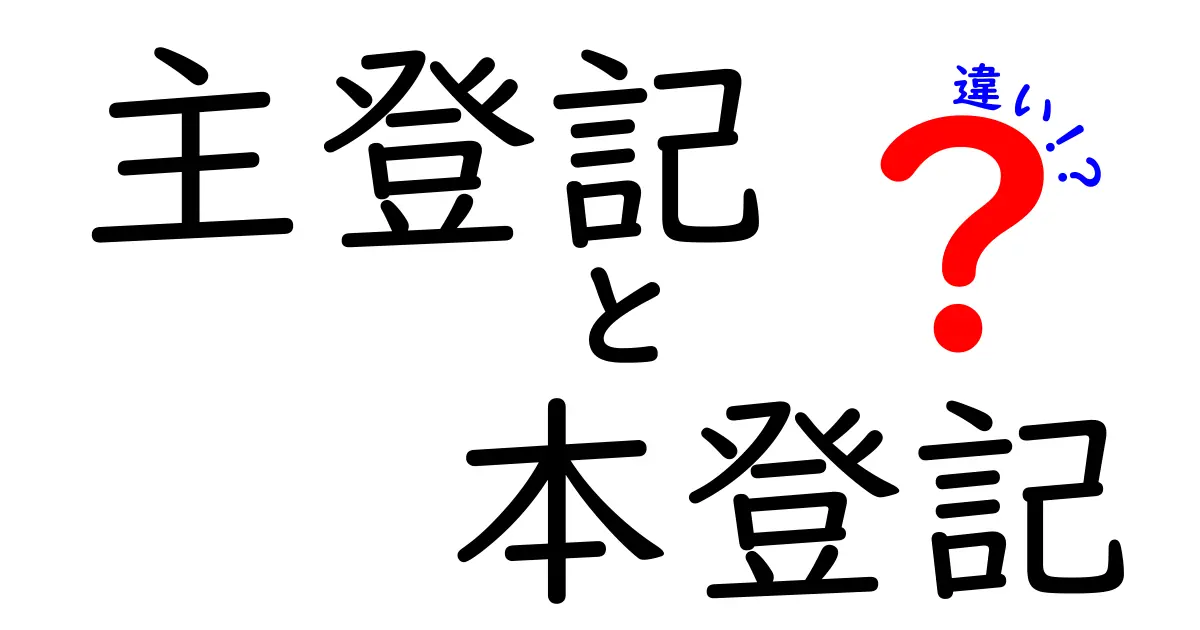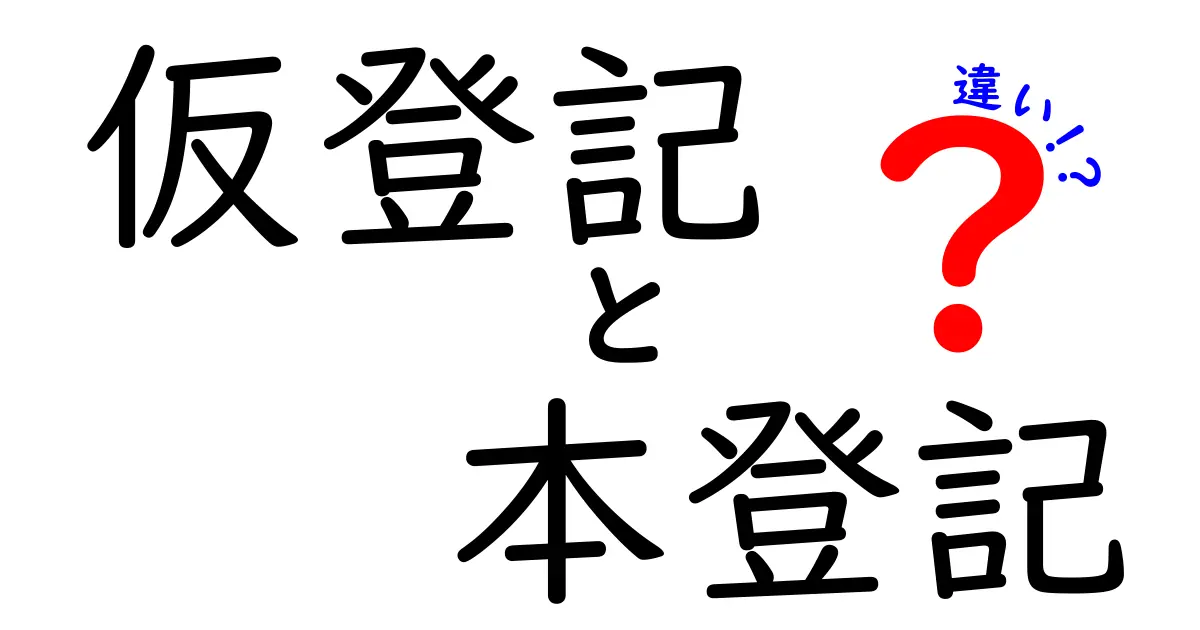この記事を書いた人
中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる)
ニックネーム:サトルン
年齢:28歳
性別:男性
職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門)
通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス
通勤時間:片道約45分(電車+徒歩)
居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション
出身地:神奈川県横浜市
身長:175cm
血液型:A型
誕生日:1997年5月12日
趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中)
性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ
1日(平日)のタイムスケジュール
6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック
7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理
8:00 出勤準備
8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット)
9:15 出社。午前は資料作成やメール返信
12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ
13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析
18:00 退社
19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物
19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム
21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成
23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる)
23:45 就寝準備
24:00 就寝
債務名義とは何か?
<まず、債務名義とは、裁判所や法律に基づいて債務者に対してお金を払う義務や何かをする義務があると認められた証明書のことです。たとえば、裁判で勝って相手にお金を払えと決まったとき、その判決が債務名義になります。
この債務名義があることで、債権者(お金をもらう人)は法的に「これは本物の借金だ」と認められた証拠を持ったことになります。つまり、相手に支払いや対応を強制する力がつきます。
債務名義はさまざまな手続きに使われ、単に「お金をもらう」ということだけでなく、契約の履行や物の返還など、多くの法的関係に関わります。
簡単に言えば、債務名義は「裁判や正式な手続きで認められた『約束』のようなもの」だと思ってください。
<執行文とは何か?
<次に、執行文について説明します。執行文は、債務名義の一部で、債務名義に書かれた内容を実際に強制執行できるようにするための証明書です。
たとえば、裁判で「お金を払え」と決まっただけでは、すぐには強制的に相手の財産を差し押さえたりできません。執行文がついていることで初めて、裁判所の力を借りて相手の給料や預金を差し押さえたり、財産を取り上げたりできます。
つまり、執行文は「債務名義に対して強制力を持たせる認め印」のようなものだと考えられます。
ただし、すべての債務名義に執行文が最初から付いているわけではなく、別途請求して裁判所から付与してもらうことが必要な場合もあります。
簡単に言うと、債務名義は『約束の証拠』、執行文はその『約束を無理やり実行する力』だと理解できます。
<債務名義と執行文の違いをわかりやすく整理
<ここで、債務名義と執行文の違いを表にまとめてみましょう。
<ding="5" cellspacing="0">< < < | 項目 | < 債務名義 | < 執行文 | <
< < | 意味 | < 法律で認められた債務の証明書 | < 債務名義に強制執行の効力を与える証明 | <
< < | 役割 | < 債権者の権利を証明する | < 債務不履行時に強制的に債務を実行させる | <
< < | 取得方法 | < 裁判や公正証書などで取得 | < 裁判所に別途申請して付与 | <
< < | 有効範囲 | < 債権の存在証明 | < 差押えなど強制処分の根拠 | <
< <able><
これらの違いを理解することで、債権回収にはただ「債務がある」というだけでなく、「それを実際に強制的に取り立てる権利がある」という二段階の準備が必要だとわかります。どちらも法律の仕組みの中でとても大切な役割を持っています。
<まとめ
<債務名義と執行文は、一見似ているようですが役割と意味が違います。
債務名義は「法律で認められた債務があるという証拠」であり、執行文はその債務名義を使って強制的に取り立てるための権利を付与するものです。
この違いを知ることで、法律手続きや債権回収の仕組みがよく理解でき、もしもの時にどう動くべきかがわかります。
法律の世界は難しく感じますが、少しずつ知ることで怖くなくなります。ぜひ、今回の内容を理解し、頼りになる知識として活用してください。
ピックアップ解説執行文って、法律の世界の“最終兵器”みたいなものなんですよね。債務名義が『お金を払ってください』という公式な約束の証拠なら、執行文はその約束を守らない人に対して『もう強制的に取り立てますよ!』と裁判所が背中を押してくれるもの。だから、執行文がなければ、たとえ裁判に勝っても相手が払わなければお金は手に入らないかもしれないんです。実はこの“強制力”の違いが、債務名義と執行文の一番大きなポイントなんですね。中学生にもわかるように言うなら、執行文は『約束の守られなさに対抗するための強い盾』だと言えます。
金融の人気記事

671viws

664viws

576viws

532viws

500viws

494viws

475viws

440viws

430viws

420viws

416viws

410viws

407viws

396viws

389viws

387viws

385viws

369viws

341viws

339viws
新着記事
金融の関連記事
この記事を書いた人
中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる)
ニックネーム:サトルン
年齢:28歳
性別:男性
職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門)
通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス
通勤時間:片道約45分(電車+徒歩)
居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション
出身地:神奈川県横浜市
身長:175cm
血液型:A型
誕生日:1997年5月12日
趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中)
性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ
1日(平日)のタイムスケジュール
6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック
7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理
8:00 出勤準備
8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット)
9:15 出社。午前は資料作成やメール返信
12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ
13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析
18:00 退社
19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物
19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム
21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成
23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる)
23:45 就寝準備
24:00 就寝
強制執行とは何か?
強制執行とは、裁判所の判決や決定に基づいて、相手が自分の義務を果たさない場合に、強制的にその義務の履行を実現する法的手続きのことを言います。簡単に言えば、例えばお金を払わない人がいた場合に、裁判所の力を借りてその人の財産を差し押さえたり売却したりして、未払いの債権を回収することが強制執行です。
この制度は、個人間のトラブルが長引かないようにするために法律で定められており、公的な力を用います。そのため、本人の同意なしに実行されることが特徴です。
具体的な例:家賃を払わない借主の預金口座を差し押さえて家主が回収する。
強制履行とは何か?
一方、強制履行とは、契約や判決で決まった「ある行為を必ず行わせる」ために、相手に直接その行為を強制することです。例えば、建物の修理をする約束を守らないなら、裁判所の命令で修理をさせることがこれに当たります。
こちらは「金銭の支払い」以外にも「物の引き渡し」「建物の解体」「ある場所からの立ち退き」など具体的な行動をさせることが目的です。
例:契約で約束した商品の引き渡しを拒む相手に対して、裁判所が商品を渡すよう命じる。
強制執行と強制履行の違いを表で比較
| 項目 | 強制執行 | 強制履行 |
|---|
| 目的 | 未払い金の回収など、金銭や物の取り立て | 約束された行為を相手に直接させる |
| 対象 | 主に金銭や物の引き渡し | 行為そのもの(修理、作業、立ち退きなど) |
| 実施方法 | 財産の差押え、換価など第三者が関与 | 直接的に行為を命じる命令 |
| 手続き | 裁判所を通じた差押えなどの実施 | 裁判所の強制履行命令を抜きにした履行は難しい |
| 強制力 | 相手の財産に及ぶ | 相手の行動に直接及ぶ |
まとめ
強制執行も強制履行も、裁判所の力を借りて相手の義務を果たさせる制度ですが、その対象や方法に違いがあります。強制執行は主に金銭の回収や物の引渡しのために相手の財産を差し押さえて回収する方法であり、強制履行は約束された具体的な行為を裁判所の命令で実現させる方法です。
どちらも法律の世界でトラブルを解決するために大切な制度ですので、その違いをしっかり押さえておくと理解が深まります。
例えば「借金の返済を強制的に回収したいとき」は強制執行を使い、「壊れた家を修理させたいとき」は強制履行を利用するイメージです。
これらの制度は複雑なので、具体的に使う際は法律の専門家に相談するのも良いでしょう。
以上、強制執行と強制履行の違いについて分かりやすく解説しました。
ピックアップ解説「強制執行」という言葉を聞くと、少し怖いイメージを持つ人も多いかもしれません。実はこの制度は、債権者が借金の返済など義務を果たしてもらえない場合に、公的な仕組みを使って相手の財産からお金を取り立てる方法です。例えば、家賃を長期間払わない借主の銀行口座を裁判所の許可で差し押さえることなどが代表例です。よく知らないと暴力的に感じるかもですが、法律のルールに基づいて厳格に行われるので安心してくださいね。強制執行は、法律の力を使ったトラブル解決の重要な手段なのです。
金融の人気記事

671viws

664viws

576viws

532viws

500viws

494viws

475viws

440viws

430viws

420viws

416viws

410viws

407viws

396viws

389viws

387viws

385viws

369viws

341viws

339viws
新着記事
金融の関連記事
この記事を書いた人
中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる)
ニックネーム:サトルン
年齢:28歳
性別:男性
職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門)
通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス
通勤時間:片道約45分(電車+徒歩)
居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション
出身地:神奈川県横浜市
身長:175cm
血液型:A型
誕生日:1997年5月12日
趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中)
性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ
1日(平日)のタイムスケジュール
6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック
7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理
8:00 出勤準備
8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット)
9:15 出社。午前は資料作成やメール返信
12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ
13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析
18:00 退社
19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物
19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム
21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成
23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる)
23:45 就寝準備
24:00 就寝
強制執行と強制徴収の基本的な意味とは?
まずは強制執行と強制徴収が、それぞれ何を指しているのかを理解しましょう。
強制執行とは、裁判所の判決や決定に基づき、債権者が債務者の財産から借金などの支払いを強制的に取り立てる法的な手続きを指します。
一方、強制徴収とは、おもに国や地方自治体など公的機関が法律に基づいて、税金や罰金、公共料金などを強制的に集めることを意味します。
つまり、強制執行は個人や会社間の金銭問題の解決手段で、強制徴収は行政が税金などを集める手段です。
強制執行の詳しい仕組みと特徴
強制執行は主に裁判所が関わり、債権者が裁判で認められた債権を回収するための制度です。
裁判の判決が出た後、債権者は「強制執行申立て」を裁判所に出し、債務者の給与差し押さえや不動産の競売などを通じてお金を得ます。
ポイントとしては、
- 裁判所の判断が必要であること
- 債権者が個人または企業でも申し立てられること
- 債務者の財産を差し押さえる・売却する手続きが含まれること
などがあります。
強制執行は法律に従って行われ、債務者の権利も一定程度守られています。強制徴収の詳しい仕組みと特徴
一方強制徴収は、主に国や地方自治体が税金や公共料金を確実に回収するために制度化した方法です。
通常は納税者が自主的に税金を納めますが、滞納すると行政は督促などを経て、場合によっては給与の差押えや財産の差押え、さらには公売によって税金などを回収します。
特徴は、
- 行政機関が強制的に徴収すること
- 主に税金・国民健康保険料・固定資産税などが対象
- 法律に基づくため正当な手続きが必要
です。
強制徴収は公共の利益や行政サービスのために欠かせない制度です。強制執行と強制徴収の違いを表で比較
ding="5" cellspacing="0">| 項目 | 強制執行 | 強制徴収 |
|---|
| 目的 | 裁判に基づき、債務者から債権回収 | 税金や公共料金の回収 |
| 申立て・実施者 | 債権者(個人・企業)が裁判所へ申立て | 国や地方自治体など行政機関 |
| 対象 | 債務者の財産(給与・不動産など) | 納税者の税金や公共料金など |
| 法的根拠 | 民事執行法・裁判所の命令 | 租税特別措置法・地方税法など |
| 手続き | 裁判判決後、差押えや競売など | 督促後の差押えや公売など |
強制執行と強制徴収は、目的や主体、対象が違いますが、どちらも法的な手続きによって権利を守る重要な制度です。
ピックアップ解説税金の強制徴収って、実はただの『お金を取る行為』だけじゃないんです。行政は納税者が払わないと、まず督促状を送りますが、それでも無視すると給与差押えや預貯金の差押えに進むことも。特に意外なのは、これが公的サービスの財源を確保するための大事な仕組みってこと。だから強制徴収は、社会全体の安心・安全を支える、ちょっとカッコいい役割もあるんですよね。知っておくと、お金の話も少し見方が変わるかもしれません。
金融の人気記事

671viws

664viws

576viws

532viws

500viws

494viws

475viws

440viws

430viws

420viws

416viws

410viws

407viws

396viws

389viws

387viws

385viws

369viws

341viws

339viws
新着記事
金融の関連記事
この記事を書いた人
中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる)
ニックネーム:サトルン
年齢:28歳
性別:男性
職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門)
通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス
通勤時間:片道約45分(電車+徒歩)
居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション
出身地:神奈川県横浜市
身長:175cm
血液型:A型
誕生日:1997年5月12日
趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中)
性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ
1日(平日)のタイムスケジュール
6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック
7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理
8:00 出勤準備
8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット)
9:15 出社。午前は資料作成やメール返信
12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ
13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析
18:00 退社
19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物
19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム
21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成
23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる)
23:45 就寝準備
24:00 就寝
主登記と本登記とは何か?基本を押さえよう
不動産の登記にはさまざまな種類がありますが、その中でも「主登記」と「本登記」は重要な用語です。
主登記とは、不動産の所有権や抵当権など、直接権利内容に関わる登記を指します。つまり、その不動産にかかわる中心的な法的立場をはっきりさせるための登記です。
一方、本登記は主登記を完了させるための手続きとして行われる登記で、法律上の効力を生じるためには主登記とセットで行われます。
このように、主登記は不動産の権利情報そのものを示し、本登記はその内容を正式に確定させる役割を持っています。
初心者にとっては分かりにくい言葉ですが、不動産売買などをする際には非常に大切な概念となっています。
主登記と本登記の違いを表で比較!わかりやすく解説
では実際に、主登記と本登記の違いを比較してみましょう。以下の表が理解を助けます。
ding="5" cellspacing="0">| ポイント | 主登記 | 本登記 |
|---|
| 意味 | 不動産の権利関係を示す登記 | 主登記の効果を正式に確定させる登記 |
| 役割 | 所有権や抵当権などの権利内容を記録 | 主登記を完成させるための手続き |
| 実施時期 | 権利が発生した時点で行う | 主登記の申請後に行われることが多い |
| 法律上の効力 | これ単独では効力が不完全な場合もある | 効力を完全に発生させる |
このように、主登記と本登記はセットで考えることが必要です。ただし、日常的には「本登記」を単に指して「主登記も含めた不動産登記」の意味で使われることもあります。
それぞれの登記の性質を理解することで、トラブルを防ぎスムーズな契約が可能になります。
不動産取引で主登記と本登記を正しく理解する重要性
不動産を買ったり売ったりする際、登記は「誰がその不動産の持ち主か」をはっきりさせるための大切な手段です。
主登記が正しく行われていないと、所有者が不明確になったり、権利の移転が有効にならなかったりします。それに対して、本登記の手続きを完了させることで法律上の保証が得られ、第三者に対しても権利を主張できるようになります。
例えば、新築住宅を購入しても、主登記が完了していなければ、その家の所有権は正式にはあなたのものになりません。こうした段階での誤解や手続きミスは、後で法的なトラブルに発展することもあるのです。
だからこそ、登記の仕組みや主登記・本登記の違いを知り、専門家への相談も活用しながら正しく手続きを進めることが重要です。
ポイントを押さえれば、不動産取引はもっと安心して行えます。
ピックアップ解説不動産登記の世界では「本登記」という言葉はとても重要ですが、実は日常的に使われる言葉ではありません。実際には「主登記」とセットで扱われることが多く、単体での区別はあまり意識されないことも多いんです。
面白いのは、『本登記』は法律の手続きを正式に終わらせるための登記で、確かに重要ですが、私たち素人にはあまり目に見えない舞台裏の作業のようなものとも言えます。
このあたりを知るだけで、不動産屋さんとの会話が少しスムーズになるかもしれませんね。
金融の人気記事

671viws

664viws

576viws

532viws

500viws

494viws

475viws

440viws

430viws

420viws

416viws

410viws

407viws

396viws

389viws

387viws

385viws

369viws

341viws

339viws
新着記事
金融の関連記事
この記事を書いた人
中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる)
ニックネーム:サトルン
年齢:28歳
性別:男性
職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門)
通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス
通勤時間:片道約45分(電車+徒歩)
居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション
出身地:神奈川県横浜市
身長:175cm
血液型:A型
誕生日:1997年5月12日
趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中)
性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ
1日(平日)のタイムスケジュール
6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック
7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理
8:00 出勤準備
8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット)
9:15 出社。午前は資料作成やメール返信
12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ
13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析
18:00 退社
19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物
19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム
21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成
23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる)
23:45 就寝準備
24:00 就寝
仮登記と本登記の違いとは?基礎知識を押さえよう
不動産を購入したり、権利を移したりするとき、仮登記と本登記という言葉を耳にします。これらは不動産登記の手続きに関わる重要なポイントで、法律面や実務に大きな影響を与えます。しかし、名前は似ていますが、意味や効果は大きく違うため、しっかり理解しておくことが大切です。
仮登記は簡単に言うと「本登記の前段階」のようなもので、将来の本登記を予約するための制度です。これに対し、本登記は不動産の所有権や抵当権などの権利を正式に法律上で認められるものです。では、それぞれの特徴や効果について、詳しく見ていきましょう。
仮登記の特徴と役割
まず、仮登記の主な役割は将来の本登記を確実にできるように予約することです。たとえば、売買契約をしたけれどまだ残金の支払いが終わっていない場合や、本登録に必要な書類が揃っていない場合に、仮登記を行います。
仮登記をすると、他の人が同じ不動産に対して先に本登記をすることを防げるため、購入者の権利を守る意味があります。また、司法書士などの専門家が手続きを行うことが多く、仮登記はその段階で記録が残るため安心感もあります。
仮登記はあくまでも「仮」なので、これだけでは不動産の権利が完全に認められるわけではありません。仮登記の期間は法律で定められており、一定期間以内に本登記に切り替えないと効力がなくなるため注意が必要です。
本登記の重要性と手続きの流れ
本登記は不動産の権利を正式に確定させる手続きで、これが完了すると法律上、権利者として認められます。たとえば、土地や建物の所有権を手に入れたときには必ず本登記が必要です。
本登記がされていないと、他の人にその不動産を奪われる可能性やトラブルが起きる恐れがあるため、とても重要です。登記簿には所有者の情報や抵当権などの担保設定も記録され、これが公的な証明となります。
本登記の手続きには法律書類の提出や登録免許税の支払いが必要で、確実に行うためには専門家のサポートが欠かせません。一般的には仮登記を経てから本登記へと手続きが進みます。
仮登記と本登記を一覧表で比較
able border="1">| ポイント | 仮登記 | 本登記 |
|---|
| 意味 | 将来の本登記の予約 | 不動産の権利を正式に確定 |
| 効力 | 仮的な効力、期限あり | 法律上の完全な効力 |
| 目的 | 権利の優先確保 | 権利の確定・公示 |
| 必要な場合 | 契約後すぐに本登記できないとき | 所有権や抵当権の移転時 |
| 期間 | 一定の期間のみ有効 | 期限なし(原則) |
このように、仮登記と本登記は双方で役割が異なり、それぞれ手続きの目的や効果も大きく違います。正確な理解があれば、不動産取引時のトラブルを防ぎ、安心して権利を守ることが可能になります。
まとめ:仮登記と本登記の違いを理解して賢く手続きしよう
不動産の登記は法律的にとても重要な制度です。仮登記は、まだ条件が整わないときに将来の本登記を確保する便利な方法であり、権利の優先順位を守る役割もあります。一方、本登記は不動産の権利を完全に確定させる手続きで、権利者として法律上認められるため必須です。
どちらも正しい流れで行わなければ無効になったり、トラブルになる可能性があります。特に不動産取引は高額なため、安心して手続きを完了させるためにも専門家への相談が有効です。
これらのポイントを理解して、仮登記と本登記の違いをしっかりつかみましょう。
ピックアップ解説仮登記の面白いポイントは、その“仮”という性質にあります。実は仮登記は『これから本登記をする予定ですよ』という予約のようなもの。でも、よく知られていないのは、仮登記がないと後から本登記できない場合や、他の人に先を越される危険もあるということです。つまり仮登記は不動産の権利を守るための大事な“保険”的存在なんです。
例えば、中学生が好きなゲームの大会予約を考えてみるとわかりやすいかもしれません。大会に参加するために名前を書いて予約席を確保しているけど、実際には参加料を払うなど準備ができていない状態。これが仮登記のイメージで、支払いが終わったり準備が整ったら本登記(正式な参加登録)になるのです。
金融の人気記事

671viws

664viws

576viws

532viws

500viws

494viws

475viws

440viws

430viws

420viws

416viws

410viws

407viws

396viws

389viws

387viws

385viws

369viws

341viws

339viws
新着記事
金融の関連記事