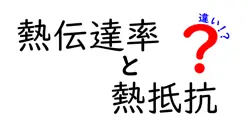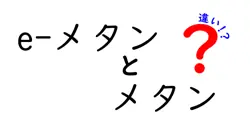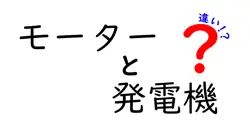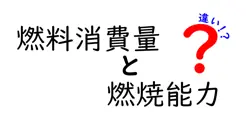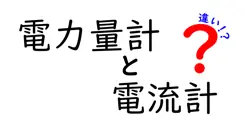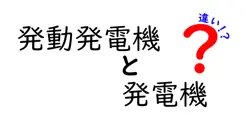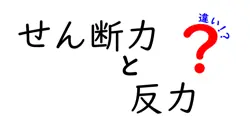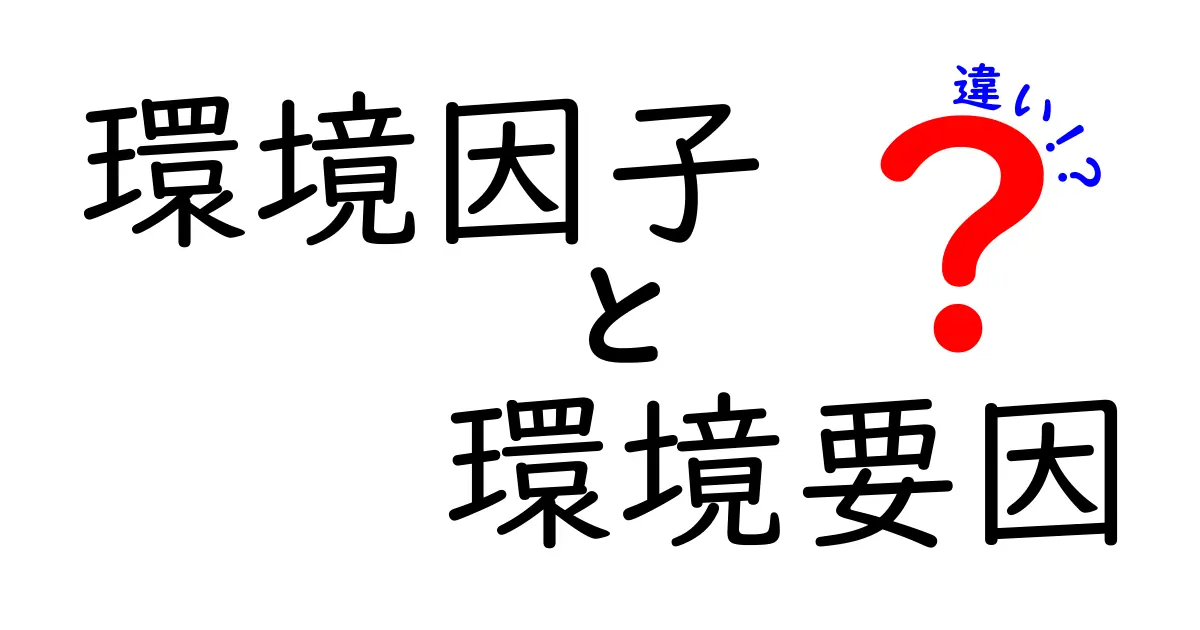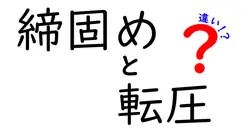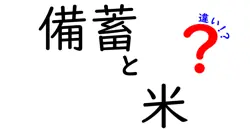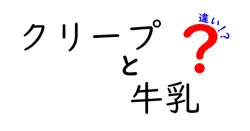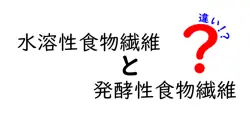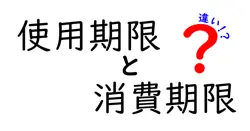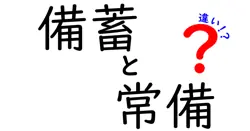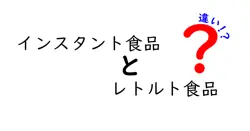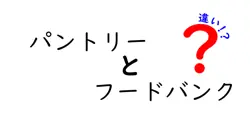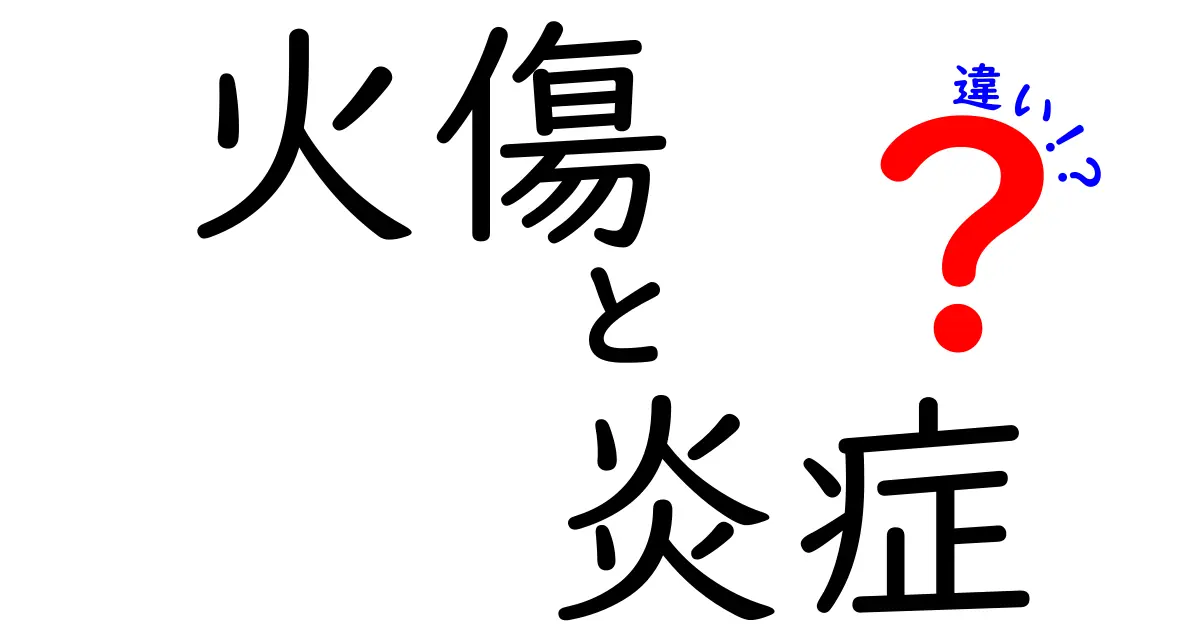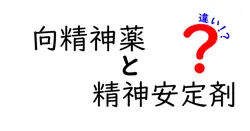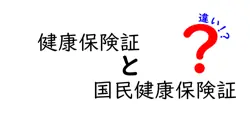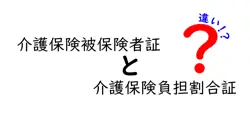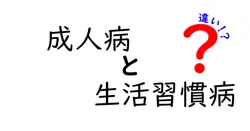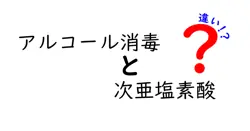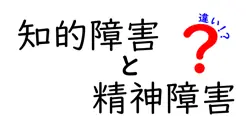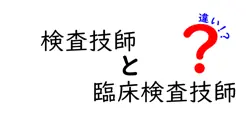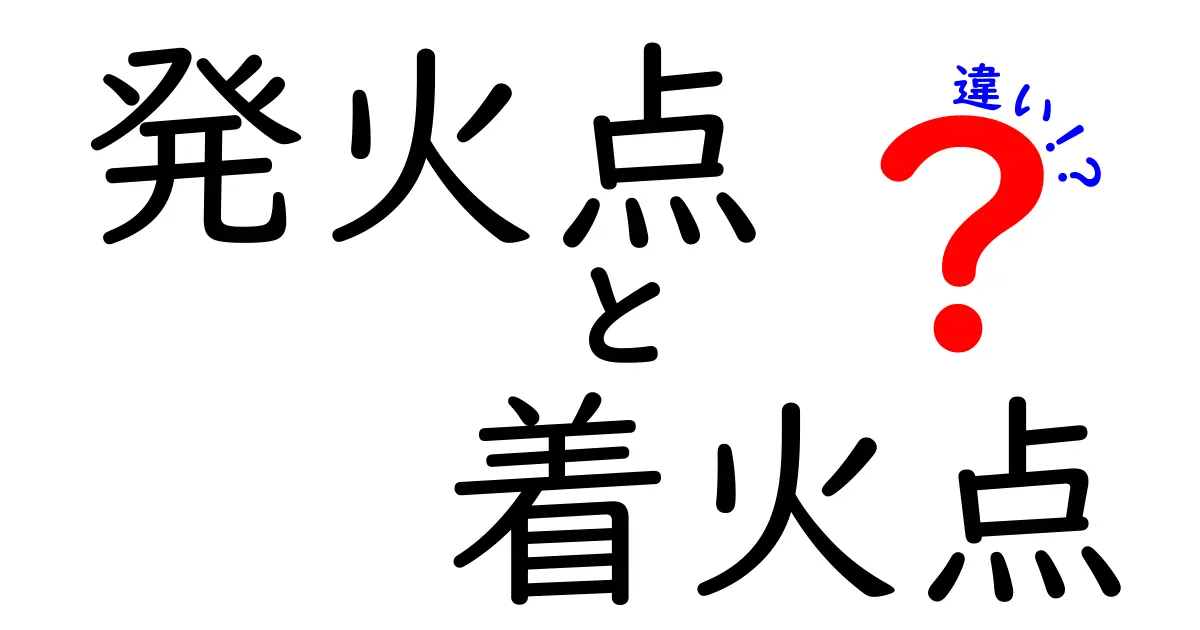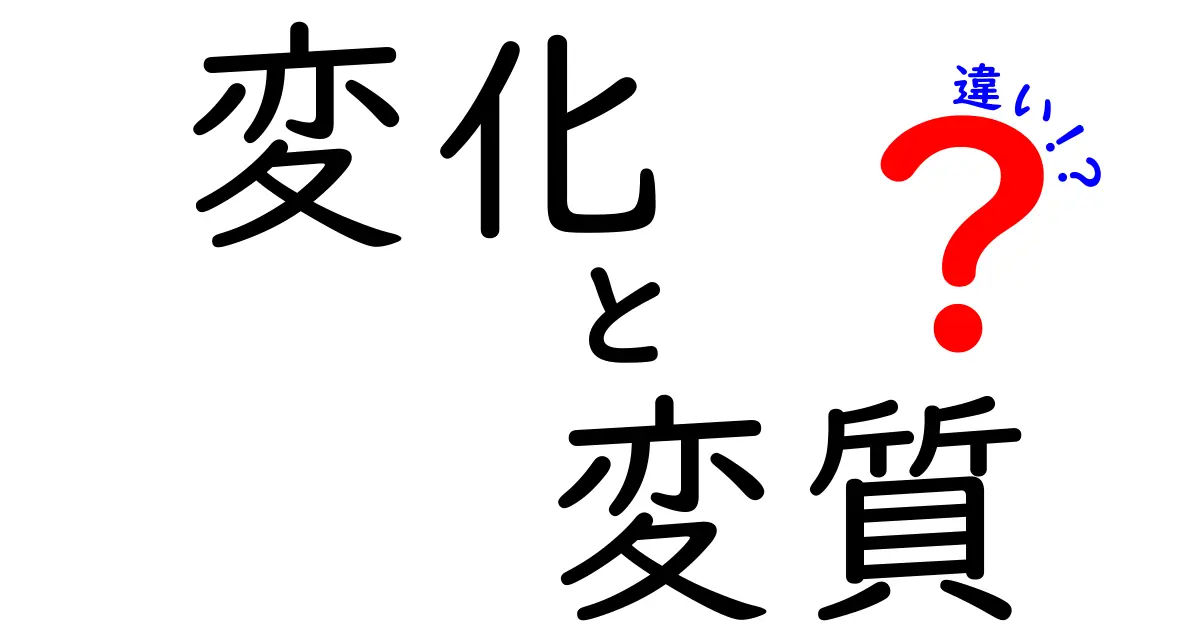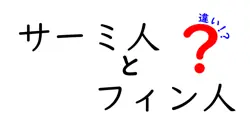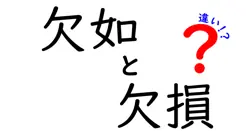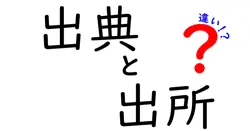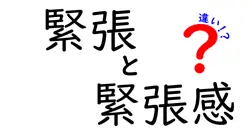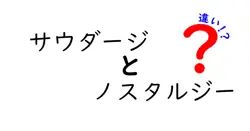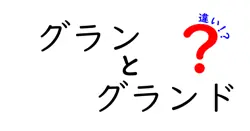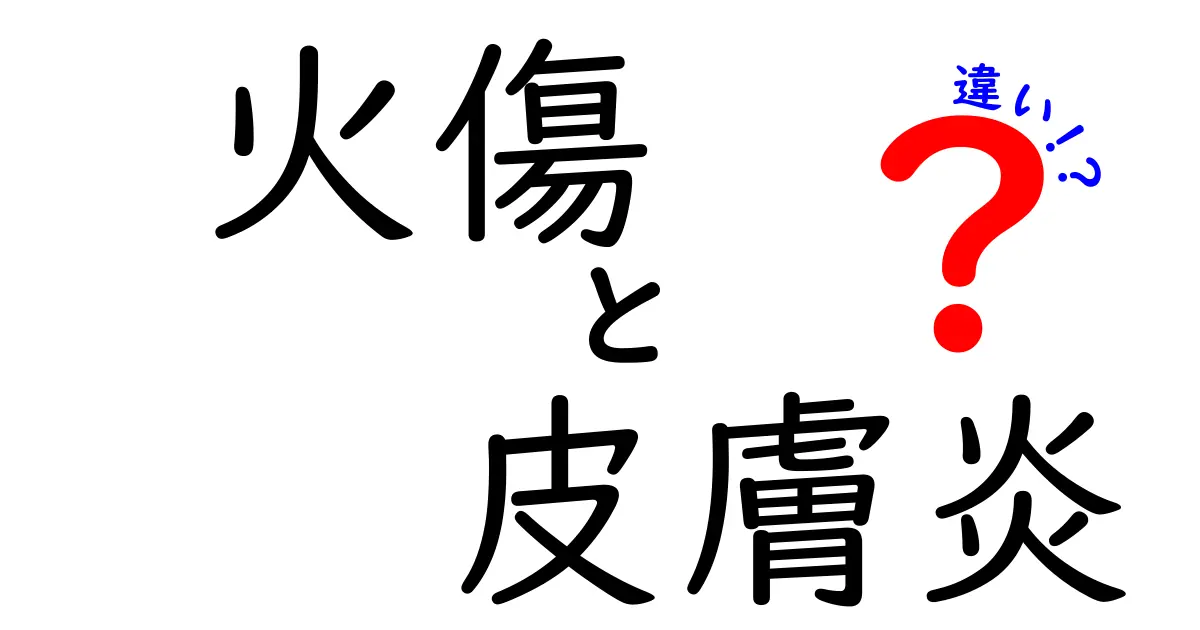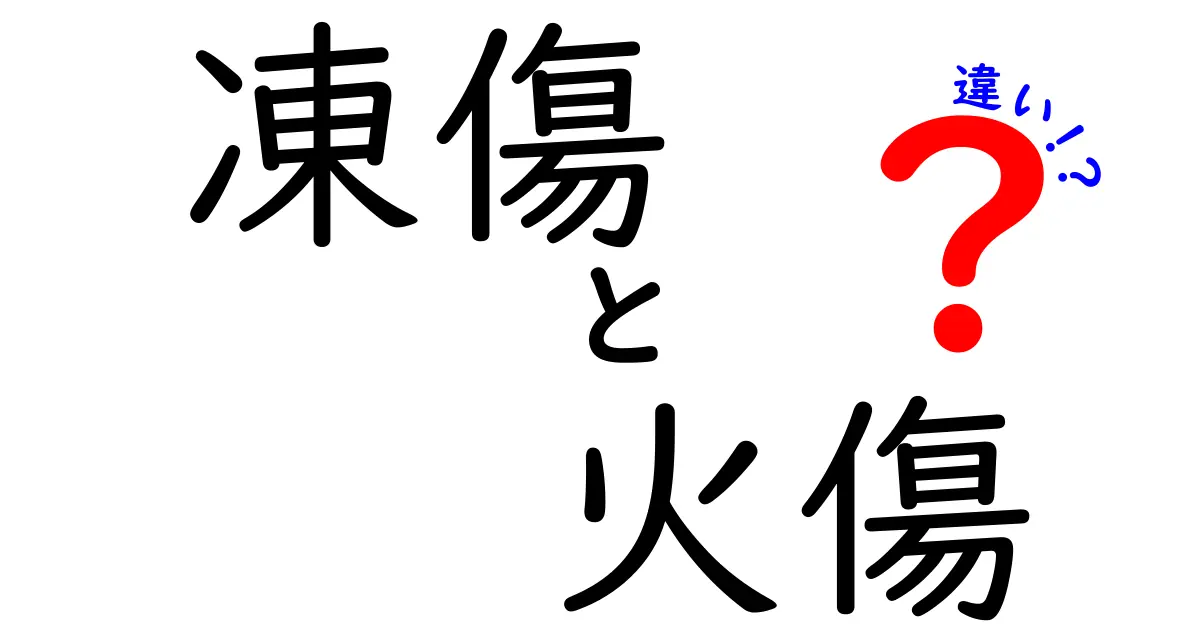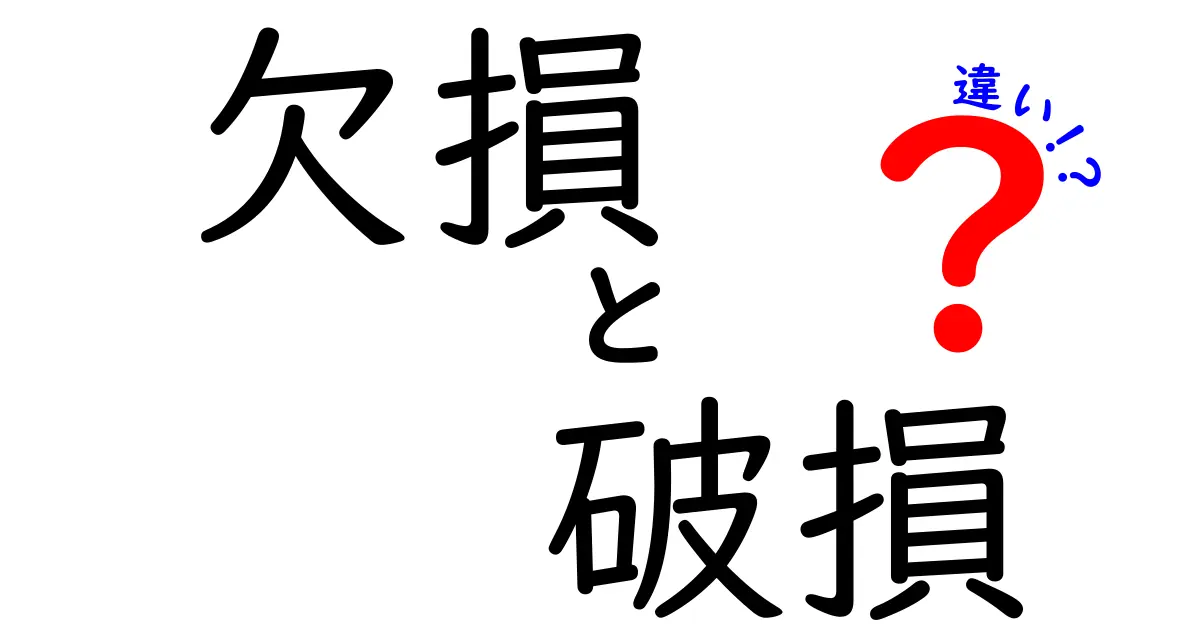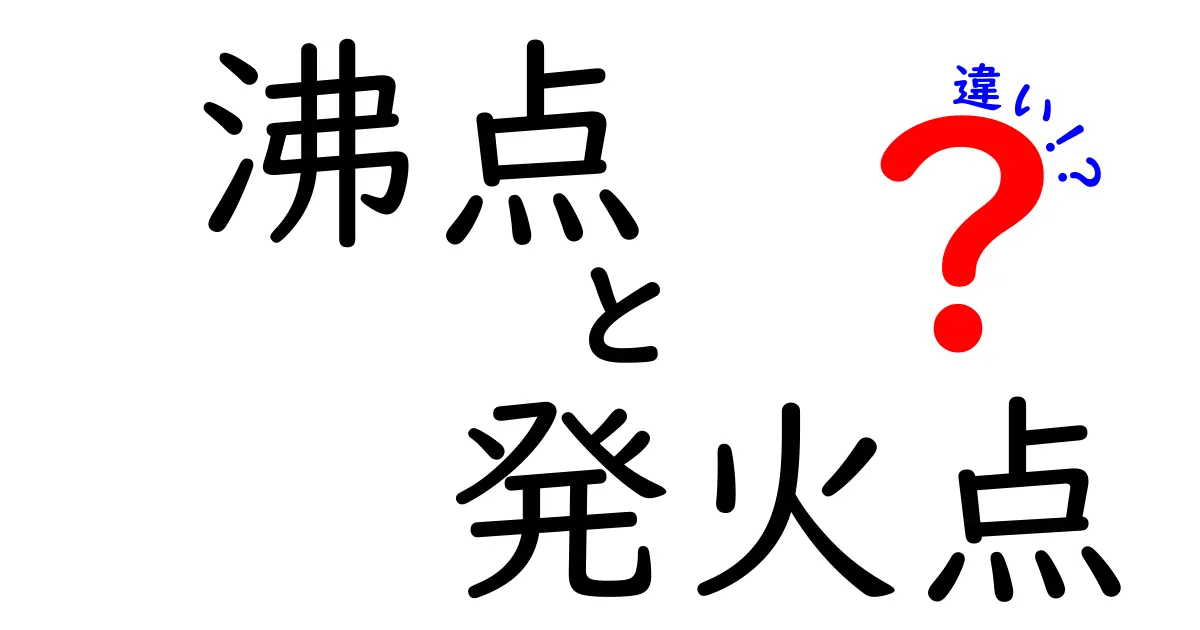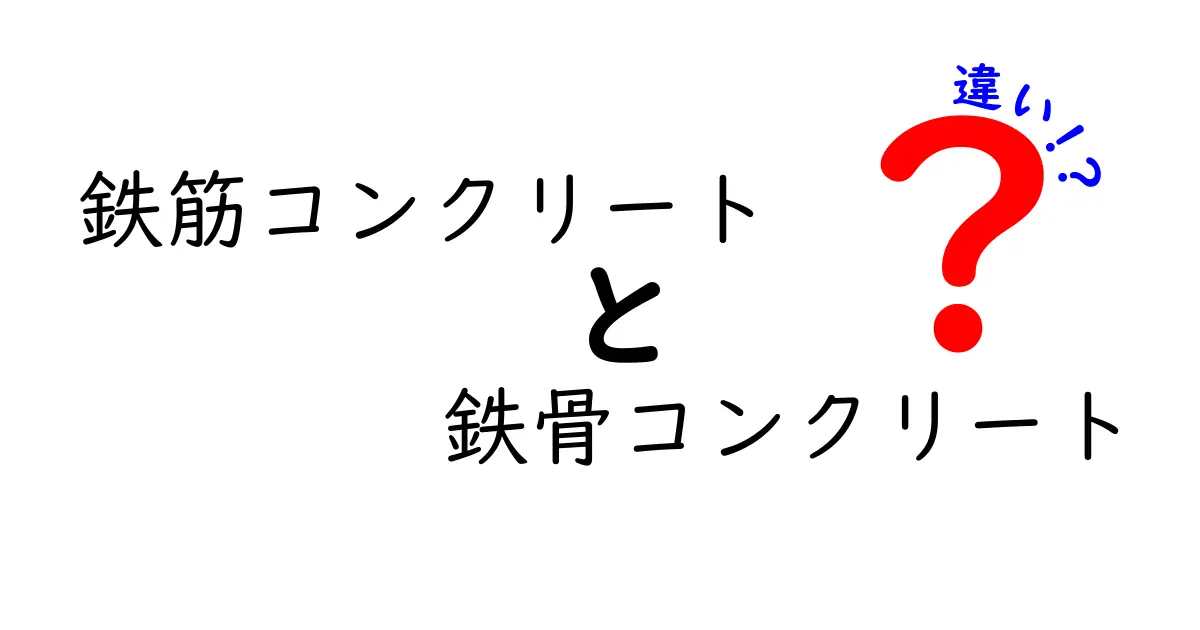
鉄筋コンクリートと鉄骨コンクリートとは?基礎から理解しよう
建築物の構造にはさまざまな種類がありますが、中でも鉄筋コンクリート(RC)と鉄骨コンクリート(SRC)はよく耳にする言葉です。
まずは、それぞれの基本を押さえておきましょう。
鉄筋コンクリートはコンクリートの中に鉄の棒(鉄筋)を入れて、
コンクリートの強度と鉄筋の引っ張り強度を合わせて建物を支える工法です。
一方、鉄骨コンクリートは鉄筋だけでなく鉄骨(太い鋼材)もコンクリートの中に入っている構造で、さらに強固な耐久力があります。
この二つは、どちらもコンクリートを使う点で似ていますが構造の考え方や性能に違いがあるのです。
これからそれぞれの特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。
鉄筋コンクリートの特徴とメリット・デメリット
鉄筋コンクリートは、住宅やビルなどでとても一般的に使われる構造です。
コンクリートは圧縮に強いですが、引っ張りには弱い性質を持っています。
鉄筋を使うことで、その弱点を補い、建物の強度を高める仕組みです。
【メリット】
- 耐火性が高く火災に強い
- 防音性や気密性に優れる
- メンテナンスが比較的楽
【デメリット】
- 重量が重いので地盤に負担がかかる
- 大きな空間を作るのは難しい
- 施工に時間がかかることもある
このように、耐久性と安全性が高い反面、重量の問題や施工の手間がデメリットです。
住まいなどで安定した強度を求めるときに選ばれることが多いですね。
鉄骨コンクリートの特徴とメリット・デメリット
鉄骨コンクリートは、鉄骨の骨組みに鉄筋も組み込み、その上からコンクリートを流し込む構造です。
このため、鉄筋コンクリートよりもさらに強い建物を作れます。
【メリット】
- 高い耐震性と耐久性を実現
- 大きな空間や複雑な造りが可能
- 長期間の使用に耐えられる
【デメリット】
- 鉄筋コンクリートよりもコストが高い
- 施工が複雑で時間がかかる
- 重量がかなり重くなることもある
鉄骨の強さとコンクリートの耐久性を合わせ持つため、ビルやマンションなど大規模建築でよく使われます。
費用や工期がかかりますが、安全性や耐久性を最優先したい場合に適しています。
鉄筋コンクリートと鉄骨コンクリートの違いを比較表でチェック!
| 鉄筋コンクリート(RC) | 鉄骨コンクリート(SRC) | |
|---|---|---|
| 構造の違い | 鉄筋をコンクリートに埋め込む 骨組みは主に鉄筋 | 鉄骨の骨組みに鉄筋を組み込み、 コンクリートを被覆 |
| 耐震性・強度 | 高いがSRCよりは劣る | 非常に高く、大規模建築に適する |
| コスト | 比較的安価 | 高価 |
| 施工期間 | 鉄骨コンクリートより短い | 複雑で時間がかかる |
| 重量 | 重い | 非常に重い |
| 用途 | 住宅や小中規模の建物 | 高層ビルや大型施設 |
| 項目 | 環境因子 | 環境要因 |
|---|---|---|
| 意味 | 生物や人体に影響を与える自然や物理的な要素 | 物事や人の状態に影響を与える自然・社会のあらゆる条件 |
| 主な対象 | 生物、健康、成長 | 人、社会、経済、自然環境 |
| 範囲 | 自然的なものが中心 | 自然的、社会的両方を含む |
| 使用される分野 | 生物学、医学、環境学 | 環境学、社会学、経済学 |
| 使用例 | 大気汚染は呼吸器疾患に関する環境因子の一つです。 | 生活習慣や労働環境は健康に影響する環境要因です。 |
環境因子と環境要因の正しい使い分け方
言葉の違いを理解したら、実際に文章や会話でどう使い分けるべきかも大切です。
環境因子は、生物や健康に直接関係する自然的・物理的な条件や刺激を表現したいときに使います。例えば、学校の周辺の空気汚染を指すときや、病気の原因となる自然要素を説明するときです。
反対に、環境要因は自然だけでなく、社会的背景や経済状況なども含んだ広範囲の外的条件を示すときに使います。たとえば、生活環境や職場環境の問題を話題にするときがこれにあたります。
身近な例を挙げると、
- 運動不足の原因を考える場合、運動しにくい住環境は「環境要因」
- 運動する屋外の気温や空気質は「環境因子」
と区別できます。
この使い分けができると、専門的な話はもちろん、日常的なコミュニケーションでもより正確に自分の考えを伝えられます。
「環境因子」という言葉は生物や健康に大きな影響を与えるものですが、その中でも特に目立つのは大気汚染や気温変化です。例えば、寒い冬の気温上昇は風邪の流行と関係があるかもしれません。環境因子は自然の影響が直接的なので、時には人間の体にもすぐ反応が出ることが多いんです。だから、医学や生物学の研究ではこの言葉がよく使われ、私たちの健康管理に役立っていますね。
前の記事: « 発酵と腐食の違いとは?見分け方と生活への影響をわかりやすく解説!
自然の人気記事
新着記事
自然の関連記事
発酵と腐食の違いとは?見分け方と生活への影響をわかりやすく解説!
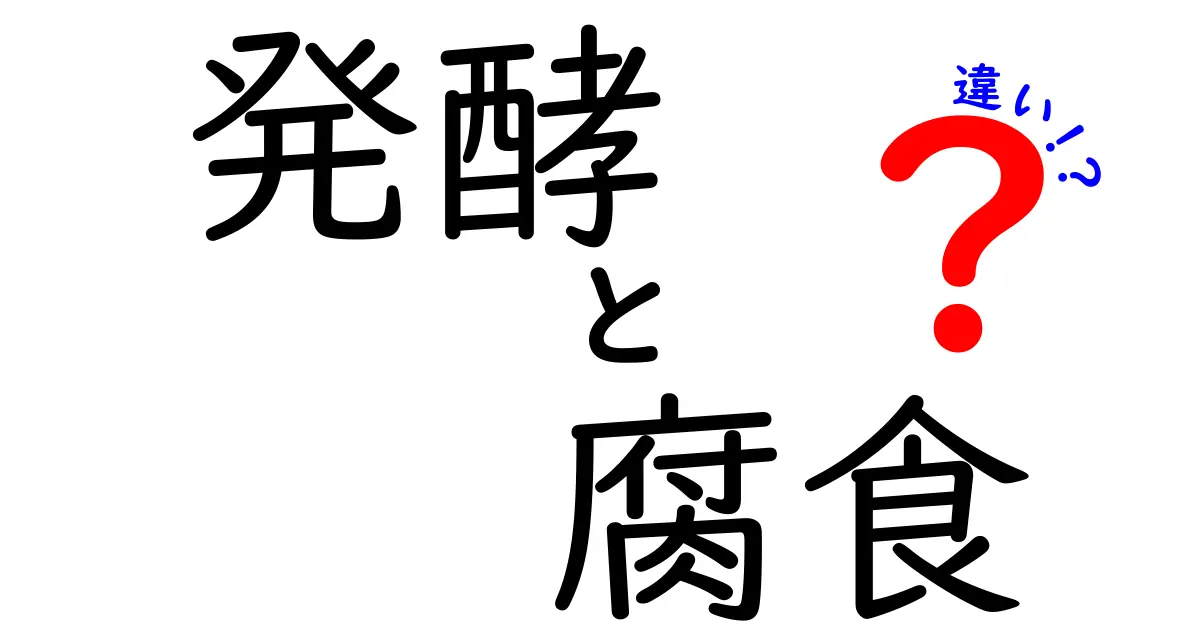
発酵と腐食の基本的な違いとは?
発酵と腐食は、どちらも食品や物質の変化を指す言葉ですが、意味は大きく異なります。発酵とは、微生物が糖を分解することで、新たに体に良い成分や味わいを生み出す過程です。これに対して、腐食は主に微生物の働きにより食品などが分解されて、悪臭や健康に悪影響を与える物質ができる不快な状態を指します。
生活の中にある例として、味噌や納豆のような発酵食品は健康に良い影響を与えますよね。一方で、食べ物が腐ってしまうと見た目も悪く、食べるとお腹を壊すかもしれません。これらの違いは、見た目やにおいの違いだけでなく、体への影響も大きく変わってくるのです。
このように、発酵は「良い変化」、腐食は「悪い変化」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
発酵の種類と体へのメリット
発酵にはいくつか種類があり、代表的なのはアルコール発酵や乳酸発酵です。アルコール発酵は酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に分解する過程で、ビールやワインの製造に使われます。乳酸発酵は乳酸菌が糖を乳酸に変えることで、ヨーグルトやキムチ、漬物などに利用されています。
これらの発酵過程は、食べ物を保存しやすくするだけでなく、消化を助けたり、腸内環境を整えたりするなど健康に良い影響ももたらします。また、独特の香りや味わいが生まれ、食文化の豊かさにつながっています。
発酵食品を取り入れることで、免疫力を高めたり、栄養の吸収を良くしたりすることが期待できるため、積極的に食生活に取り入れるのがおすすめです。
腐食が引き起こす問題と見分け方のポイント
一方で腐食は、食品が衛生的に劣化し、食べられなくなる状態を指します。主に細菌やカビが関わり、不快な臭いや色の変化、ネバネバやぬめりが現れます。腐食した食品を食べると食中毒になる危険もあるため注意が必要です。
発酵と腐食の見分け方のポイントは、臭いや見た目、味の違いにあります。発酵は酸味や旨味が特徴で、腐食は嫌な臭い(酸っぱい以外の腐った臭い)がすることが多いです。また、腐食はカビが生えていたり、異常に柔らかくなったりして触感も変わります。
食品を安全に食べるためには、これらの違いを理解して上手に見分けることが大切です。気になる場合は無理に食べずに処分しましょう。
発酵と腐食の違いを表でまとめると?
まとめ
発酵と腐食は見た目や臭いが似ていることもありますが、発酵は健康的な食品作りの過程であり、腐食は食品の劣化を意味します。日常生活で食品を安全に楽しむためにも、この違いを正しく理解して役立ててください。
発酵といえば、私たちの身近に数え切れないほどありますが、中でも「納豆」は面白いですね。納豆は大豆を納豆菌という微生物で発酵させますが、その過程で強烈なにおいが出ます。このにおい、実はタンパク質が分解されてできる成分が原因で、最初は不快に感じても、慣れると旨味に感じるようになります。つまり発酵では、雑菌の腐食とは違い、不快な臭いも「文化」として楽しめる部分があるんです。
発酵の奥深さは、こうしたにおいの違いを理解するともっと面白くなりますよ。
前の記事: « 火傷と炎症の違いとは?見分け方と対処法をわかりやすく解説!