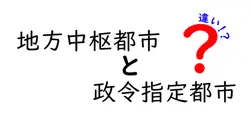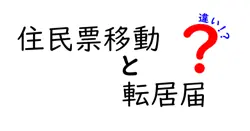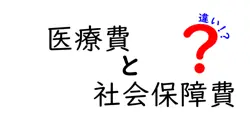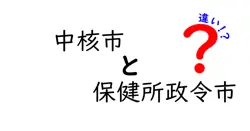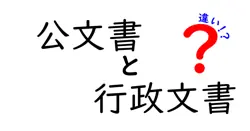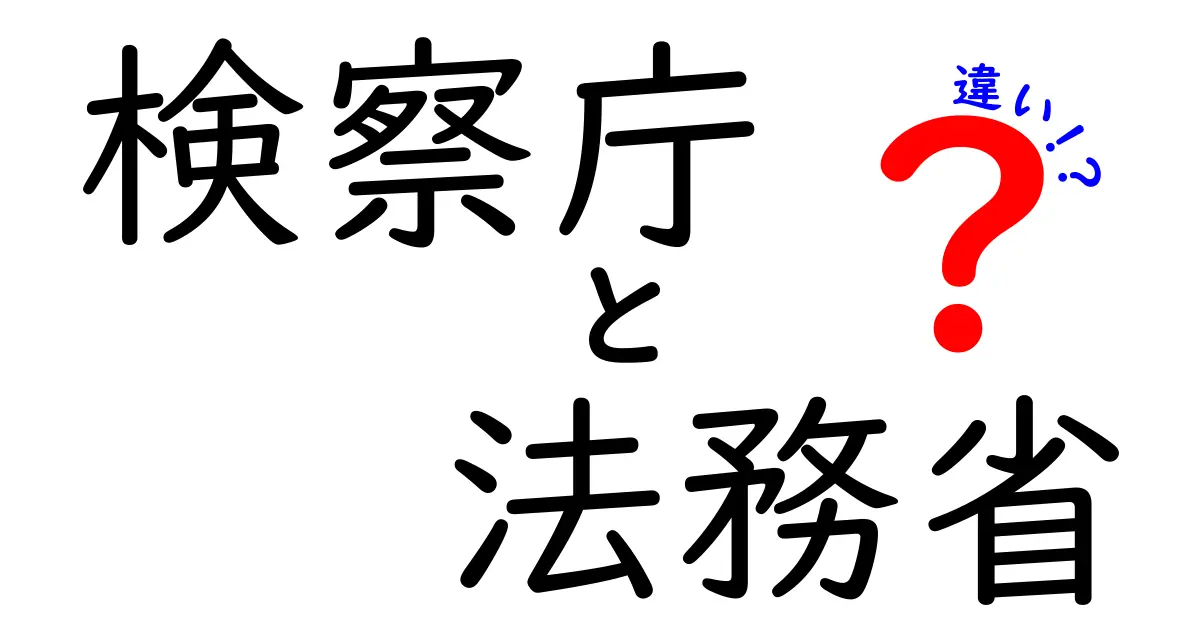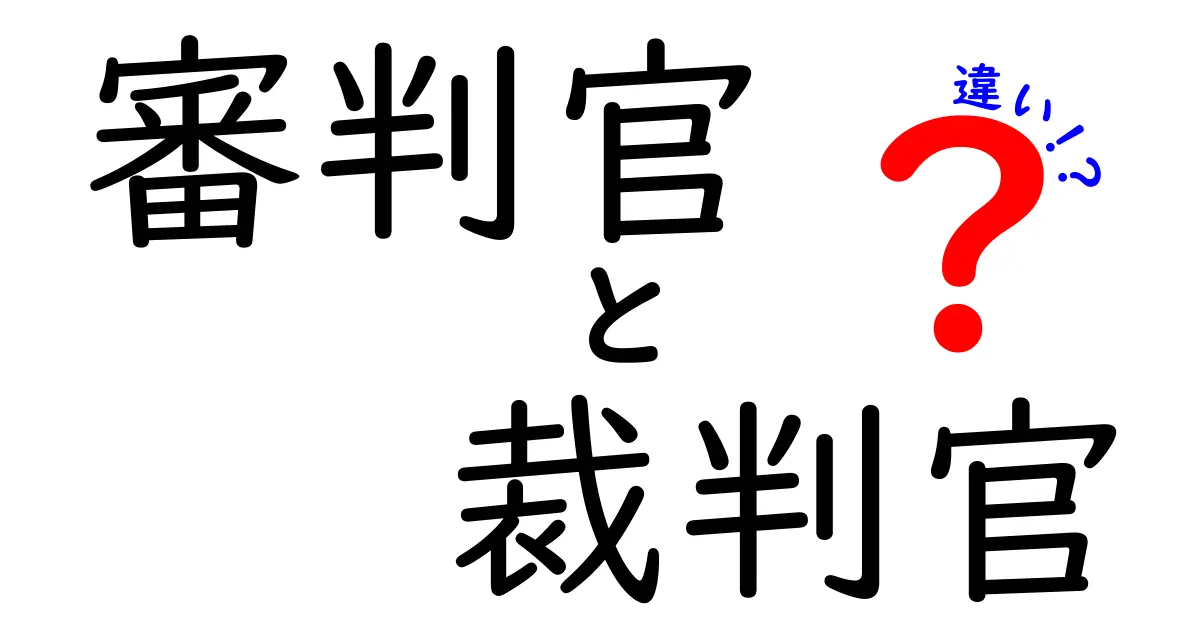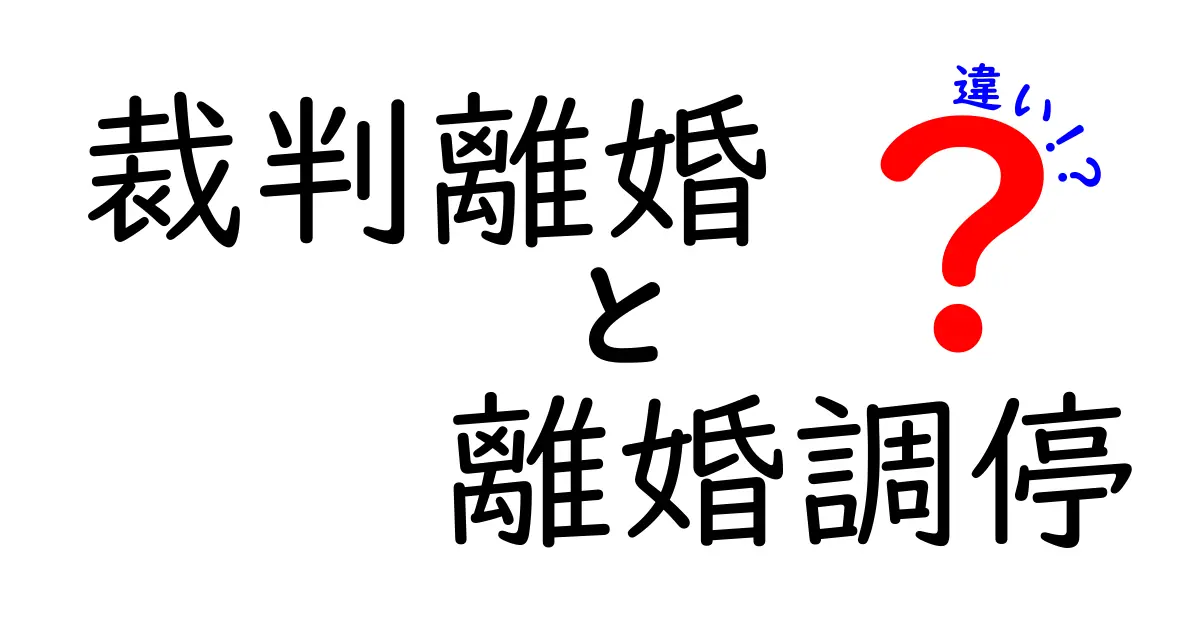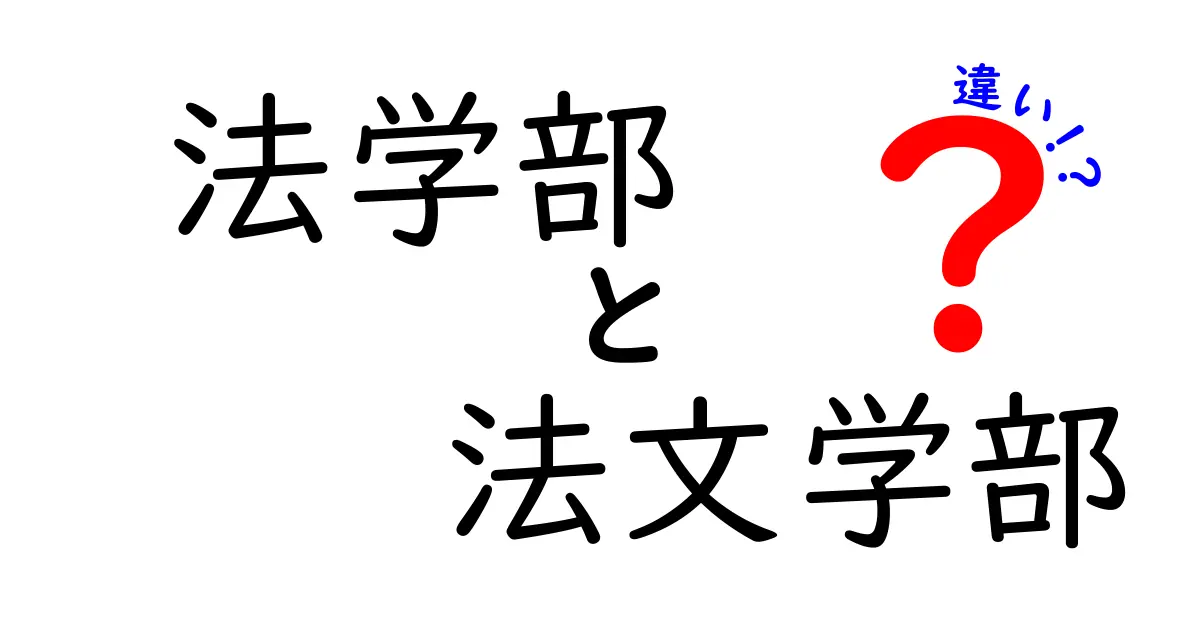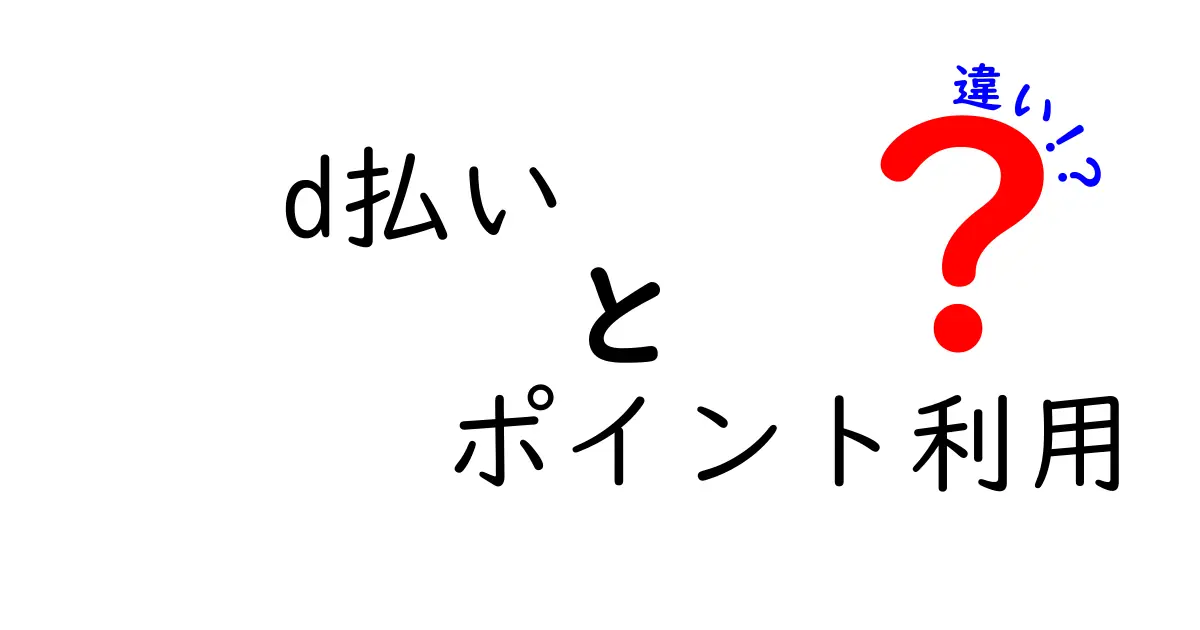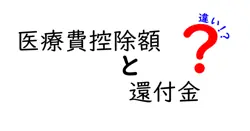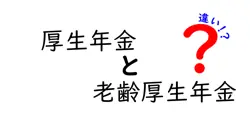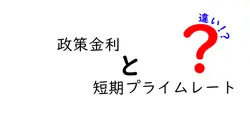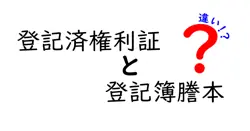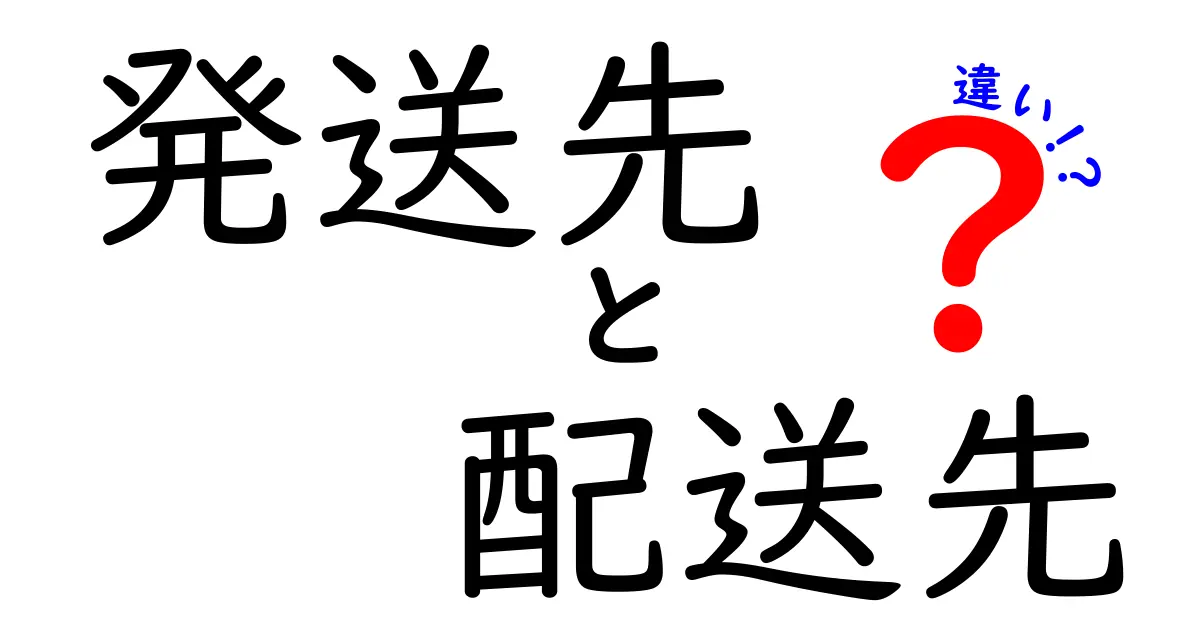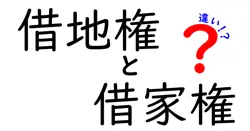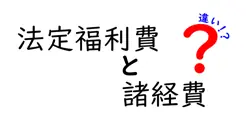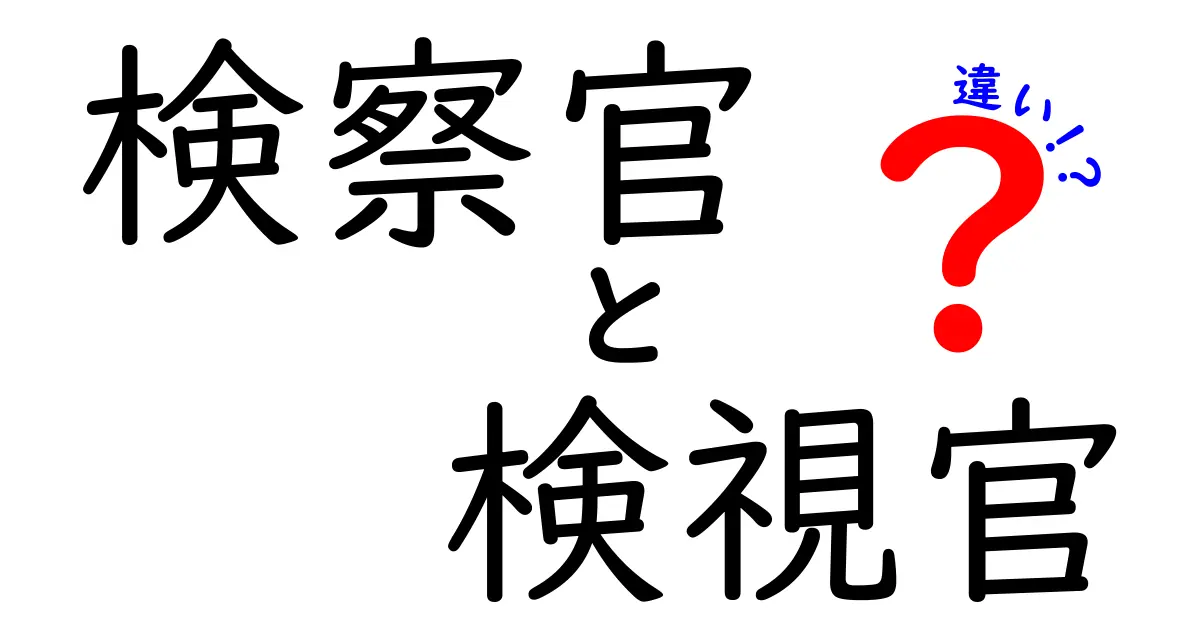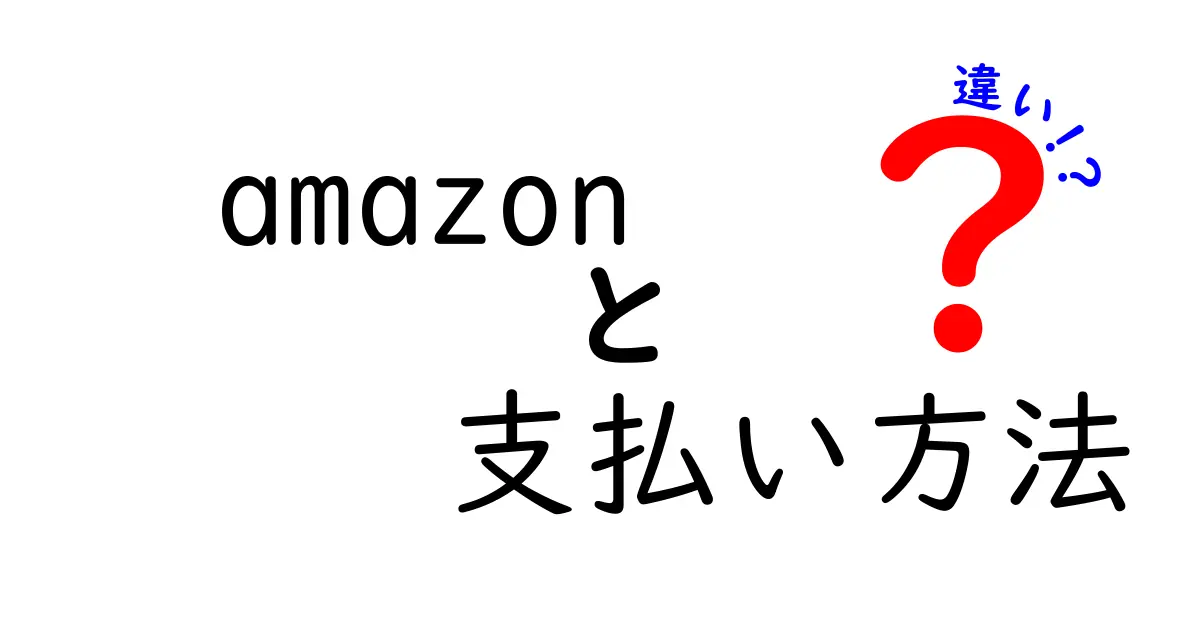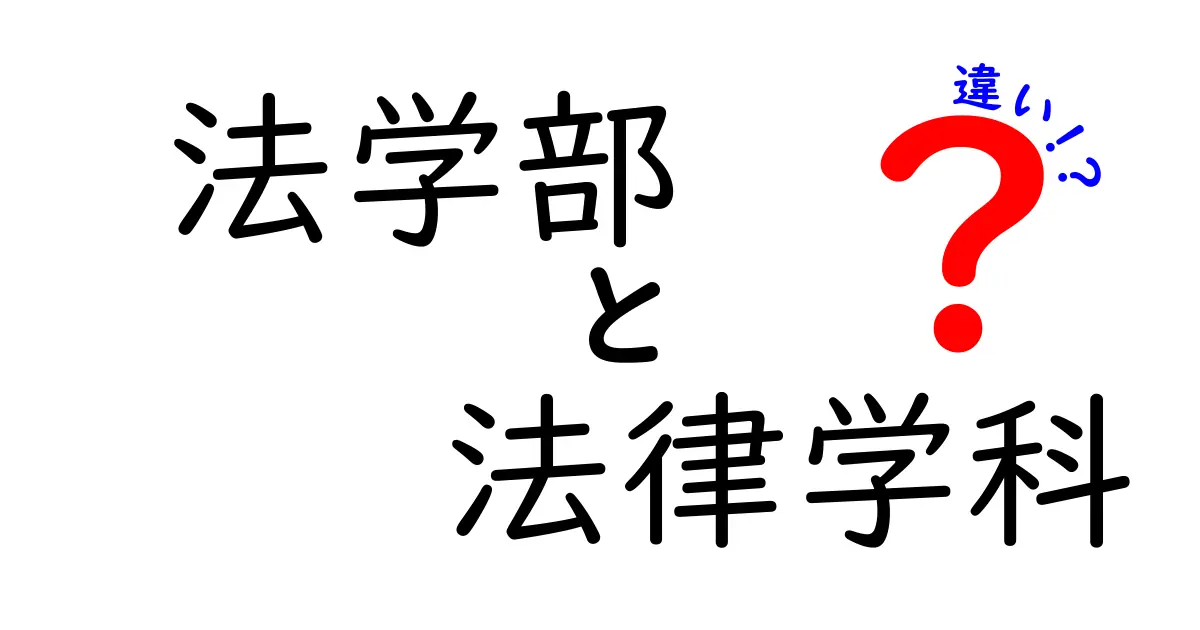
法学部と法律学科の違いとは?
大学を選ぶときに「法学部」と「法律学科」という言葉をよく耳にしますよね。
でも、この二つは実際どう違うのでしょうか?
法学部は大学の学部の名前で、法律学科は法学部の中にある学科の一つである場合がほとんどです。
つまり、法学部には法律を中心に学ぶ法律学科のほかに、政治学科や公共政策学科があることもあります。
それに対して、「法律学科」という名前の学科は、主に法律の専門知識を深く学ぶ学科を指します。
この違いを理解しないと、どこの大学で何を学ぶべきか迷ってしまうことも多いので、しっかり知っておきましょう。
法学部は、法律だけでなく政治や社会の仕組みについて幅広く学ぶ場であり、法律学科はより法律そのものに特化した学びを提供しているのです。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
法学部とは何か?
法学部は大学の1つの学部で、法律や政治、社会のルールについて学ぶ学部です。
日本の多くの大学で「法学部」という学部名があり、そこでは法律はもちろん、政治学や行政学、国際関係論なども勉強できます。
つまり、法学部は法律そのものだけでなく、社会や政治の仕組みを広く学ぶ場となっています。
法学部に進むと、民法や刑法などの法律の基本を学べるのはもちろん、政治のしくみや行政の役割など社会を支える仕組みにも触れることができます。
これは将来、法律関係の仕事だけでなく、公務員や企業の法務部門など、幅広い分野で役立つ知識となります。
法学部の中には複数の学科がある場合が多く、例えば「法律学科」「政治学科」「行政学科」「国際関係学科」などに分かれている大学もあります。
それぞれの学科で学ぶ内容や重視する分野は異なります。
法律学科とは何か?
法律学科は、法学部の中に設置されていることが多い「法律の勉強に特化した学科」です。
法律学科では、法律のルールや判例、法律をどう使うかという応用知識まで幅広く学びます。
たとえば、憲法、民法、刑法、商法などの基礎法だけでなく、会社法や労働法、環境法などの専門分野も深く勉強できます。
司法試験や行政書士試験などの国家資格の対策としても強い学科です。
法律学科は法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を目指す人にとっては特に重要な学科となりますが、法律の専門家を目指さなくても、企業や行政機関で役立つ知識を身につけられます。
また、法律学科のカリキュラムは法律の専門性が高く、理論的な学習と実践的な学習の両方をバランスよく取り入れています。
法学部と法律学科の主な違いを表でまとめると
| ポイント | 法学部 | 法律学科 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 大学の学部名 複数の学科を含むことが多い | 法学部の中の1つの学科 法律の専門分野 |
| 学ぶ内容 | 法律・政治・行政・国際関係など幅広い | 法律に特化した専門的な内容 |
| 将来の進路 | 公務員や企業、国際関係の仕事など幅広い | 法律家(弁護士など)や法務担当者向き |
| カリキュラムの特徴 | 多様な科目を基礎から学ぶ | 法律理論と実務を深く学ぶ |
| ポイント | 検察庁 | 法務省 |
|---|---|---|
| 主な仕事 | 犯罪の捜査や起訴、裁判での立証 | 法律の政策立案、司法制度の運営、検察庁の監督 |
| 組織の位置 | 検察官が働く現場の機関 | 内閣の省庁のひとつ、国家の行政機関 |
| 取り扱う範囲 | 具体的な事件や犯人の対応 | 法律や司法システム全般、外国人政策など |
| 目的 | 正しい裁判のために証拠を集める | 日本全体の法的な秩序を作り、守る |
まとめ
検察庁と法務省は
・検察庁は実際に事件を扱う捜査・起訴機関
・法務省はそれらを統括し、法律や司法の政策を決定する省庁
という関係にあります。
ニュースや社会の動きを理解するために、どちらの役割かを知っておくと情報がスムーズに入ってきますよ。
ぜひ身近な法律のしくみを知るヒントにしてください!
今回は「検察庁」というキーワードについて小ネタを紹介します。
検察庁は事件の捜査や裁判でとても重要な役割を持っていますが、意外と知られていないのが『検察官は法の番人』と呼ばれていることです。これは不正や犯罪を見逃さず、社会のルールを守る役割からきています。
また、検察官は単に犯人を起訴するだけでなく、無罪の人を守る義務もあるのです。このバランス感覚が検察庁の信頼を支えています。
だからニュースで検察庁の話が出たら、その裏には「公平に法律を守ろうとする強い意志」があると思ってくださいね。
前の記事: « 裁判官と裁判長の違いを徹底解説!知られざる役割と責任とは?
政治の人気記事
新着記事
政治の関連記事
裁判官と裁判長の違いを徹底解説!知られざる役割と責任とは?
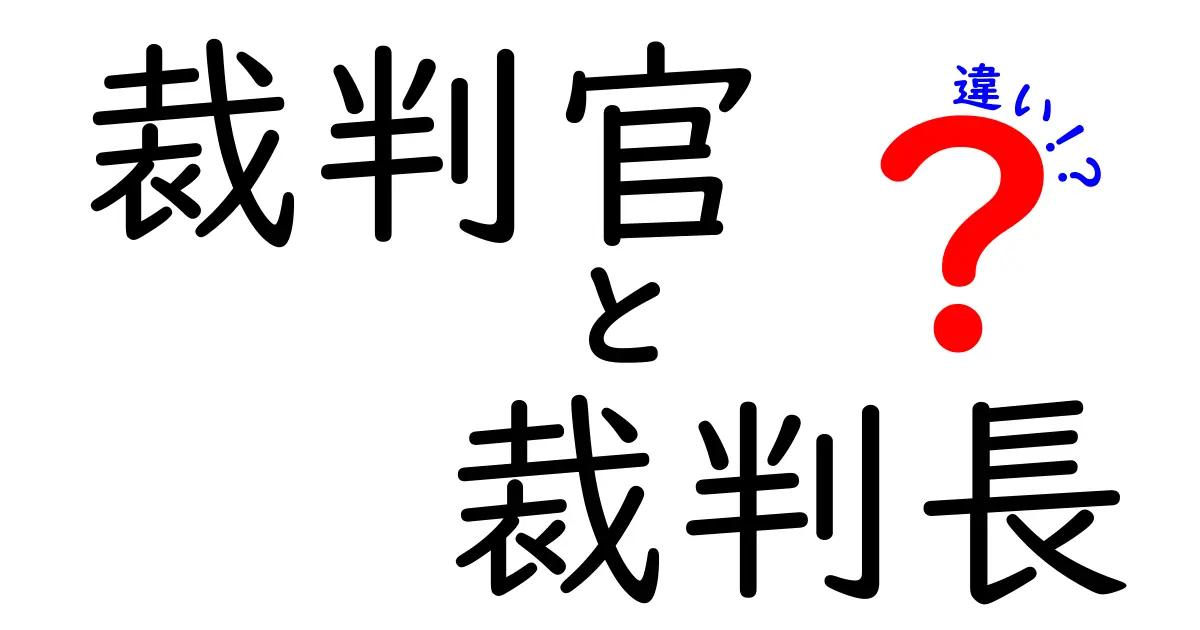
裁判官と裁判長って何?基本を押さえよう
裁判に関する言葉として「裁判官」と「裁判長」がありますが、実はこの二つは同じではありません。裁判官は裁判を行う人全般を指す言葉で、一人の裁判に複数の裁判官が参加することもあります。一方、裁判長はその裁判における裁判官のリーダーの役割を持つ人のことです。
まずは裁判の現場で、どのように裁判官が配置されているかを理解しましょう。裁判官は複数人で構成される合議体と呼ばれる形で裁判を行うことが多く、合議体の中で決定的な責任を持つのが裁判長です。
このように、裁判官が裁判全体を担当する役割の総称として使われるのに対し、裁判長はその中でも裁判を指導し進行させる責任者という明確な役割があります。
わかりやすく言うと、裁判官がチームのメンバー全員であるのに対し、裁判長はそのチームのキャプテンのような存在です。
裁判官と裁判長の具体的な違い
裁判官は法律に基づいて証拠を検討し、判決を下す役割を持つ一方で、裁判長は裁判の進行管理や手続きの司会、裁判官間の意見調整も行います。
裁判長は例えば、裁判の日程調整や開廷の宣言、証人尋問の進行指示も担当します。合議体の意見が割れた時には裁判長の意見が重視される傾向があります。
裁判官には単独で裁判を行う場合もありますが、多くの重要事件では裁判長を含む複数の裁判官が合議体を組んで判断します。
以下の表で主な違いをまとめました。
なぜ裁判長が必要なのか?役割の重要性とは
裁判はたくさんの意見や証拠をもとに公平な判断を下さなければなりません。複数の裁判官が関わる場合、意見が食い違うこともあるでしょう。そんな時に裁判長のリーダーシップが重要です。
裁判長は裁判の進行を円滑にし、誰も発言機会を失わないようまとめ、最終的な決定をスムーズに行う役割を持っています。裁判が長引かず、効率よく進むことが、正しい判決を導くためにも欠かせません。
また、裁判長は裁判官の中でも経験豊富であり、若手裁判官の指導的役割も担うことがあります。裁判全体の質を高め、社会正義を守る重要な立場と言えます。
裁判官一人ひとりが法律の専門家であるのはもちろんですが、裁判長がいなければまとまりのある裁判は難しいと言えるでしょう。
裁判長という役割は、意外に知られていませんが、実は裁判の"司会者"のような役割を持っています。
証人が話したり、弁護士が質問したりするとき、裁判長が全体の流れを管理していて、意見がぶつかったときには調整役としても重要な存在です。
裁判長の経験や判断力で裁判の質も変わると言われるので、表には出ないけどすごく大事な役割なんですよ。
前の記事: « 審判官と裁判官の違いは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: 知っておきたい!検察庁と法務省の違いをわかりやすく解説 »