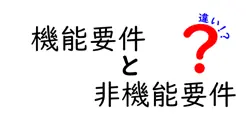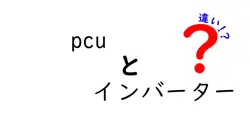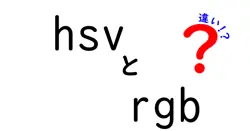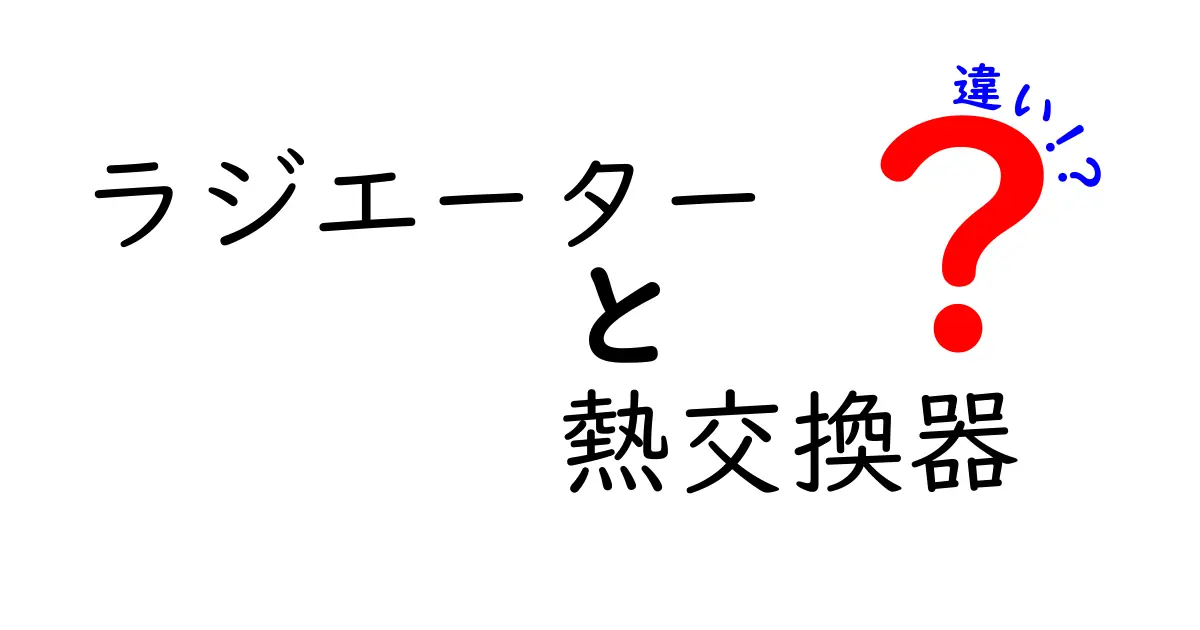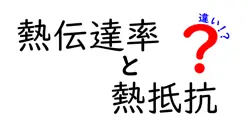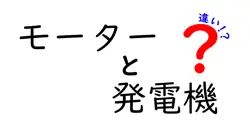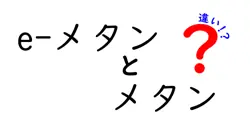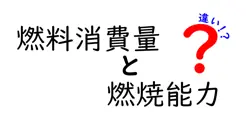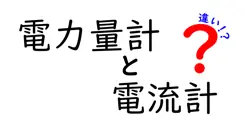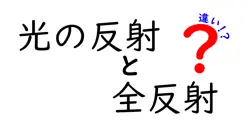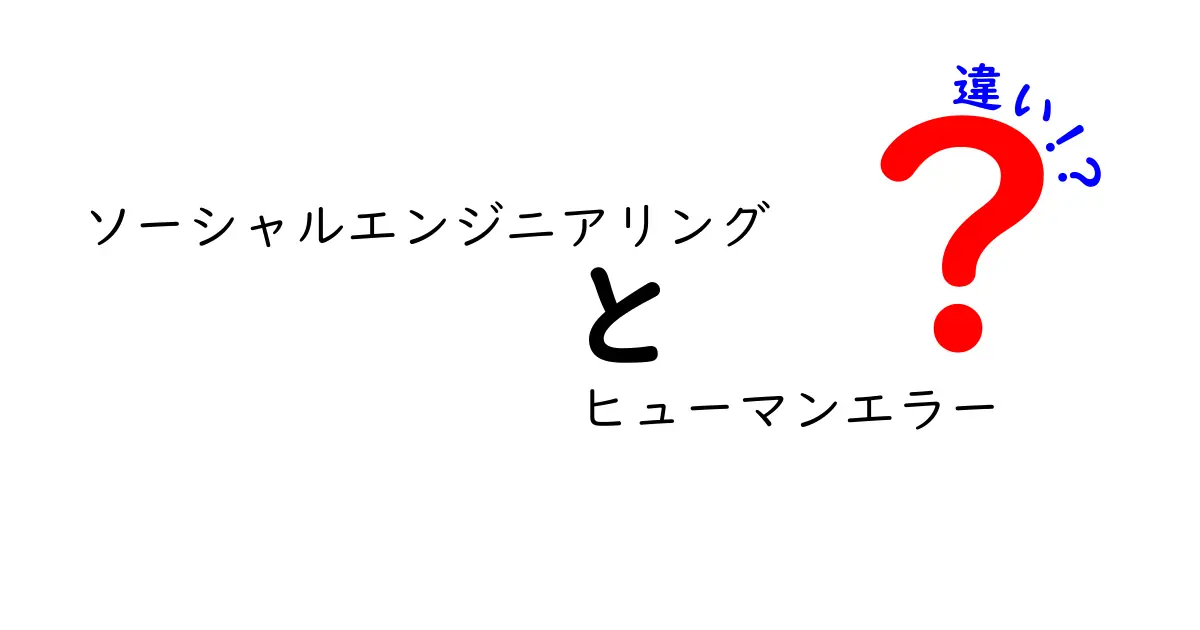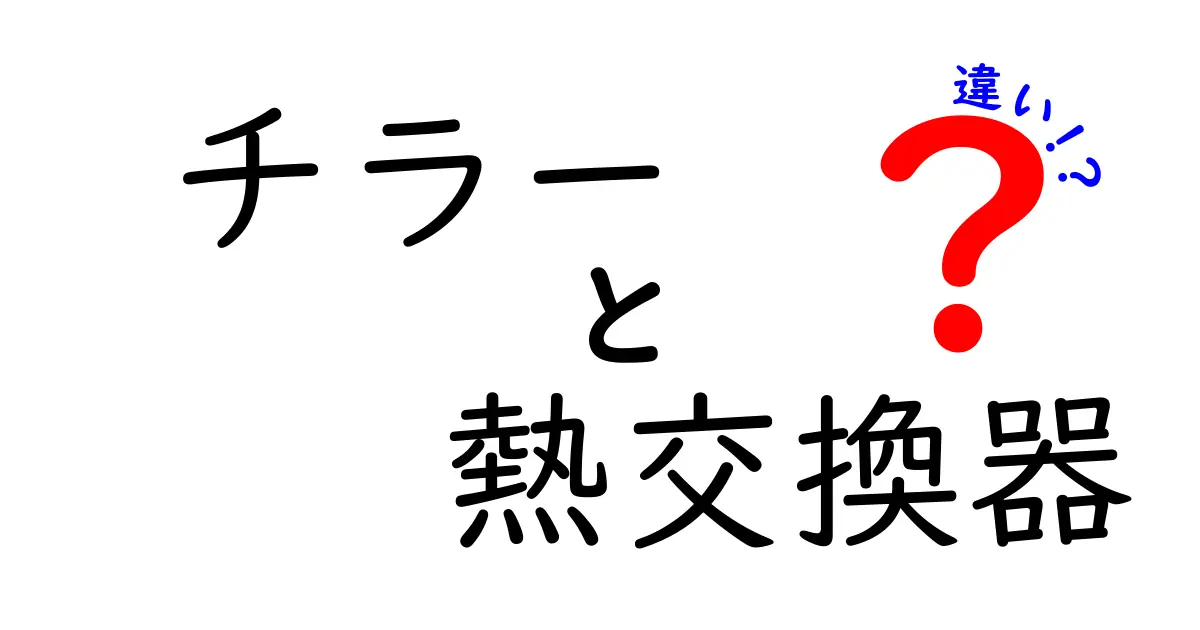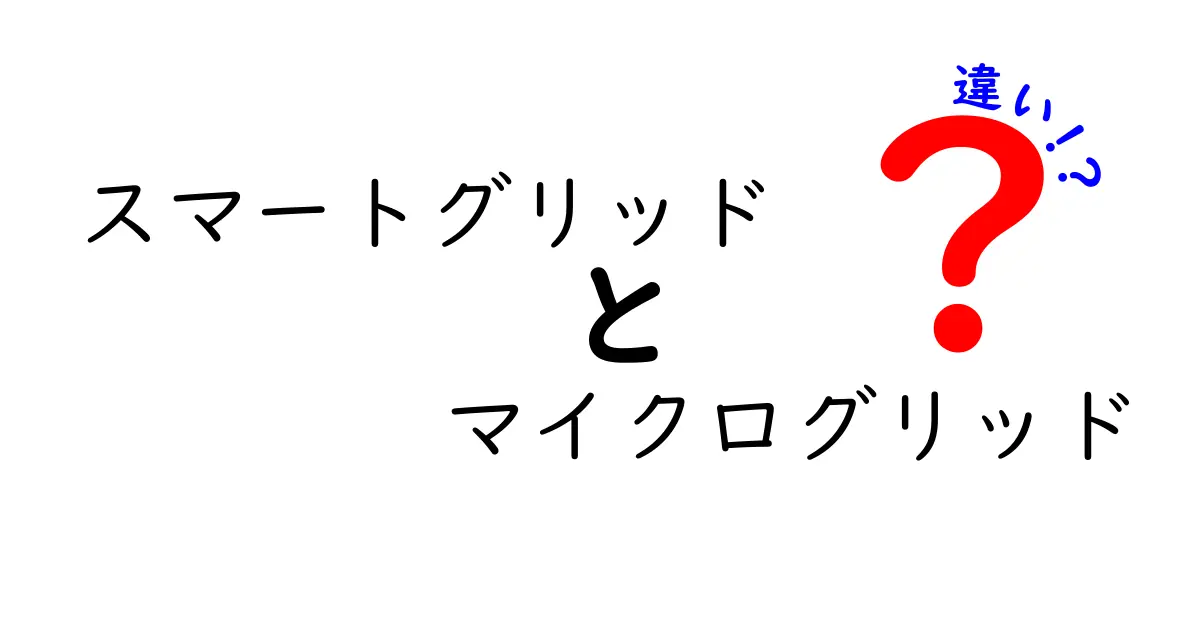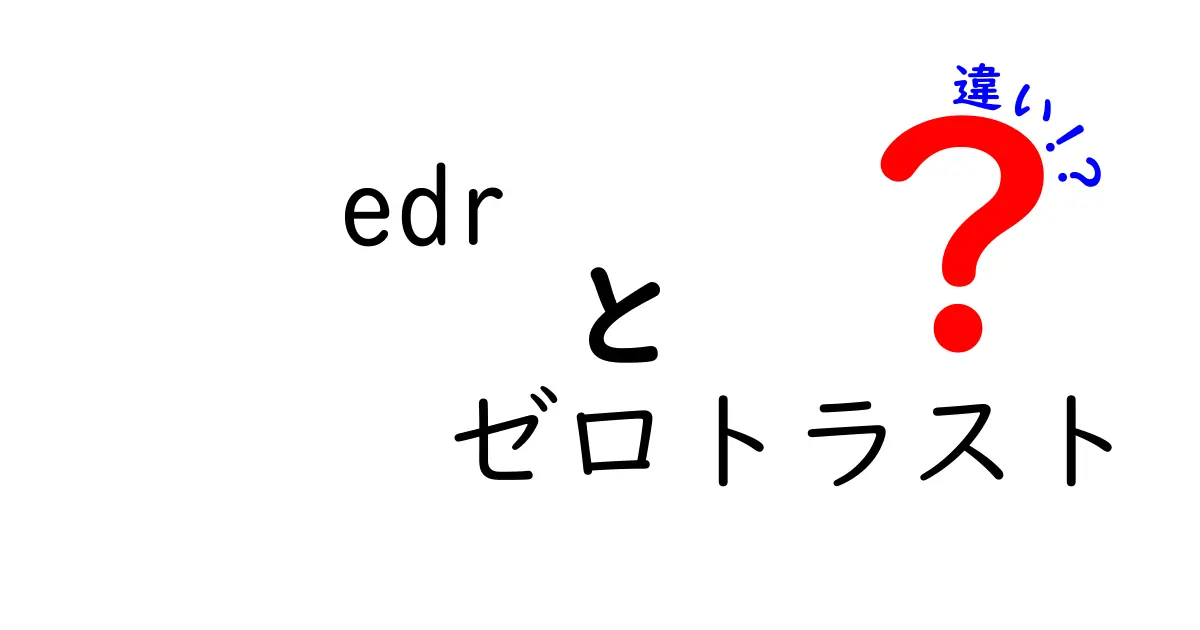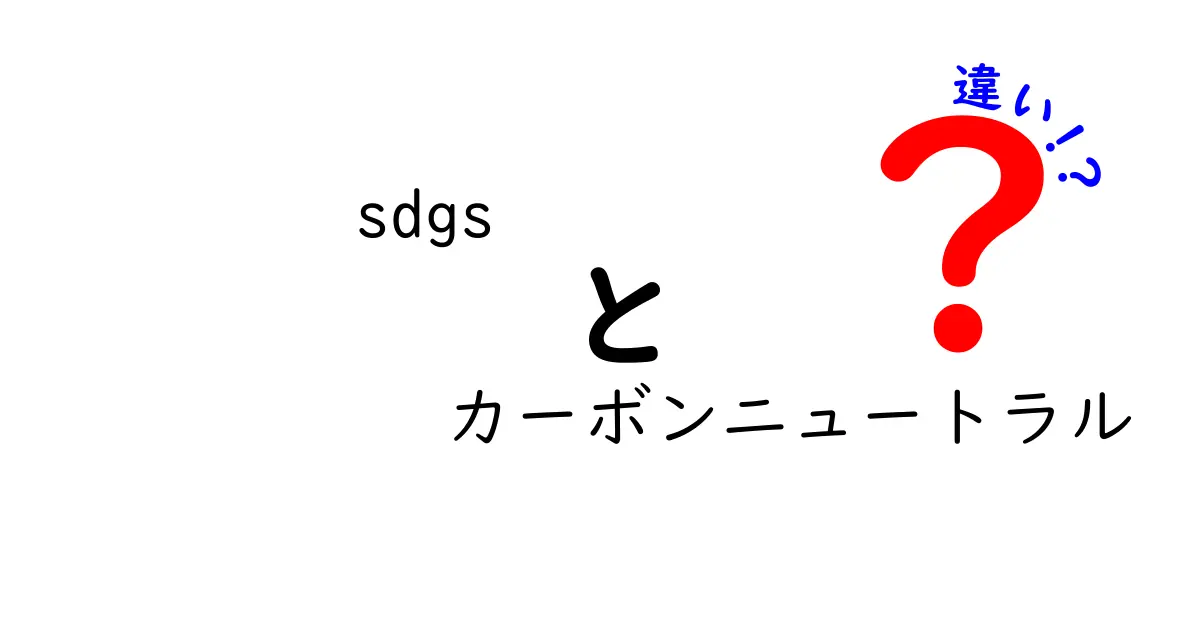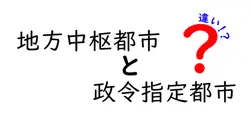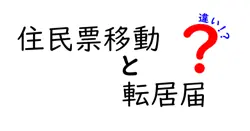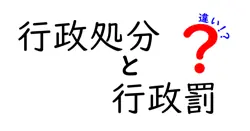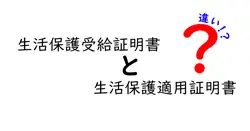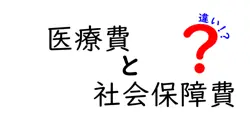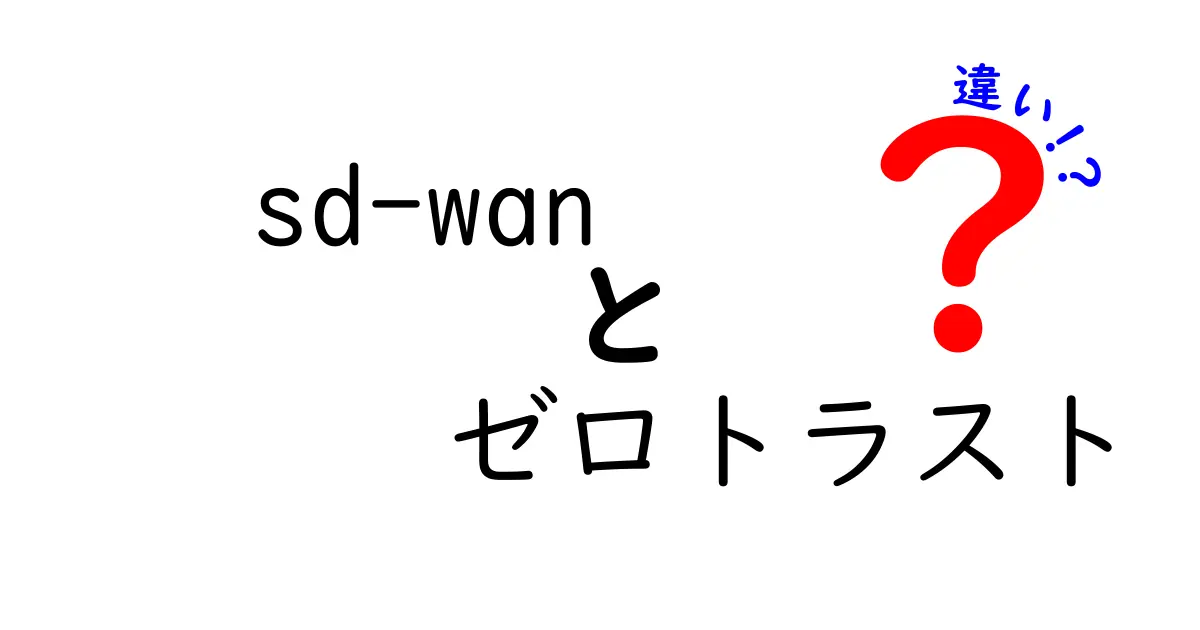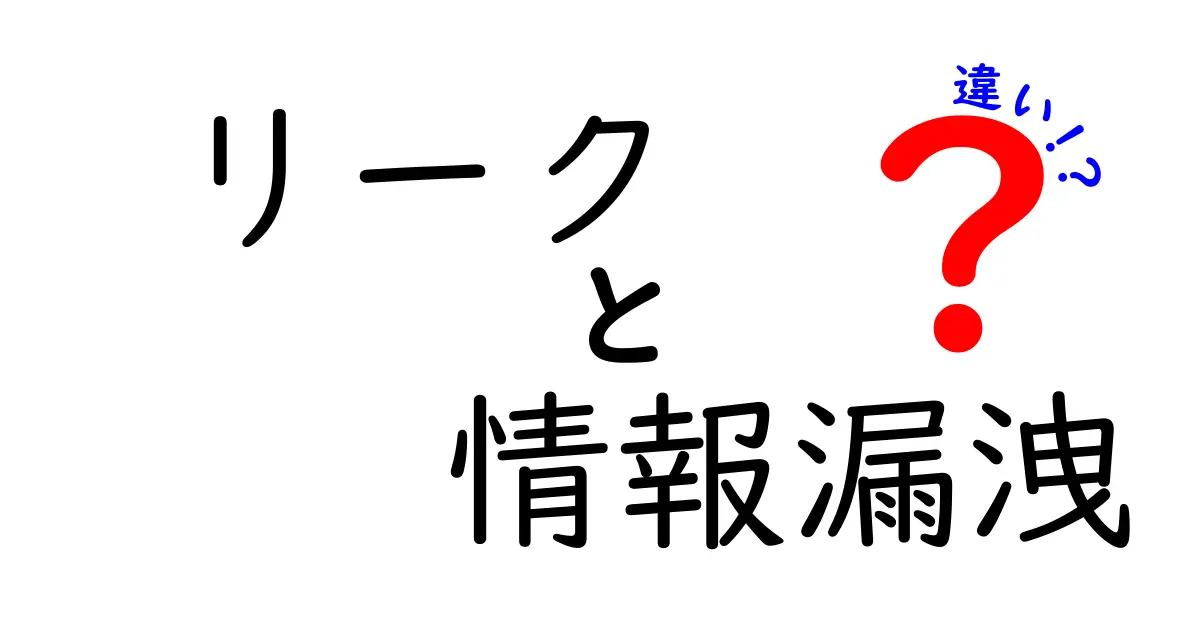
リークと情報漏洩の基本的な違い
<日常生活や仕事の中で「リーク」と「情報漏洩」という言葉をよく聞きますが、両者には明確な違いがあります。
まず、リーク(Leak)は「意図的に、または非公式に情報が外部に流れること」を指し、時には内部からの情報公開や報道目的で行われます。
一方、情報漏洩(じょうほうろうえい)は「守るべき秘密や個人情報が不注意や悪意によって外部に漏れてしまうこと」を意味し、企業や組織にとって大きなリスクとなります。
つまり、リークは必ずしも悪意や事故だけで起こるものではなく、情報漏洩は通常、守るべき情報が不適切に流出する「問題行為」である点が異なります。
この二つの言葉は混同されやすいですが、意味や背景を知ることで、状況に応じた対策や理解が可能になります。
リークが起こる背景と事例
<リークは時に
例えば、企業の新製品情報が公式発表前に外部に流れたり、政治家の不正行為を告発するために内部情報が外に出るのがリークの一例です。
多くの場合、リークは情報提供者の意思が伴い、意図的であることが多いです。
そのためリークは、情報の透明性や社会的正義のために役立つこともありますが、一方で情報管理上のトラブルや混乱を招く危険性も含んでいます。
リークが報道された際は、情報の真偽や背景をしっかり確認することが重要です。
情報漏洩の原因と防止策
<情報漏洩は主に不注意やハッキング、内部の人的ミスなどで発生します。
例えば、社員がパスワードを書いたメモを紛失したり、サイバー攻撃により企業の顧客情報が盗まれるケースが典型的です。
情報漏洩は信頼の喪失や法的な問題、経済的損失に繋がるため、企業にとって重大なリスクです。
防止策としては、
- アクセス権限の適切な管理
- 定期的なセキュリティ教育
- 強固なパスワード設定と多要素認証
- 不正アクセスの監視システム導入
また、情報は扱う人全員が意識を高く持つことも非常に重要です。<<
リークと情報漏洩の比較表
<| 項目 | リーク | 情報漏洩 | |
|---|---|---|---|
| 意味 | 意図的または非公式に情報が外部に流れること | 守るべき情報が不注意や悪意で漏れてしまうこと | |
| 発生原因 | 内部告発や報道目的等の意図的な場合が多い | ヒューマンエラー、セキュリティ不備、サイバー攻撃など | |
| 影響 | 社会的な議論を生むこともある | 損失や信用低下など企業に悪影響が大きい | |
| 対応 | 情報の真偽確認や法的判断が必要 | セキュリティ強化と教育が重要 |
| ポリシー名 | TLSバージョン | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ELBSecurityPolicy-2016-08 | TLS 1.0~1.2 | 古いTLSも使える。互換性重視。 | 旧式のクライアント対応 |
| ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 | TLS 1.2のみ | 強力な暗号スイートのみ許可。 | 高い安全性を求める場合 |
| ELBSecurityPolicy-FS-2018-06 | TLS 1.2のみ | 前方秘匿(PFS)対応。通信の秘密性向上。 | 最も安全性が高い設定 |
このように、ALBのセキュリティポリシーには複数の種類があり、特徴も少しずつ違います。
選び方は、どの程度安全を重視したいか、どんなユーザー環境に対応したいかで判断します。
セキュリティポリシーの選び方と使い分けのポイント
1. 利用者の環境を考える
最新のブラウザーやOSを使っている利用者が大半なら、TLS1.2の強力なポリシーがおすすめ。古い端末やOSも多く使われている場合は、互換性の高いポリシーも検討しましょう。
2. セキュリティの重要性を考える
銀行や病院など重要情報を扱うサイトの場合は、できるだけ前方秘匿(PFS)に対応した強力なポリシーを使うべきです。
3. テスト環境で動作確認をする
実際に利用者がアクセスできるか、サイトの安全性が保たれているかをテストします。問題があればポリシーを変更して調整しましょう。
これらを踏まえると、セキュリティポリシーは「安全と使いやすさのバランス」を取ることが大切だとわかります。
まとめ:ALBのセキュリティポリシーの違いを理解しよう
ALBのセキュリティポリシーは、通信の安全性や対応する機器・ブラウザの範囲を決める重要な設定です。
代表的なポリシーはTLSのバージョンや暗号スイートの種類が違い、選択によって安全性と互換性のバランスが変わります。
ユーザー環境やサービスの性質を考えて、適切なポリシーを選ぶことがALBのセキュリティ強化に繋がります。
まずは代表的なポリシーの違いを理解し、テスト環境でしっかり動作確認をするところから始めましょう!
ALBのセキュリティポリシーでよく使われる「前方秘匿(PFS)」について、ちょっと掘り下げてみましょう。PFSとは、一度の通信が終わった後に秘密の情報が漏れても、その後の通信内容は守られる仕組みです。
例えば秘密の手紙を書いて送っているとき、もし誰かに途中で手紙の内容がバレても、その後書く手紙は別のキーで暗号化されるので内容秘匿が続くのです。
このPFS対応のセキュリティポリシーは、特に大切な情報を扱うウェブサイトで多く利用されていて、セキュリティの強さをぐっと高める役割を果たしています。ALBを使うならぜひチェックしておきたいポイントですよね。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
セキュリティインシデントとセキュリティ事故の違いとは?初心者にもわかりやすく解説!
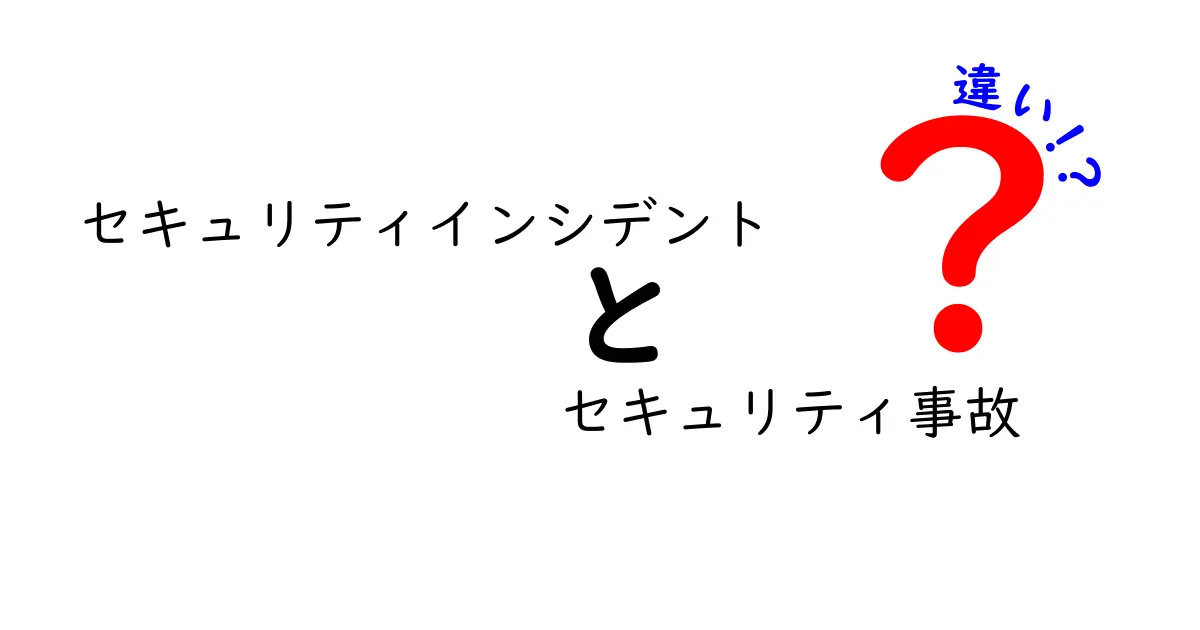
セキュリティインシデントとセキュリティ事故の基本的な違いとは?
セキュリティの分野でよく使われる「セキュリティインシデント」と「セキュリティ事故」という言葉は、似ているようで意味や使い方に違いがあります。
セキュリティインシデントとは、セキュリティ上の問題が起こったり、その可能性がある事象のことを指します。例えば、不正アクセスの試みや不審な通信など、まだ大きな被害が出ていないが注意すべき出来事です。
一方で、セキュリティ事故はインシデントが進展し、実際に情報漏えいやシステム障害などの被害が発生してしまった状態を意味します。つまり、インシデントは予兆や初期段階、事故はその被害が確定した段階で使われる言葉です。
この違いを理解することは、事故対応の適切な判断や防止策の構築に役立ちます。
具体例でわかるセキュリティインシデントとセキュリティ事故の違い
もう少し具体的に考えてみましょう。例えば、あなたの会社のパソコンで誰かが不正ログインを試みた痕跡があったとします。
この時点ではまだ情報が盗まれたりシステムが壊されたわけではありません。これがセキュリティインシデントです。
しかし、その不正ログインに成功して顧客情報が外部に漏れてしまった場合は、これがセキュリティ事故となります。
また、ウイルスに感染した疑いがあるが詳細はまだ不明な状態もインシデント、感染が確定しシステムが広範囲に破壊されたら事故と区別されます。
このように、インシデントは問題発生の可能性や初期段階、事故は被害が確定した状態をあらわします。
セキュリティインシデントとセキュリティ事故の管理と対応の違い
セキュリティインシデントとセキュリティ事故は発生した時の対応が異なります。
インシデント管理は、いち早く問題を検知し、拡大を防止、被害になる前に対応することが目的です。例えばログの監視や疑わしい通信の遮断、調査などが中心になります。
一方、事故対応はすでに被害が発生し、被害の拡大防止と復旧、原因調査を実施します。被害者への連絡や法的対応、再発防止策の策定も求められます。
以下の表に違いをまとめます。項目 セキュリティインシデント セキュリティ事故 意味 問題発生や発生の疑いがある状態 被害が確定し実際の損害が出た状態 例 不正アクセスの試み、ウイルス感染の疑い 情報漏えい、システム破壊 対応 早期検知、拡大防止、調査 被害対応、復旧、再発防止策の実施
このように、両者は因果関係にあり、インシデントの適切な管理が事故発生防止につながります。
「セキュリティインシデント」という言葉は、実は『まだ被害が発生していないけれど、問題の兆候がある状態』を指します。ちょっとした怪しい動きや間違いが原因でもインシデントになり得るので、実は日常的に企業のセキュリティ担当者が注意深く見ている警告音のようなものなんです。だからインシデントを見つけたらすぐに対処することで、大きな事故を防ぐ第一歩になるんですよ。まるで病気の初期症状を見逃さないようにするイメージですね。