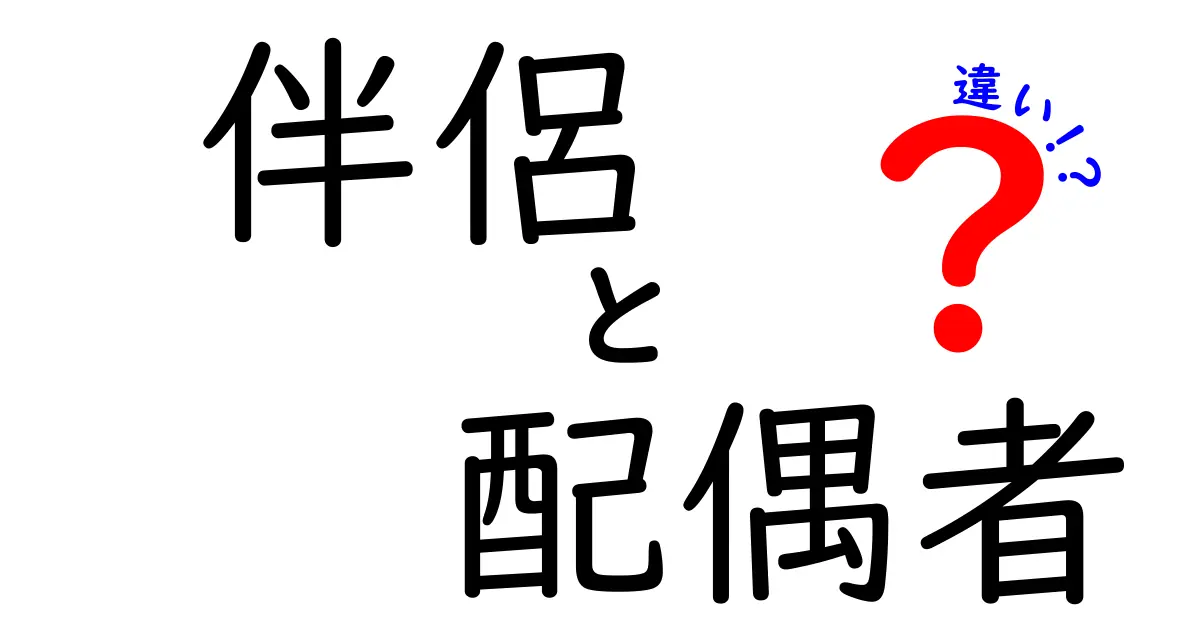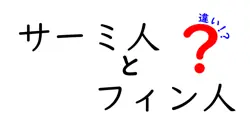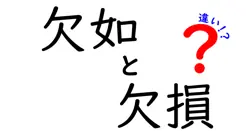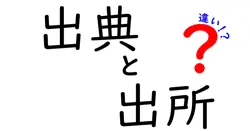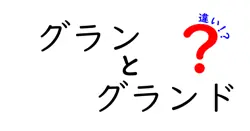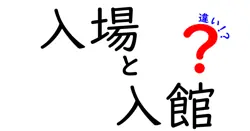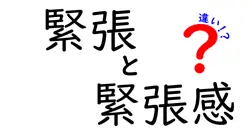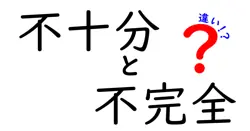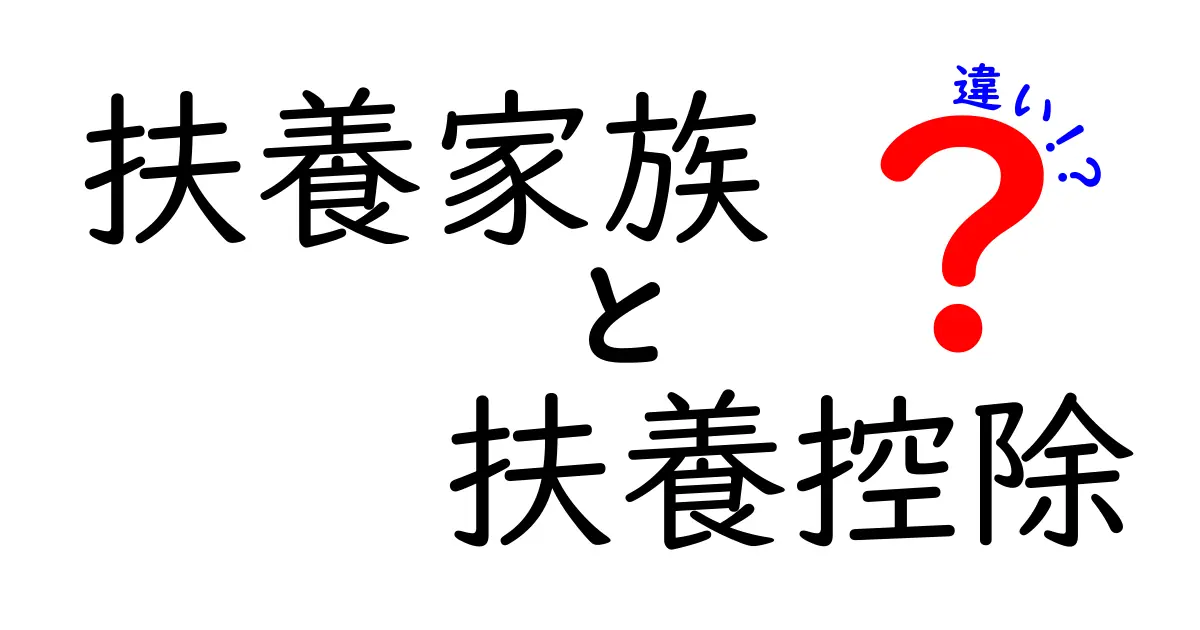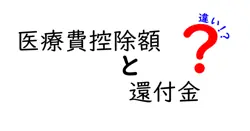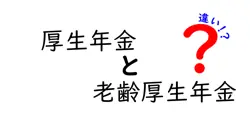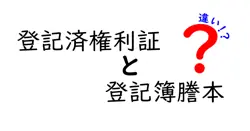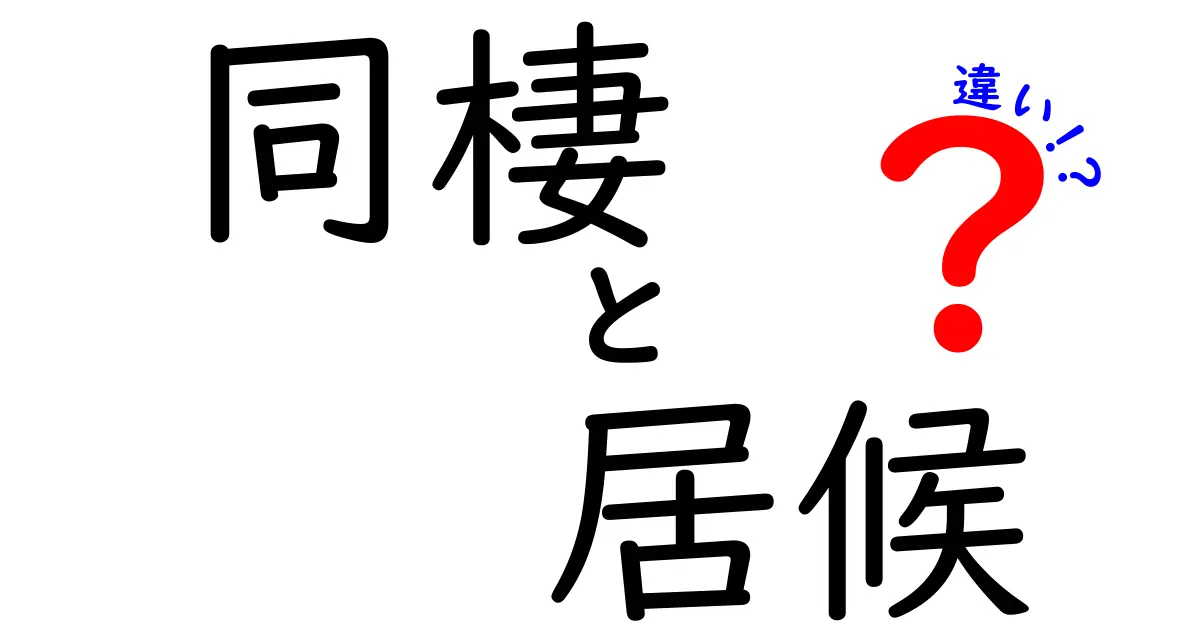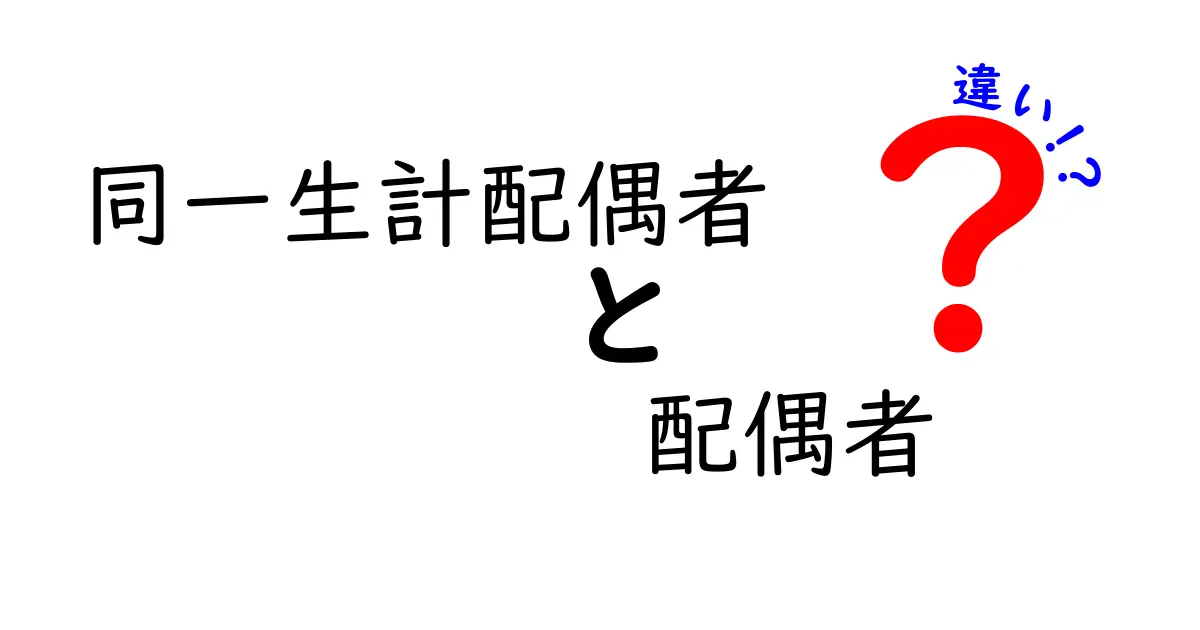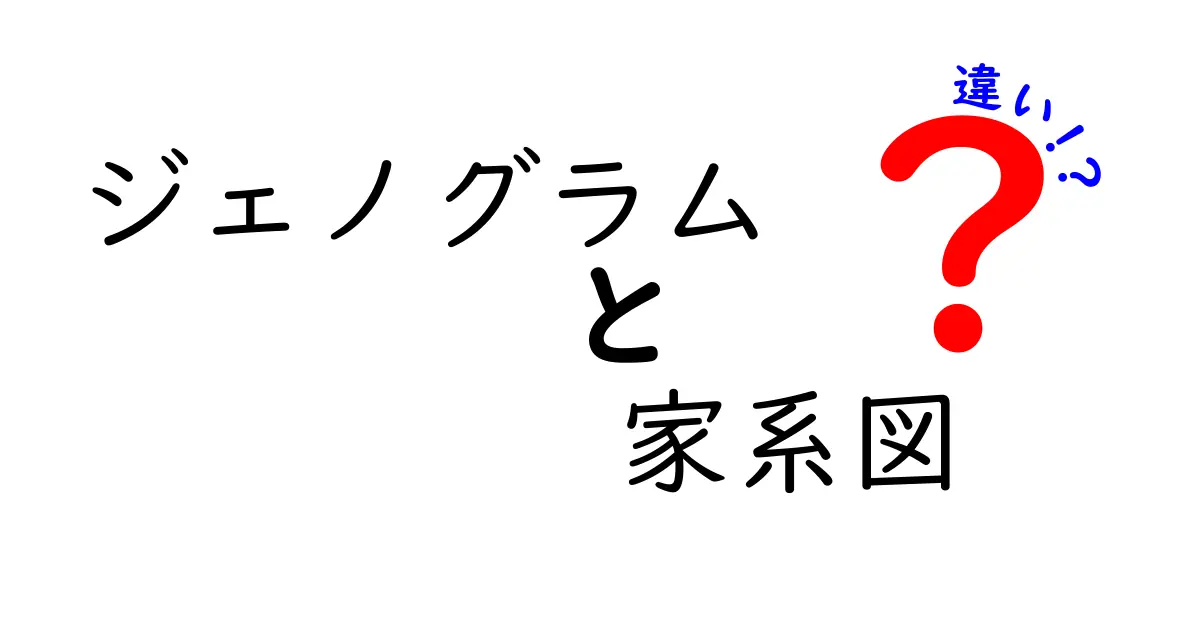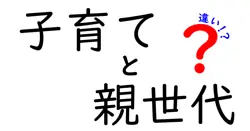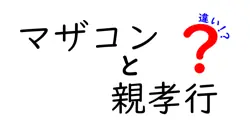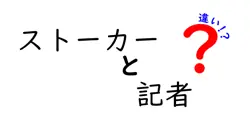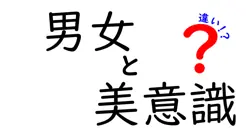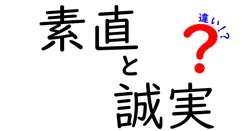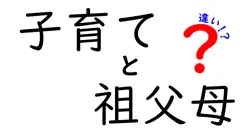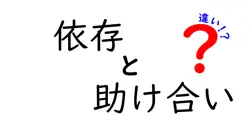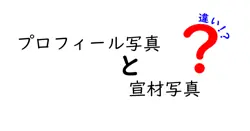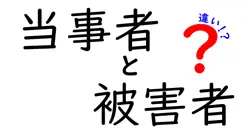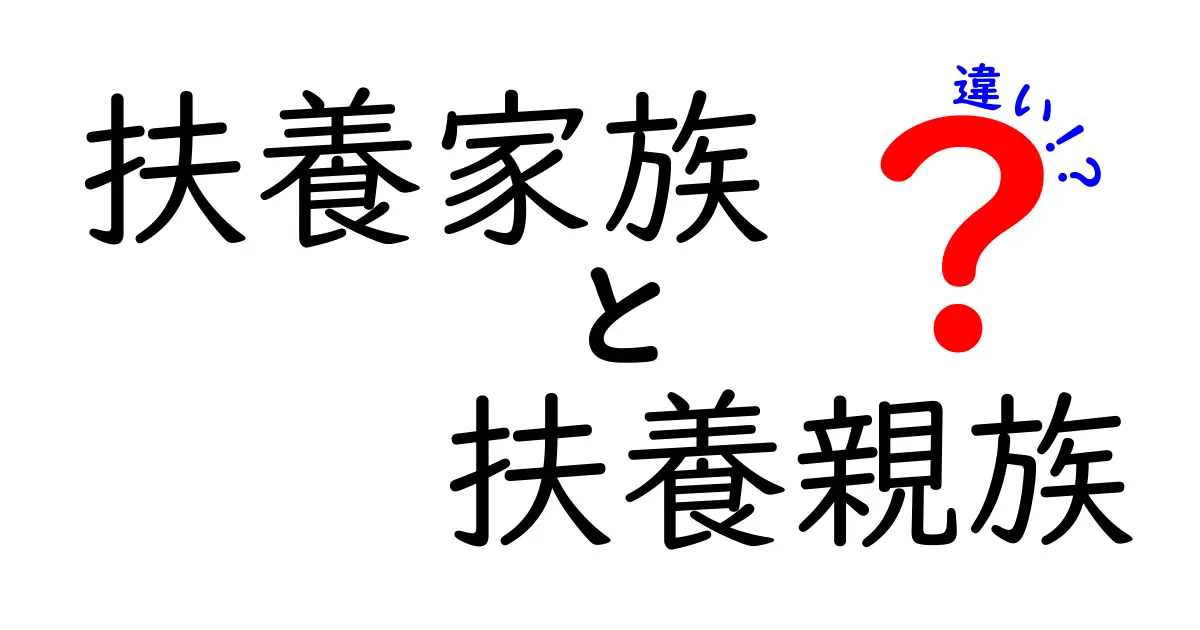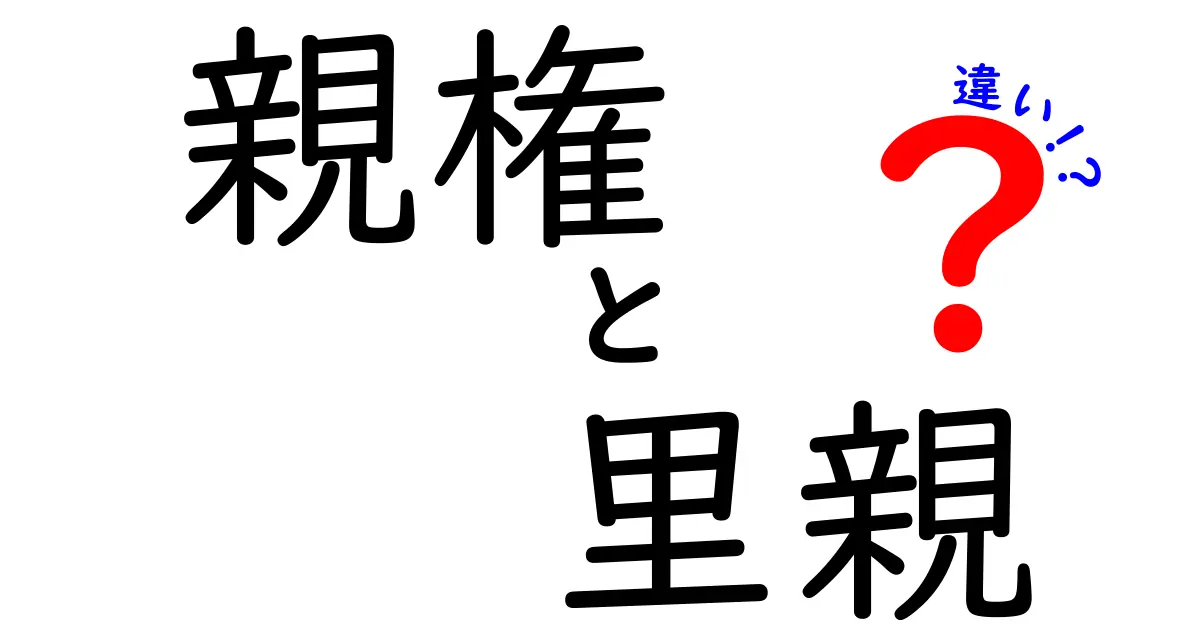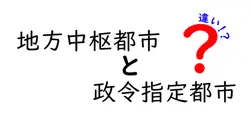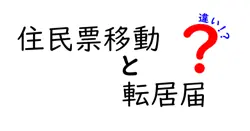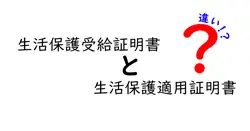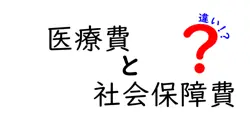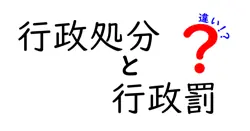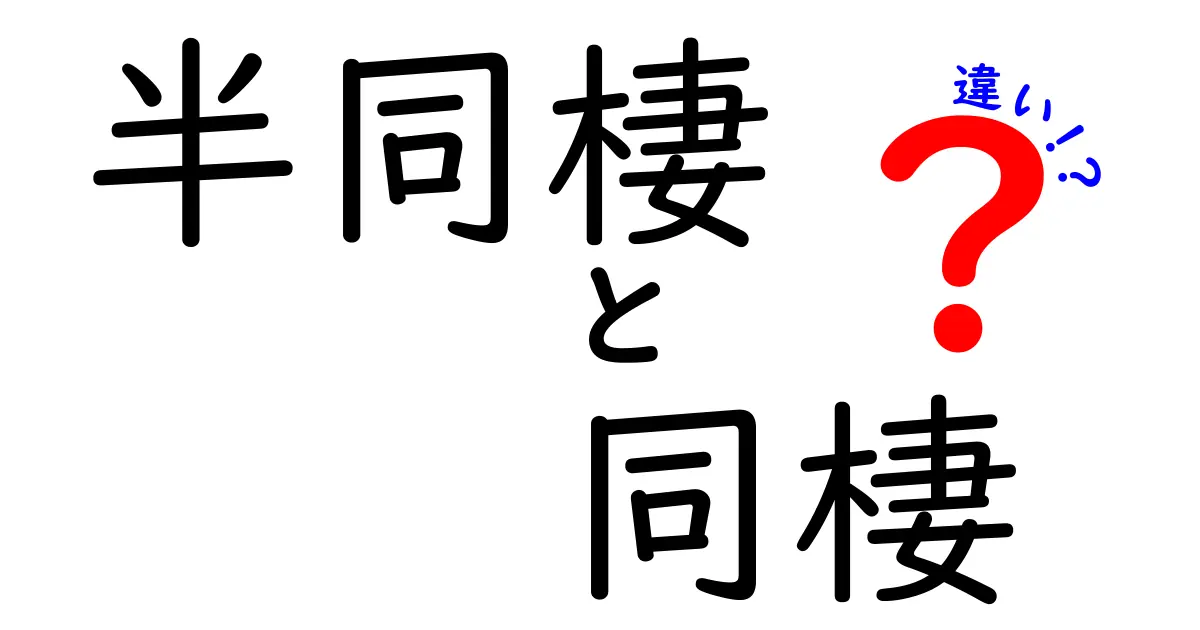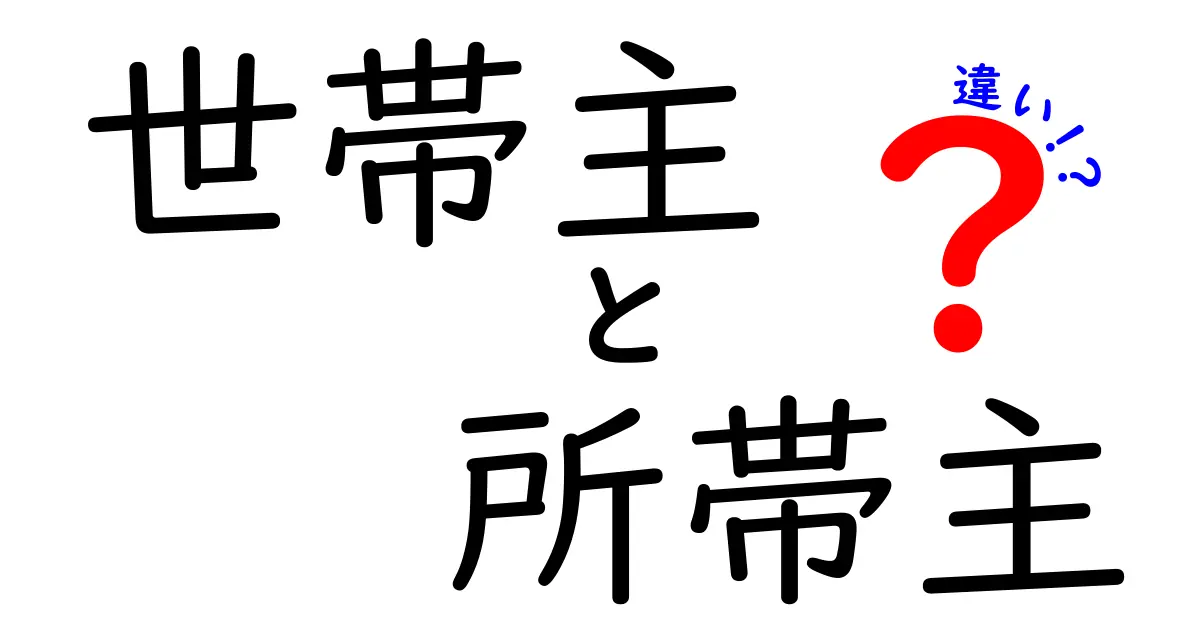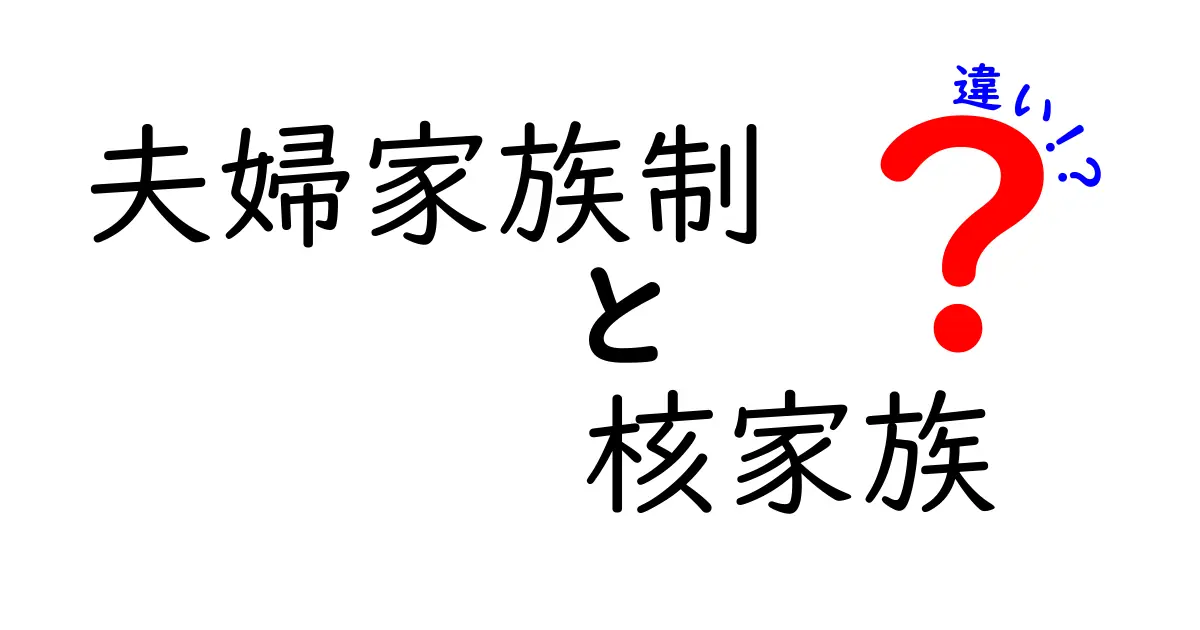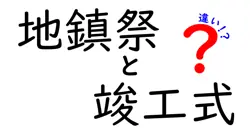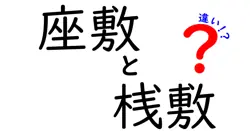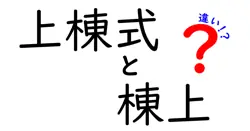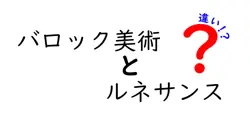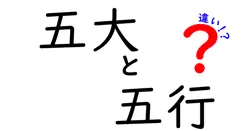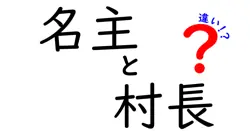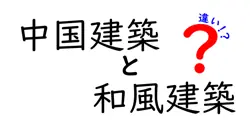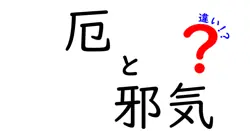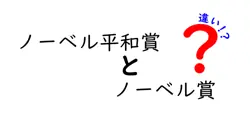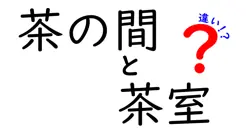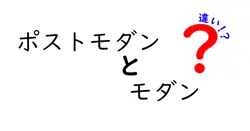半同棲と同棲の基本的な違いとは?
みなさんは「半同棲」と「同棲」という言葉を聞いたことがありますか?どちらもカップルの生活形態を表す言葉ですが、その意味や内容には大きな違いがあります。まずは基本的な違いを見ていきましょう。
同棲は、恋人同士が一緒に同じ家や部屋に住み、生活を共有することを指します。まるで結婚生活のように、一緒に住んで日々の家事や食事、時間を共に過ごします。
一方、半同棲とはお互いの家を行き来しながらも、どちらかの家に完全には住まずに生活するスタイルのことをいいます。例えば、週の半分だけお互いの家に泊まり、残りは別々に過ごすような形態です。
このように、住む場所や時間の割合が異なるのが最大の違いです。半同棲はある意味で自由が多く、同棲よりも責任や拘束感が薄いという特徴があります。
半同棲・同棲のメリット・デメリット比較
次に、それぞれの生活スタイルのメリットとデメリットを詳しく比較してみましょう。
まず同棲のメリットは、毎日の生活を共にすることで相手の価値観や習慣を深く理解できる点です。
家事や生活費の分担もでき、経済的にも効率的になることが多いです。
一方で、デメリットとしてはプライベートな時間が減ったり、生活リズムが合わない場合ストレスになることがあります。
半同棲のメリットは、適度な距離感を保ちつつ、会いたい時に会える自由な関係が築けることです。
自分の時間もしっかり確保できるので、精神的な負担が少ないです。
ただし、同じ家に住まないので、家事や生活費の分担が難しかったり、お互いの価値観の違いが見えにくい場合もあります。
ding="5">| 生活スタイル | メリット | デメリット |
|---|
| 同棲 | 相手の生活を深く理解できる
生活費や家事の分担が可能 | プライベートの時間が少ない
生活リズムの不一致でストレス |
| 半同棲 | 自由な時間が多い
適度な距離感で負担が少ない | 生活費や家事の共有が難しい
相手の本当の姿が見えにくい場合も |
able>
どちらを選ぶべき?おすすめの人や注意点
では、半同棲と同棲のどちらを選ぶのがいいのでしょうか?それぞれに合う人のタイプがあるので紹介しましょう。
同棲をおすすめする人は、将来結婚を強く考えており、日常生活を共にして相手のことをよく知りたい人です。
また、生活費の節約をしたいカップルにも向いています。
一方で、半同棲に向いている人は、仕事が忙しくてあまり家にいられない人や、自分の趣味や友人関係を大切にしたい人です。
お互いに干渉しすぎず、自由を尊重したいカップルにおすすめです。
ただし、どちらの場合も重要なのは話し合いとルール作りです。
生活スタイルや将来の展望、負担の分担についてお互いの考えをしっかり話し合いましょう。
無理をせず、お互いが納得できる形を見つけることが大切です。
ピックアップ解説「半同棲」という言葉を聞くと、なんとなく『半分だけ一緒に暮らす』イメージがありますよね。でも実際は、単に家を行き来するだけじゃなくて、お互いの自由を尊重しながら関係を続けるためのひとつのスタイルなんです。
たとえば、仕事の忙しいときは自分の家でゆっくり過ごし、週末だけ彼や彼女の家に泊まる。
これならプライベートも守れて、押し付けがましくない距離感が保てるんですよね。
半同棲は単なる住む場所の問題だけじゃなく、相手との関係性やお互いのペースを大切にする心の在り方も含まれているんです。
だから、今の若いカップルには特に注目されている形なんですよ。
の人気記事

595viws

361viws

307viws

287viws

261viws

260viws

249viws

230viws

225viws

221viws

218viws

211viws

207viws

206viws

202viws

201viws

200viws

195viws

191viws

187viws
新着記事
の関連記事
世帯主と所帯主の違いって何?基本をわかりやすく説明します
世の中には「世帯主(せたいぬし)」や「所帯主(しょたいぬし)」という言葉がよく出てきます。
しかし、両方とも似ているように感じて、「同じ意味かな?」と思う人も多いはずです。
実は「世帯主」と「所帯主」にはちゃんとした違いがあるんです。
ここでは、その違いをできるだけわかりやすく説明していきます。
まずは、それぞれの言葉の意味を見てみましょう。
世帯主とは?
「世帯主」とは、ある住まいの中で一つの世帯を代表する人のことです。
世帯とは、「一緒に住んでいる人のグループ」を指し、家族だけでなくルームシェアなどのグループも含みます。
役所や行政の書類では、「世帯主」は世帯の中心的な存在を指し、多くは生活費をまとめたり、住民票に名前が記載されたりします。
所帯主とは?
「所帯主」というのは、ほとんどの場合「世帯主」と同じ意味で使われています。
ただし、正式な行政用語としてはあまり使われないことが多いです。
所帯主は「所帯=世帯」を束ねる人という意味ですが、現代の公的な場面では「世帯主」が一般的です。
つまり、所帯主は古い表現や口語的な言い方として残っている場合があります。
世帯主と所帯主の違いを表で整理してみる
文章だけだとわかりにくいので、簡単に比較できるように表にまとめました。
able border="1">| 項目 | 世帯主 | 所帯主 |
|---|
| 意味 | 住んでいる世帯の代表者 | 世帯の代表者(同じ意味で使われることが多い) |
| 使われる場面 | 公的書類や行政手続きなどで正式に使用 | 日常会話や古い文章で使われることが多い |
| 正式な用語か? | はい | いいえ(または非正式) |
| 例 | 住民票の世帯主欄に記載される人 | 祖父母の古い日記や話の中で使われることがある |
なぜ違う言葉があるのか?
「世帯主」は法的にも使われる基準化された言葉で、
「所帯主」は昭和前半まで一般的に使われていた古い言葉や、
口語として残っている言葉です。
地方や年代によってはどちらも使われていますが、正式に意味を区別すると上の通りです。
まとめ:世帯主と所帯主は似ているが正式な違いがある
ここまでの説明でわかるように、
「世帯主」は公式で使われる公的な言葉、
「所帯主」はほとんど同じ意味だが、古い表現・口語的な表現であるということです。
つまり、役所で使う場合や書類を書くときは、必ず「世帯主」という言葉を使いましょう。
日常会話で「所帯主」と言っても意味はわかってもらえますが、時と場合によって言い方を変えるのが良いです。
少し言葉の歴史を知ると、暮らしの中の様々な表現の違いにも気づけて楽しいですよね。
ピックアップ解説「世帯主」という言葉をもう少し掘り下げると、実は単に『一緒に住んでいる代表者』というだけでなく、税金や福祉の対象にも大きな関わりがある点が面白いんです。たとえば、世帯主の収入でその世帯の課税状況が決まったり、児童手当や医療費控除を申請するときに代表の名前が必要になったりします。だから、世帯主は書類上だけでなく、行政サービスを受けるうえでも重要な役割を持っています。こうした仕組みを知ると、普段何気なく見ている住民票や申請書もぐっと身近に感じられますよね。
ビジネスの人気記事

287viws

249viws

218viws

206viws

202viws

201viws

200viws

195viws

187viws

181viws

177viws

172viws

170viws

159viws

152viws

151viws

144viws

144viws

143viws

141viws
新着記事
ビジネスの関連記事