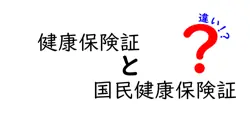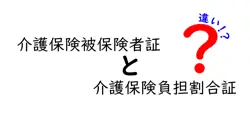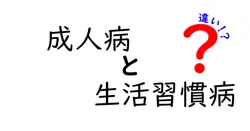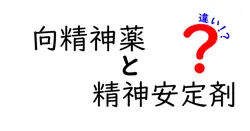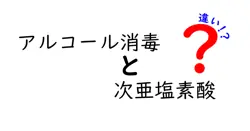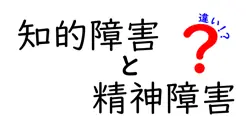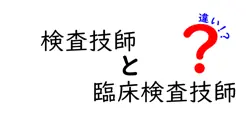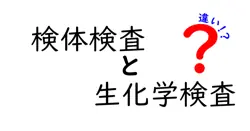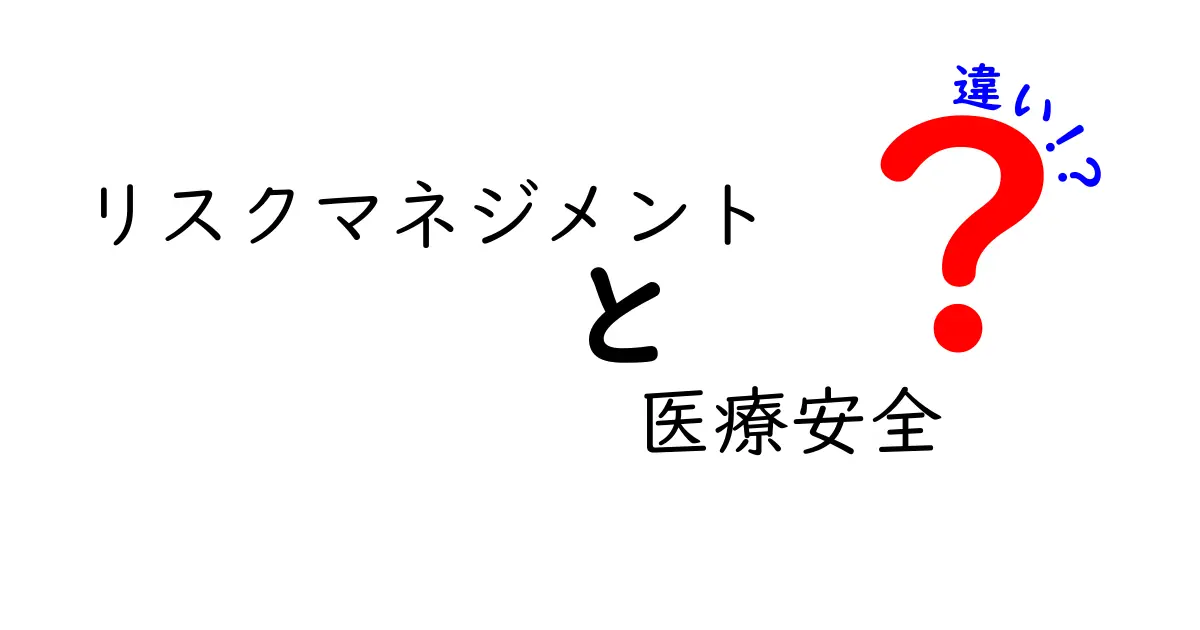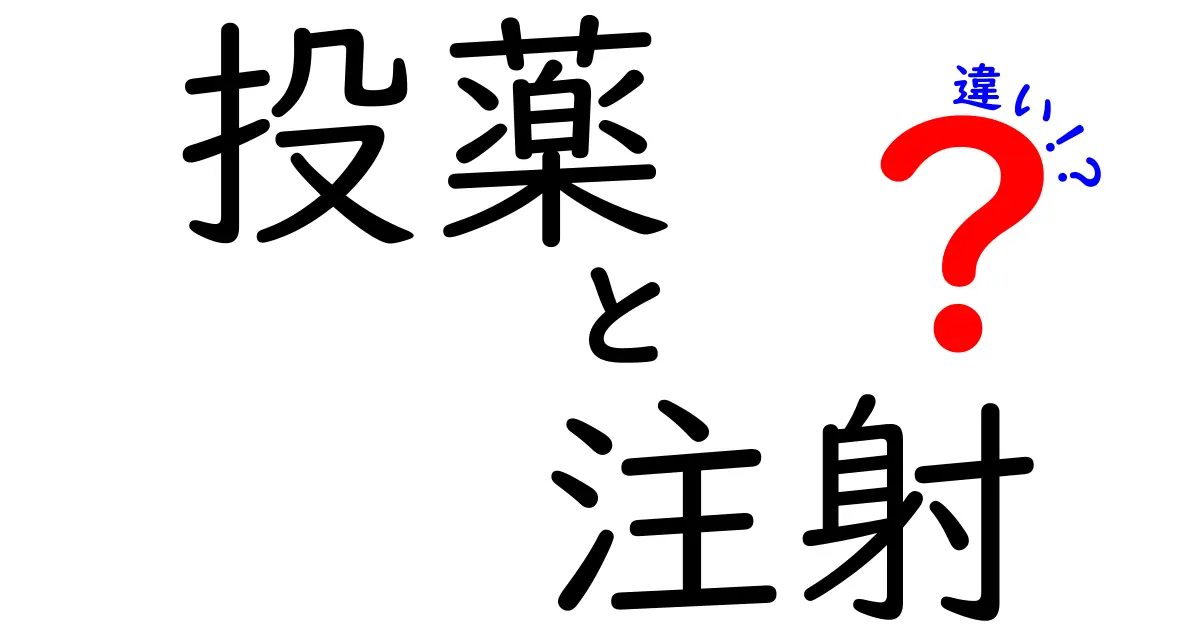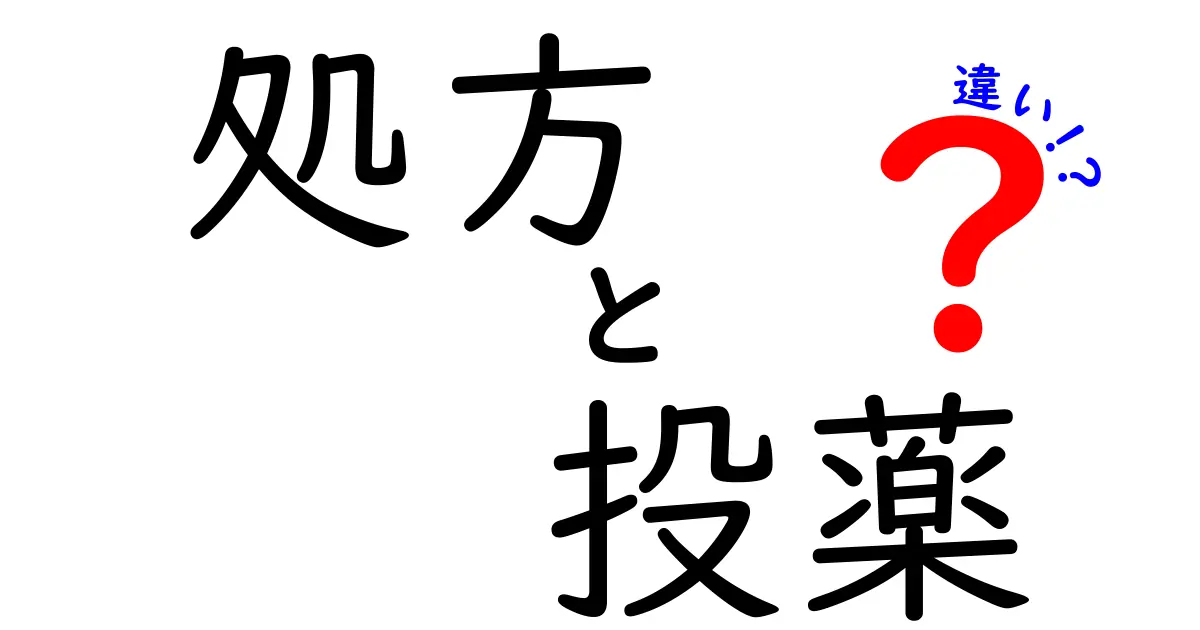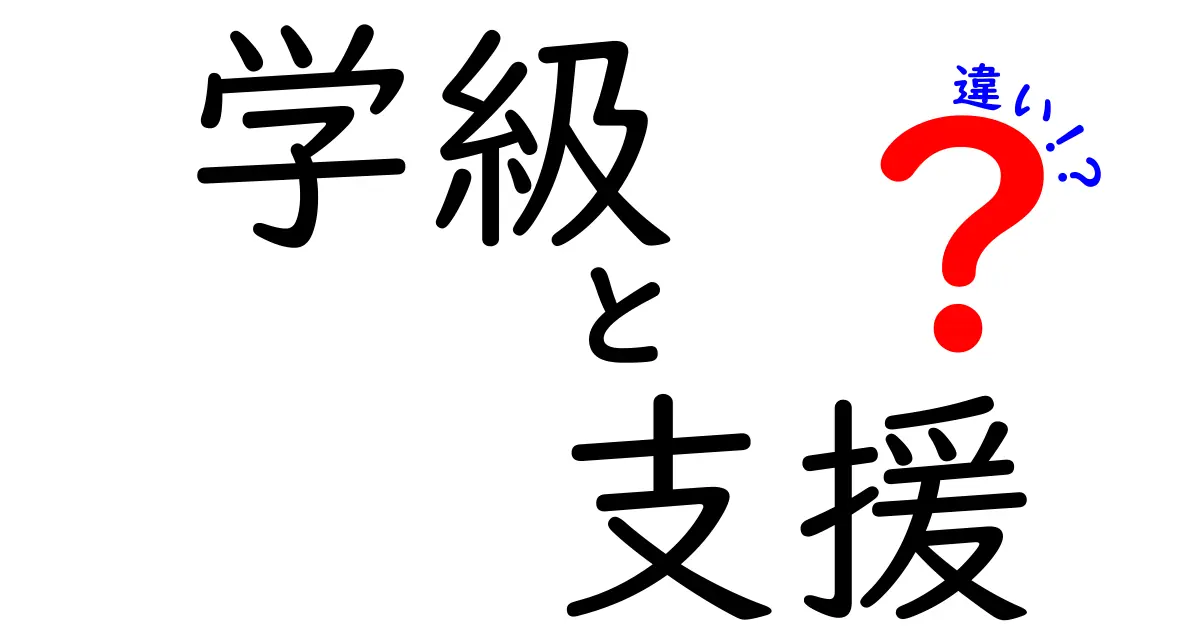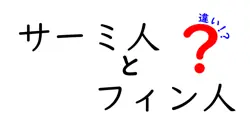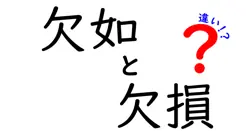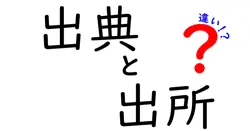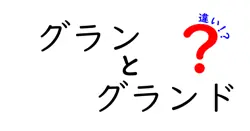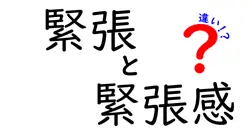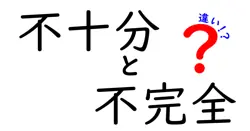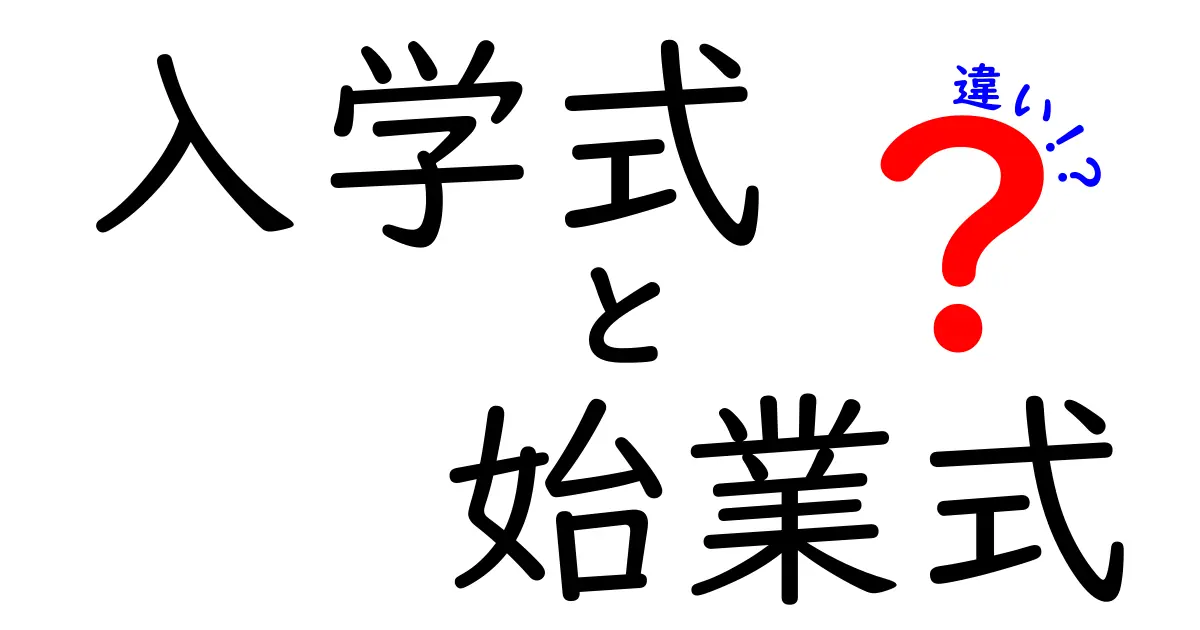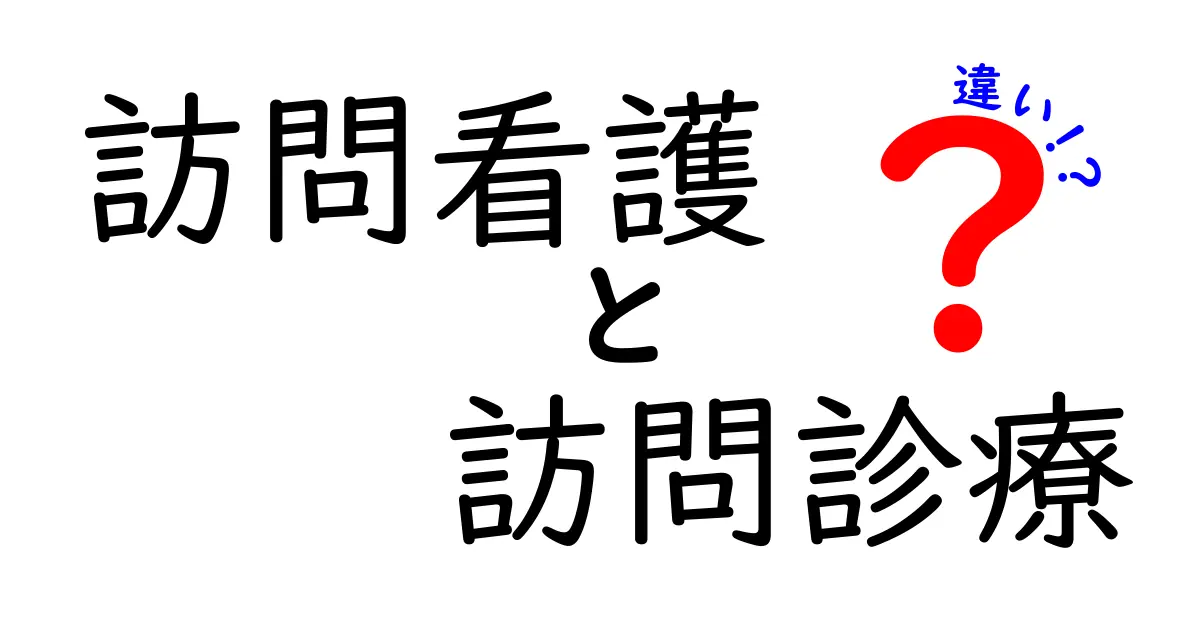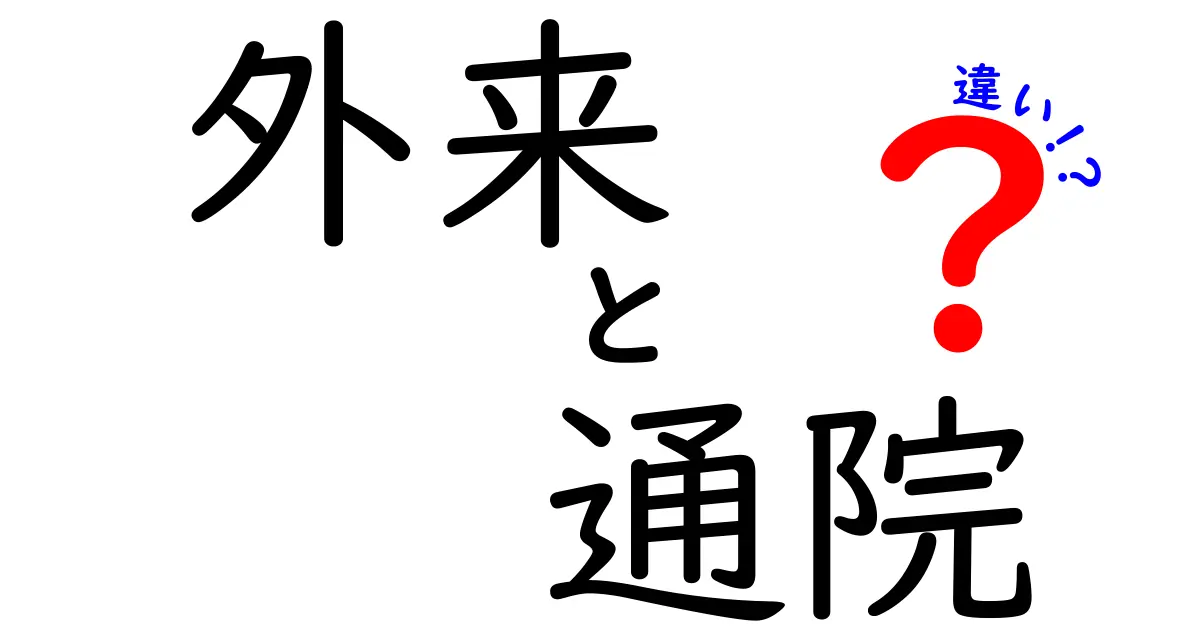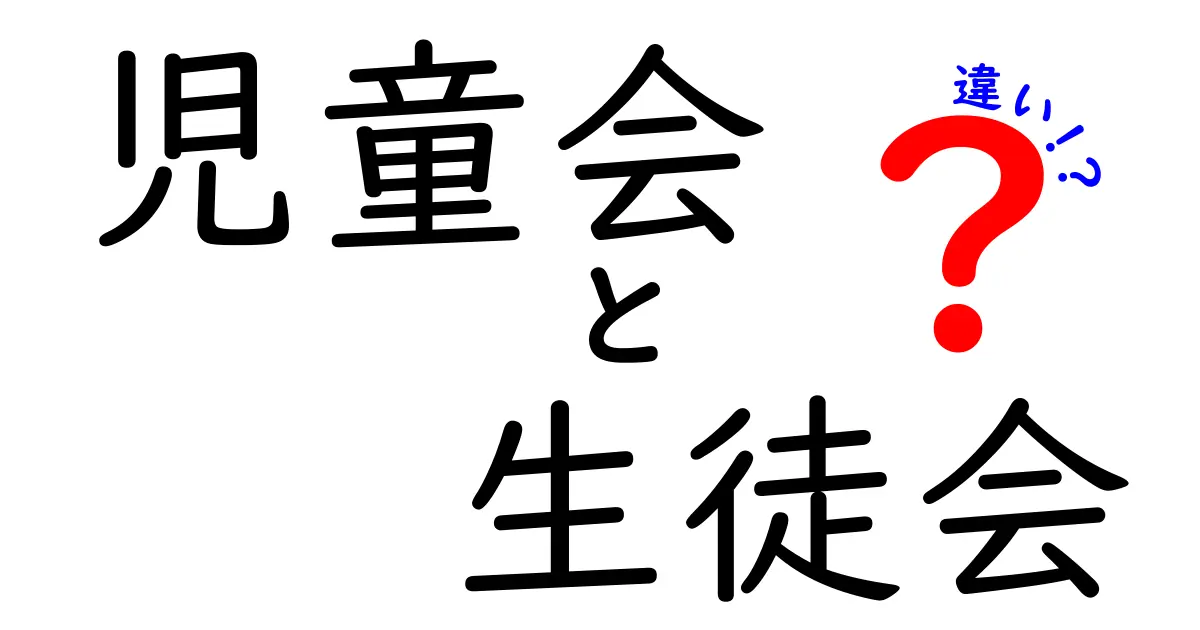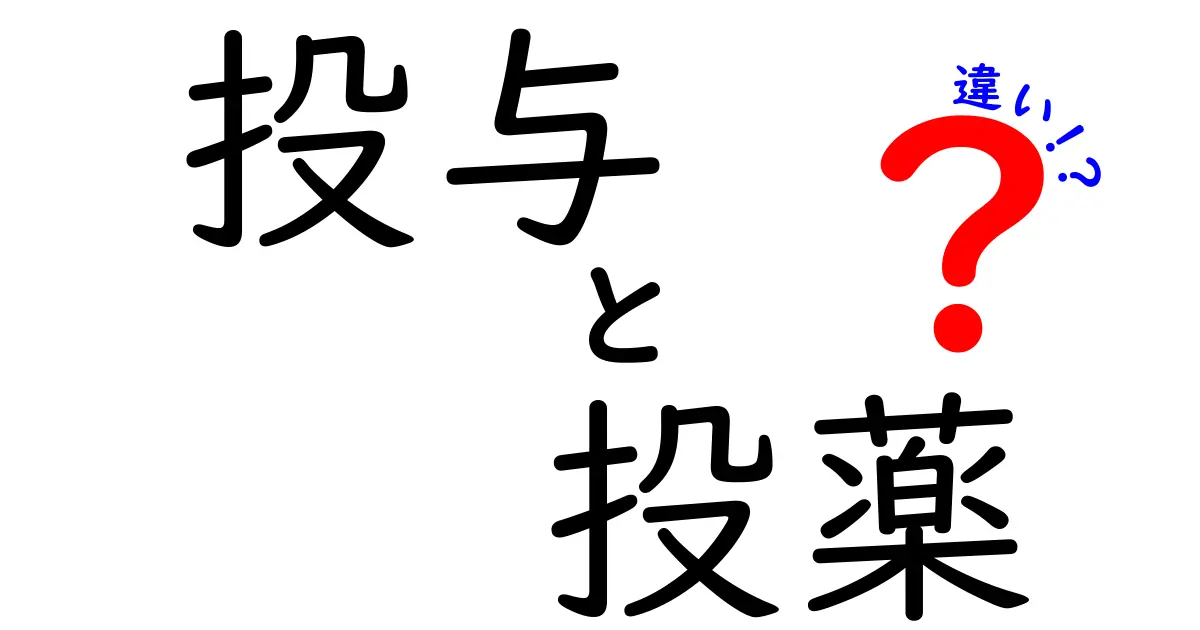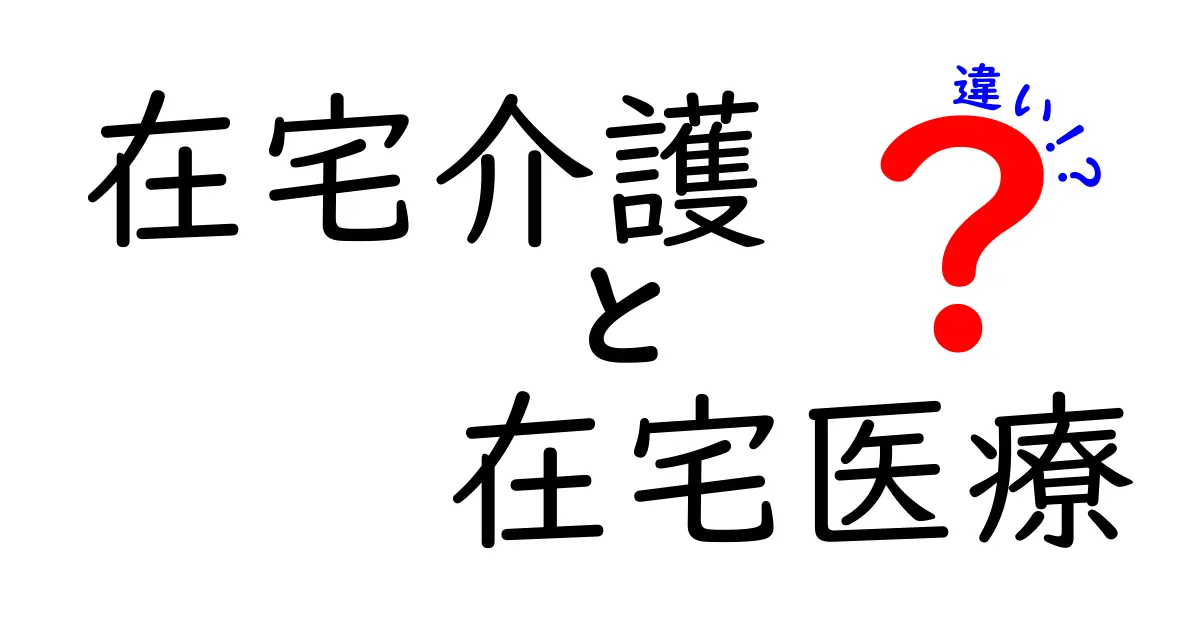
在宅介護と在宅医療の違いについて知ろう
日常生活で耳にすることの多い「在宅介護」と「在宅医療」。似ている言葉ですが、実際には役割や内容に大きな違いがあります。在宅介護は、主に介護が必要な人が自宅で安心して暮らせるようにサポートするサービスです。一方、在宅医療は医療的な処置や診察を自宅で受けることを指します。この記事では、両者の違いやどんな人に必要なのか、具体的にどんなことが行われるのかを詳しく解説していきます。
理解することで、もしもの時に適切な支援を受けやすくなります。ぜひ参考にしてください。
在宅介護とは?その役割と特徴
在宅介護は、高齢者や障がいを持つ人が自宅で日常生活を送るのを支えるサービスです。具体的には、食事の準備や掃除、洗濯、買い物、入浴の手伝いなど日常の生活全般をサポートします。専門の介護スタッフや家族が行うことが多いです。
特徴としては「身体的な介助」だけでなく、利用者の心のケアや生活環境の整備も含まれることが多く、一人ひとりの状況に合わせたサービス計画が立てられます。要介護認定を受けている人が利用しやすい制度です。
在宅医療とは?医療面でのサポート内容
在宅医療とは、病院に通うことが難しい人が自宅で医師や看護師から医療サービスを受けることを言います。例えば、定期的な診察、薬の管理、点滴や注射、床ずれの予防や治療、リハビリテーションなど、医療的な処置を自宅で行います。
病気の再発防止や症状の悪化を防ぐことが目的であり、医療専門職が関わるため医療の専門知識が必要です。緊急時には病院への連携もスムーズに行われます。
在宅介護と在宅医療の違いを表で比較
| 項目 | 在宅介護 | 在宅医療 |
|---|---|---|
| 目的 | 日常生活のサポート 快適な生活環境づくり | 病気や症状の治療 医療的ケア |
| 主な担当者 | 介護職員、ヘルパー、家族 | 医師、看護師、リハビリ専門職 |
| サービス内容 | 食事介助、掃除、入浴支援、外出支援など | 診察、投薬管理、点滴、傷の手当てなど |
| 対象者 | 要介護認定を受けた高齢者や障がい者 | 慢性疾患や重い病気の患者 |
| ポイント | リスクマネジメント | 医療安全 |
| 目的 | あらゆるリスクを管理し防止すること | 患者への安全な医療を提供すること |
| 主な対象 | 医療現場全体のリスク全般 | 患者の安全に関わるリスク |
| 具体的な例 | トラブル予防のルール作りや研修 | 医療ミスの防止、感染症対策 |
| 活動の範囲 | 幅広いリスクを含む | 患者安全に特化 |
このようにリスクマネジメントは医療安全も含めた大きな枠組みであり、医療安全はその中の重要な分野だと覚えておくとわかりやすいでしょう。
「医療安全」という言葉を聞くと、単にミスを防ぐことだけを想像しがちですが、実はそれ以上の意味があります。たとえば、患者さんが手術前に正しい部位をしっかり確認するようなプロセスも医療安全の一部です。こうした細かな確認作業が、実は医療ミスを大幅に減らしているんですね。中学生のみなさんも、テスト前の見直しやチェックをしっかりすることで、ミスを減らせるのと似ています。身近な行動との共通点を意識すると、医療安全の大切さがもっと理解しやすくなりますよ。
前の記事: « 投薬と注射の違いを徹底解説!知っておきたいポイントとは?