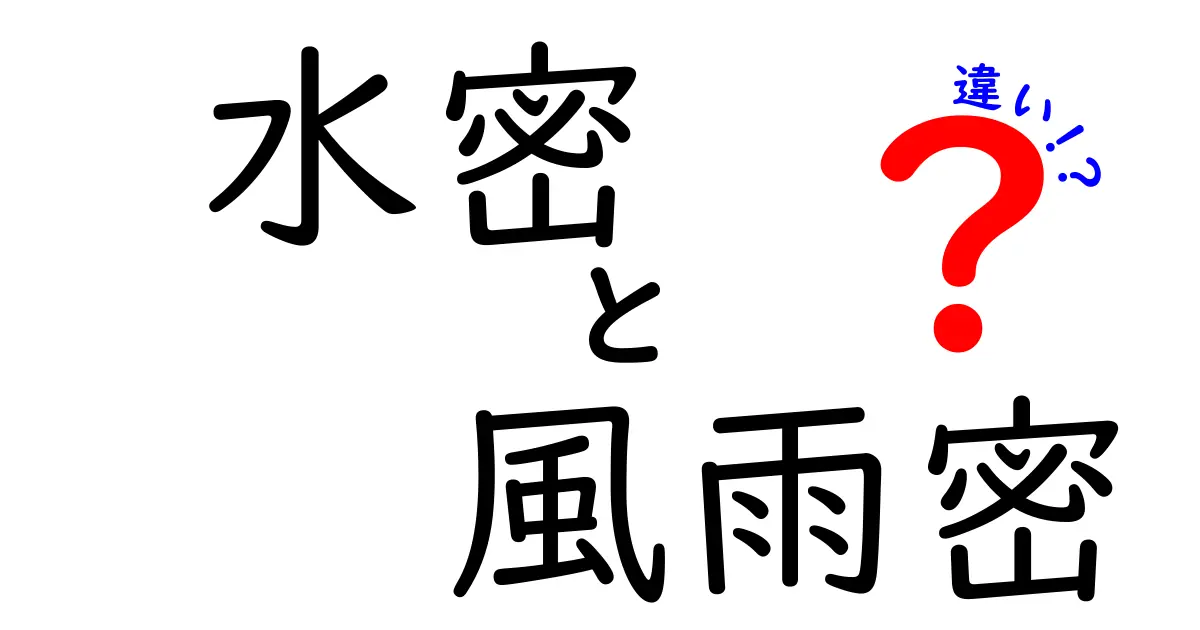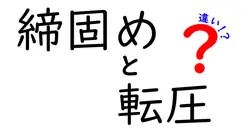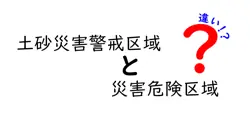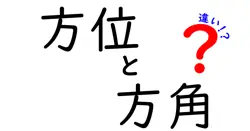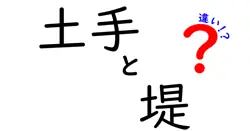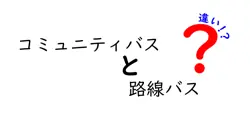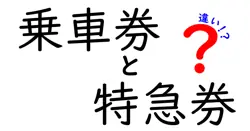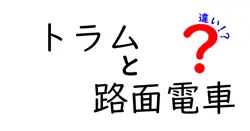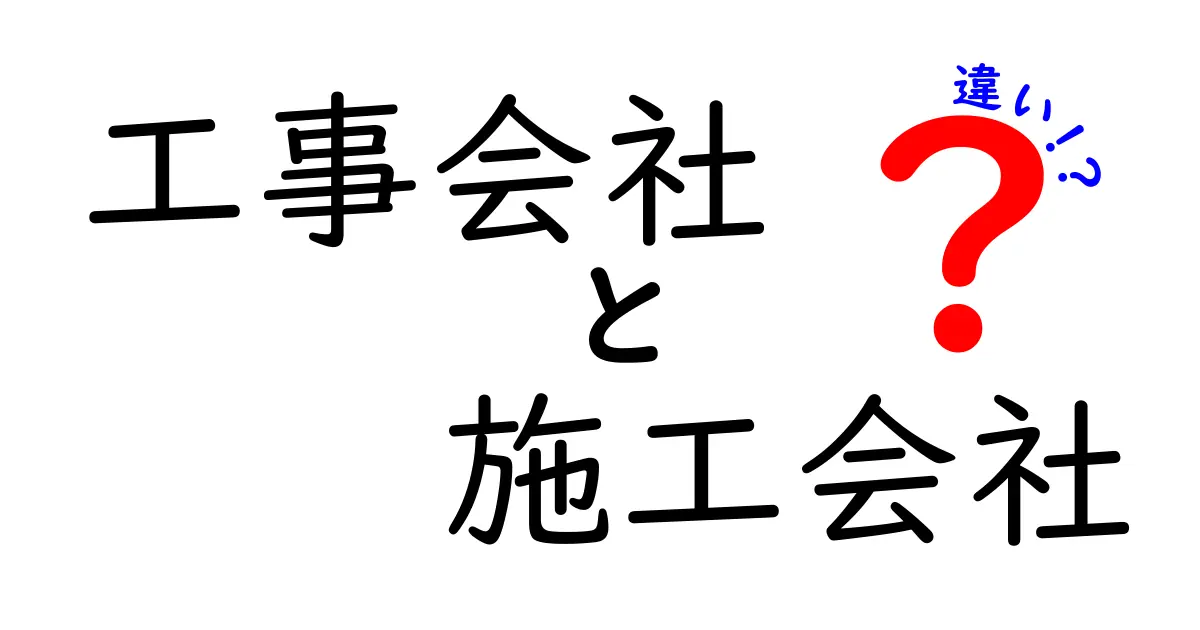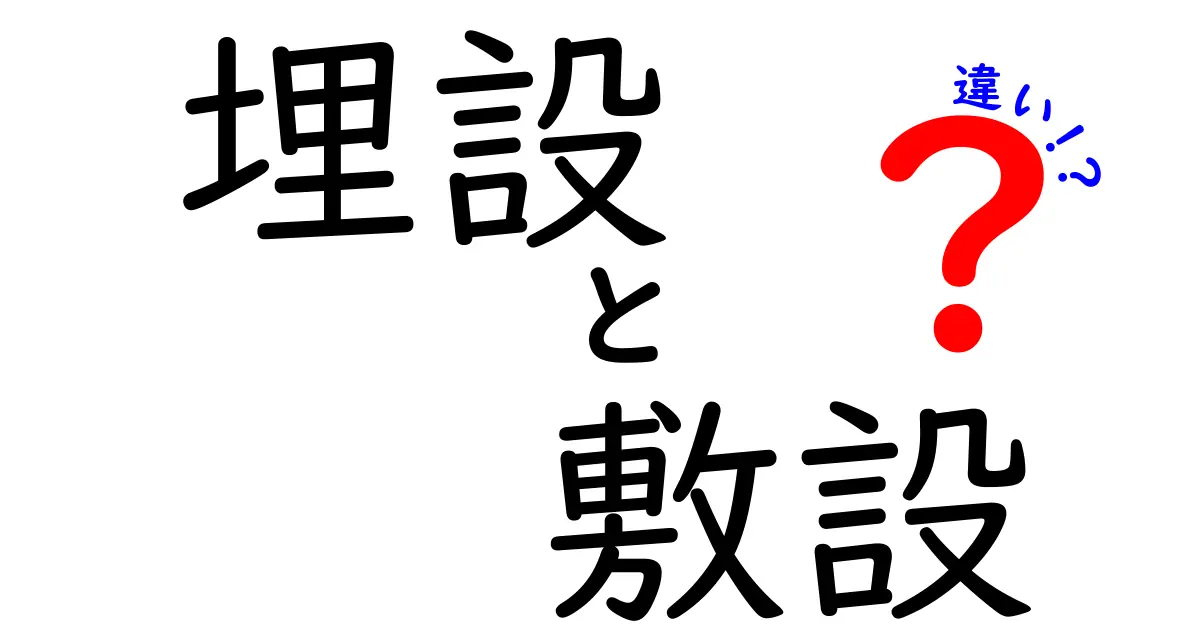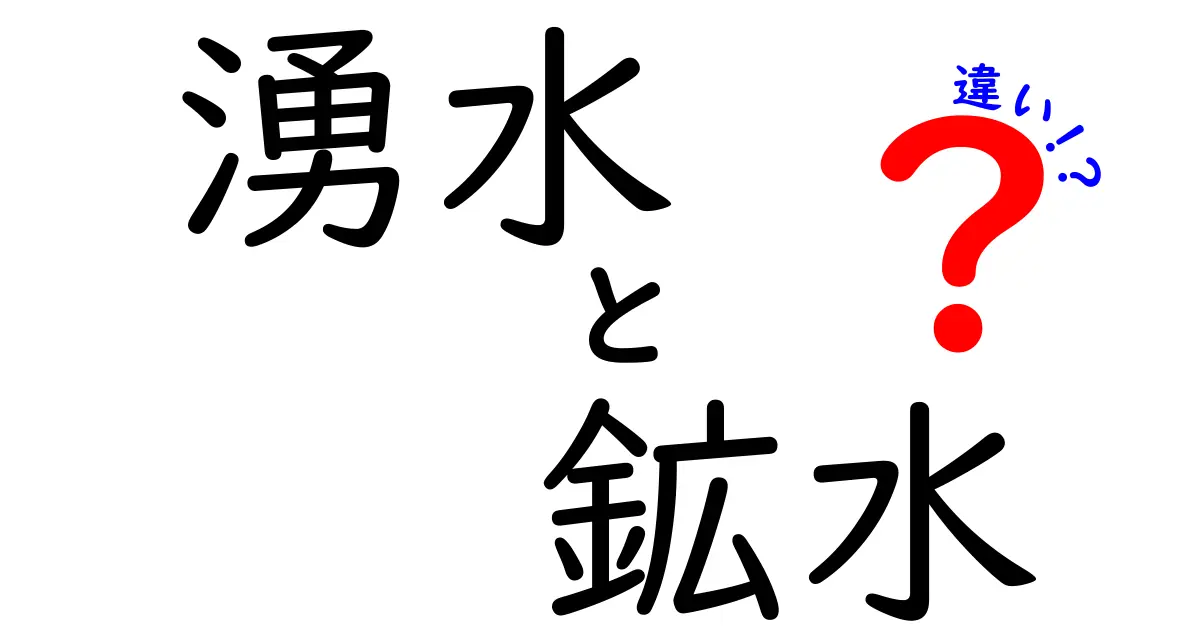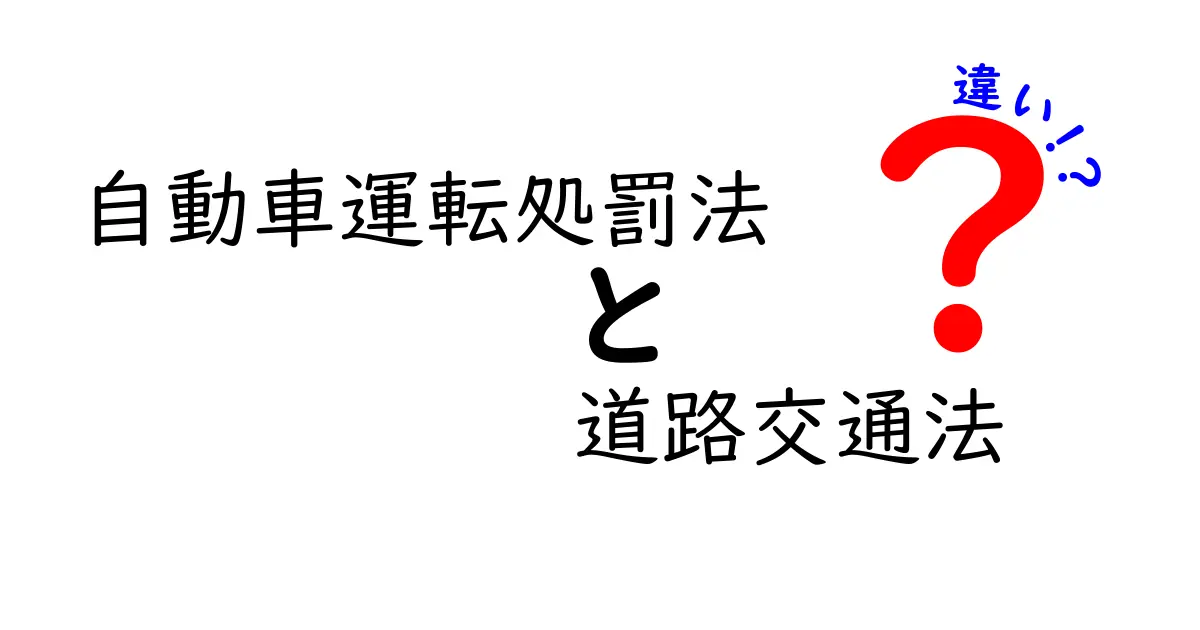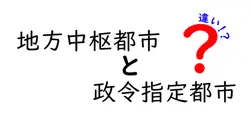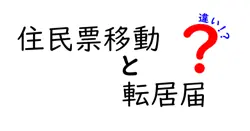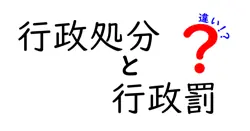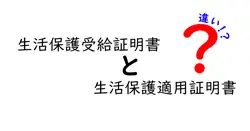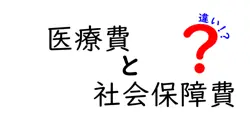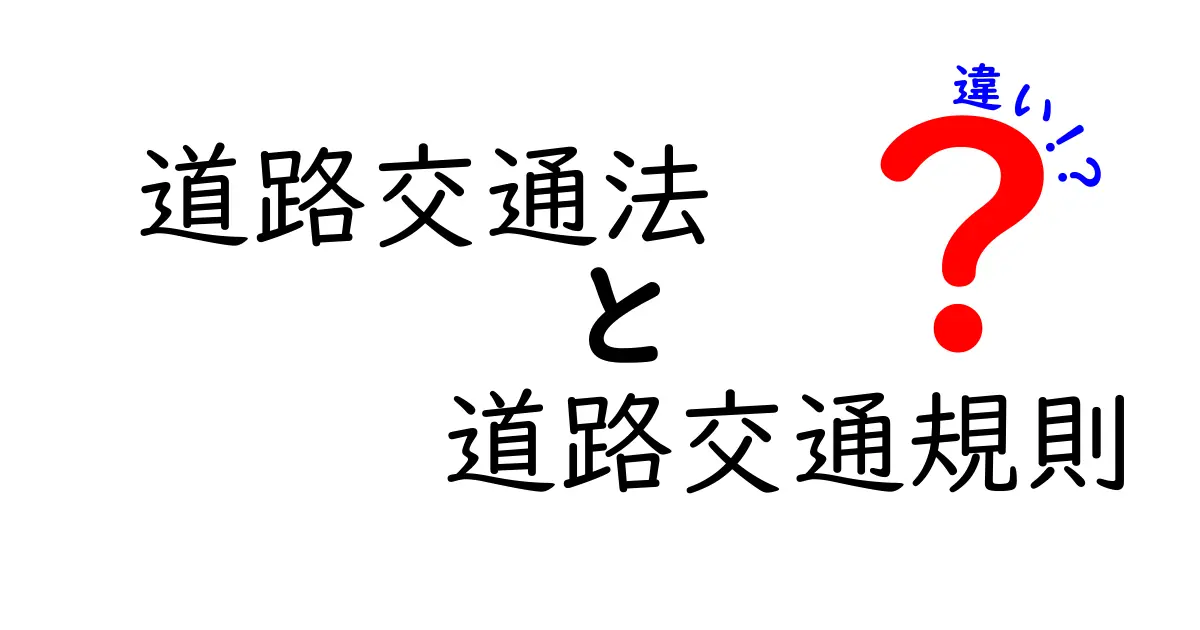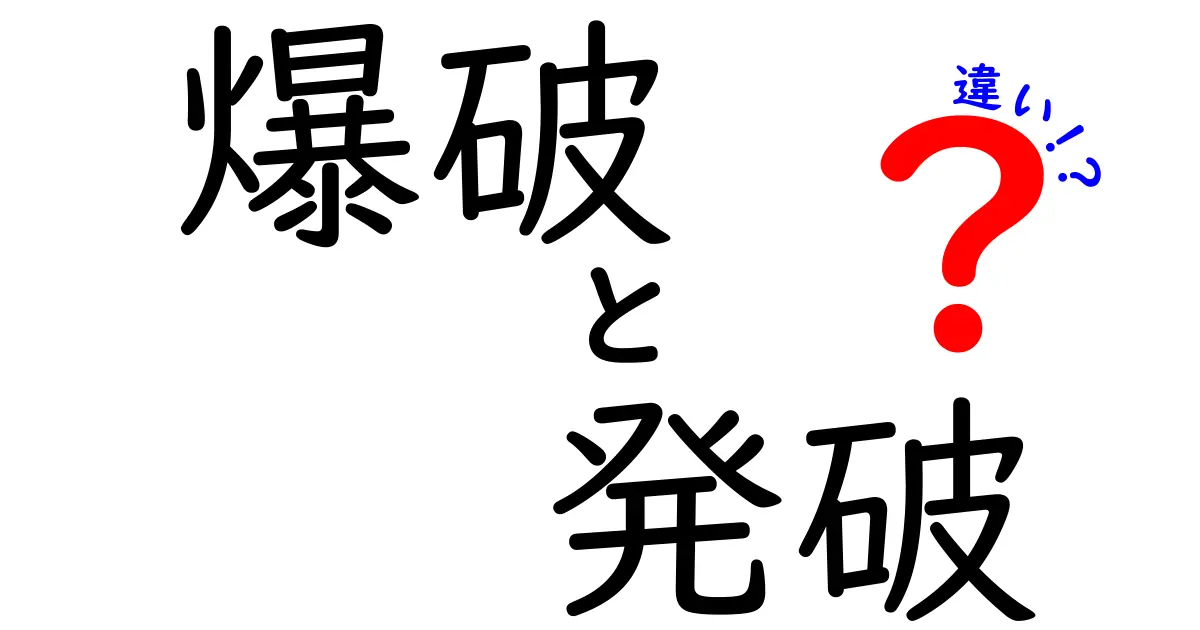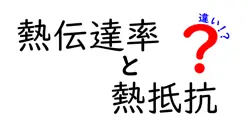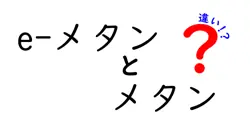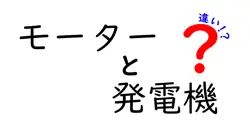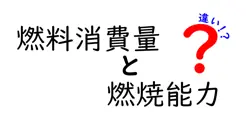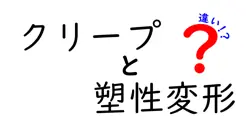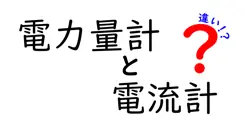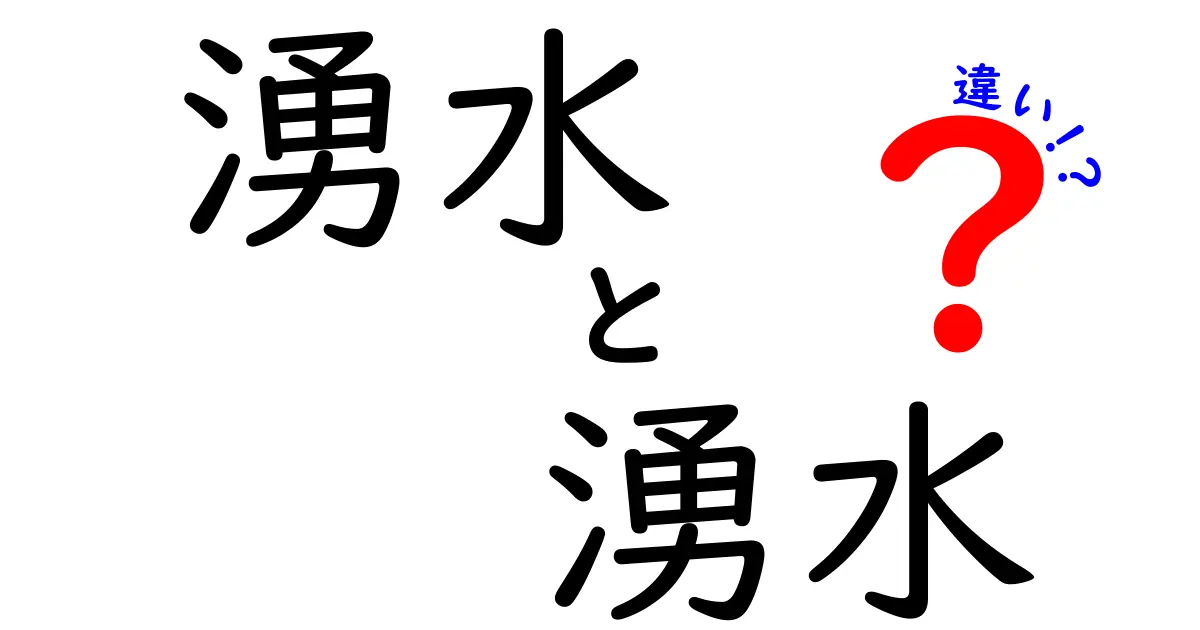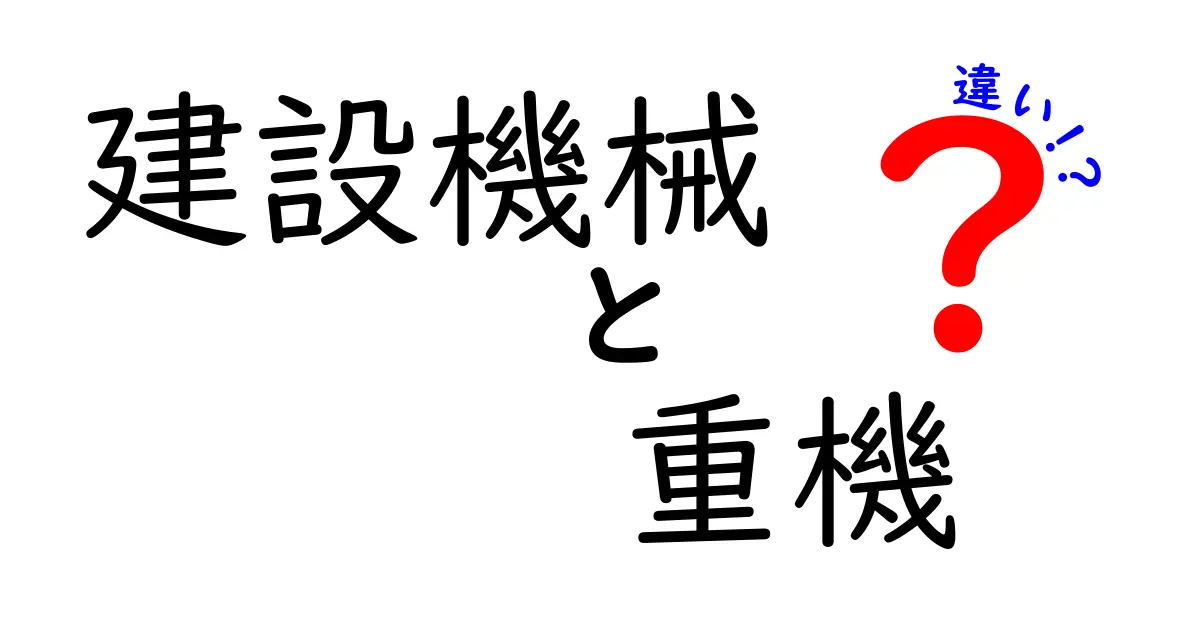
建設機械と重機の違いを理解しよう
建設現場でよく耳にする「建設機械」と「重機」という言葉。この二つは似ているようで実は意味が違うことをご存じですか?両者はよく混同されがちですが、対象になる機械の範囲や使われ方に違いがあります。ここではその違いを中学生にもわかりやすく解説していきます。
まず、建設機械とは建設工事に使われるさまざまな機械の総称です。例えば、掘削機(ショベルカー)、ブルドーザー、クレーン、コンクリートポンプ車などがあります。これらはすべて建物や道路などの建設作業をサポートする機械です。
一方、重機とは主に大型で重量があり、力の強い建設機械のことを指します。つまり、建設機械の中でも特に大きなものや重いものを重機と呼ぶのです。重機は土砂を掘ったり、運んだり、物を持ち上げたりする作業に使われます。
このように、建設機械は種類が幅広く、重機はその中の大型機械にあたる、とイメージするとわかりやすいでしょう。
建設機械と重機の違いを具体的に比較してみよう
より理解を深めるために、建設機械と重機の特徴と例を比較してみましょう。
| 種類 | 特徴 | 代表例 | |
|---|---|---|---|
| 建設機械 | 工事に使う機械全般で小型から大型まで幅広い 種類が存在 | ショベルカー、ミニバックホー、コンクリートミキサー車、クレーンなど | |
| 重機 | 重量が大きく、強力なエンジンを持つ大型建設機械 主に土工事に使う | 油圧ショベル(パワーショベル)、ブルドーザー、油圧クレーン、ロードローラーなど |
| 性能名 | 意味 | 主なチェック項目 | 使用場所の目安 |
|---|---|---|---|
| 水密性能 | 単に水の侵入を防ぐ性能 | 水が浸入しないかテスト | 屋内側、シャワールームの窓など |
| 風雨密性能 | 強風の中での雨の侵入を防ぐ性能 | 風圧試験、噴霧試験を含む | 屋外、強風の吹く地域や雨が強い場所 |
このように、用途や環境に応じて適切な性能を選ぶことが大切です。
水密が備わっていても、風雨密性能が低ければ大雨や台風では侵入が起きることもあるので注意しましょう。
まとめ:水密と風雨密はどちらも重要な防水性能です
今回は水密と風雨密の違いについて詳しく解説しました。
簡単に言うと、水密は静かな水の侵入防止で、風雨密は強風でも雨水が入り込まない耐性です。
建物の窓やドア選びでは、この二つの性能をよく理解しておくことで、より質の高い防水・耐候性能を得ることができます。
ぜひ今回の記事を参考に、住まいの防水性能について考えてみてくださいね。
最後に、風雨密性能を示す数値はJIS規格や建築基準法にも関係しますので、専門家に相談して最適なものを選ぶのもおすすめです。
「風雨密」という言葉、実はちょっと面白いんです。普通の「水密」は水が入らないだけですが、風雨密は『風と雨が一緒になった時の強さ』に耐える性能なんです。例えば、台風のような強風の中では、雨はただ落ちてくるわけじゃなく、風に乗って横から窓やドアに吹き付けます。こうなると普通の水密性能だけでは防ぎきれないことがあるんですよね。だから風雨密は特に風が強い地域で重要視されます。思いのほか風の影響って大きいんだな、と知っておくと防災にも役立ちますよ!
前の記事: « メトロと地下鉄の違いって何?わかりやすく解説します!
次の記事: 建設機械と重機の違いとは?初心者でもわかる基本ポイント解説! »
自然の人気記事
新着記事
自然の関連記事
メトロと地下鉄の違いって何?わかりやすく解説します!

メトロと地下鉄はどう違うの?基本を押さえよう!
日本でよく使われる言葉に「メトロ」と「地下鉄」があります。どちらも都市の交通手段でよく目にしますが、同じように見えて実は少し違いがあるんです。まずは簡単に言うと、「地下鉄」は地下を走る鉄道そのものを指す言葉で、地下の路線網全体を指します。一方、「メトロ」はフランス語の「métropolitain(メトロポリタン)」の略で、都市の地下鉄路線や運営会社の名前として使われています。
だから、「メトロ」は具体的な地下鉄のブランド名や会社名として使われることが多く、「地下鉄」はもっと広い意味の交通手段の呼び方です。
例えば東京メトロは東京にある地下鉄の会社名であり、路線の総称にも使われています。でも他にも「都営地下鉄」や「大阪市営地下鉄」など別の運営会社もあるため、単に「地下鉄」と言うと地下を走る鉄道全体を指すのが普通なんですよ。
メトロと地下鉄の違いをわかりやすく表で比較!
どうしてメトロと地下鉄が混ざって使われるの?
日本では地下鉄の呼び方が地域や会社ごとに異なり、それが理由で「メトロ」と「地下鉄」が混ざって使われることが多いです。例えば大阪では2020年に「大阪市営地下鉄」から「大阪メトロ」に名称変更しました。つまり、運営会社名として「メトロ」を使うことでブランドイメージを変えたり、親しみやすさを狙ったわけです。
でも多くの人は「地下鉄」という言葉で地下を走る電車全体を指すので、普段の会話ではどちらもほぼ同じ意味で使っていることが多いんですね。
このように「メトロ」はブランド名や愛称的な役割も持っているため、状況によっては「地下鉄」よりもカッコよく聞こえることもあります。だから広告や宣伝などでは「メトロ」という言葉が多用されるのです。
まとめ:メトロと地下鉄の違いを覚えよう!
ここまでを簡単にまとめると、
- 地下鉄は「地下を走る鉄道全般」の意味で、鉄道路線の総称
- メトロはフランス語由来の言葉で、都市の地下鉄を指す具体的なブランド名や運営会社名によく使われる
- 地域や会社によって呼び方が違い、日常会話ではほぼ同じ意味で使われている場合も多い
だからもし誰かが「メトロ」と言ったら、それは単にその都市の地下鉄を指していると思って大丈夫です。
ちょっとした違いはありますが、使い分けに困ったら「地下鉄=地下を走る電車全体」「メトロ=特定の地下鉄ブランドや会社名」と覚えておくと便利ですよ。
今回の記事が、普段の暮らしの中でよく聞く言葉の意味の違いを理解する助けになれば嬉しいです!
「メトロ」という言葉はフランス語の「métropolitain」から来ているんですが、実はこの言葉、元々「大都市の」という意味なんです。そう考えると、地下鉄の名前として使われているのも納得ですよね。日本の「東京メトロ」や「大阪メトロ」など、都市の地下交通のブランド名になるのは、その都市の“大都市”としてのイメージを意識しているからです。地下鉄自体はどの都市にもありますが、「メトロ」と呼ぶことで何だか都会的でカッコいい響きになっているんですよ。こんな小さな言葉の背景を知ると、普段の通学や通勤も少し面白く感じるかもしれませんね!
次の記事: 水密と風雨密の違いとは?防水性能の基礎からわかりやすく解説 »