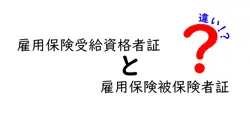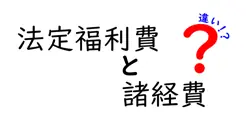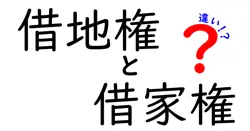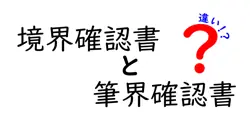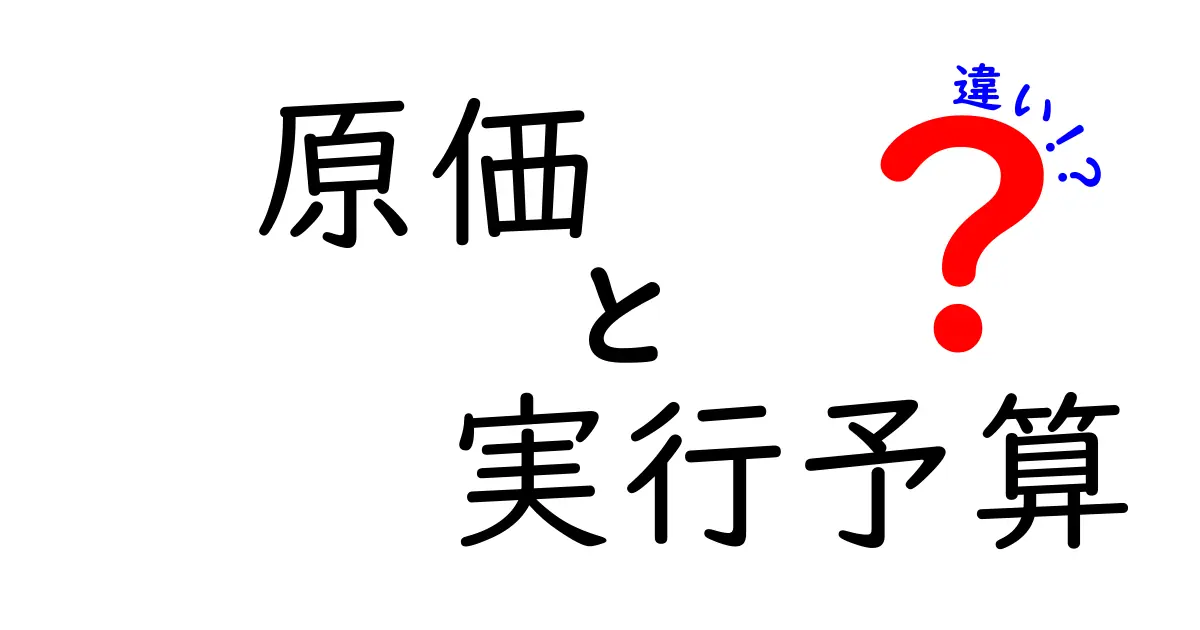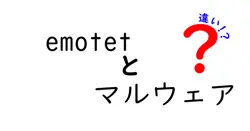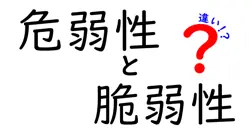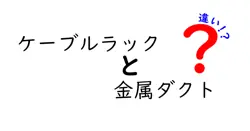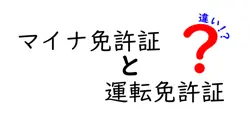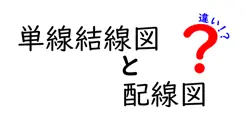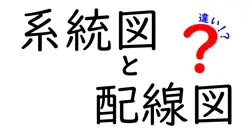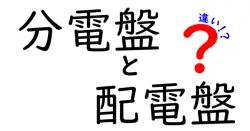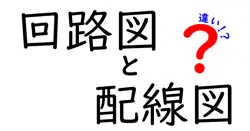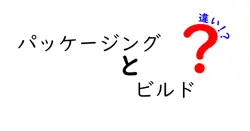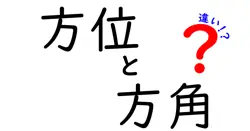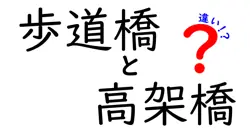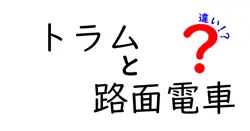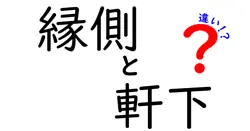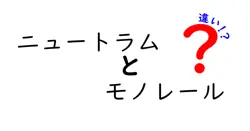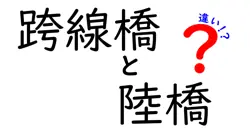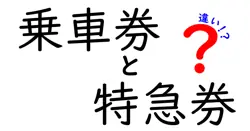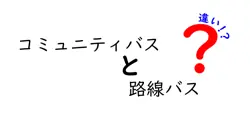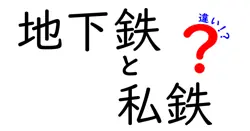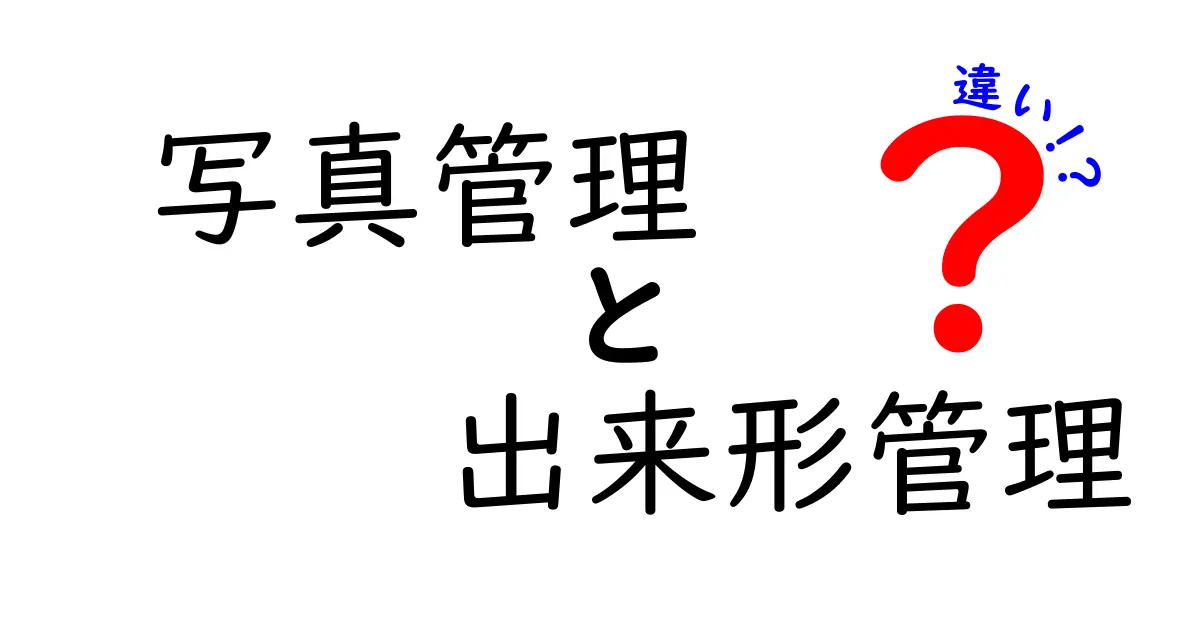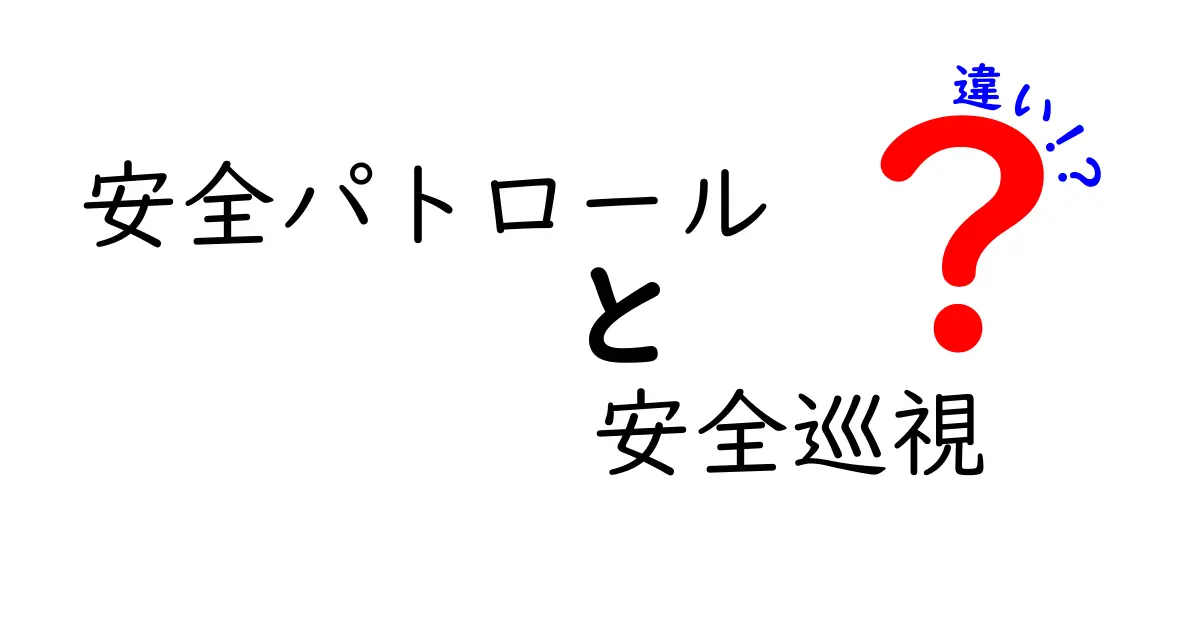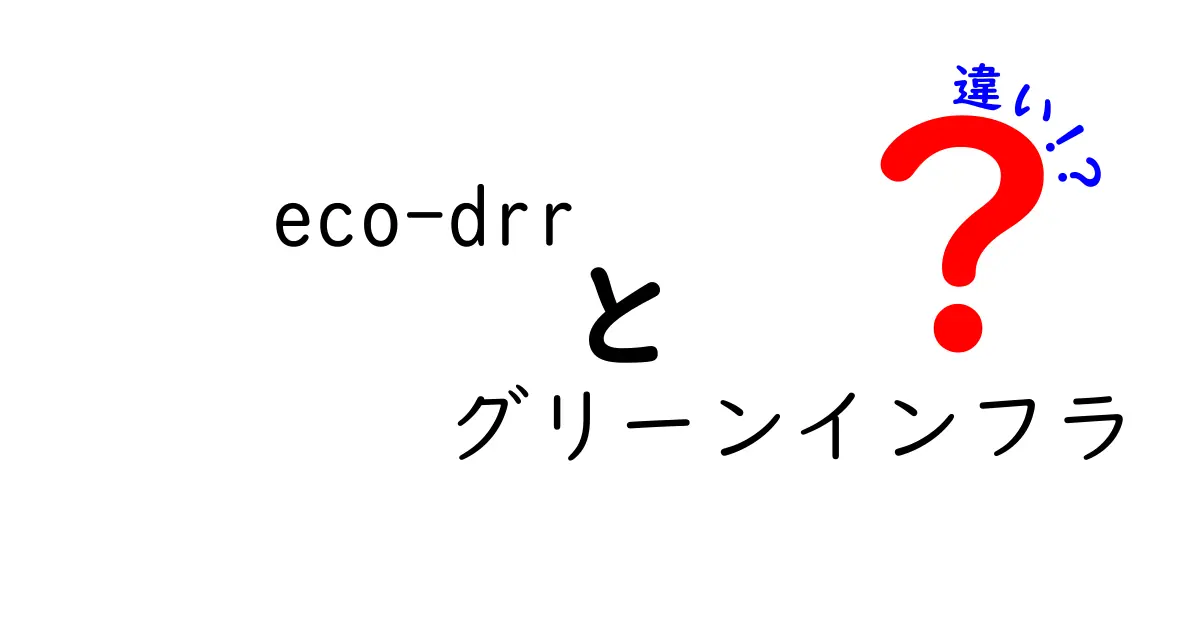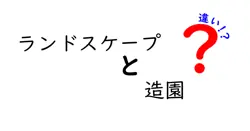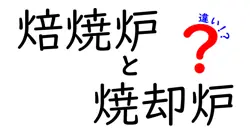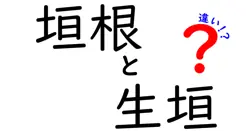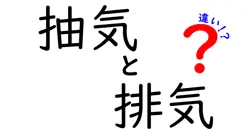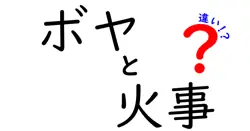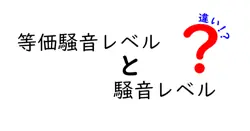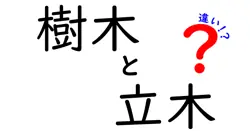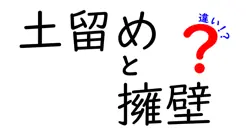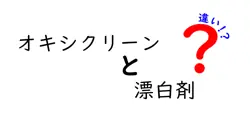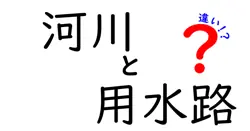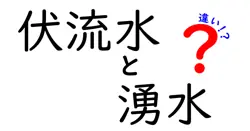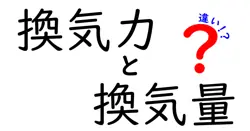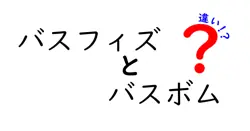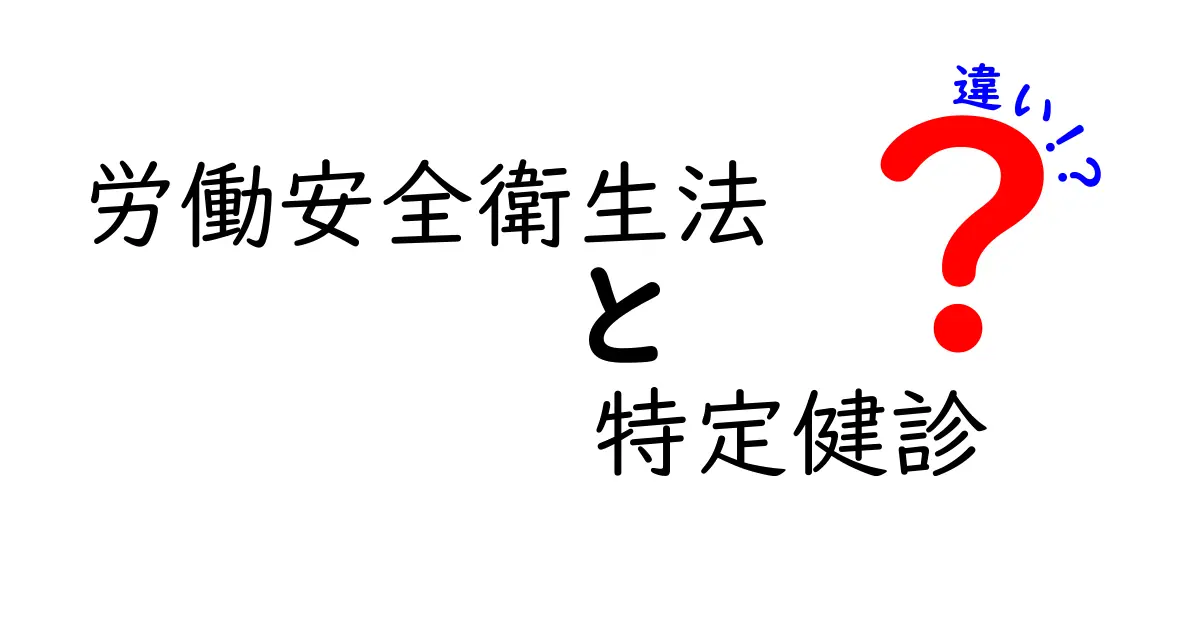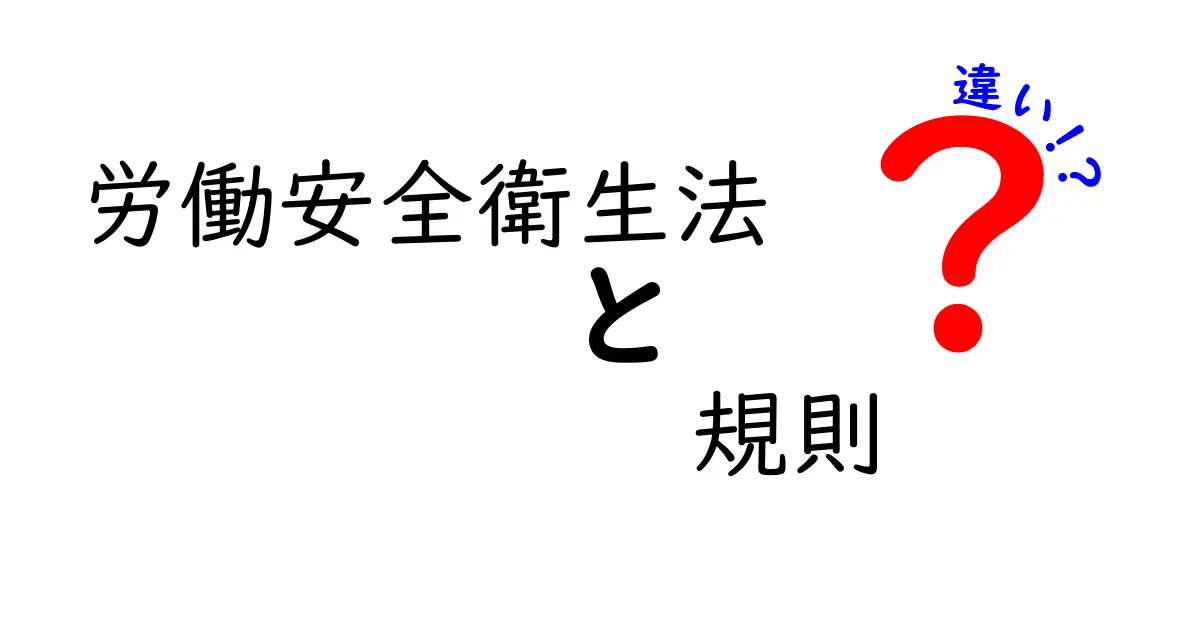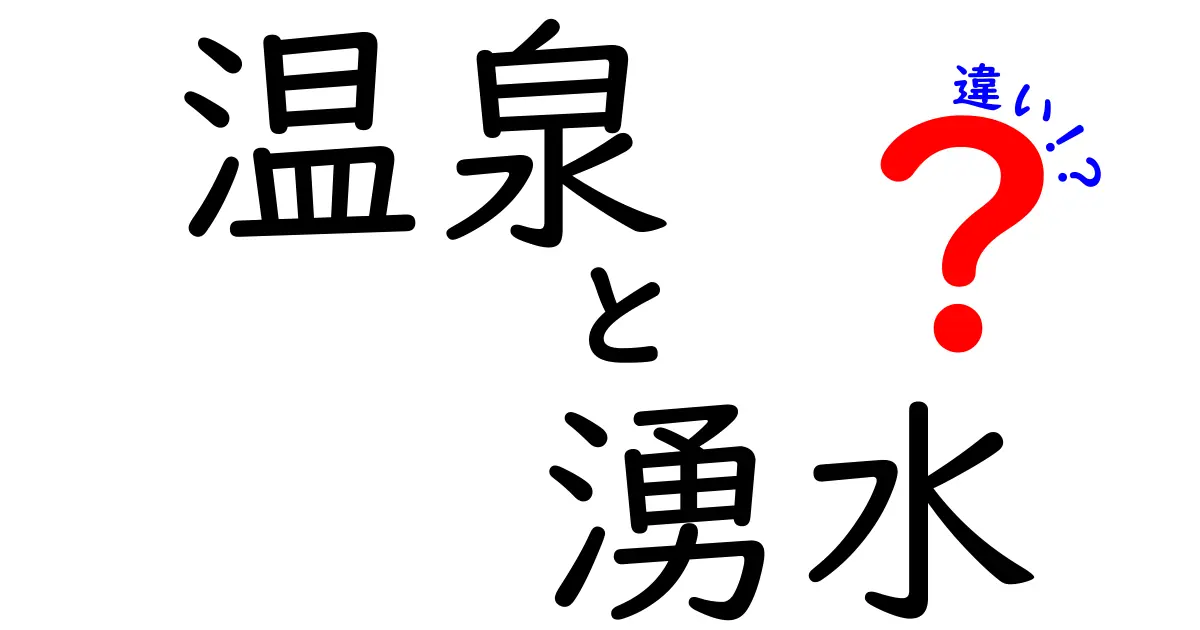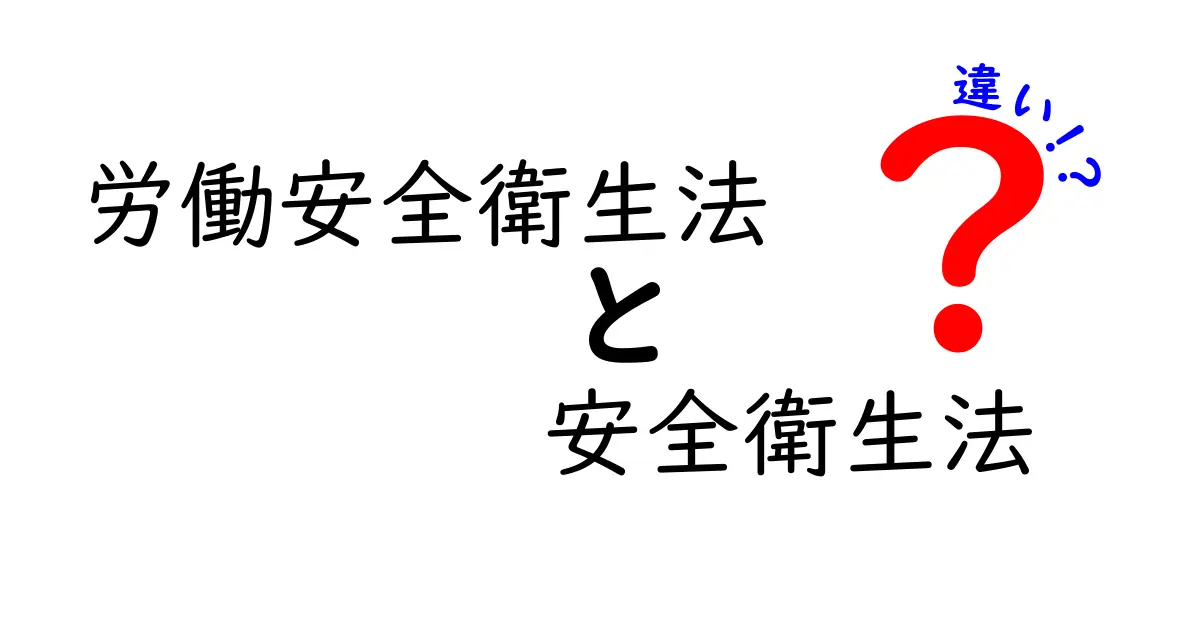
労働安全衛生法とは?
<労働安全衛生法は、日本の働く人々の安全と健康を守るための法律です。特に工場や建築現場などでの事故や病気を防ぐために作られました。
この法律は、働く場所で危険がないかをチェックしたり、安全な道具や設備を使わせたりすることを企業に義務付けています。
例えば、高いところでの作業や有害な化学物質を使う場合は特に注意が必要で、そうした作業に関するルールがこの労働安全衛生法で定められています。
また、職場の環境を快適に保つために、換気や休憩時間の確保なども求められています。
この法律の目的は、働く人が安心して働ける環境を作ることです。
<
安全衛生法とは?
<安全衛生法という名前は、実は「労働安全衛生法」を省略した言葉として使われることがあります。
つまり、安全衛生法という法律が別にあるわけではなく、正式には「労働安全衛生法」が正式名称です。
ただし、日常の会話や文章で「安全衛生法」と略して呼ぶケースが多々あります。
そのため、混乱しやすいですが、この場合は「労働安全衛生法」のことを指しています。
他の類似の法律(例えば食品衛生法など)と混同しないよう注意が必要です。
<
労働安全衛生法と安全衛生法の違いを表で比較
<| 項目 | 労働安全衛生法 | 安全衛生法 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 労働安全衛生法 | 正式な法律名ではない(略称や通称) |
| 目的 | 労働者の安全と健康の保持・増進 | 労働安全衛生法を指すことが多い |
| 適用範囲 | 労働現場全般(製造業、建設業等) | 特定の法律ではない |
| 法律の有無 | 日本の法律の正式名称 | 正式な法律名ではないため存在しない |
| 項目 | 原価 | 実行予算 |
|---|---|---|
| 意味 | 製品やサービスを作るために実際にかかった費用 | 仕事やプロジェクトに使う予定のお金の上限 |
| 時期 | 作業や生産が終わったあとでわかる | 作業や生産を始める前に計画して決める |
| 目的 | コストを把握し、利益計算をする | コストを抑え、計画を守るための管理 |
| 使う場所 | 会計報告や経費分析 | 予算管理やプロジェクトの進行管理 |
実践!原価と実行予算をどう管理すればよい?
では、原価と実行予算をビジネスでどう管理すればいいのでしょうか?
まず、実行予算はプロジェクトの始めに設定します。このとき、「どれだけお金を使っても大丈夫か?」を計画します。
次に、実際にかかった費用(原価)を逐一チェックしながら、予算内で仕事が進んでいるかを確認します。
もし原価が予算を超えるおそれがある場合は、どこを削減できるか検討したり作業内容を見直したりすることが必要です。
このように、計画(実行予算)と実績(原価)を比べて改善していく作業は、企業が無駄をなくし利益を守るために欠かせません。
「原価」という言葉はよく聞きますが、実はその中には「直接原価」と「間接原価」という2つの種類があります。直接原価は製品に直接かかる費用、たとえば材料費や直接作業者の給料。間接原価は工場の家賃や光熱費など、製品に直接は結びつかない費用です。ビジネスでは、この区別をすることで、もっと正確にコストを計算できるんですよ。原価が一言で済まない奥深さ、ちょっと面白いですね。
前の記事: « 転送ケーブルと通信ケーブルの違いとは?初心者でもわかる徹底解説!
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
転送ケーブルと通信ケーブルの違いとは?初心者でもわかる徹底解説!
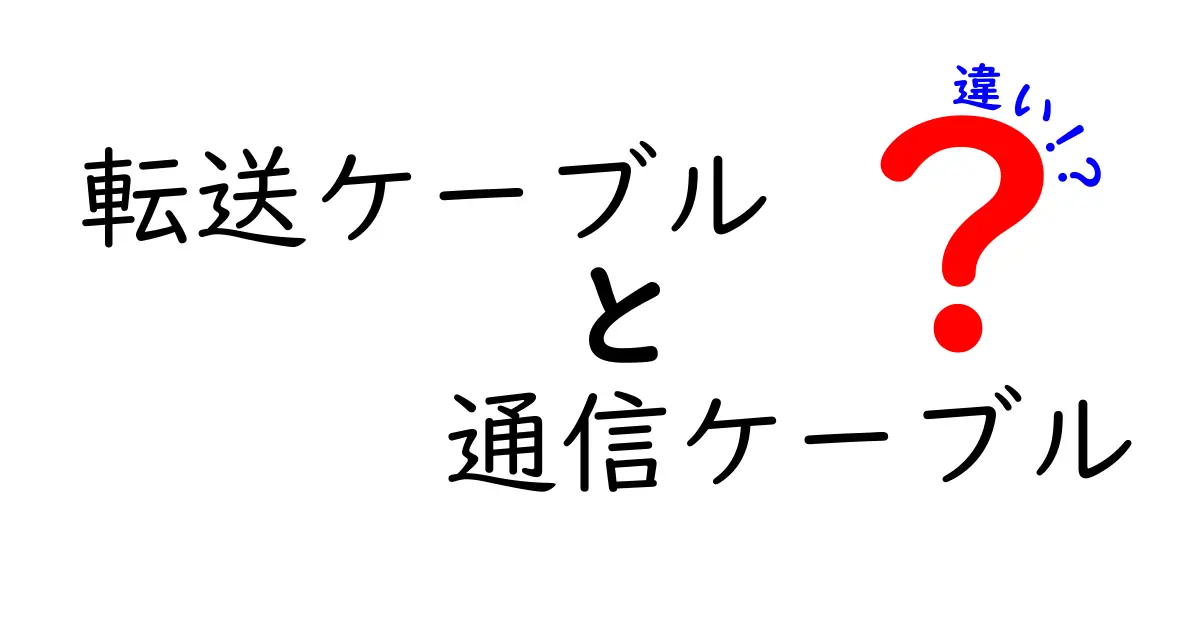
転送ケーブルとは何か?基本を理解しよう
転送ケーブルは、主にデータを一つの機器から別の機器へ転送するために使われるケーブルです。例えば、スマートフォンとパソコンを繋いでデータを移す時に使うUSBケーブルが代表的な転送ケーブルです。
このタイプのケーブルは、データのやり取りをスムーズに行うために設計されており、ケーブルの形状や内部の配線が転送速度や対応する機器に応じて違います。重要なのは、転送ケーブルは主に点対点でデータを直接やりとりするために使う点です。
通信ケーブルとは?ネットワークの要になる存在
通信ケーブルは、コンピュータやスマートフォン、さらにはテレビやゲーム機など、様々なデバイスがネットワークを介して情報をやり取りするために使われます。
代表的なのはLANケーブル(イーサネットケーブル)で、これを使うことでインターネットへの接続や複数の機器同士の通信が可能になります。転送ケーブルとは違い、通信ケーブルは多くの機器をつなぎネットワークでの情報のやりとりに重きを置いています。
転送ケーブルと通信ケーブルの違いを一目で比較
| ポイント | 転送ケーブル | 通信ケーブル |
|---|---|---|
| 主な用途 | 機器間の直接データ転送 | 複数機器のネットワーク接続 |
| 代表的な例 | USBケーブル、Thunderboltケーブル | LANケーブル(Cat5e、Cat6) |
| 接続方式 | 点対点接続 | ネットワーク構築 |
| 使用場所 | 家庭やオフィスの機器間 | ネットワーク全体、インターネット接続 |
転送ケーブルと通信ケーブル、それぞれの選び方とポイント
もし、スマートフォンからパソコンへ写真やデータを移したいなら転送ケーブルを使うのが適しています。USBやThunderboltが便利です。
しかし、インターネットに接続したい、もしくは複数のパソコンや機器をつないで情報を共有したい場合は通信ケーブル(LANケーブル)が必要です。種類もCat5eやCat6、Cat7など速度や対応性能に違いがあるため、自分の使用環境に合ったケーブルを選ぶことが大切です。
強いて言えば、使用目的によっては両方のケーブルが必要になることも多く、ケーブルの役割を理解して正しく選ぶと快適にデバイスを使うことができます。
まとめ:用途に応じて転送ケーブルと通信ケーブルを使い分けよう
結論として、転送ケーブルは1対1のデータ移動に特化し、通信ケーブルは複数機器の通信やネットワーク構築に使われます。
使い方や目的に合ったケーブルを選び、パソコンやスマホ、ネット環境をより便利にしましょう。
知っておくと役立つ豆知識や最新規格も意識しながら、今後のケーブル選びにぜひ役立ててください。
転送ケーブルの中でもUSBケーブルは、ただ繋ぐだけでなく、実は規格によって転送速度や対応機器が大きく異なります。例えばUSB 2.0は最大480Mbpsで、USB 3.0は最大5Gbpsの高速転送が可能。これはダウンロードやファイル移動のスピードに直結します。中学生にとってはピンとこないかもしれませんが、これだけ差があるとデータの移し替えがずいぶん早くなるんですよ。さらに最近のUSB Type-Cは形状も小型でリバーシブルなので使いやすさも抜群。ケーブルの“見た目”にも進化があることを知っておくと面白いですね。
前の記事: « サブウェイと地下鉄の違いとは?わかりやすく徹底解説!
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
サブウェイと地下鉄の違いとは?わかりやすく徹底解説!
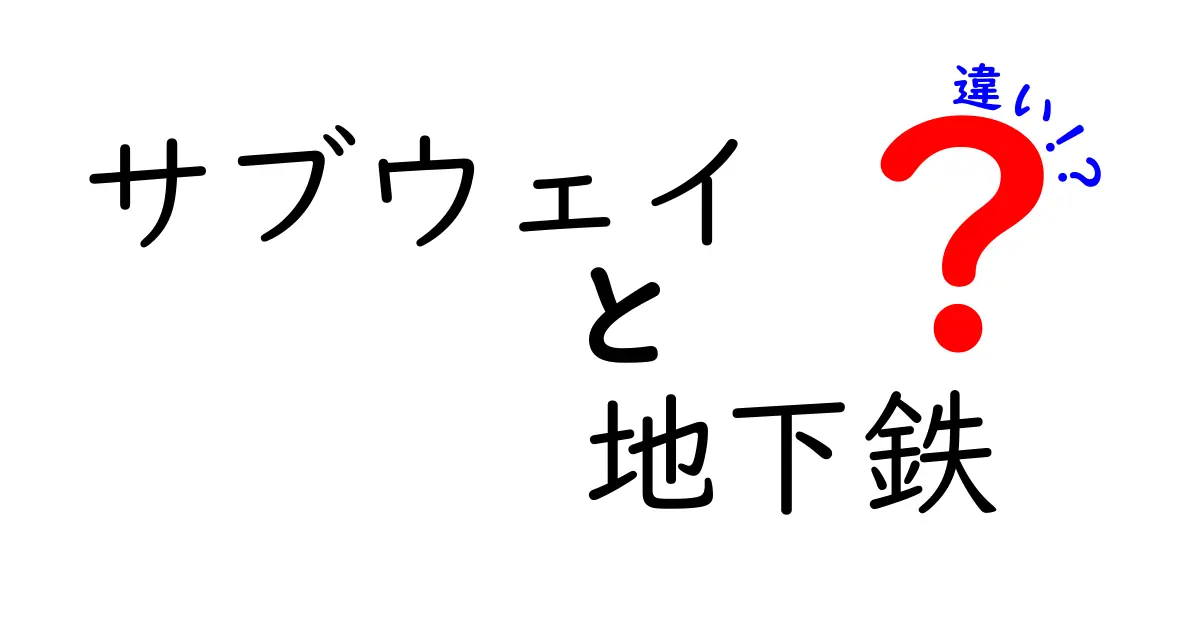
サブウェイと地下鉄って何が違う?基本から学ぼう
皆さんは「サブウェイ」と「地下鉄」という言葉を聞いたときに、どんな違いがあるか知っていますか?実は、この2つはほとんど同じ意味で使われることもありますが、厳密には異なる部分もある
まずは「地下鉄」とは何かから見ていきましょう。地下鉄はその名の通り、都市の地下に敷設された鉄道のことで、人々が日常的に使う交通手段の一つです。多くの都市で交通の混雑を減らすために設置され、例えば東京の東京メトロや大阪メトロが代表的です。
次に「サブウェイ」ですが、これは英語の「subway」が語源です。英語圏では「地下鉄」の意味として使われますが、アメリカなどの一部の地域では「地下道」や「歩道橋」などを指すこともあります。日本では外国語由来の言葉としてそのまま「地下鉄」を指すことが多いです。
呼び方の違いとその由来
「地下鉄」という言葉は、日本で使われる公式な呼び名であり、目的は地下を走る鉄道を示しています。
一方「サブウェイ」は英語の単語なので、主に英語圏での呼称になります。例えばニューヨークの「New York Subway」は世界的にも有名な地下鉄で、「サブウェイ」と呼ばれています。
日本では一般的に「地下鉄」が使われているので、「サブウェイ」はあまり日常会話の中で使われません。ただし、国際的な文脈や英語の情報を得るときには「サブウェイ」という言葉が登場することがあります。
このような呼び方の違いは、言語や文化の違いによるものであり、実態としてはほぼ同じシステムを指しているケースが多いです。
表で比較!サブウェイと地下鉄の特徴まとめ
ここで「サブウェイ」と「地下鉄」の違いについて、わかりやすい表にまとめてみましょう。
まとめ:日常でどちらの言葉を使うべき?
結論から言うと、日本では地下鉄という言葉を使うのが自然で正しい使い方です。
海外や英語の文章を読むときは「サブウェイ」という表現を見ることがありますが、それは単に英語での呼び方です。どうしても使うならば、対象の地域や状況に合わせて使うことが大事です。
ですから、日本で地下鉄の話をするときは「地下鉄」と言えば間違いありません。英語圏の話題や海外旅行のときには「サブウェイ」を知っていると便利です。
このように意味はほぼ同じですが、言葉の使い分けを知っておくと、より深くコミュニケーションがとれて楽しいですよね。ぜひ覚えてみてください!
サブウェイという言葉は、英語の“subway”から来ているのですが、面白いことにアメリカでは地下鉄だけでなく“地下道”や“歩道橋”を指すこともあるんです。だからニューヨークの地下鉄は『サブウェイ』ですが、駅の中や街の歩行者用の地下通路もサブウェイと呼ばれています。日本で言う地下鉄のイメージより少し幅広い使い方ですね。こんな言葉の違いを知ると、海外旅行や英語のニュースがより理解しやすくなりますよ。
次の記事: 転送ケーブルと通信ケーブルの違いとは?初心者でもわかる徹底解説! »