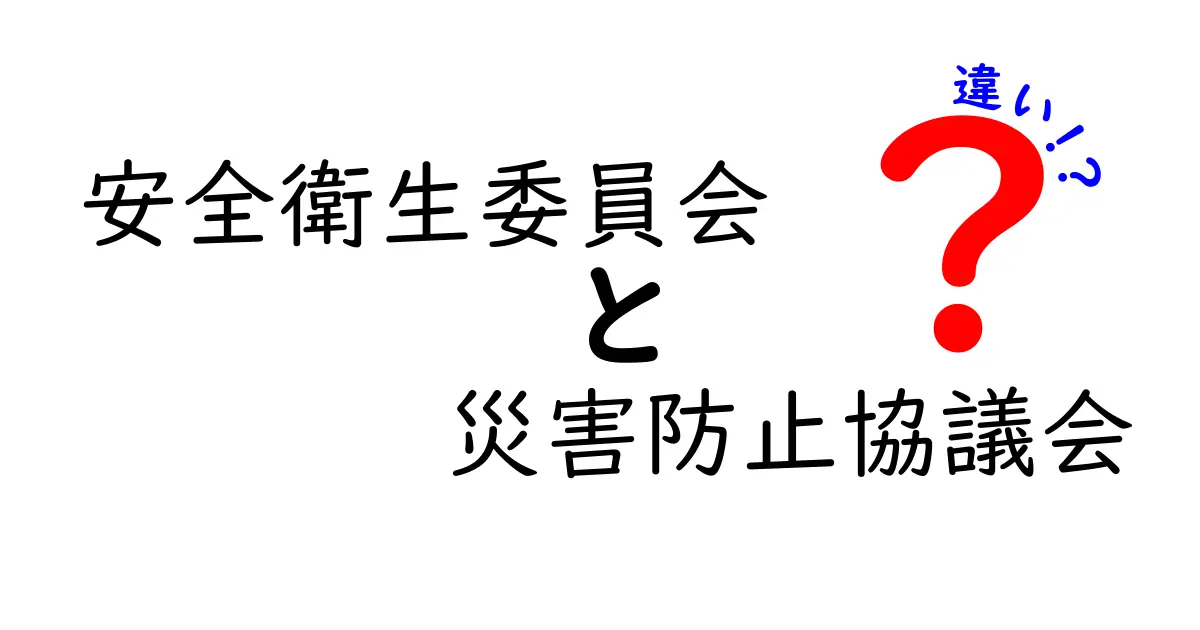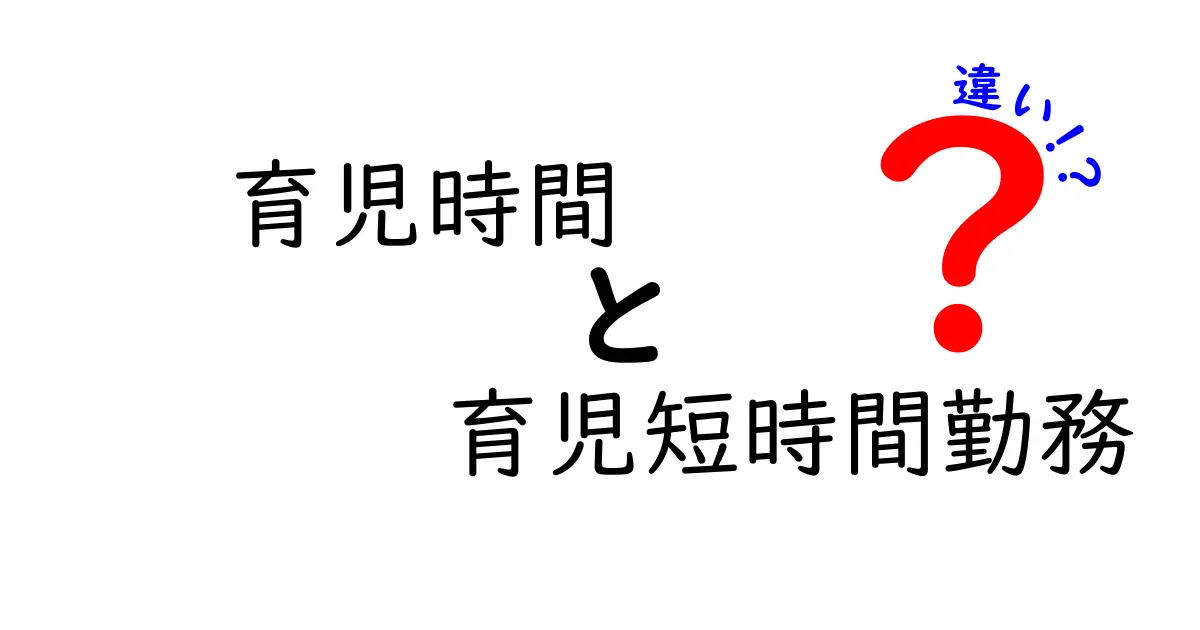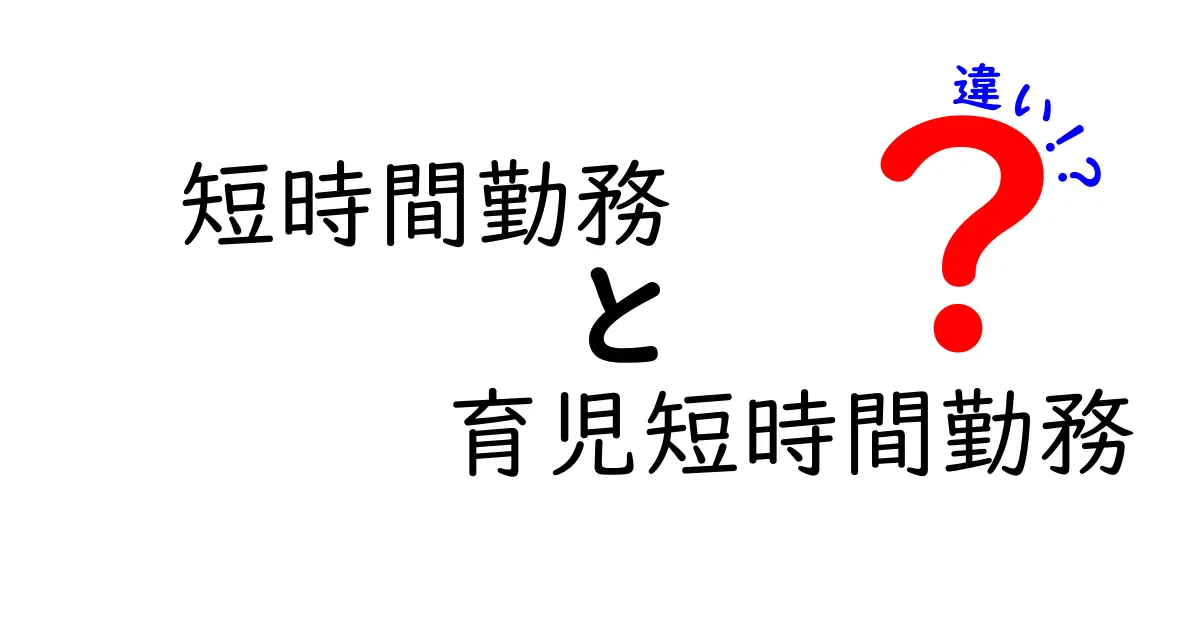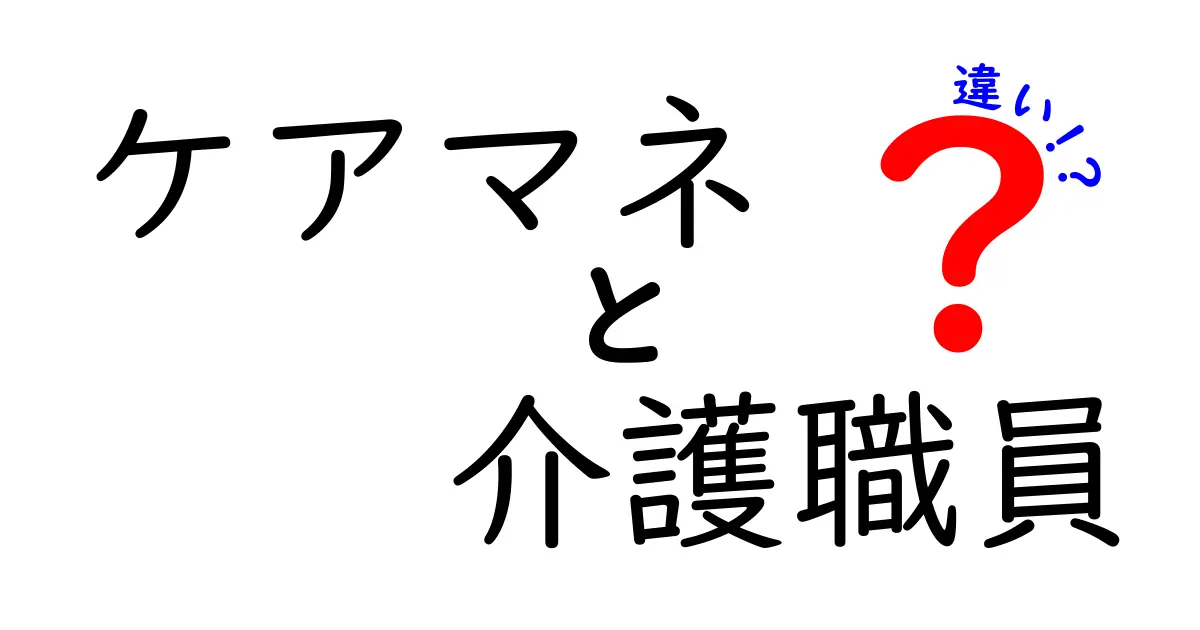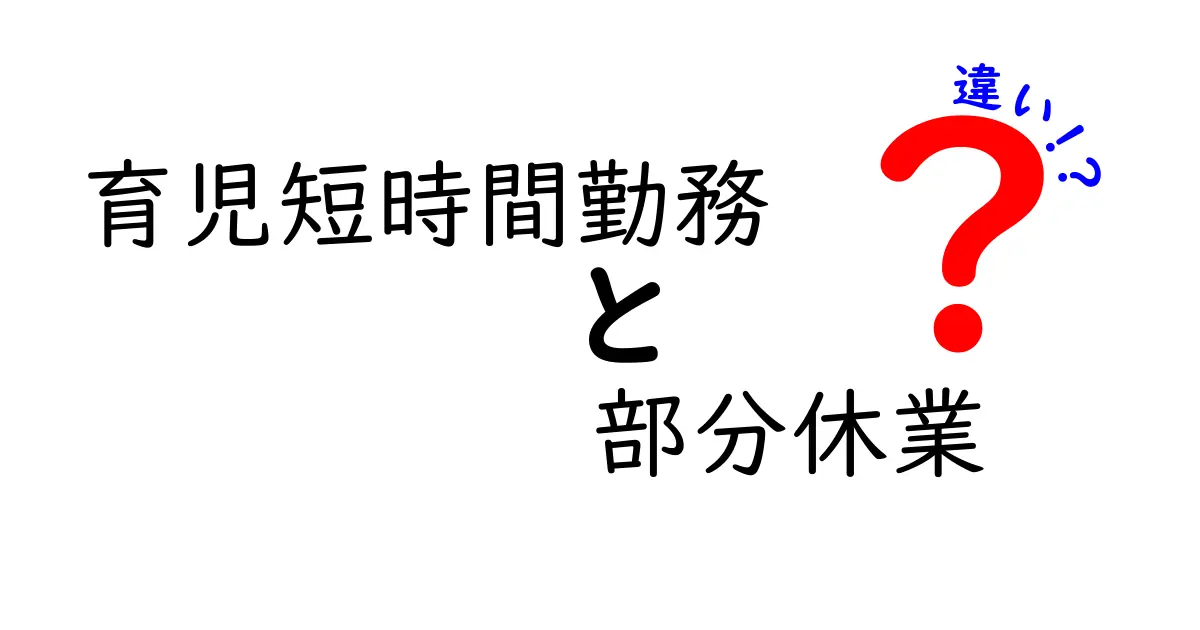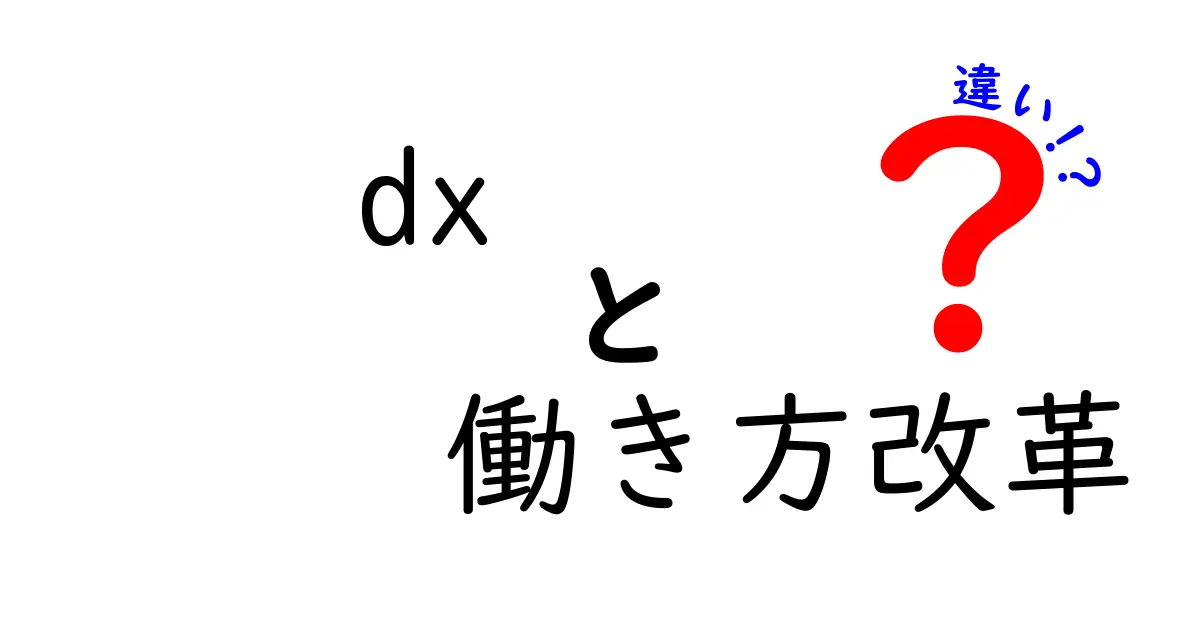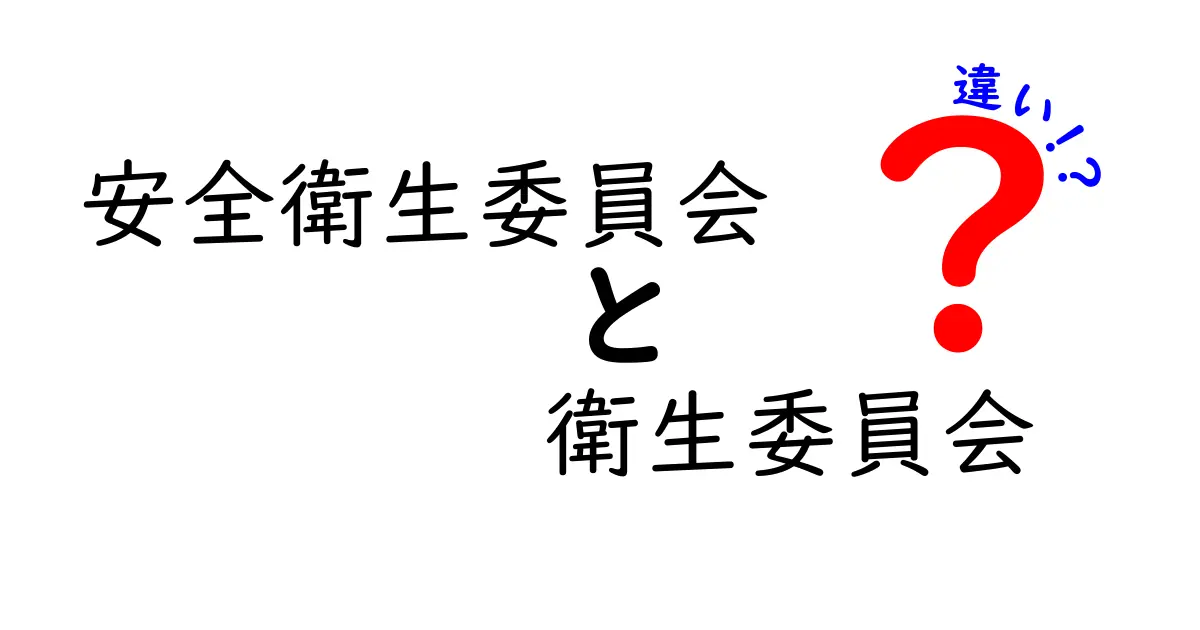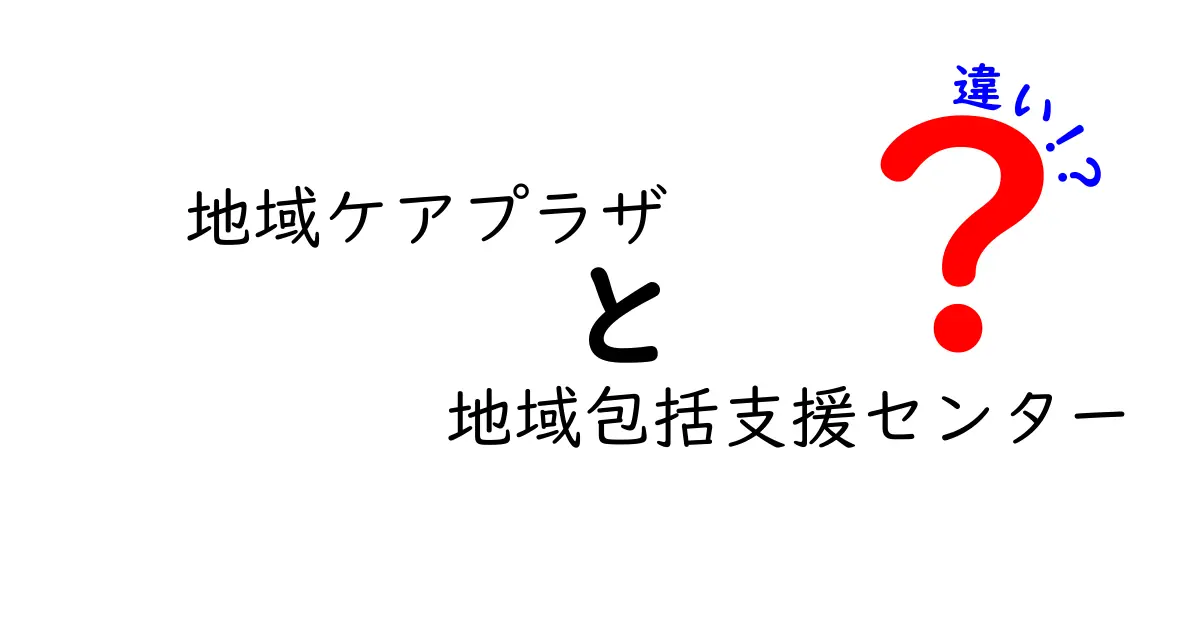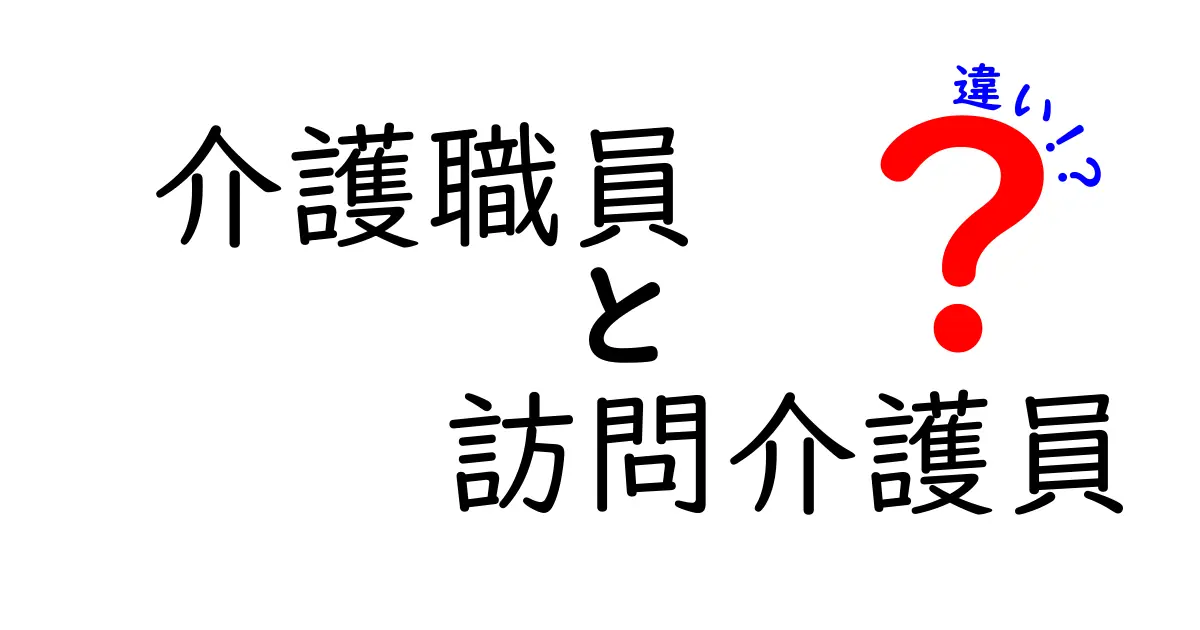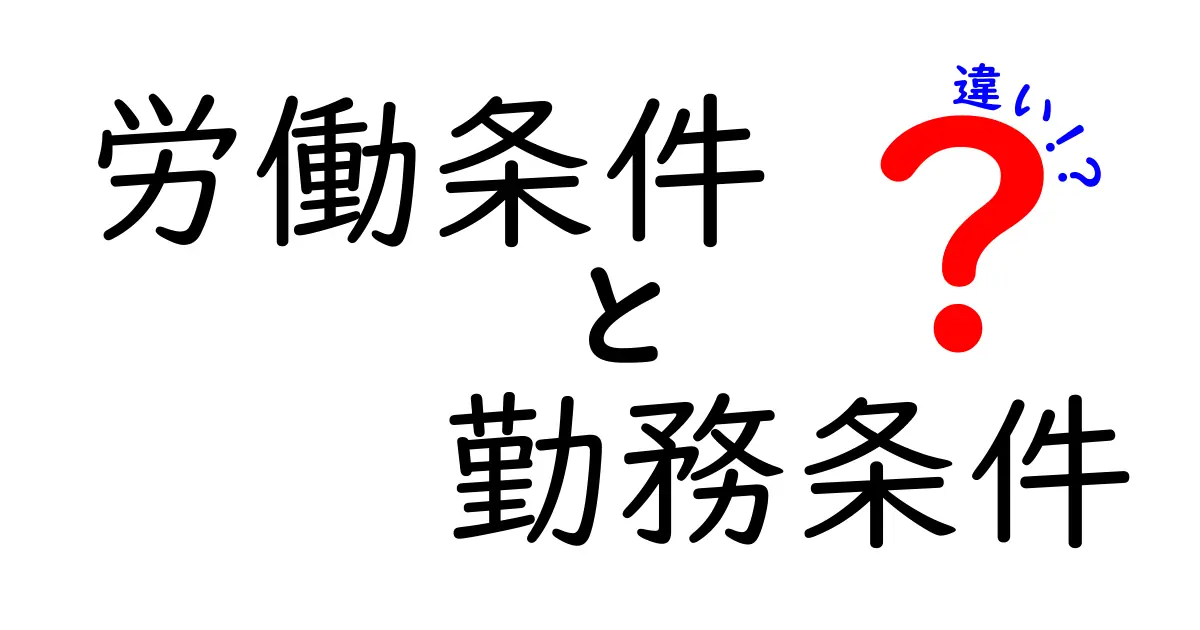
はじめに:労働条件と勤務条件の違いについて知ろう
仕事をするうえで「労働条件」と「勤務条件」という言葉はよく耳にしますよね。しかし、どちらも似た言葉なので、違いがわかりにくいことも多いです。
労働条件と勤務条件は実は少し異なる意味を持っています。
この記事では、それぞれの意味や違いをわかりやすく説明して、仕事探しや職場での理解に役立つ情報をお伝えします。
労働条件とは?その意味と内容を詳しく解説
まずは労働条件についてです。労働条件とは、働くときの約束事のことを言います。
具体的には、給料の額や働く時間、休みの取り方、仕事内容、勤務場所など、働く人と会社が守るべきルールや取り決めが含まれます。
たとえば、「月給20万円」「1日8時間勤務」「年間休日120日」「残業は月に20時間まで」といった項目が労働条件にあたります。
労働基準法という法律によって、労働条件は一定の基準が決められており、会社はそれを守らなければいけません。
まとめると、労働条件は働く人と会社の間で決められた働くためのルールや約束事の内容なのです。
勤務条件とは?労働条件との違いを具体的に見てみよう
次に勤務条件ですが、こちらは労働条件の中の一部と考えてよいでしょう。
勤務条件とは、主にいつ、どこで、どのように働くかについての決まりごとを指します。
たとえば、勤務時間(午前9時から午後5時まで)、勤務場所(本社や支店)、休日の曜日(週休2日制の土日)、勤務体制(シフト制か固定か)などが勤務条件に該当します。
つまり、勤務条件は労働条件のうち「勤務にまつわる具体的な取り決め」を示しているため、
『労働条件=会社で働く上での全体のルール』
『勤務条件=その中でも勤務時間や場所などの働く環境やスケジュールの約束』
という関係です。
労働条件と勤務条件の違いを表でまとめてみました
| 項目 | 労働条件 | 勤務条件 |
|---|---|---|
| 含まれる内容 | 給与、労働時間、仕事内容、勤務場所、休暇、労働契約の期間など | 勤務時間、勤務場所、休日、シフトなど |
| 意味 | 働く全体のルールや約束事 | 働く時間や場所、休日などの具体的な勤務に関する決まり |
| 関係性 | 勤務条件を含む広い概念 | 労働条件の中の一部 |
| 項目 | 安全衛生委員会 | 災害防止協議会 |
| 設置根拠 | 労働安全衛生法による義務設置(規模や業種による) | 主に大規模工事現場や特定の作業現場で任意または法的義務がある場合も |
| 目的 | 職場全体の安全と健康の維持改善 | 労働災害・事故の防止と安全作業の徹底 |
| 対象範囲 | 事業所や企業全体 | 工事現場や特定の作業現場単位 |
| メンバー | 使用者側と労働者代表の委員 | 事業者、作業責任者、労働者代表、関係団体 |
| 活動内容 | 安全衛生教育、環境改善、事故分析、健康管理提案 | 危険要因の把握、防止策の検討、現場安全対策の実施強化 |
| 開催頻度 | 定期的(例:月1回など) | 工事の進行状況に応じて随時開催 |
以上の違いからわかるように、安全衛生委員会は幅広い職場の安全衛生全般を見守り、災害防止協議会は特定の危険作業にフォーカスして対策を練る役割があるのです。現場や職場の環境に応じて両者がうまく連携することで、より安全な労働環境が実現します。
安全衛生委員会と災害防止協議会、似た名前ですが、役割の違いが大きいことが面白いです。安全衛生委員会は会社全体の健康や安全を長期的に見守りますが、災害防止協議会は特定の現場や工事における緊急性の高い安全確保に向けて具体的な対策を議論します。まるで、学校の定期的な保健委員会と運動会の安全対策チームの違いのようです。こうした組織の使い分けが、安全で事故のない職場作りの鍵なんですね。