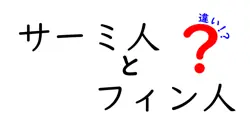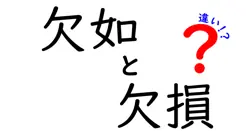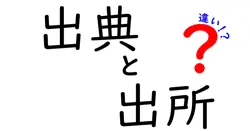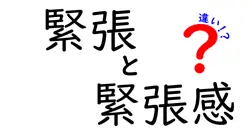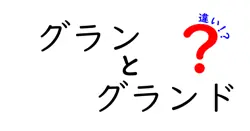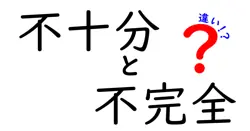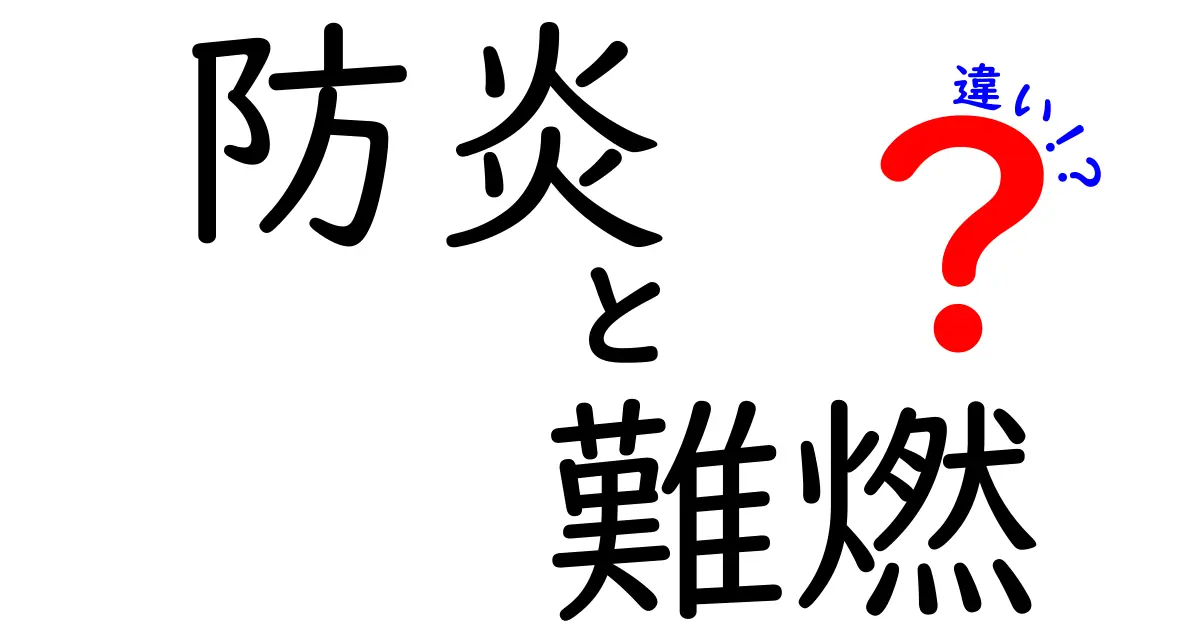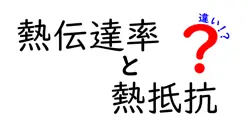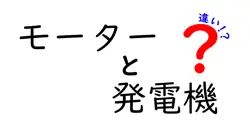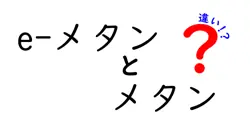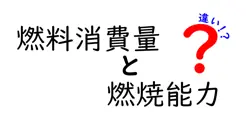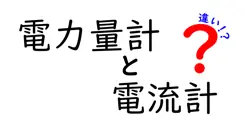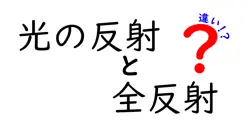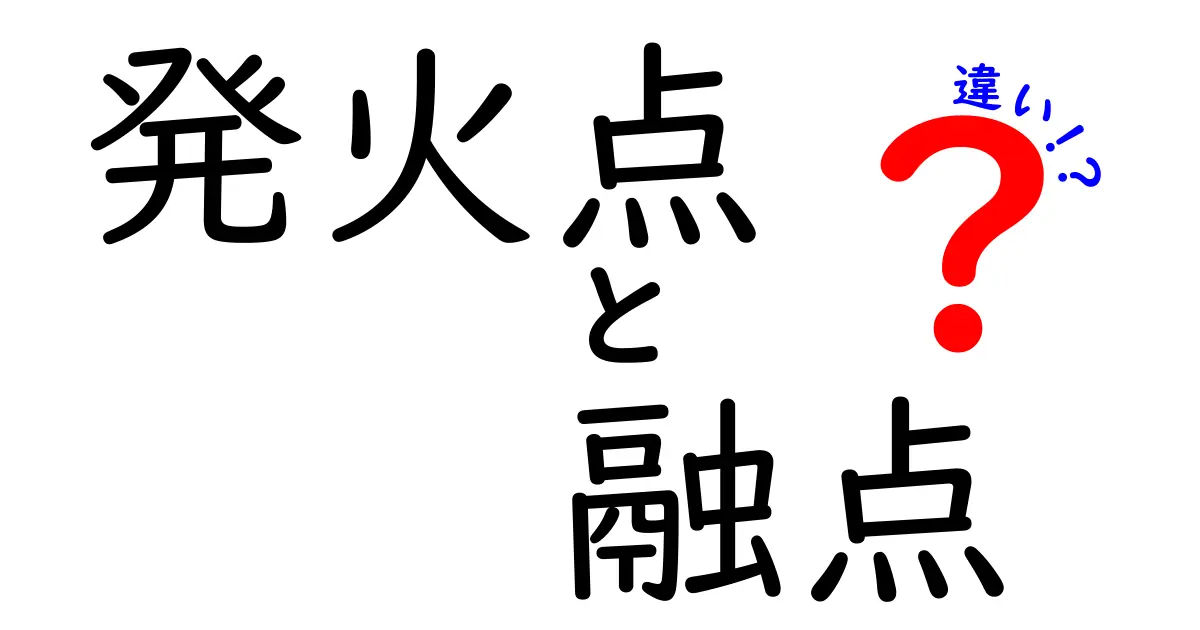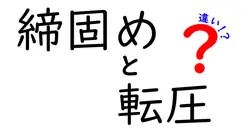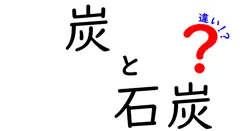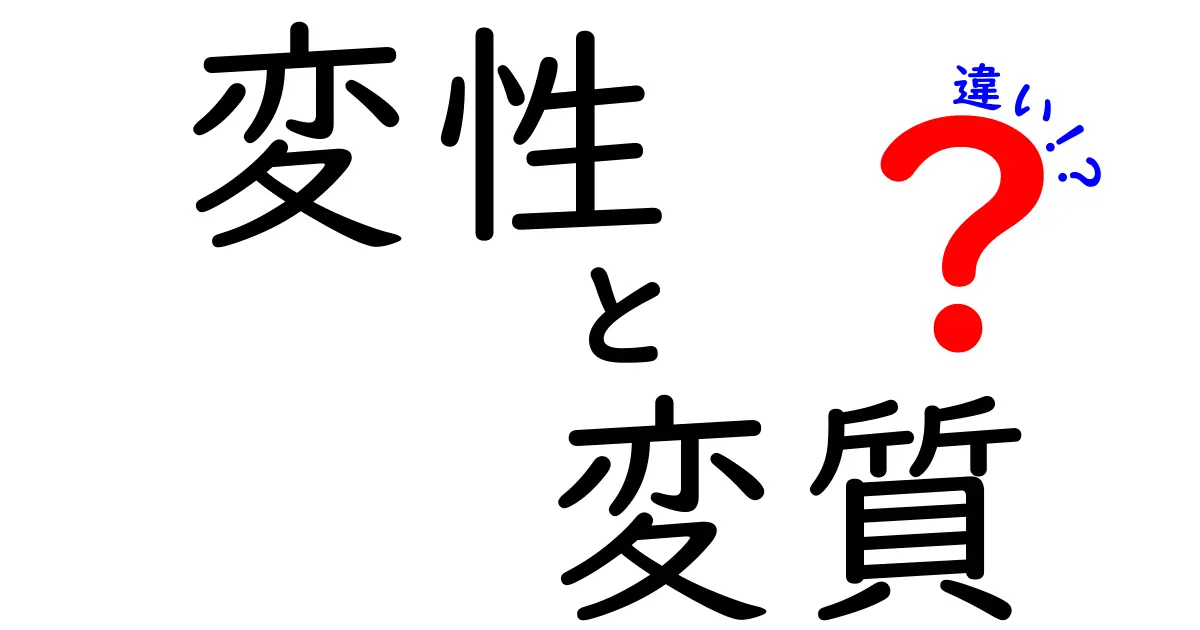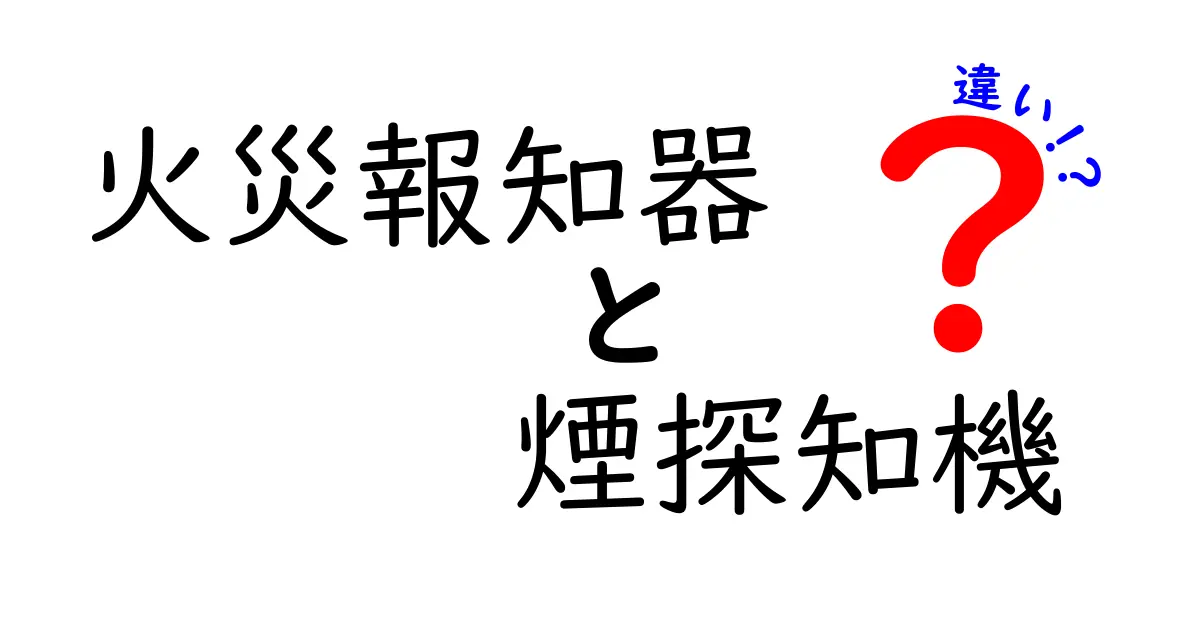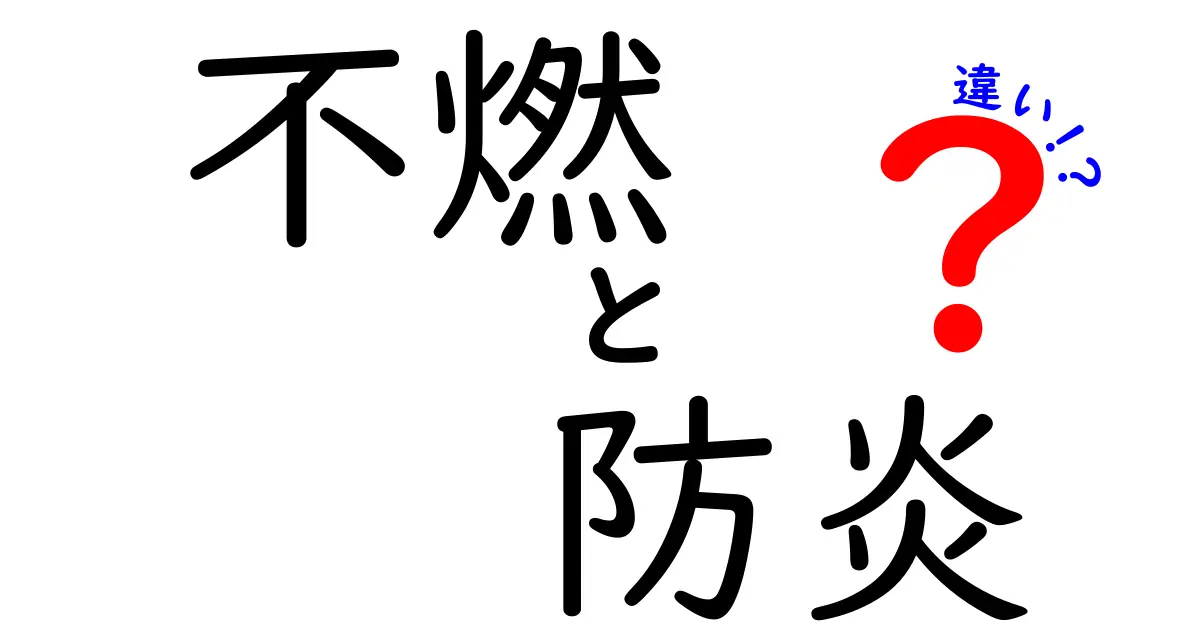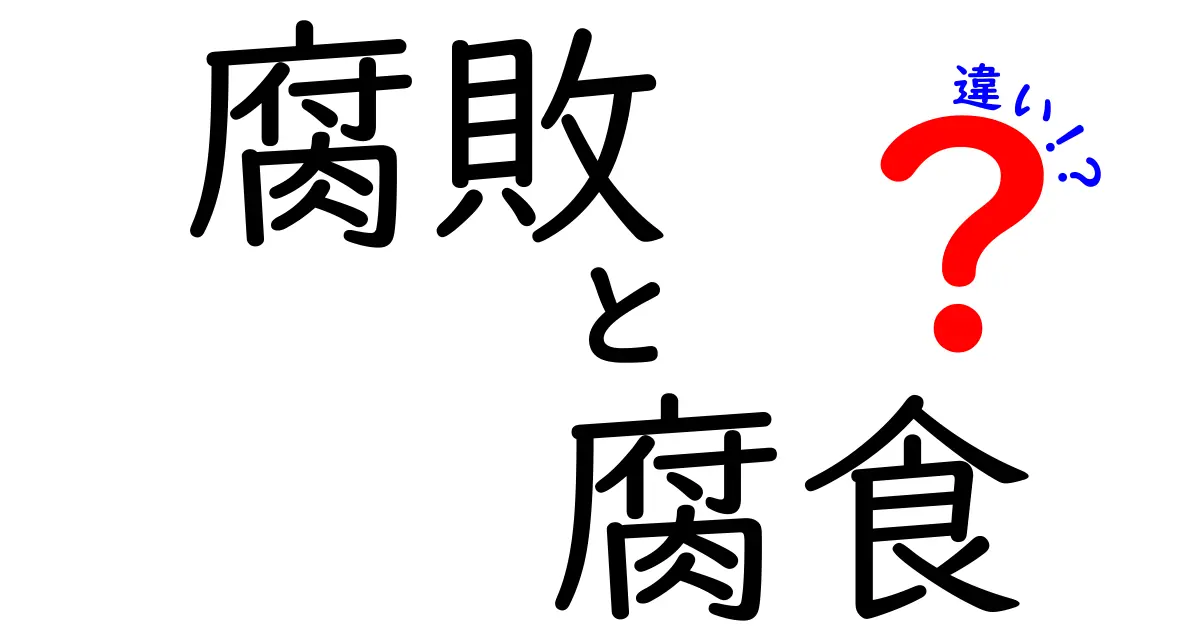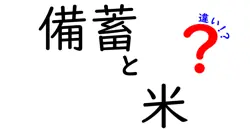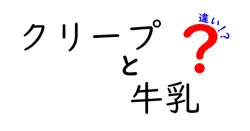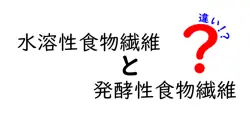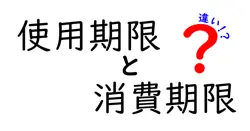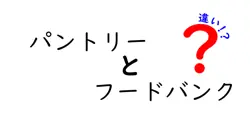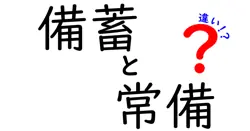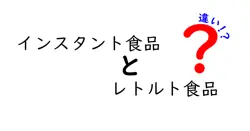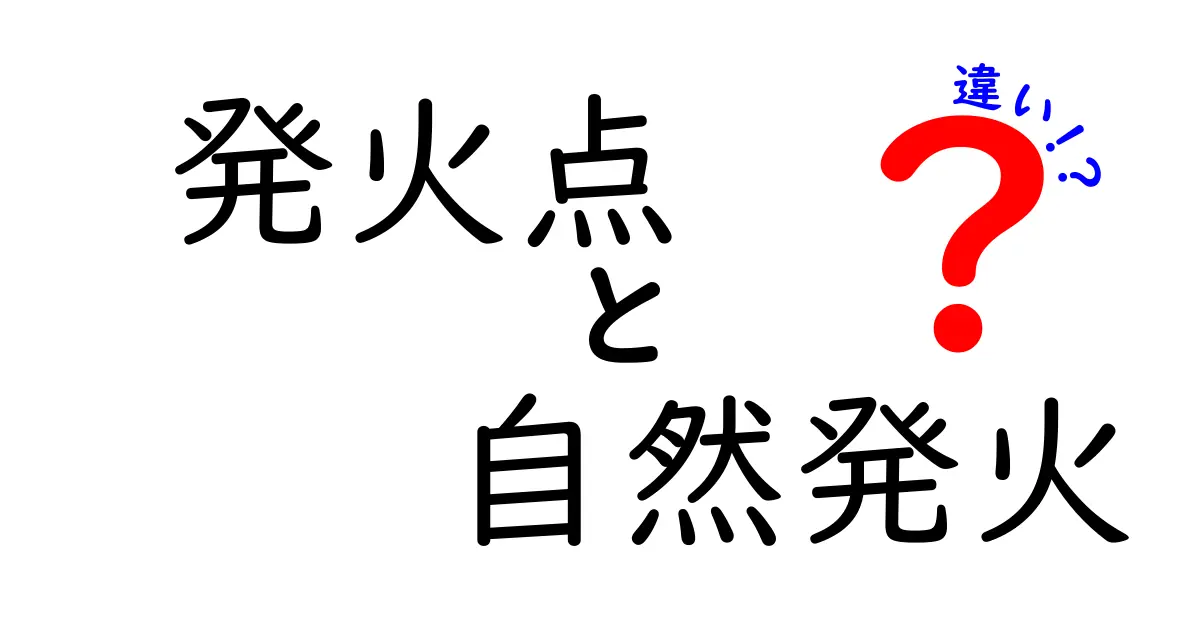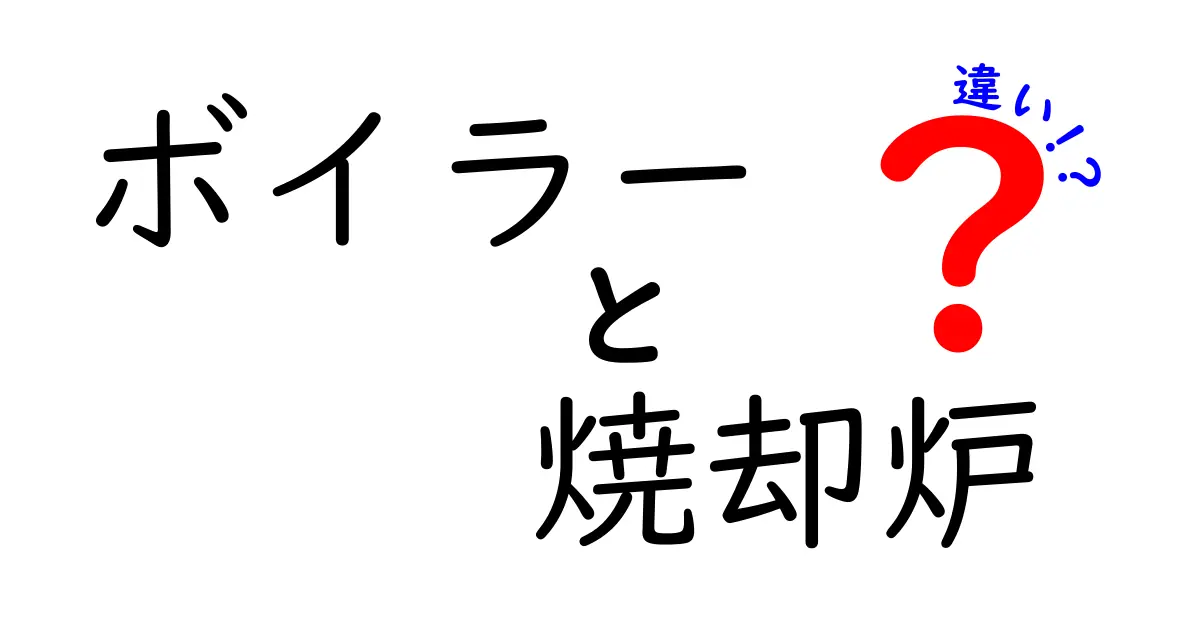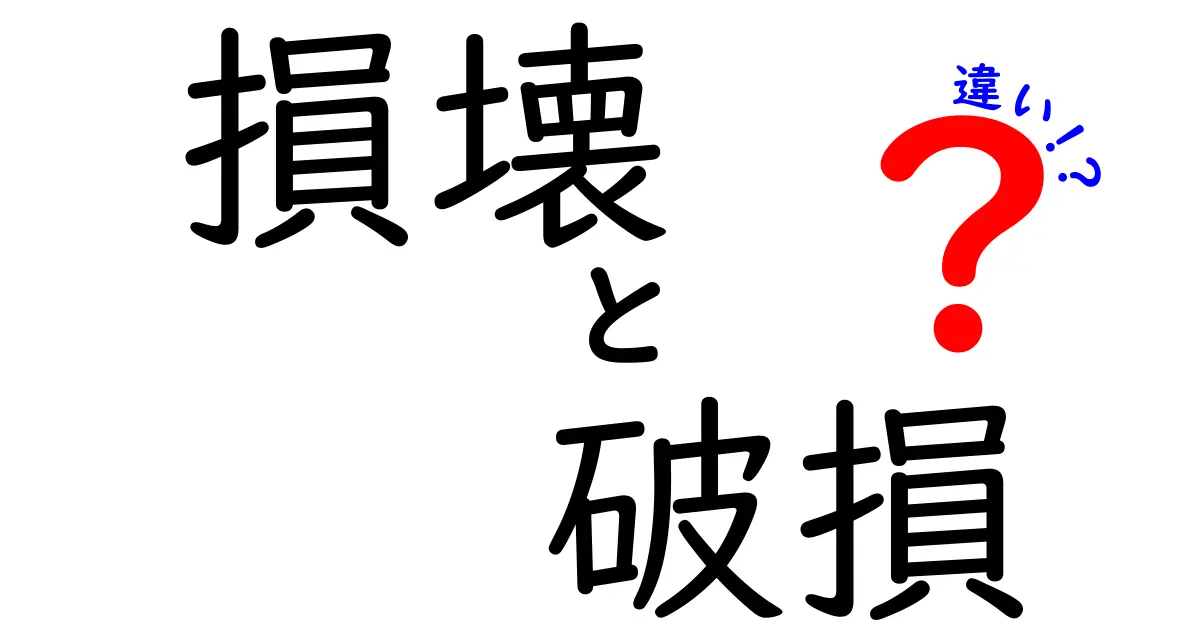
損壊と破損の基本的な意味の違いについて
まずは、「損壊」と「破損」という言葉の基本的な意味について理解しましょう。
損壊は、物や建物などが大きく損なわれて壊れることを指します。特に、自然災害や戦争、事故などで大規模に壊れてしまう場合によく使われます。
一方、破損は、物の一部分が壊れ壊れて機能しなくなることを意味します。日常生活の中でもよく使われ、物の欠損や故障、小さな損傷にも使われることが多い言葉です。
このように、損壊は大規模な損傷、破損は細かな損傷を表す点が大きな違いです。
違いを理解することで、正しく使い分けることができます。
使い方の具体例と状況別の違い
実際に使われる場面を例に挙げて、「損壊」と「破損」の違いを見てみましょう。
損壊の例:
・地震によって家屋が大きく倒壊し、損壊した。
・台風で橋が破壊され、交通が遮断され損壊が激しい。
これらは建物や構造物が広範囲にわたり大きく壊れた場合に使われます。
破損の例:
・スマートフォンの画面が割れて破損した。
・車のバンパーがぶつかって破損した。
これは部分的または小さな破損でも使えることが多いです。
このように損壊は大規模な壊れ方、破損は部分的な傷や壊れを表現する時に便利です。
損壊と破損を比較した表でのまとめ
最後に、損壊と破損の違いを分かりやすく比較した表を作ってみました。
| 項目 | 損壊 | 破損 |
|---|---|---|
| 意味 | 大規模に壊れること 重度の損傷 | 部分的に壊れること 小さな損傷や故障 |
| 使用場面 | 災害や事故で建物や設備が壊れた時 | 日常生活で物品の破損、一部の割れや故障 |
| ニュアンス | 全体に影響し復旧が困難な場合が多い | 局所的で修理可能な場合が多い |
| 例 | 橋の損壊、家屋の損壊 | スマホの画面破損、車のバンパー破損 |
| 特徴 | 防炎 | 難燃 |
|---|---|---|
| 定義 | 火の侵入を防ぎ燃え広がりにくい加工 | 元々燃えにくい素材の性質 |
| 処理方法 | 後加工(薬剤塗布など) | 素材の原材料段階で備わる |
| 耐久性 | 洗濯や経年で効果が薄れることがある | 長期間安定した性能 |
| 使用例 | 防炎カーテン、シート | 難燃衣料、電気機器部品 |
| 価格 | 比較的安価で加工可能 | やや高価な場合が多い |
まとめ:防炎と難燃を正しく選ぼう
防炎は火を防ぐ加工であり、難燃は燃えにくい素材の性質です。
防炎は手軽に加工できて広く使われますが、時間とともに効果が薄れるデメリットがあります。
一方、難燃は初めから燃えにくく、長くその性能を維持できます。
目的や使用環境に応じて適切な素材や加工を選ぶことが、安全で快適な生活につながります。是非、次にカーテンや布製品を買う時の参考にしてくださいね。
「防炎」と聞くと火を完全に防げるイメージが強いですが、実は防炎は「火がつきにくく燃え広がりにくい」加工のこと。
例えば、劇場やホテルのカーテンは防炎性能を持っていることが法律で決まっています。これは万が一火事が起きても燃え広がりを遅くし、安全に避難できる時間を作るためです。
ちなみに防炎加工は布に薬剤を塗っているので、洗濯を繰り返すと効果が弱くなることもあります。このため、定期的に防炎検査が必要な場所もあるんですよ。身近な素材の工夫が実は大切な安全対策になっていますね!
次の記事: 損壊と破損の違いとは?使い方や意味をわかりやすく解説! »
の人気記事
新着記事
の関連記事
耐熱と防炎の違いを徹底解説!素材選びで失敗しないために知っておくべきポイント
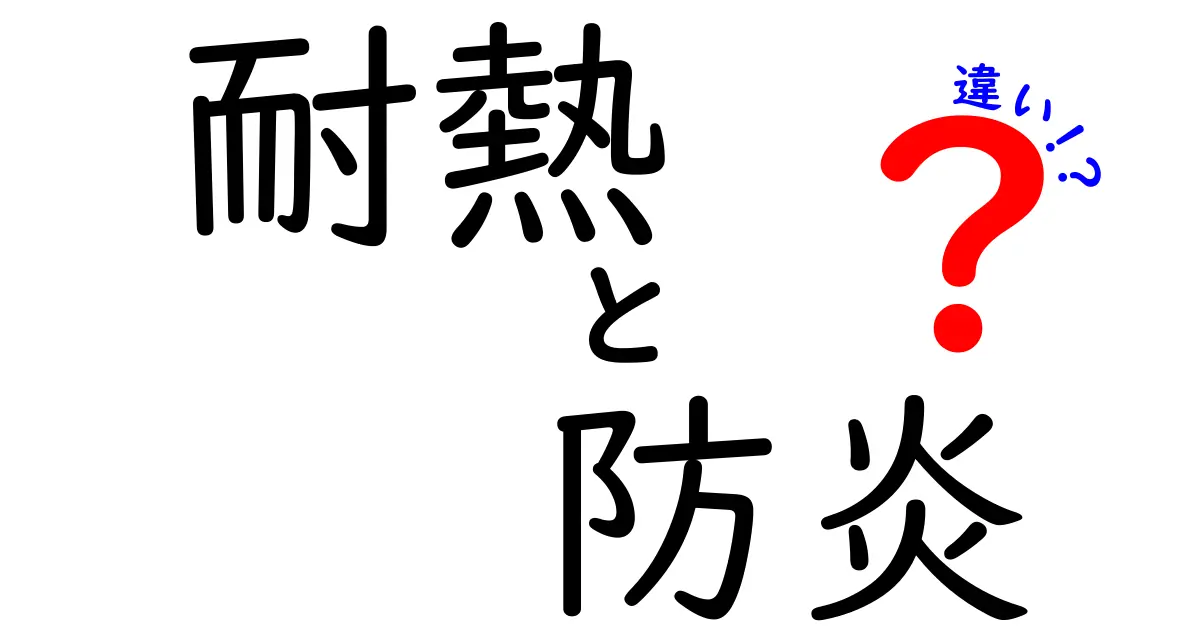
耐熱と防炎の基本的な違いとは?
私たちの日常生活や仕事の場面でよく耳にする「耐熱」と「防炎」。この2つは似ているようで、実は全く異なる性質を持っています。
耐熱とは、物が高い温度に耐える力を意味します。例えば、お鍋の取っ手が熱くならずに持てるのも耐熱素材が使われているからです。一方で、防炎とは火に対して燃えにくい性質を指し、火災の際に火の拡大を防ぐために使われる素材や加工を指します。
耐熱は「熱に強い」、防炎は「火に強い」と覚えるとわかりやすいですが、この違いは素材選びで非常に重要です。これを理解しないと、例えば火の近くで使う製品を誤って選び、危険な目に遭うこともあるため注意が必要です。
耐熱素材の特徴と使われる場所
耐熱素材は熱に強い素材で、主に調理器具や電子機器の部品などに使われます。
耐熱素材は高温でも形状が変わりにくく、性質が変わりにくい特徴があります。たとえば耐熱ガラスは急な温度変化にも耐えられ、直接火にかけても割れにくいです。
調理器具の取っ手、鍋敷き、電子レンジの容器など、日常生活の中で高温に触れる製品に使われます。
耐熱性の表現は「耐熱温度」として数字で示される場合が多く、耐熱温度が高いものほど高温に耐えられますが、耐熱性能が高いからといって防炎性があるとは限りません。
防炎素材の特徴とその重要性
防炎素材は火がつきにくい、または燃え広がりにくい素材や加工のことです。防炎処理されたカーテンや建材が夏場や公共の施設でよく使われています。
火災から人命や財産を守るために、防炎性能はとても大切です。しかし、防炎素材であっても完全に火を防げるわけではなく、火がつきにくかったり延焼を遅らせたりすると理解することが重要です。
また、防炎素材は燃えにくい特殊な繊維を使ったり、燃えにくくする薬品を生地に浸透させて作られます。公共施設のカーテンや衣類、テントなど安全基準が求められる場所で使われることが多いです。
耐熱と防炎の比較表
どちらを選ぶべき?使い方に合わせた素材選びのポイント
素材や製品を選ぶとき、耐熱か防炎かどちらが必要かを考えることが大切です。
火のそばや火災のリスクが高い場所では防炎素材を優先し、安全性を確保しましょう。
電子レンジや高温で使う調理器具には耐熱素材が不可欠です。
また、製品によっては耐熱と防炎の両方の性能を兼ね備えたものもありますが、予算や使用シーンに合わせて適切に選ぶことが望ましいです。
このように、耐熱と防炎の違いをしっかり理解すれば、安全かつ快適に使える製品選びができるようになります。ぜひ参考にしてください。
防炎素材というと、「火に強い素材」と思われがちですが、実は完全に燃えないわけではありません。たとえば防炎カーテンは燃えにくく、燃えても燃え広がりにくいのが特徴です。昔は防炎加工が燃えやすい繊維に薬品をかけるだけでしたが、今ではもともと燃えにくい繊維を使った素材も登場しています。つまり、防炎とは火災時の被害を抑えるための工夫であって、火を完全に止める魔法ではないんですよ。
この点を知っておくと、防炎素材の実際の意味や用途がより深く理解できます。
前の記事: « 【発火点と融点の違い】身近な物質を使ってわかりやすく解説!
次の記事: 防炎と難燃の違いを徹底解説!安全な素材選びのポイントとは? »