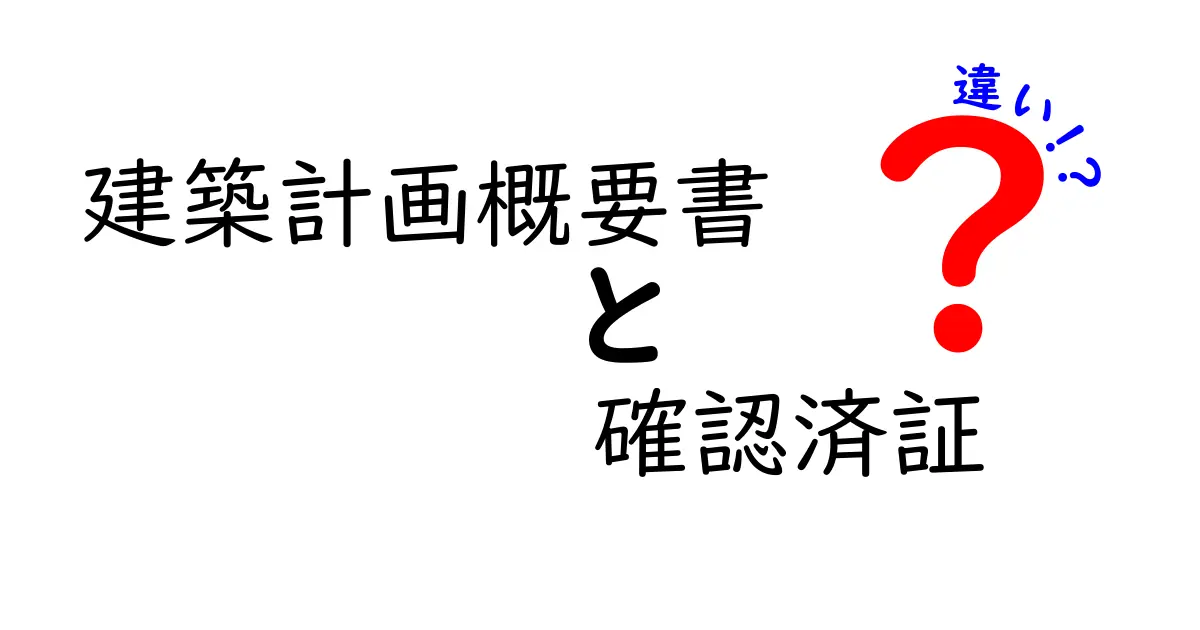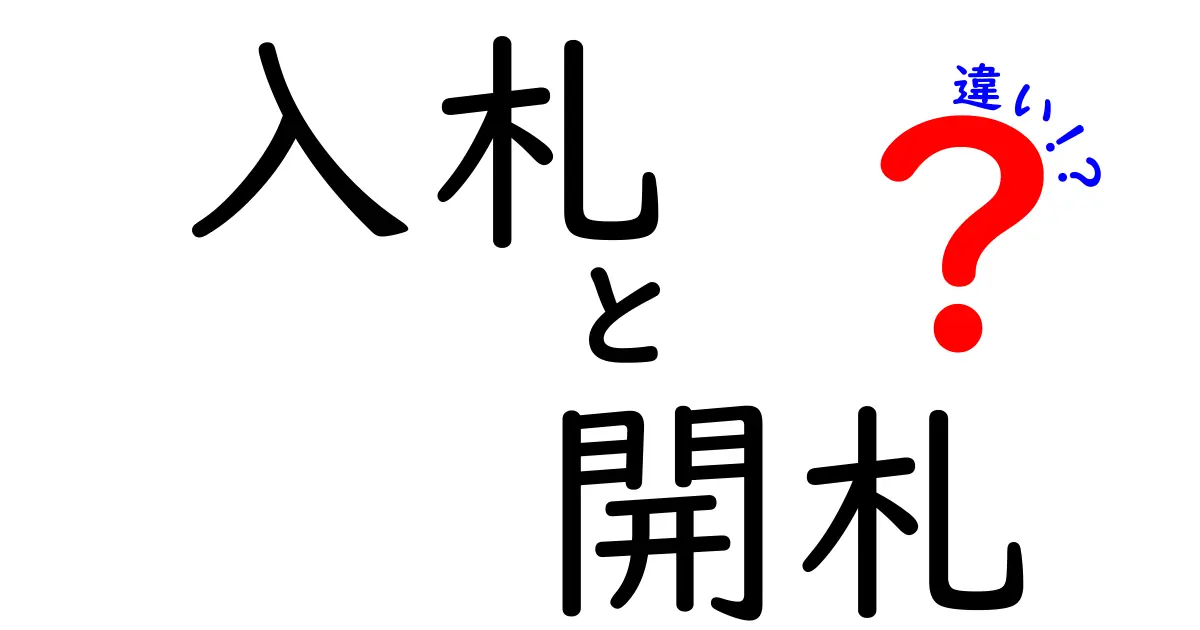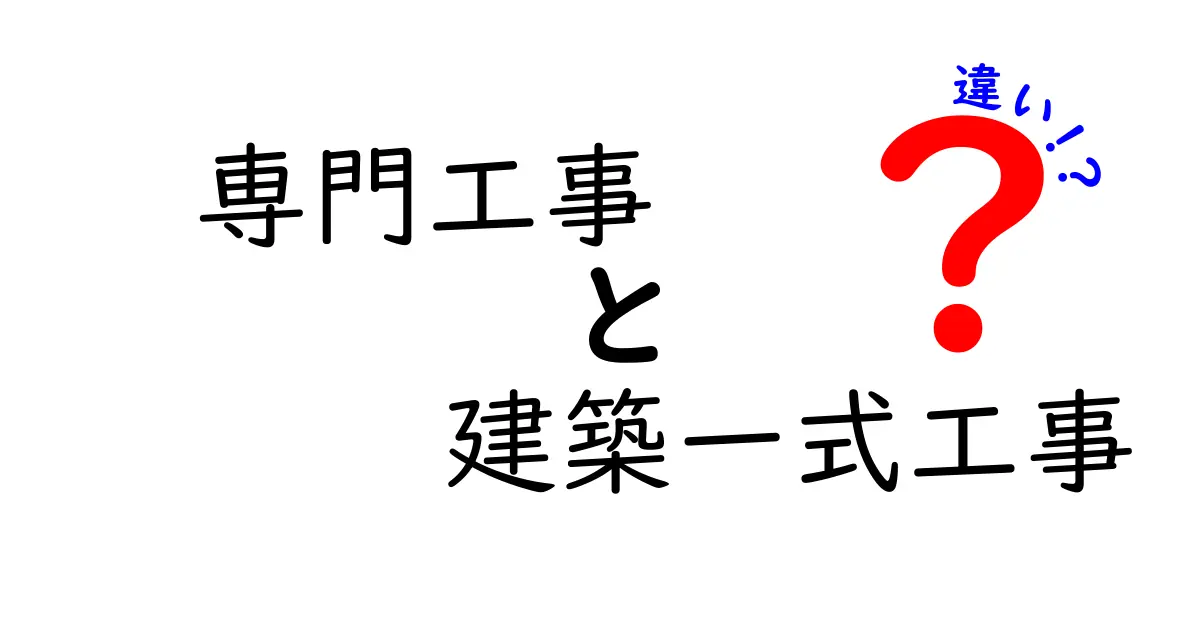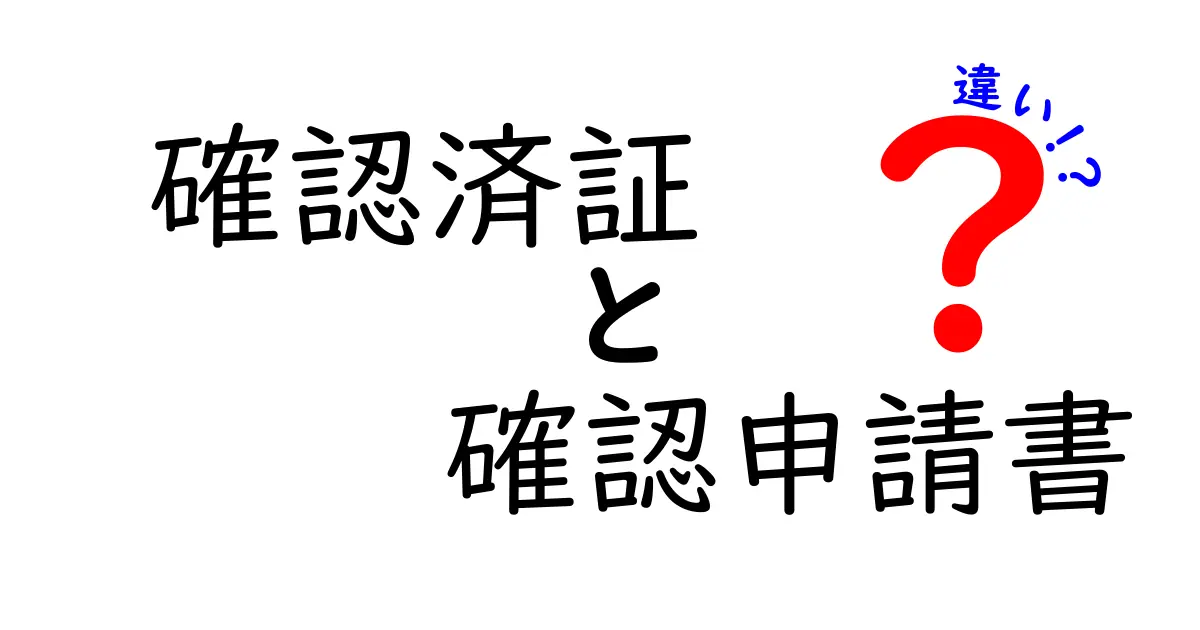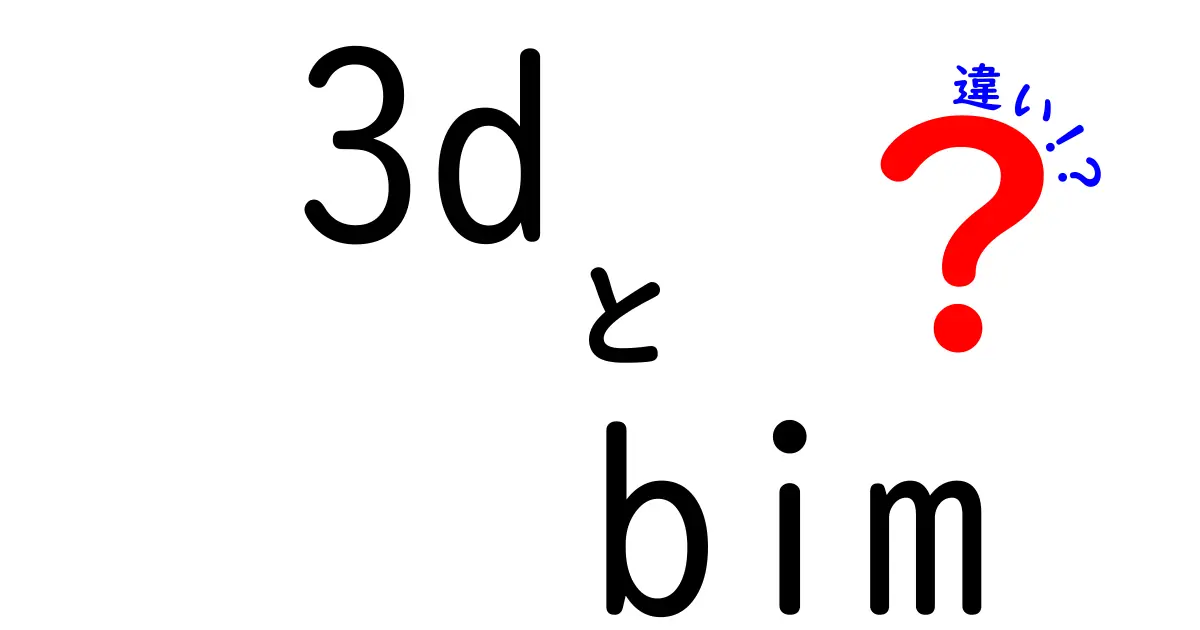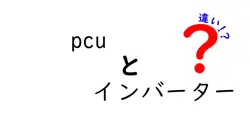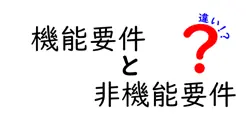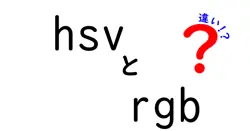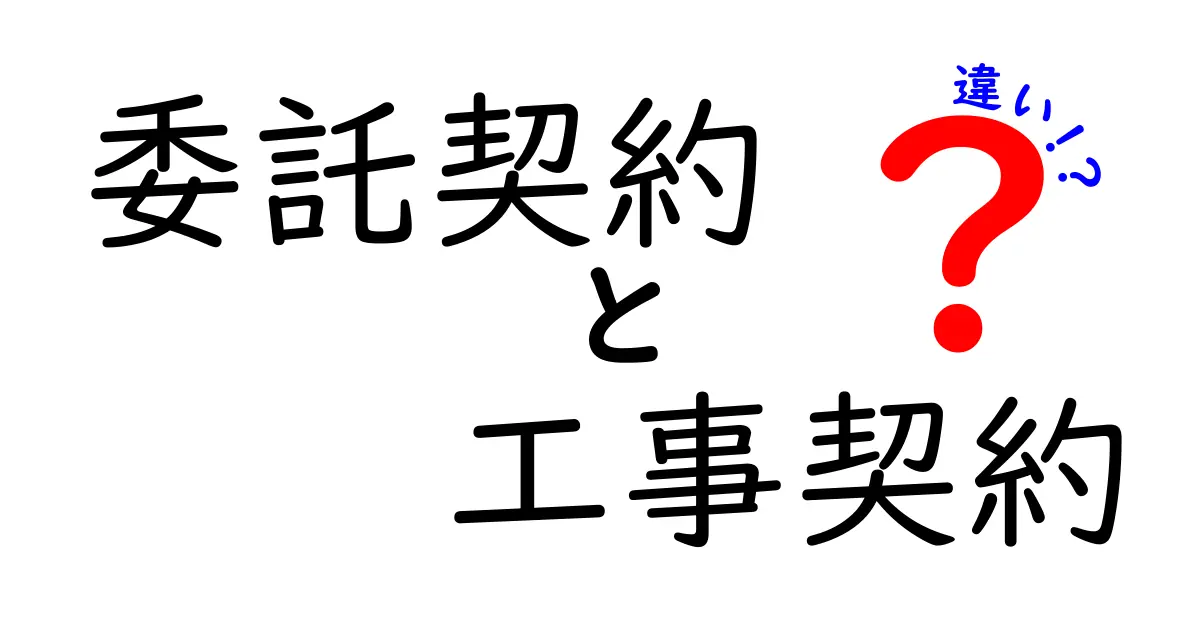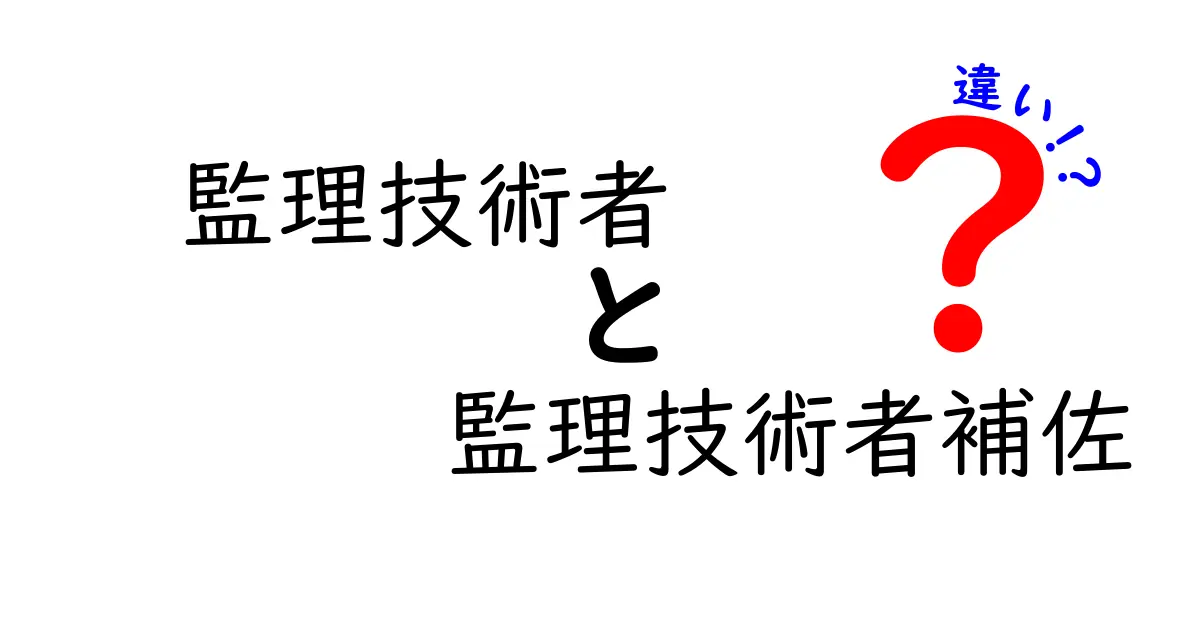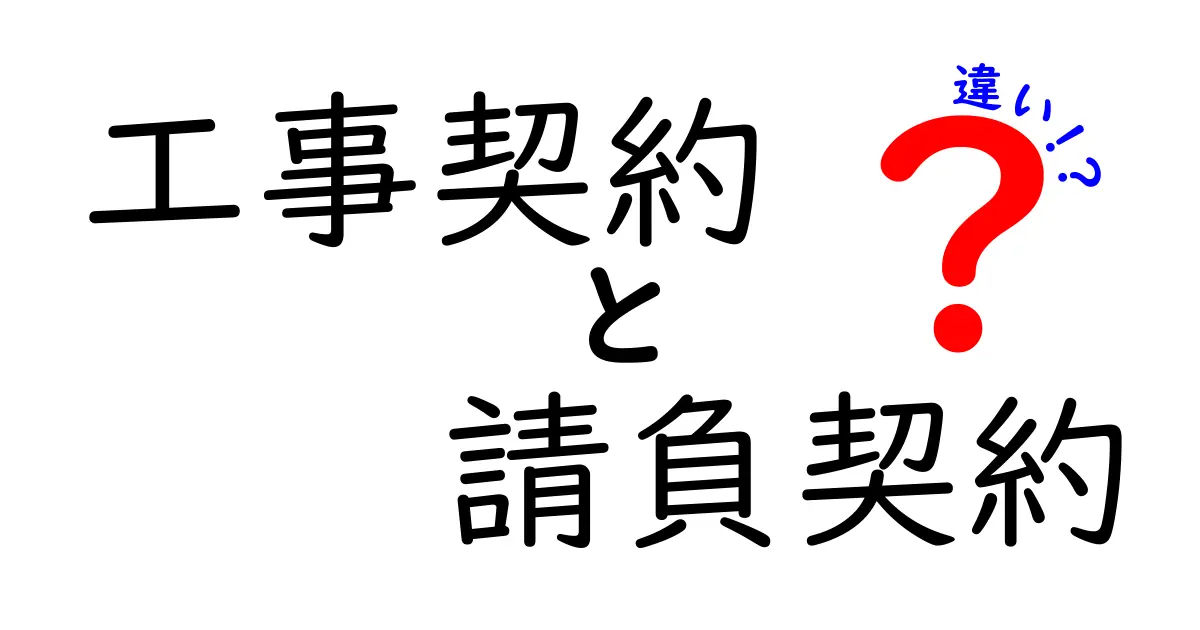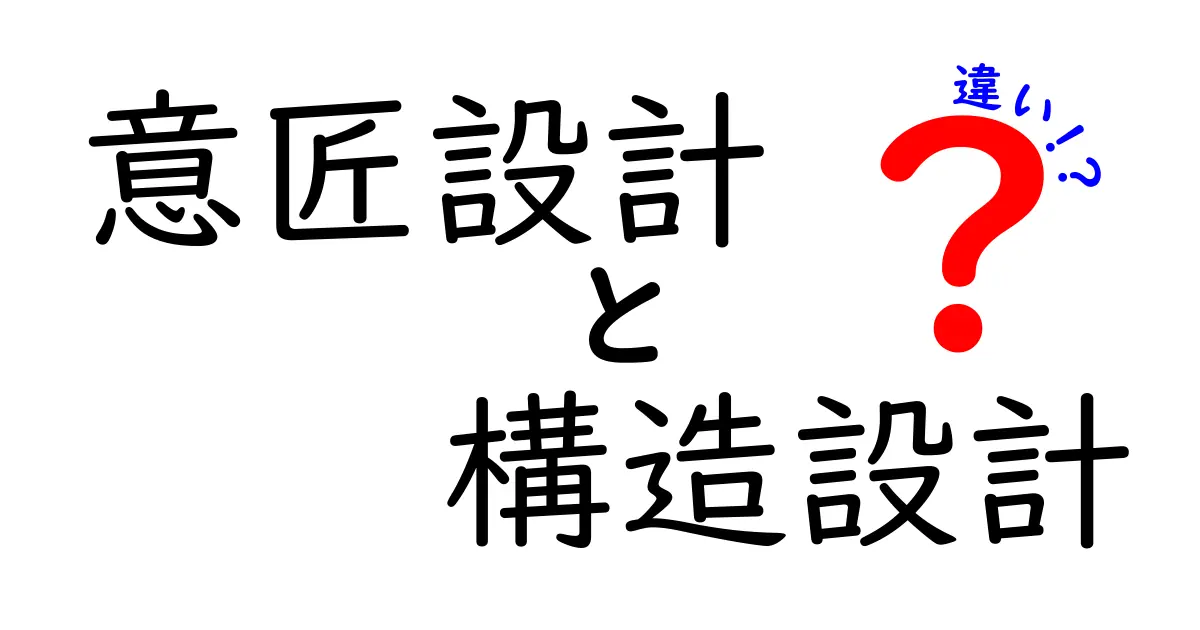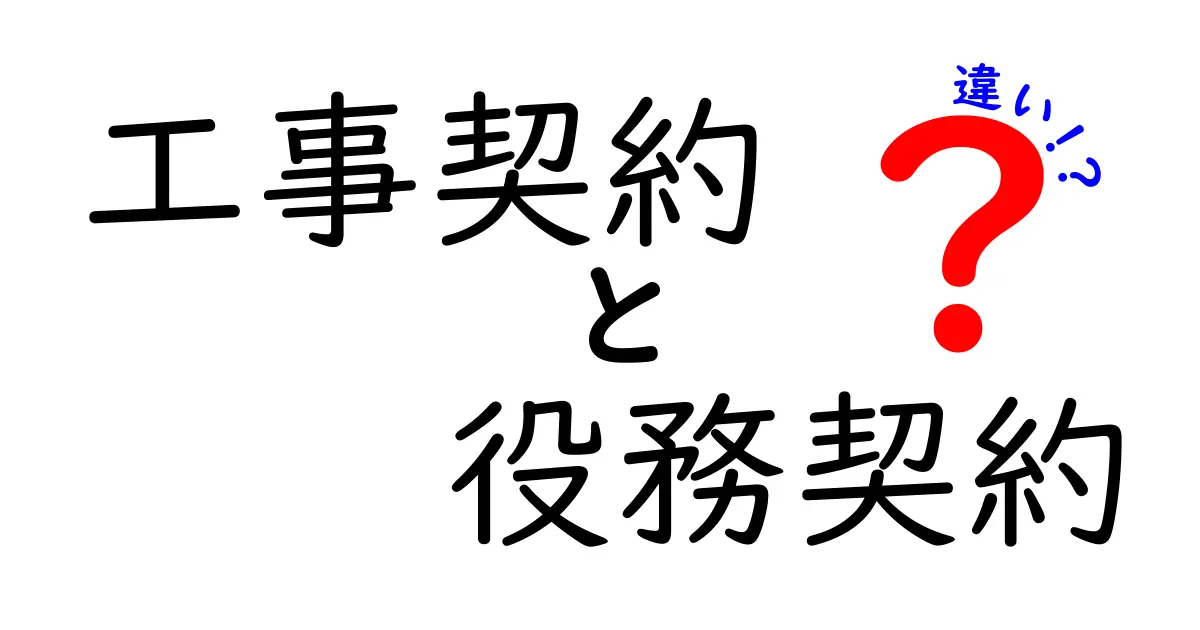
工事契約と役務契約、そもそも何が違う?
私たちの日常や仕事の中で、「工事契約」と「役務契約」という言葉を耳にすることがあります。
工事契約は、建物や設備を新しく作ったり修理したりするための契約です。一方で、役務契約は、サービスや作業そのものを提供する契約になります。
この二つの契約は似ているようで目的や内容が異なるため、正しく理解することが大切です。
たとえば、家を建てるときの「工事」は工事契約ですが、建物の清掃や管理を頼む場合は役務契約となります。
どちらの契約も法律上のルールや支払い方法、責任の範囲などに違いがあるため、トラブル防止のためにも知識を深めましょう。
工事契約の特徴とポイント
工事契約では、主に「ものを作る」「修理する」「改良する」作業が対象です。
一般的に以下のようなポイントがあります。
- 契約の目的は「有形の建造物や設備の完成」
- 成果物の引き渡しが重要なポイント
- 途中で変更や追加工事が発生することもある
- 支払いは契約内容に合わせて分割や一括など様々
- 瑕疵(かし、欠陥)に対する保証やアフターケアの期間が設けられることが多い
工事契約は目に見える成果物が納品されるため、完成の有無や品質が評価の基準になります。また、工事が完了するまでに多くの調整や管理が必要です。
発注側も受注側も、仕様や納期の確認をしっかり行うことが重要です。
役務契約の特徴とポイント
役務契約は、人の労働や技術、サービスの提供を目的とした契約です。
主な特徴には以下のようなものがあります。
- 形のないサービスや作業の提供が目的
- 成果物ではなく「提供されたサービス」で契約が成立
- 継続的にサービスを受ける場合が多い
- 契約解除や期間終了後にサービスも停止する
- 品質や対応の良さが評価基準になることが多い
たとえば、ビルの清掃や警備、コンサルティングなどは役務契約の代表例です。
契約期間中に提供される「サービスの内容」や「時間帯」などが具体的に定められることが多く、提供されたサービスの質が重要視されます。
そのため、問題があった場合は契約内容に基づいて適切な対応や補償が求められます。
工事契約と役務契約を比較した表
| 項目 | 工事契約 | 役務契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 建築物・設置物の作成・修理 | サービスや作業の提供 |
| 契約対象 | 有形の成果物 | 無形のサービス |
| 評価基準 | 成果物の完成・品質 | サービスの質・対応 |
| 支払い方法 | 分割・一括など多様 | 期間契約や作業契約が多い |
| 保証期間 | 瑕疵保証がある場合が多い | 保証は契約内容による |
| 項目 | 建築計画概要書 | 確認済証 |
| 役割 | 建築物の計画概要を示す書類 | 建築計画が法律に適合している証明書 |
| 提出時期 | 建築計画の初期段階で提出 | 建築確認申請が承認された後に交付 |
| 発行者 | 建築主や設計者が作成・提出 | 行政(建築主事または指定確認機関)が発行 |
| 目的 | 計画内容の説明と共有 | 建築の法的適合を証明 |
| 法的効力 | 特に法的効力はなし | 建築工事の着工許可として必要 |
この表を参考にすると、書類の役割や使うタイミング、発行元など様々な面で違いがあることがわかります。
どちらも建築に関する大切なものですが、用途と意味を正しく理解することが安全で確実な建築を進めるポイントです。
まとめ:建築計画概要書と確認済証を正しく理解して快適な住まいづくりを
今回は建築計画概要書と確認済証の違いをテーマに解説してきました。
初心者でもわかりやすいように説明すると、
・建築計画概要書は計画の説明書、建築の基本情報をまとめた書類
・確認済証は建築計画が法律に合っていると認められた証明書
ということがポイントです。
どちらも建築の安全性や適法性を確保するための重要な役割を果たしています。
理解していると、住宅や建物を建てる際の手続きがスムーズになり、安心して工事を任せることができます。
将来、建築に関わる場合や疑問がある時も、この違いを覚えておくと役立ちます。
快適な住まいづくりのために、ぜひ参考にしてみてください。
建築計画概要書って聞くとすぐに難しい書類を想像しちゃいますが、実はこれは建物の計画をざっくりまとめたメモのようなものなんです。
例えば、学校のクラスで行う遠足の計画を先生に簡単に説明するイメージですね。
この概要書で計画が大まかに理解できたら、次に法律に合っているかのチェックが入ります。
それが確認済証としての役割だから、順番としては建築計画概要書が先にあるというのが自然なんです。
こんな風に考えると、2つの書類の違いや役割もイメージしやすくなりますよ。