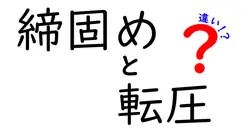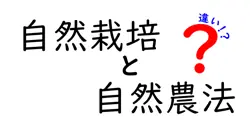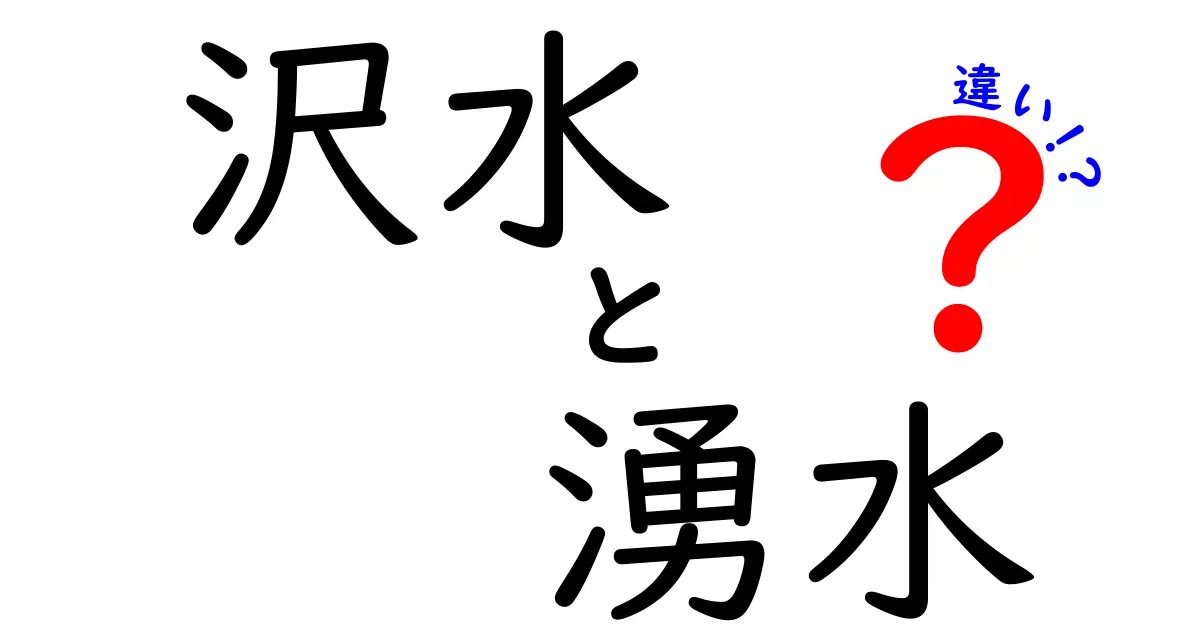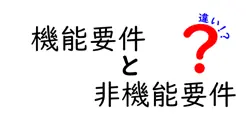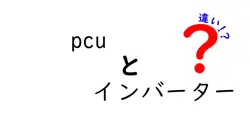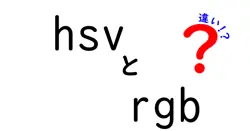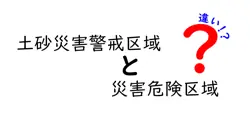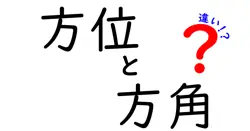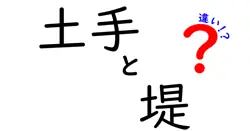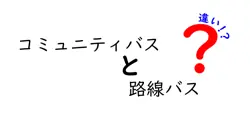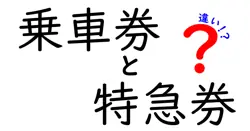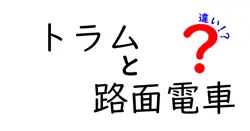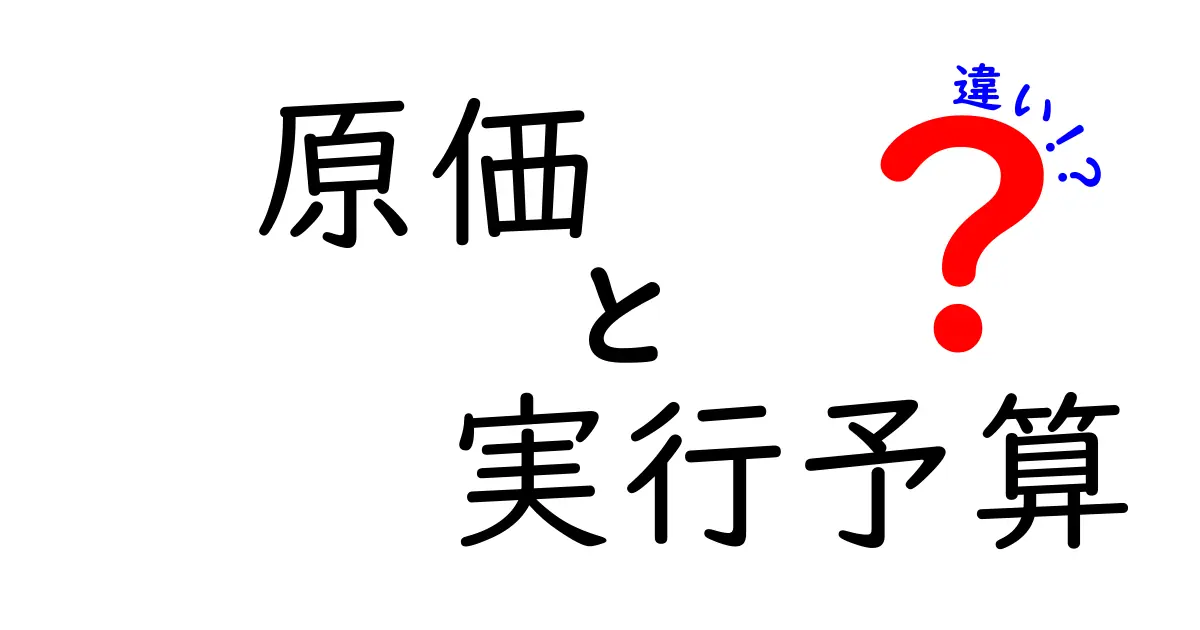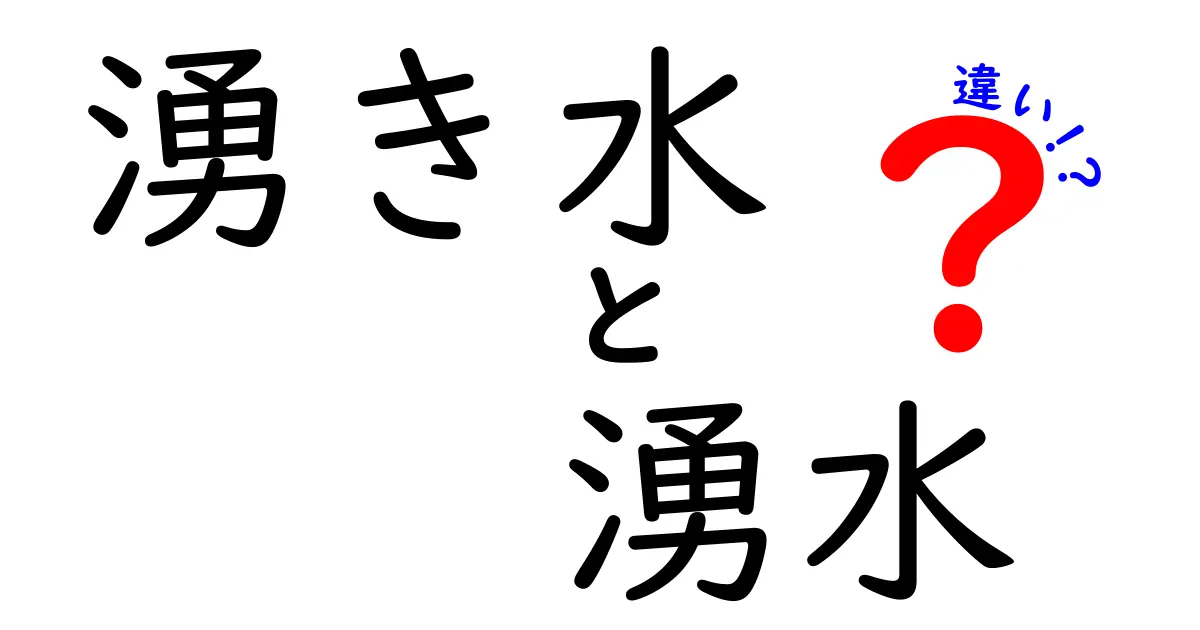
湧き水と湧水、どちらが正しい?言葉の違いについて
私たちが自然の中で見かける清らかな水の湧き出る場所を表す言葉には「湧き水」と「湧水」という2つがあります。見た目も意味もほとんど同じに思えますが、実は使い分けや由来に少し違いがあります。
「湧き水」は、動詞「湧く(わく)」に助詞の「き」と名詞の「水」を組み合わせた言葉で、特に口語や日常会話で多く使われます。一方「湧水」は、「湧」と「水」という漢字を組み合わせた熟語で、文章や公的な文書、地理用語として使われることが多いです。
このように「湧き水」は話し言葉に近く、「湧水」は文章的でフォーマルな印象を持っています。どちらも自然からわき出る水であることに変わりはありません。
実際の使い分け事例と意味の違い
日常生活では「湧き水」は親しみやすく、散策やアウトドアの際によく使われます。例えば「近所の公園にはきれいな湧き水があるよ」といった形です。
それに対し、「湧水」は地理学や環境学、行政の文書などの専門的な場面でよく使われます。例えば「この地域の湧水は水質が良い」といった表現です。
こうした使い分けは絶対的なルールではありませんが、話し言葉では「湧き水」、書き言葉や正式な資料では「湧水」と覚えておくとよいでしょう。
以下の表にまとめてみました。
| 言葉 | 読み | 特徴 | 使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 湧き水 | わきみず | 動詞の形を生かした言葉 話し言葉で多用 | 日常会話、観光案内 アウトドア情報等 |
| 湧水 | ゆうすい、わきみず | 熟語的な形 書き言葉・専門的文章 | 地理学、環境学 行政文書等 |
| 項目 | 沢水 | 湧水 |
|---|---|---|
| 水の出どころ | 雨水や雪解け水が地表を流れて集まる水 | 地下水が地表に自然に湧き出る水 |
| 水質の特徴 | 自然の影響を受けやすく不安定 | 地中でろ過されて清らかで安定 |
| 水量の変化 | 季節や天候で変動しやすい | 比較的安定している |
| 主な利用 | 自然観察や一時的な利用 | 飲み水や農業用水、観光資源 |
まとめ:沢水と湧水、それぞれの役割と魅力
沢水は山に降った雨や雪が集まって流れる水で、季節や天候により変わりやすい特徴があります。
自然の中で生きる生き物たちにとって水場となり、自然のサイクルの一部を担っています。
湧水は地下に染みこんだ水が地表に湧き出たもので、清らかでミネラルが豊富なことが多いです。
昔から生活用水や農業用水として重宝され、大切な自然の資源となっています。
このように、一見似ているようで、沢水と湧水はその成り立ちや特徴、利用のされ方に大きな違いがあります。
これを知ることで、自然の水のありがたさやその大切さをもっと感じられると思います。
ぜひ、自然の中で水を見かけたときには『これは沢水かな?それとも湧水かな?』と考えてみてくださいね!
湧水って、実は地下の“天然のろ過装置”を通って地上に出てくるんです。
だからとってもキレイでミネラルも豊富なんですよ。
昔の人はこの湧水を神聖なものとして大切に扱っていました。
ただし場所によっては湧水が枯れることもあるので、守ることが大切ですね。
自然と地下の関係って面白いですよね!
前の記事: « 信号ケーブルと通信ケーブルの違いとは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: 湧き水と湧水の違いとは?意外と知らない言葉の使い分けを解説! »
自然の人気記事
新着記事
自然の関連記事
信号ケーブルと通信ケーブルの違いとは?わかりやすく徹底解説!
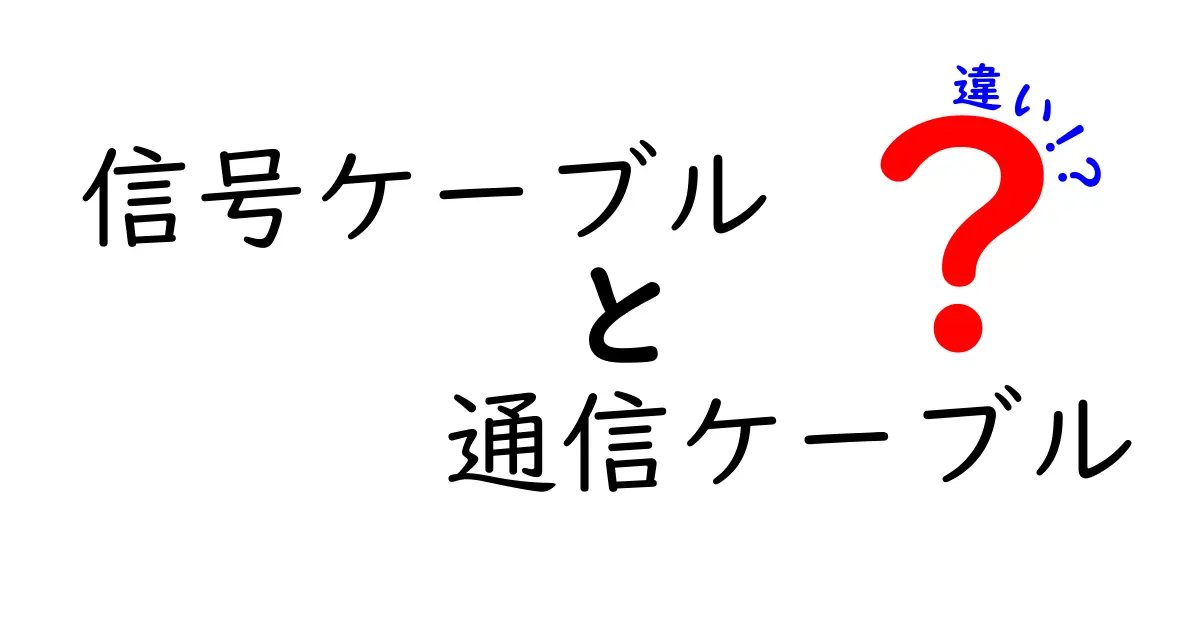
信号ケーブルと通信ケーブルの基本的な違いとは?
電子機器を使う上でよく聞く言葉に「信号ケーブル」と「通信ケーブル」があります。これらはどちらもデータや情報を伝えるためのケーブルですが、役割や性能、使われる場所には明確な違いがあります。
まず、信号ケーブルとは、機械や装置の中で信号(音声、映像、制御信号など)を伝えるためのケーブルです。主に機械内部や家電製品の中で用いられ、電気信号を正確に伝えることが目的となっています。
一方、通信ケーブルは、遠く離れた場所同士のデータのやり取りを行うためのケーブルです。インターネット接続や電話回線など、多くの情報を高速かつ安定して送受信することが求められます。
このように、信号ケーブルは主に機械内部の信号伝達に、通信ケーブルは外部とのデータ通信に使われるという違いがあります。
信号ケーブルと通信ケーブルの特徴をわかりやすく比較
信号ケーブルと通信ケーブルの違いをより理解しやすくするため、性能や用途などの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 信号ケーブル | 通信ケーブル |
|---|---|---|
| 主な用途 | 音声や映像の機器内伝送、制御信号の伝達 | インターネットや電話など遠距離データ通信 |
| 伝送距離 | 短距離(数cm~数m) | 長距離(数十m~数km) |
| 伝送速度 | 比較的低~中速 | 高速(ギガビット単位もあり) |
| ノイズ対策 | シールドやツイストペアを使用 | 高度なノイズ対策と誤り訂正機能あり |
| 代表的な種類 | 同軸ケーブル、オーディオケーブル、制御用ケーブル | LANケーブル(Ethernet)、光ファイバーケーブル、電話線 |
このように、通信ケーブルは厳しい通信環境でも安定した高速伝達を可能にするために設計されています。一方で、信号ケーブルは機器内部での安定した信号伝達に重点を置いています。
実際の使い方と選び方のポイント
どんなケーブルを使うべきか迷ったときは、以下のポイントを参考にするといいでしょう。
1.使用環境と距離を確認する
機器内部や短距離なら信号ケーブル、遠距離やネットワーク接続なら通信ケーブルが適しています。
2.伝送する信号の種類と速度
映像や音声の単純な信号なら信号ケーブルでも十分ですが、映像の高解像度化や高速なデータ通信には通信ケーブルが必要です。
3.ノイズ対策
周囲に電気的ノイズが多い場合は、ノイズ対策が優れた通信ケーブルを選ぶことでトラブルを防げます。
さらに、最近では光ファイバーを使用した通信ケーブルが増えてきていて、これによりより高速で長距離の通信が実現されています。
用途に応じた正しいケーブル選びが、機器の性能を最大限に引き出すポイントです。
信号ケーブルと言うと、家の中の電気製品をつなぐためのケーブルが浮かびますよね。でも面白いのは、同じ「信号」でも鉄道の信号システムにも使われているんです。鉄道の信号ケーブルは、列車の安全運行に欠かせない情報伝達を担っていて、耐久性が非常に高く作られています。こうした専門的な用途もあるからケーブル選びは奥が深いんですよ。
前の記事: « 【徹底比較】TBM工法とシールド工法の違いとは?初心者向け解説!
次の記事: 沢水と湧水の違いとは?自然の水が持つ特徴をわかりやすく解説! »
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
【徹底比較】TBM工法とシールド工法の違いとは?初心者向け解説!
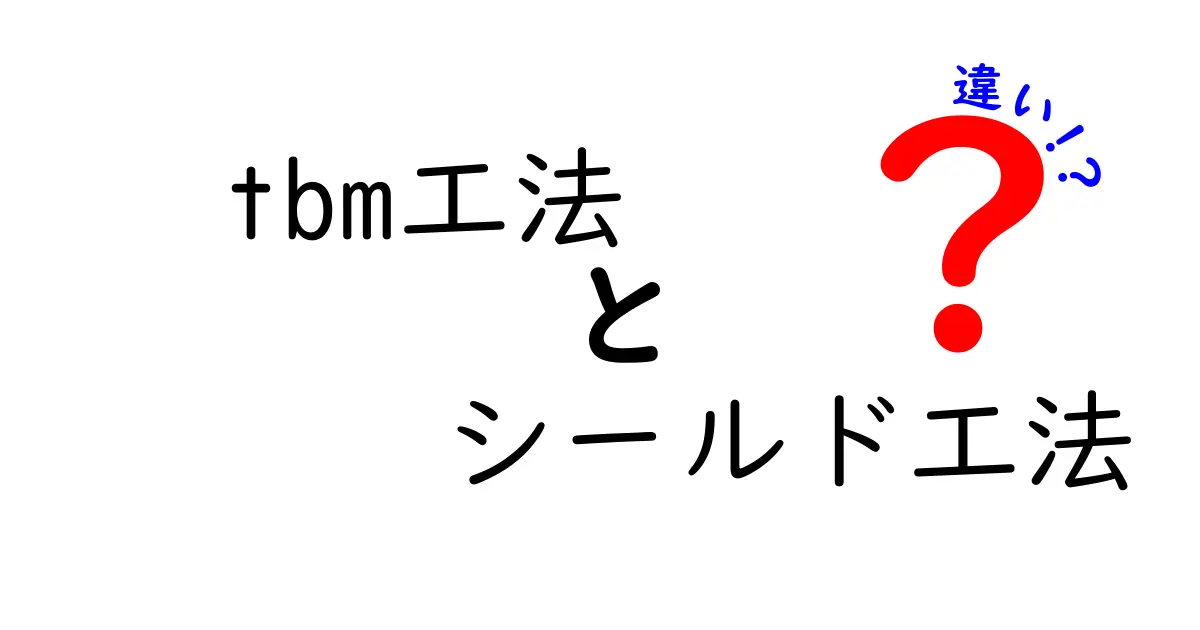
TBM工法とシールド工法の基本とは?
トンネルを掘る工法には様々な方法がありますが、TBM工法(トンネルボーリングマシン工法)とシールド工法は特によく使われる技術です。
まず、TBM工法は掘削機械の先端に丸いドリルのような掘削刀を備え、地下を掘り進めながらトンネルを一気に掘り進める方法です。
一方、シールド工法は、掘削機械の前方に覆い(シールド)を設置しながら掘削を行うため、地盤がゆるい場所でも崩れにくく安全に掘り進める特徴があります。
どちらも地下トンネルの掘削に使われる技術で、機械を使って地中を掘る点は共通していますが、構造や使い方、適応する地質で違いがあります。
ここからは、両工法をさらに詳しく分かりやすく見ていきましょう。
TBM工法とシールド工法の違いとは?
1. 機械の構造
TBM工法では、専用の掘削機械(TBM)を使い、掘削盤が地盤を回転して掘り進めます。
掘削後は機械がトンネル断面の形に合ったセグメントを設置してトンネルの壁を作ります。
シールド工法では、掘削機械の周りをシールドと呼ばれる円筒形の外装で覆い、地盤の崩壊を防ぎます。
掘削装置はシールド内にあり、掘り出した土を機械後方に運びながら掘削し、同時にトンネルの壁も設置していきます。
2. 適用地盤の違い
TBM工法は比較的硬い岩盤や土質に適していて、長い距離のトンネル掘削に向いています。
ただし地盤が非常に軟弱な場合、掘削時に崩壊が起きるリスクがあります。
シールド工法は軟弱地盤や湧水の多い地点などで活躍します。
シールドが地盤を支えながら掘削するので、安全に掘り進められます。
3. 工期やコストの違い
TBM工法は機械の性能によって高速で掘進が可能ですが、機械の準備や運搬に時間と費用がかかります。
シールド工法は安全や地盤の安定性を重視するため施工が慎重で、現場の状況に応じて工期が延びる場合があります。
一般的には、現場の地質条件によってどちらを使うか判断されます。
TBM工法とシールド工法の比較表
| ポイント | TBM工法 | シールド工法 |
|---|---|---|
| 適用地盤 | 硬い岩盤や良好な土質 | 軟弱地盤や湧水地帯 |
| 掘削機構 | 掘削盤が回転して掘る | シールドで覆いながら掘る |
| 安全性 | 堅い地盤で安全 | 軟弱地盤でも崩壊防止 |
| 工期 | 速いが準備時間が必要 | やや慎重で時間がかかる |
| コスト | 機械費用が高い | 施工管理費用が多め |
まとめ:どちらを選ぶ?
TBM工法は硬い地盤で効率よく長距離トンネルを掘るのに適した方法です。
そのため、新幹線や高速道路の長いトンネルなどで多く使われます。
シールド工法は地盤の崩壊を防ぎ安全に掘進できるため、都市部の軟弱な地盤や地下鉄工事でよく用いられます。
つまり、地盤の性質や工事の場所・条件によって、TBM工法とシールド工法は使い分けられているのです。
どちらの工法も高い技術が必要で、安全のための綿密な計画が重要です。
トンネル工事を見る時は、それぞれの特徴を知って工程を見守るとより楽しくなりますよ!
今回はTBM工法とシールド工法の違いについて解説しましたが、実は『TBM』という言葉自体が重厚な機械のイメージを持たれることが多いです。TBMとはトンネルボーリングマシンの略で、その巨大な機械は地下を高精度で掘り進めるロボットのような存在です。昔は人力や爆破で掘ることも多かったですが、現在ではTBMの滑らかな掘削でトンネル工事が格段に安全かつ高速になっています。こうした機械技術の進歩が未来のインフラ整備に不可欠なのですね。
前の記事: « トンネルと地下道の違いって何?わかりやすく解説!
次の記事: 信号ケーブルと通信ケーブルの違いとは?わかりやすく徹底解説! »
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
トンネルと地下道の違いって何?わかりやすく解説!
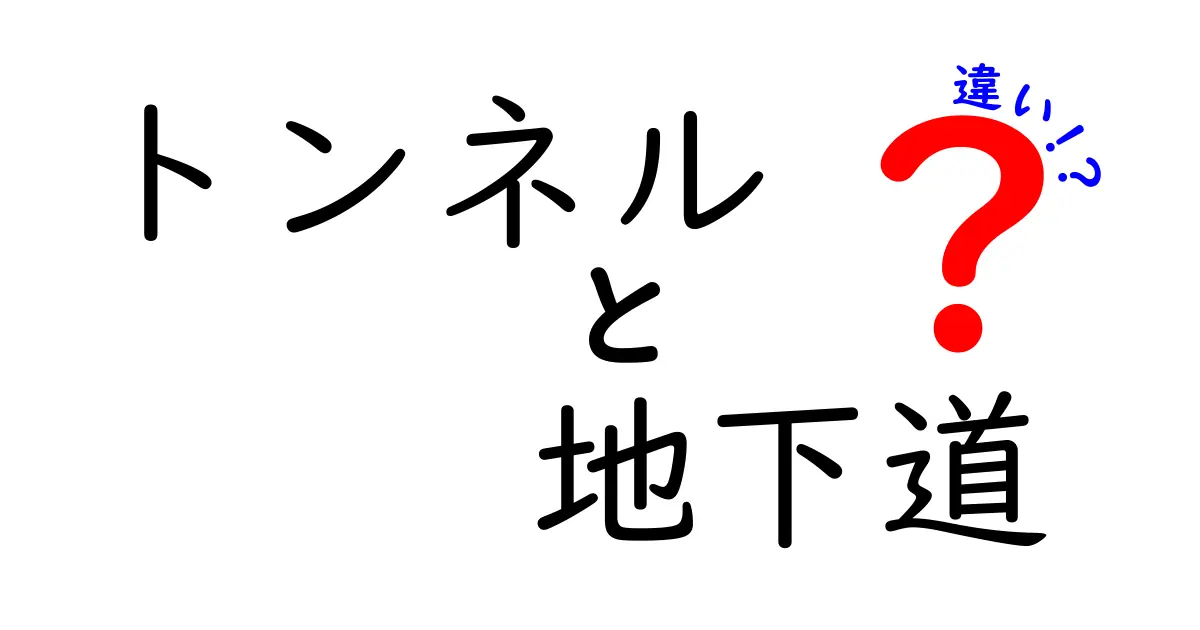
トンネルと地下道は何が違う?まずは基本の意味を理解しよう
私たちが街中でよく目にするトンネルや地下道。どちらも地下を通って人や車が通る通路ですが、実はそれぞれに違いがあります。
トンネルとは、山や川の下を車や電車、人が通るために掘られた人工の地下通路のことを指します。交通の便を良くするための大きな建造物で、例えば高速道路のトンネルや鉄道トンネルなどがこれに当たります。
一方、地下道は主に人が安全に道路を渡るために作られた地下の通路です。歩行者専用であることが多く、駅の地下や道路の下に設置されていることが多いです。地下道は通勤通学時に多くの人が利用し、交通事故を防ぐ役割も持っています。
このように、トンネルと地下道は「誰が通るのか」「どのような目的で作られるか」が違うのです。
用途や規模の違いを表にしてみた!
トンネルと地下道の違いをまとめると次の表のようになります。
| ポイント | トンネル | 地下道 |
|---|---|---|
| 主な利用者 | 車、電車、人 | 歩行者のみ |
| 目的 | 交通の短縮や地形の障害回避 | 歩行者の安全確保、道路横断 |
| 規模 | 大きく長い | 比較的小さい |
| 設置場所 | 山や川の下、長距離区間 | 駅近辺や道路の下、都市部 |
| 安全設備 | 換気設備や非常用通路があることが多い | 照明や手すり、スロープが設置されていることが多い |
トンネルと地下道、知っておきたいポイント
さらに違いをわかりやすくするためのポイントをお伝えします。
- 交通手段の違い:トンネルは車や電車も利用できることが多いのに対し、地下道は基本的に人だけです。
- 長さや規模の違い:トンネルは山や川を通り抜けるため長いですが、地下道は道路の下を渡る程度なので短いことがほとんどです。
- 安全設備の違い:トンネルは大きな構造物で換気や非常口が設けられていますが、地下道は歩行者の安全を守るための手すりや滑りにくい床材が使われています。
これらの違いを知っていると、街を歩くときに見かけたトンネルや地下道の役割をより正確に理解できるようになります。
地下道というと「ただの通路」と思いがちですが、実は地下道の設計にはたくさんの工夫が隠されています。たとえば、地下道の床は滑りにくい素材が使われていて、急いでいる人も安全に通れるようになっています。さらに、手すりがあることでお年寄りや子供も安心して利用できます。また、地下道には案内表示がしっかり設置されており、初めて使う人でも迷わないように工夫されているんですよ。こう考えると、地下道はただの通路以上に“みんなの安全を守る道”なんですね。町の中で見かけたら、ちょっと気にしてみると面白いかもしれません。
次の記事: 【徹底比較】TBM工法とシールド工法の違いとは?初心者向け解説! »
地理の人気記事
新着記事
地理の関連記事
シールド工法とセミシールド工法の違いを徹底解説!初心者でもわかる鉄道・トンネル工事の基礎知識
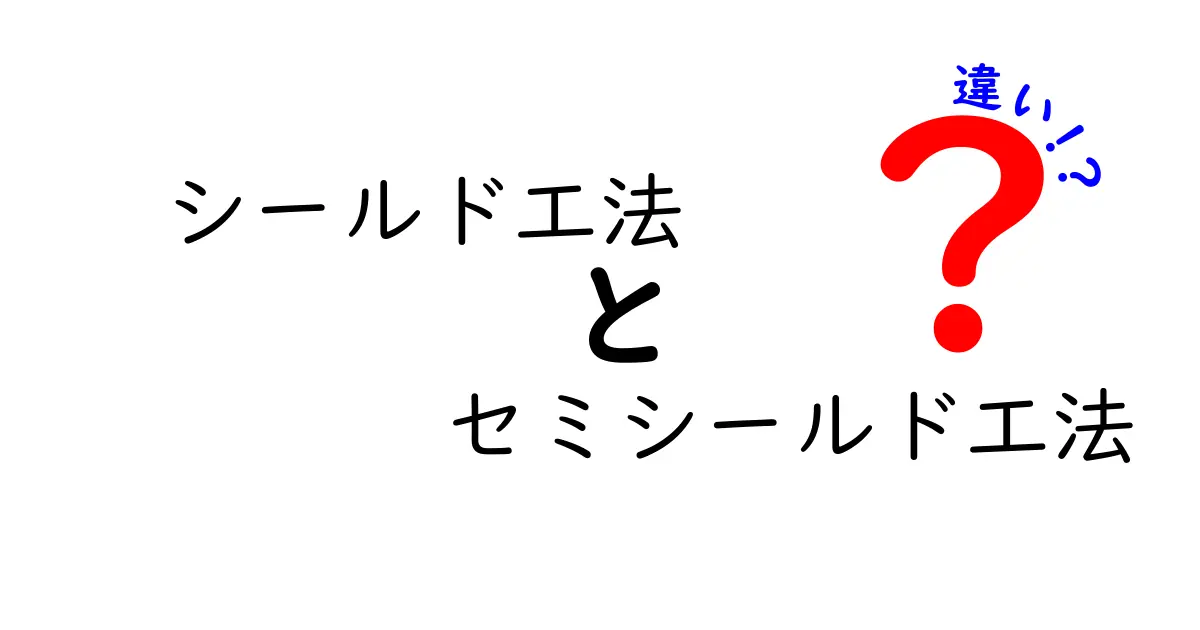
シールド工法とセミシールド工法とは?
まず最初に、シールド工法とセミシールド工法の基本的な意味について説明します。
シールド工法は、地下のトンネルや鉄道などを掘るときに使われる工事の方法の一つです。巨大な円筒形の機械、通称「シールドマシン」を使って、地面を掘りながらトンネルの壁を作っていく工法です。これにより地下の土や岩が崩れにくく、作業が安全に行えます。
一方、セミシールド工法は、シールド工法の特徴を一部取り入れつつ、地盤の状態や工事の目的に合わせて圧力管理を部分的に行う工法です。名称の通り『セミ(半分の)シールド』という意味で、完全に閉じたシールド内部の圧力制御はしませんが、地下水や土圧の影響を和らげるための工夫を行います。
この二つの工法は似ているようで異なり、使用される場所や安全性、工事の難しさが異なります。
「セミシールド工法」は、完全なシールド工法と比べて圧力制御が部分的なので作業の自由度が高く、コストも抑えられる場合があります。ですが、地盤が弱い場所や地下水が多い場所ではトラブルになりやすいので、その使いどころの見極めが非常に重要なんですよ。まるでハーフマラソンとフルマラソンの違いみたいに、それぞれの特徴を理解することが大切なんです。
次の記事: トンネルと地下道の違いって何?わかりやすく解説! »
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
地下鉄と東京メトロの違いをわかりやすく解説!利用者が知っておくべきポイントとは?
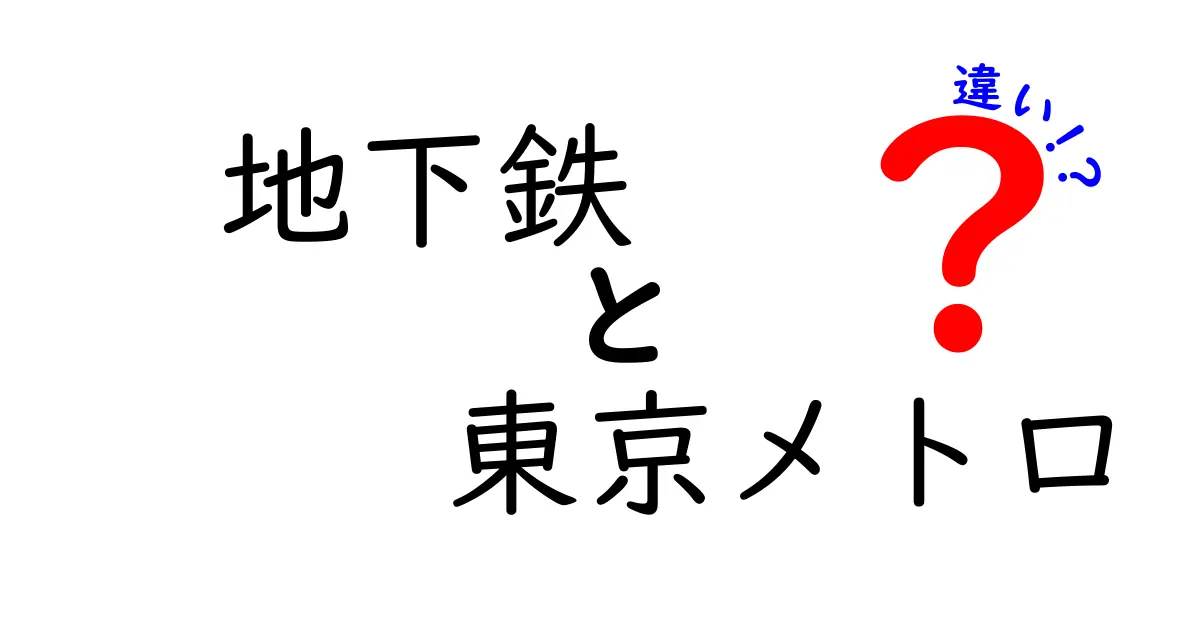
地下鉄とは?基礎知識をチェックしよう
まず、地下鉄とは、都市の地下に走る鉄道システムのことを指します。都市部の交通渋滞を防ぎ、多くの人がスムーズに移動できるように設計された公共交通機関です。
日本全国の主要都市にはそれぞれ地下鉄が存在し、東京だけでも複数の地下鉄会社が路線を運営しています。地下鉄は施設全体の総称であり、具体的な運営会社や路線名が存在します。
こうした地下鉄は都市の発展や交通需要に応じて拡大しており、多くの利用者にとって便利な移動手段となっています。
東京メトロとは?地下鉄との関係
一方、東京メトロは東京にある地下鉄路線のうち、主に6つの路線を運営する民間企業の名前です。簡単に言えば、地下鉄の運営会社の一つが東京メトロです。
東京メトロは1954年に設立され、その後、東京都交通局(都営地下鉄)と共に東京の地下鉄網を支えています。
つまり、地下鉄は鉄道システムの「総称」であり、東京メトロは東京地下鉄グループの「運営会社」の名称。利用者が使う駅名や路線図にも「東京メトロ」の名前が表示されています。
地下鉄と東京メトロの違いを表で比較してみよう
| 項目 | 地下鉄 | 東京メトロ |
|---|---|---|
| 定義 | 都市部の地下にある鉄道システム全般 | 東京の地下鉄路線を運営する鉄道会社の名称 |
| 運営主体 | 複数の会社や自治体が運営(例:東京メトロ、都営地下鉄など) | 民間企業(東京地下鉄株式会社) |
| 路線数 | 東京の場合、地下鉄全体で約13路線以上 | 6路線 |
| エリア | 全国の主要都市に存在 | 東京都内が中心 |
| 料金体系 | 会社や自治体ごとに異なることが多い | 東京メトロ独自の料金体系 |
地下鉄と東京メトロの違いを知っておくメリット
なぜこの違いを知ることが大切なのでしょうか?
まず、乗車料金や乗り換え方法に関わるポイントを押さえられること。たとえば、東京では東京メトロと都営地下鉄で料金体系が異なり、ICカードでスムーズに乗り換えが可能ですが、時には追加料金がかかる場合があります。
また、旅行や引っ越し、通勤通学で地下鉄を使う際に、どの会社の路線を利用するか知ることで、チケットの購入や路線検索がスムーズになります。
このように地下鉄全体の仕組みと東京メトロの役割を理解しておくことで、より賢く地下鉄を利用できるようになるのです。
東京メトロが運営する路線には、銀座線や丸ノ内線など有名なラインがありますよね。実は、東京メトロの路線は歴史的に見ても日本で最も古い地下鉄路線の一つも含まれています。例えば、銀座線は1927年に開業し、日本初の地下鉄路線として有名です。なので、東京メトロの路線を使うことで、日本の地下鉄の歴史を体感しているとも言えるんですよ。ちょっとした雑学としても面白いポイントです。
地理の人気記事
新着記事
地理の関連記事
通信ケーブルと電力ケーブルの違いをわかりやすく解説!用途や構造のポイントを徹底比較
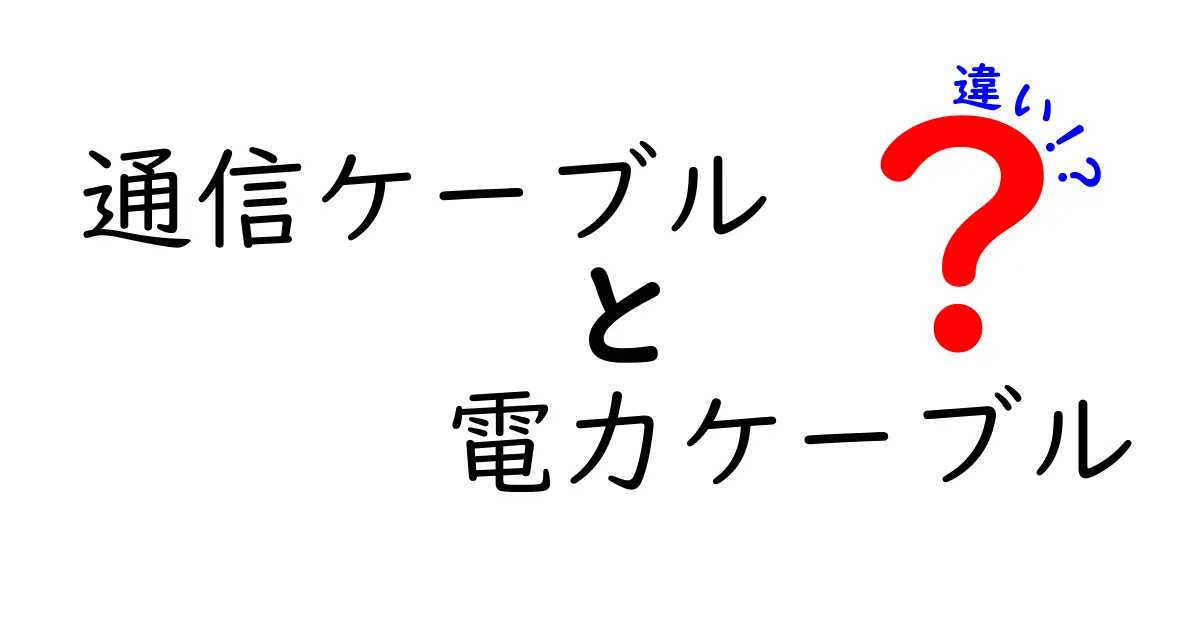
通信ケーブルと電力ケーブルの基本的な違いとは?
私たちの生活に欠かせない配線には、大きく分けて通信ケーブルと電力ケーブルがあります。見た目では似ていることもありますが、実はそれぞれ全く違う役割と構造を持っています。通信ケーブルは情報を伝えるためのもの、電力ケーブルは電気を送るためのものです。
通信ケーブルは電話回線、インターネット接続、テレビ信号などのデータ伝送に使われます。一方で電力ケーブルは家庭や工場に電気を届け、コンセントや大型機械に電気を供給します。
このように利用目的によって設計や性能が大きく異なっているのが大きな特徴です。
通信ケーブルと電力ケーブルの構造の違いを表で比較
それでは、通信ケーブルと電力ケーブルの構造の違いを具体的に見ていきましょう。以下の表にまとめました。
| 項目 | 通信ケーブル | 電力ケーブル |
|---|---|---|
| 用途 | データや信号の伝送 | 電力供給 |
| 導体素材 | 細い銅線や光ファイバー | 太い銅線やアルミ線 |
| 絶縁体 | ノイズ防止のための絶縁とシールドあり | 電気漏れ防止用の厚い絶縁 |
| 構造 | 複数の細い芯線や繊維の束 | 単芯や多芯で太い太さ |
| 耐熱性 | 中程度 | 高い熱耐性が必要 |
| シールド | ノイズ対策で必須 | 通常不要 |
通信ケーブルの特徴詳細
通信ケーブルは、電話回線やLANケーブル、光ファイバーなど数多くの種類があります。情報の伝送速度や信号品質を良くするために、絶縁体やシールドがしっかり施されています。
特にノイズに強い構造が重要で、外部の電磁波から信号を守るためにアルミ箔や銅の編組シールドが使用されます。
また、細い銅線がたくさん集まって信号を安定的に伝えるようになっている場合も多いです。光ファイバーケーブルは光の反射を利用して遠くまで高速伝送するため、金属線とは違う素材を使っています。
電力ケーブルの特徴詳細
一方で電力ケーブルは、強い電流を安全に通すために太くて丈夫な導体を持っています。家庭用のコンセントにつながるケーブルや、送電線まで様々な種類があります。
電力を確実に運び、事故を防ぐために耐熱性や絶縁が重視されていて、外側の被覆も硬くて頑丈です。
また、シールドは基本的に不要ですが、特殊な環境では電磁波の影響を抑えるためのシールドが使われることもあります。
まとめ
通信ケーブルと電力ケーブルの違いは、何を送るか(データか電力か)で大きく違ってきます。
通信ケーブルはノイズを防ぎながらデータを正確に届けるのが重要で、そのために繊細な構造やシールドが施されています。
一方、電力ケーブルは大量の電気を安全かつ効率的に届けることを重視し、太くて高耐熱性の材料を使っています。
このような違いを知ることで、ケーブルを選ぶ時やトラブル対策で役立てていただければ幸いです。
通信ケーブルでよく使われる“シールド”って実は面白いんですよ。シールドは外からのノイズを防いで信号を守る役割があり、アルミ箔や銅の編組で作られてます。特にLANケーブルの中には2重や3重構造のシールドがあるものもあり、これは隣のケーブルや家電製品からの電磁波を防ぐため。意外と目立たないけど、通信の安定性に超重要な役割を果たしているんです。だからケーブル売り場でシールドの種類をチェックすると、信号の強さや安定感が変わるヒントが得られますよ!
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
労働安全衛生法と安全衛生法の違いとは?初心者にもわかりやすく解説!
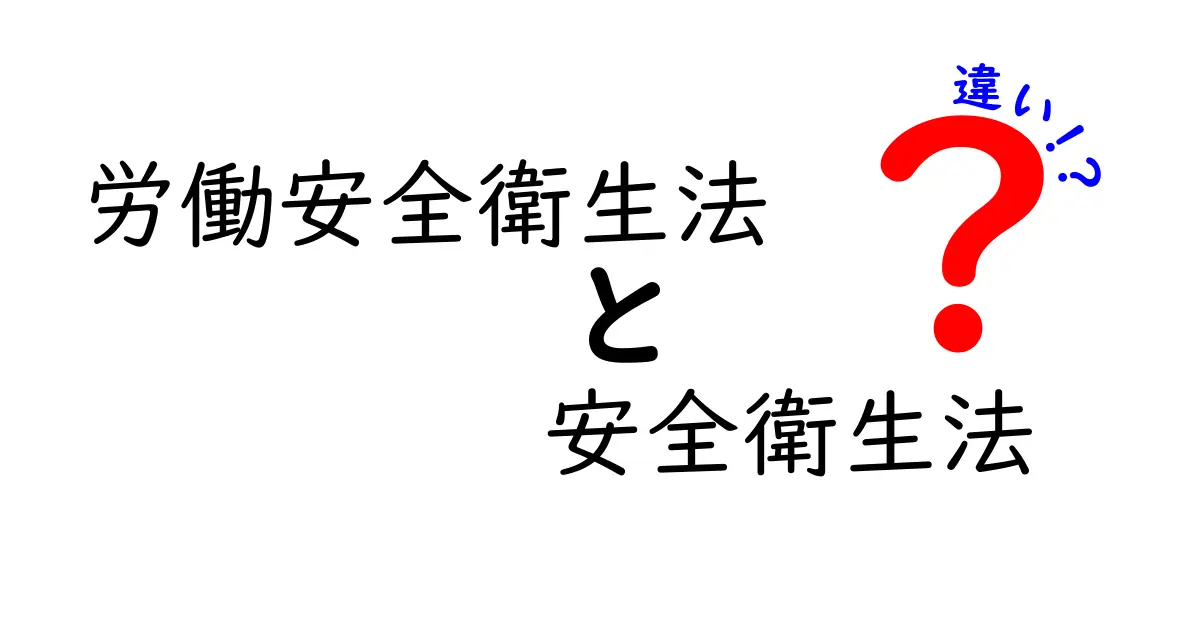
労働安全衛生法とは?
<労働安全衛生法は、日本の働く人々の安全と健康を守るための法律です。特に工場や建築現場などでの事故や病気を防ぐために作られました。
この法律は、働く場所で危険がないかをチェックしたり、安全な道具や設備を使わせたりすることを企業に義務付けています。
例えば、高いところでの作業や有害な化学物質を使う場合は特に注意が必要で、そうした作業に関するルールがこの労働安全衛生法で定められています。
また、職場の環境を快適に保つために、換気や休憩時間の確保なども求められています。
この法律の目的は、働く人が安心して働ける環境を作ることです。
<
安全衛生法とは?
<安全衛生法という名前は、実は「労働安全衛生法」を省略した言葉として使われることがあります。
つまり、安全衛生法という法律が別にあるわけではなく、正式には「労働安全衛生法」が正式名称です。
ただし、日常の会話や文章で「安全衛生法」と略して呼ぶケースが多々あります。
そのため、混乱しやすいですが、この場合は「労働安全衛生法」のことを指しています。
他の類似の法律(例えば食品衛生法など)と混同しないよう注意が必要です。
<
労働安全衛生法と安全衛生法の違いを表で比較
<| 項目 | 労働安全衛生法 | 安全衛生法 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 労働安全衛生法 | 正式な法律名ではない(略称や通称) |
| 目的 | 労働者の安全と健康の保持・増進 | 労働安全衛生法を指すことが多い |
| 適用範囲 | 労働現場全般(製造業、建設業等) | 特定の法律ではない |
| 法律の有無 | 日本の法律の正式名称 | 正式な法律名ではないため存在しない |
| 項目 | 原価 | 実行予算 |
|---|---|---|
| 意味 | 製品やサービスを作るために実際にかかった費用 | 仕事やプロジェクトに使う予定のお金の上限 |
| 時期 | 作業や生産が終わったあとでわかる | 作業や生産を始める前に計画して決める |
| 目的 | コストを把握し、利益計算をする | コストを抑え、計画を守るための管理 |
| 使う場所 | 会計報告や経費分析 | 予算管理やプロジェクトの進行管理 |
実践!原価と実行予算をどう管理すればよい?
では、原価と実行予算をビジネスでどう管理すればいいのでしょうか?
まず、実行予算はプロジェクトの始めに設定します。このとき、「どれだけお金を使っても大丈夫か?」を計画します。
次に、実際にかかった費用(原価)を逐一チェックしながら、予算内で仕事が進んでいるかを確認します。
もし原価が予算を超えるおそれがある場合は、どこを削減できるか検討したり作業内容を見直したりすることが必要です。
このように、計画(実行予算)と実績(原価)を比べて改善していく作業は、企業が無駄をなくし利益を守るために欠かせません。
「原価」という言葉はよく聞きますが、実はその中には「直接原価」と「間接原価」という2つの種類があります。直接原価は製品に直接かかる費用、たとえば材料費や直接作業者の給料。間接原価は工場の家賃や光熱費など、製品に直接は結びつかない費用です。ビジネスでは、この区別をすることで、もっと正確にコストを計算できるんですよ。原価が一言で済まない奥深さ、ちょっと面白いですね。
前の記事: « 転送ケーブルと通信ケーブルの違いとは?初心者でもわかる徹底解説!