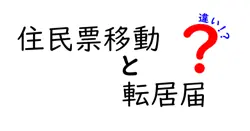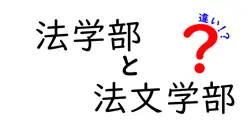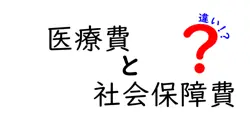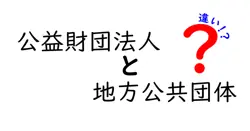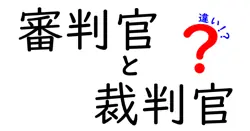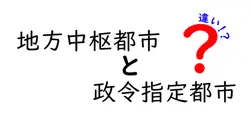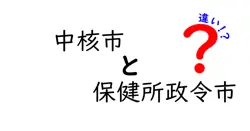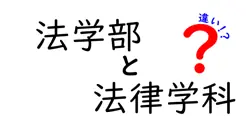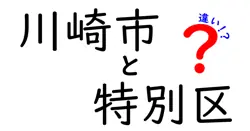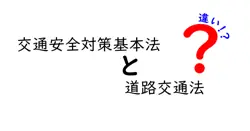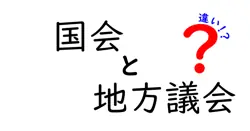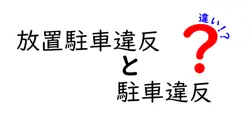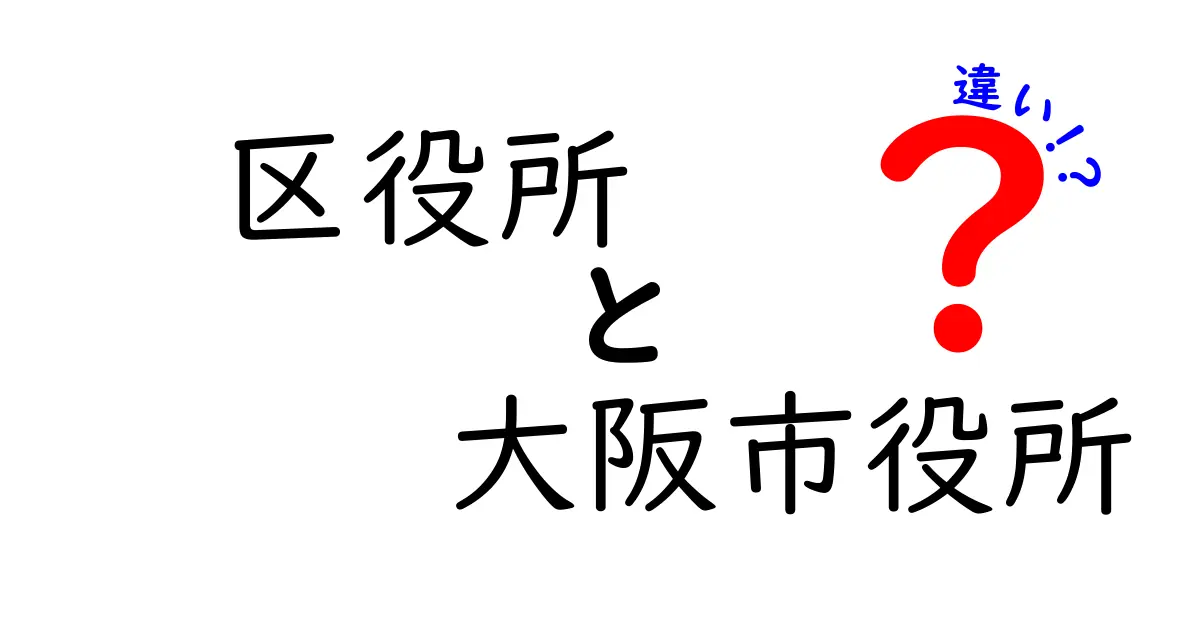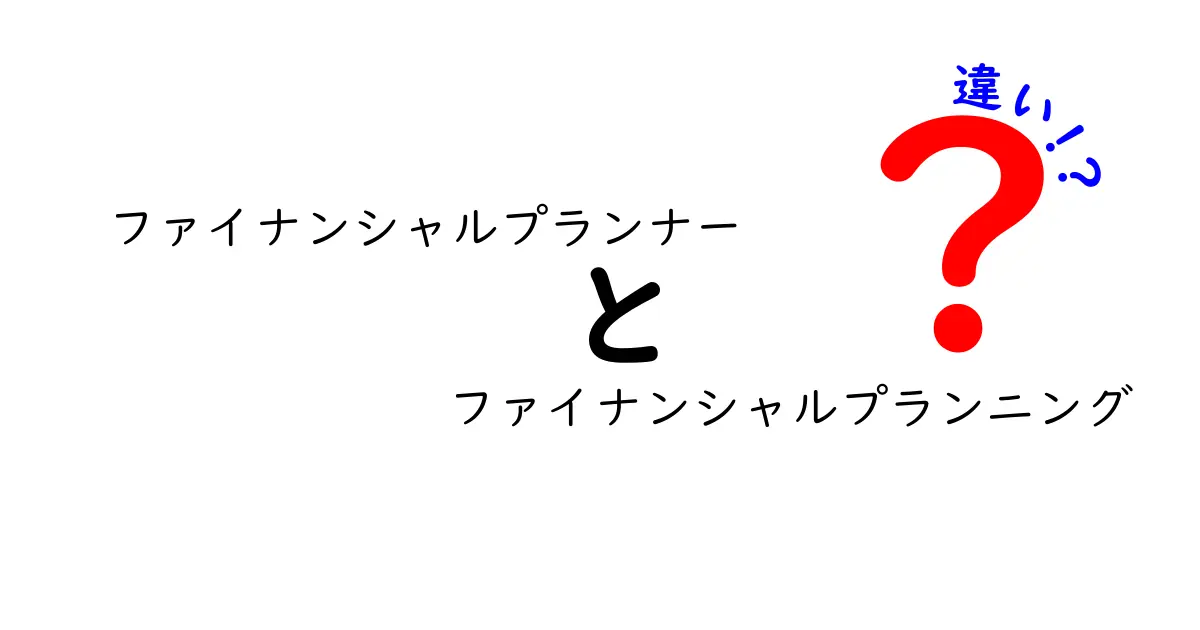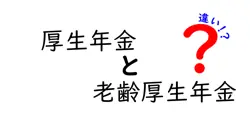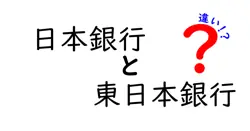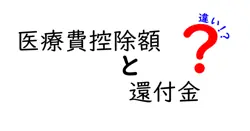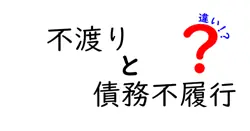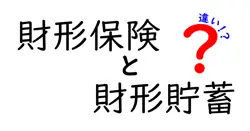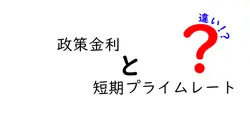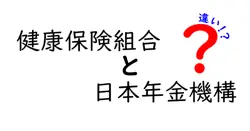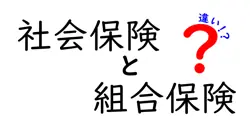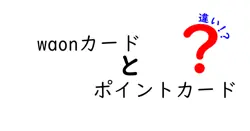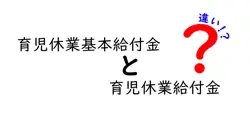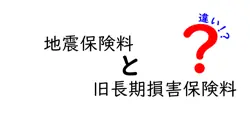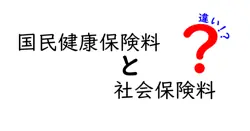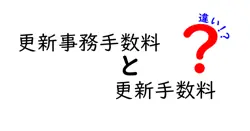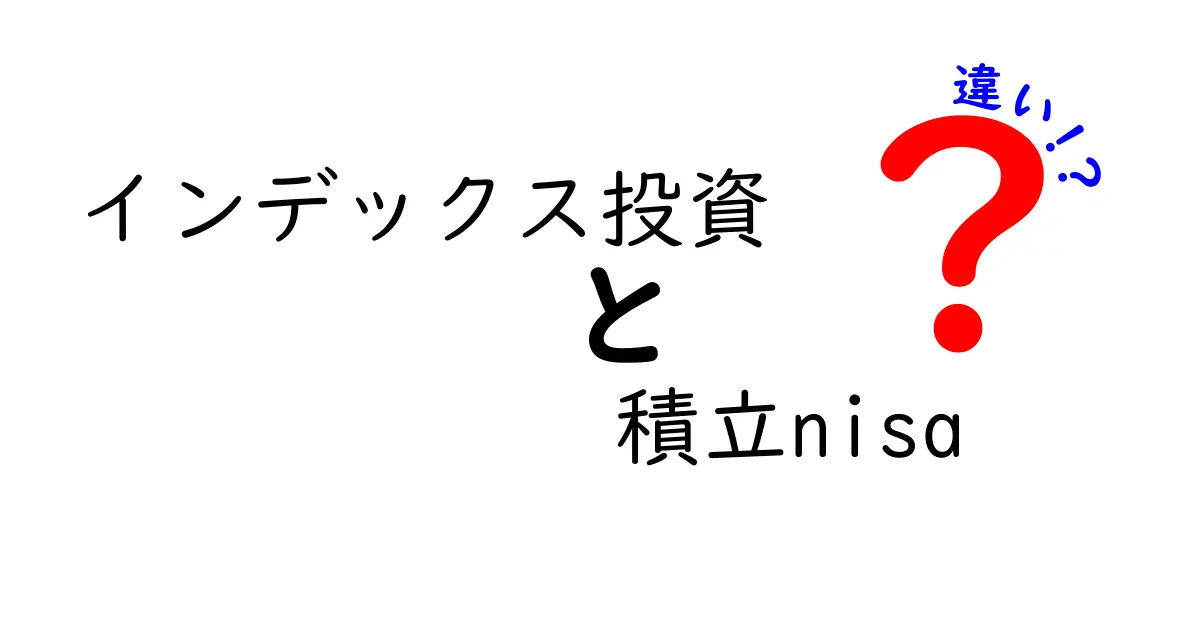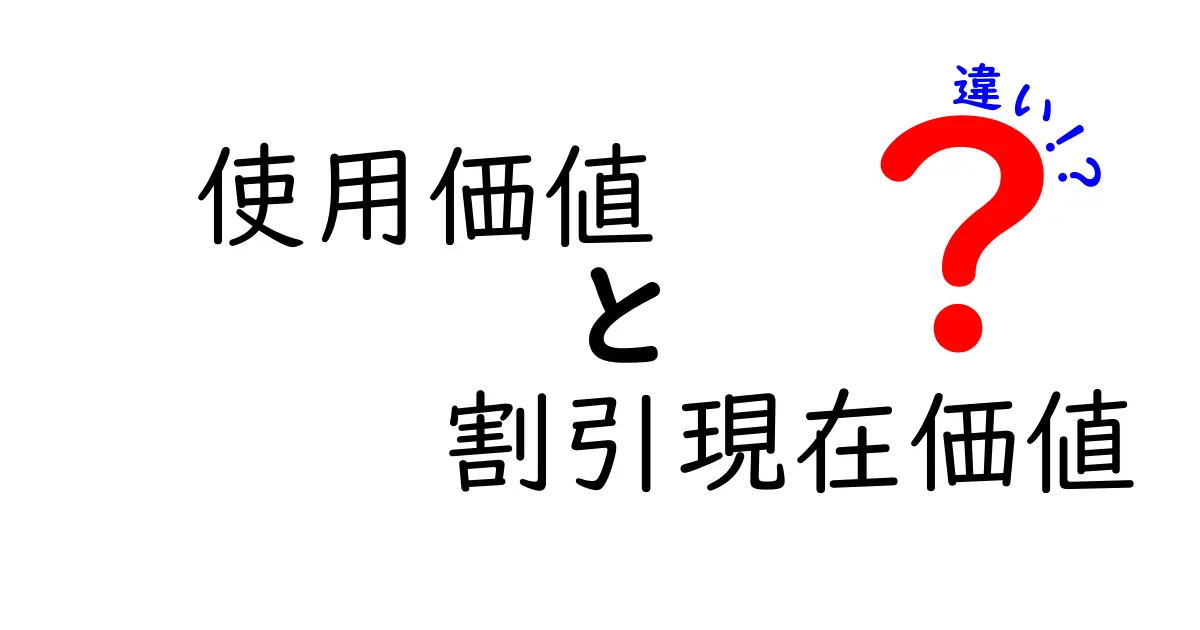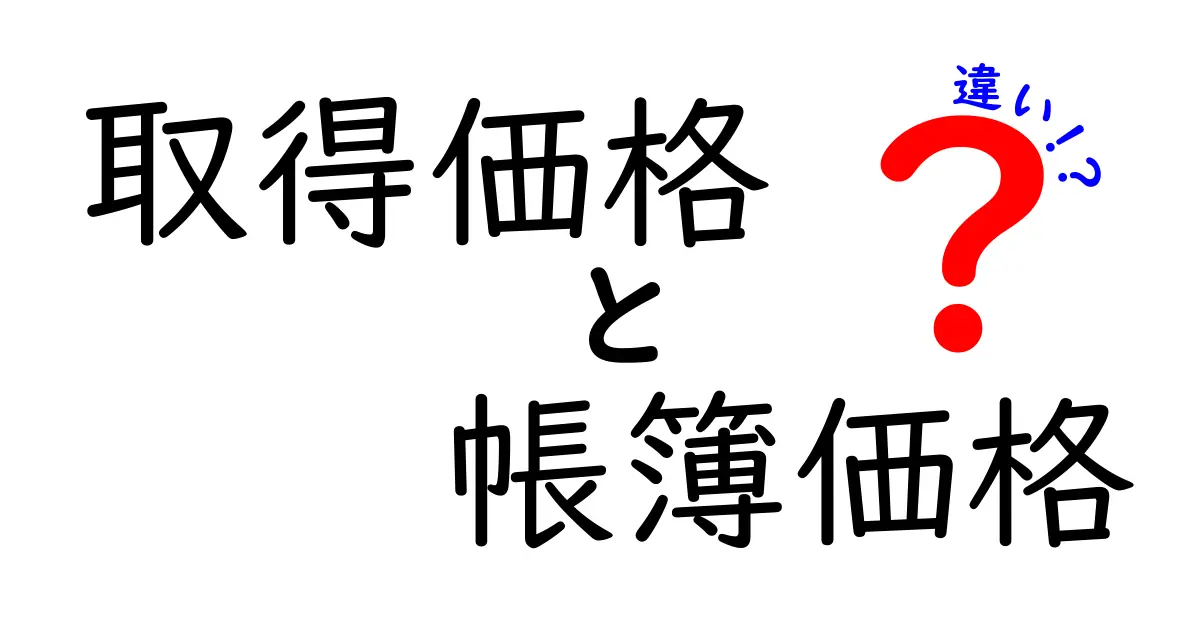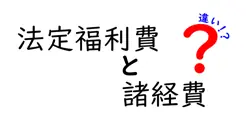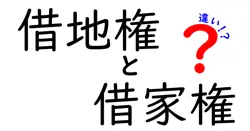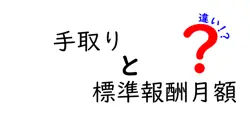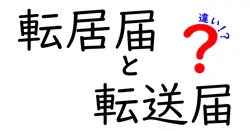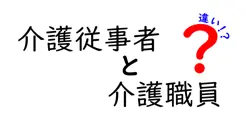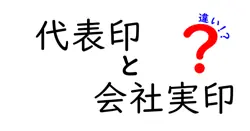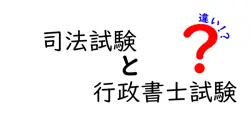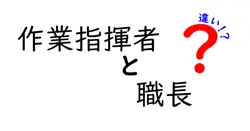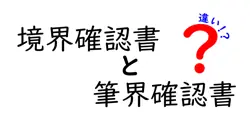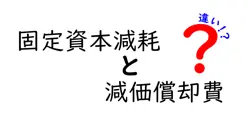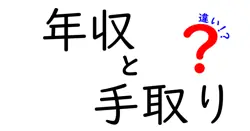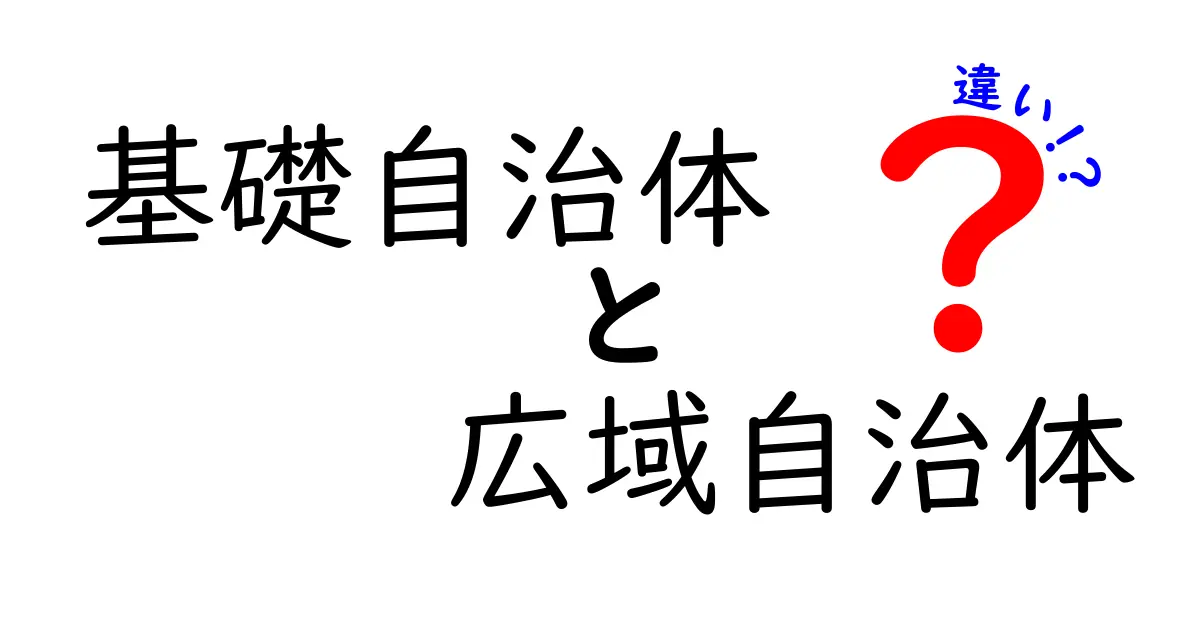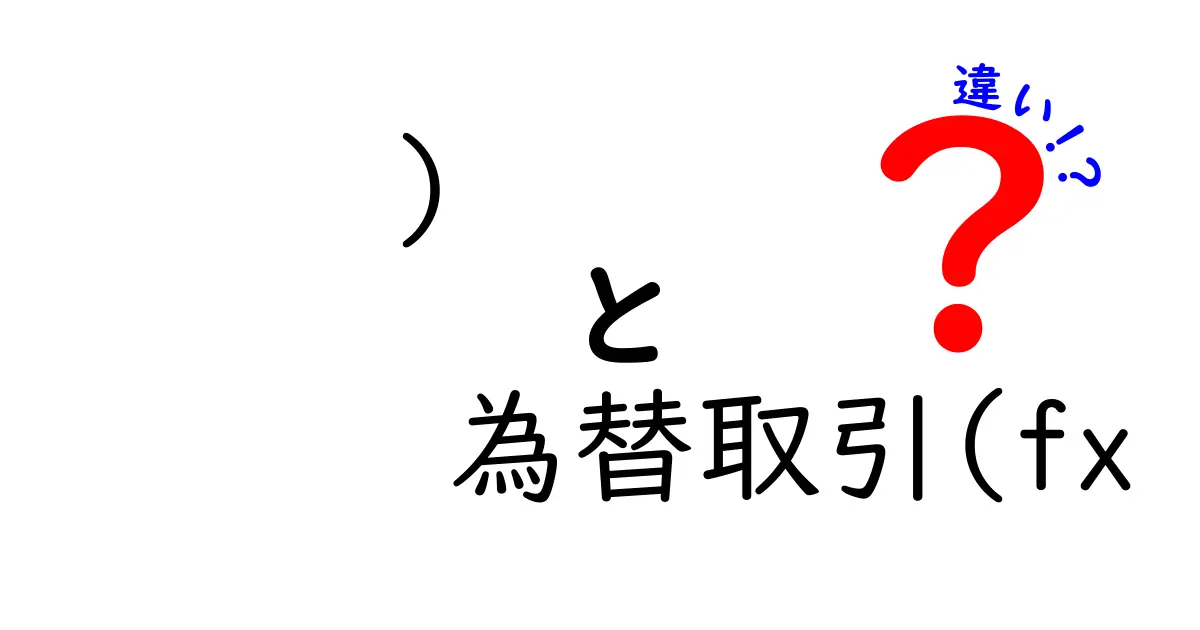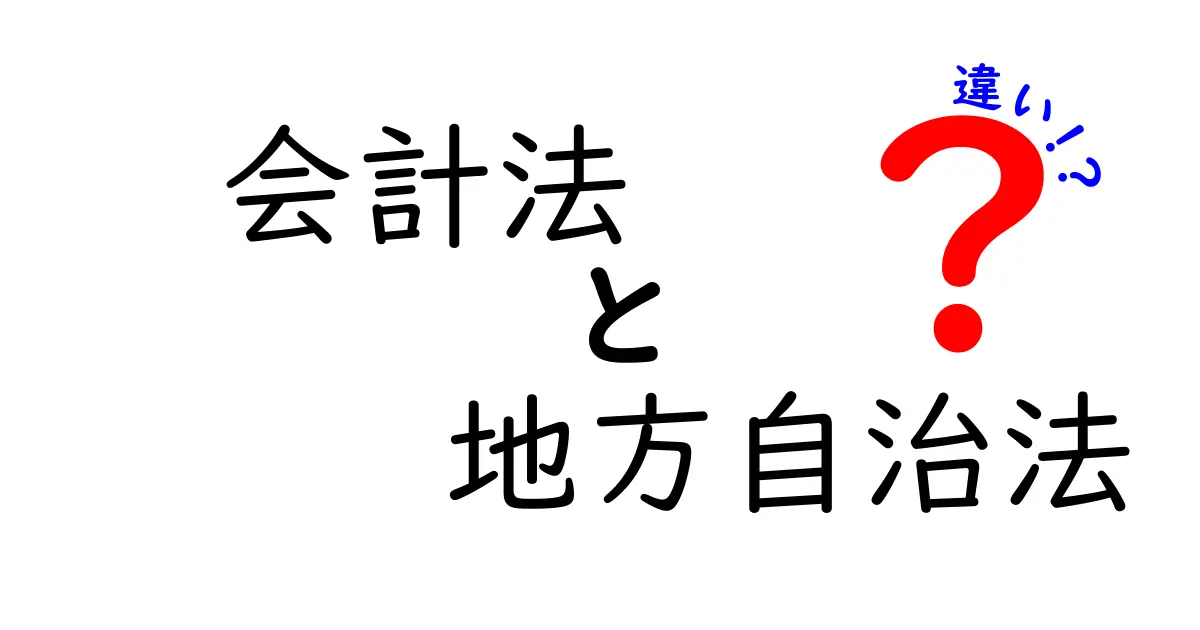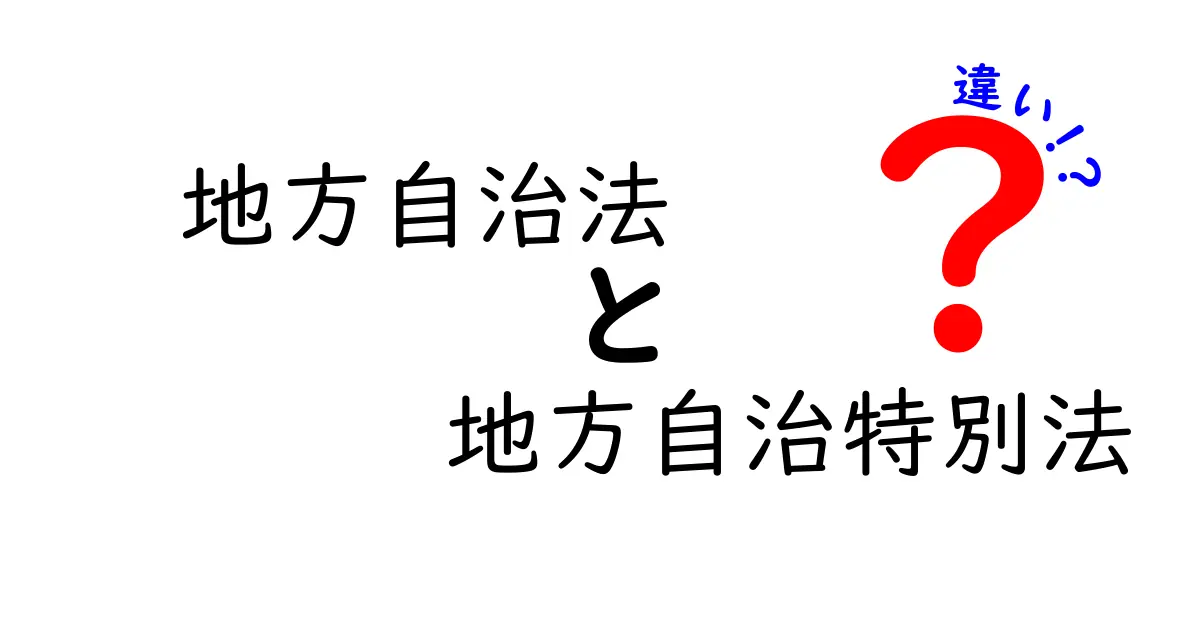
地方自治法と地方自治特別法とは?その基本を押さえよう
まずは地方自治法と地方自治特別法の基本的な意味について説明します。
地方自治法は、日本の地方自治体を運営するための基本的な法律です。都道府県や市町村がどのように自治を行うか、そのルールや仕組みをまとめています。つまり、全国の地方自治体が共通して守る基本的なルール集だと考えてください。
一方で地方自治特別法は、特定の地方自治体や地域の事情に合わせて定められる法律です。たとえば、小笠原村のような離島の特別な事情や、特定の制度を設けるために作られます。つまり、一般的なルールとは別に、例外や特別な対応を定める法律です。
地方自治法と地方自治特別法はどこが違う?ポイントを比較表で解説
では、具体的にどこが違うのか表でまとめてみましょう。
| 項目 | 地方自治法 | 地方自治特別法 |
|---|---|---|
| 対象 | 全国のすべての地方自治体 | 特定の地域や自治体 |
| 目的 | 地方自治の基本的な枠組みを定める | 特定地域の特殊事情に対応するため |
| 規模 | 全国共通の法律 | 限定的な法律 |
| 制定方法 | 国会で制定される一般法 | 同じく国会で制定されるが対象限定 |
| 適用範囲 | 広範囲かつ一般的 | 狭い範囲かつ特化 |
このように地方自治法は全国共通のルール、地方自治特別法は例外的なルールという違いがあります。
具体例から理解する!地方自治法と地方自治特別法の使い分け
さらに理解を深めるために、それぞれの法律が実際にどう使われているか例をあげてみましょう。
代表的な地方自治法の内容には、市町村の議会のしくみや知事・市長の選挙方法、行政の財政管理などがあります。これらは全国共通のルールとして全自治体に適用されています。
一方、地方自治特別法はたとえば小笠原村のための「小笠原諸島特別措置法」や沖縄の基地問題に関する特別法などがあり、対象や対応が限られています。
こうした特別法は、その地域の歴史的背景や地理的な事情など複雑な状況に応じて作られるものです。つまり、例外的な扱いが必要なときに用いられることが多いと覚えておくと良いでしょう。
まとめ:地方自治の仕組みを知って地域の未来を考えよう
地方自治法と地方自治特別法は、どちらも地方自治体の運営に欠かせない法律ですが、役割や対象に大きな違いがあります。地方自治法は日本全国の自治体が守る基本ルール、地方自治特別法は特別な事情を持つ地域のために作られた例外法ということです。
この違いを知ることで、ニュースや地域の話題で聞く法制度の意味が分かるようになりますし、地方政治や地域づくりに関心が深まります。
地域ごとの特別な法律があることは、その地域の歴史や文化、課題が反映された証でもあります。それを理解することは、より良い日本の未来を考える一歩になるでしょう。
ぜひこの記事をきっかけに、地方自治の仕組みに興味を持ってみてください。
地方自治特別法について少し話しましょう。これは全国共通の法律とは違って、特定の地域だけに適用される法律です。たとえば東京とはまた違った特別な事情を持つ離島や歴史的に特別な場所で使われます。そのため、法律が地域ごとに少し違うことがあるんです。学校のルールみたいに、みんなに同じ基本ルールがあるけど、クラスごとに少し違う決まりがあるイメージですね。そう考えると、地方自治特別法の役割がもっと身近に感じられますよね。
次の記事: 【簡単解説】偶発債務と引当金の違いを5分で理解しよう! »