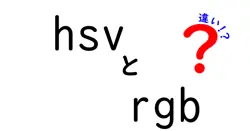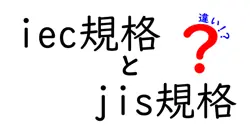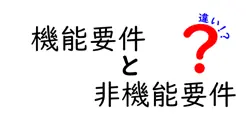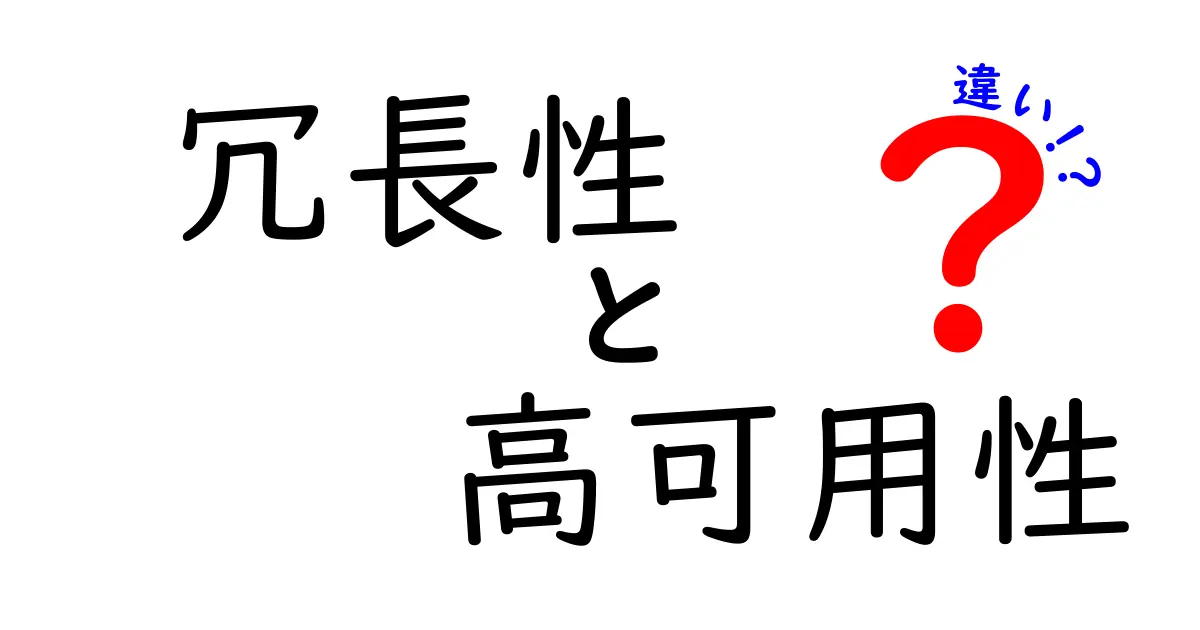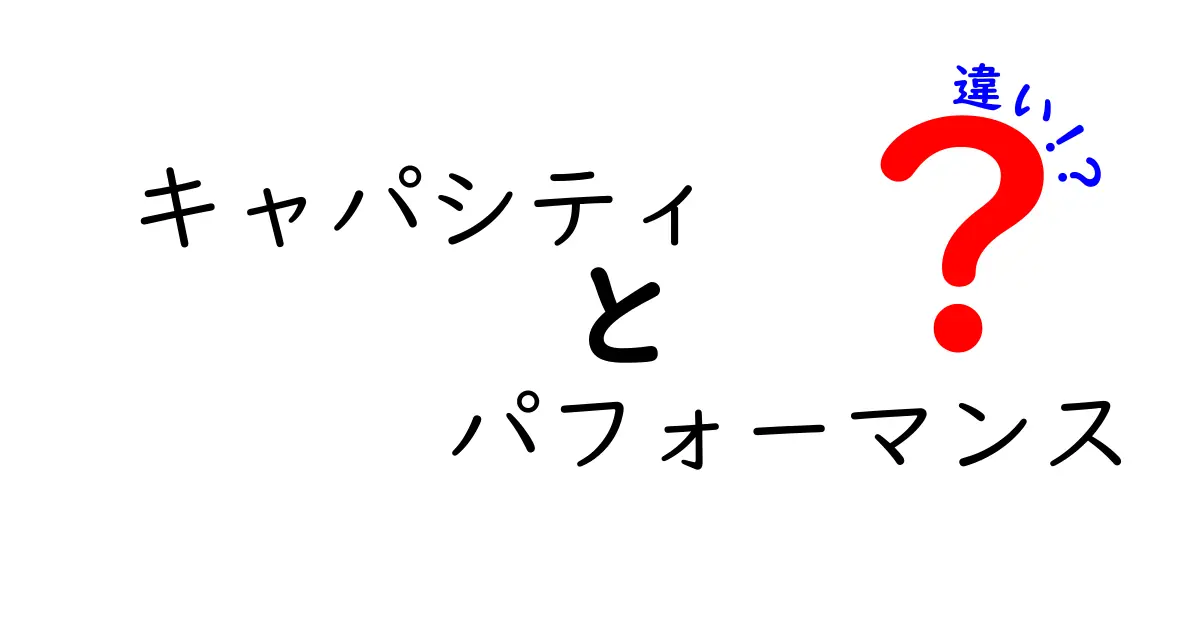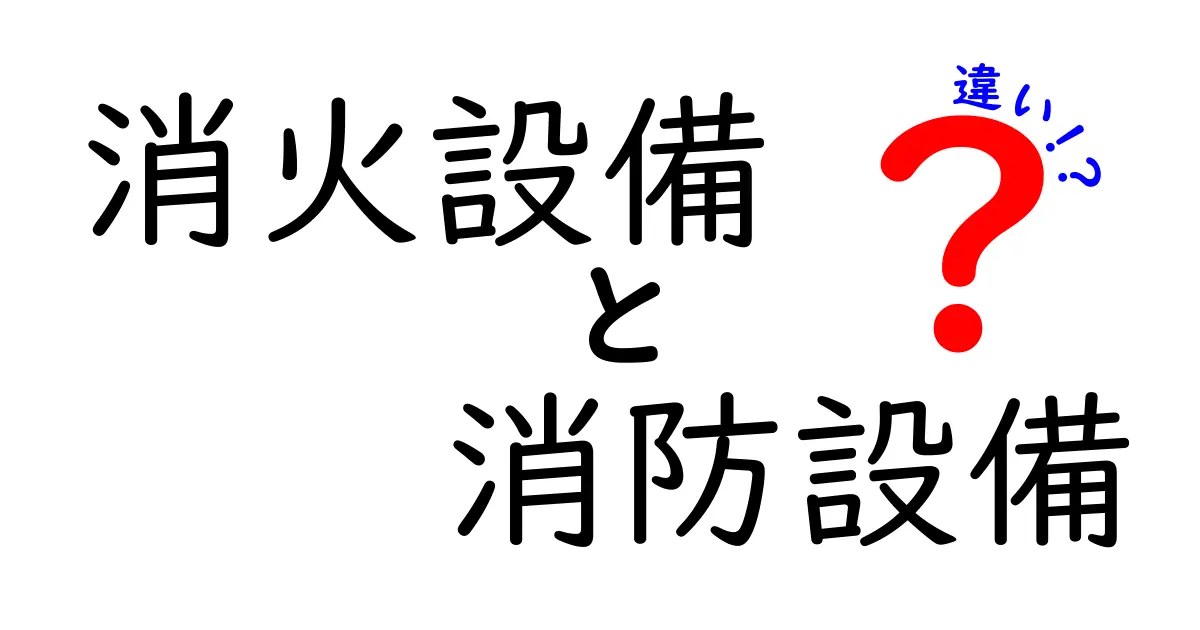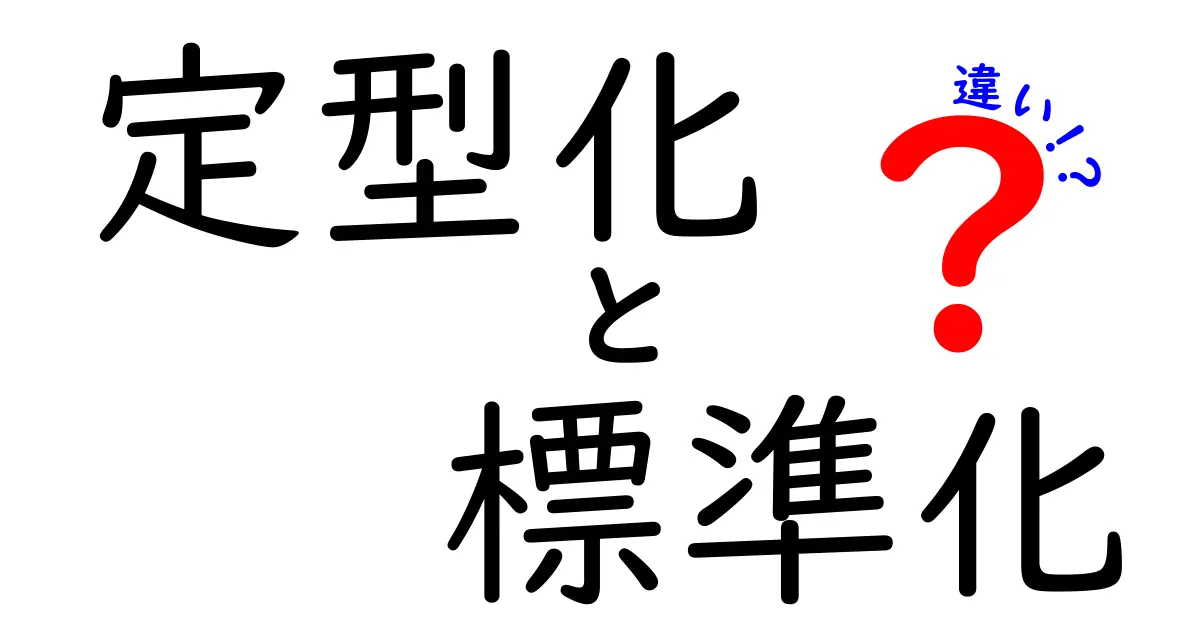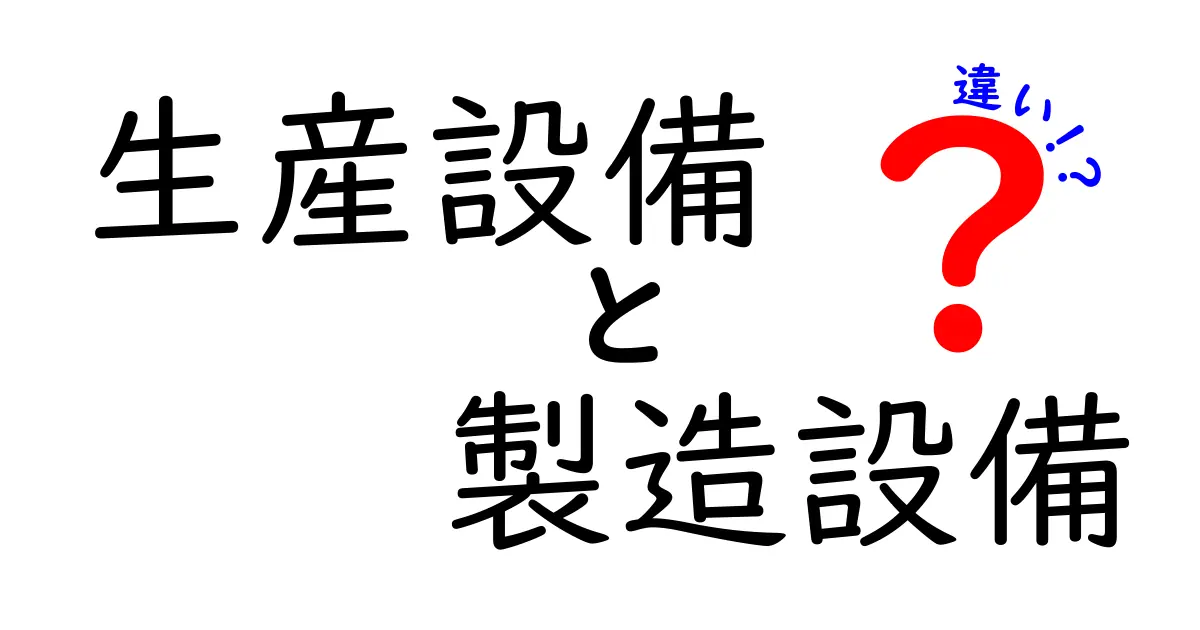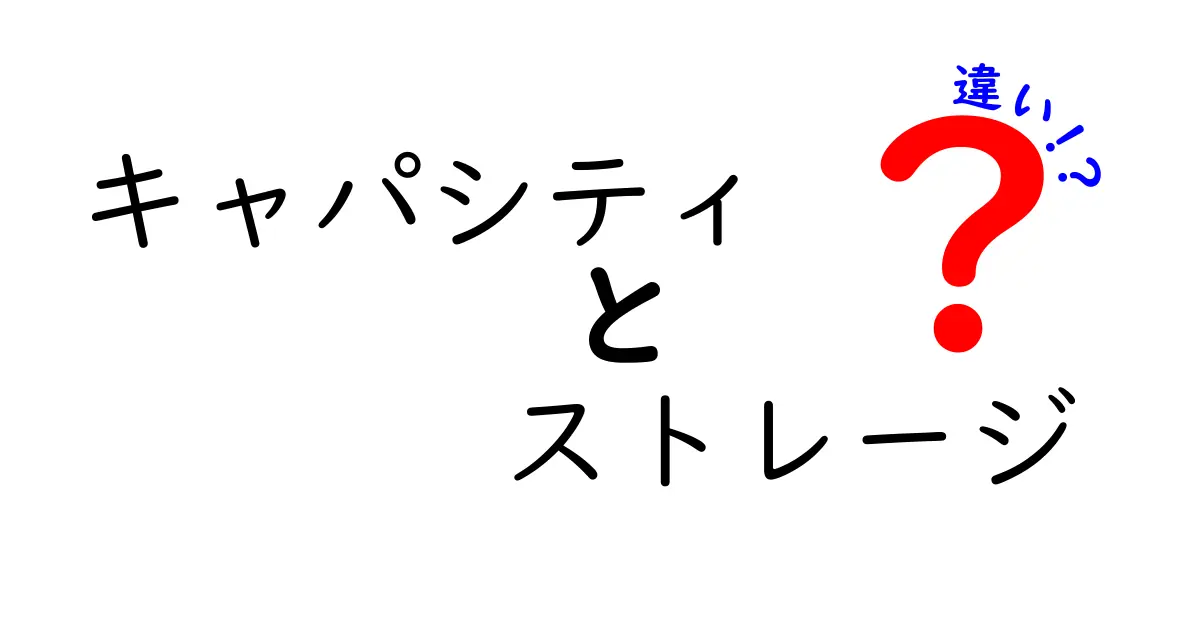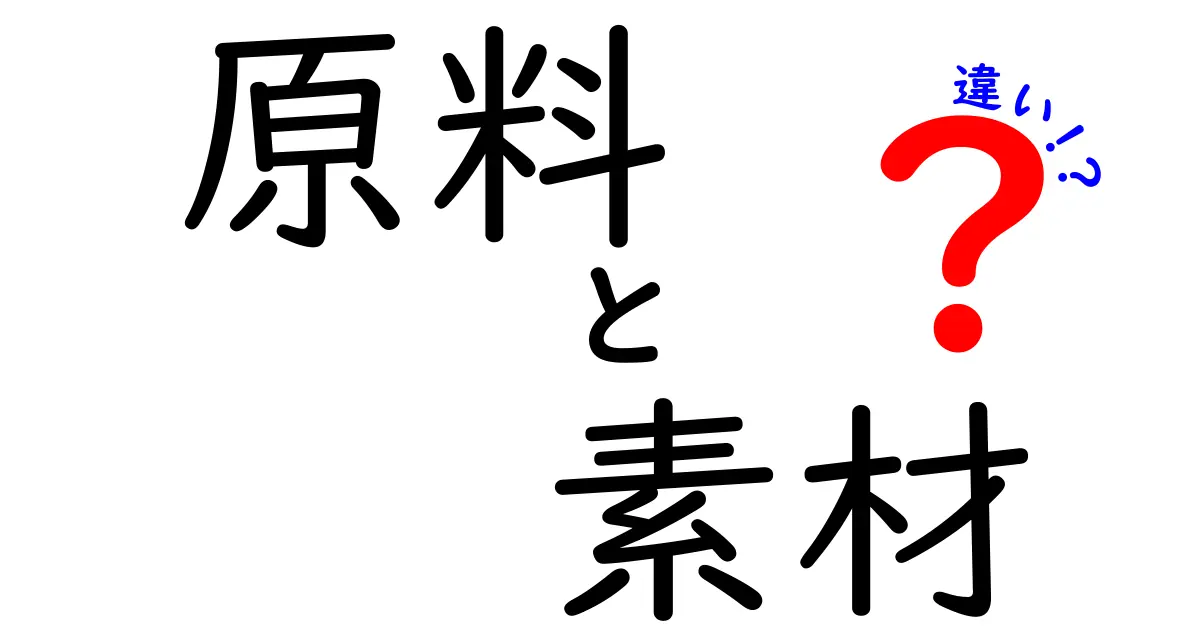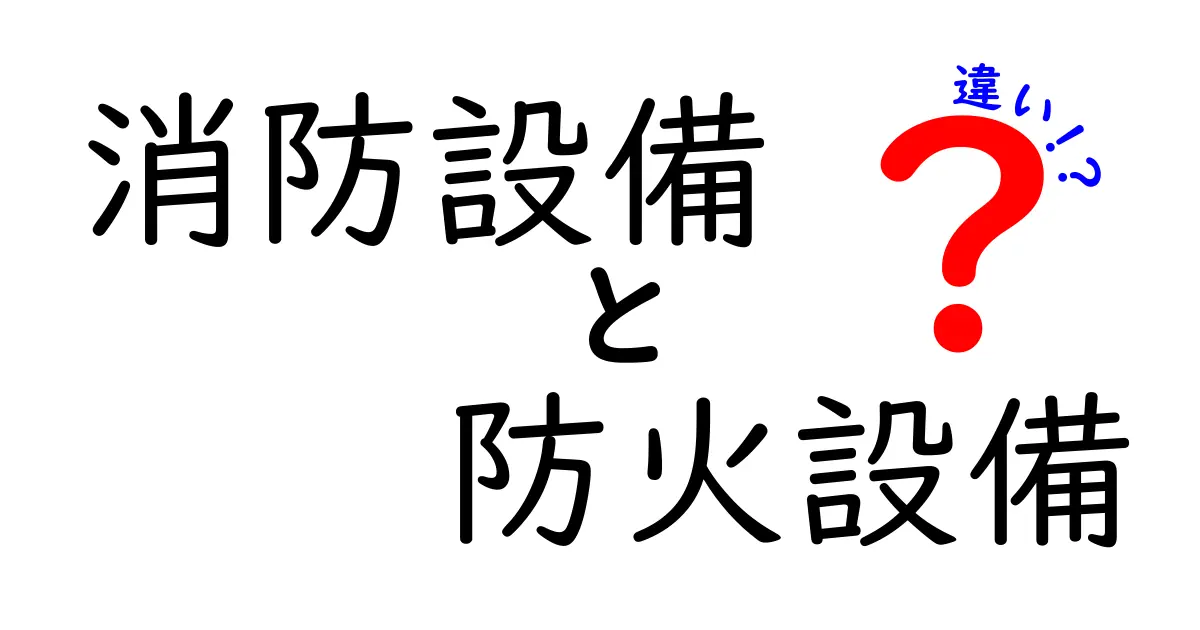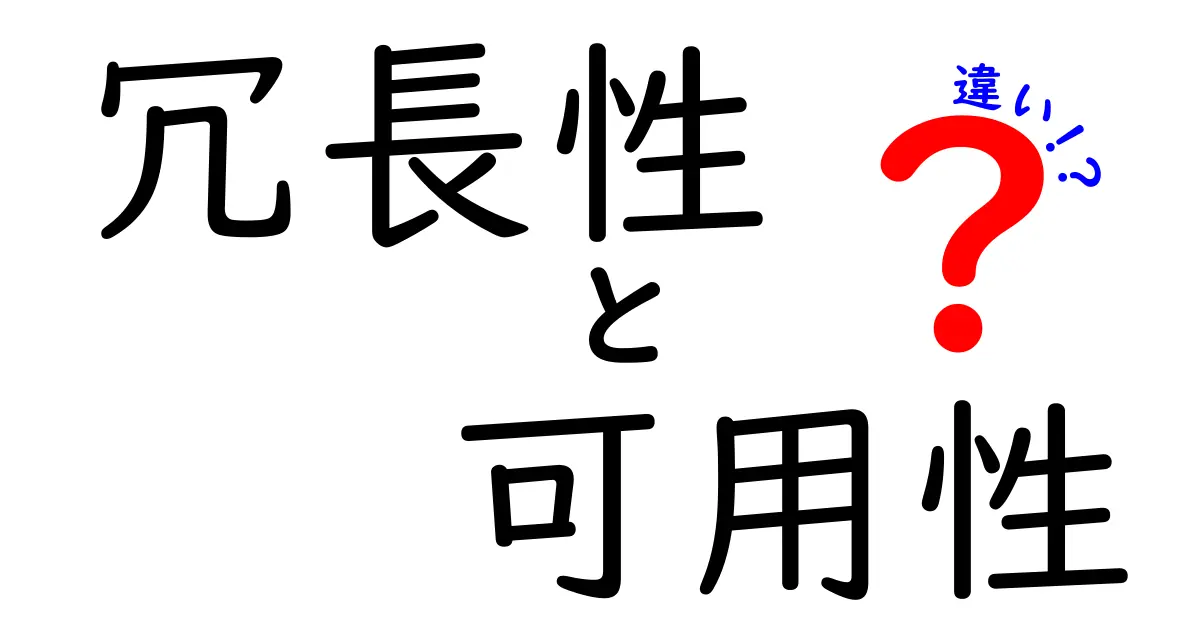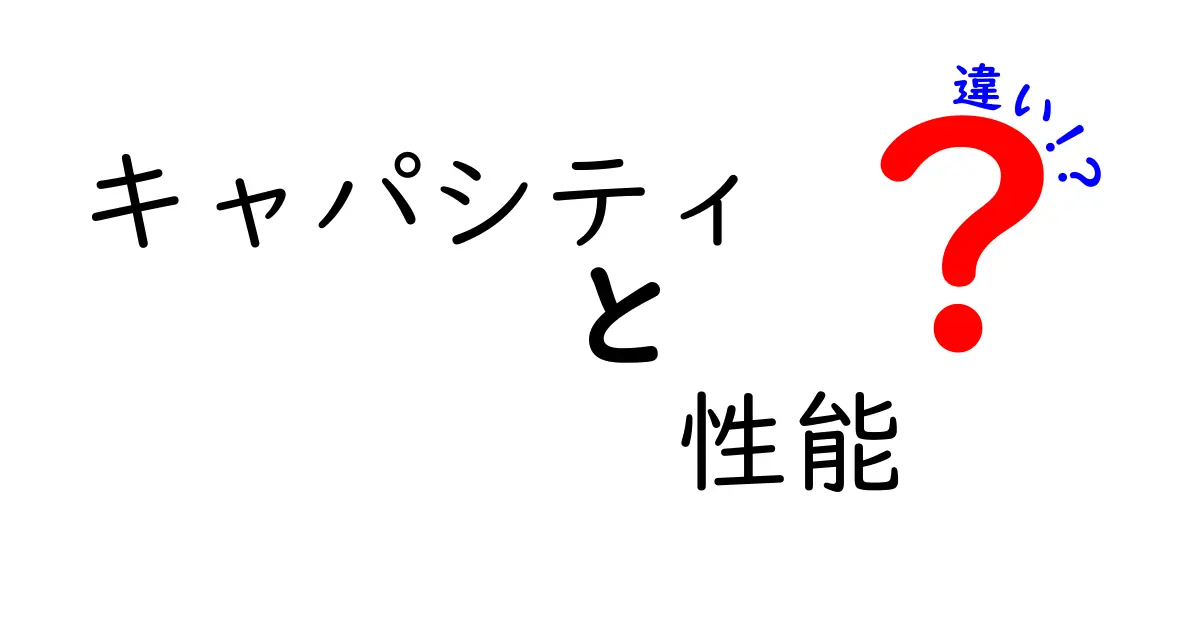
キャパシティと性能って何が違うの?基本の理解
まずは「キャパシティ」と「性能」という言葉の基本的な意味を押さえておきましょう。
キャパシティとは、物や設備がどれだけの容量や量を収納・処理できるかを示す数値です。例えば、スマートフォンのストレージ容量や倉庫の最大収容量などがキャパシティに当たります。
一方で性能とは、それがどれだけ効率的に動くか、どれだけ優れているかを示す能力や機能の指標です。パソコンの処理速度や車の燃費性能などがこれにあたります。
つまりキャパシティは「どれだけ入るか」、性能は「どれだけうまく働くか」の違いがあるのです。
この区別を知ることが、機械や道具を選ぶときにとても大切になります。
キャパシティと性能の違いを具体例で理解しよう
1. スマートフォンの場合
キャパシティ=ストレージ容量(例:64GBや128GBなど)
性能=CPUの速さやカメラの画質
ストレージは写真やデータをどれだけ保存できるかの能力、CPUはアプリをスムーズに動かす速さを示します。
2. 車の場合
キャパシティ=トランクの大きさや車内の席数
性能=エンジンの馬力や燃費、安全性能
荷物がたくさん入るキャパシティと、走る力や燃料の使い方の効率である性能はまったく違います。
3. コンピューターの場合
キャパシティ=メモリー容量やハードディスク容量
性能=CPUの処理速度やグラフィック性能
大量のデータが保存できること(キャパシティ)と処理が速いこと(性能)は異なる評価ポイントです。
これらの例からも、キャパシティは「量に関する能力」、性能は「質やスピードに関する能力」と理解するとわかりやすいでしょう。
キャパシティと性能の違いを表で比較してみよう
| 項目 | キャパシティ | 性能 |
|---|---|---|
| 意味 | 容量・収容力・処理できる量 | 能力・効率・機能の質 |
| 例 | スマホのストレージ容量(64GBなど) 車のトランクの大きさ | スマホのCPU速度 車の燃費やエンジンパワー |
| 評価基準 | どれだけ多くのものを扱えるか | どれだけ速く・正確に行えるか |
| 製品選びのポイント | 必要な容量や搭載量を確認 | 求める動作速度や機能を重視 |
| ポイント | 冗長性 | 高可用性 |
| 意味 | 同じものを複数用意しておくこと | サービスやシステムが長時間止まらず使えること |
| 目的 | 故障や障害時の対応力を高める | サービスの安定稼働を保証する |
| 役割 | バックアップやコピーの配置 | 障害検知・切り替え・復旧の仕組み全体 |
| 例 | サーバーの複数台用意・データの複製 | 障害発生時の自動切り替えや負荷分散 |
このように冗長性はハードやソフトの準備、
高可用性はそれを活用しながらサービスを止めない仕組みや運用も含めた広い意味だと理解すると良いでしょう。
まとめ
最後に要点を振り返ります。
- 冗長性は同じ機器やデータを複数用意し、万が一の障害に備えること。
- 高可用性はサービスができるだけ止まらず稼働し続けること。冗長性を含む障害対策が必要。
- 冗長性は高可用性を実現するための重要な手段の一つ。
これらの考え方はシステムを作る上でとても大切です。ぜひ今後もITの基礎知識として覚えておくと役に立つでしょう。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
冗長性って、一言で言うと「予備を持つこと」なんですが、実はただコピーを増やせばいいだけじゃなくて、その予備がちゃんと切り替わる仕組みがないと意味がないんです。だから冗長性はハードやデータの複製を準備すること、でもそれを活かす切り替えや監視は高可用性の範囲。こんな風に両方セットで考えるとイメージしやすいですよね。
例えばスマホの写真を2台のクラウドに保存しても、もし一つのクラウドが落ちても自動で切り替えが無ければ間に合わない。だから冗長性だけあっても高可用性がなければ安心はできません。まさに連携プレーみたいな関係なんですよ。
前の記事: « キャパシティとパフォーマンスの違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: キャパシティと性能の違いとは?初心者にもわかりやすく徹底解説! »