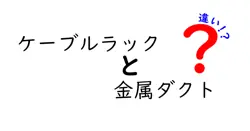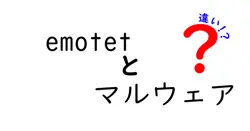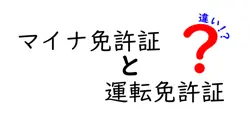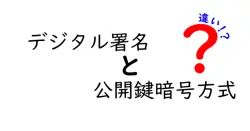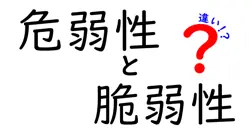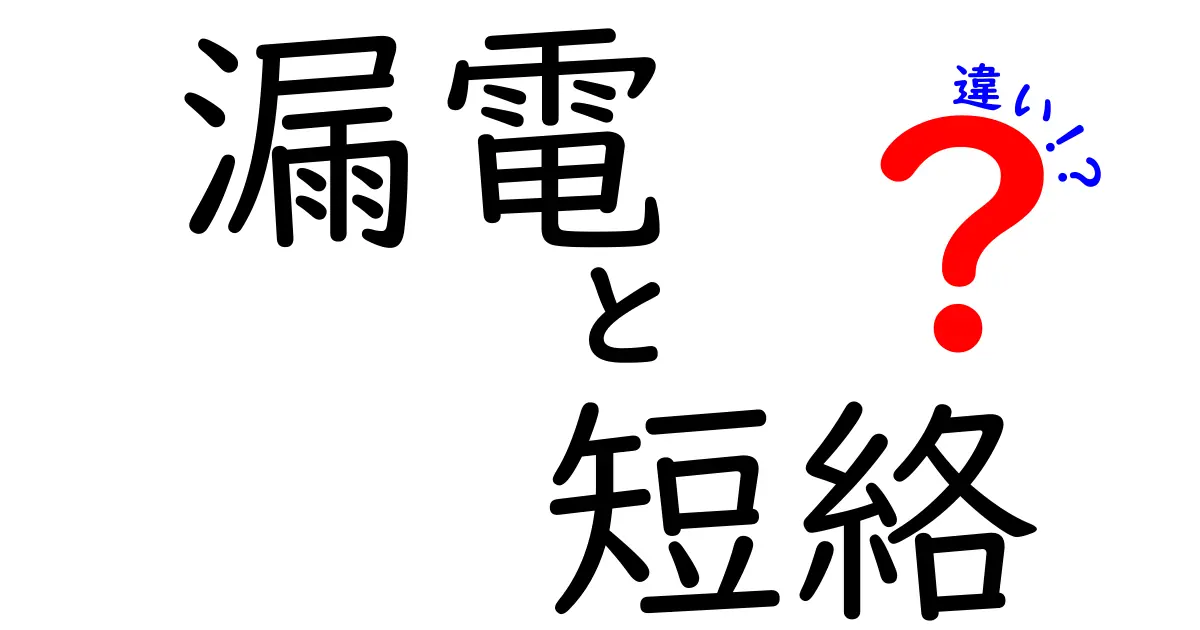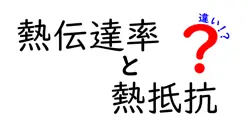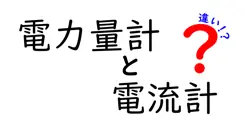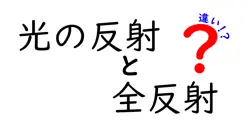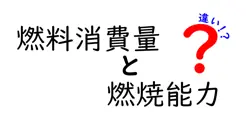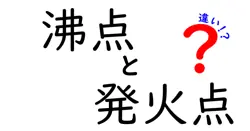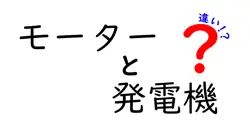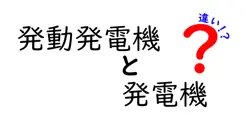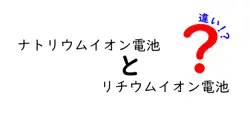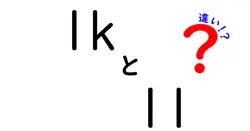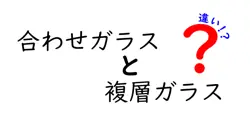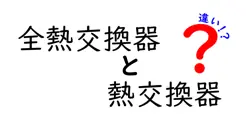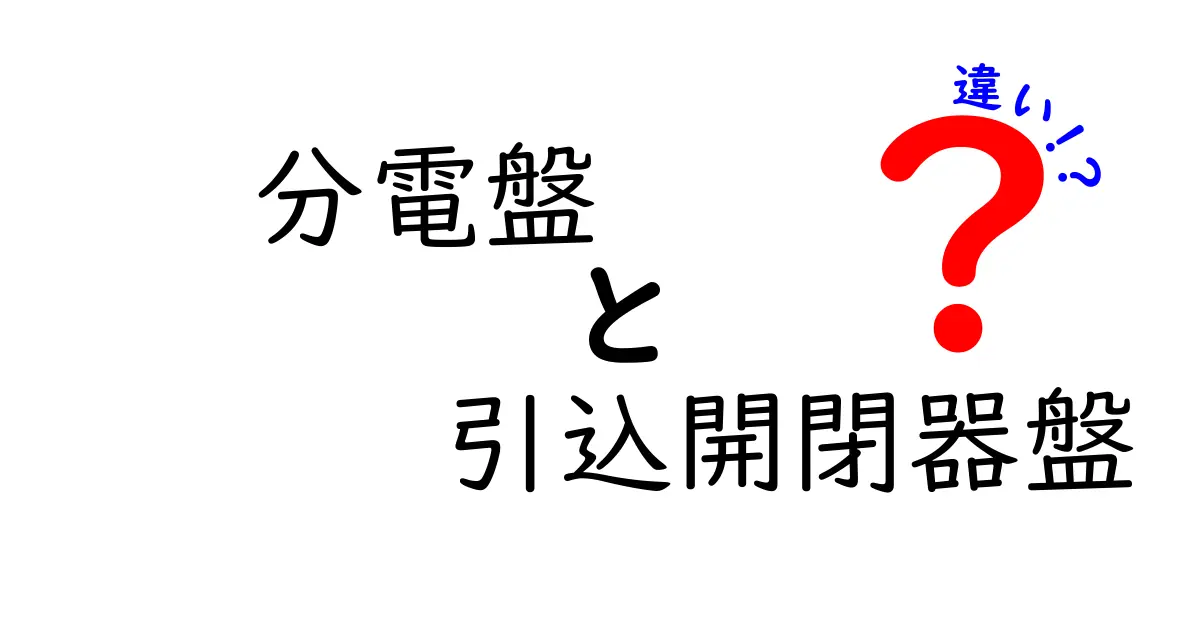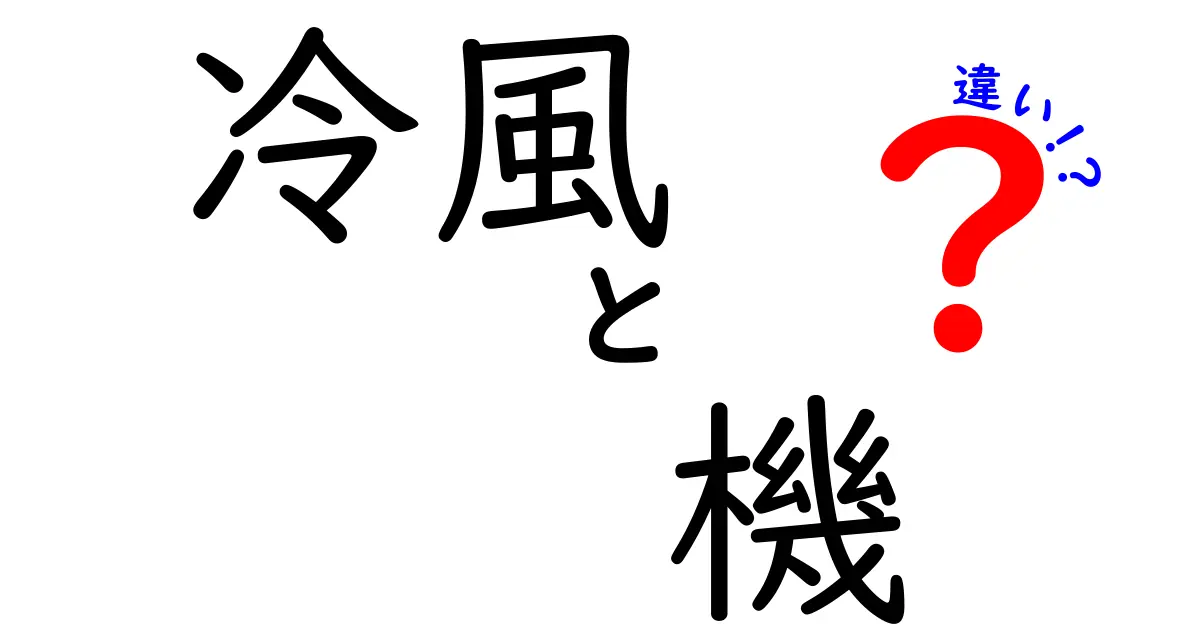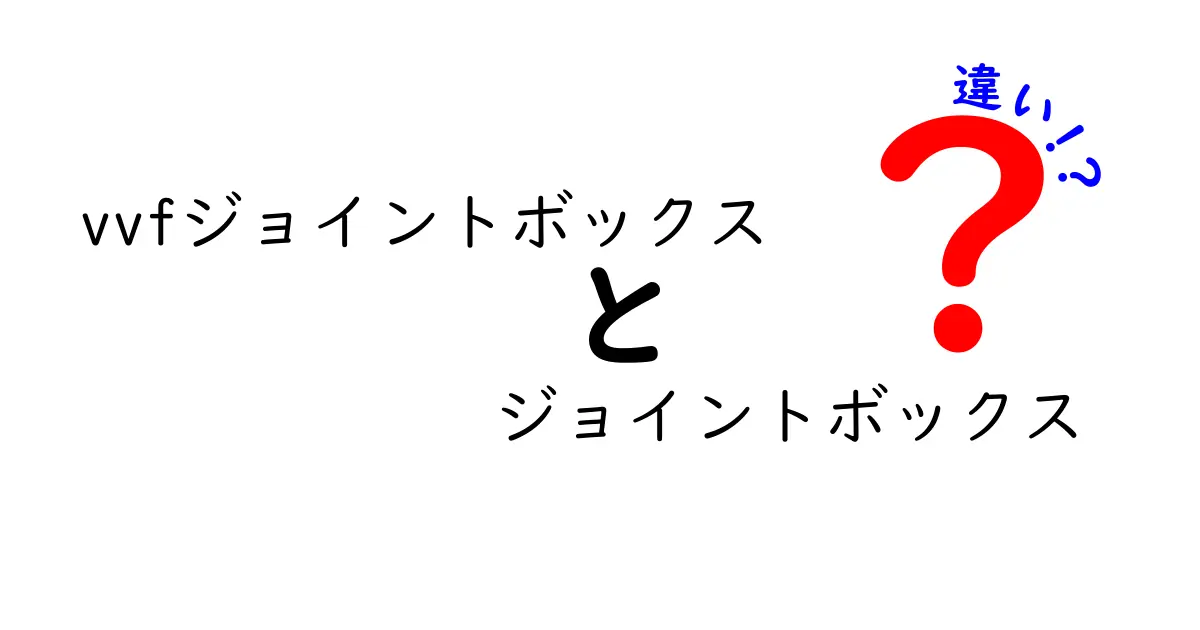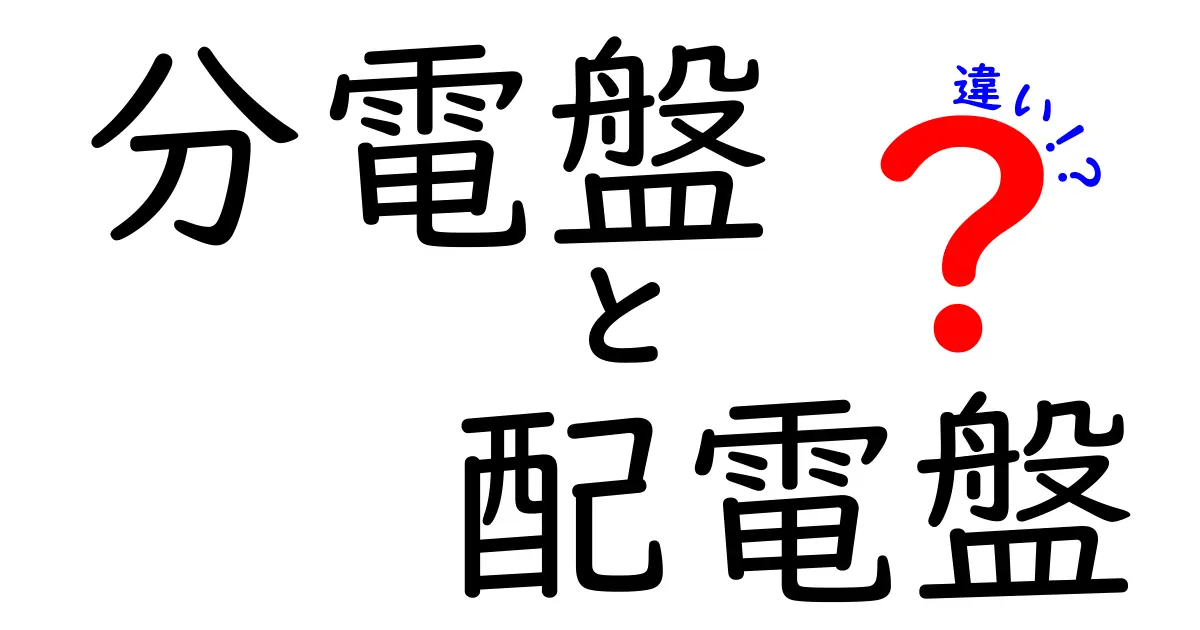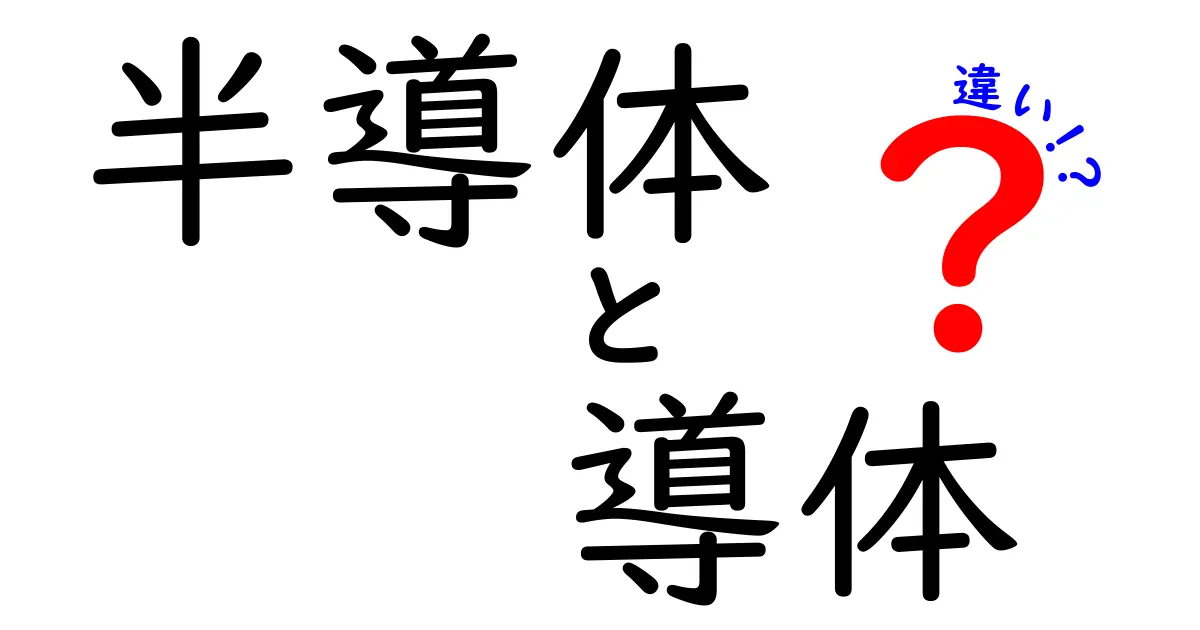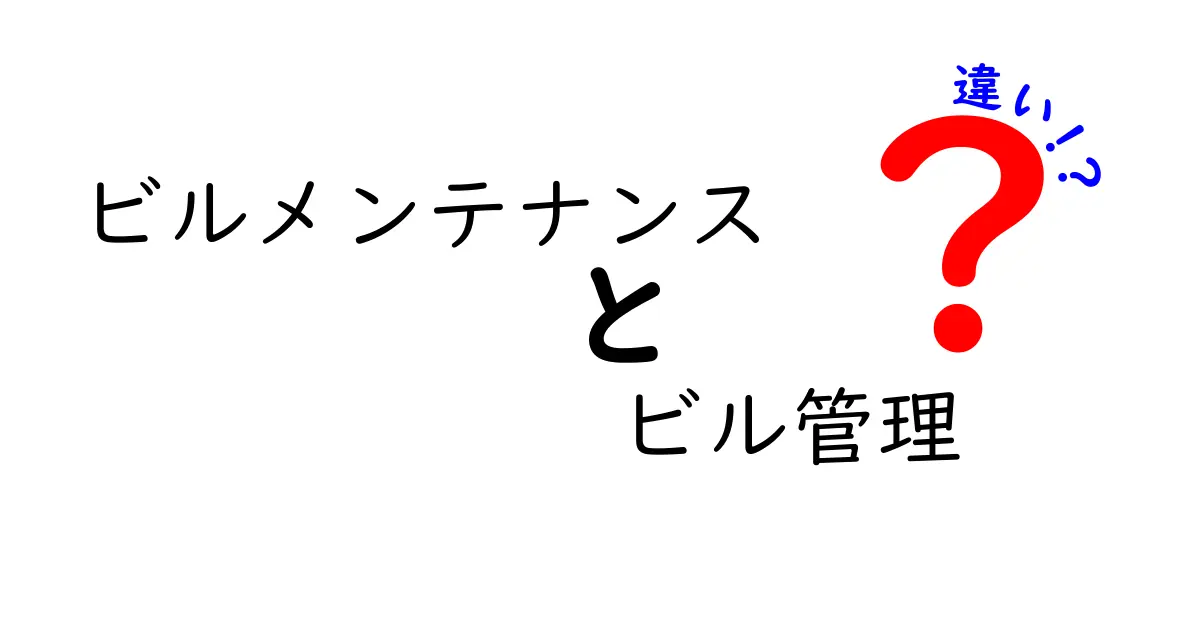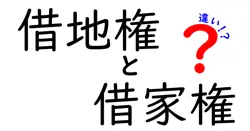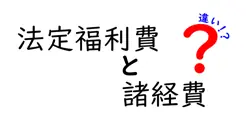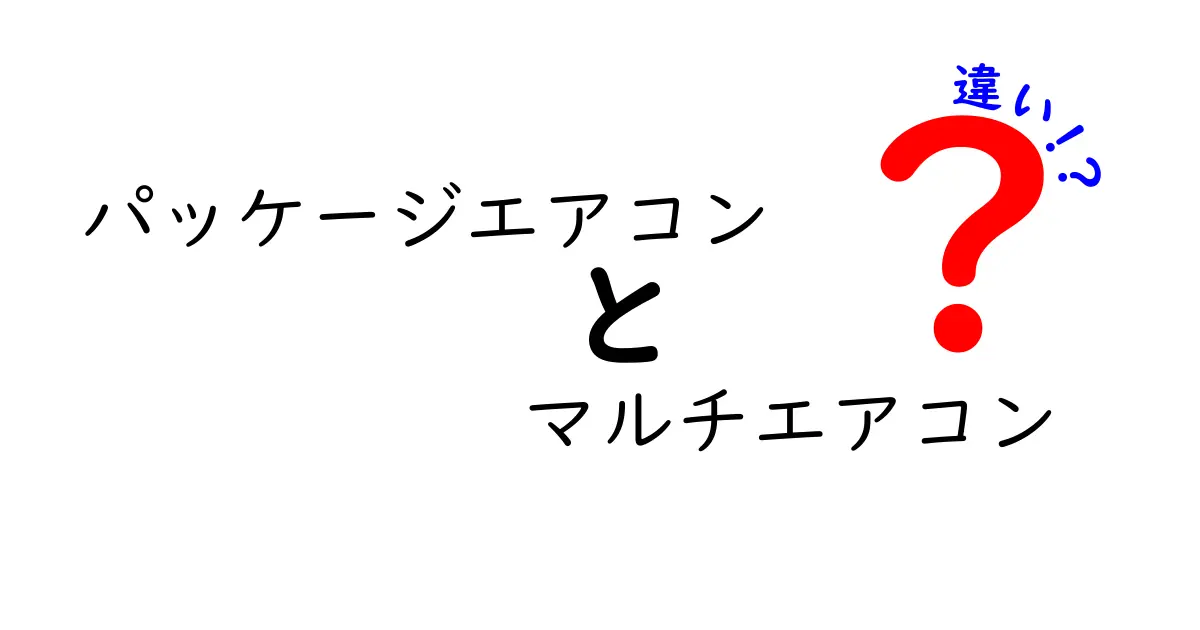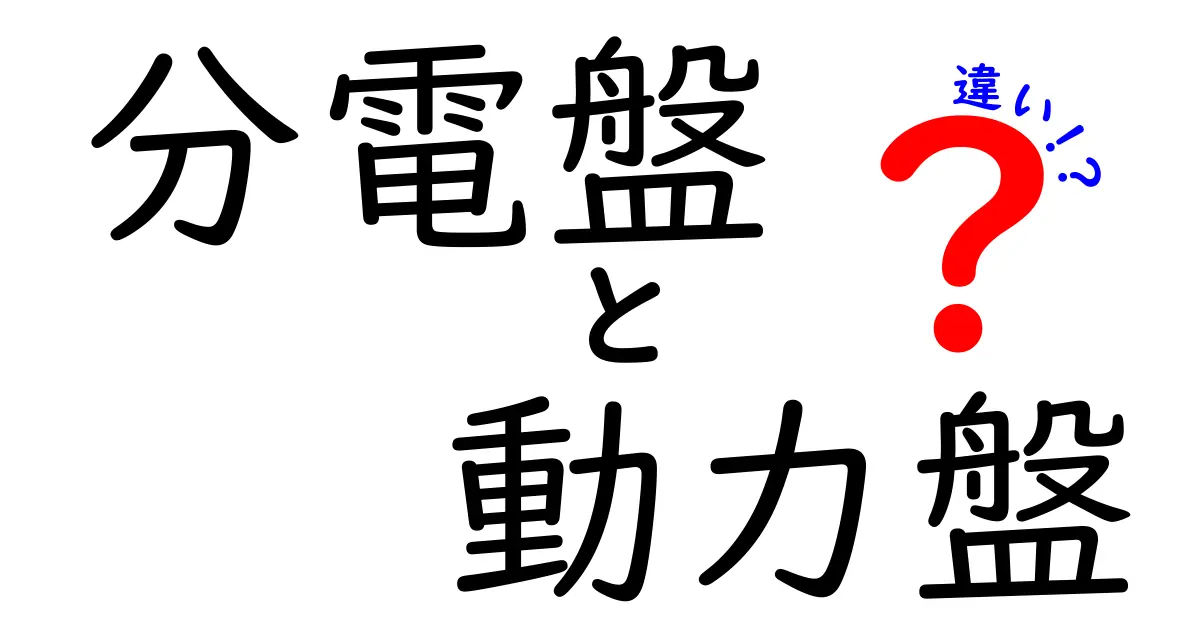
分電盤と動力盤とは何か?基本の説明
電気を安全に使うためには、電気設備が正しく設置されていることが重要です。
その中でよく耳にする「分電盤」と「動力盤」は、一見似ているようで役割が違います。
分電盤とは、家庭や建物に電気を配るための機械で、いろいろなところに電気を分けて送る役割をします。
一方、動力盤は主に工場などで使われるもので、大きな機械やモーターを動かすための電気を扱います。
この二つは見た目や名前も似ていますが、使い方や中身の構造が違うのです。
これから詳しく解説していきますので、電気に詳しくない人でもわかりやすいよう説明します。
分電盤の役割と特徴
分電盤は、建物のメインの電源から来た電気を、各部屋や機器に分けて送る役割を持っています。
家庭のブレーカーがついているボックスとイメージしてもらうとわかりやすいです。
主な特徴として、一般的な家庭用電気を管理している点です。
電灯やコンセントに電気を供給し、安全に使えるようにブレーカーがついています。
電気の流れが多すぎたり、短絡(ショート)が起きたときに電気を遮断し、火災防止などの安全対策をしています。
また、分電盤は単相200V(二線式や三線式)を扱うことが多く、中小規模の建物に使われます。
そのため、日常生活に欠かせない設備です。
動力盤の役割と特徴
次に動力盤ですが、これは産業用の電気設備として重要です。
工場や大きな施設で使うモーターや大型の空調機械を動かすための電気を管理しています。
三相交流(200Vまたは400V)を用い、たくさんの電力を安定供給することが求められます。
このため、動力盤は強力な装置や機械を動かせるように設計されています。
また、過電流遮断器や制御装置が組み込まれており、機械の安全運転や保護を行っています。
動力盤は一般住宅にはほとんど使われず、工場やビルの設備で活躍しています。
専門的な知識が必要で、電気工事士などの資格者が扱うことが多いです。
分電盤と動力盤の違いを表で比較
| 項目 | 分電盤 | 動力盤 |
|---|---|---|
| 用途 | 建物内の電気の分配・管理 主に家庭や中小規模施設 | 工場や大型設備の電気管理 大型モーターや機械の制御用 |
| 電源種類 | 単相交流(100V・200V) | 三相交流(200V・400V) |
| 役割 | 電灯やコンセントへの電気分配 過電流保護 | モーター等の動力供給 機械の安全運転・保護 |
| 設置場所 | 住宅、オフィス、店舗 | 工場、大型施設 |
| 取り扱い者 | 一般ユーザーや電気工事士 | 資格保持者・専門技術者 |
| 特長 | 漏電 | 短絡(ショート) |
|---|---|---|
| 現象 | 電流が回路外へ漏れる | 電路が異常に直接つながる |
| 原因 | 絶縁破損・水分・劣化 | 電線が接触・配線ミス |
| 危険性 | 感電、火災の危険あり | 火災や機器破損の危険大 |
| 対策 | 漏電遮断器・点検修理 | 短絡遮断器・安全配線 |
| 発生場所 | 配線の一部や電気機器 | 配線の接続部や機械内 |
日常生活で注意するポイントと安全に使うために
漏電も短絡も、どちらも電気を安全に使う上で重要なポイントです。定期的な点検とメンテナンスが事故を防ぎます。湿気や水気に注意したり、配線の劣化を見逃さないことが大切。
電気製品を扱うときは説明書をよく読み、規定通りに使うことが事故防止につながります。
また、漏電遮断器やブレーカーの故障は見逃しがちなので、専門家による定期点検を依頼するのが安心です。
漏電と短絡の違いを知って、正しい対策を取ることで、安心して電気製品を使っていきましょう。
漏電と短絡は似ているように見えますが、実は電気の流れ方が違うんです。漏電は電気が回路の外に流れることで感電や火災のリスクが高まります。一方、短絡はプラスとマイナスの線が直接つながって大量の電流が流れ、火事の危険がさらに大きくなります。漏電は水や劣化が原因になることが多く、短絡は配線のミスや傷が原因です。両方ともブレーカーが働きますが、それぞれの原因と対策を知ることが大切なんですよ。みんなも電気を安全に使うために、これらの違いを覚えておくと安心ですね!
前の記事: « 不導体と導体の違いを徹底解説!電気の流れが変わる理由とは?
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事
不導体と導体の違いを徹底解説!電気の流れが変わる理由とは?
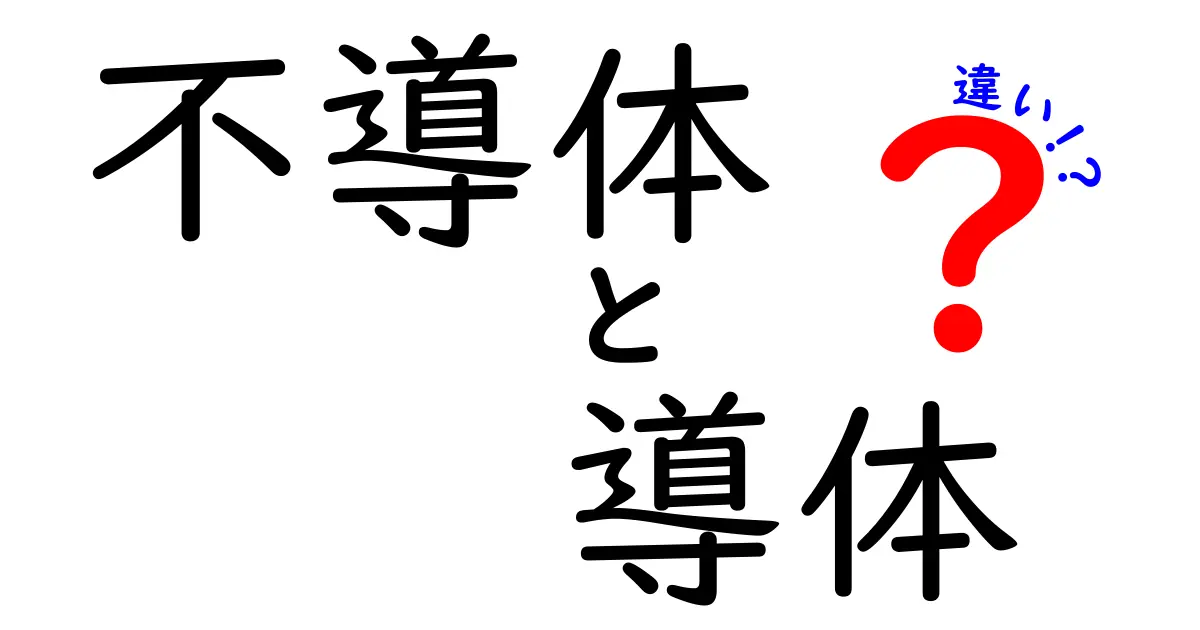
不導体と導体とは?基本の違いをわかりやすく解説
まずは不導体と導体の基本的な違いについて説明します。簡単にいうと、導体は電気を通しやすい材料のこと、不導体は電気をほとんど通さない材料を指します。
例えば、銅やアルミニウムは導体に分類され、電気配線に使われることが多いです。一方、ゴムやガラス、プラスチックは不導体で、電気を通しにくいため絶縁体として使われます。
この違いは、材料の中に自由電子(電気を運ぶ電子)がどれだけ存在するかに関係しています。導体は自由電子が多く、簡単に電気が流れます。不導体は自由電子がほとんどいないため電気が流れにくいのです。
導体の特徴と利用例
導体の最大の特徴は電気抵抗が非常に低いことです。抵抗が低いと電気がスムーズに通り、電気エネルギーのロスが少なくなります。
導体によく使われる銅は、加工しやすく丈夫で、安価であるため電線や電気機器の内部配線に使われます。アルミニウムも軽くて錆びにくいので送電線などで重宝されています。
導体は電気以外にも熱を通しやすい性質があり、熱伝導率が高いため、熱交換器などでも使われることがあります。
不導体の特徴と利用例
不導体は電気をほとんど通さず、電気の流れを遮断する役割があります。そのため絶縁体とも呼ばれます。
例えばプラスチックやゴムは電線の被覆材料として使われ、私たちが触っても感電しないように保護しています。ガラスやセラミックスも優れた不導体で、電子機器の部品や絶縁器具に利用されます。
不導体は熱の伝わりにくさも特徴で、断熱材に使われることもあります。これらの材料は電気の安全利用に欠かせません。
不導体と導体の違いをまとめた表
まとめ:不導体と導体は何が違う?
不導体と導体の違いは、電気を通すか通さないかという性質の違いです。これは材料内部の電子の動きやすさに由来していて、日常生活や科学技術で大切な役割を持っています。
導体は電気をスムーズに流すことから、電気回路や配線に使われます。不導体は電気の漏れや感電から守るための絶縁体として使われ、電気の安全利用には欠かせません。
この2つの違いを知ることで、身の回りの電気製品の構造や安全性が見えてきます。ぜひ覚えておきましょう!
導体の一つである銅は、実は金よりも電気の伝導率が高いことをご存じですか?銅は手に入りやすく安価なので配線に使われますが、銀のほうが電気をもっとよく通します。とはいえ銀は値段が高いので、電気回路の最も重要な部分だけに使われることが多いんですよ。普段何気なく見ている配線でも、素材の特性がしっかり活かされているんですね。
次の記事: 漏電と短絡の違いとは?わかりやすく解説!安心な電気の使い方 »