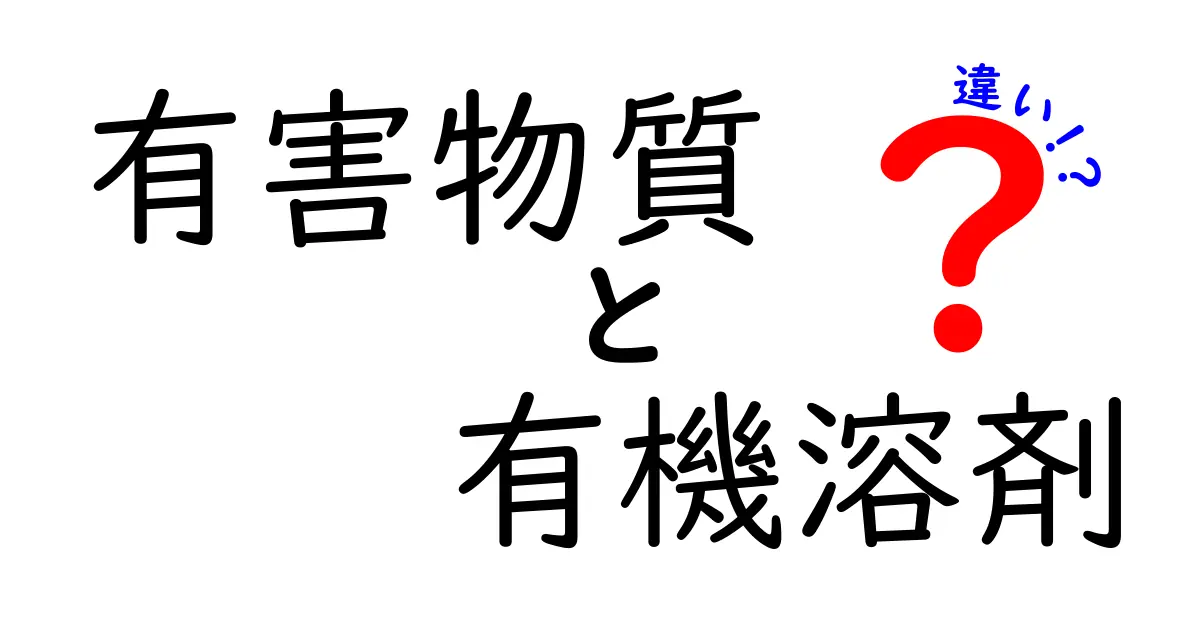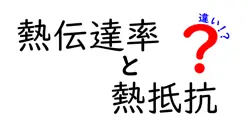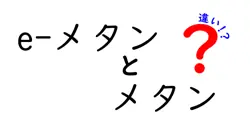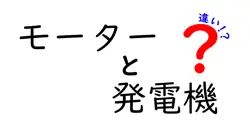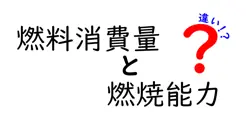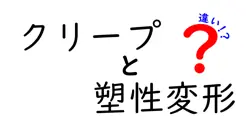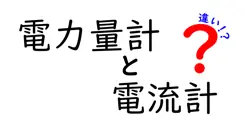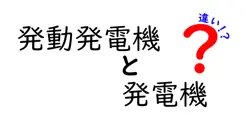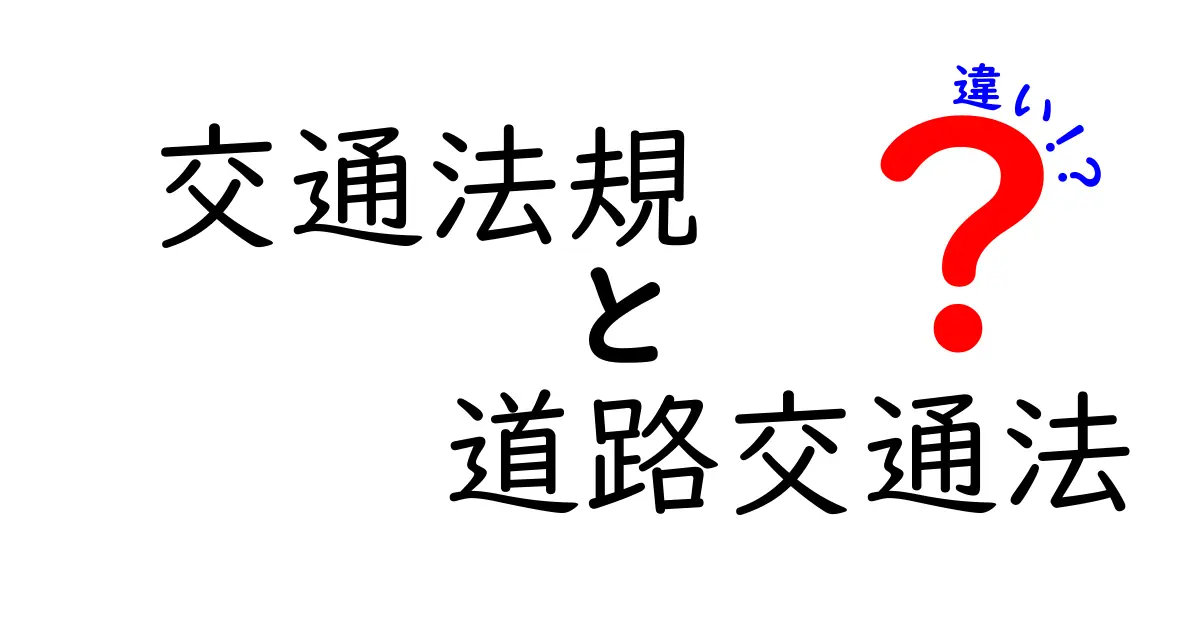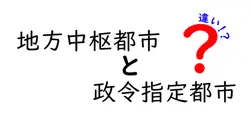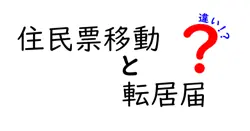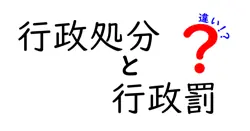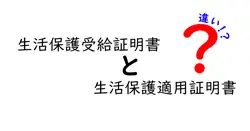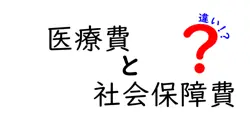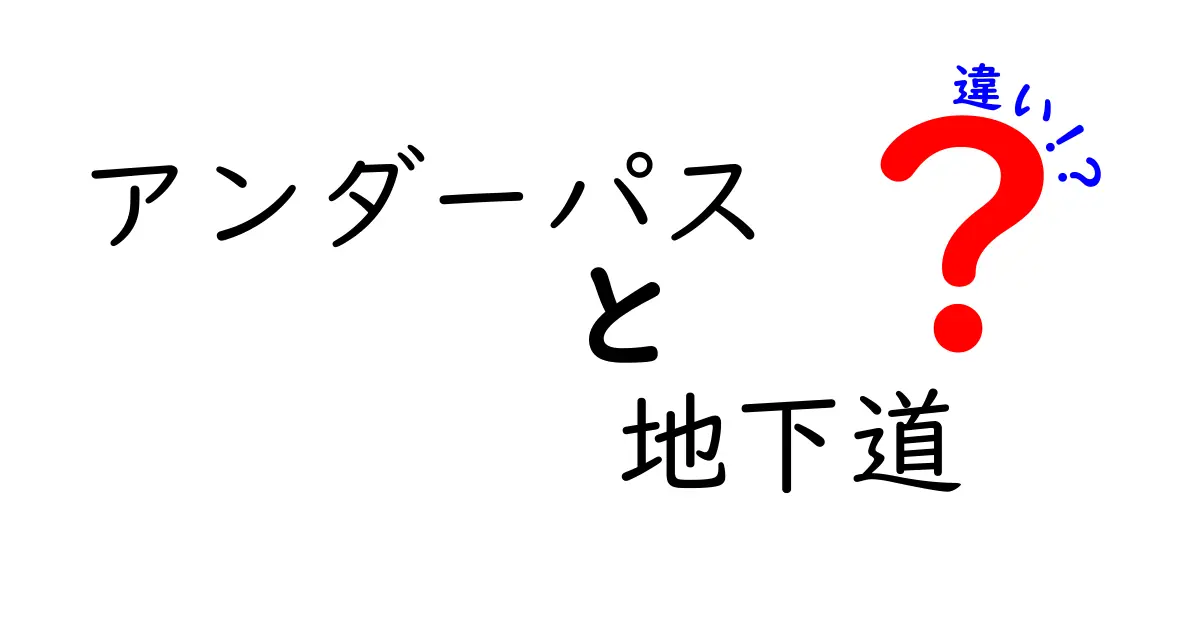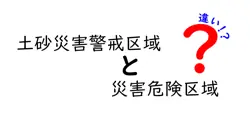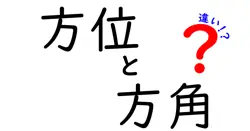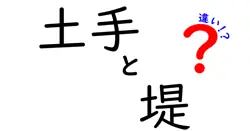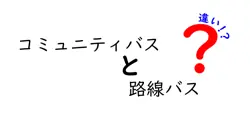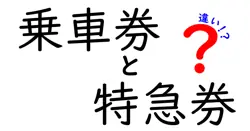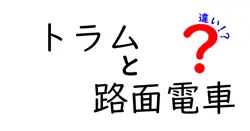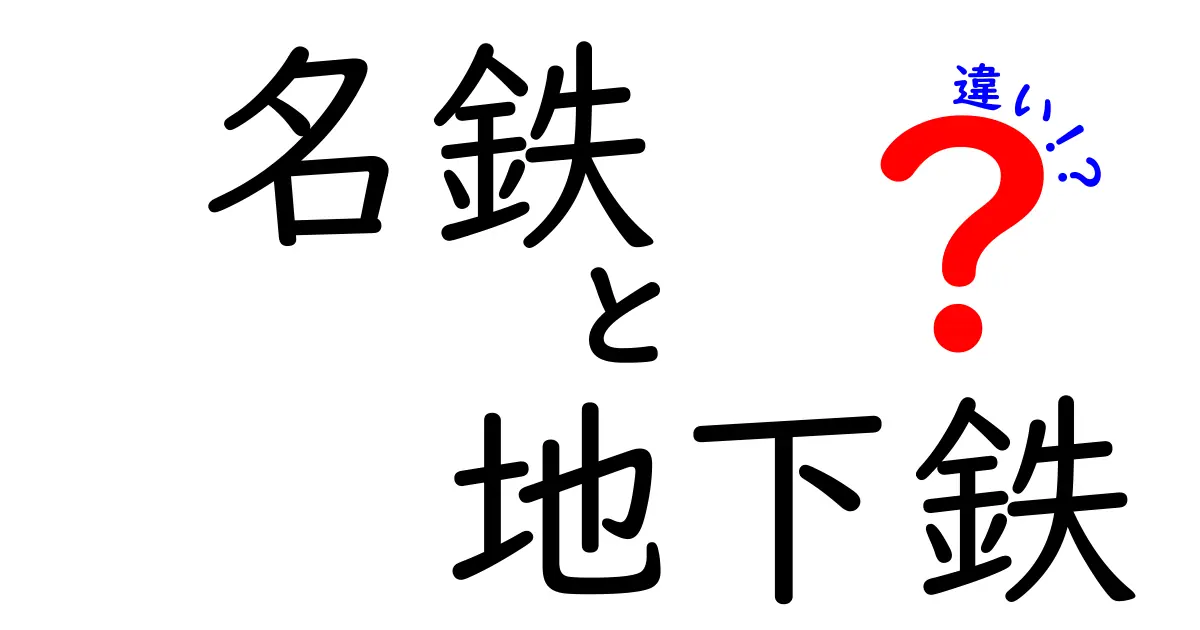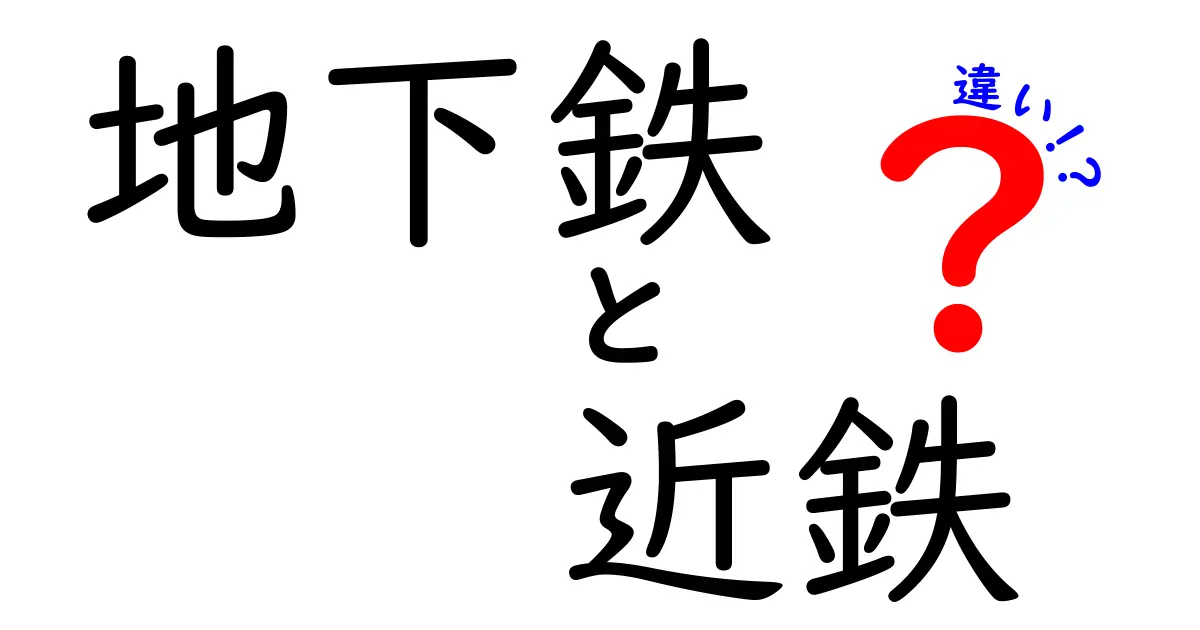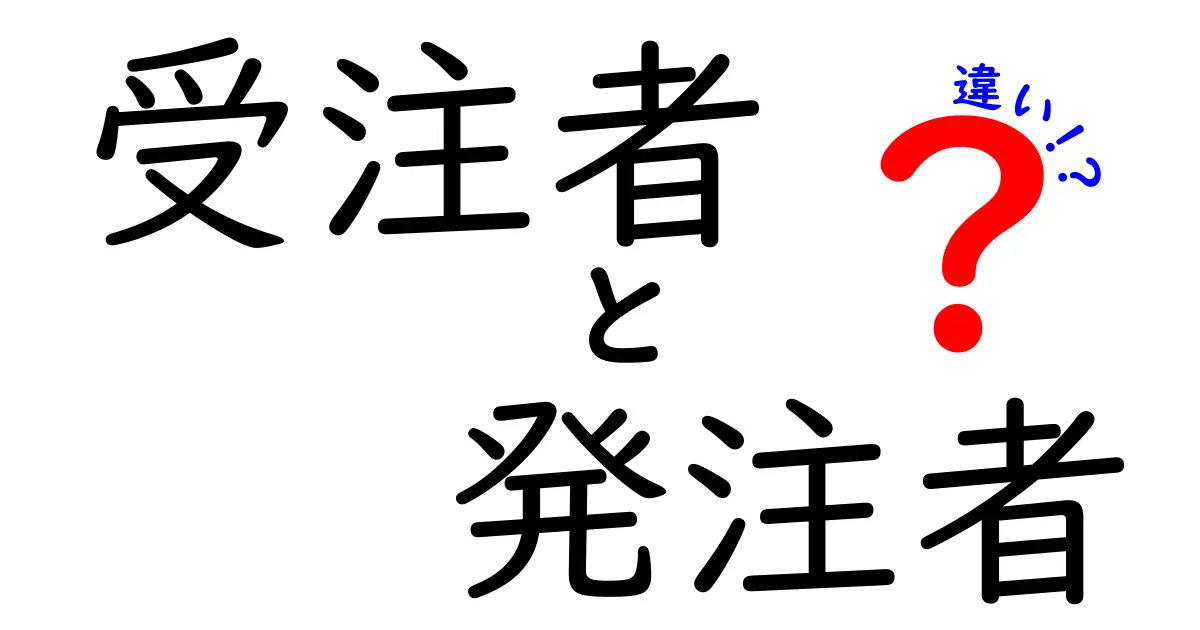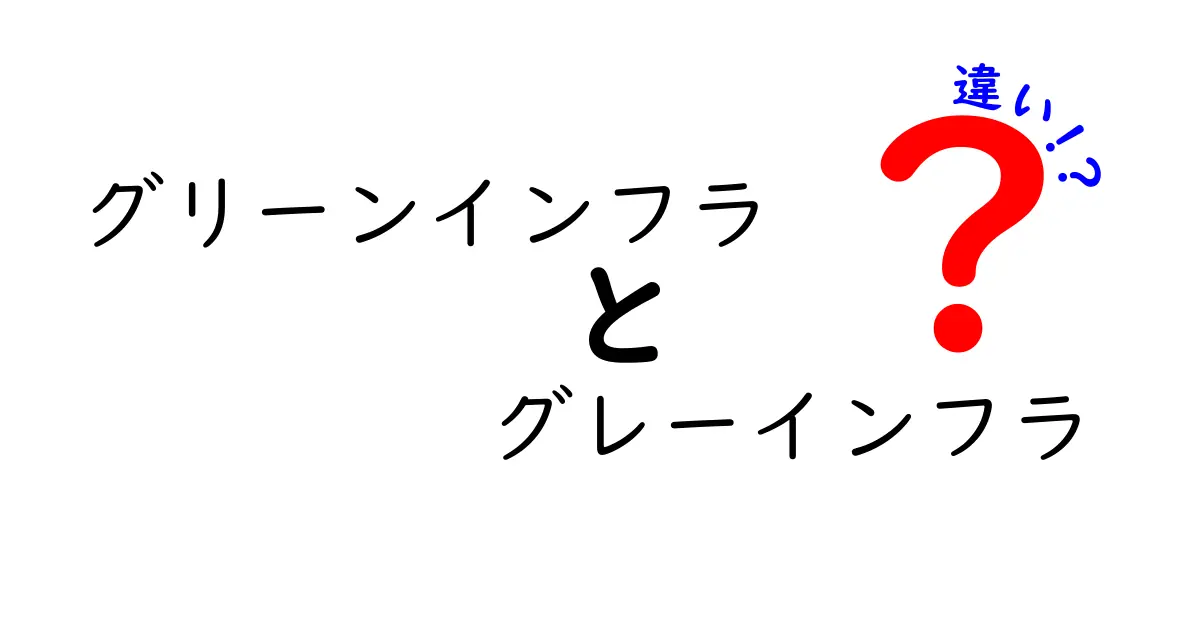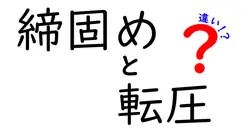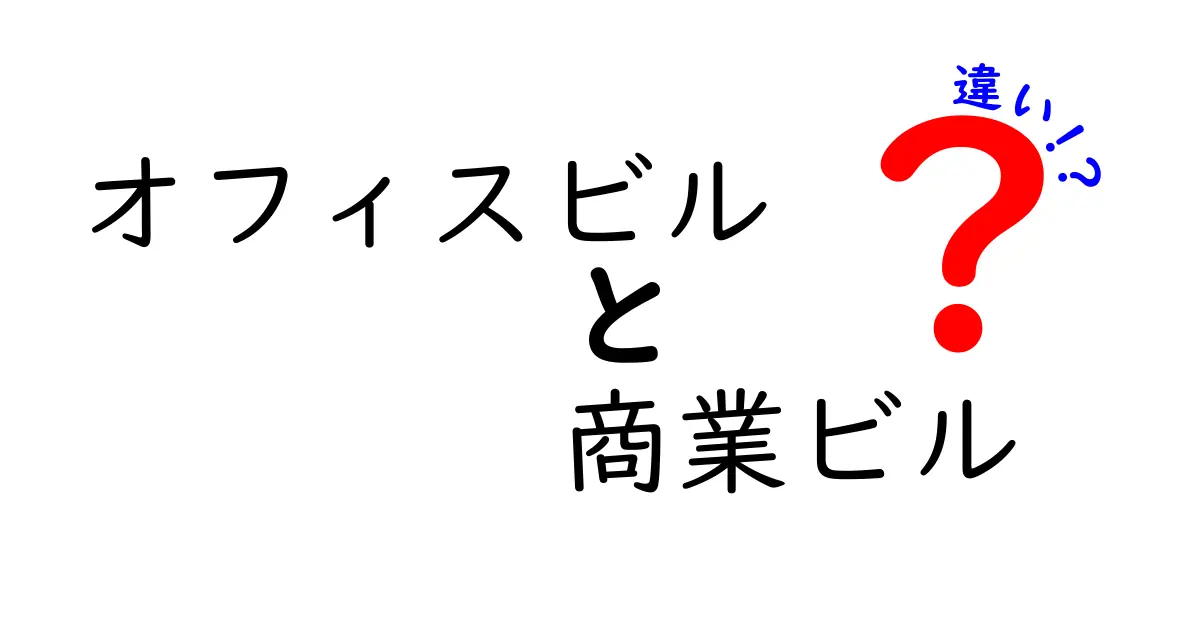
オフィスビルと商業ビルの基本的な違い
オフィスビルと商業ビルは、どちらも街中でよく見かける建物ですが、その用途や役割にははっきりとした違いがあります。
オフィスビルは主に会社や企業が仕事をする場所として利用される建物で、普通はたくさんの部屋があり、企業の事務作業を行うスペースが中心です。
一方、商業ビルはお店やレストラン、サービス業などが集まっている建物のことを指し、人々が買い物や食事、さまざまなサービスを受ける場所とされています。
つまり、オフィスビルは「働く場所」、商業ビルは「買い物やサービスを受ける場所」と覚えるとわかりやすいでしょう。
オフィスビルの特徴と用途
オフィスビルは主に会社の仕事場として使われ、机やパソコン、会議室などが設置されています。
たとえば銀行や広告会社、IT企業などが入っていることが多く、一般の人は仕事をしにいく場所です。
また、オフィスビルは清潔で静かに保たれていることが多く、集中して作業ができる環境作りがされています。
高層のものも多く、多数の企業がひとつのビルに入っていることもあります。エレベーターや防犯設備、空調など仕事に快適な設備が揃っているのも特徴です。
商業ビルの特徴と用途
商業ビルはスーパーや洋服店、レストラン、カフェ、美容院など、多くの店舗や飲食店が集まった建物です。
人々は買い物をしたり、食事を楽しんだり、いろんなサービスを利用したりするために訪れます。
営業時間も店舗ごとに異なりますが、基本的には一般の人向けに開かれており、にぎやかな雰囲気が特徴です。
また、商業ビルは駅近くにあったり、交通の便が良いところにあることが多いです。駐車場やエスカレーターも整備されていて、歩きやすさや便利さが重視されます。
オフィスビルと商業ビルの違いを一覧表で比較
| ポイント | オフィスビル | 商業ビル |
|---|---|---|
| 主な用途 | 企業の仕事場 (事務作業、会議等) | 店舗や飲食店などのサービスの提供 |
| 利用者 | ビジネスマンや働く人 | 一般のお客さん、買い物客 |
| 雰囲気 | 静かで落ち着いている | にぎやかで活気がある |
| 設備 | 会議室、オフィス家具、防犯設備 | エスカレーター、駐車場、レジ |
| 場所 | オフィス街やビジネスエリア | 駅周辺、商店街、ショッピングモール内 |
| 項目 | 有害物質 | 有機溶剤 |
|---|---|---|
| 定義 | 健康や環境に悪影響を及ぼすすべての物質 | 有機化合物でできた、物質を溶かす液体 |
| 範囲 | 非常に広範囲(無機物・有機物・重金属・放射性物質など) | 有害物質の中の一部で、有機化合物に限定 |
| 使用例 | 農薬、重金属、放射性物質など多数 | 塗料、接着剤、洗浄液、化粧品成分 |
| 健康影響 | 様々(中毒・発がん・神経障害など) | 主に神経毒性・呼吸器障害・皮膚障害など |
| 管理 | 法律や規制が多岐にわたる | 換気・防護具の着用が推奨される |
このように、有機溶剤は有害物質の一部ですが、特に揮発性が高く人体への影響も大きいため、区別して理解することが大切です。
まとめ:日常生活での注意点と安全対策
有害物質と有機溶剤を正しく理解することは、健康被害を防ぐために欠かせません。
日常生活で注意すべきポイントは以下の通りです。
- 製品ラベルをよく読むこと:どのような有害物質が含まれているか確認しましょう。
- 換気を十分に行うこと:特に有機溶剤を使う場合は、窓を開けたり換気扇を使用しましょう。
- 保護具の着用:手袋やマスク、目を守るゴーグルなどを使用し直接触れないようにすること。
- 調べて理解すること:知らない物質や危険な成分については調べて理解を深めることが安全行動につながります。
仕事や趣味で有機溶剤やその他の有害物質を扱う場合は、必ず専門の指導を受け、正しい取扱いや廃棄方法を守りましょう。
健康と環境を守るための知識をもつことが、自分自身や周囲の安全を守る第一歩です。
有機溶剤って聞くと難しそうに感じますが、実は日常生活にも結構身近なんです。例えば、除光液やマニキュアのリムーバーには「アセトン」という有機溶剤が使われています。換気をしっかりしないと頭がぼーっとしたり、気分が悪くなったりすることもあるので、使うときは窓を開けて新鮮な空気を取り入れるのがおすすめですよ。有機溶剤は便利ですが、臭いや揮発性を甘く見ると体調に響くんです。ちょっとした工夫で快適に使えるんですね。
科学の人気記事
新着記事
科学の関連記事
シールド工法と推進工事の違いをわかりやすく解説!土木工事で使われる2つの技術とは?
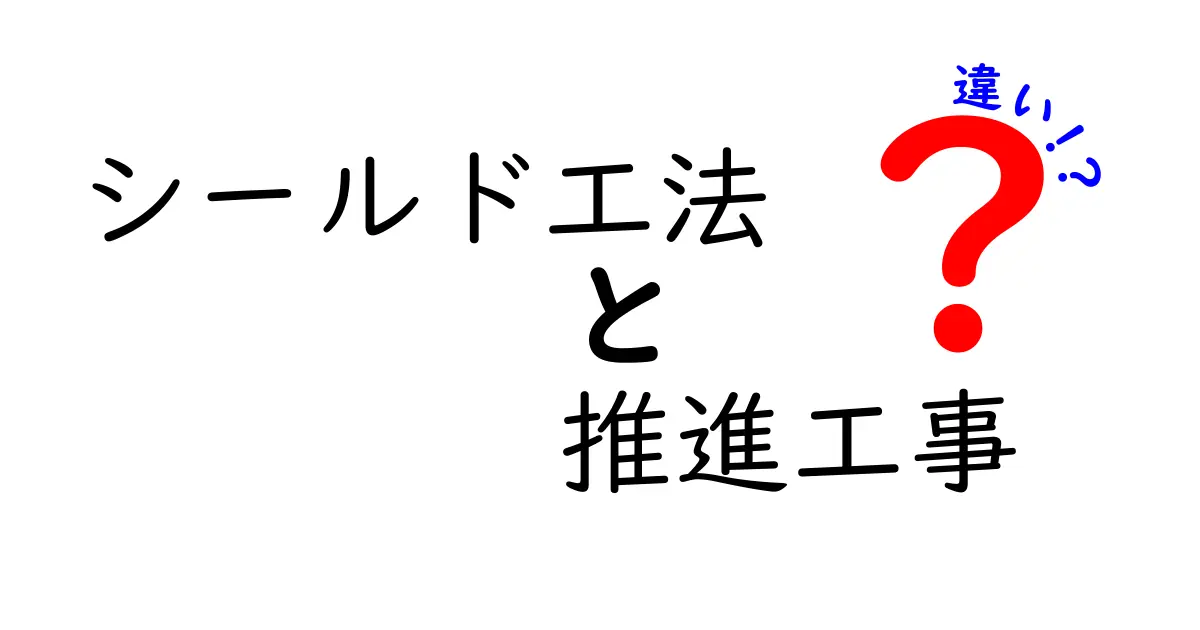
シールド工法とは何か?
シールド工法は、地中にトンネルを掘り進めるための代表的な工法の一つです。大きな円筒形の機械(シールドマシン)を使いながら土や岩を掘り取り、同時にトンネルの壁を支える構造物を設置していきます。
この方法は地下鉄や道路のトンネル工事でよく使われており、周囲の地盤を安定させながら安全にトンネルを作ることができます。掘削と支保工の設置が同時進行で行われるため、地盤の崩壊リスクが減り、工事の安全性が高いのが特徴です。
特に都市部の地下でのトンネル掘削に向いているため、交通の邪魔をせずに地下空間を作り出すことができます。
推進工事とは?その仕組みと使われ方
推進工事は、主にパイプや箱型の構造物を地中に押し込んで設置する工法です。トンネルを掘るのではなく、既製の管を地面の中に直接押し込んでいく方法です。
この工法は下水管や水道管、電線管路を設置する際によく選ばれます。トンネルのような大きな空間を作るわけではなく、必要なパイプを土の中に埋め込むイメージです。
地上の掘削が難しい場所や、交通が多い道での作業にも適しているため、工期が短く、周囲への影響が少ないメリットがあります。
シールド工法と推進工事の主な違い
では、この2つの工事方法はどう違うのでしょうか。以下の表で主な違いをまとめてみました。
| ポイント | シールド工法 | 推進工事 |
|---|---|---|
| 目的 | トンネル掘削・掘り進める | パイプや管の地中埋設 |
| 施工方法 | シールドマシンで掘削しながら支保工設置 | パイプを地盤に押し込む |
| 施工範囲 | 大規模な地下空間 | 比較的小規模で狭い断面 |
| 適用例 | 地下鉄、道路トンネル | 下水管、水道管、ケーブル管路 |
| 工期・コスト | 長く高コスト | 短く低コスト |
このように用途や施工方法によって使い分けられています。
特に作りたい地下空間の大きさや目的によって、どちらの工法が適しているかが変わってきます。
まとめ:どちらの工法を選ぶべき?
シールド工法と推進工事は、一見似ているようで土木建設において全く違う役割を持っています。
地下の大きなトンネルを掘るにはシールド工法が適していますし、パイプや小さな管路を埋設するなら推進工事が選ばれます。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、工事内容に応じて使い分けることが大切です。
今後、地下空間の利用やインフラ整備が進む中で、これらの工法の重要性はますます高まっていくでしょう。
これを機に、土木工事の基礎知識として知っておくと役立つ技術です。
シールド工法の機械、シールドマシンは巨大なトンネル掘削の主役ですが、その構造は驚くほど精密です。なんと、前方の掘削ヘッドは地層を細かく削りながら回転し、後方ではトンネル壁のコンクリートパネルを組み立てる専用の装置が備わっています。これにより、掘削しながら即座に壁を作る、まさに未来の地下工事ロボットのような働きかけをしています。都市の地下でこれだけスムーズに安全にトンネルを作れるのは、最新技術のおかげと言えますね。
前の記事: « 番頭と職長の違いを簡単解説!仕事内容や役割、責任の違いって何?
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事
番頭と職長の違いを簡単解説!仕事内容や役割、責任の違いって何?
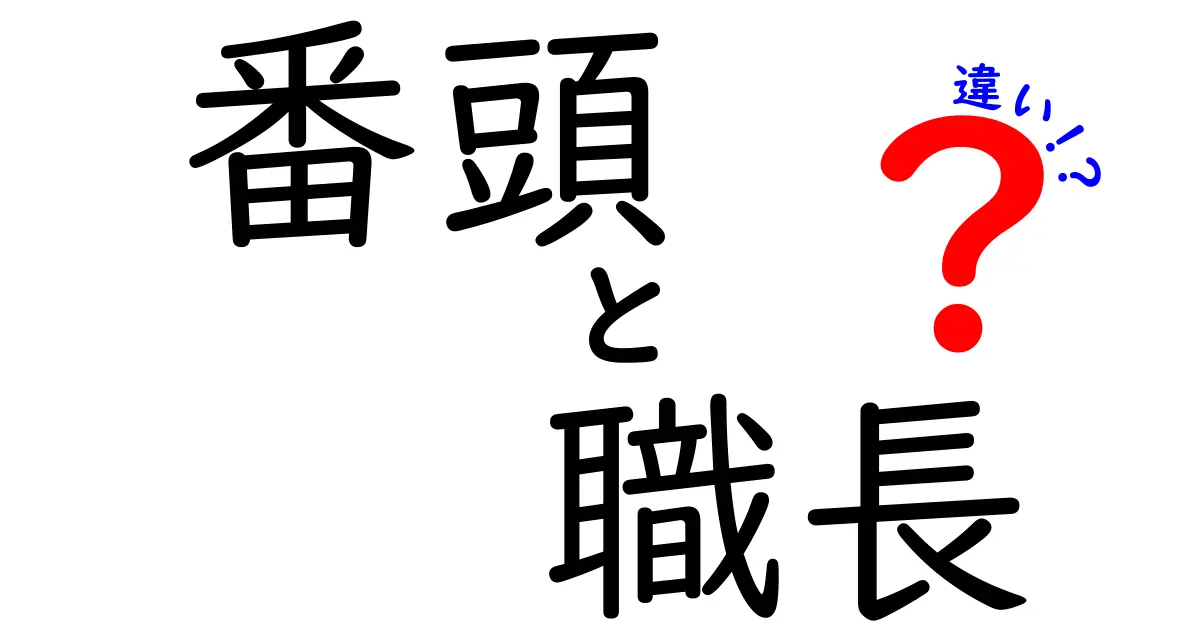
番頭と職長って何?基本の意味からチェック!
日本の職場や現場では「番頭」と「職長」という言葉をよく耳にします。でも、両者はどんな役割があるのか、何が違うのか意外と知られていません。
まず「番頭」とは、昔から日本の商売や店舗で店主や社長の右腕的存在として、店の運営や管理全般を任されています。単なる従業員ではなく、現場のまとめ役として責任あるポジションです。
一方「職長」は主に建設現場や工場などで、作業員のリーダーとして現場の仕事を管理・指導する役割を持っています。現場での作業の安全や効率を考える重要な役職です。
それぞれの言葉のイメージや使われる場所が違うため、役割も異なるのです。
番頭と職長の仕事の違い|具体的な役割を比較!
では、具体的にどう違うのでしょうか?簡単にまとめると次のようになります。役割 番頭 職長 主な職場 商店、会社の事務所 建設現場、工場などの作業現場 仕事内容 店舗運営、経理、従業員管理 作業指導、安全管理、作業計画の調整 責任範囲 経営補佐、店舗全般の管理 現場作業の安全と効率 資格・肩書き 専門的な資格は不要 職長教育の受講が義務付けられる場合あり
番頭は経営側の管理職的存在
番頭は会社や店舗の運営を支える役割で、経理や在庫管理、人の採用や教育にも関わることが多いです。つまり、経営者に近い立場でお店や会社の状態を把握し、改善案を考えたり実行したりします。
職長は現場のリーダー
職長は実際の現場作業をまとめる役目で、作業員に仕事を割り振り、安全を守りながら効率良く仕事を進める役割があります。ですから現場管理のスキルや安全に関する知識も必要になります。
まとめ:番頭と職長はどんなときに使い分ける?
最後に違いをまとめると、
- 番頭は会社やお店の中で経営者のサポートをする管理職的ポジション
- 職長は現場作業をまとめ安全と効率を守るリーダー的存在
用途や現場が大きく違うので、職場や仕事内容によって使い分けられています。
仕事の責任も範囲も違うため、あなたが仕事で関わるならば役割や求められるスキルをよく理解したほうが良いでしょう。
こうした日本独特の職務名は、現代でも根強く使われていることが多く、職場内の役割を知るヒントになるので覚えておくと役立ちます。
「番頭と職長の違い」を理解して、職場でのコミュニケーションや役割分担に活かしていきましょう!
「職長」という言葉は、建設現場や工場でよく使われますが、実は「安全管理者」としての役割が非常に大切です。作業員をまとめるだけでなく、事故を防ぐために安全教育を受けたり、安全器具の準備をしたりする責任があります。小さな現場でも職長がしっかり役割を果たすことで、大きな事故が防げることも。現場の裏方というよりは、みんなの安全を守るリーダーなんですね。そう考えると、職長の責任と役割の重大さがよくわかります!