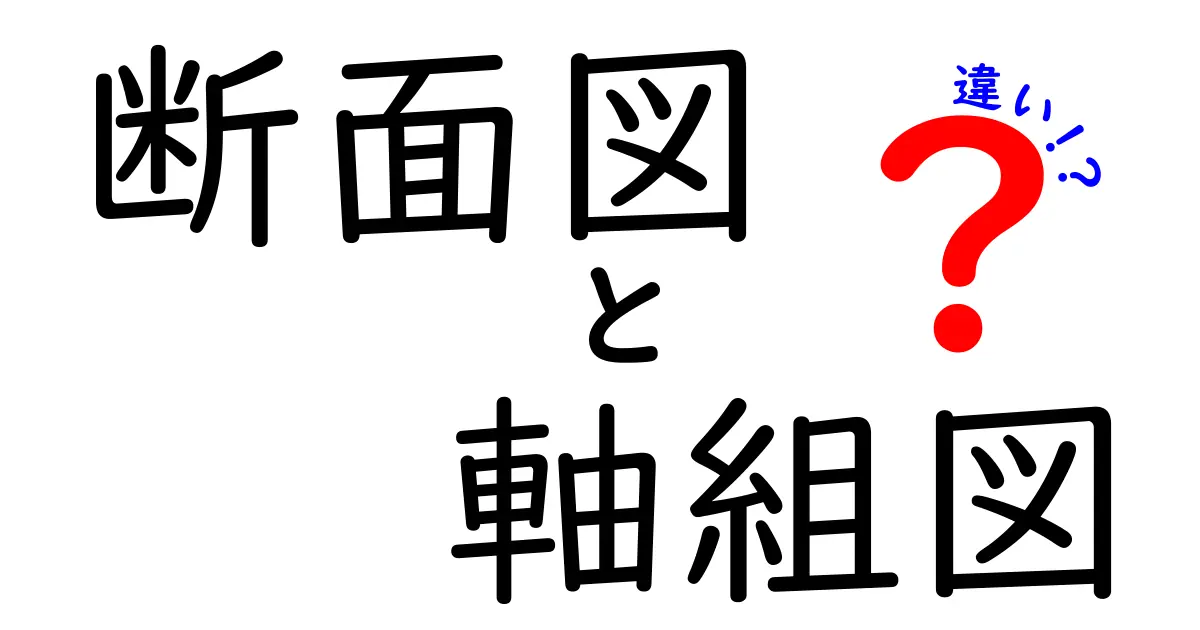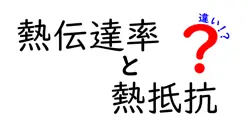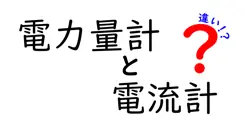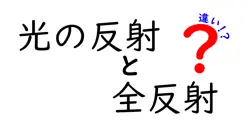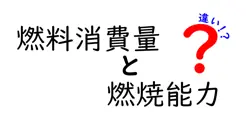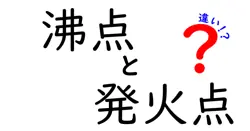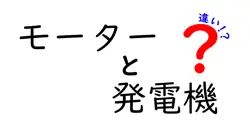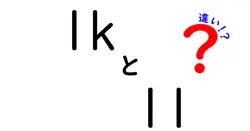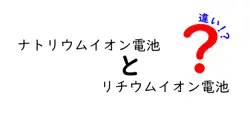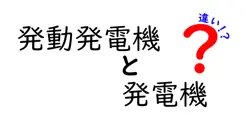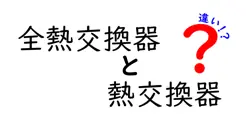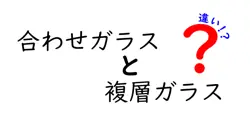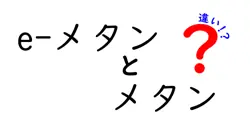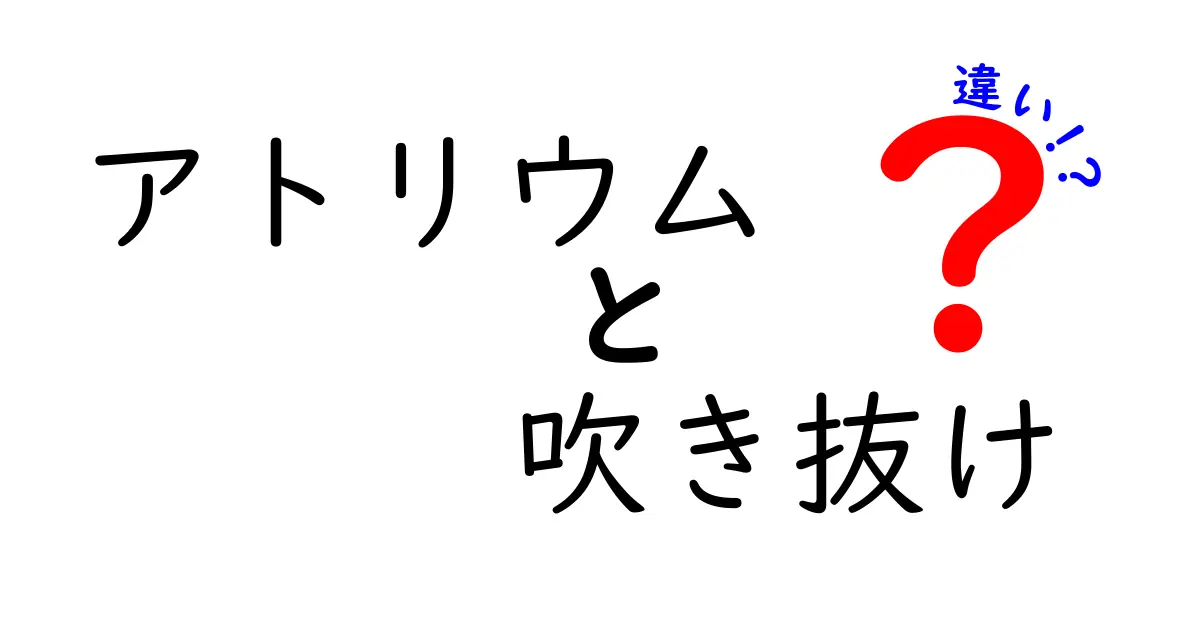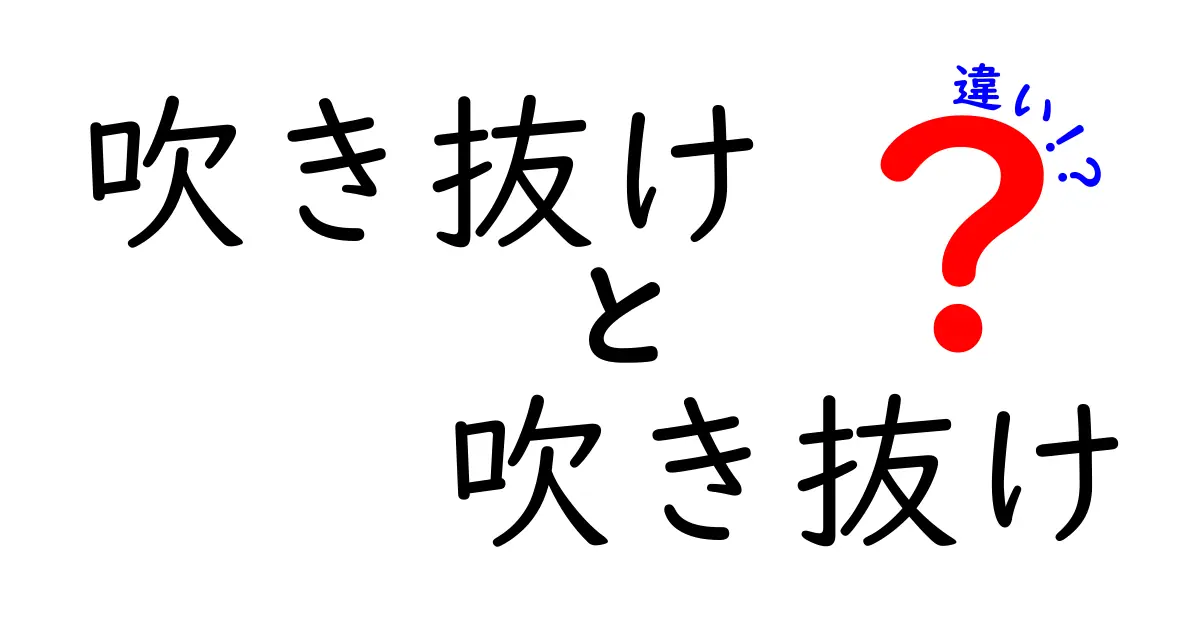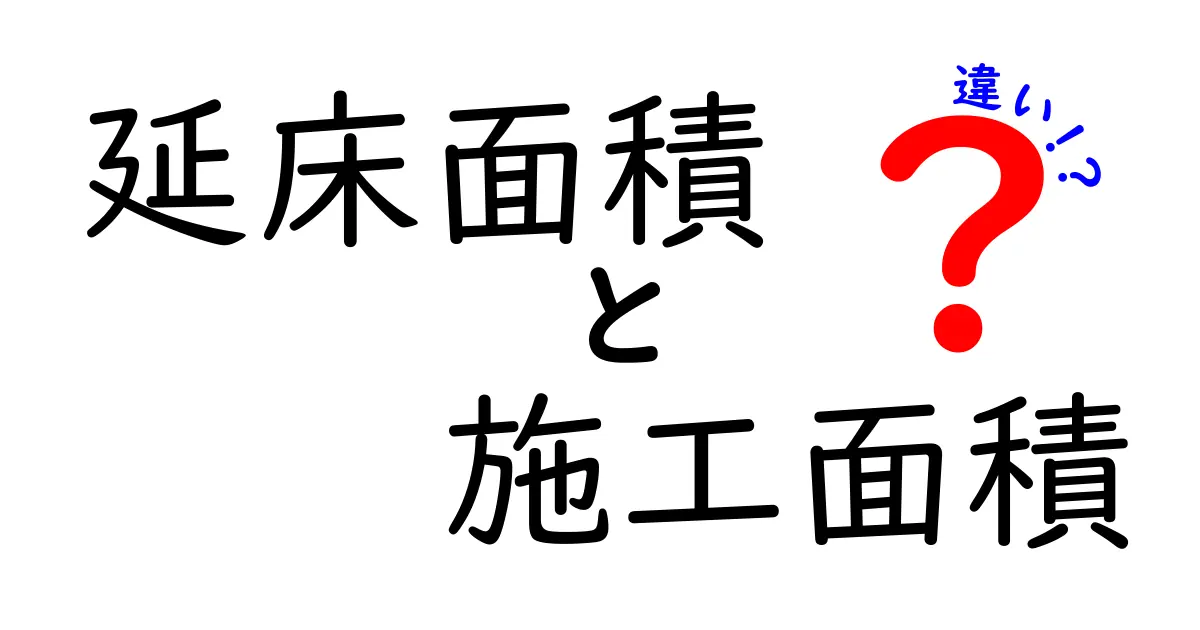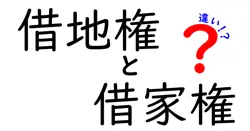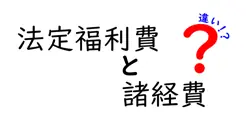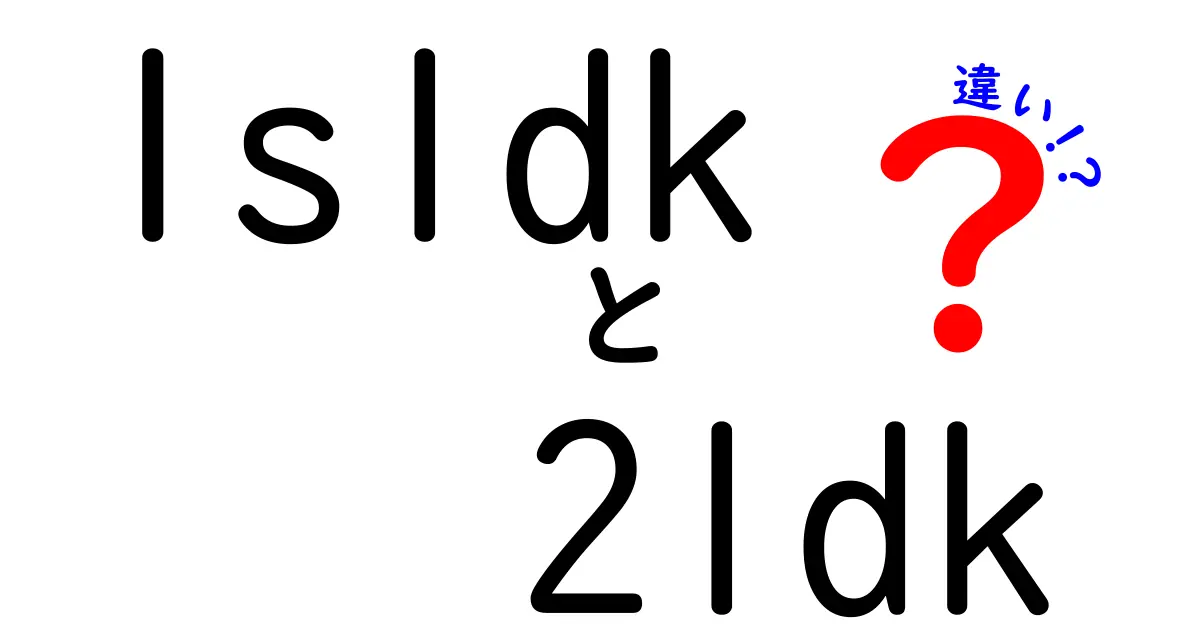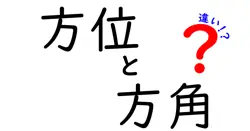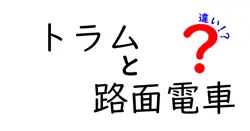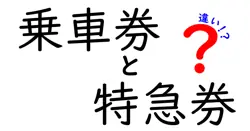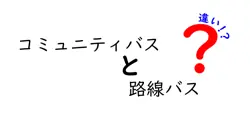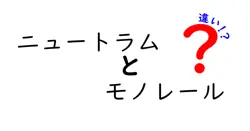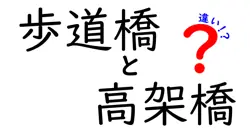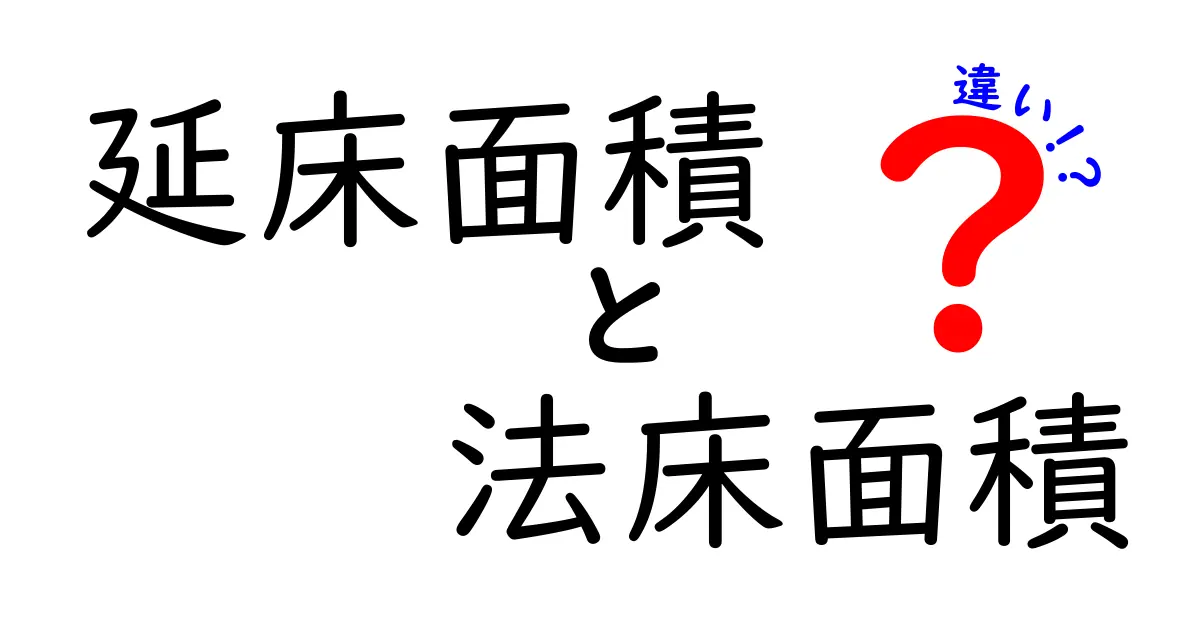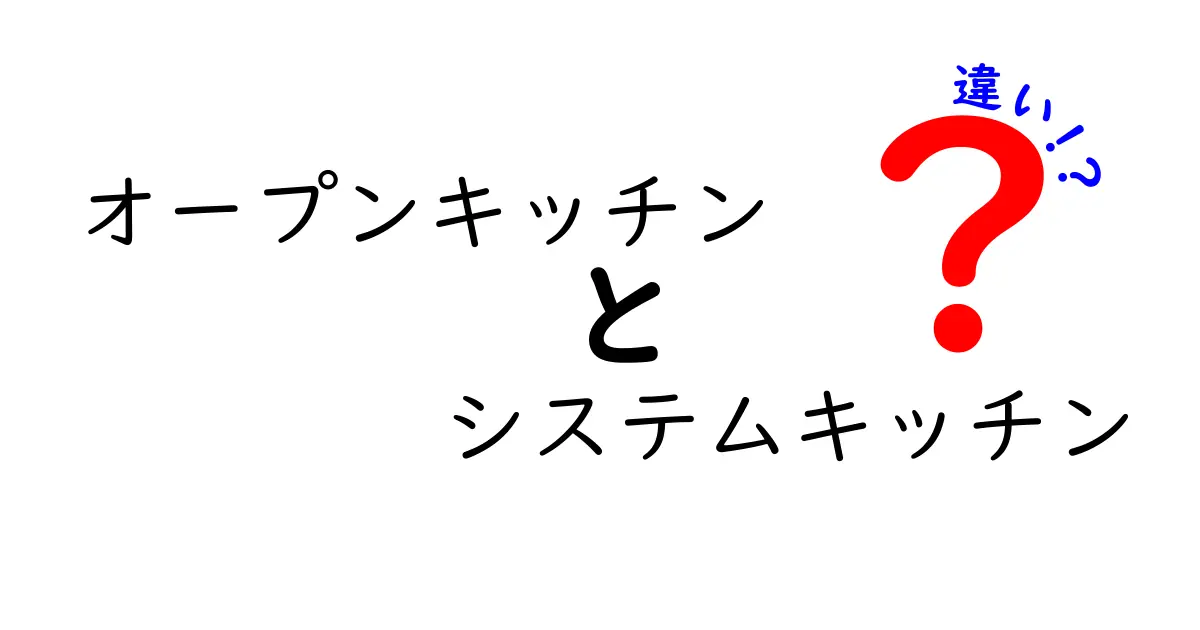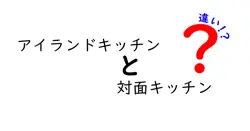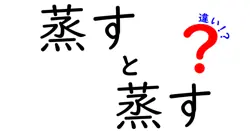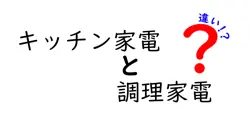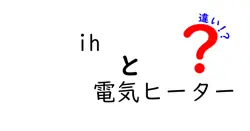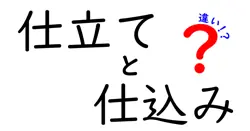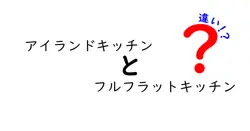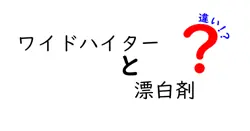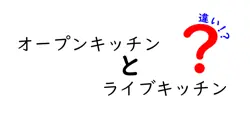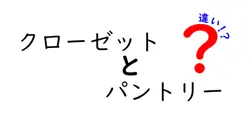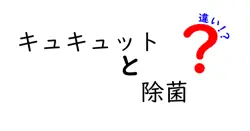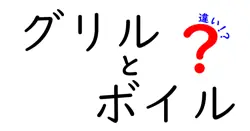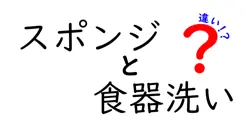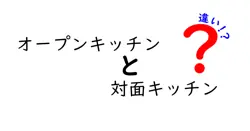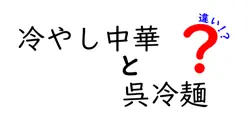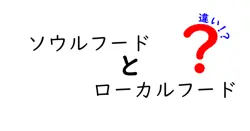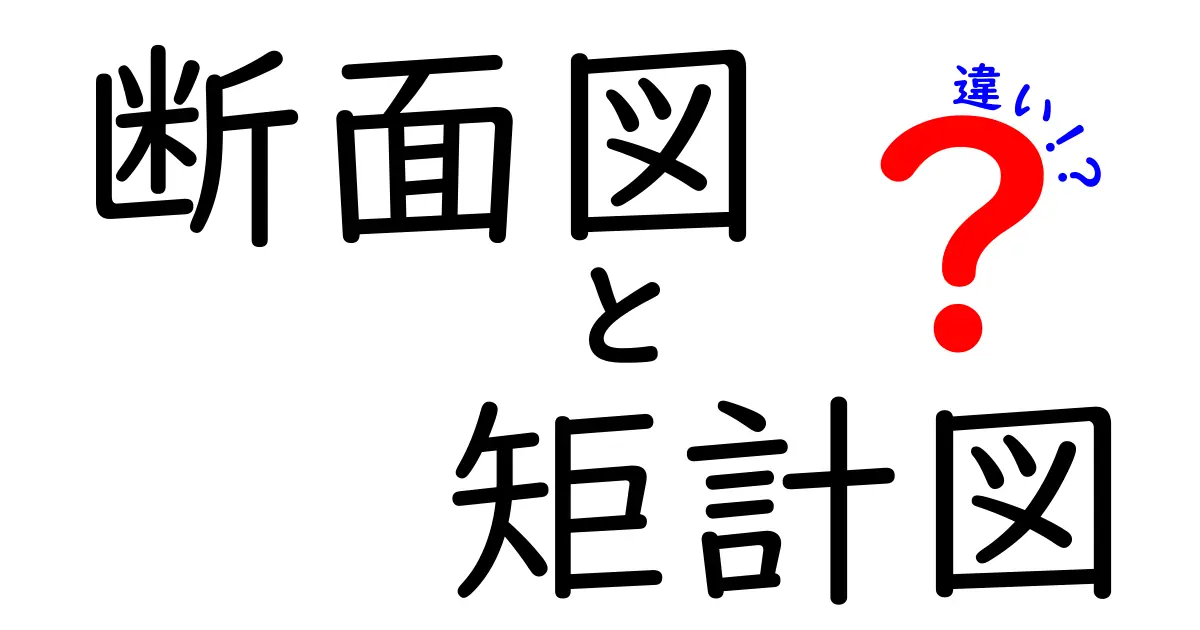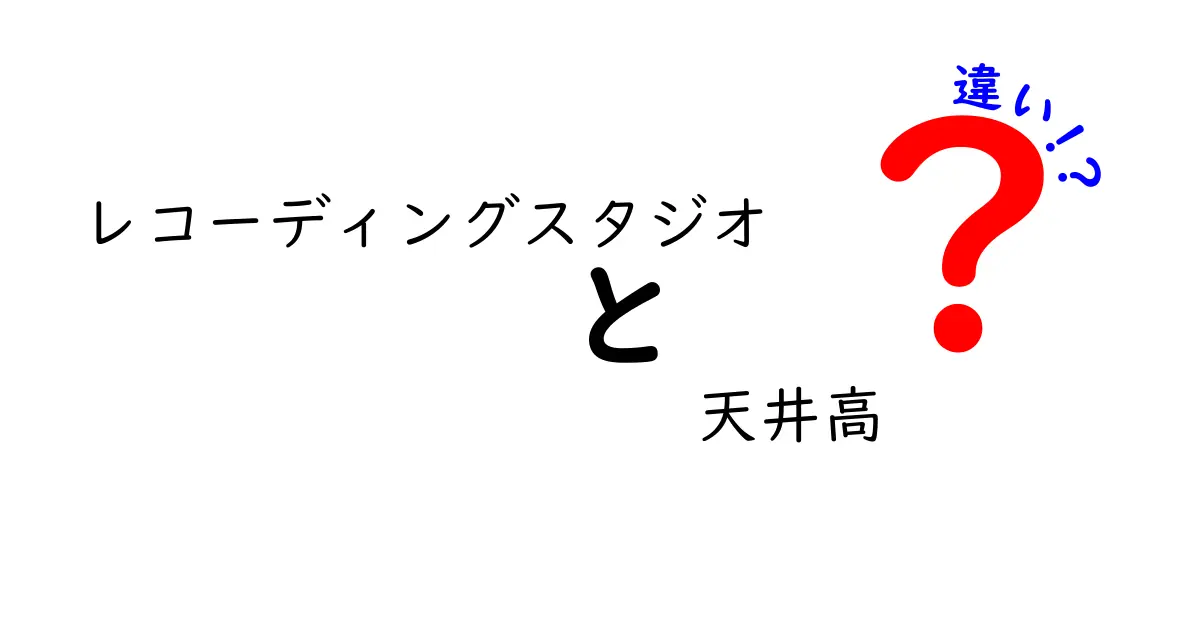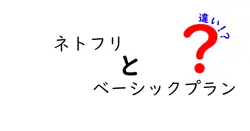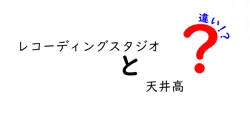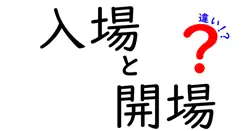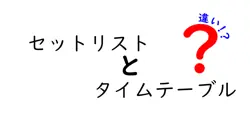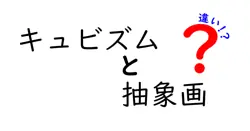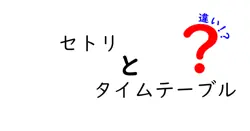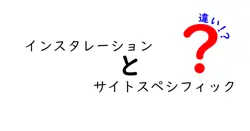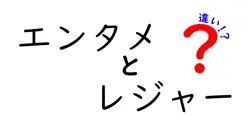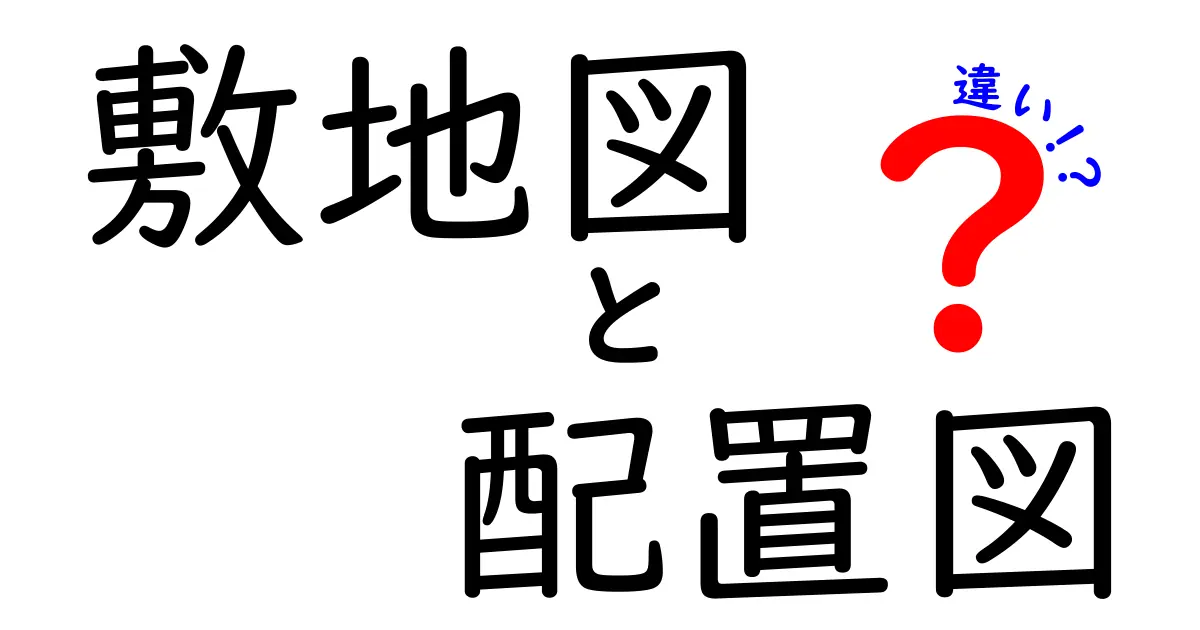延床面積と施工面積の基本的な違いとは?
家づくりや不動産の話でよく出てくる言葉に「延床面積(のべゆかめんせき)」と「施工面積(せこうめんせき)」があります。
この2つの言葉は似ているようで意味が違います。まず、延床面積とは建物の各階の床面積を合計した数値のことを指します。例えば、2階建ての家なら1階と2階の床面積を足したものです。
一方、施工面積は建物の外壁の中心線で囲まれた水平投影面積の合計になります。
つまり、延床面積は部屋の中の床の面積の合計で、施工面積は建物自体のボリュームや建築範囲を表す数字として使われます。
この違いを理解することは建物の広さや使用感を知るうえでとても大事です。
延床面積と施工面積の具体的な見方と注意点
延床面積は、広告や設計図面でよく見かける「㎡(平方メートル)」で表され、基本的に各階の床に壁や柱の内側の部分を含む床の合計です。
例えば、1階が50㎡で2階が40㎡の家なら、延床面積は90㎡となります。
それに対し、施工面積は壁の中心線で囲まれた外観の面積なので、その建物の外寸を含み、ベランダやバルコニーなども含むことがあります。
ですので施工面積は延床面積より広くなることが多いです。
実際に家の大きさをイメージするには延床面積を参考にし、施工面積は工事の規模やコストを測るために使うことが多いです。
しかし、業者によっては施工面積の範囲が異なることもあり、注意が必要です。
延床面積と施工面積の違いをまとめた表
ここで、それぞれの違いがひと目で分かるように表にまとめてみました。
ding="5" cellspacing="0">| 用語 | 意味 | 含まれる部分 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| 延床面積 | 建物の各階の床の合計面積 | 内壁や柱の内側の床全体
(居住空間が中心) | 建物の広さや居住空間を示す | 実際の生活スペースの目安になる |
| 施工面積 | 建物の外壁中心線で囲まれた水平投影面積 | 外壁の厚みやベランダなども含む | 施工範囲や工事費の見積もりに使用 | 延床面積より広いことが多い |
able>
このように、目的によってどちらの面積を見るかが変わります。家を購入するときや建築計画を立てるときにも知っておきたい大切なポイントです。
まとめ:延床面積と施工面積の違いを理解して賢く家づくりを!
今回ご紹介した延床面積と施工面積は
似ているようで用途も意味も違います。
延床面積は家の中の床の広さ、つまり実際に使える生活スペースの広さを示し、
施工面積は建物の外形や工事規模を示す数値です。
これを理解すると、建物の大きさやコストの見方がわかりやすくなります。
家づくりや不動産選びでしっかり活用しましょう!
ピックアップ解説延床面積についてもっと掘り下げると、実は住宅ローンの審査や固定資産税の計算にも関係していることが多いんです。
延床面積は生活空間の広さの目安だから、銀行や税金を扱うところはそれを基準にしています。
だから、同じ100㎡でも施工面積が違う建物があるとコストや税金が変わってくることがあります。
家の広さだけでなく、経済的な面でも大事な数字と言えますね。
ビジネスの人気記事

200viws

155viws

149viws

144viws

144viws

143viws

139viws

137viws

123viws

123viws

112viws

111viws

107viws

106viws

99viws

97viws

95viws
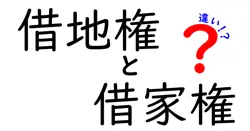
90viws

89viws
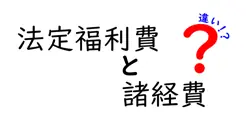
87viws
新着記事
ビジネスの関連記事
1SLDKと2LDKの違いとは?基本の間取りをチェックしよう
賃貸物件やマンションの広告でよく見かける“1SLDK”や“2LDK”という言葉。
これらはお部屋の間取りを表す記号ですが、実は意味合いや使い勝手が少し違います。
まず、“LDK”は「リビング(Living)、ダイニング(Dining)、キッチン(Kitchen)」が一緒になっている部屋のこと。
数字は“寝室の数”を表していて、1LDKは寝室1つにLDKという間取り、2LDKは寝室2つにLDKという間取りです。
では、“S”は何かというと、“サービスルーム”の略で、収納や書斎、小さな部屋として使えるスペースを指します。
ただし窓がなかったり、居室(生活する部屋)として正式に認められていない場合も多いです。
つまり、1SLDKは寝室1つ+サービスルーム+LDK、2LDKは寝室が2つ+LDK、となります。
実際の暮らしでの違いは?どんな人におすすめ?
1SLDKと2LDKの違いは見た目だけでなく、使いやすさや生活スタイルに影響します。
1SLDKは「サービスルーム」があるため、書斎や収納スペースとして活用しやすいです。
例えばリモートワークが増えた今、ちょっとした仕事部屋として別のスペースが欲しい人にはぴったり。
一方、2LDKは寝室が2つあるので、家族や同居人がいる場合におすすめです。
夫婦それぞれの寝室や子ども部屋を確保するなど、プライバシーもしっかり守れます。
とはいえ、2LDKは部屋数が多いため、家賃や光熱費が高くなる傾向があります。
また、1SLDKは広さでは劣ることもありますが、スペースの工夫次第で快適に暮らせます。
1SLDKと2LDKの間取りの特徴を比較した表
ding="5" cellspacing="0">| ポイント | 1SLDK | 2LDK |
|---|
| 寝室の数 | 1室+サービスルーム | 2室 |
| サービスルームの有無 | あり(窓なしや狭いことも) | なし |
| 使い方 | 書斎や収納など多目的に活用可能 | 寝室や子ども部屋として適している |
| 家賃・維持費 | やや安い傾向 | やや高い傾向 |
| プライバシー | 少ないが工夫でカバー可能 | しっかり確保できる |
まとめ~選び方のポイントは?
1SLDKと2LDKはどちらも魅力的な間取りですが、
1SLDKは独身の人や二人暮らしで仕事部屋や収納が欲しい人に向いていると言えます。
逆に2LDKは家族や同居人が多い場合、または部屋数を重視したい人にぴったりです。
どちらが良いかは、人数や生活スタイル、予算によって変わってきます。
内見時には実際の広さやサービスルームの使用感なども確かめて、快適なお部屋を探しましょう!
ピックアップ解説「サービスルーム(S)」という言葉、ちょっと変わっていますよね。実は法律上の扱いでは、窓がなかったり換気が難しいと“居室”とは認められないことが多いんです。つまり、正式には寝室とは言えないけど、家の中でちょっとしたスペースが欲しい時に便利なんです。書斎にしたり、パソコンルームにしたり、収納を増やしたりと使い方は自由。だからこそ、1SLDKはちょっと工夫次第で生活スタイルに合わせやすい間取りなんですよね。
地理の人気記事

84viws

84viws

81viws

55viws

48viws

48viws

41viws

37viws

37viws

34viws
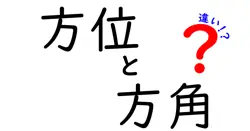
32viws
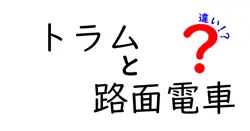
31viws

29viws
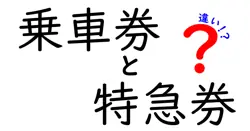
29viws

29viws

28viws

28viws
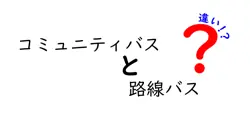
26viws
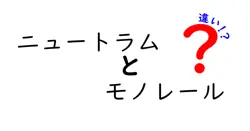
25viws
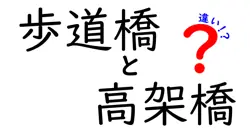
25viws
新着記事
地理の関連記事
延床面積と法床面積とは?基本の違いを知ろう
建物の広さを表す言葉には、よく「延床面積」と「法床面積」というものがあります。
しかし、この2つは似ているようで実は意味や計算方法が違います。見た目のサイズだけでなく、法的な意味合いや計算方法に違いがあるので、間違えないように理解しておくことが大切です。
まず、延床面積とは、建物の各階の床面積をすべて合計した面積のことです。たとえば、2階建ての家なら1階と2階の床面積を足したものです。
これに対して、法床面積は法律で定められた特殊な面積のことで、建築基準法などに基づいて計算されます。延床面積と似ていますが、法的な用途で厳密に使われます。
このように、延床面積は実際の住める床の合計面積を表し、法床面積は法のルールにそって計算される広さだと考えましょう。
延床面積と法床面積の計算方法・使い方の違い
延床面積の計算方法はシンプルです。建物の各階の床面積を全部足します。
例えば、1階が60平方メートル、2階が40平方メートルなら、延床面積は100平方メートルとなります。
一方、法床面積は建築基準法で特に定められた方法で計算し、天井の高さや壁の厚さ、バルコニーや外廊下の取り扱いなど細かいルールがあります。そのため、延床面積より減る場合もあれば、場合によっては増えることもあります。
使い方も違いがあり、延床面積は実際の住空間の目安として住宅購入者や設計者がよく使うのに対し、法床面積は建築確認申請や税金の計算など、法律で必要な場面で使用します。
つまり、延床面積は目安の広さ、法床面積は法令に則った正確な広さと覚えておくと良いでしょう。
延床面積と法床面積を比べやすくまとめた表
ding="5" cellspacing="0">| 項目 | 延床面積 | 法床面積 |
|---|
| 定義 | 建物のすべての階の床面積を合計した面積 | 建築基準法などの法律に基づいて計算された床面積 |
| 計算方法 | 単純に各階の床面積を合計 | 壁の厚さ、天井高、バルコニーの扱いなど法律上の基準に従う |
| 使い方 | 住宅の広さの目安や設計の参考に | 建築確認申請や税金計算に使用 |
| 特徴 | 実際の住空間の広さに近い | 法律的に正確な広さを表す |
まとめ:違いを理解して正しく使い分けよう
建物の広さを示す「延床面積」と「法床面積」は、一見似ていますが、計算方法も用途も違う重要な指標です。
延床面積は、建物の実際に使える床の合計で、住宅の広さや設計の目安に使います。
一方、法床面積は法律に従って計算され、建築確認や税金の計算など、法的な判断に使われます。
これらの違いを知っておけば、不動産購入や建築計画のときに安心して知識を活かせます。ぜひ、建物の広さを考えるときはどちらの面積を参考にしているのかを確認してください。
ピックアップ解説「法床面積」という言葉はあまり普段の生活で聞きなれないですよね。でも建築や不動産の世界ではすごく重要なんです。たとえば、バルコニーが建物の面積に入るかどうかは法律で決まっていて、それが法床面積の計算に影響します。だから、同じ家でも延床面積と法床面積で数字が違うことがあるんです。意外と知られていないけど、建物の広さを決める奥深いルールがあるんですね。
ビジネスの人気記事

200viws

155viws

149viws

144viws

144viws

143viws

139viws

137viws

123viws

123viws

112viws

111viws

107viws

106viws

99viws

97viws

95viws
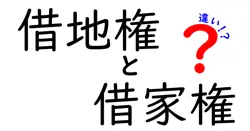
90viws

89viws
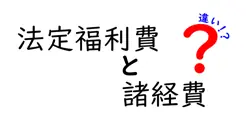
87viws
新着記事
ビジネスの関連記事
オープンキッチンとシステムキッチンの基本的な違いについて解説
私たちの生活に欠かせないキッチンですが、最近よく耳にする「オープンキッチン」と「システムキッチン」という言葉。みなさんは、この二つのキッチンの違いをご存知でしょうか?
オープンキッチンは、リビングやダイニングと仕切りがなく、キッチンが開放されているスタイルを指します。家族や友人とコミュニケーションを取りながら料理ができるため、人気が高まっています。
一方、システムキッチンとは、あらかじめ決まったパーツ(調理台、収納、シンク、コンロなど)がセットになっており、効率的に使えるよう設計されたキッチンのことです。機能性やデザイン性に優れ、使いやすさが魅力です。
ここで注意したいのは、オープンキッチンは「空間のスタイル」であり、システムキッチンは「キッチンのタイプ」という点です。つまり、システムキッチンがオープンキッチンの一部として使われることもあります。
このように、両者は分類の視点が異なるため混同しやすいですが、それぞれの特徴を理解することが、理想のキッチン選びに役立ちます。
オープンキッチンのメリットとデメリット
まずはオープンキッチンのメリットから見てみましょう。
- 家族とのコミュニケーションが取りやすい:壁がなくリビングと繋がっているため、会話や様子を見ながら料理ができます。
- 空間が広く見える:仕切りがないため、部屋全体が広く感じられ、開放感があります。
- おしゃれなデザインが多い:モダンでスタイリッシュな印象を与えるキッチンが選べます。
しかし、デメリットもあります。
- 調理中の臭いや煙がリビングに広がりやすい:換気設備にも注意が必要です。
- キッチンの乱雑さが丸見えになることも:片付けや掃除がこまめに必要です。
- 収納スペースが制限される場合が多い:壁が少ないため、収納は工夫が必要です。
これらを踏まえ、生活スタイルや家族構成に合わせた選択が重要です。
ピックアップ解説オープンキッチンにすると、料理をしている人が家族や友人と話しやすくなるのが最大の魅力です。でも、毎日料理のにおいや煙がリビングに流れてしまうことも。だから換気扇の性能がとっても大事なんですよ。面白いのは、最近の換気扇はおしゃれなデザインだけでなく、音が静かで効率も良くなっているんです。リビングの快適さを保ちながら、キッチンの開放感も得られるなんて、一石二鳥ですよね。
料理の人気記事

14viws
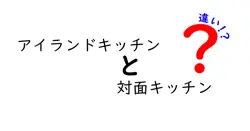
11viws

10viws
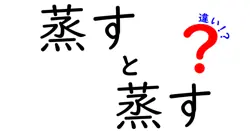
9viws

8viws
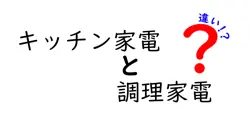
8viws

8viws
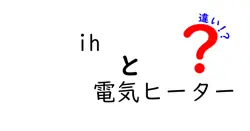
8viws
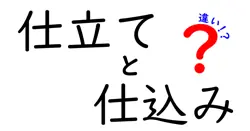
8viws
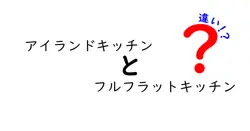
7viws
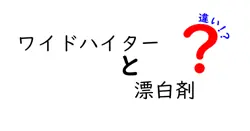
7viws
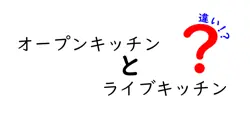
7viws
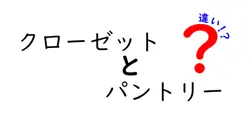
7viws

6viws
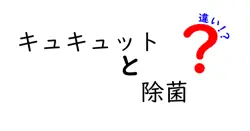
6viws
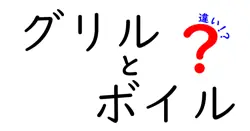
6viws
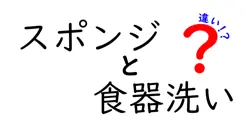
6viws
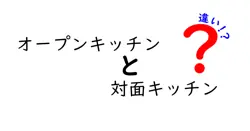
6viws
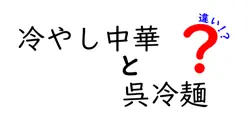
6viws
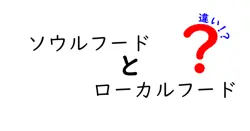
6viws
新着記事
料理の関連記事
断面図と矩計図って何?基礎から理解しよう
建築の図面にはいろいろな種類がありますが、その中でも「断面図」と「矩計図(かなばかりず)」はよく混同されやすいものです。
断面図とは、建物を水平面で切り取った断面の状態を示す図面で、建物全体の構造や内部の様子がわかるものです。例えば、壁の厚さや窓の配置、梁(はり)や柱の位置まで確認できます。
一方、矩計図は建物の一部分、特に壁や床、屋根などの構成を垂直方向に細かく拡大して描いた詳細図面です。
つまり、断面図は建物全体の大まかな構造を示す全体図であり、矩計図はその断面の中でも特に重要な部分をとても詳しく表したものと言えるでしょう。
断面図と矩計図の具体的な違いと役割
両者の違いをより詳しく見ていきましょう。
1. 図面の範囲と目的
断面図は建物全体の断面をどこかの箇所を切り取って示すため、全体のバランスや構造の配置を理解するために使います。
矩計図は断面図の一部分を拡大し、構造や材料の詳細を記述する図面で、施工する職人が正確に作業できるように使われます。
2. 表現される情報の深さ
断面図は壁の大まかな厚みや床の位置などが分かる程度ですが、矩計図は断熱材の厚みや仕上げ材の種類、基礎の構造まで細かく述べられています。
3. 用途
断面図は設計の段階で建物全体のイメージを伝えるために使われ、クライアントとの共有も行われます。矩計図は施工者向けの技術的な図面で、建築現場での正確な作業に役立ちます。
断面図と矩計図の違いをわかりやすく比較!表で整理
| ポイント | 断面図 | 矩計図 |
|---|
| 範囲 | 建物全体の断面 | 断面の一部分を詳細に拡大 |
| 詳細度 | 大まかな構造 | 材料や寸法の細かい指定 |
| 用途 | 設計イメージの説明 | 施工のための具体的指示 |
| 対象者 | 設計者やクライアント | 施工者・職人 |
| 作成タイミング | 設計初期~中期 | 設計後期~施工時 |
このように、断面図と矩計図は目的や使う場面、表現の詳細さに大きな違いがあるのです。
両方の図面を見ることで、建物の全体像を把握しつつ、細かい作業指示も理解できるため、建築に関わる人は両方の意味を知っておく必要があります。
まとめ:断面図と矩計図を使いこなして建築を理解しよう
断面図は建物の構造の全体像を示す大まかな断面図で、設計段階からクライアントへ説明する役割をもちます。
矩計図はその断面の一部を拡大し、材料の厚みや構造の細かい部分まで詳細に表現した施工向けの図面です。
表現の内容や使う目的が異なるため、この二つの図面はどちらも建築設計・施工の過程で欠かせない存在です。
これらの違いを理解することで、建築の設計図面を読む力がぐっと上がり、専門的な話もより楽しくなります。
ぜひ今日の記事を参考に、断面図と矩計図の違いを押さえて、自分の建築知識を深めてみてください。
ピックアップ解説今回の記事の中で特に面白いのは【矩計図】という言葉です。矩計図は建物の断面図の一部をすごく細かく描いたもので、例えば壁の中に入っている断熱材の厚みや、どんな素材が重なっているのかまで詳しく見えます。これは施工するときにとても役立ちますが、実は一般の人にはあまり知られていません。建築のプロだけでなく、家の設計に興味がある人が知っておくと、自分の家の図面を見るときにすごく理解が深まりますよ!
科学の人気記事

105viws

69viws

68viws
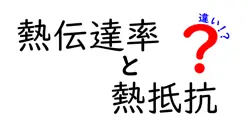
58viws

49viws
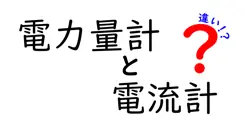
48viws
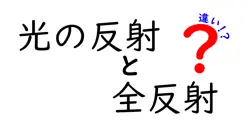
47viws

46viws
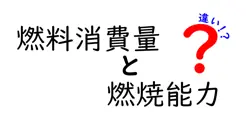
40viws
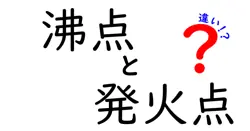
39viws
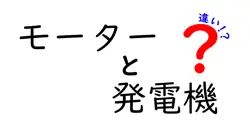
37viws

37viws
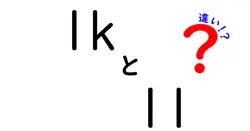
35viws
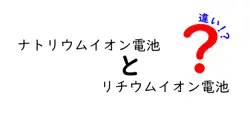
35viws
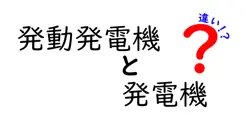
34viws
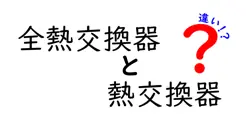
33viws
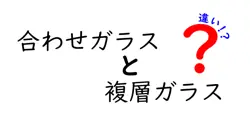
32viws

32viws

31viws
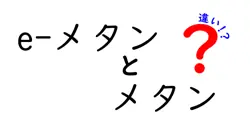
30viws
新着記事
科学の関連記事
レコーディングスタジオの天井高がなぜ重要なのか?
レコーディングスタジオでの録音時、天井の高さは音質に大きな影響を与えます。天井が高いと音の響き方が変わり、逆に低いと音がこもりやすくなるのです。特にボーカルや楽器の録音の際には、その違いがはっきりと感じられます。
この違いを知らずに録音を行うと、思い描いていた音とは違った仕上がりになることも多いです。音の反射や拡散が音の広がりやクリアさを左右するため、天井の高さは録音環境を整える上でとても重要なのです。
天井高の違いが音響に与える影響
スタジオの天井が高い場合、音が広い空間を行き来するため、自然な響きや残響音が豊かになります。これは、クラシック音楽やアコースティック楽器の録音で好まれています。
一方で天井が低いスタジオでは、音波が短時間で壁や天井に反射しやすく、音がどちらかというとこもった印象を与える傾向があります。ロックやポップスなど、はっきりした音を求める音楽には適していることもあります。
レコーディングスタジオの天井高比較表
以下の表は、一般的なレコーディングスタジオの天井の高さごとの音響特徴のまとめです。
able border="1">| 天井高 | 音響の特徴 | 録音に適した用途 |
|---|
| 3m以下(低い) | 反射音が強く、音がこもりやすい | ロック、ポップス、ボーカル録音 |
| 3~5m(中間) | 響きと明瞭さのバランスが良い | 多用途、バランスのとれた録音 |
| 5m以上(高い) | 豊かな残響と自然な響きが特徴 | クラシック、アコースティック楽器の録音 |
理想的な天井高を選ぶためのポイント
レコーディングスタジオの天井高は、録音する音楽のジャンルや演奏スタイルによって変えるべきです。例えば、ジャズやクラシックなど繊細で響きを大切にする音楽では、高い天井が向いています。反対に、はっきりとした音を求めるロックやポップスでは、低めの天井でも問題ありません。
また、天井だけでなく、壁や床の材料、スタジオ内部の音響処理も大切です。天井高だけで判断せず、総合的な音響環境をチェックすることが良い音を録るコツとなります。
まとめ
レコーディングスタジオの天井高の違いは、録音する音楽のジャンルや求める音響効果によって最適な高さが変わります。天井が高いと自然な響きが出やすく、低いと音がこもりやすくなる特徴があります。
スタジオ選びや自宅録音の際は天井高を意識して、理想の音質に近づけましょう。
ピックアップ解説レコーディングスタジオで使われる「天井高」という言葉、一見するとただの高さだけの話に思えますが、実は音の響きに大きな秘密があります。例えば、高い天井があると音が空間をゆっくりと伝わり、まるでコンサートホールのような自然な響きを作り出します。一方で低い天井は音がすぐ反射して全体がこもった印象に。面白いのは、この違いを作り出すのは単なる物理的な高さだけでなく、壁材や吸音材と組み合わせることで実験的に変化がつくこと。つまり、天井高はスタジオ設計の重要なパズルの一部なのです。こんな視点でスタジオを見てみると、録音の面白さがもっと身近に感じられますね。
エンタメの人気記事

21viws

19viws

14viws
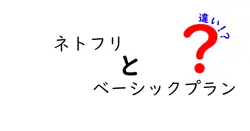
13viws
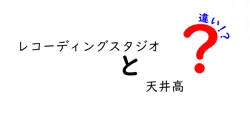
12viws
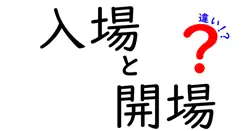
11viws
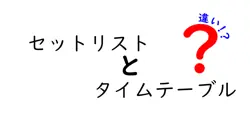
11viws

11viws

11viws

10viws

9viws

8viws

8viws
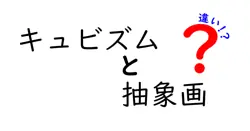
7viws

7viws
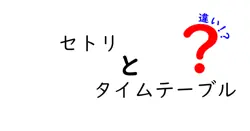
7viws

6viws
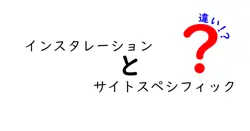
6viws

6viws
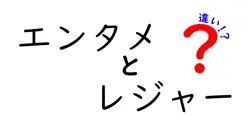
6viws
新着記事
エンタメの関連記事