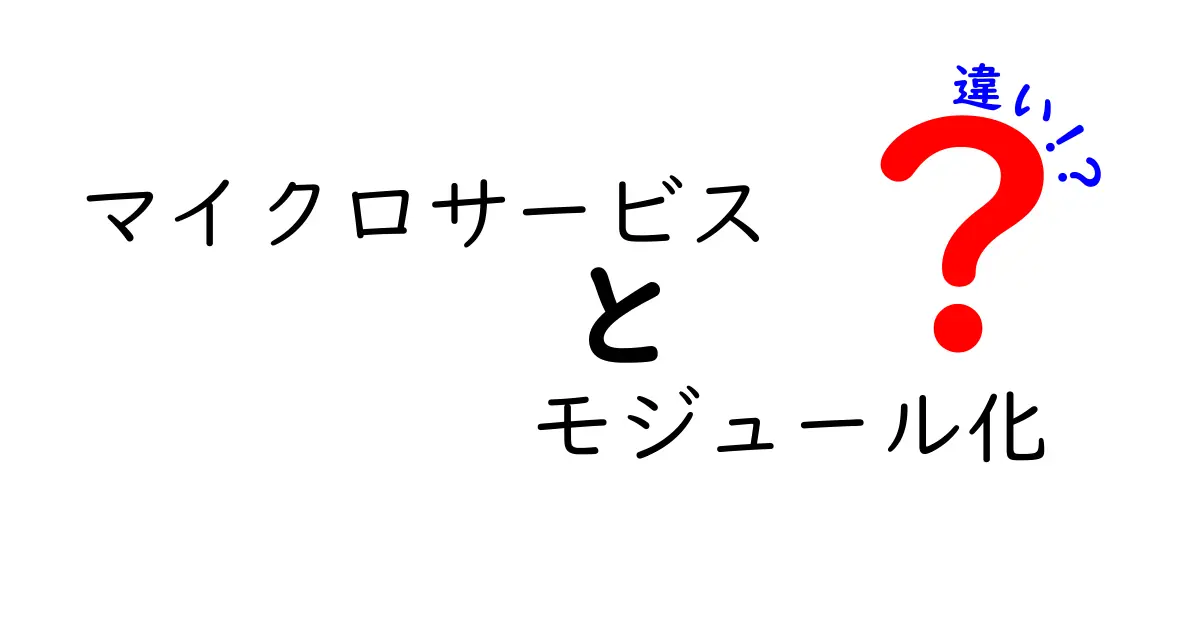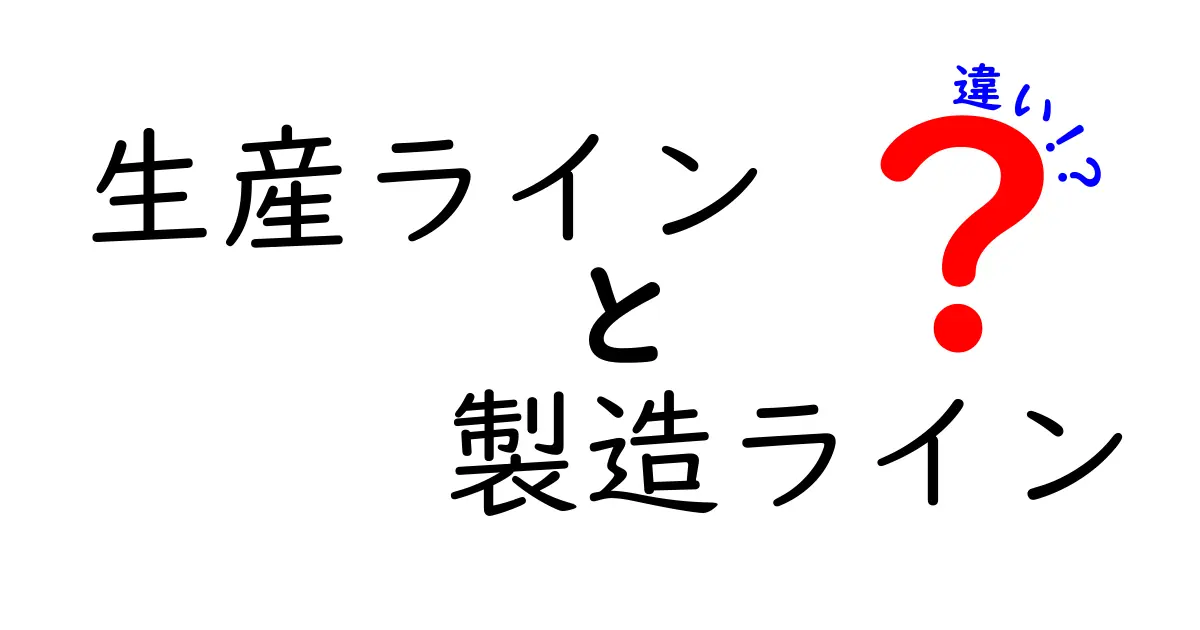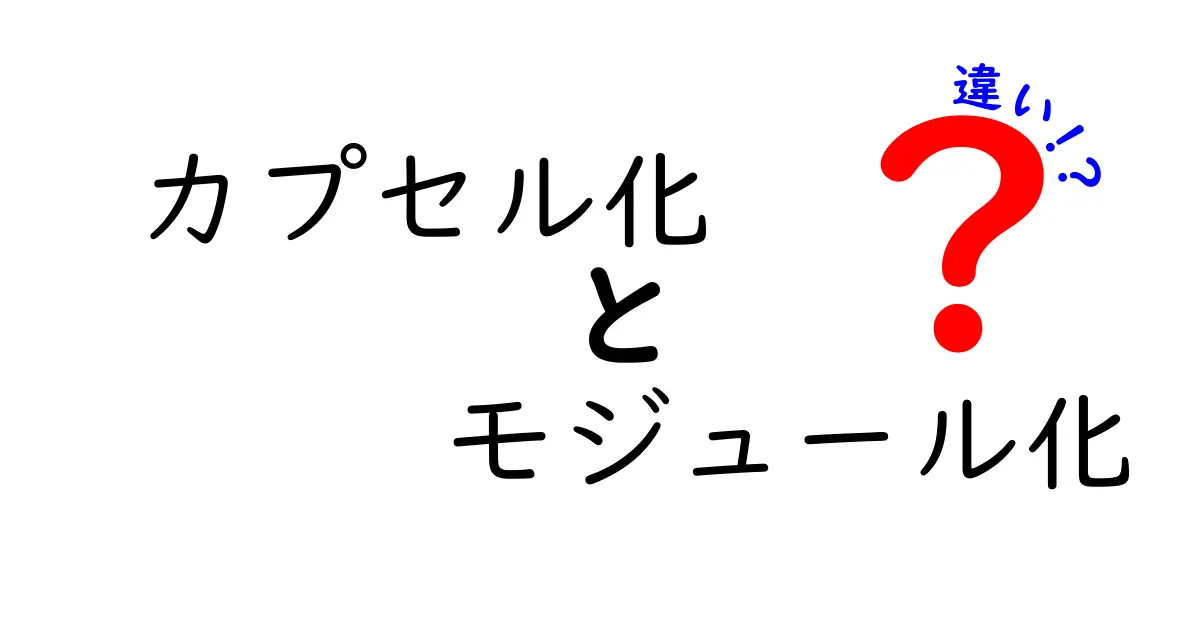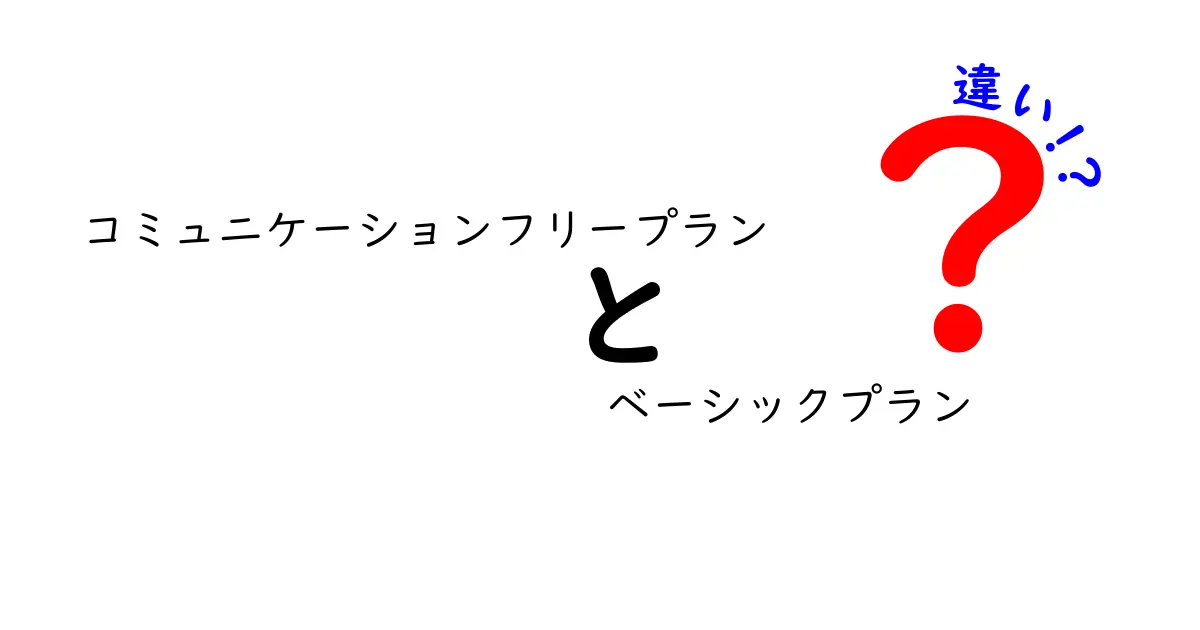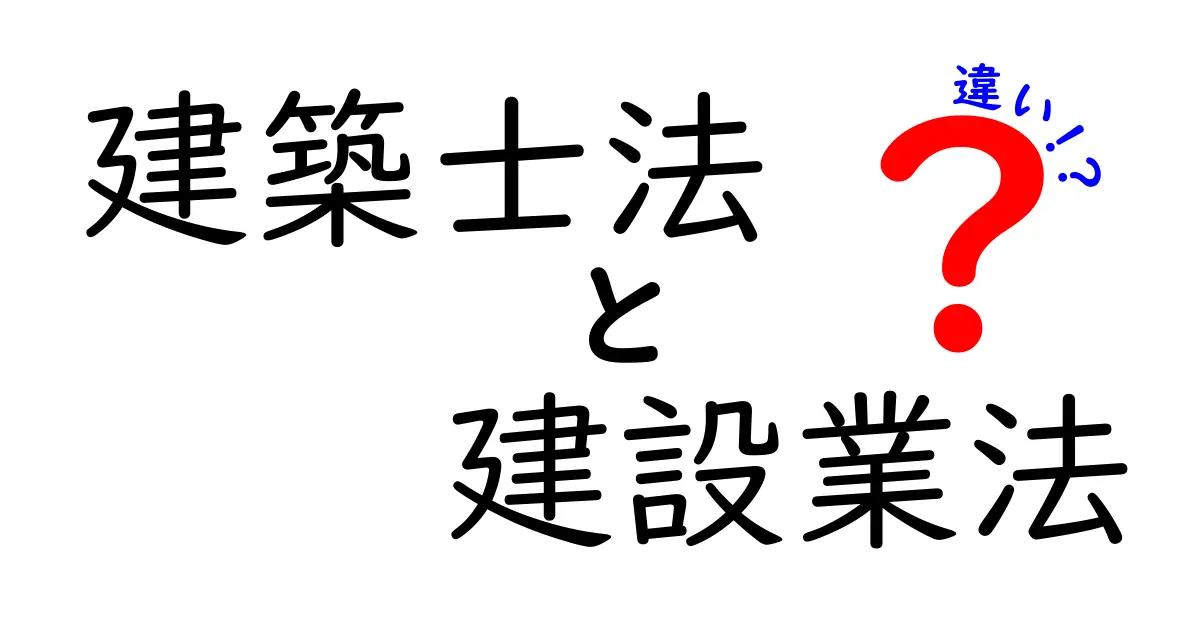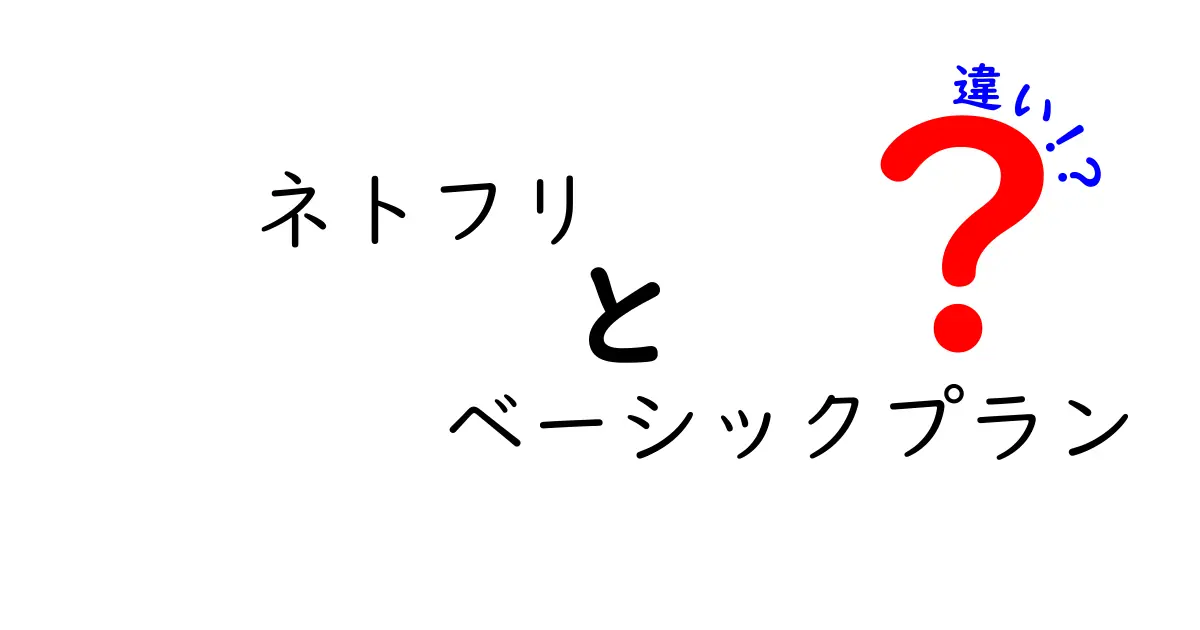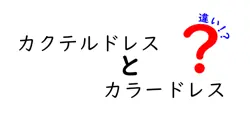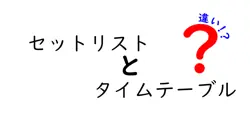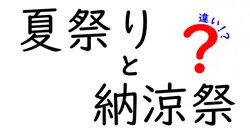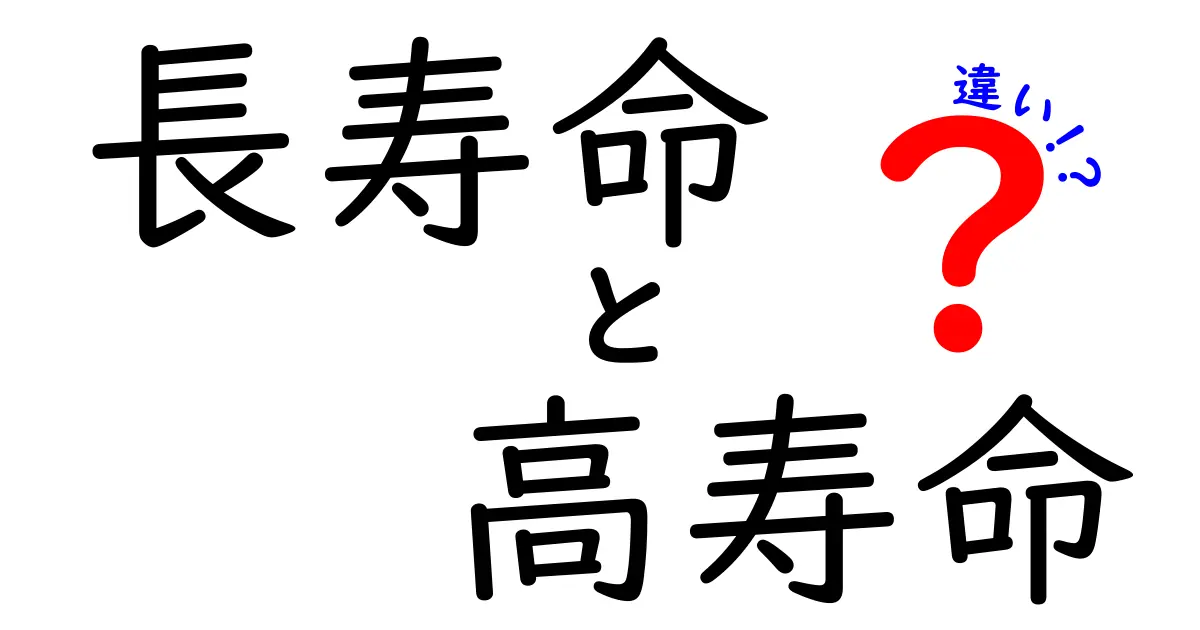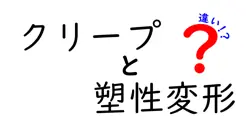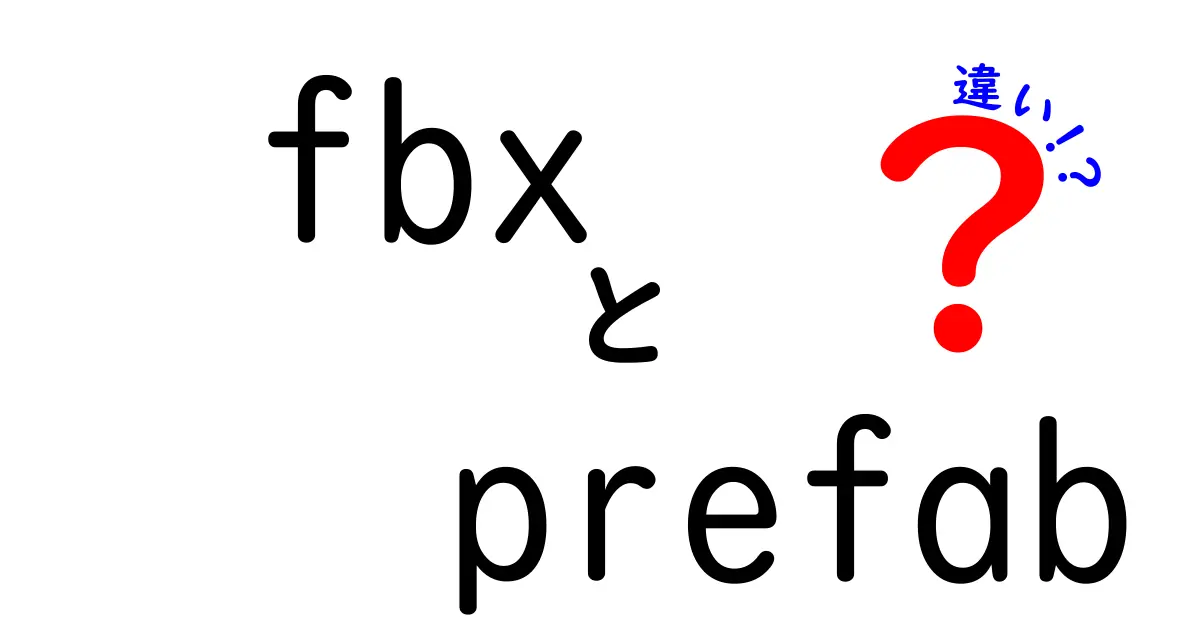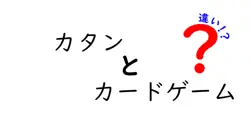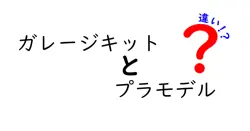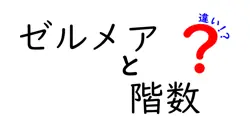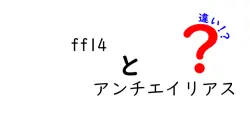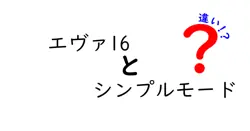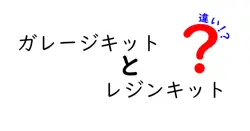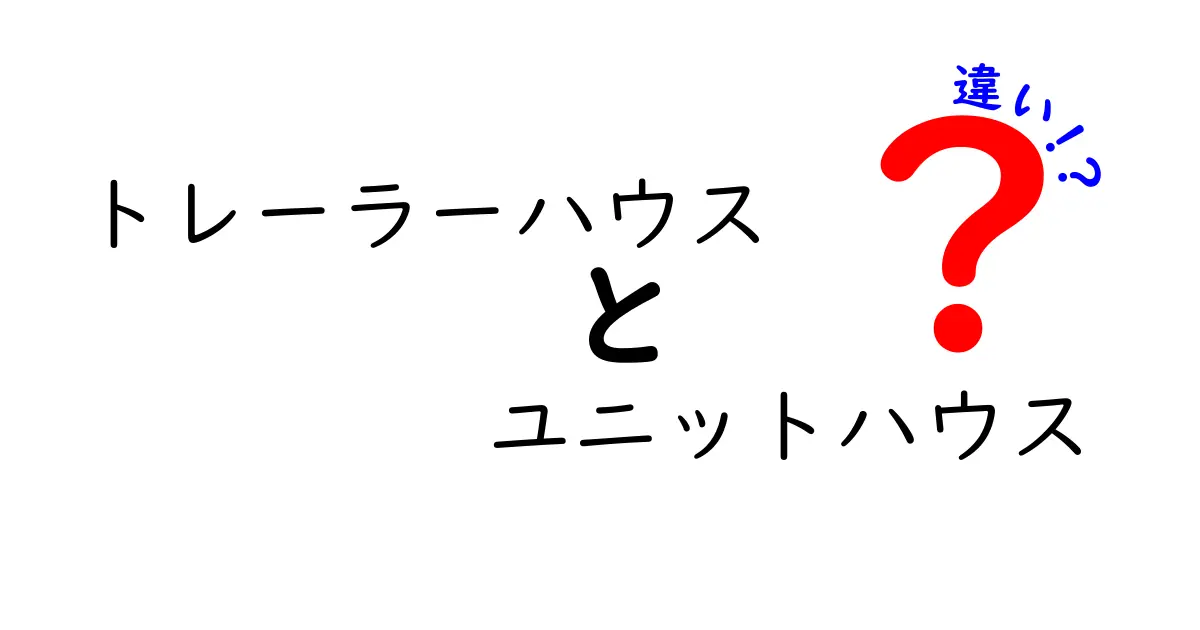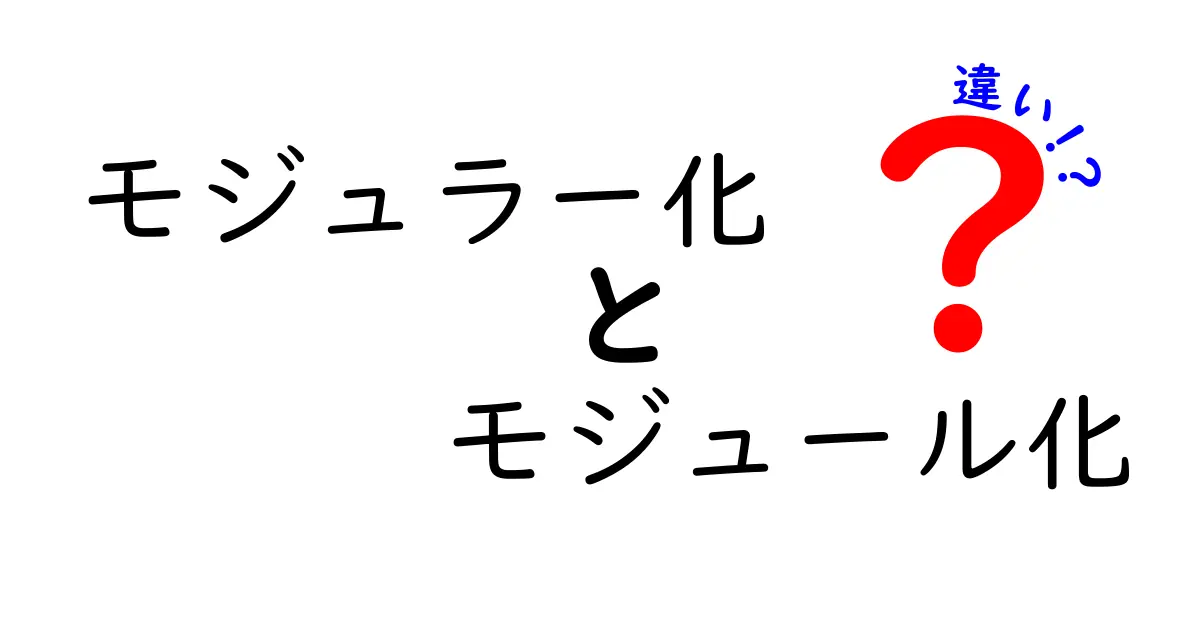

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
モジュラー化とモジュール化って何?基本の違いを理解しよう
まず、モジュラー化とモジュール化という言葉は似ているようで、少し違った意味を持っています。両方とも「大きなものを小さな単位に分ける」という意味合いがありますが、使われる場面やニュアンスが違います。
モジュラー化は、一般に製品やソフトウェア、システムなどをいくつかの「モジュール(部品)」に分割して、容易に組み立てたり改良したりできる設計手法を指します。
一方、モジュール化は「モジュールにすること」つまり、具体的に何かを一つのモジュールとして成立させるプロセスや状態を表します。
簡単に言うと、モジュラー化は大きな全体をパーツ化する考え方や仕組み全体のことで、モジュール化は個々のパーツ作りや設定のことと言えます。
このような区別は日本語の使い方や専門用語の慣例によっても変わることがあるため、両者をあまり厳密に分けず、状況に応じて理解しておくことが大切です。
モジュラー化の実例とメリット
モジュラー化の代表例としては、家電製品や自動車の設計があります。たとえば、パソコンはCPU、メモリ、ハードディスク、グラフィックボードなどさまざまなモジュールが組み合わさってできています。
これをモジュラー化することで、壊れた部分だけを交換したり、性能を上げたい部分だけを強化できるため、メンテナンスやアップデートが楽になります。
このように、モジュラー化は製品の柔軟性を高め、効率よく改良や修理ができることが最大のメリットです。
また、ソフトウェア開発においても、機能をいくつかのモジュールに分けて作ることでチームでの作業が分担しやすく、バグの発見や修正も早くなります。
このようにモジュラー化は、複雑なものを扱いやすくするための仕組みだと覚えておくと良いでしょう。
モジュール化の具体的な意味と使い方
モジュール化は、特にソフトウェアでよく使われる言葉で、ある機能や処理の単位を一つの「モジュール」としてまとめることを指します。
つまり「モジュールとして独立させること」がモジュール化。これにより、使い回しやテストが簡単になる利点があります。
例えば、ゲームのプログラムで「キャラクターの動きを制御するモジュール」「音声を再生するモジュール」「スコアを管理するモジュール」が別々に作られているイメージです。
こうしたモジュールは、必要に応じて単独で修正や交換が可能なので、保守性や拡張性が高まります。
また、モジュール化は「プログラムのコードを理解しやすく、再利用しやすくなる」という観点でも重要です。
このように、モジュール化は「モジュールを作る具体的な行為」であり、設計・開発の中で実際に分割・整理する作業を指します。
モジュラー化とモジュール化の違いを表でまとめてみよう
| ポイント | モジュラー化 | モジュール化 |
|---|---|---|
| 意味 | システムや製品全体を複数のモジュールに分割すること (仕組み・考え方) | 個々の機能や部品をモジュールとしてまとめること (具体的な操作・状態) |
| 使われる場面 | 設計や企画段階、製品開発全体 | プログラム開発や部品の作成段階 |
| 例 | 家電の部品分割、ソフトの大枠設計 | プログラムの関数をまとめる作業など |
| 効果 | 柔軟性や拡張性の向上、管理のしやすさ | 再利用性や保守性の向上 |
| 比較ポイント | マイクロサービス | モジュール化 |
| 構造 | 独立したサービス群で構成 | 単一のプログラム内の部品のような形 |
| 実行環境 | 複数のサーバーやコンテナで別々に動作 | 同じ環境内で一緒に動作 |
| 変更のしやすさ | 独立したサービスだけ変更可能で影響範囲が小さい | 変更は分割されているが同一システムへの影響あり |
| 開発体制 | チームごとにサービス単位で担当可能 | 大きなチームでまとまって開発 |
これらの違いを理解することで、どの方法が自分のプロジェクトに合うか見極めやすくなります。
なぜマイクロサービスとモジュール化を使い分けるのか?選び方と活用例
それでは、どんな時にマイクロサービスを選び、どんな時にモジュール化を選べばよいのでしょうか?
マイクロサービスは、大規模で複雑なサービスや、頻繁に新機能を追加したり更新したりする必要がある時に向いています。複数のチームが独立して作業できるためスピードアップが可能です。
一方、モジュール化は、中小規模のシステムや単一の大きなプログラムを整理するときに便利です。全体の構造をわかりやすくし、保守や改修を簡単にします。
例えば、オンラインショッピングサイトの物流管理はモジュール化で整理し、注文処理や支払い、配送追跡のそれぞれをマイクロサービスに分けて運用するケースもあります。
まとめると、マイクロサービスは「独立性の高い小さなサービス」の集合体、モジュール化は「プログラム内部の整理技術」と理解するとわかりやすいでしょう。
マイクロサービスは独立した小さなサービスとして動くため、例えば一つのサービスがトラブルを起こしても他のサービスに影響をあまり与えません。これは映画で言うと、役者ごとに独立して演じているようなもので、一人が休んでも他の役者は影響なく舞台を続けられるイメージです。こうした性質により、開発チームもバラバラに作業でき、システムの全体的な柔軟性がぐっと高まります。意外とこうした映画的な例えで考えると理解しやすいですよね!
次の記事: モジュール化と標準化の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »