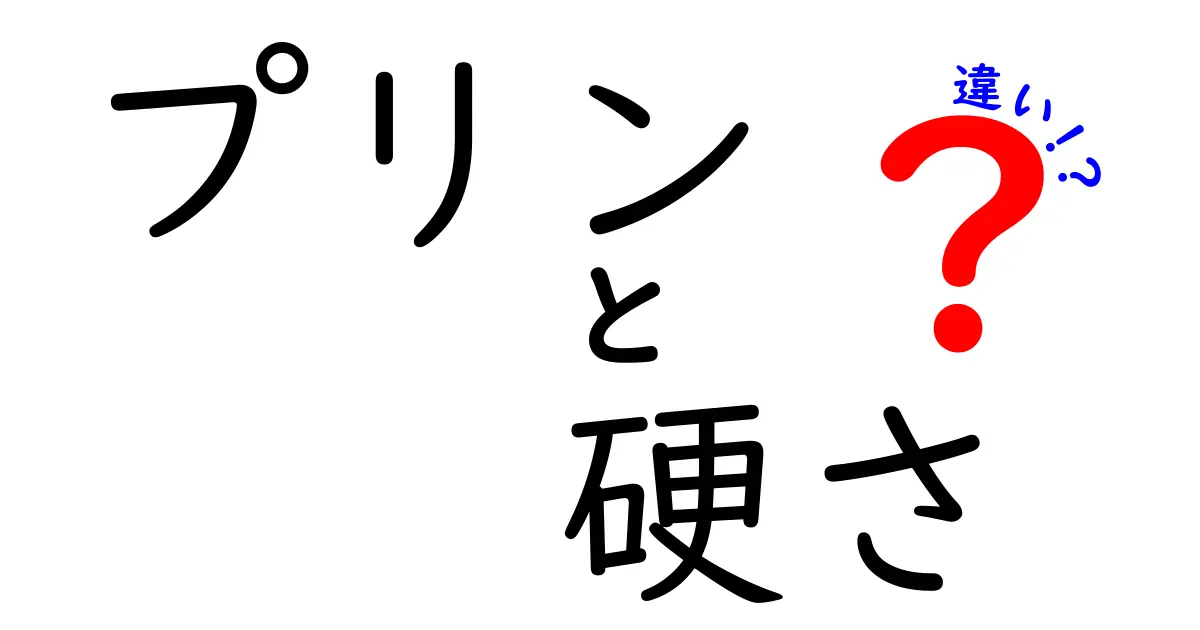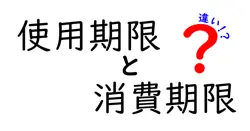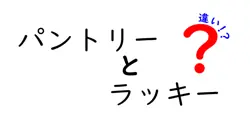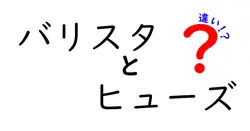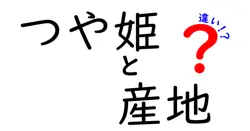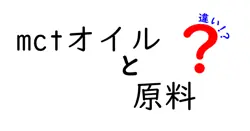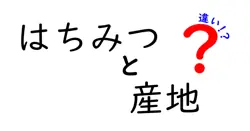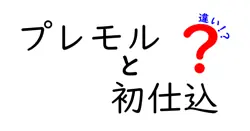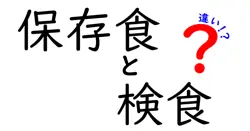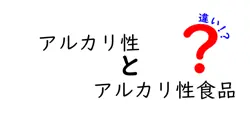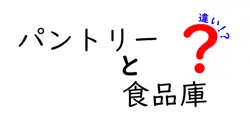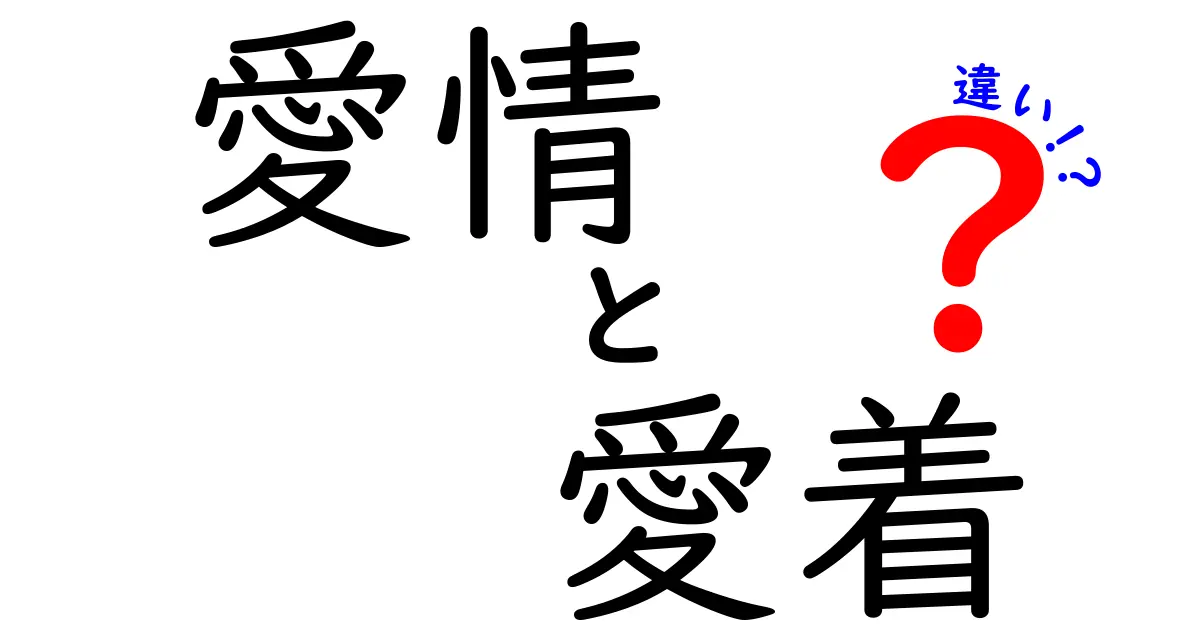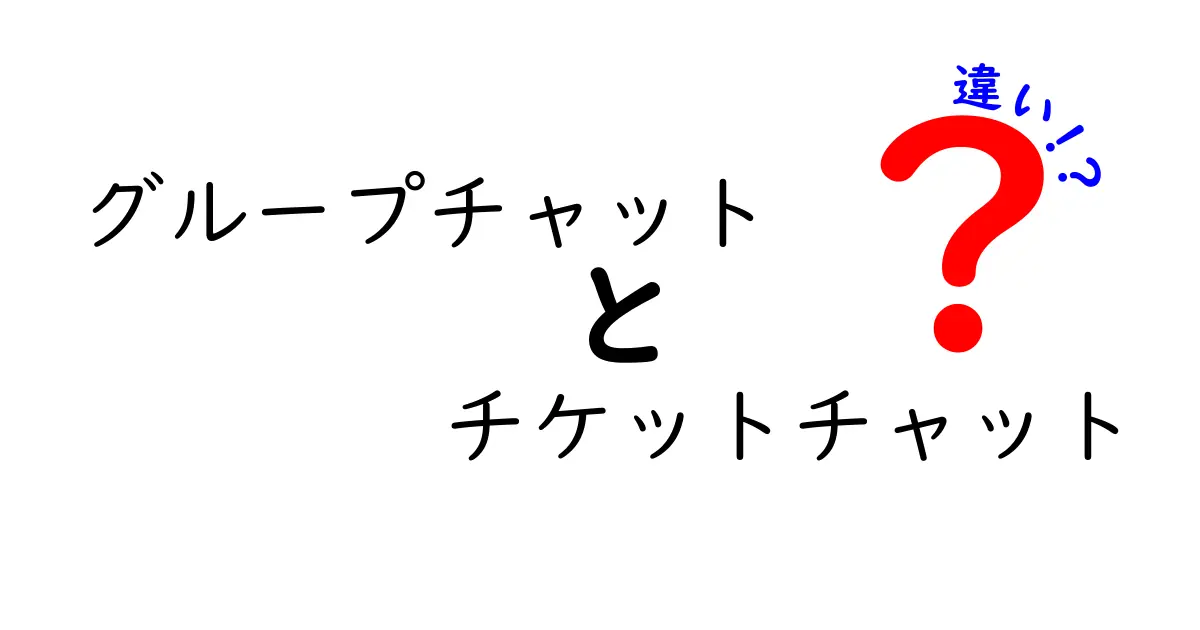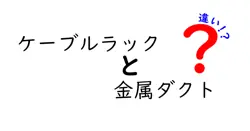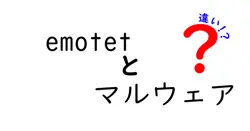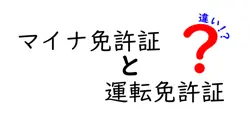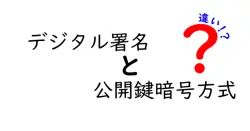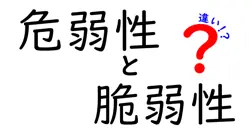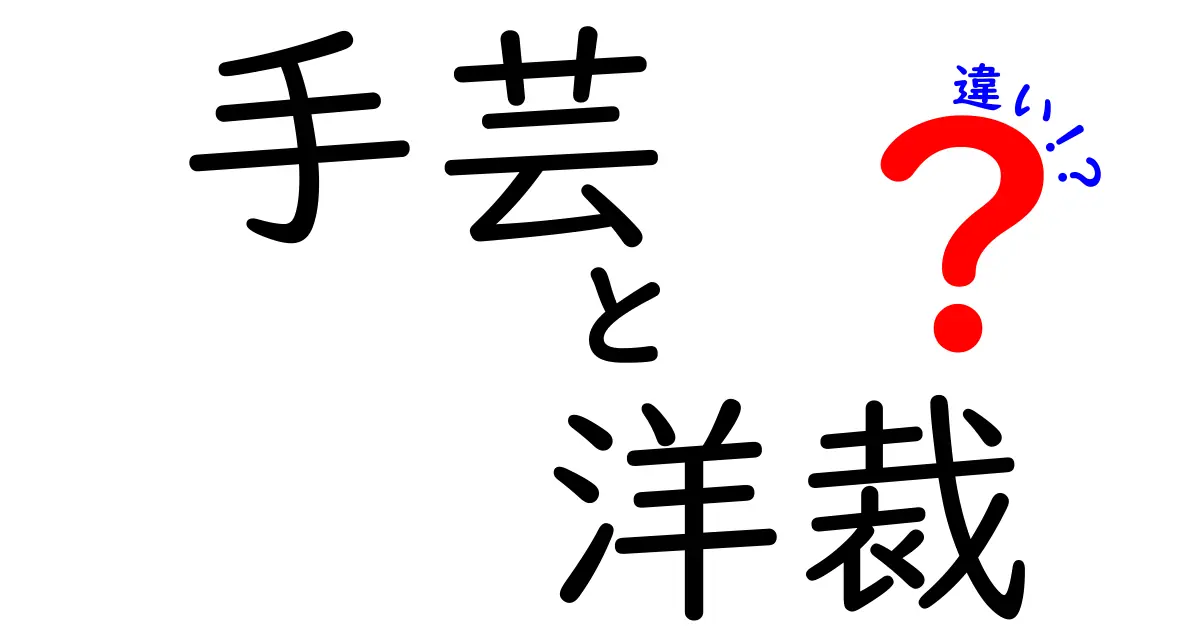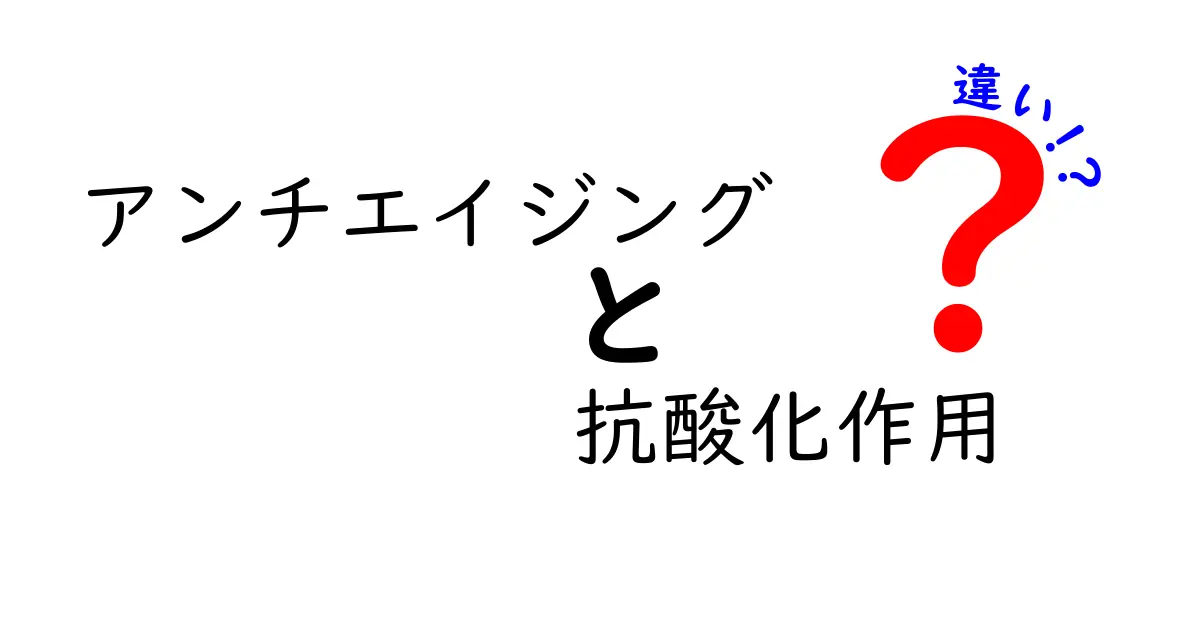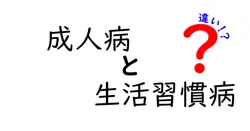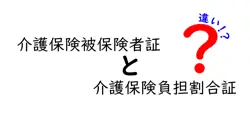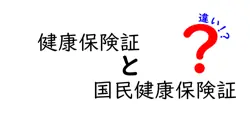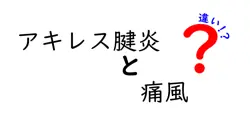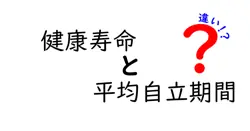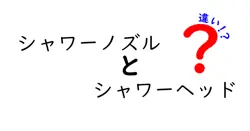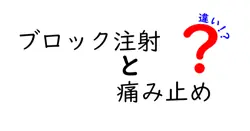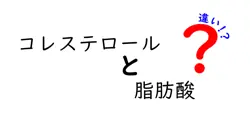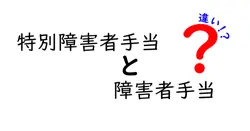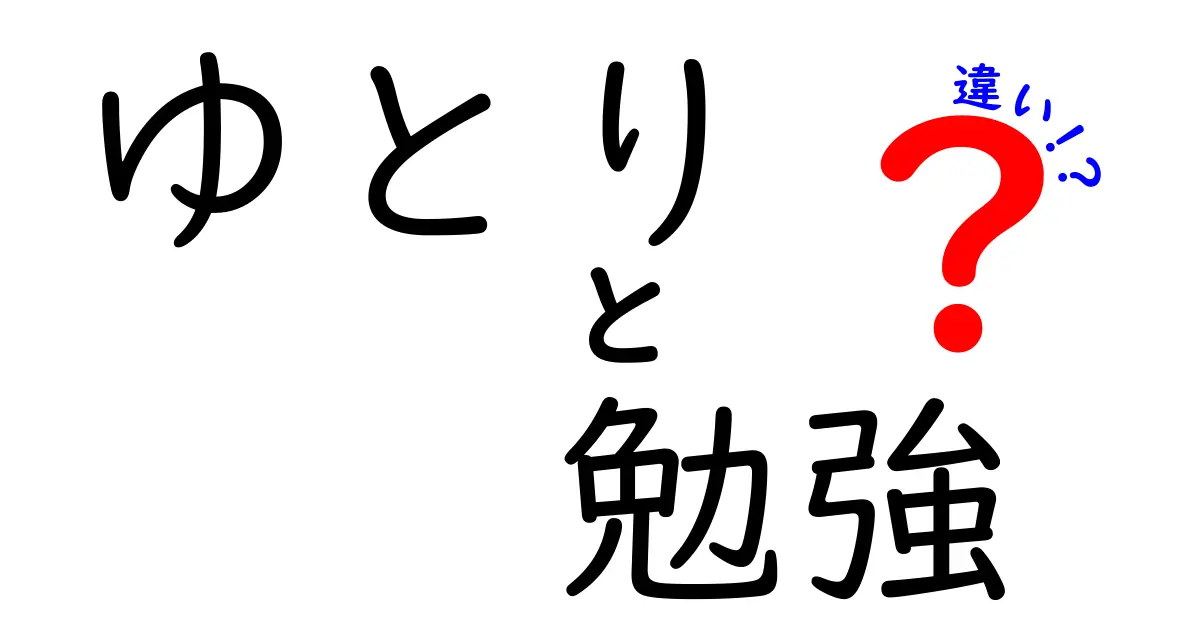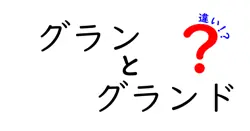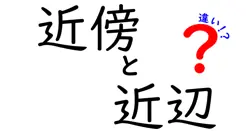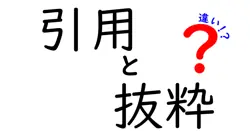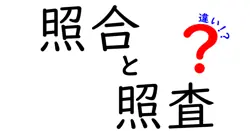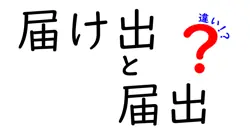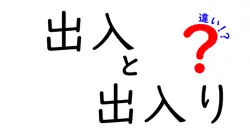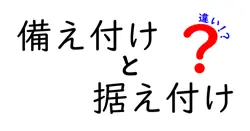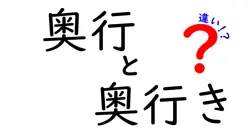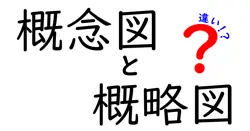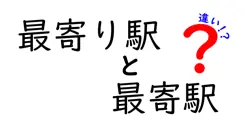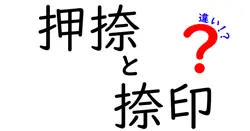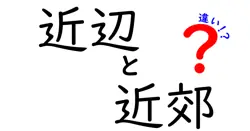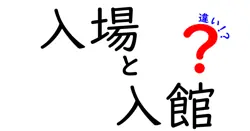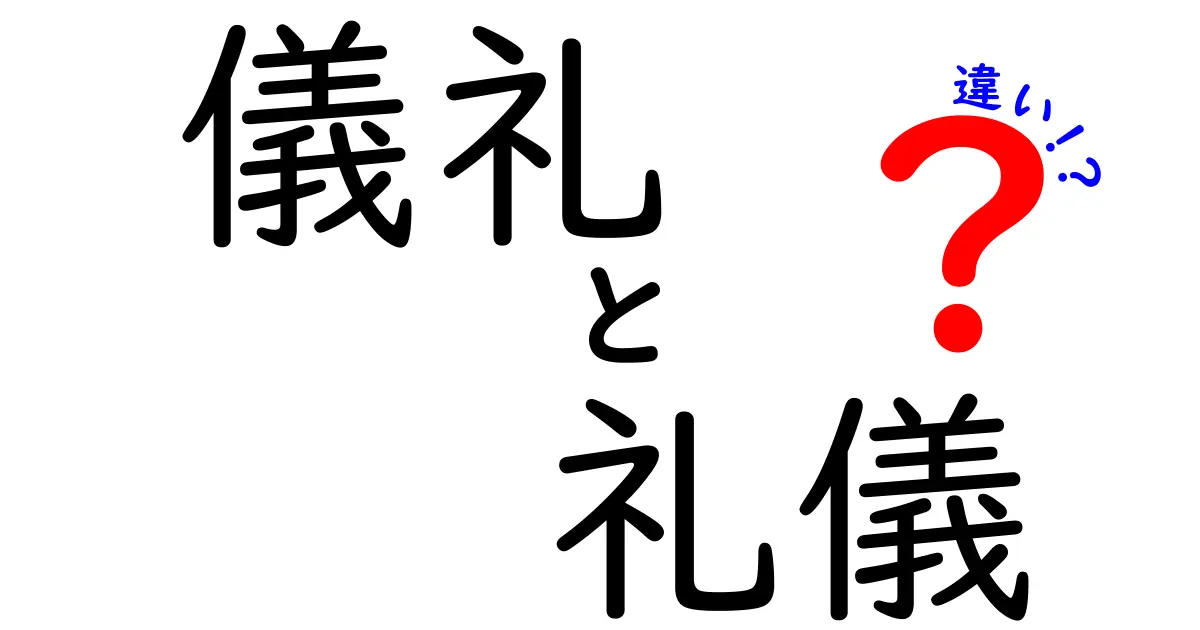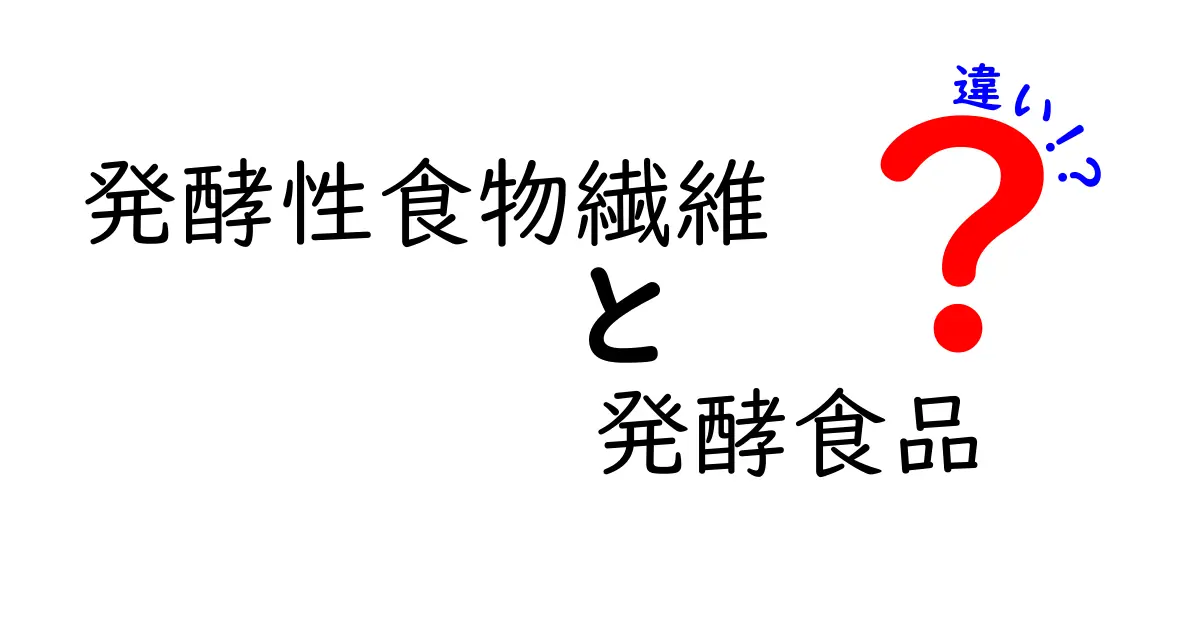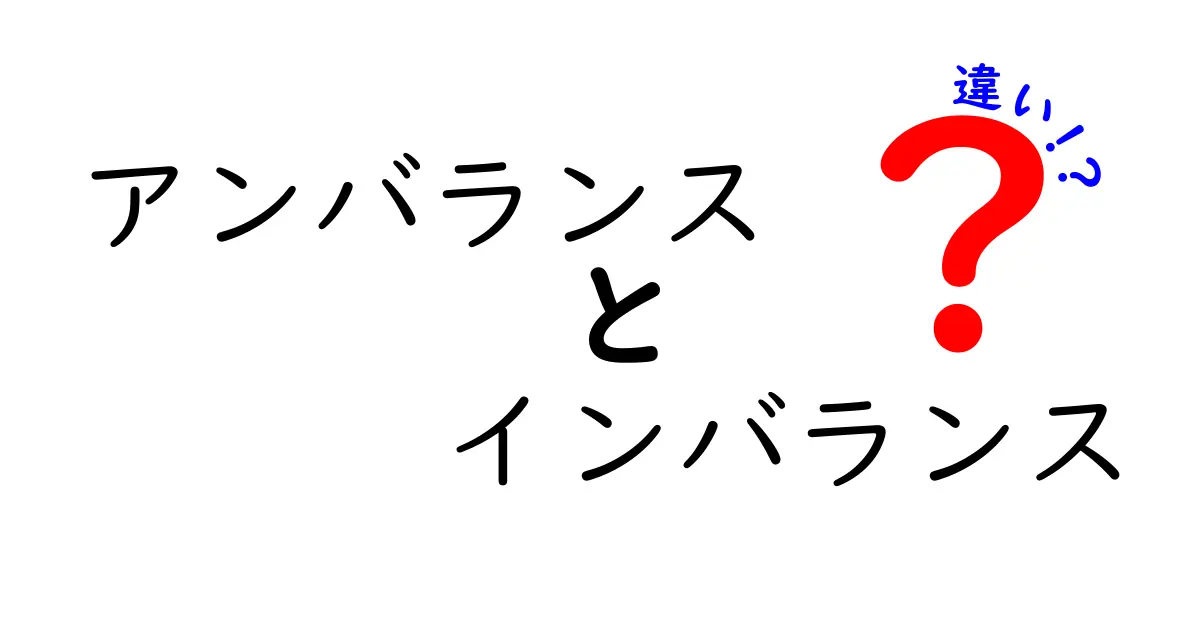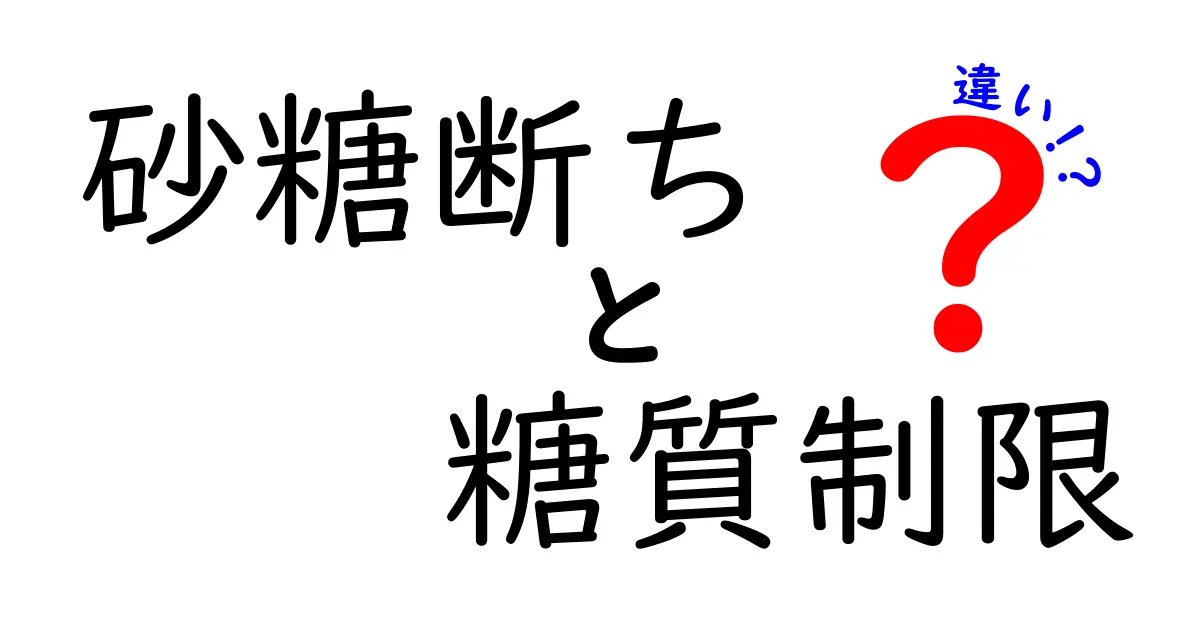「ゆとり世代」と「勉強法」の違いを理解しよう
「ゆとり世代」という言葉を聞いたことがありますか?これは日本で1987年から2004年の間に生まれた人たちのことを指し、学校の勉強内容がゆとり教育という政策で変わった世代を意味しています。
一方で「勉強法」というのは、効果的に学習を進めるための方法のことです。この二つは全く違う対象であることを最初に理解しましょう。ゆとり世代の生徒たちは、ゆとり教育の影響を受けているため、勉強内容や勉強時間が従来と違うケースが多いですが、勉強法は個人が選ぶものなので、ゆとり世代でもそれぞれ違います。
ゆとり世代の特徴と教育の変化
ゆとり世代は日本の教育改革の一環として生まれました。1987年に学習指導要領が変更され、学校の勉強が減り,時間数も削減されました。
具体的には、国語や算数の授業時間が減り、宿題の量も少なくなりました。理由は勉強の負担を減らし、自分で考える力や創造力を伸ばすことを目的にしたからです。
ですが、この「ゆとり教育」は賛否両論あり、勉強量の減少により学力低下を心配する声もありました。このため2011年から学習内容が見直され、「脱ゆとり教育」と呼ばれる方向に変わっていきました。
効率的な勉強法との関係
ゆとり世代の教育環境は変わりましたが、個々の勉強法は人それぞれです。
勉強法には、「反復学習」「アクティブリコール」「メタ認知」など効果的な方法があります。どの世代でも、自分に合った勉強法を見つけることが大切です。
ゆとり教育で時間が少ない分、効率よく勉強する工夫が求められました。また、勉強のストレスを減らすために、興味の持てる内容から学ぶなど工夫している生徒もいます。
つまり「ゆとり=勉強しない」ではなく、「効率よく勉強する必要があった」ということです。
まとめ:ゆとり世代と勉強の違いを表で比較
| 項目 | ゆとり世代 | 勉強法 |
|---|
| 内容 | 学校の教育改革の対象
(1970年代末〜2000年代前半の世代) | 個人が勉強を効率良く進める方法 |
| 特徴 | 学習時間や内容が削減され、創造力重視の教育 | 反復や思考力アップ、集中を工夫する |
| 影響 | 教育方針や学校生活に影響 | 成績や理解度に直接影響 |
| 重要性 | 世代・社会背景を理解するため | 個人の学力向上に重要 |
able>
ゆとり世代と勉強法は全く違うものですが、互いに関連している点もあります。ゆとり教育の中で効率的な勉強法を身につけることが、学習の成績アップに繋がります。
これからの勉強では、自分に合った方法を見つけ、楽しく続けることが大切です。ぜひ、ゆとり世代の背景を理解しながら、自分の勉強法を工夫してみてください。
ピックアップ解説「ゆとり世代」という言葉、よく聞きますよね。これは学校教育の時間や内容が減った世代のこと。実は、ゆとり教育は子どもたちの創造力を伸ばすことを目的としていました。だから単に「勉強量が減った」というだけでなく、『自分で考える力を大切にした新しい教育』として考えると面白いんです。だから、彼らが効率的な勉強法を探すきっかけにもなったんですよ!
言語の人気記事

67viws

59viws

48viws

45viws
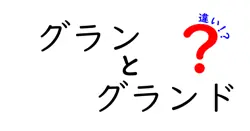
31viws
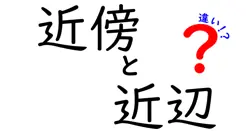
30viws
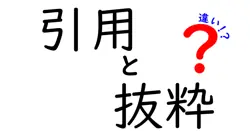
29viws
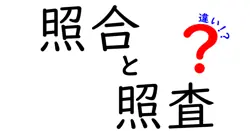
28viws
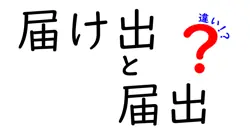
27viws

26viws
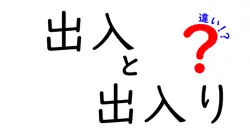
26viws
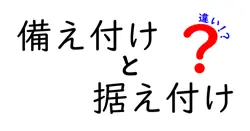
25viws
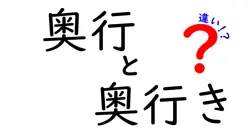
25viws
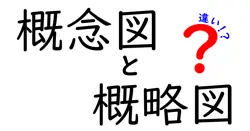
25viws
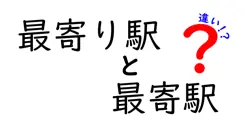
25viws
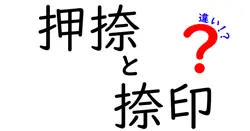
24viws
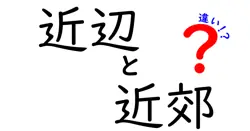
24viws

24viws

23viws
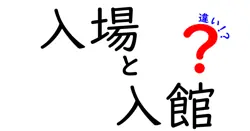
23viws
新着記事
言語の関連記事
「儀礼」とは何か?その意味と使われ方
まずは「儀礼」という言葉について説明します。「儀礼」とは、主に正式な場面や伝統的な行事で行われるルールや決まりのことをいいます。
例えば、結婚式での進行や神社でのお参りの手順など、決まったやり方で行う行為が「儀礼」にあたります。
これは社会や文化によって異なり、国や地域、時代によって変わることがあります。
ですから、「儀礼」はある程度決まった形式を重視し、主に儀式や公式の場で用いられるものと考えてください。
日常生活で使われることは少なく、学校の入学式や卒業式、国の式典などで重要視されることが多いです。
「礼儀」とは?日常生活のマナーや相手への思いやり
一方で「礼儀」は、もっと身近な言葉です。
「礼儀」とは、他人に対して失礼のないように振る舞う態度やマナーを指します。
例えば、挨拶をきちんとする、言葉遣いを丁寧にする、約束を守るといった行動が「礼儀」です。
学校や職場、家庭など、さまざまな日常の場面で必要であり、人との関係を円滑にするための「思いやりの心」として大切にされています。
つまり、「礼儀」は日常生活の中で相手に敬意や感謝の気持ちを表す方法であり、「儀礼」とは違って、形式に縛られすぎない柔軟な部分も持っています。
「儀礼」と「礼儀」の違いを詳しく比較!わかりやすい表で解説
ここまで説明してきた「儀礼」と「礼儀」の違いを、表で整理してみましょう。
ding="5" cellspacing="0">| ポイント | 儀礼 | 礼儀 |
|---|
| 意味 | 公式・伝統的な形式やルール | 日常のマナーや相手への思いやり |
| 場面 | 結婚式・式典・伝統行事 | 挨拶・会話・日常生活全般 |
| 特徴 | 決まったやり方を重視 | 相手を思いやる気持ちが中心 |
| 柔軟性 | 厳格 | 比較的柔軟 |
| 例 | 国家の礼儀作法・宗教の儀式 | お辞儀や言葉遣い、時間を守ること |
このように、「儀礼」は形式やルールを重視し、主に公式な場面で使うもの。
「礼儀」は相手への気遣いやマナーとして、日常でも大事にされることです。
まとめ:正しく使い分けよう!
「儀礼」と「礼儀」は似ているようで違う言葉です。
日常生活やビジネスで大切なのは「礼儀」です。
一方、公式な式典や伝統行事など、決まったフォーマットがある場合は「儀礼」についての理解が必要となります。
言葉の意味をしっかり理解して、場面に応じて使い分けましょう。
ピックアップ解説「儀礼」という言葉は普段あまり使われないかもしれませんが、実は日本の文化や伝統の中でとても重要な役割を持っています。例えば、神社の参拝方法や結婚式の進行にはきちんとした儀礼があります。これらは単なるルールではなく、歴史や文化への敬意を表す方法でもあるのです。日常ではあまり意識しませんが、儀礼を知ることは日本人としてのアイデンティティを理解することにもつながりますね。
言語の人気記事

67viws

59viws

48viws

45viws
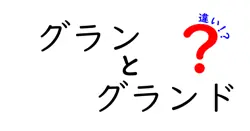
31viws
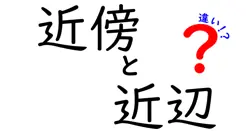
30viws
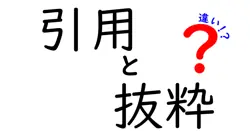
29viws
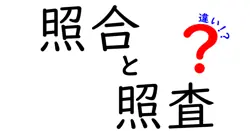
28viws
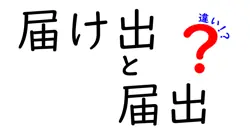
27viws

26viws
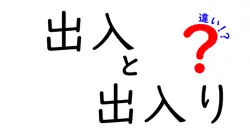
26viws
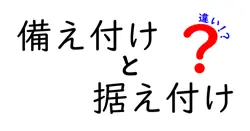
25viws
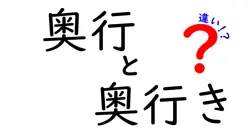
25viws
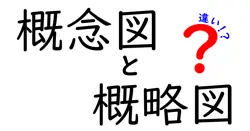
25viws
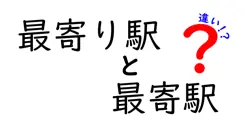
25viws
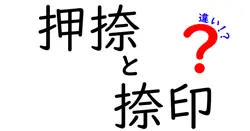
24viws
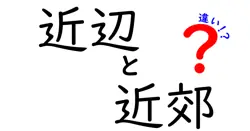
24viws

24viws

23viws
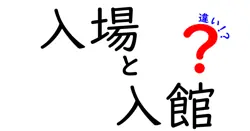
23viws
新着記事
言語の関連記事
発酵性食物繊維と発酵食品の違いについて理解しよう
健康に良いとされる「発酵性食物繊維」と「発酵食品」。
この2つは名前が似ているため、混同されがちですが、まったく別のものです。
発酵性食物繊維は、私たちの体で消化されずに大腸まで届き、腸内の善玉菌のエサとなって発酵する食物繊維の一種。
一方、発酵食品は、微生物の働きで食品自体が発酵してできた食べ物を指します。
この違いをしっかり理解することで、毎日の食事で健康維持や美容効果を高めやすくなります。
このページでは、中学生にもわかりやすく、発酵性食物繊維と発酵食品の特徴や違いを、詳しくかつ楽しく解説していきます!
発酵性食物繊維とは?
発酵性食物繊維は簡単に言うと、消化されにくい繊維質で大腸の中の善玉菌が餌にして発酵するものです。
食物繊維は体内の消化酵素では分解されず、そのまま腸まで届きます。
発酵性食物繊維は特に腸内の善玉菌にとって栄養源となり、腸内環境を整えるのに役立ちます。
例えば、大根の皮や玉ねぎの繊維、バナナに含まれるイヌリンなどがあります。
これらは腸で発酵して短鎖脂肪酸などの有益な物質を作り出し、便秘対策や免疫力アップにつながることも知られています。
主なポイント:
- 食物繊維の一種
・体の消化酵素では分解されない - 大腸で善玉菌が発酵して栄養を生み出す
- 便秘改善や免疫サポートに効果的
発酵食品とは?
発酵食品とは、微生物の働きによって食品が発酵し、味や栄養が変化した食品のことです。
日本の伝統的なものだと味噌、納豆、醤油、漬物、ヨーグルトなどが有名ですね。
発酵の過程で微生物がたんぱく質を分解して旨味を増やしたり、ビタミン類を生成したりします。
また、発酵食品にはその微生物も多く含まれているため、食べることで腸内の善玉菌が増えやすくなり健康に良いとされます。
主なポイント:
- 微生物の働きで食品が変化(発酵)した食品
・味や栄養価がアップ - 乳酸菌や酵母などの有益な菌が含まれる
- 日本の味噌やヨーグルトなどが代表例
発酵性食物繊維と発酵食品の違いを表でまとめてみよう
able border="1">| 項目 | 発酵性食物繊維 | 発酵食品 |
|---|
| 定義 | 消化されにくく腸内で発酵する食物繊維の一種 | 微生物の働きで発酵させて作られた食品 |
| 主な役割 | 腸内善玉菌のエサとなり腸環境を整える | 食品の味や栄養を変化させ、健康をサポート |
| 含まれるものの例 | 玉ねぎの繊維、バナナのイヌリン、キノコ類 | 味噌、納豆、ヨーグルト、漬物 |
| 身体への影響 | 便秘改善、免疫強化など | 腸内細菌のバランス改善、栄養補給 |
| 微生物が含まれるか | 含まれない(あくまで繊維質) | 含まれる(有益な菌が多い) |
まとめ:どちらも健康に欠かせない存在
発酵性食物繊維も発酵食品も、どちらも私たちの健康を守る強い味方です。
違いを理解し、発酵性食物繊維は食材から摂り、発酵食品は発酵の力で作られた食品を取り入れようというのがポイントです。
両方をバランス良く摂ることで、腸内環境が良くなり、免疫力向上や美容にも効果的!
ぜひ、日々の食事に積極的に取り入れてみてくださいね。
ピックアップ解説発酵性食物繊維って聞くと、単なる食物繊維とすぐに思いがちですが、実は腸内の善玉菌がエサにして発酵する特別な繊維のことです。
この発酵、実は私たちの体の免疫力をグーンとアップさせる秘密のカギ!
特に便秘がちな人や疲れやすい人は、積極的に発酵性食物繊維が含まれる食材を取ると体調が変わるかもしれませんよ。
発酵食品とセットでバランス良く食べるとさらに効果的なので、ぜひお試しあれ!
食品の人気記事

56viws

53viws

37viws

30viws
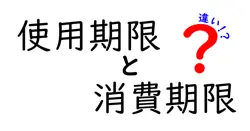
23viws

21viws

20viws

17viws

16viws

15viws
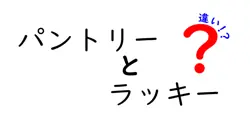
15viws
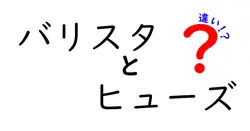
15viws

14viws
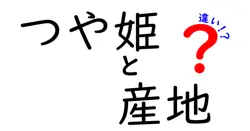
14viws
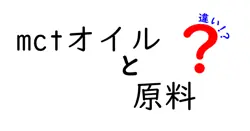
14viws
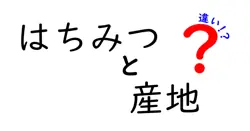
13viws
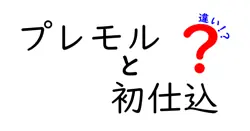
13viws
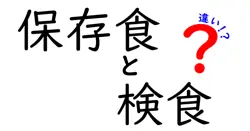
13viws
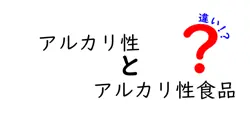
13viws
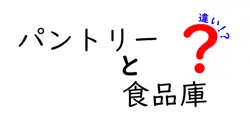
13viws
新着記事
食品の関連記事