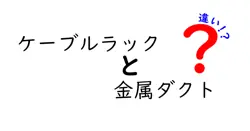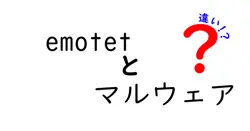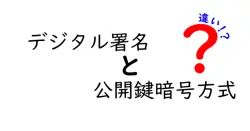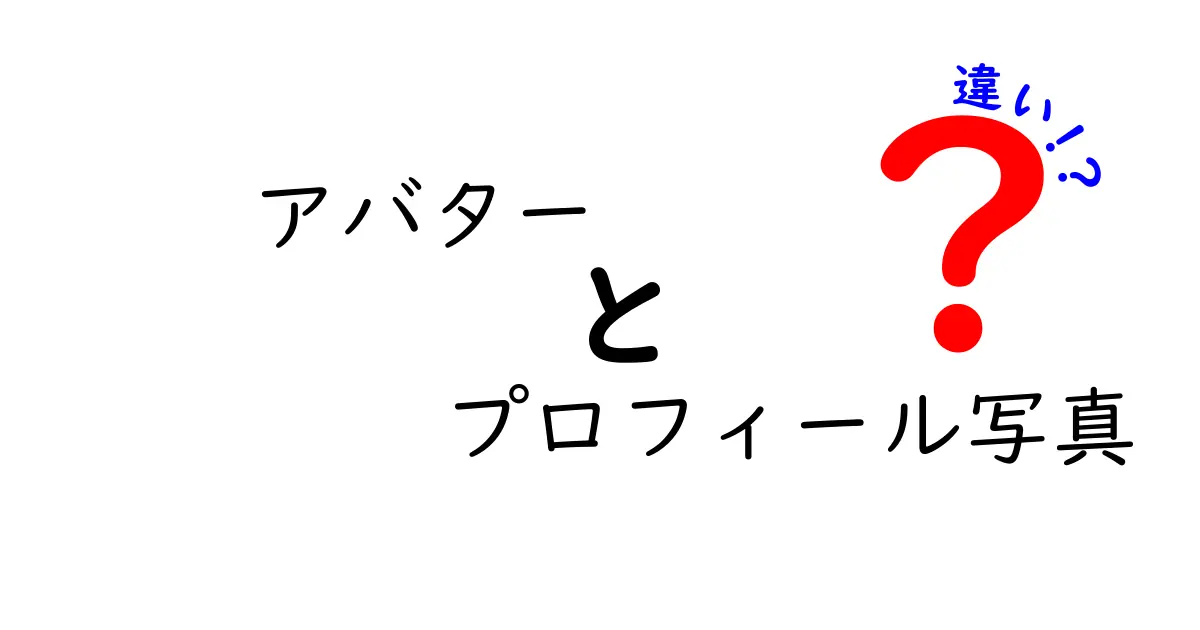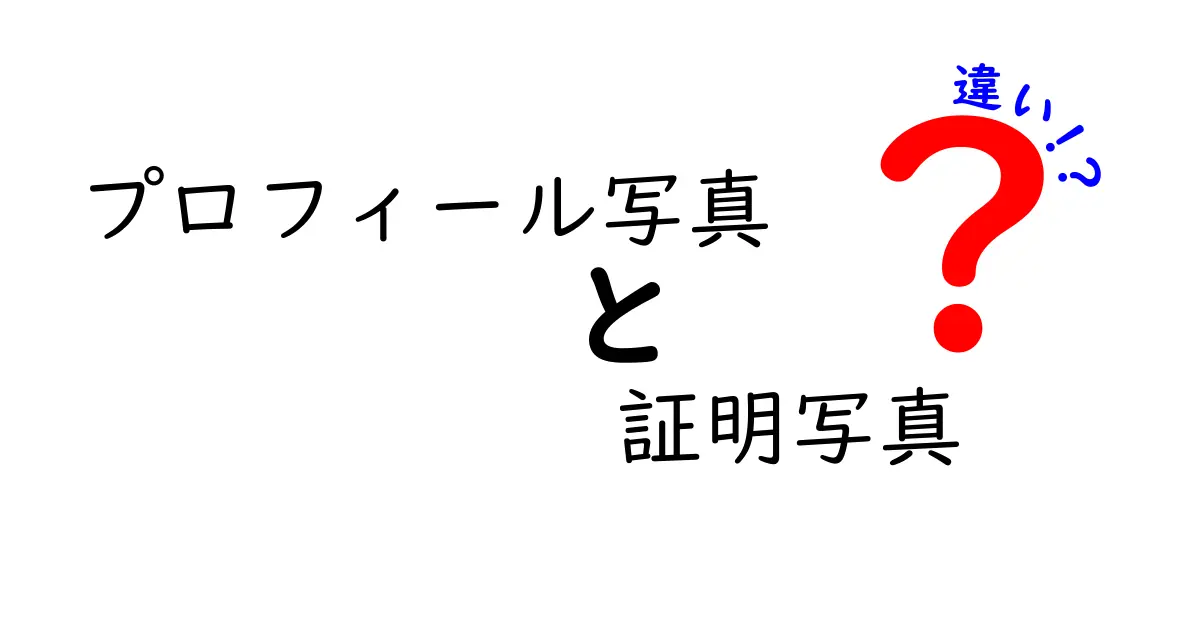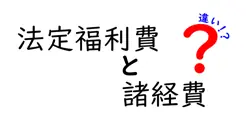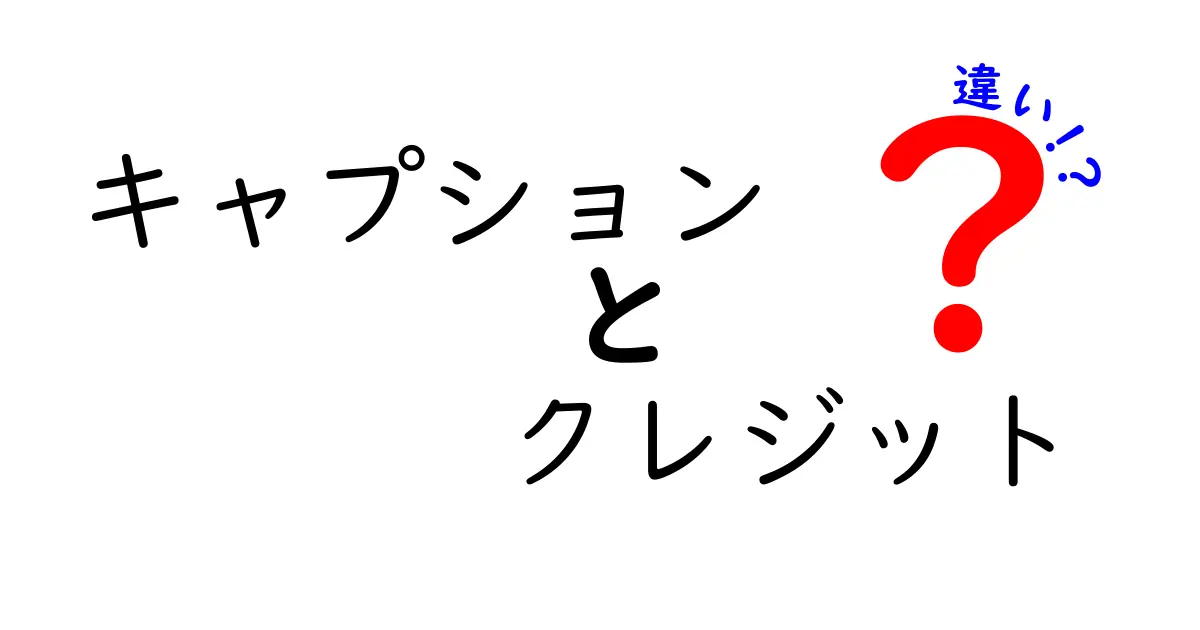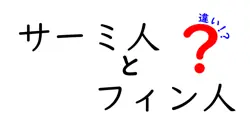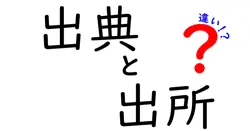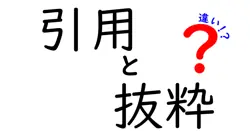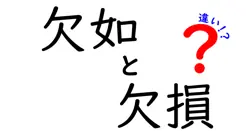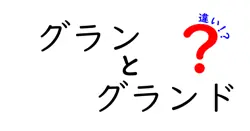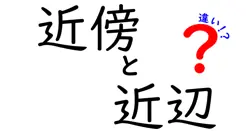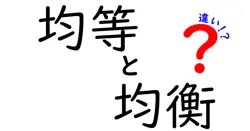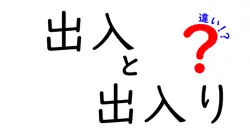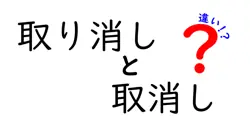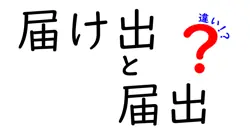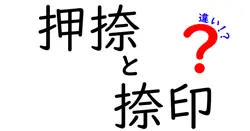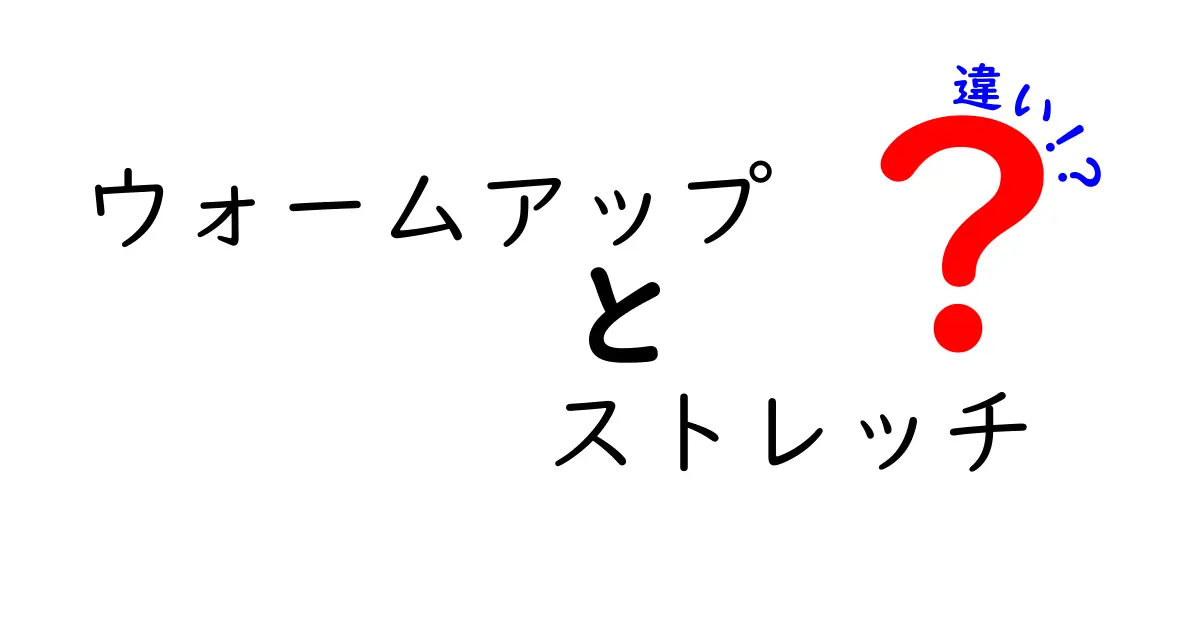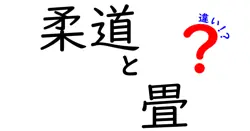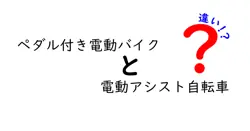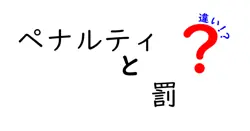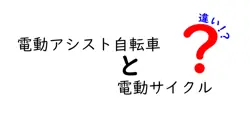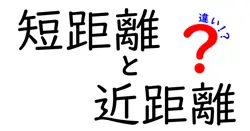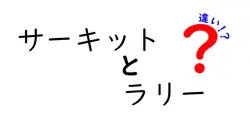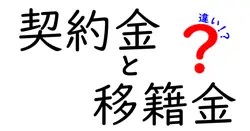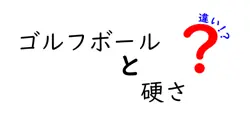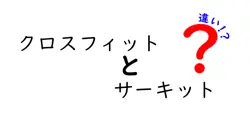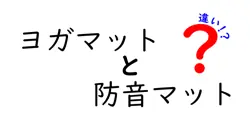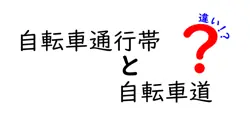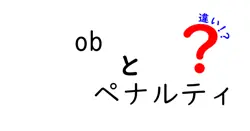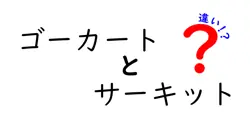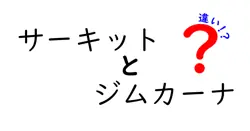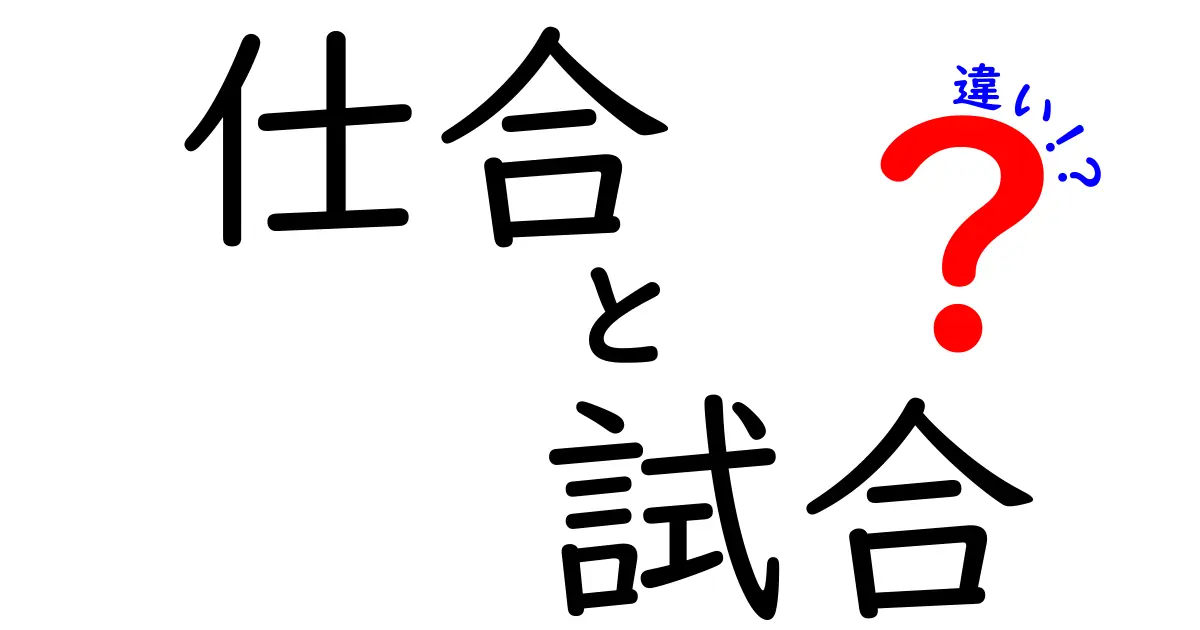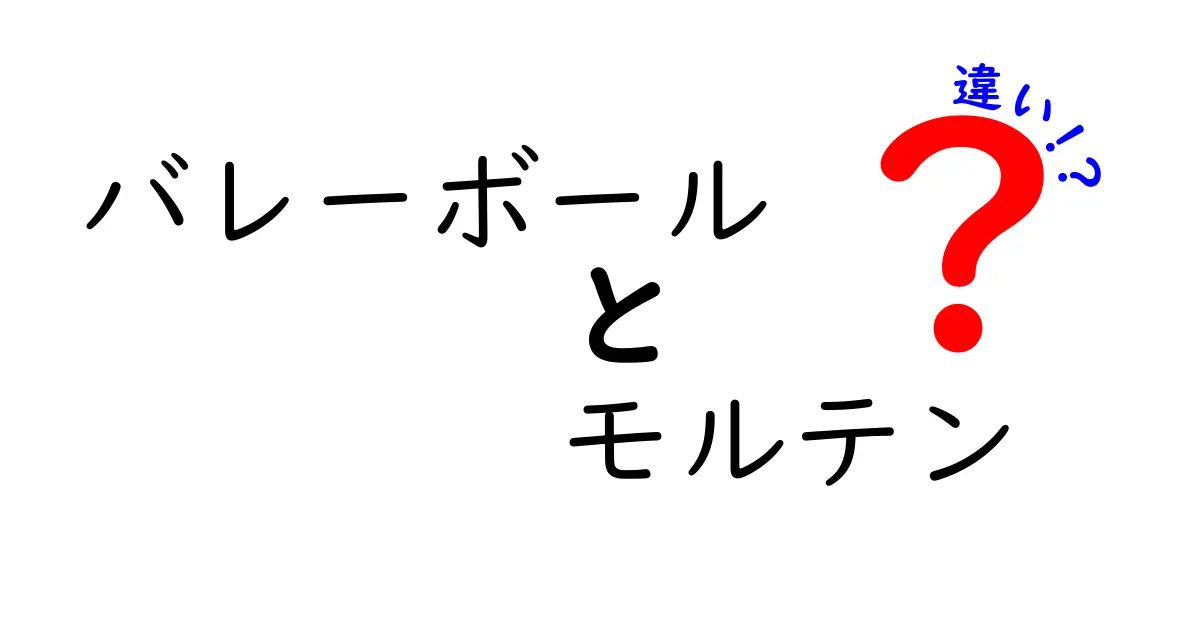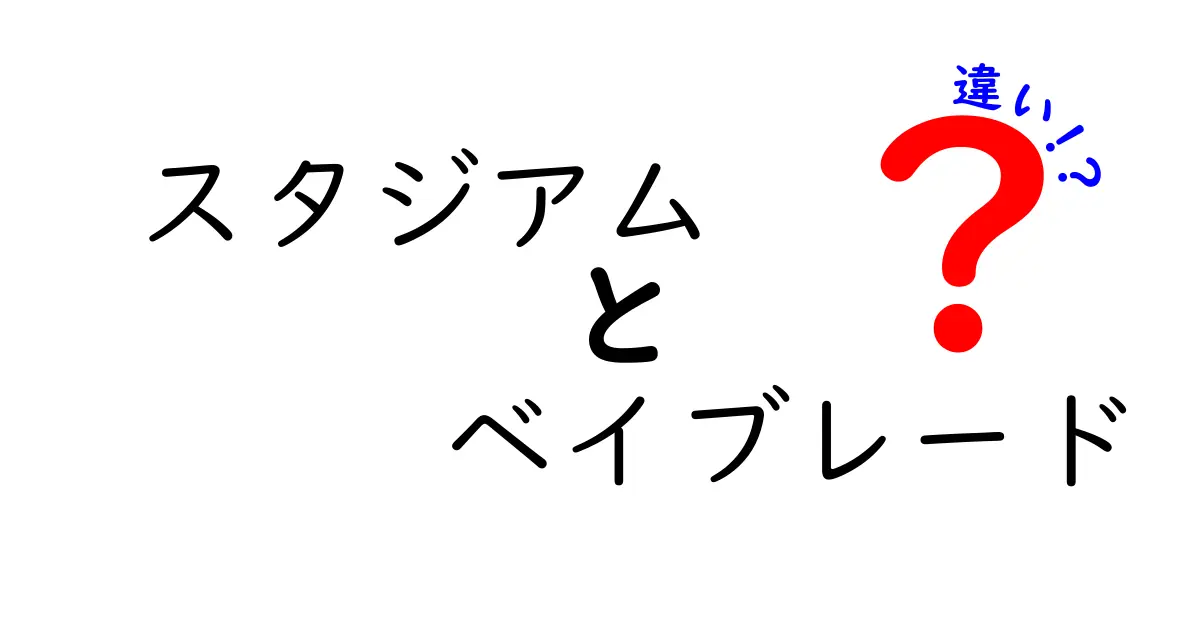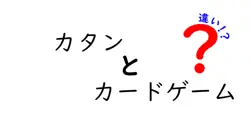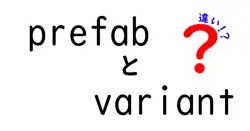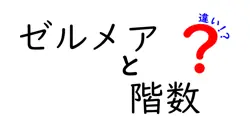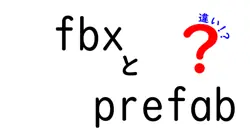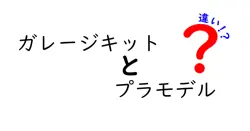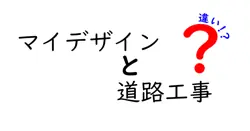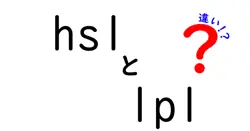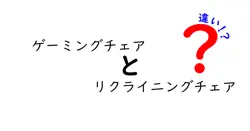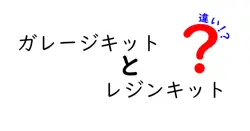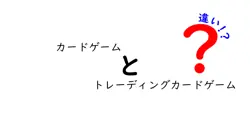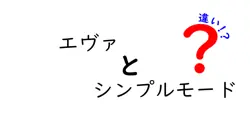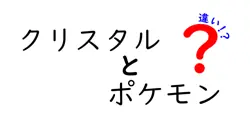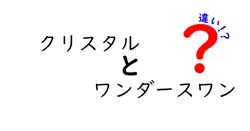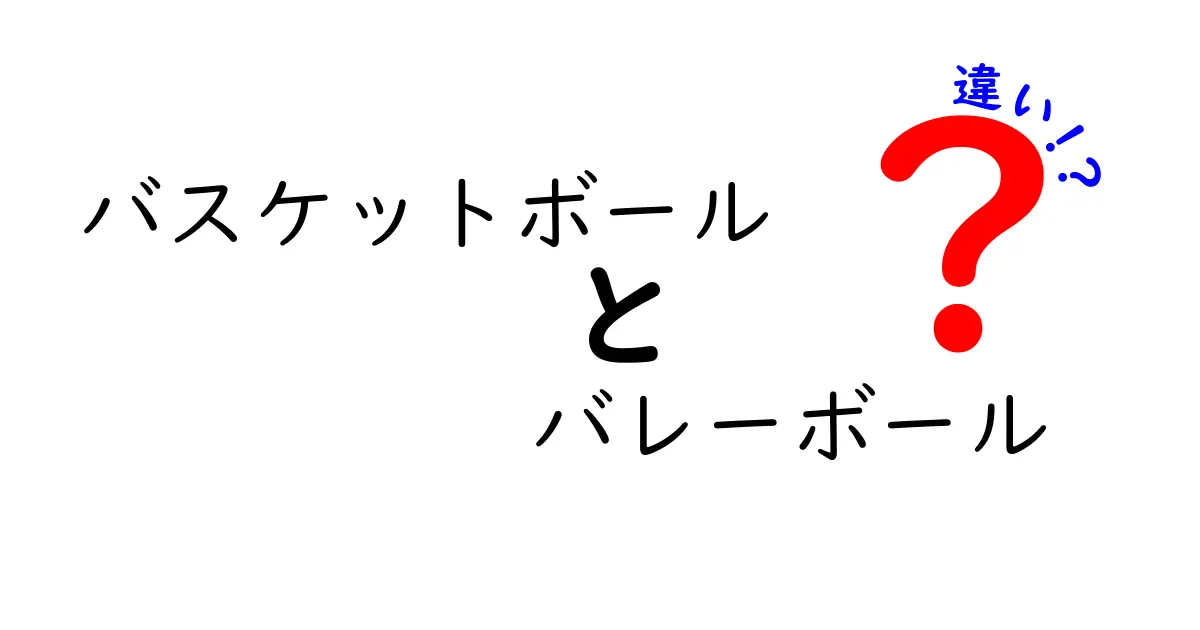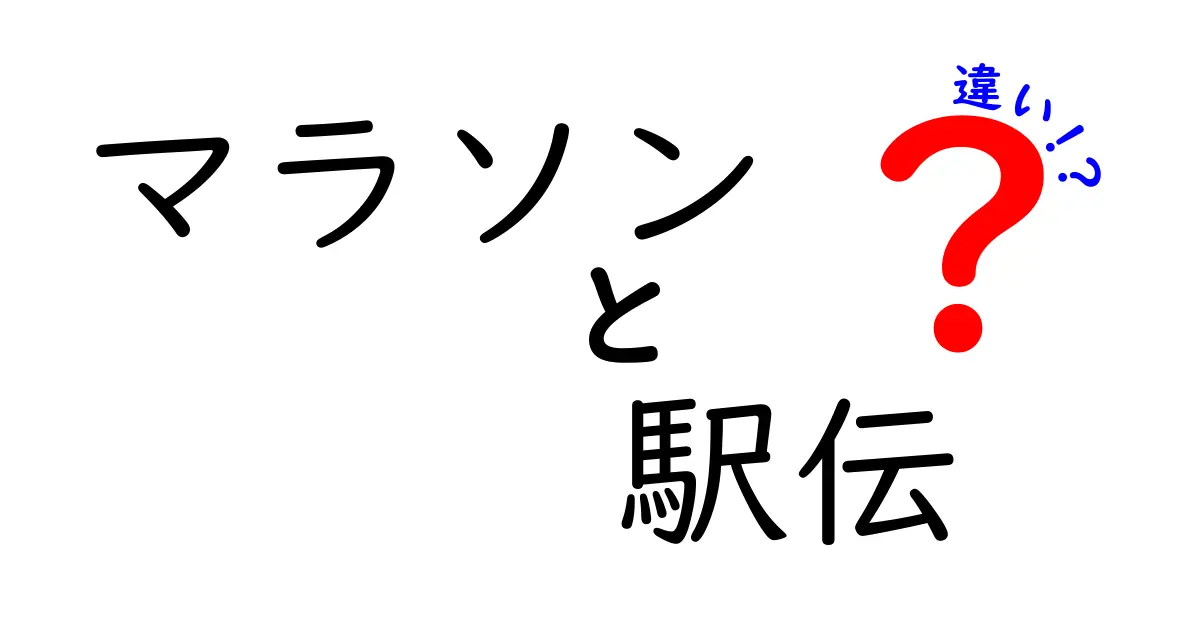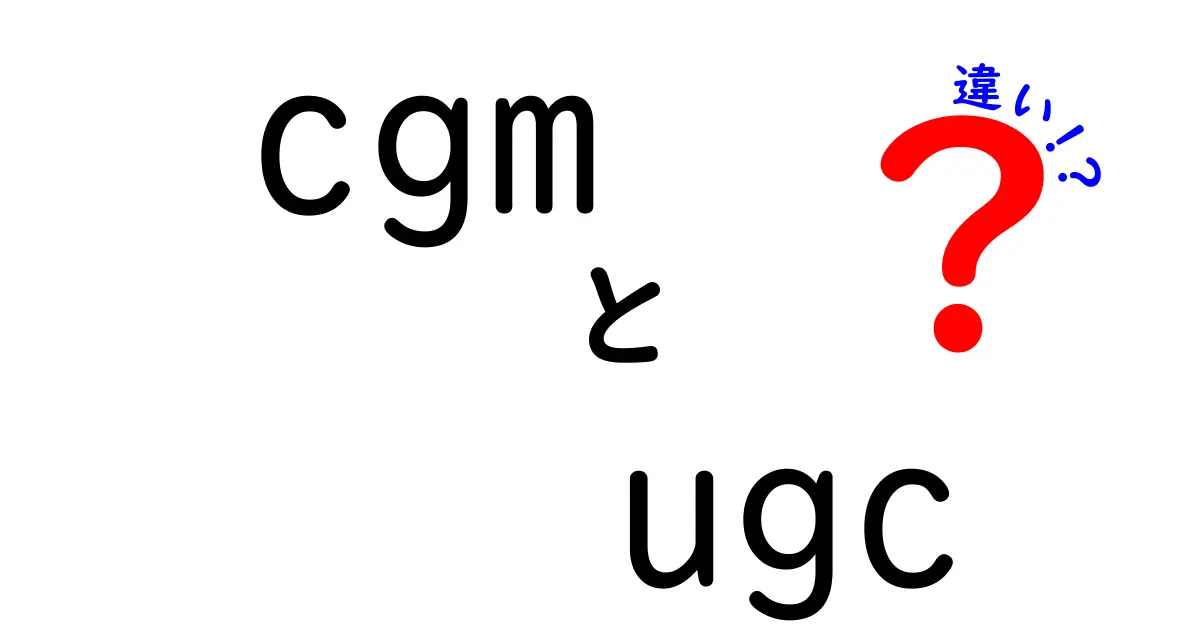
CGM(消費者生成メディア)とは何か?
まずはCGMという言葉について説明します。CGMは「Consumer Generated Media」の略で、一般の消費者がインターネット上で自由に情報やコンテンツを作り、発信することを指します。たとえば、ブログ、SNSの投稿、レビューサイトへの口コミなどがCGMに含まれます。
つまり、企業やメディアではなく、消費者自身が主体となって情報を作り出すメディアのことです。このようなCGMは、リアルな声や体験が反映されているため、他のユーザーにとって参考になることが多いです。
メリットとしては、信頼性が高く、拡散力が強いことが挙げられます。
消費者同士のコミュニケーションの場としても重要な役割を果たしています。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは何か?
次にUGCという言葉について説明していきます。UGCは「User Generated Content」の略称で、ユーザー、つまりインターネットを利用する個人やグループが作ったコンテンツのことを指します。写真、動画、ブログ記事、レビュー、コメント、SNSの投稿などが含まれます。
CGMと似ていますが、UGCはより広い意味で使われることが多く、「コンテンツそのもの」を指すことが多いです。たとえば、YouTubeに投稿される動画やInstagramの写真はすべてUGCです。
また、UGCは企業がマーケティングで活用することも盛んで、ユーザーが作った商品レビューや体験談を掲載することで、信頼性や親近感を高める効果があります。
CGMとUGCの違いまとめ:ポイントと表で解説
ここまでCGMとUGCの意味を説明してきましたが、違いをわかりやすくまとめてみましょう。
まず、CGMは「メディアとしての場所や仕組み」を指すことが多く、UGCは「ユーザーが作るコンテンツそのもの」を指すという違いがあります。
したがって、CGMはUGCを含む広い概念ともいえます。
下の表で具体例とともに整理しましたので、ご覧ください。
| 用語 | 意味 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| CGM(消費者生成メディア) | 消費者が自由に情報を発信するメディアの仕組み | ブログサイト、SNS、口コミサイト | 消費者主体で情報が作られ、広がる場所や仕組み |
| UGC(ユーザー生成コンテンツ) | ユーザーが作成したコンテンツの総称 | 投稿された動画、写真、レビュー、コメント | コンテンツそのものを指し、CGM内の一部でもある |
このようにCGMの中にUGCが存在し、CGMはプラットフォームや環境も含めた概念、UGCは具体的なコンテンツを指すと覚えると理解しやすいです。
企業のマーケティングやWeb運営において、両者の違いをきちんと理解し活用することが非常に重要になります。
まとめにかえて
今回は「CGMとUGCの違い」について解説しました。どちらもユーザーや消費者が主体となる情報発信の形ですが、CGMは『場所や仕組み』、UGCは『コンテンツそのもの』という違いがあります。
この理解があれば、インターネット上の情報収集や発信、そして企業のマーケティング戦略をより深く知ることができます。
ぜひ本記事を参考に、CGMとUGCを正しく理解して活用してみてください。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)って言うと、動画や写真だけを思い浮かべがちだけど、実はブログのコメントやレビューも全部UGCの一種なんだ。
例えばYouTubeの動画はUGCだけど、その動画の再生リストやフォロワー数が増えることで、その動画の価値が高まっていくんだよね。
面白いのは、UGCの中でも『いいね』『共有』といった反応もユーザーが作る新たなコンテンツといえるから、UGCはどんどん広がるし、多様な形で存在しているんだ。
この広がりがWeb上のコミュニケーションを豊かにしているんだよね。
前の記事: « アバターとプロフィール写真の違いとは?わかりやすく解説!