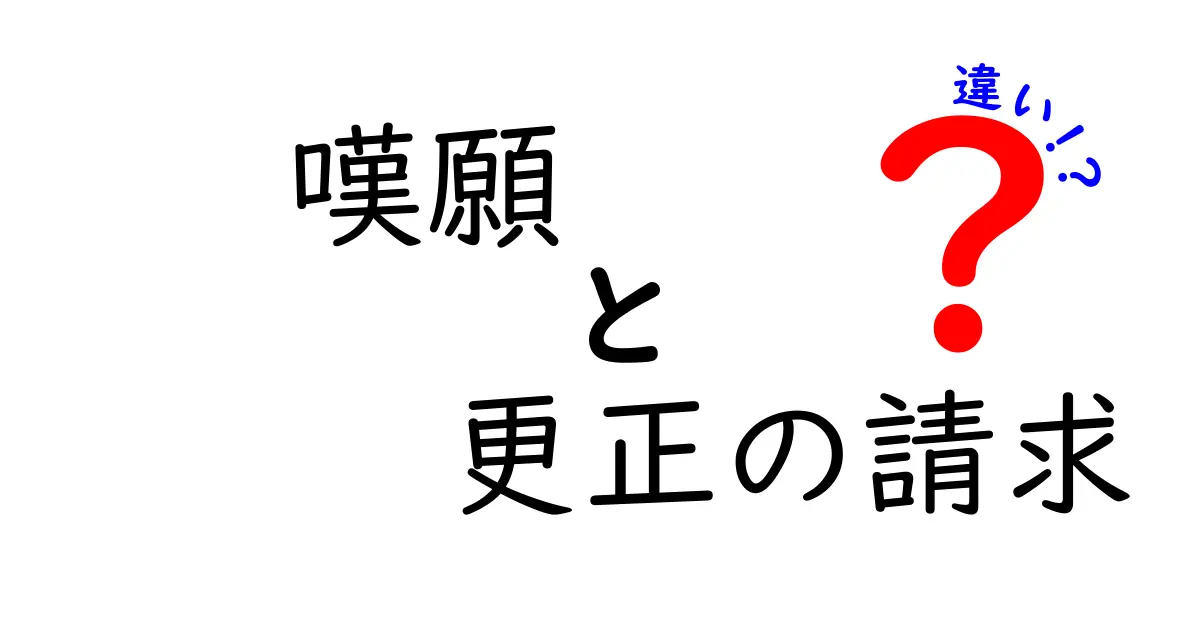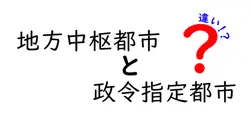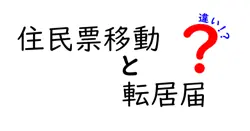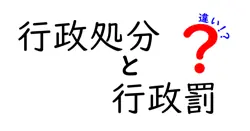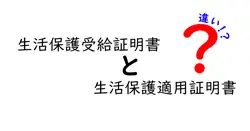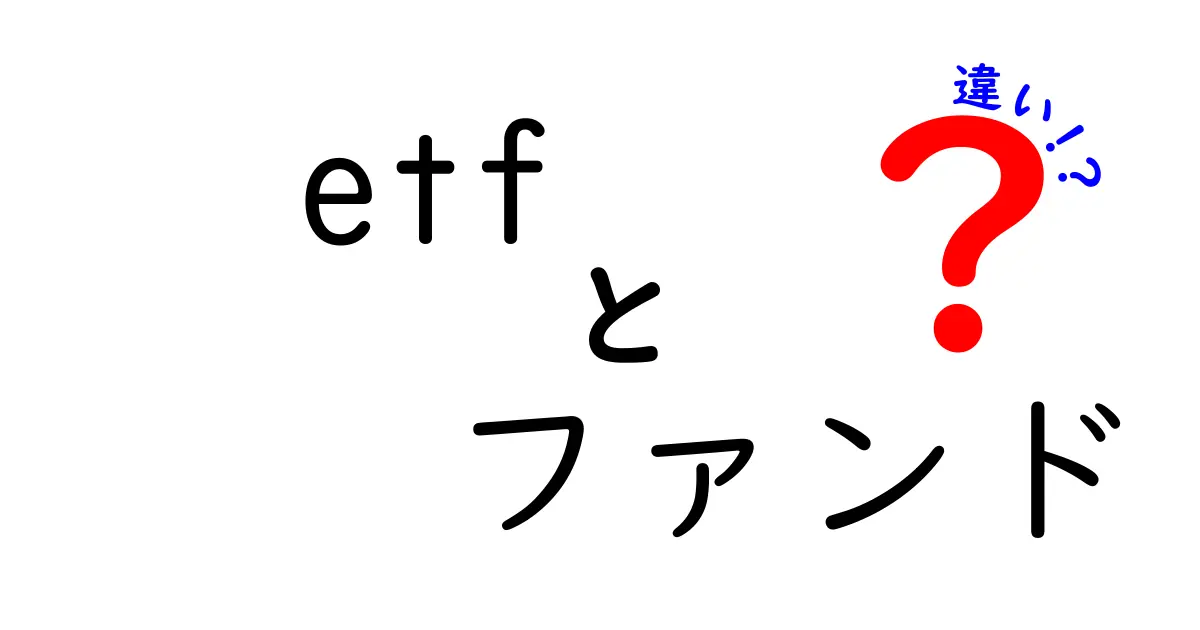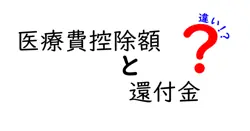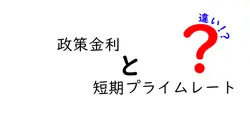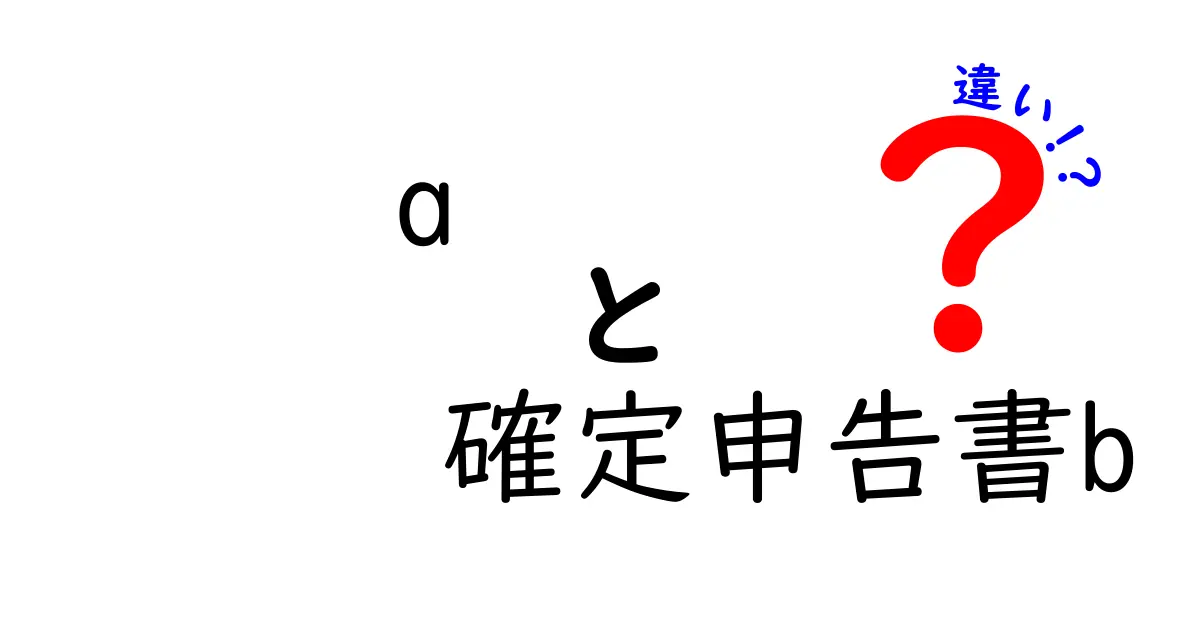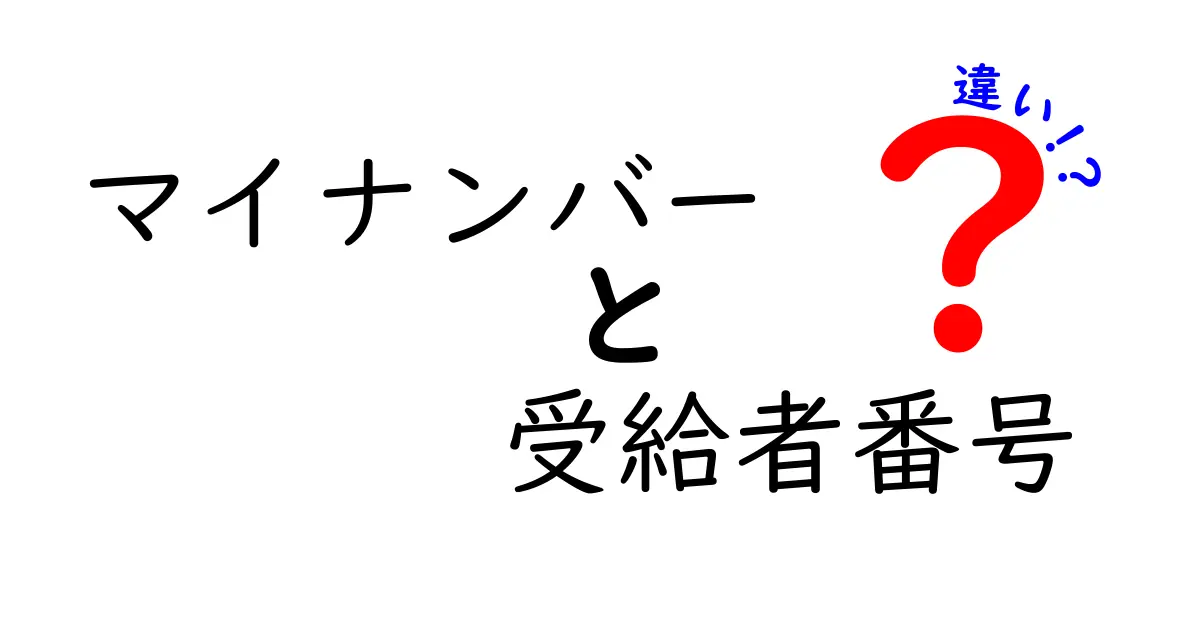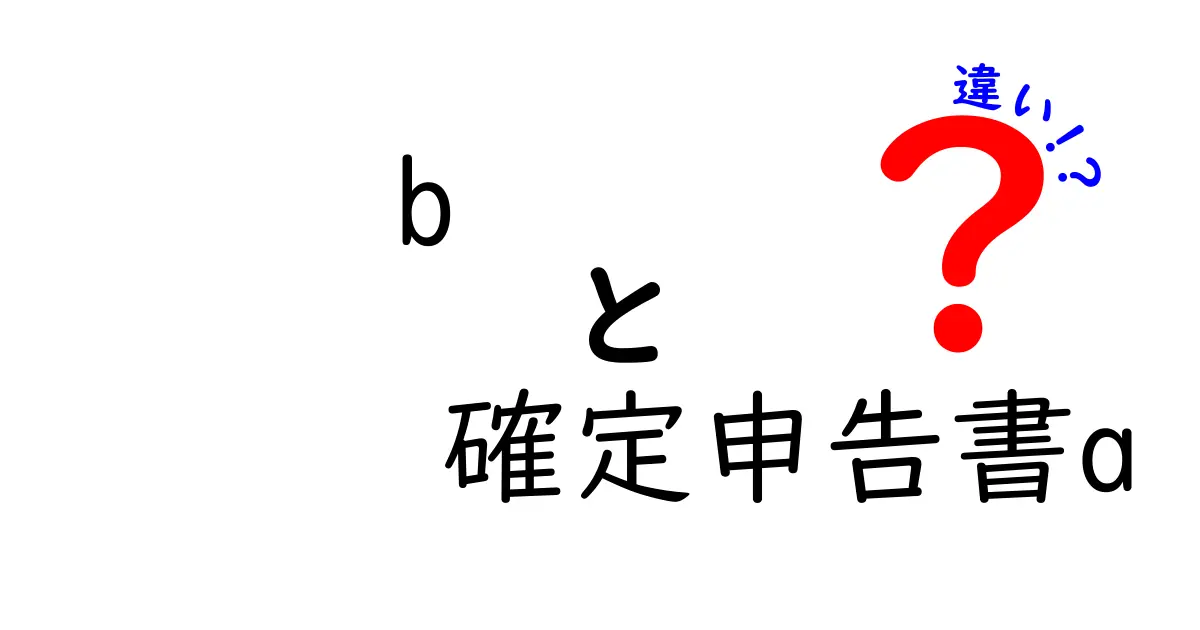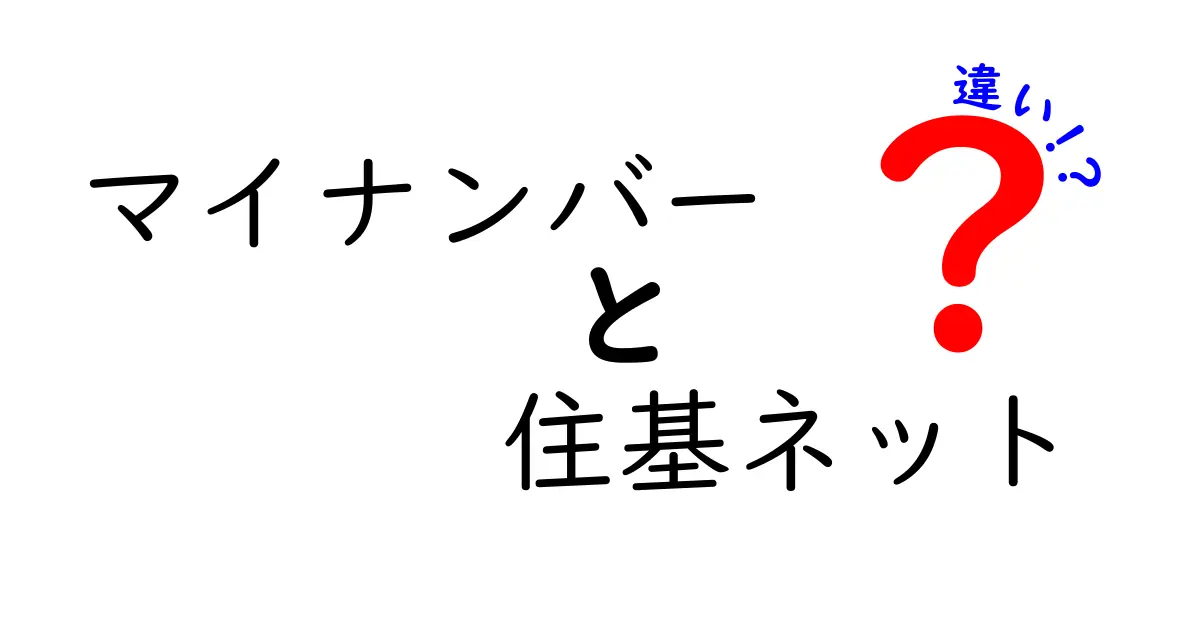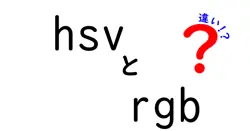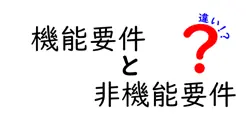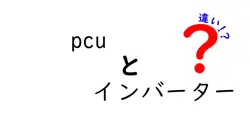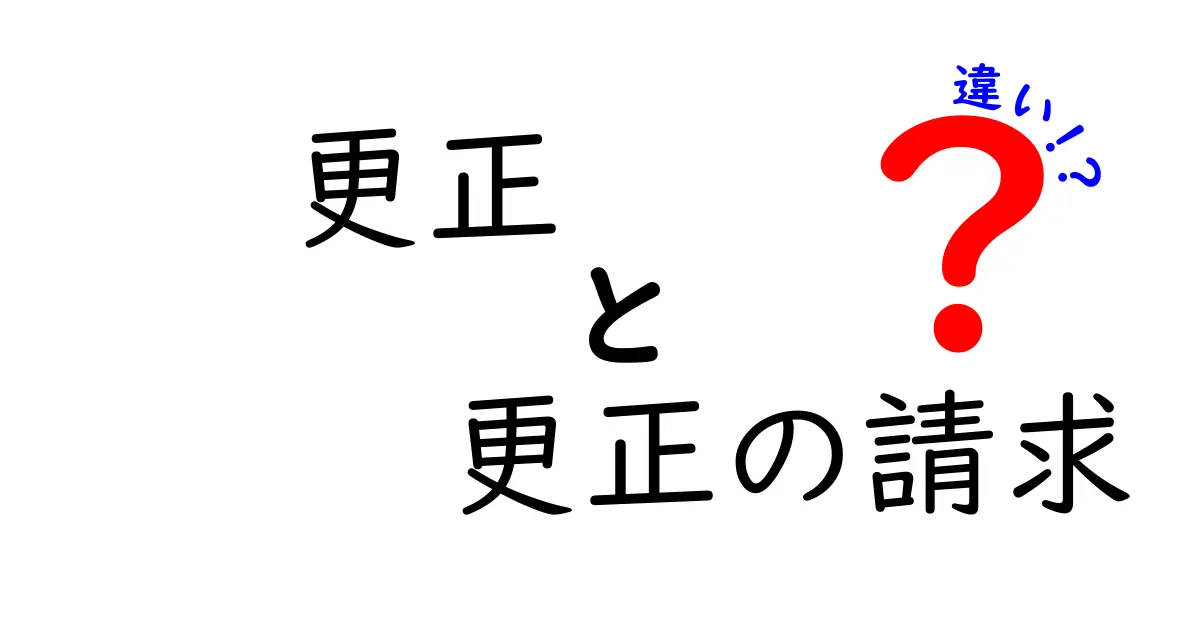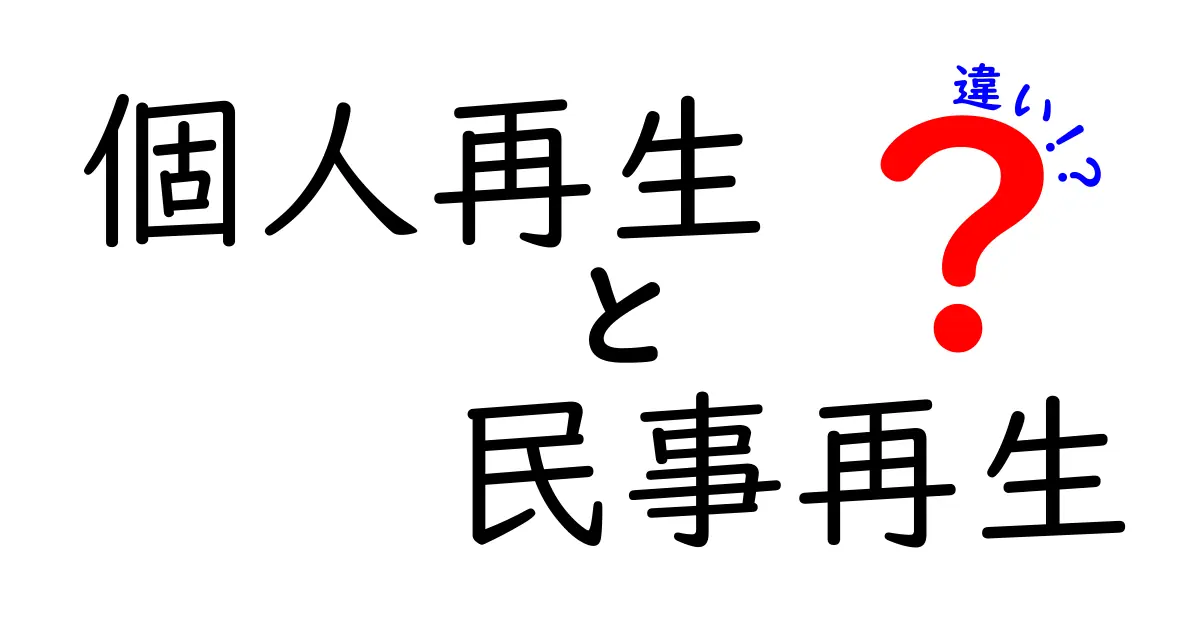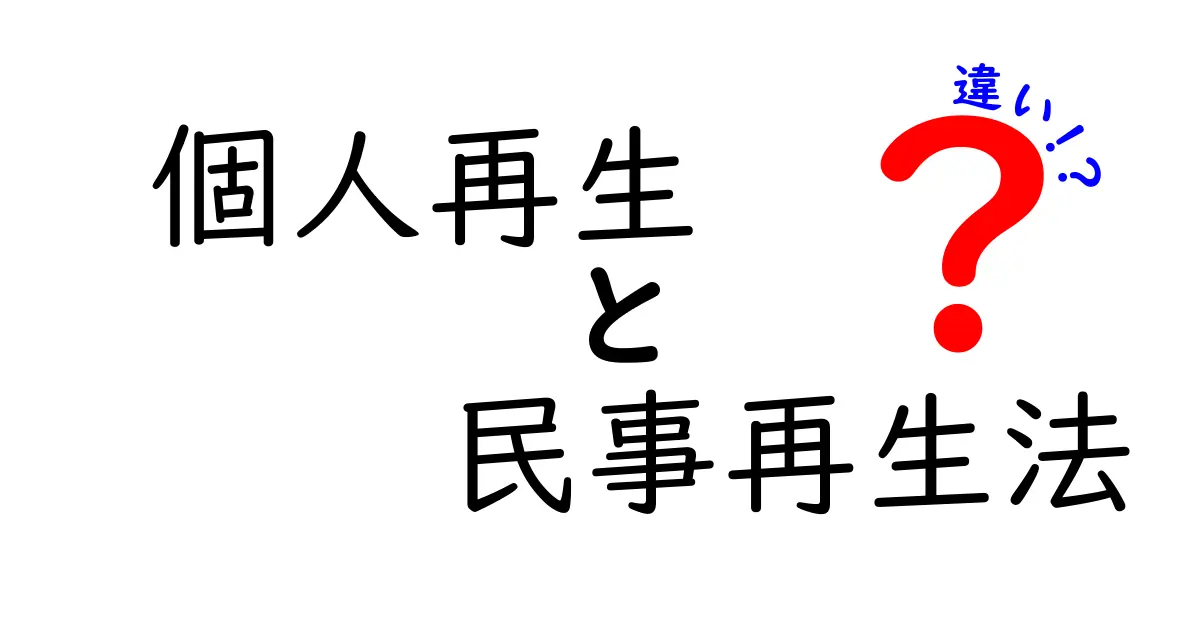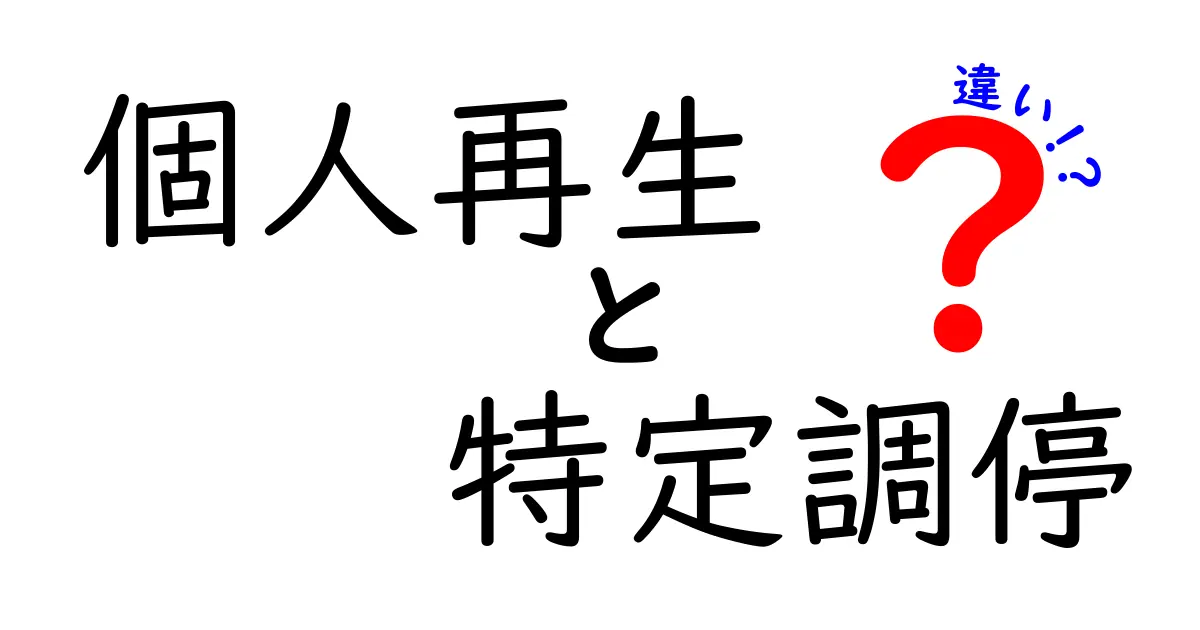更正と更正の請求の基本的な違いとは?
税金の話をするときに、「更正(こうせい)」と「更正の請求」という言葉を聞くことがあります。
この二つは似ているようで、実は重要な違いがあります。
まずはそれぞれの意味から説明しますね。
「更正」とは、税務署が申告内容を調べ直して、申告内容に誤りや不足がある場合に訂正することを言います。つまり、税務署側からの指摘で修正が行われるんです。
一方、「更正の請求」は、納税者本人が自分の申告した内容に誤りがあったと気づいて、正しい金額に直して欲しいと税務署にお願いすることを意味します。
要するに、更正は税務署のアクションで、更正の請求は納税者のアクションだと覚えてください。
次の章では、もっと具体的に流れや目的をくわしく紹介します。
更正の仕組みと更正の請求の流れを詳しく解説
「更正」は税務署が行うので、税務署の職員が申告された内容をチェックし、間違いを見つけたときに修正処理をします。これによって追加の税金を請求されたり、逆に還付されたりすることがあります。
この更正は、例えば確定申告後に税務署が調査を行い、申告内容に間違いがあると判断した場合に使われます。
これに対して「更正の請求」は、納税者自身が申告ミスに気付いたとき、一定期間内に税務署に申し出て、申告内容を修正してもらう制度です。
例えば経費の計上漏れがあったり、所得の過小申告が見つかった場合に使われます。
更正の請求は、申告期限から5年以内に申し出る必要があります。期間を過ぎると請求できませんので注意しましょう。
このように、更正は税務署主導、更正の請求は納税者主導で行われるのが大きな特徴です。
更正と更正の請求の違いをわかりやすく比較表でチェック!
ポイントを一覧で整理すると、両者の違いがより鮮明になります。以下の表をご覧ください。
ding="8" cellspacing="0">| 項目 | 更正(こうせい) | 更正の請求 |
|---|
| 実施主体 | 税務署 | 納税者(申告者) |
| 目的 | 申告内容の誤り訂正
(税務署が発見) | 申告の誤り訂正
(納税者が発見) |
| 申告期限 | 調査後に更正通知 | 申告期限から5年以内 |
| 処理の方向 | 税額の追加請求や還付 | 過払い税額の還付請求など |
| 納税者への通知 | 必ず通知がある | 請求後に納税者へ通知 |
able>
この表から分かるように、どちらも誤りを正すための手続きなのですが、主体や申告期限、処理の流れに違いがあることがわかりますね。
税金のトラブルを避けるためにはこの違いを理解し、必要に応じて適切な手続きを行うことがとても重要です。
続いて、実際にどんなときに使われるのか、具体例を紹介しておきます。
更正と更正の請求はどんな場合に使う?具体例でイメージしよう
更正のケース
例えば、税務署があなたの申告書を調べて、申告していた所得が実際より少ないことがわかったとします。
その場合、税務署が更正を行い、不足分の税金を請求します。
更正の請求のケース
反対に、自分で申告した時に経費計上を忘れてしまい、払う税金が多くなっていたと気づいた場合。
このとき、納税者は更正の請求を税務署に出して、過払い分の還付を求めることができます。
このように、税務署からの指摘か、納税者からの申請かが、どちらを使うかのポイントになります。
ただし、税の専門用語や手続きに不慣れな人は、税理士さんに相談すると安心ですよ。
ピックアップ解説「更正の請求」という言葉を聞くと、ちょっと難しいイメージがありますよね。でも、〈納税者が自分の申告ミスに気づいて訂正をお願いする行動〉なんです。
例えば、お小遣い帳をつけているときに、収入や支出を間違えて記録したと気付いたら、直しますよね?
それと同じで、自分で申告の誤りを正したいときには更正の請求を使います。
意外と知られていませんが、申告期限から5年以内ならこの請求ができるため、とても便利な制度なんです。
これを知っておくと、もし間違いに気づいたときあわてずに済みますよね!
ビジネスの人気記事

328viws

308viws

265viws

254viws

247viws

226viws

220viws

220viws

214viws

211viws

210viws

203viws

199viws

194viws

188viws

182viws

177viws

172viws

170viws

169viws
新着記事
ビジネスの関連記事
個人再生と民事再生とは?基本的な違いについて
借金問題でよく耳にする「個人再生」と「民事再生」という言葉。
一見、似ているようですが、実はそれぞれ目的や対象が違う法律手続きです。
まずはその基本から押さえましょう。
個人再生は主に個人が借金を大幅に減らして返済するための手続きです。
生活を立て直すために借金を原則5分の1~10分の1程度に減らし、3年かけて返済していきます。
一方、民事再生は個人だけでなく法人(会社)も利用できる再建手続きです。
経営不振の会社が裁判所の管理のもとで債務を減らし、事業を続けながら借金を整理します。
個人再生は個人の生活再建が目的、民事再生は会社も含む広い範囲の再建制度と考えればわかりやすいです。
つまり、個人再生=個人向けの借金減額制度、民事再生=個人・法人双方の事業再建制度です。
個人再生と民事再生の手続きの違いと特徴
個人再生と民事再生の大きな違いは手続きの対象と進め方です。
【個人再生】
・裁判所に申し立てて開始
・財産価値に応じた最低返済額が決まる
・原則3年で借金を返済
・住宅ローンがあっても住宅を手放さずに再生可能な場合が多い
・ブラックリストに掲載されるが自己破産より少し軽い印象がある
【民事再生】
・会社や個人の経営状態を裁判所で審査
・会社の場合は破産よりも経営継続を重視
・再建計画案を作成し債権者の合意が必要
・監督委員がつくこともあり手続きが複雑になる場合が多い
つまり個人再生は個人の生活再建に特化し、比較的スムーズに進むのに対し、民事再生は事業再建に向けて裁判所や債権者とも交渉しながら進める複雑な手続きです。
このような違いから、借金の性質や申請者の状況に応じて使い分けられます。
個人再生と民事再生のメリット・デメリット比較表
able border="1">| 項目 | 個人再生 | 民事再生 |
|---|
| 対象 | 主に個人 | 個人・法人(会社) |
| 手続きの目的 | 借金の大幅減額と返済計画の作成
生活再建重視 | 事業再建と債務整理
経営継続重視 |
| 返済期間 | 原則3年(最長5年まで) | 計画により異なる |
| 住宅ローン特則 | 利用可能で住宅を守りやすい | 適用制限あり |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 複雑で時間がかかる |
| 影響(信用情報など) | ブラックリスト登録あり | 債権者との交渉多く影響広範囲 |
まとめ:自分に合った債務整理方法を選ぶポイント
借金問題は法律手続きを使って解決できますが、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
個人再生は、大きな借金があり住宅ローンを残したい個人の方に適しています。
生活再建を目指しつつ、裁判所の手続きを使って借金を減らすため、とても人気があります。
一方、民事再生は事業を続けながら借金を減らし再建したい会社や個人事業主に向いています。
手続きは時間や労力がかかりますが、ビジネスを続ける上で重要な制度です。
もし借金に困っているなら、専門家に相談して、自分の生活や事業に合う方法を選びましょう。
このブログでは、「個人再生」と「民事再生」の違いを理解して、あなたに合った借金整理のヒントを提供しました。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
ピックアップ解説「個人再生」と聞くとどうしても借金を減らすことばかりに目が行きがちですが、住宅ローン特則があるため、自宅を手放さずに借金整理ができるのが大きな魅力です。
これは、「個人再生」の中でもとても重要なポイントで、住宅ローン以外の借金だけを減額し、マイホームは守ることができる制度です。
意外と知られていませんが、住宅を残したい人には非常に頼りになる法律の仕組みです。
借金問題はきついですが、こんな制度があることを覚えておくと安心ですね。
金融の人気記事

422viws

287viws

246viws

226viws

205viws

202viws

189viws

181viws

179viws

178viws

171viws

170viws

168viws

153viws

131viws

129viws

125viws

122viws
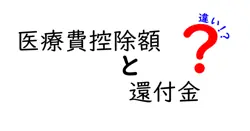
121viws
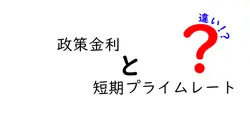
118viws
新着記事
金融の関連記事