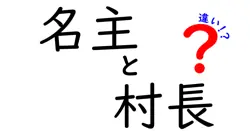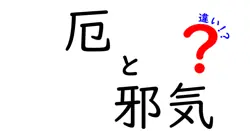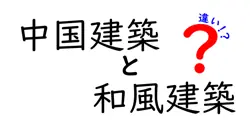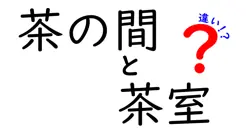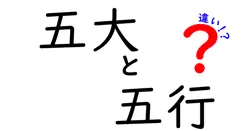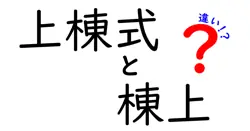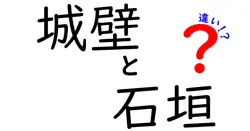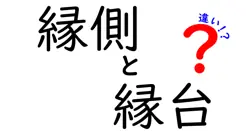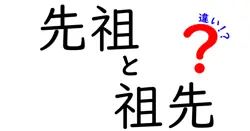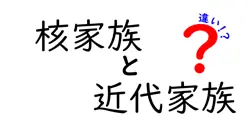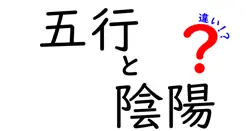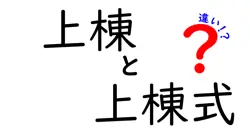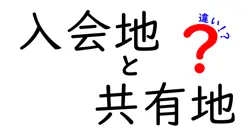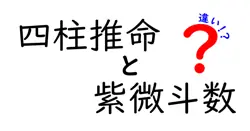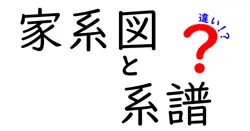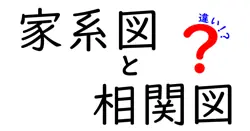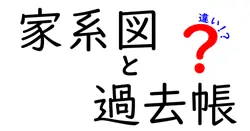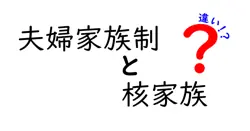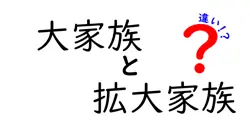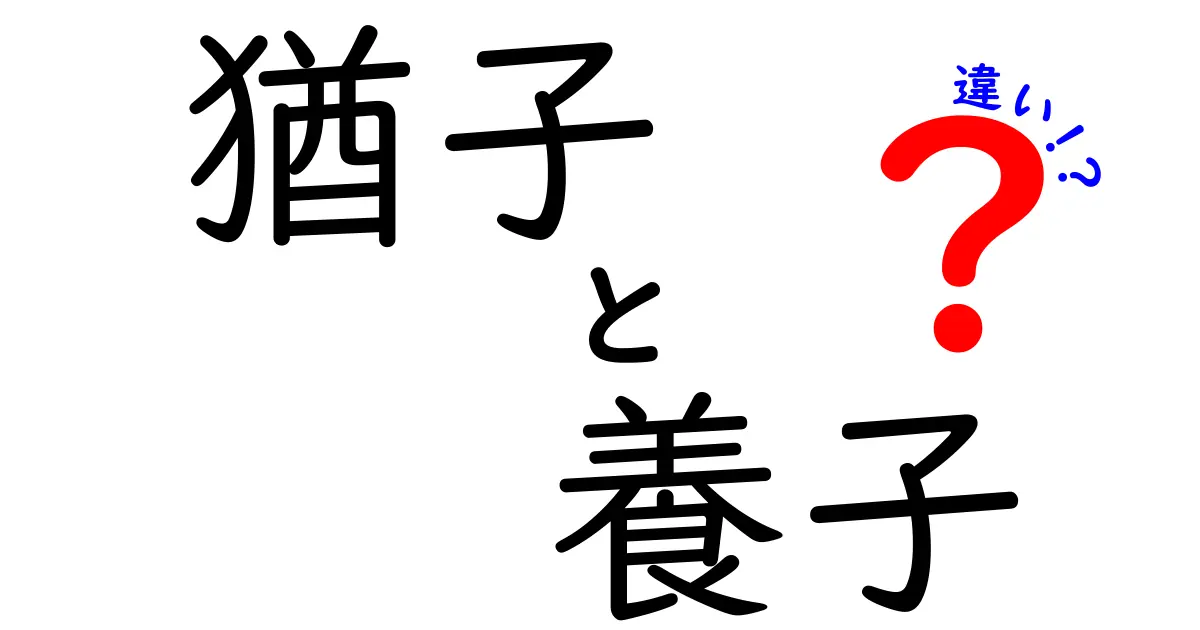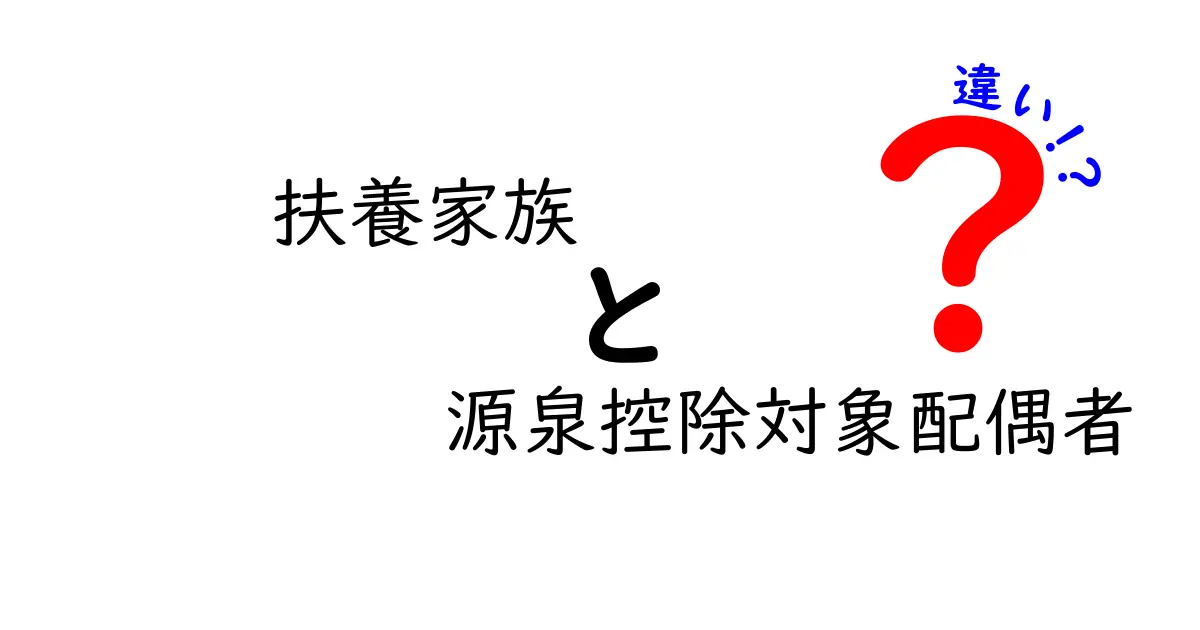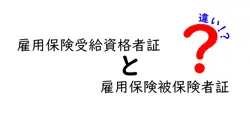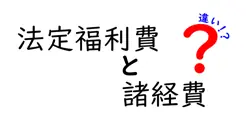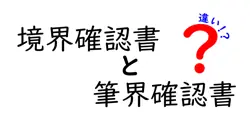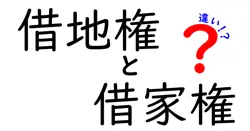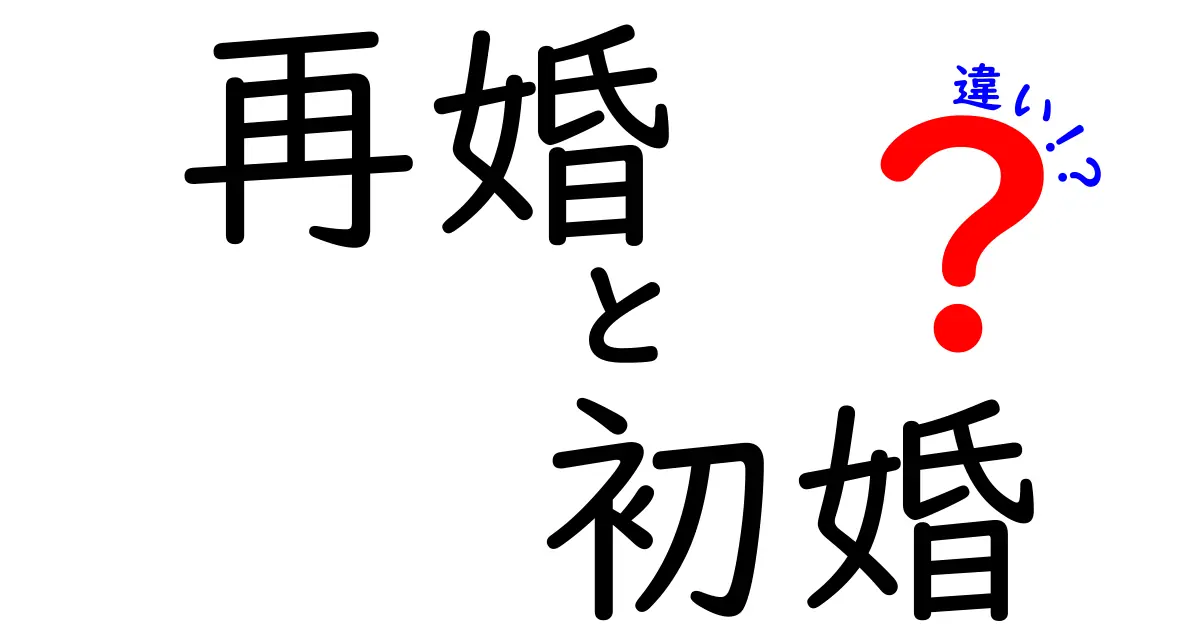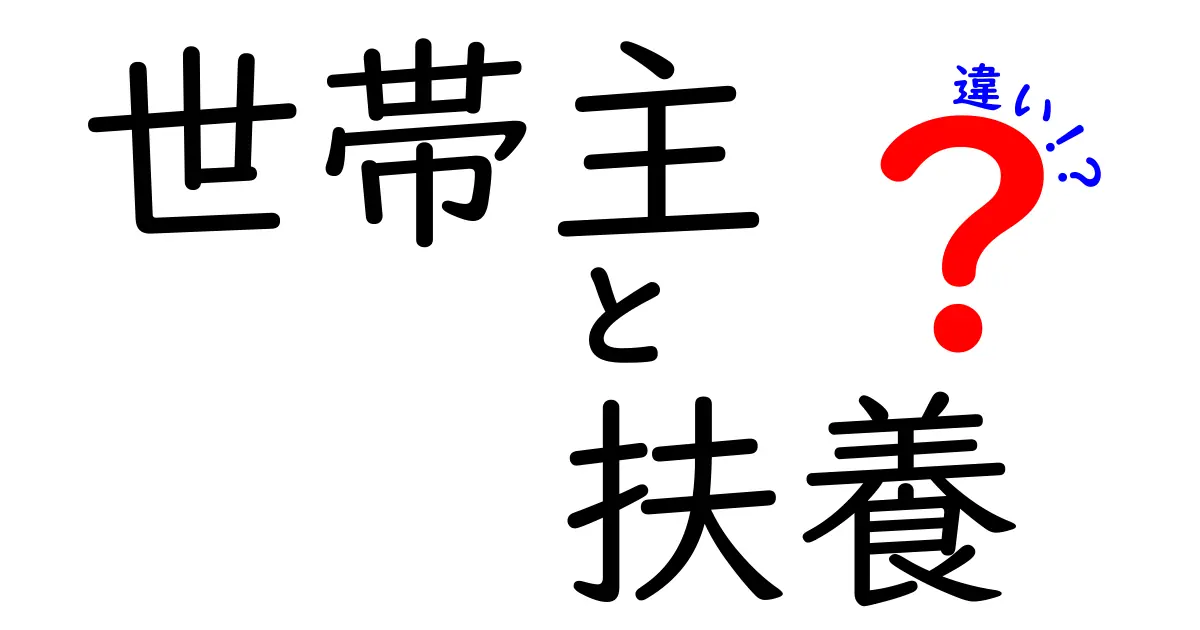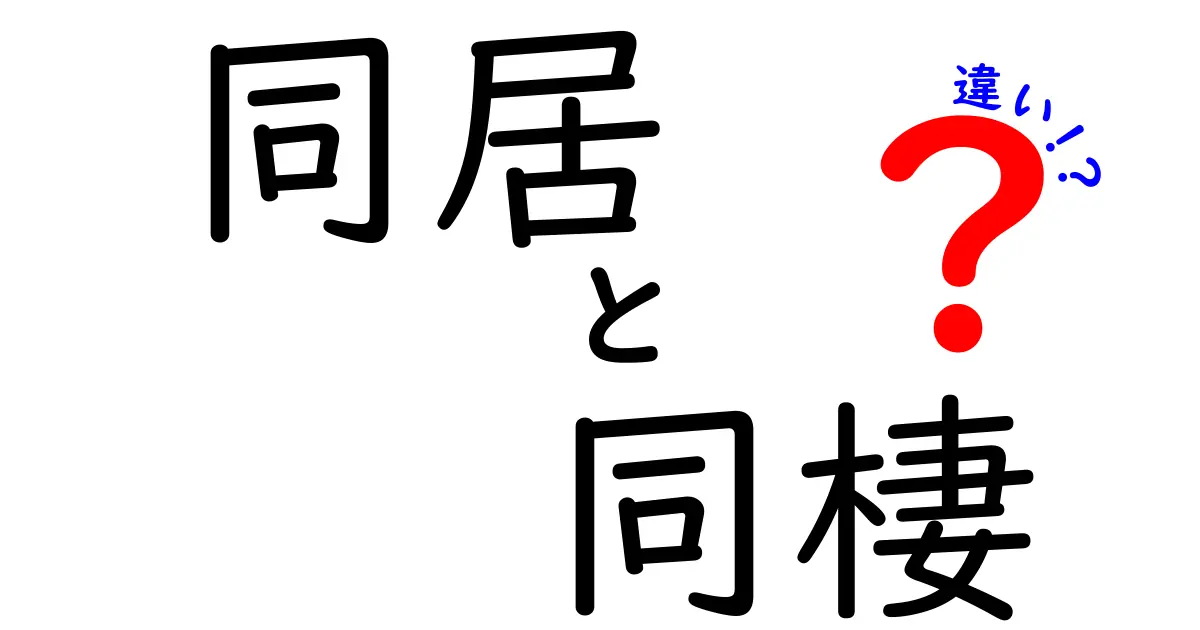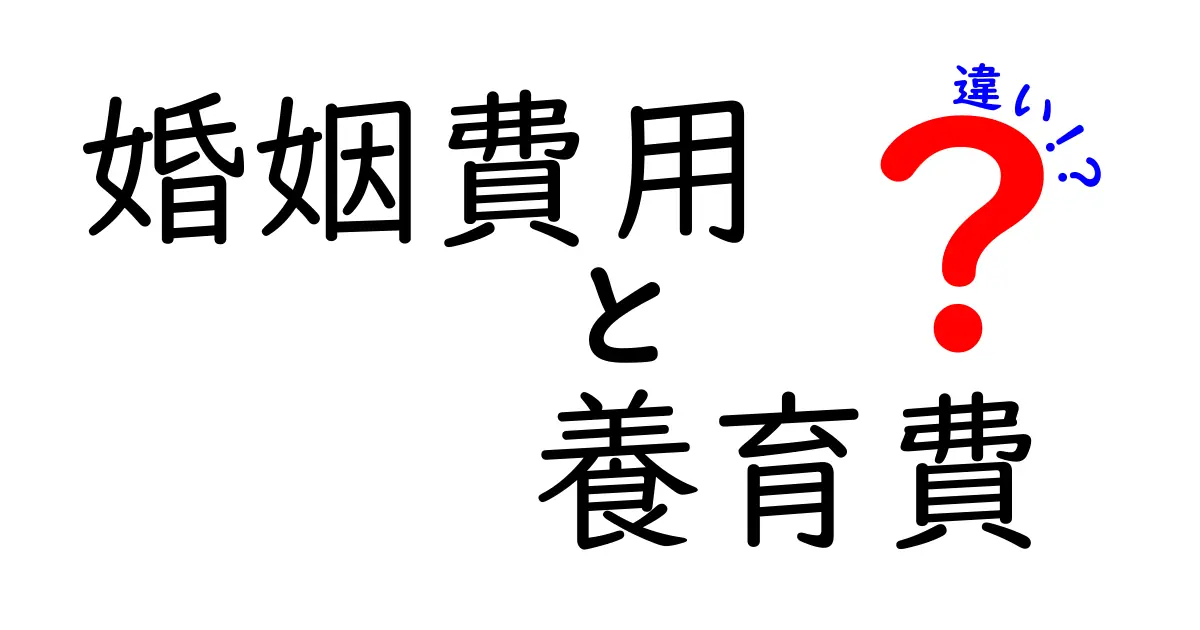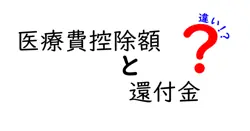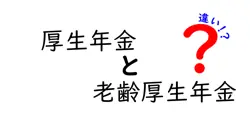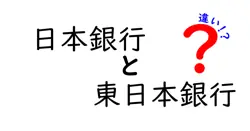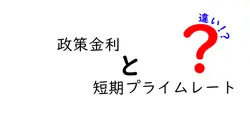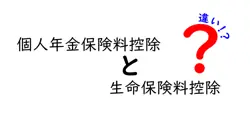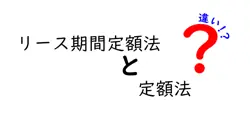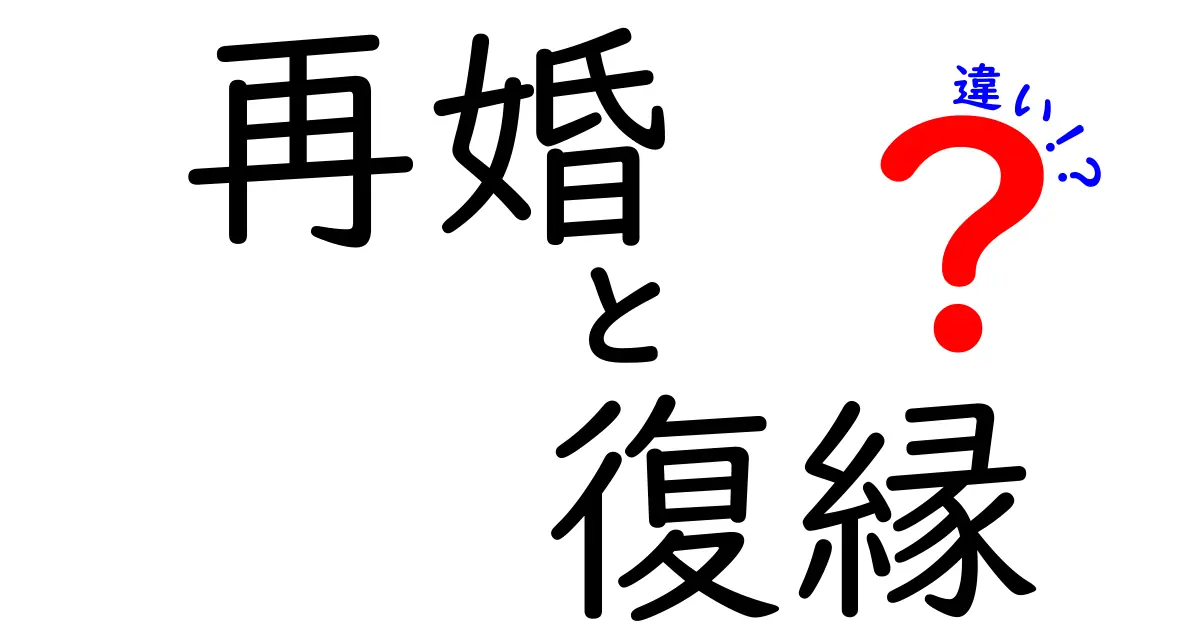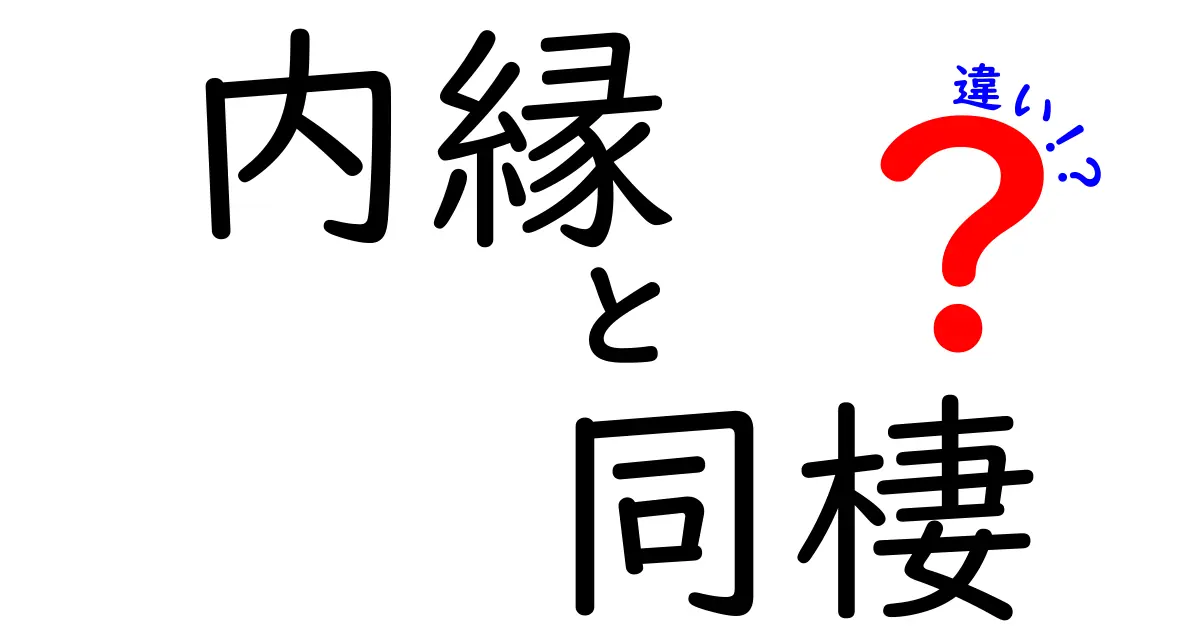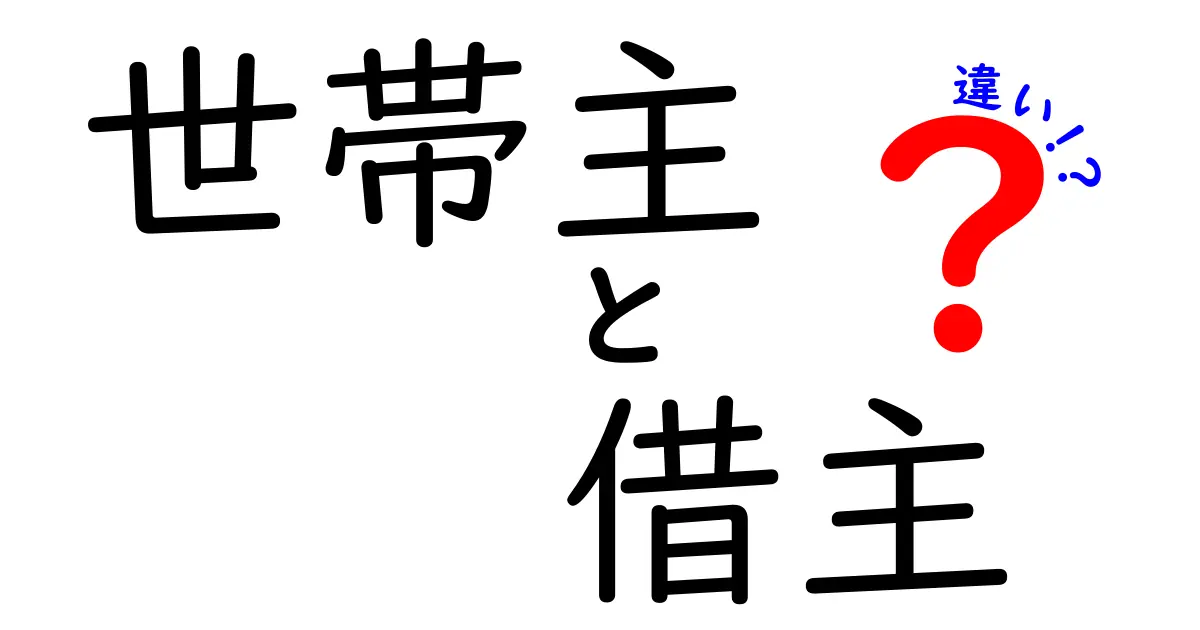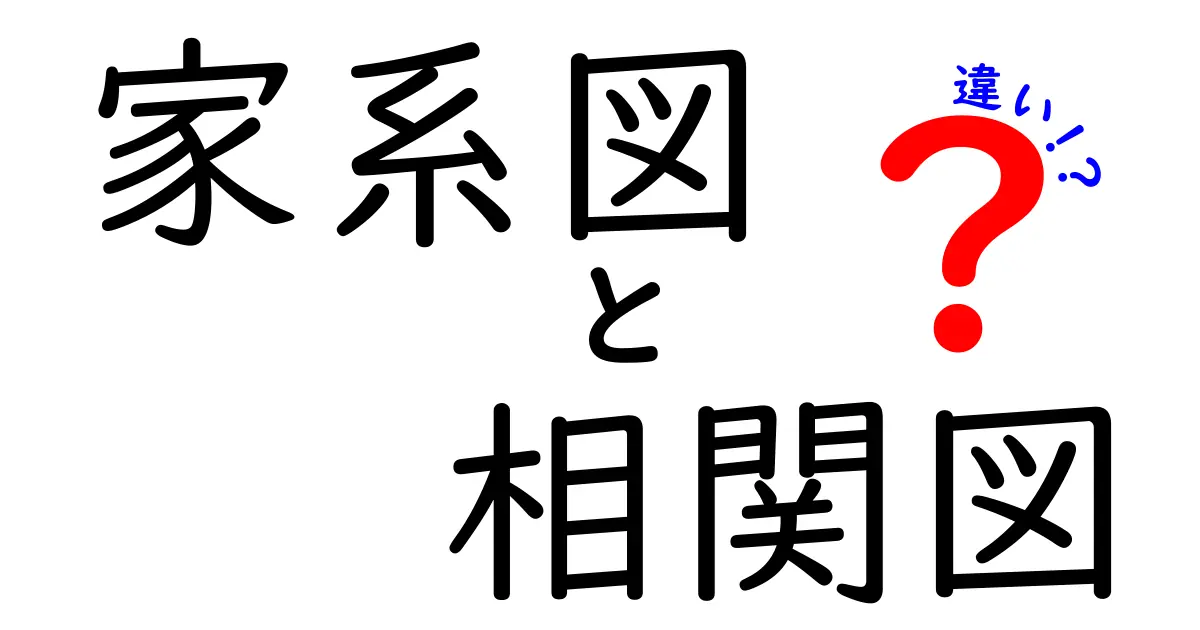
家系図と相関図の基本的な違い
家系図と相関図は、見た目が似ていることもあり、混同されやすいですが、それぞれ目的や使い方がはっきり異なります。家系図は主に家族の血縁関係を表す図であり、代々の親子や兄弟のつながりを示します。
一方、相関図は人間関係や組織内の関係性を示す図で、血縁関係だけでなく、仕事上の関係や友人関係なども含みます。
つまり、家系図は家族や先祖を中心にした系譜の図で、相関図はさまざまな人や物事の関係をわかりやすく示す図です。
家系図の特徴と使い方
家系図は自分のルーツや家族のつながりを知るために作られます。多くの場合、親から子へ年齢順に線や矢印で結び、父母・祖父母・曾祖父母などの世代をわかるようにします。
家系図を作成することで、自分がどんな家族のもとに生まれ、どんな先祖がいるのかがわかってきます。また、歴史的な資料や戸籍を参考にして作ることも多く、家族の歴史を確認・記録する意味もあります。
特にお正月やお盆の家族集まりのときに家系図を見て話すのは、親戚のつながりを強める大切な作業とも言えます。
相関図の特徴と使い方
相関図は、ドラマや小説の登場人物関係図としてよく見かけます。物語の中で誰が誰とどんな関係でつながっているかをわかりやすく伝えるために使われます。
また、企業の組織図やプロジェクトでの担当者間の関係を示したり、社会問題で関係する組織や人物のつながりを説明したりする用途もあります。
家系図より広範囲で血縁以外の友情、敵対関係、協力関係などあらゆる人間関係を網羅可能です。
相関図は関係性の複雑さや相互作用を簡単に伝えるための便利なツールと言えます。
家系図と相関図の違いを表にまとめると?
| ポイント | 家系図 | 相関図 |
|---|---|---|
| 目的 | 家族の血縁関係を示す | 人的・組織的関係全般を示す |
| 対象 | 親子、兄弟、祖先など家族のみ | 血縁以外も含めたあらゆる関係 |
| 使われる場面 | 家族歴の確認・記録 | ドラマ、会社組織、社会分析など多用途 |
| 関係線のタイプ | 親子・血縁中心 | 友情、敵対、協力関係など多様 |
| 項目 | 養子 | 猶子 |
| 法律上の親子関係 | 成立する(養子縁組が必要) | 成立しない |
| 戸籍への記載 | 養子として記載される | 記載されない |
| 相続権 | 実子と同等の権利がある | 基本的にない |
| 扶養義務 | 養親に扶養義務がある | 扶養される関係だが法的拘束力は弱い |
| 手続き | 家庭裁判所などでの手続きが必要 | 手続きは特にないことが多い |
まとめと注意点
以上のように、猶子と養子は見た目や呼び方だけでなく、法的な意味合いが大きく異なります。
現代では、特に相続や親子関係の明確化が重要なため、法律的にも認められた養子縁組を選ぶケースが多いです。
ただし、猶子は家族として大切にされる場合も多く、歴史的・文化的背景も理解しておくと役立ちます。
家族形態や事情に合わせて適切な形を選び、法律や手続きについて専門家に相談することもおすすめします。
「猶子」という言葉は馴染みが薄いかもしれませんが、昔はよく使われていました。特に江戸時代や大正時代の資料を見ると、猶子は正式な養子縁組ではないけれど、家族の一員として大切に扱われていました。現在は法律的な効力が弱いためあまり使われませんが、歴史や文化の中での位置づけを知ると、現代の養子縁組制度の大切さや仕組みがよりよく理解できます。猶子とは「法的な親子ではないけれど、家族として認められた存在」と考えるとわかりやすいですね。
次の記事: 家系図と相関図の違いとは?簡単解説でわかりやすく理解しよう! »