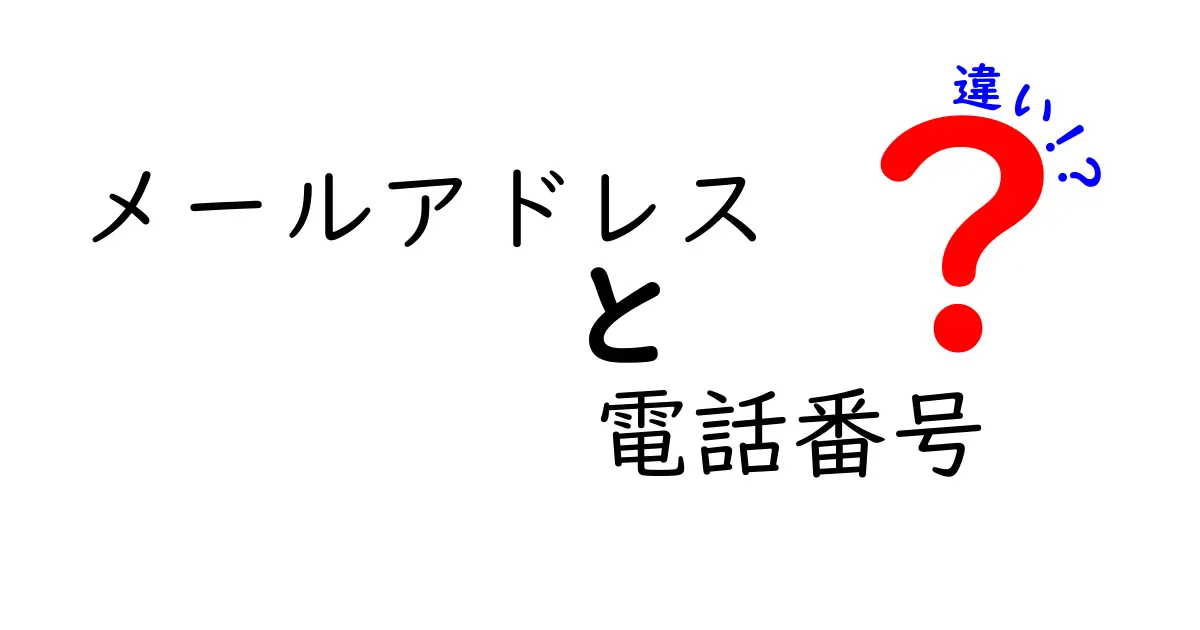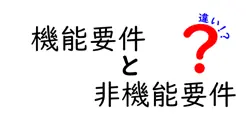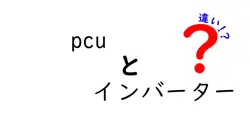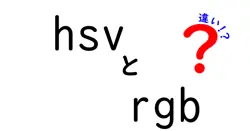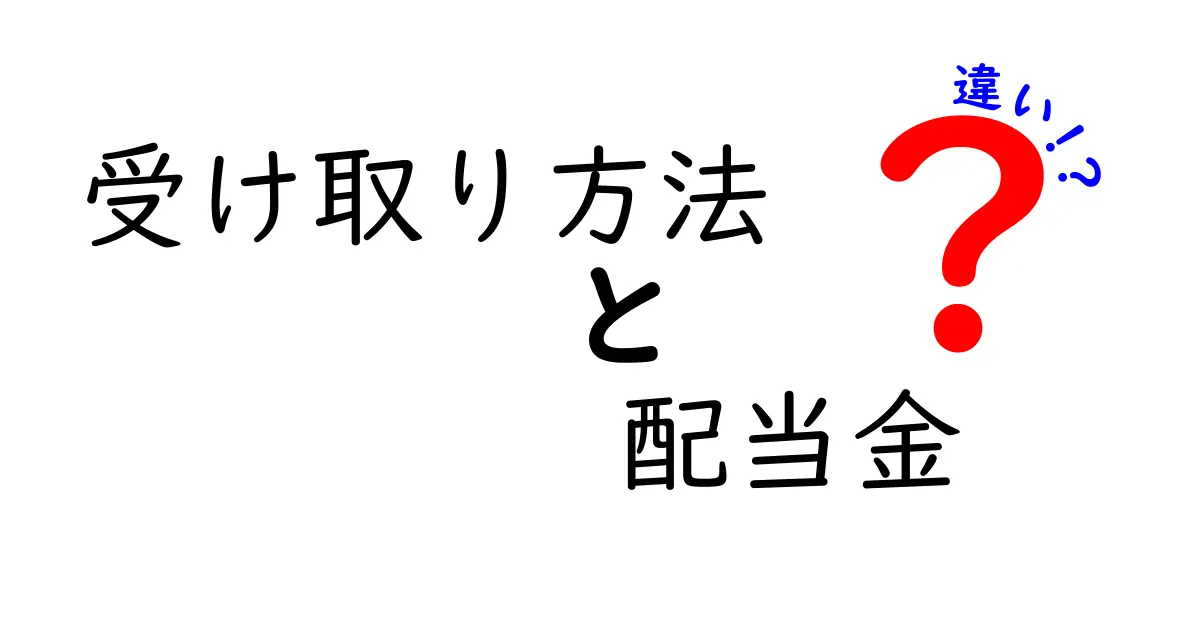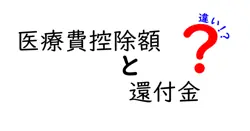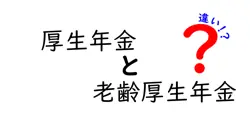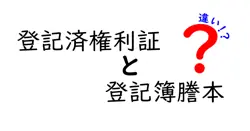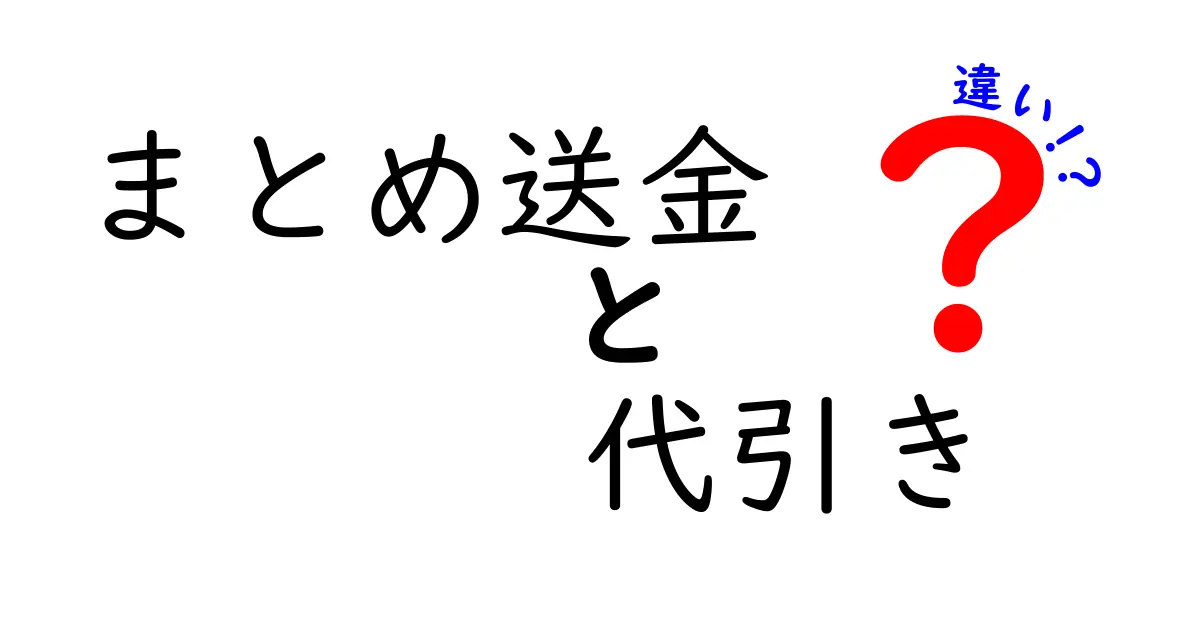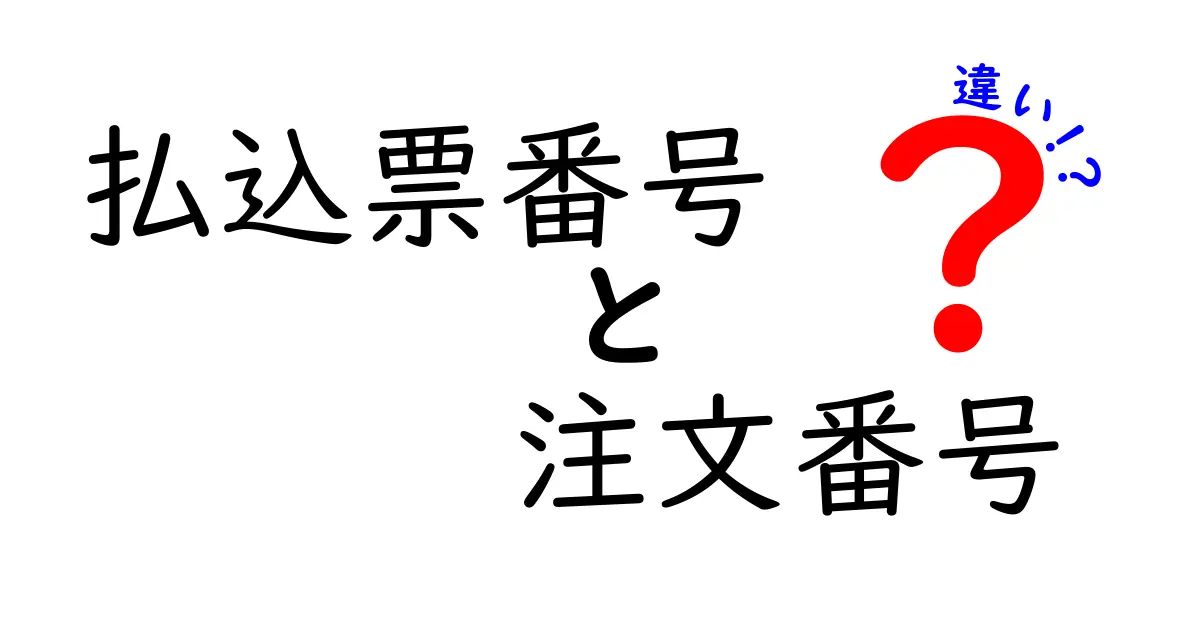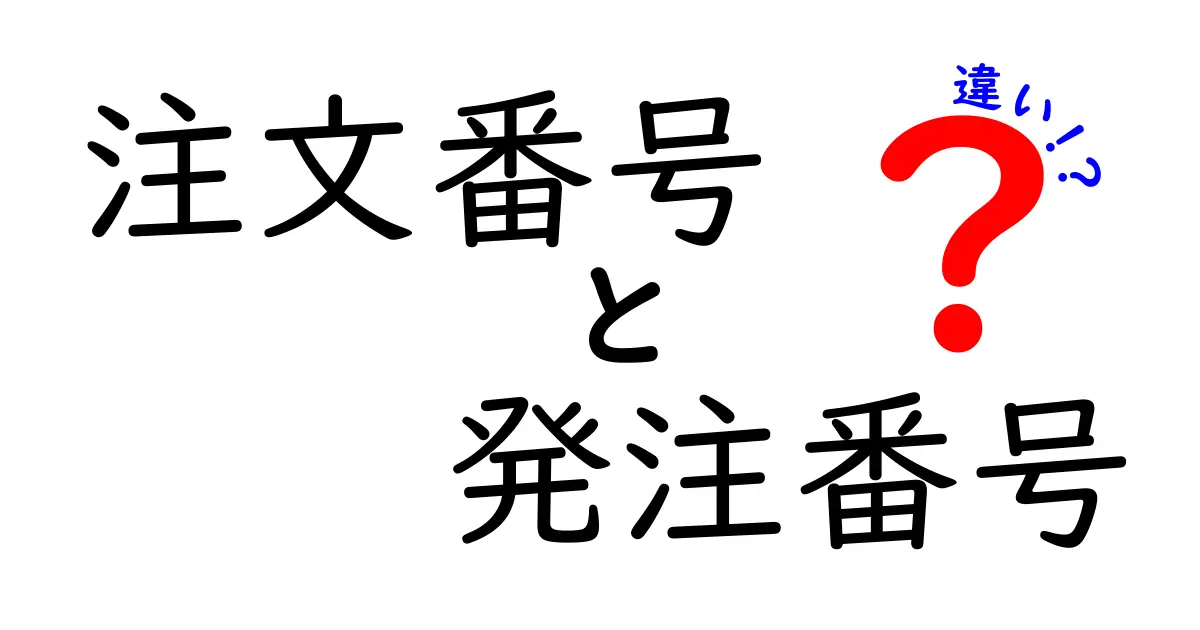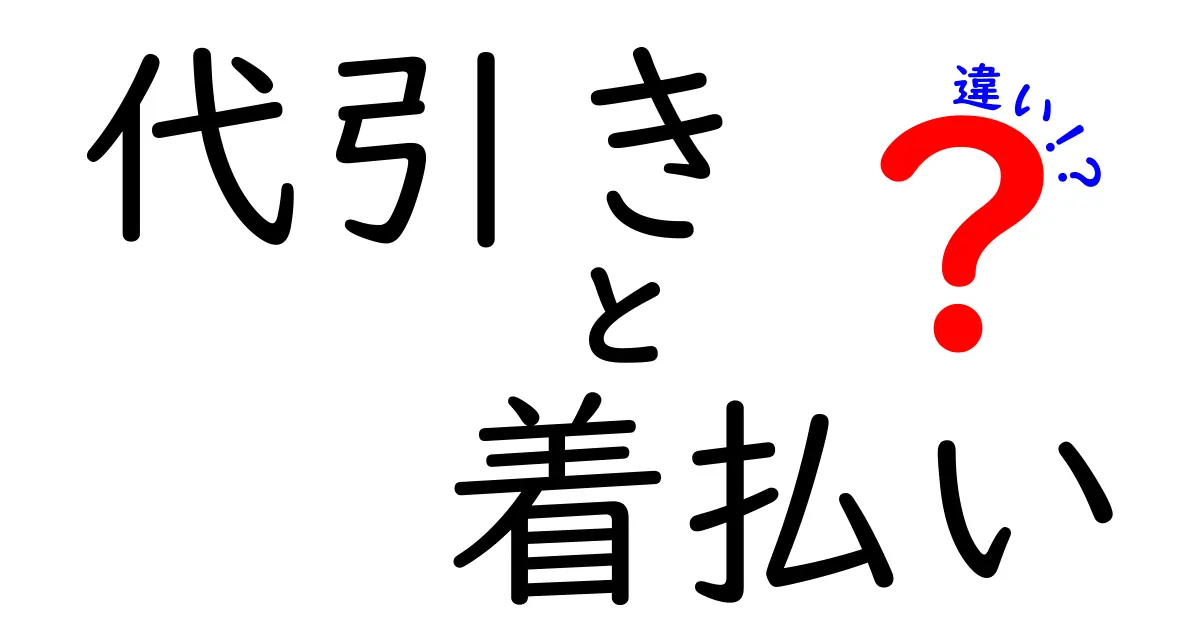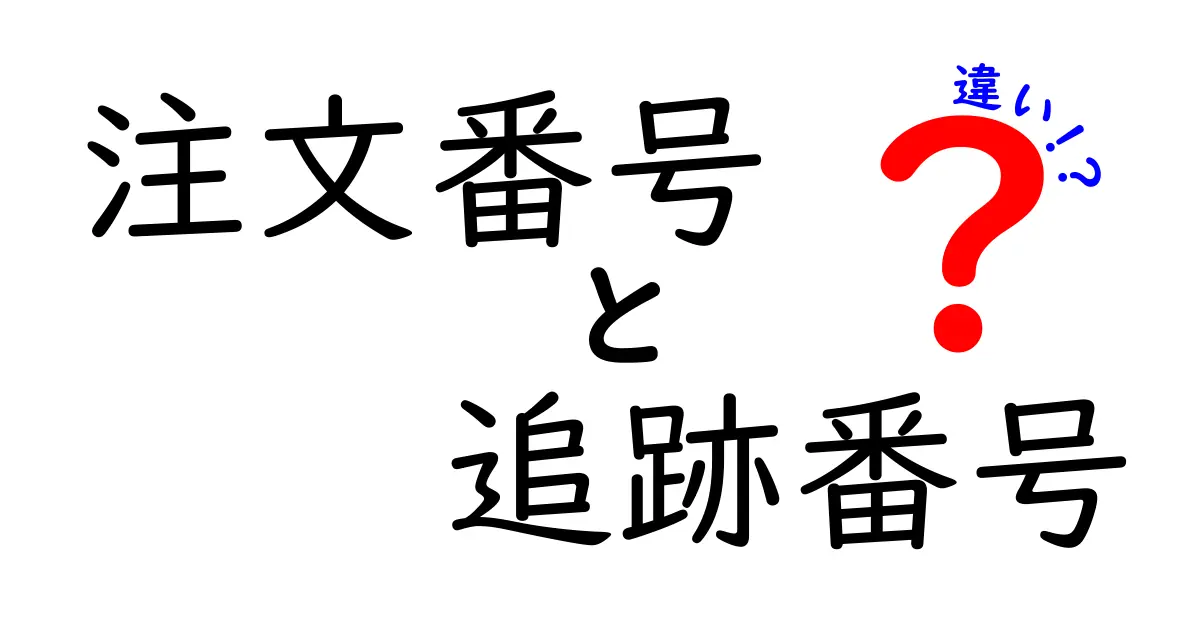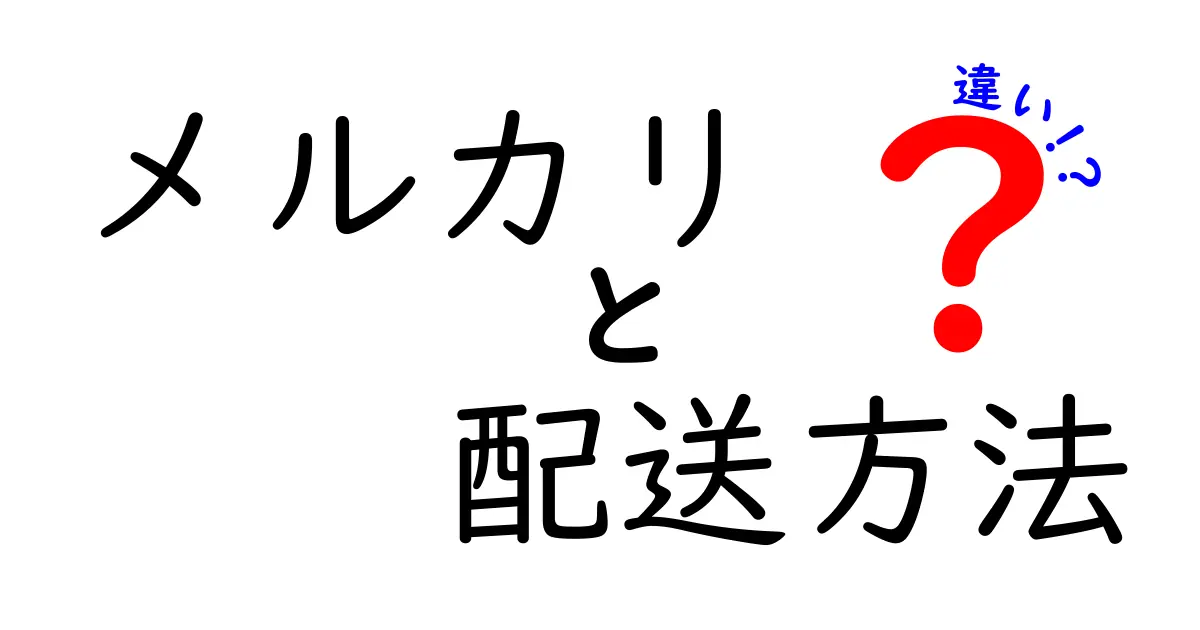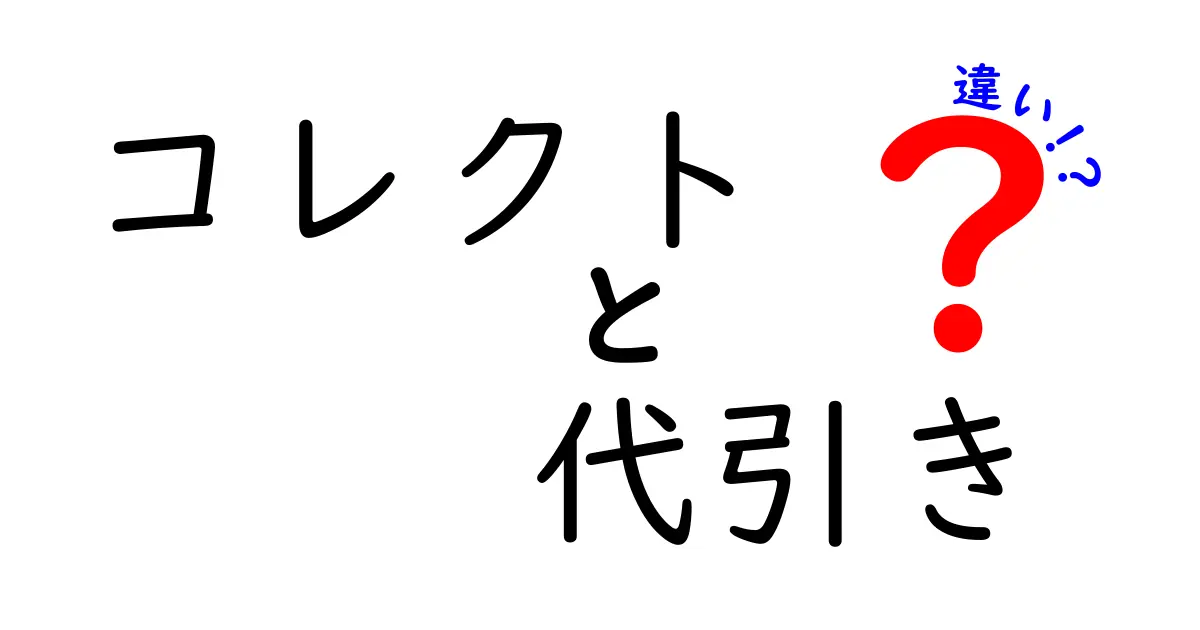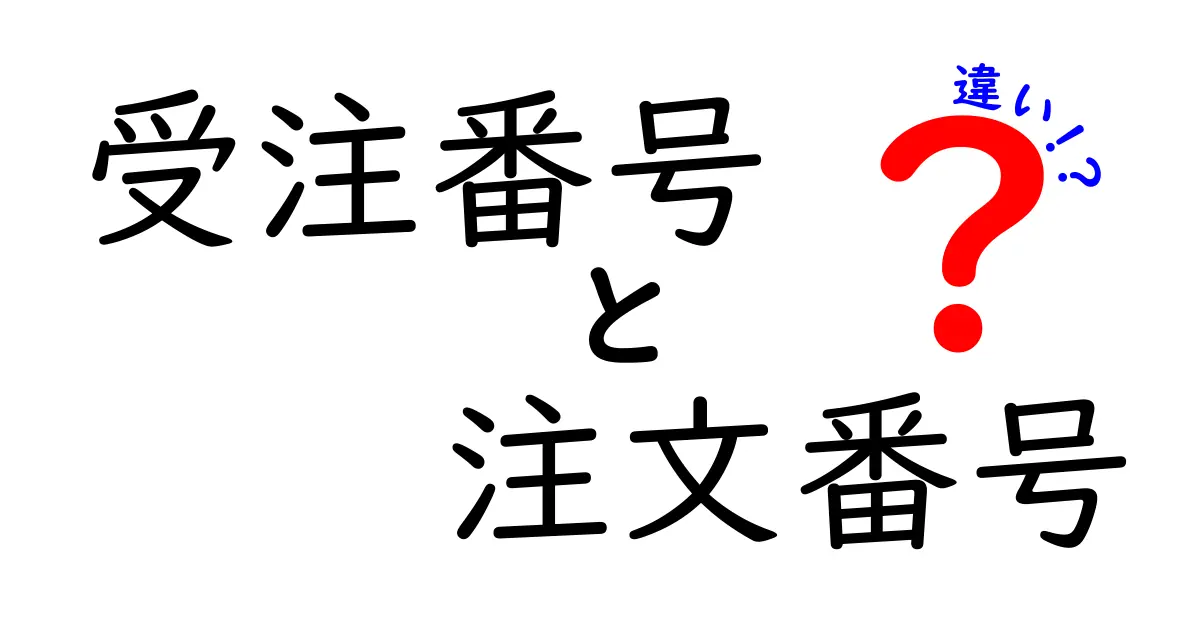配当金の受け取り方法とは?基本を理解しよう
配当金とは、株式を持っている人に会社が出す利益の一部のことです。
配当金の受け取り方法にはいくつか種類がありますが、代表的なのは「現金受け取り」と「株式受け取り」の2つです。
現金受け取りは、そのままお金として銀行口座に振り込まれる方法。
一方、株式受け取りは、その配当金分に相当する株をもらう方法です。
どちらの方法を選ぶかで、資産の増え方や税金の扱いも変わってくるので違いを理解しておくと役立ちます。
受け取り方法ごとのメリットとデメリット
現金受け取りのメリット
すぐに現金を手に入れられるので、自由に使えます。
例えば日々の生活費に使ったり、ほかの投資に回したりできます。
現金受け取りのデメリット
受け取った配当金には税金がかかり、その後の複利効果が弱くなる場合があります。
株式受け取りのメリット
配当金を現金にせず株に替えると、株数が増えて、将来の配当金も多くなる可能性があります。
長く持つことで資産を増やす戦略として効果的です。
株式受け取りのデメリット
現金ではないため、すぐに使えません。また、株価が下がると資産価値が減るリスクもあります。
このように、受け取り方法によってリスクとリターンのバランスが変わります。
受け取り方法の違いを表で比較
ding="5">| 受け取り方法 | メリット | デメリット |
|---|
| 現金受け取り | すぐに現金を得られる
使い道が自由 | 税金負担がそのまま
複利効果が薄れることも |
| 株式受け取り | 株数増加で将来の配当増加
長期投資に有利 | 現金化できない
株価下落リスクあり |
able>
まとめ:あなたに合った受け取り方法を選ぼう
配当金の受け取り方法は「現金受け取り」と「株式受け取り」それぞれに特徴があります。
すぐにお金が必要であれば現金受け取りが向いていますし、資産をコツコツ増やしたいなら株式受け取りが適しています。
自分の生活スタイルや投資の目的に合わせて、賢く選択しましょう。
ぜひこの記事を参考に、配当金の受け取り方法の違いを理解して、より良い投資ライフを送りましょう!
ピックアップ解説「株式受け取り」という方法に注目すると面白いことがあります。実は、この方法は配当金をそのままお金で受け取るのではなく、新しい株をもらうことです。こうすると、持っている株の数が増えるので、次の配当金がもっと多くなる可能性があるんです。まるで小さな雪だるまを転がして大きくしていくイメージですね。ただし、株価が下がるリスクもあるので注意も必要です。この仕組みをうまく使うと、長い目で見て資産を増やせるかもしれません。面白いですよね!
金融の人気記事

377viws

270viws

216viws

215viws

195viws

193viws

176viws

171viws

170viws

167viws

161viws

161viws

147viws

144viws

120viws
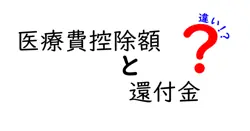
117viws

105viws
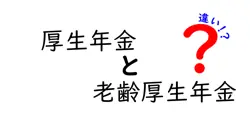
104viws

104viws
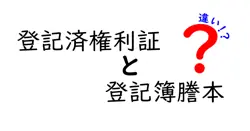
103viws
新着記事
金融の関連記事
まとめ送金と代引きの基本的な違いについて
通販やビジネスでお金のやり取りをするとき、「まとめ送金」と「代引き」という方法があります。
まとめ送金とは、複数の支払いをひとつにまとめて後日一括で送金する方法です。たとえば、月末に1ヶ月分の請求をまとめて支払う場合などに利用されます。
一方、代引き(代金引換)は、商品が届いたときに配送業者に直接お金を支払う方法です。
この2つは支払いのタイミングや方法が大きく違うため、知っておくと注文や支払い時のトラブルを防げます。
「まとめ送金」と「代引き」のメリット・デメリット比較
両者の特徴をわかりやすくするために、メリットとデメリットを整理しましょう。
まとめ送金のメリット
- 支払いが一度で済むので事務処理が楽
- 複数回の請求をまとめて効率的に支払える
- 銀行振込や口座振替で安全に支払い可能
まとめ送金のデメリット- 支払いまでタイムラグがあるため、資金繰りの管理が必要
- 相手先が信用できないとトラブルになることも
代引きのメリット- 商品受け取り時に支払うため安心感がある
- クレジットカードを持っていなくても利用可能
代引きのデメリット- 手数料がかかる場合が多い
- 宅配での現金支払いは紛失やトラブルのリスクもある
- 商品を受け取らないと支払いが発生しない
まとめ送金と代引きの利用シーンと注意点
それぞれの支払い方法は使う場面によって向き不向きがあります。
まとめ送金は、企業間取引や定期的なサービス利用でよく使われます。クレジットカードや銀行振込などでまとめて支払うので、信用関係がしっかりしている場合に向いています。
ただし、支払いが後になるため、お金の管理をしっかりしないと資金繰りが苦しくなることがあります。
代引きはネット通販など、個人のお客様が初めて利用する際に選ばれやすいです。
配送時に支払うため、安心感がありますが、手数料が必要で高額商品には向いていないことも。
配送トラブルやキャンセル時の処理も事前に確認しておくと安心です。
まとめ送金と代引きの違いをわかりやすくまとめた表
ding="5" cellspacing="0">| 項目 | まとめ送金 | 代引き(代金引換) |
|---|
| 支払いタイミング | 後日一括でまとめて支払う | 商品受け取り時に支払う |
| 主な利用場面 | 企業間取引や定期取引 | ネット通販や個人購入 |
| 支払い方法 | 銀行振込・口座振替など | 現金やクレジットカード(配送業者指定の場合も) |
| メリット | 事務処理が楽で効率的 | 受け取り時に支払うので安心 |
| デメリット | 資金管理が重要になる | 手数料がかかりやすい |
これらの違いを理解して、自分に合った支払い方法を選びましょう。
まとめ送金は会社間の信頼関係があってこそ成り立つ方法ですし、代引きは消費者の安心感を優先した方法です。使い方によっては便利な方法なので、状況に応じて賢く使い分けることが大切です。
ピックアップ解説まとめ送金は、企業が複数の請求をまとめて一度に支払う便利な方法ですが、資金繰りのタイミング管理が重要です。例えば、毎月末に今月の請求をまとめて振り込む場合、支払いが遅れると信用問題にもつながることがあります。一方で代引きは、商品を受け取るときその場で支払うので、お金が手元にないときは利用できませんね。このように支払いのタイミングが違うことで、相手との信頼関係やお金の管理方法が大きく変わることがわかると面白いですよ。
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事
払込票番号とは?その意味と役割を詳しく解説
払込票番号とは、主に銀行やコンビニで支払いをする際に使われる番号です。払込票番号は、支払いを特定の請求や取引に結びつけるための番号で、支払いが正しく処理されたかどうかを確認するために利用されます。
例えば、通販で商品代金を支払うときや公共料金の払込みで、この番号が記載された払込票(紙や電子メールの指示書)を使います。この番号があれば、支払先は誰がいつ、どの請求に対して支払ったのかをスムーズに確認できます。
また、払込票番号は一枚の払込票ごとに異なり、支払う側も受け取る側も支払いの履歴を管理しやすくなります。
つまり、払込票番号は支払い行為を追跡するための番号と覚えるとわかりやすいでしょう。
注文番号とは?通販やサービスで使われる理由と意味
注文番号はインターネット通販や店舗で注文をした際に発行される番号です。注文番号は購入手続きを特定し、管理するための識別子です。
例えば、オンラインショッピングで商品を購入したとき、注文番号があれば注文内容の確認や配送状況の追跡、問い合わせがスムーズになります。注文番号は重複しない番号で、1つの注文に対して1つの注文番号が付与されます。
注文番号を使うことで、販売者と購入者の双方が取引情報を正確に把握でき、トラブルを防ぐ役割もあります。
つまり、注文番号は商品やサービスの申し込み情報を特定し、管理する番号といえます。
払込票番号と注文番号の違いとは?わかりやすい比較表つき
ここまでで、それぞれの番号の役割はわかりましたね。ここで両者の違いを表にまとめてみましょう。
ding="5" cellspacing="0">| 項目 | 払込票番号 | 注文番号 |
|---|
| 主な用途 | 支払いの識別および追跡 | 注文の管理および識別 |
| 発行タイミング | 支払票(払込票)発行時 | 注文確定時 |
| 使われる場所 | 銀行・コンビニ等での支払い | 通販サイトや店舗の注文受付 |
| 役割 | 支払処理の特定 | 注文内容の特定 |
| 番号の単位 | 1票ごとに発行 | 1注文ごとに発行 |
なぜ両者を正しく理解することが重要なのか?
払込票番号と注文番号は、似たような数字の羅列ですが、その使い道や意味は異なります。この違いを知らずに混同すると、支払いの確認ができなかったり、注文内容の問い合わせがうまく進まなかったりします。
特にネットショッピングや公共料金の支払いでは、支払いの証拠を残すことはとても大切です。
正確に番号を伝えることでトラブルを未然に防ぎ、迅速に対応してもらえるので、番号の役割を覚えておきましょう。
まとめると、払込票番号は『支払いの確認』のため、注文番号は『注文管理』のために存在する重要な番号です。
ピックアップ解説話題に出た払込票番号ですが、実は、この番号はただの数字の羅列に見えても、支払い確認の要となる大切な情報なんです。
面白いのは、払込票番号は払込票ごとに異なるため、もし忘れてしまうと支払いが正しく処理されたか追跡するのが難しくなることもあるんですよ。
銀行やコンビニで払込票番号を見せるのは、正しい請求へ支払う証拠を示しているわけです。
だから、その番号をきちんと覚えたり控えたりするのは、トラブル回避のための重要なポイントなんです。
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事
注文番号と発注番号は何が違う?基本の理解
ビジネスの場や通販サイトを利用すると、よく「注文番号」や「発注番号」という言葉を目にしますが、この2つは似ているようで役割や意味合いが異なります。今回は中学生にもわかりやすく、注文番号と発注番号の違いについてじっくり解説します。
まず、それぞれの言葉を簡単に説明すると、
- 注文番号:お客さんが商品やサービスを注文した際にお店や会社が管理のためにつける番号
- 発注番号:企業やお店が商品や材料を仕入れる際に仕入先に注文した内容を管理するための番号
つまり、注文番号は消費者側からの注文に対して付けられ、発注番号は企業やお店が業者へ注文する際に使う番号です。
この違いをしっかり理解することで、仕事の流れや各番号の使い道がはっきり分かります。
注文番号と発注番号の具体的な使い方と管理目的
注文番号はよく通販サイトや店舗で商品を注文したときに伝えられます。
例えば、ネットショッピングで何かを購入したら、注文確認メールに「注文番号12345」と記載されていますよね。この番号はお客様がどの注文かを識別するため、お店が管理するためのものです。
一方、発注番号は企業の調達担当者が使います。お店や会社が商品を販売するために、メーカーや卸売業者に対して「商品をこれだけください」と注文するとき、その注文を区別するために発注番号をつけます。
発注番号は社内や取引先で取引内容をスムーズに確認しやすくする目的があります。
具体的には、
- 注文番号は顧客対応の管理
- 発注番号は仕入れ・調達の管理
に使用されるのです。
こうした番号があることで、トラブルを防ぎ、進捗を追跡しやすくなります。
注文番号と発注番号の違いを表で比較!
ding="5" cellspacing="0">| ポイント | 注文番号 | 発注番号 |
|---|
| 使う人 | お客さん(消費者)← お店で管理 | 企業やお店の調達担当者 |
| 目的 | 注文内容の確認や顧客管理 | 仕入先との注文管理や進捗把握 |
| 発行タイミング | 消費者が注文した直後 | 企業が仕入先に注文を出すとき |
| 例 | ネットショッピングの注文番号 | 会社の仕入れ担当者が発注書に記載する番号 |
この表のように、注文番号と発注番号は使う立場や目的が違うため、混同しないことが大切です。
また、会社によっては両者を別々に厳密に管理することはもちろん、システムで一括管理しつつも役割を区別している場合もあります。
まとめ:注文番号と発注番号の違いを正しく理解しよう
注文番号は消費者が商品やサービスを注文したときに発行され、お店側が注文を管理・確認するための番号です。
一方、発注番号はお店や企業が仕入れ業者に対して商品を注文するときに使い、社内外で注文状況の管理・伝達を円滑にするための番号です。
この2つは似ていますが、使われる立場や目的が異なります。混同せずに理解しておくと、ビジネスの流れがスムーズに把握でき、職場でも役に立つでしょう。
今後も通販やビジネスに携わるときは、この違いを思い出してみてくださいね。
ピックアップ解説注文番号についてもう少し面白い話をしましょう。注文番号はただの管理用の数字と思われがちですが、実はその番号を見れば注文した内容や日時、店舗情報などが一目でわかる仕組みになっていることも多いんです。
たとえば、ある通販会社の注文番号は「20240601-12345」のように、最初に注文日を入れ、後ろに連番を付けることで、いつ誰が注文したかを瞬時に把握できるんですね。
こうした工夫があるから、カスタマー対応が迅速になり、トラブル防止にもつながります。番号一つにも企業の工夫や努力が隠れているんですよ。
ちなみに発注番号にも同じような工夫がなされているので、番号の構造を理解すると業務がスムーズに進みます。見た目以上に番号には意味があるんですね!
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事
代引きと着払いって何?基本の違いを知ろう
通販や宅配を利用するとき、よく耳にする言葉に「代引き」と「着払い」があります。どちらも商品を受け取るときの支払い方法に関するものですが、実は意味や支払う人が違います。
簡単に説明すると、代引きは商品代金と送料を受け取り人(買う人)が受取時に支払う方法、
一方、着払いは送料だけを受取時に支払う方法です。
この違いを知らないと、受け取り時に「え、支払いが違う!?」と戸惑ってしまうかもしれません。
ここからは、それぞれの特徴や支払いタイミング、利用シーンの違いについて詳しく解説していきます。
代引き(代金引換)の特徴やメリット・デメリット
代引きは正式には「代金引換」と呼ばれ、通販などでよく使われる支払い方法です。
商品が届いた時に購入者がその場で商品代金と送料・手数料を配達員に支払います。
メリットとしては
- 商品を見てからお金を払える安心感がある
- クレジットカードがなくても支払いができる
- 配達時にまとめて支払えるのでわかりやすい
デメリットは- 送料以外に代引き手数料がかかることが多い
- 高額な商品だと一度に大きな現金を用意しなければならない
- 配達時に受取人がいないと再配達になりやすい
着払いの特徴やメリット・デメリット
着払いは配送料金を荷物を受け取る人が支払う方法です。
商品代金は送り主(販売者など)が支払っていて、受取人は配送料だけを払います。
例えば無料サンプルやプレゼントで商品代は0円の場合もあり、そのときは送料のみの負担になります。
メリットとしては
- 受取人は商品代金を払わず送料だけ負担で済む場合がある
- 発送者側は代金回収のリスクを減らせる
デメリットは- 送料が高い場合、受取人に負担がかかる
- 無料のつもりが後で送料請求になるケースもある
- 受取拒否や放置が起きやすい
代引きと着払いの違いをわかりやすく比較した表
ding="8" cellspacing="0">| ポイント | 代引き | 着払い |
|---|
| 支払いタイミング | 受け取るときに購入者が支払い | 送料を受取人が支払い、商品代金は送り主負担 |
| 支払い内容 | 商品代金+送料+手数料 | 送料のみ |
| 受取人の負担 | 商品代金も支払う負担がある | 送料だけの負担 |
| 利用場面 | 一般的な通販や近年は購入者に安心感あり | 試供品やプレゼント、代金前払いの品物など |
| 手数料 | 代引き手数料がかかることが多い | 通常は手数料なし(送料は別) |
具体的な使い分けのポイントと注意点
まとめると、代引きは基本的に商品を購入するときに使う支払い方法で、
着払いは主に送料だけ受取人が払うケースに使われます。
通販ショップで商品を届けて代金も回収したい場合は代引きを選び、
無料サンプルやギフトなど商品代が不要な時に送料だけ払ってほしい場合は着払いが便利です。
ただし着払いだと受取人の負担感が強いため、受け取り拒否が起きるリスクがあります。
代引きは手数料が高いことが多いので、場合によっては別の支払い方法を案内することもあります。
また、受取時に支払いが必要なため、どちらも受取人が現金や支払い手段を準備しておく必要がある点も注意しましょう。
以上のポイントを踏まえて、配送時の支払い方法を選んでみてください。
ピックアップ解説代引きの手数料は意外と見落とされがちですが、通常数百円かかることが多いんです。これは宅配業者が現金を扱うリスクや手間をカバーするため。だから代引きを多用すると送料以外に結構なコストが増えちゃいます。最近はクレジットカード決済やコンビニ払いが増えたのも、その手数料を避けるための工夫。購入者としては便利ですが、手数料はしっかり確認しておくのが賢い買い方ですよね!
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事
注文番号と追跡番号の違いとは?
インターネットで買い物をすると、対応する「注文番号」や「追跡番号」という言葉をよく見かけますよね。
注文番号と追跡番号はどちらも購入や配送に関係しますが、その役割や使い方には大きな違いがあります。
このブログでは、その違いをわかりやすく解説していきます。
注文番号とは何か、追跡番号とは何か、そしてそれぞれの目的や使い方まで収めているのでぜひ最後まで読んでみてください。
注文番号とは?
注文番号は、ネットショップや通販で商品を注文したときにお店から発行される番号です。
この番号はあなたの注文を特定するためのもので、レシートや確認メールに必ず記載されています。
お店側からすると、一つ一つの注文を区別しやすくするためのIDのようなものです。
たとえば商品に不備があったり、注文内容を変更したいときに注文番号を伝えるとスムーズに対応してもらえます。
また、オンラインショップのマイページで注文履歴を確認するときにもこの番号が役立ちます。
追跡番号とは?
追跡番号は、商品が発送された後に運送会社から付けられる番号です。
この番号を使うことで、商品が今どこにあるのか、配達状況をネット上で確認できます。
たとえば「佐川急便」や「ヤマト運輸」などの配送業者のサイトで追跡番号を入力すると、配達進行状況や到着予定時間がわかります。
この番号は発送連絡メールに記載されていることが多く、商品を待つ間に安心できるツールの一つです。
注文番号と追跡番号の違いを表でまとめてみた
| 項目 | 注文番号 | 追跡番号 |
|---|
| 発行者 | 通販サイトや販売店 | 運送会社 |
| 発行されるタイミング | 注文完了時 | 商品の発送後 |
| 目的 | 注文内容の管理や確認 | 配送状況の確認 |
| 利用場所 | 販売店のサイトや問い合わせ時 | 運送会社の追跡サイトやアプリ |
| 重要性 | 注文の識別に必須 | 配送状況の把握に必須 |
なぜ違いを理解することが大切なのか?
注文番号と追跡番号は似ているようで全く別の役割を持っています。
これらの違いを正しく理解しておくと、商品に関するトラブル時の問い合わせがスムーズになります。
たとえば「商品が届かない」と問い合わせる場合、まず注文番号を伝えることが基本です。
一方で「商品の配送状況を知りたい」ときは追跡番号を使って自分で確認できます。
このように意味を間違えると、問い合わせ先で対応が遅れたり、混乱が起きることも。
だからこそ、この違いを把握して正しく使い分けることが大事と言えます。
まとめ
今回は注文番号と追跡番号の違いを
- 注文番号は注文を管理するための番号で、お店が発行する。
- 追跡番号は配送状況を確認するための番号で、運送会社が発行する。
- それぞれ使うタイミングや問い合わせ内容が異なる。
というポイントで解説しました。
通販を快適に利用するためには、この2つの番号を混同せず正しく理解しておくことが重要です。
これからネットショッピングを安心して楽しむための参考になれば嬉しいです。ピックアップ解説追跡番号って、ただの番号じゃないんです。実は、配送会社によって形式や意味が微妙に違うんですよ。佐川急便やヤマト運輸では使うコードが違うだけでなく、番号の長さやアルファベットの使われ方も少しずつ違います。こうした細かい違いを知っていると、配送状況の確認がもっとスムーズになります。ネットショッピングが当たり前の今、追跡番号にも注目してみると面白いですよ!
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事
メルカリの配送方法って何が違うの?
メルカリを使って物を売ったり買ったりするとき、配送方法を選ぶ場面があります。
でも「どの配送方法を選べばいいのかわからない」「それぞれの特徴や違いが知りたい」という人は多いはずです。
メルカリにはいくつかの代表的な配送方法があり、それぞれ送料や追跡の有無、保障の内容が違います。
ここではそれらの配送方法の違いをわかりやすく説明します。
主な配送方法の特徴と違い
代表的な配送方法は次のとおりです。
- ネコポス
- らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト・宅急便)
- ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケット・ゆうパック)
- 普通郵便やレターパック、クリックポスト
それぞれの特徴を表でまとめました。able border="1">| 配送方法 | 送料 | 追跡 | 補償 | サイズ制限 |
|---|
| ネコポス(ヤマト運輸) | 195円〜 | あり | 3,000円まで保証 | A4サイズ以内、厚さ2.5cm以内、重さ1kg以内 |
| らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト) | 380円 | あり | 3万円まで保証 | 専用BOXを使用 |
| らくらくメルカリ便(宅急便) | 600円〜 | あり | 3万円まで保証 | サイズ・重さにより変動 |
| ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケット) | 175円〜 | あり | 3,000円まで保証 | 厚さ3cm以内、重さ1kg以内 |
| ゆうゆうメルカリ便(ゆうパック) | 600円〜 | あり | 3万円まで保証 | サイズ・重さにより変動 |
| 普通郵便等 | 最安だが変動 | なし | なし | サイズによる |
ネコポスとらくらくメルカリ便の違い
ネコポスは小さくて軽い物の配送に向いています。料金が安くて追跡可能ですが、補償は3,000円までなので高価な品物には向いていません。
らくらくメルカリ便はヤマト運輸のサービスで、宅急便コンパクトや宅急便を使えます。宅急便コンパクトは専用BOXを使いますが、3万円まで保証がついているので安心です。
どちらもメルカリ便なので送料は出品者負担が多いですが匿名配送で住所を知られずに安心して取引できます。
ゆうゆうメルカリ便との大きな違い
ゆうゆうメルカリ便は日本郵便を使った配送方法です。ゆうパケットやゆうパックがあり、こちらも追跡や補償があります。
ヤマト運輸と違うのは、ゆうゆうメルカリ便はコンビニから発送可能なところ。ファミリーマートやローソンなどから送れます。
また全国展開の郵便局のネットワークを使うため、配達エリアや時間帯の違いが出ることがあります。
どうやって配送方法を選べばいい?おすすめの選び方
配送方法を選ぶときは以下のポイントを考えましょう。
- 商品のサイズや重さ
- 補償の有無と金額
- 送料の安さ
- 匿名配送や追跡の必要性
- 発送しやすい場所
例えば、小さくて軽いアクセサリーならネコポスやゆうパケットが送料も安くておすすめです。
壊れやすい物や少し高価なものはらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトや宅急便にすると、補償も付いていて安心です。
また、自分が近くにあるコンビニを基準にヤマト運輸か日本郵便か選んでも良いでしょう。
匿名配送を使えばお互いの住所がわからず、安心して取引できることも忘れないでください。
まとめ
メルカリで物を送るときには配送方法がいくつかありますが
・料金やサイズ・重さの上限
・追跡や補償の有無
・発送できる場所
が異なります。
商品にあった配送方法を選ぶことで安心で安く送れます。
初めての人でも今回の解説を参考にして、適切な配送方法で気持ちよく取引をしてみてくださいね。
ピックアップ解説「ネコポス」という配送方法、名前を聞くとなんだか猫が運んでくるみたいで可愛いですよね。でも実際はヤマト運輸の小さい荷物用の配送サービスです。特徴はA4サイズまでOKで厚さ2.5cm以内、そして料金がとっても安いこと。軽いものを送りたい時にぴったりなんです。3,000円までの補償も付いてるので、少し安心ですよ。とはいえ高価なものや壊れやすいものには向かないので、使い分けがポイントですね。メルカリでよく使う人は特に覚えておくと便利ですよ!
ビジネスの人気記事

296viws

264viws

228viws

218viws

213viws

212viws

203viws

200viws

191viws

189viws

187viws

180viws

176viws

166viws

158viws

158viws

155viws

155viws

154viws

152viws
新着記事
ビジネスの関連記事