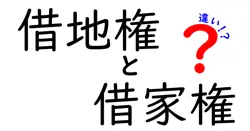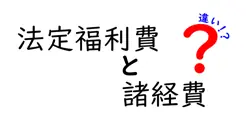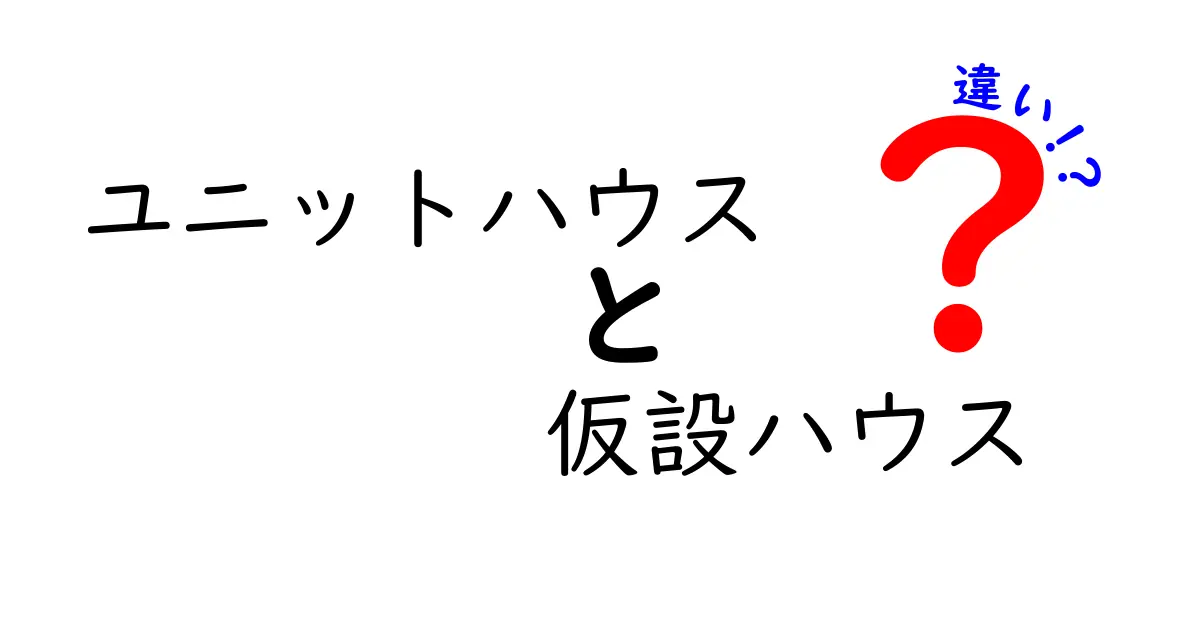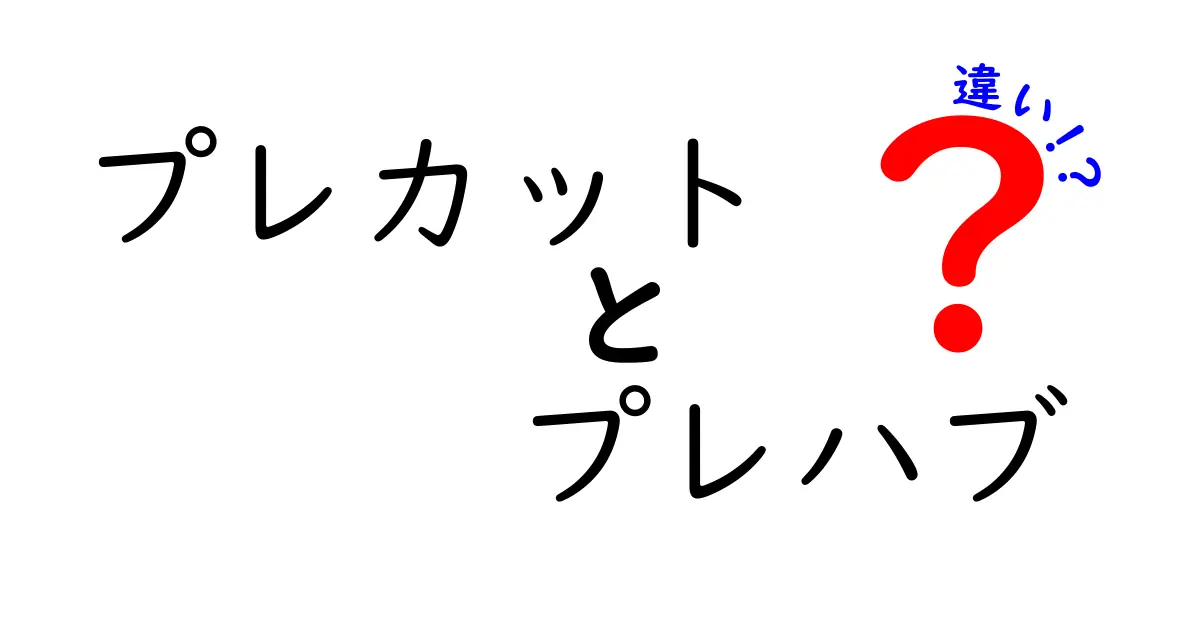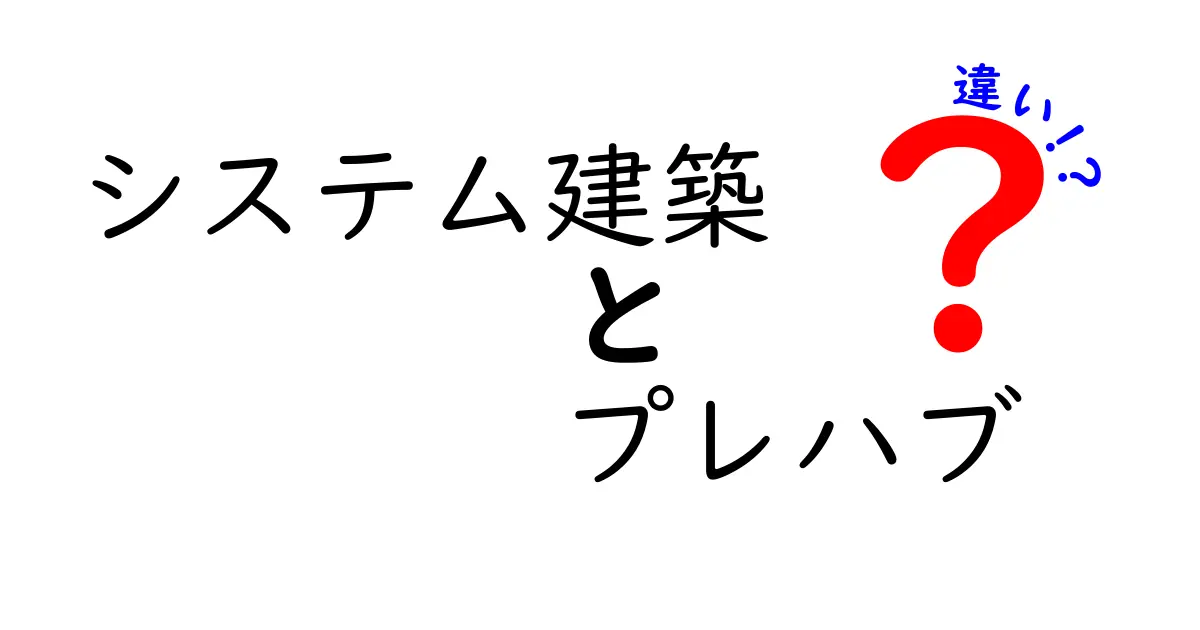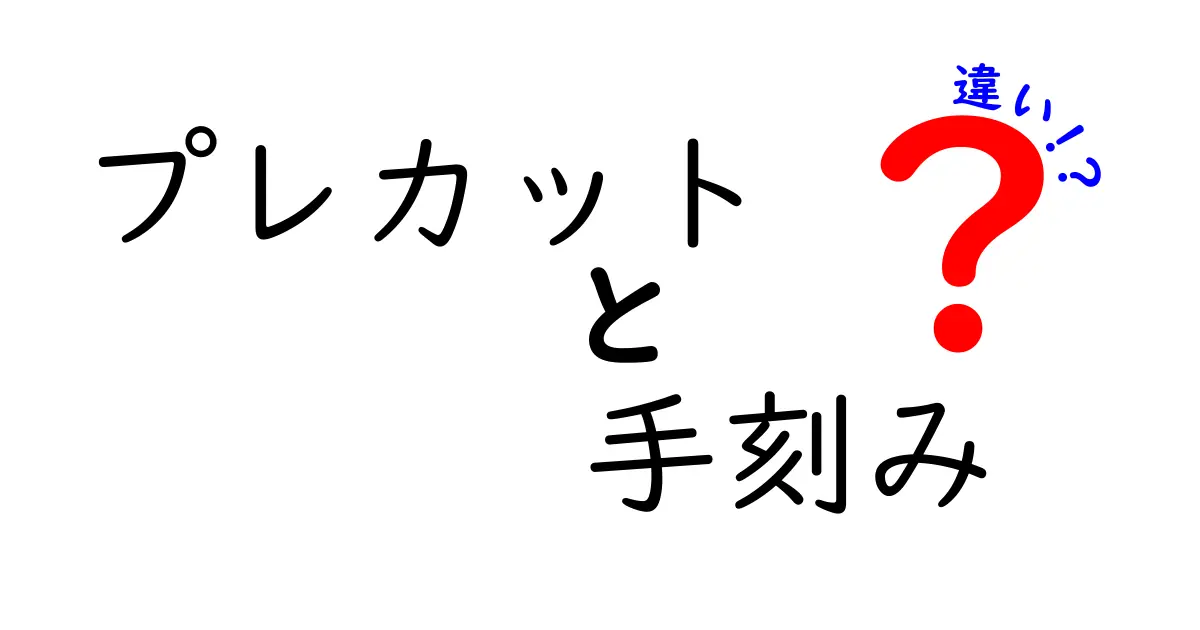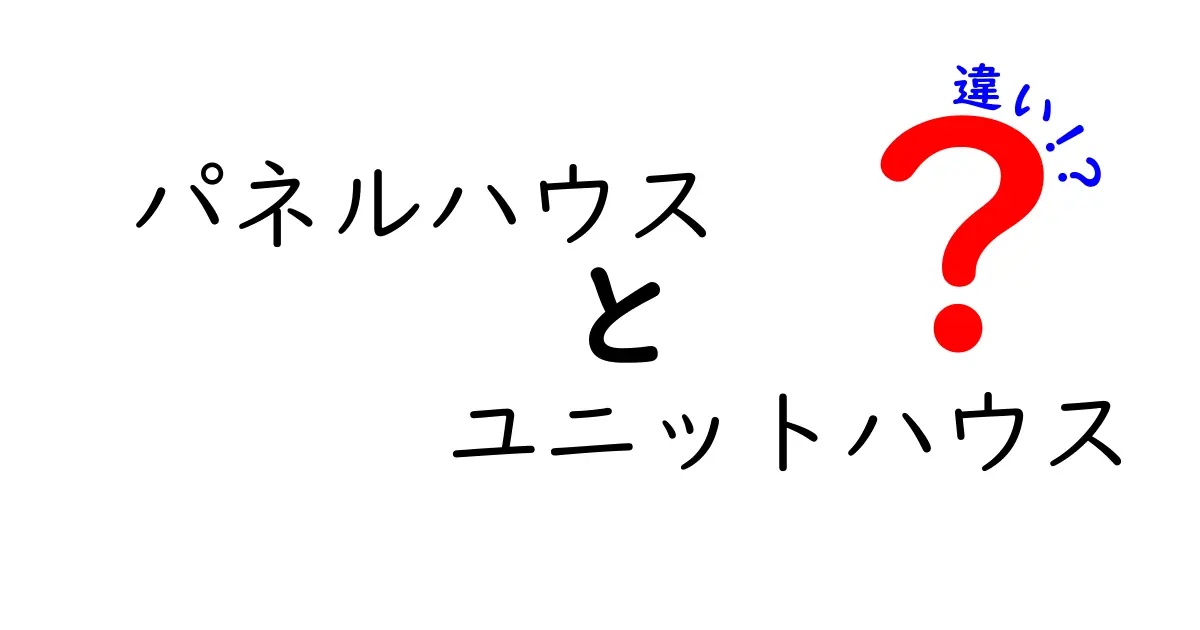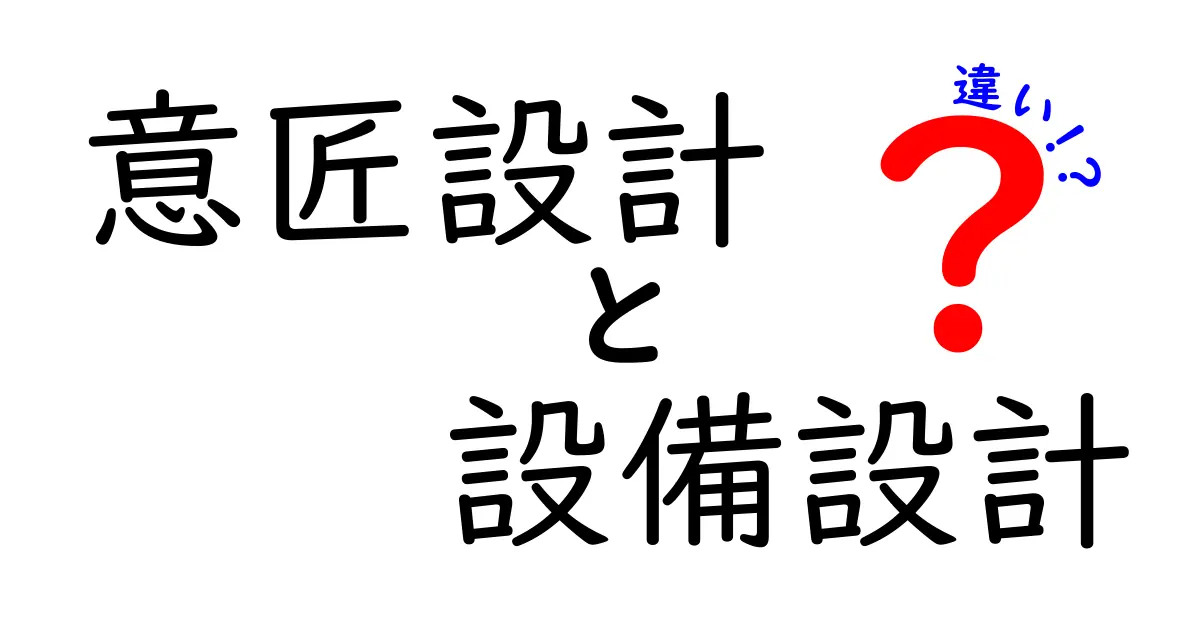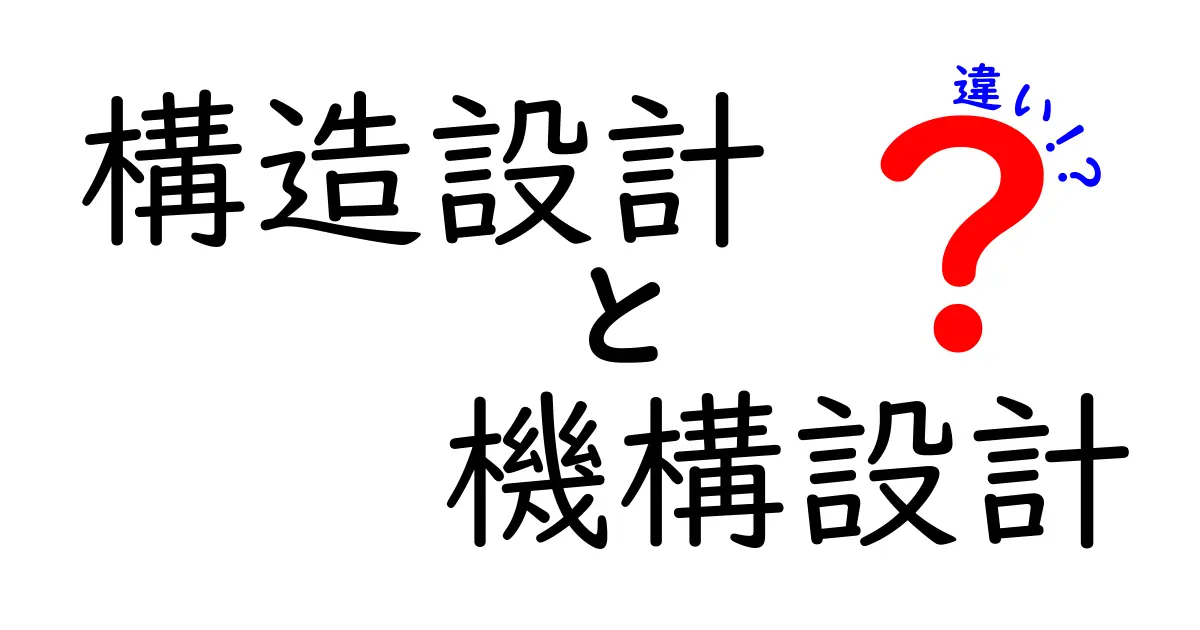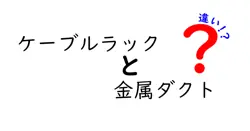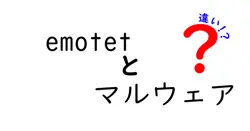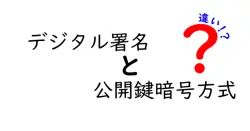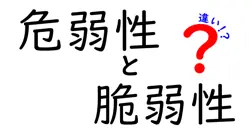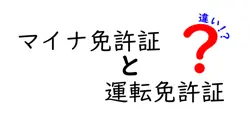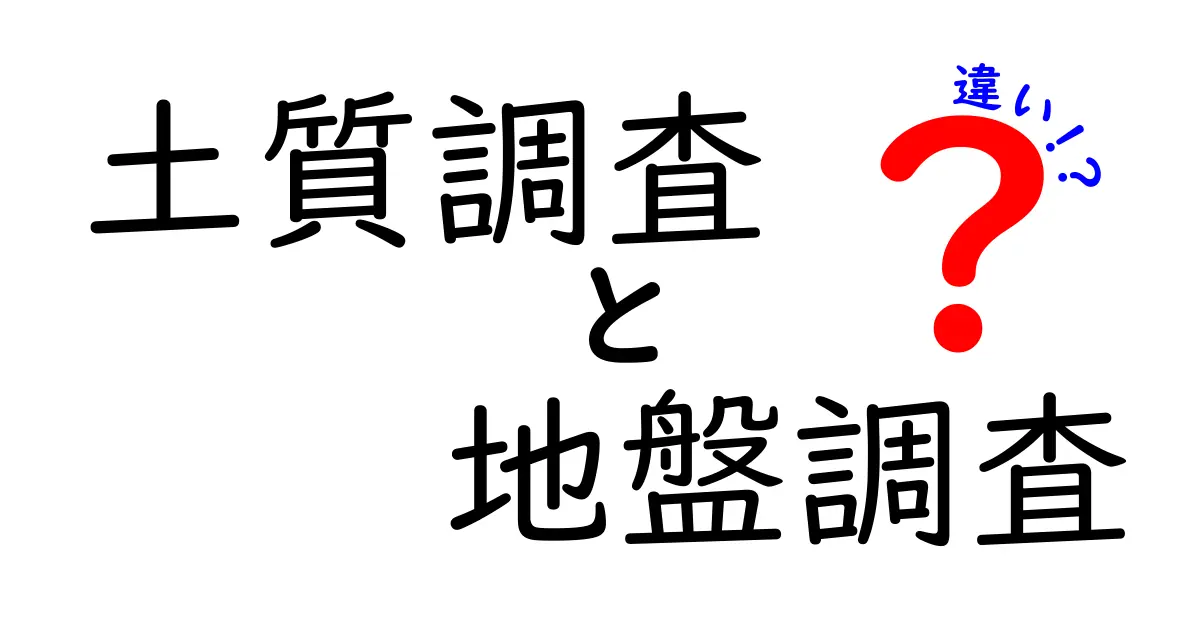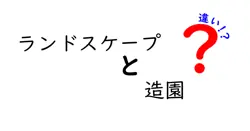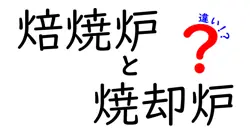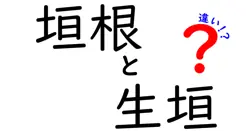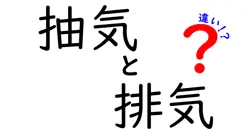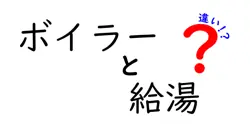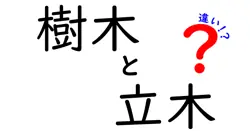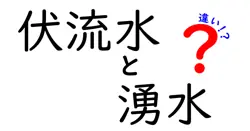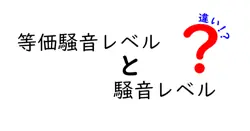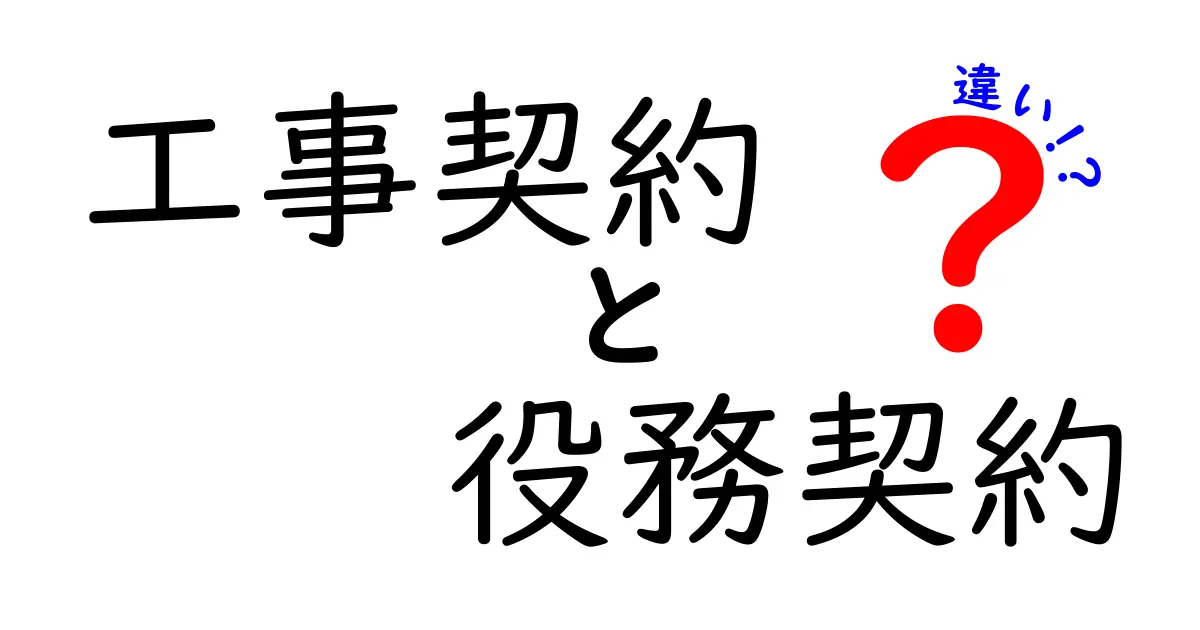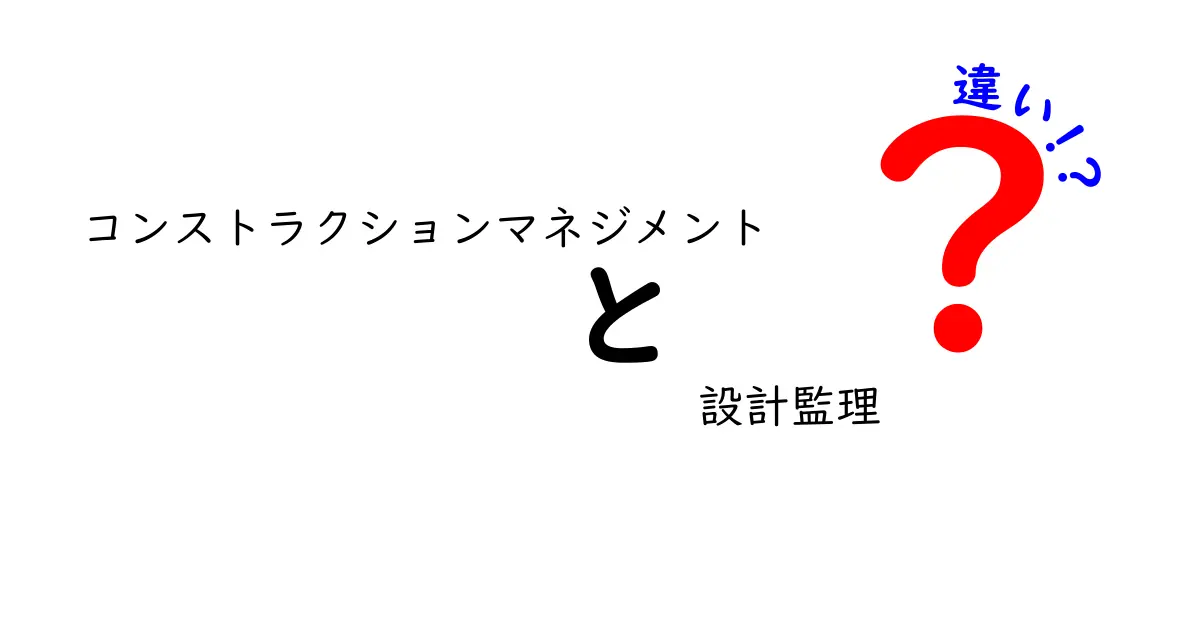
コンストラクションマネジメントと設計監理って何?
建築の世界ではよく「コンストラクションマネジメント(CM)」と「設計監理」という言葉を聞きますが、具体的に何が違うのか分からない人も多いでしょう。
簡単に言うと、これらはどちらも建物を作る上で重要な役割ですが、担当する仕事や責任範囲が異なります。
これから、それぞれの特徴や役割、そして違いについてわかりやすく説明していきます。
コンストラクションマネジメント(CM)の役割
コンストラクションマネジメントとは、建築工事を計画から完成まで全体的に管理することを指します。主な仕事は、工事スケジュールの管理、予算の調整、工事の品質チェックなどです。
建物を作る際には、多くの業者や職人が関わります。CMは、それらの人たちの作業がスムーズに進むように調整し、トラブルを未然に防ぎます。
例えば、工事の予定が遅れていれば迅速に対処したり、予算がオーバーしそうならコストダウン策を考えたりします。
つまり、CMは建物が完成するまでのプロジェクト全体の舵取り役です。
設計監理の役割とは?
一方で設計監理は、主に建築物の設計図に基づいて工事が正しく行われているかをチェックし監督することです。
この役割は通常、建築士や設計事務所の担当者が行います。設計図通りに壁の位置や材料、仕上げなどが実際の工事で守られているかを確認し、不具合があれば指摘します。
設計監理は設計図の意図を現実の建物に忠実に再現するための品質管理とも言えます。
工事担当者が安全で正確に仕事を進められるよう、専門的な視点で助言や指導を行うのが特徴です。
コンストラクションマネジメントと設計監理の違いを比較表で理解しよう
| ポイント | コンストラクションマネジメント | 設計監理 |
|---|---|---|
| 主な担当者 | CM会社や専門マネージャー | 建築士や設計事務所 |
| 仕事の内容 | 工事全体の調整・管理・コスト管理 | 設計図通りの施工チェック・品質管理 |
| 目的 | プロジェクトをスムーズに進める | 設計意図を正しく実現する |
| 関わる時期 | 企画から竣工まで (計画・予算・工事) | 主に工事中の施工段階 |
| 重要な役割 | 全体の問題解決・進捗管理 | 設計の品質保持と施工監督 |
| ユニットハウス | 仮設ハウス | |
| 構造 | 工場生産のプレハブ部材を組み合わせた箱型の建物 | 現地組立式の物、移動式のものなど多様 |
| 設置期間 | 中長期的に使われることが多い | 短期間、臨時で使われることが多い |
| 用途 | 事務所・住居・店舗など幅広い | 工事現場の休憩所・仮住まいなど |
| 耐久性 | 比較的高い | やや簡易的な作りが多い |
| 移動性 | 移動は簡単ではないが解体・再設置可能 | 移動式は簡単に位置変更が可能 |
このようにユニットハウスはしっかりした作りで長期間使うことが多いのに対して、仮設ハウスは短期利用でより 軽量・移動しやすい設計であるケースが多いです。
どう選ぶ?ユニットハウス・仮設ハウスのメリットとデメリット
実際に使う時はそれぞれの利点と欠点を知って選ぶことが大切です。
ユニットハウスのメリットは、工場で規格化された部品を使うため品質が安定していること、耐久性が高くて長期利用に向いていることです。ただし設置費用や解体費用はやや高めになります。
仮設ハウスのメリットは、軽量で簡単に組み立て・解体ができるため、短期間の利用に便利なこと、また移動がしやすいものもあります。その分、長く使うと劣化しやすいデメリットがあります。
こんなふうに使う期間、使い方、費用を考えて選ぶと良いでしょう。
まとめ:ユニットハウスと仮設ハウスの違いを簡単に振り返ろう
最後に、今日のポイントをまとめます。
- ユニットハウスは工場製作のプレハブで耐久性があり、長期間の事務所や住居向けに使われる。
- 仮設ハウスは臨時で現場に設置されることが多く、組み立てや移動が簡単で短期利用に向く。
- 用途や予算、使用期間によってどちらが最適かを選ぶことが大切。
どちらも建設現場やイベント、臨時のオフィスなどで役立つ便利な建物です。違いを知って賢く活用しましょう。
ぜひこの記事を参考にして、ユニットハウスと仮設ハウスの違いを理解し、目的に合った建物選びにお役立てください!
「ユニットハウス」って聞くとなんだか大きくてしっかりした建物のイメージがありますよね。でも実は、工場でパーツを作って現場で組み立てるから、さまざまな場所に対応できるのが便利なんです。
例えばオフィスとして使う場合、工場生産なので断熱性や耐震性がしっかりしていて、長く安心して使えます。逆に持ち運びは簡単ではないですが、解体すれば別の場所にまた設置できるので、計画的な長期利用にぴったりなんです。
ちなみにユニットハウスの名前は、この「ユニット単位の箱を組み合わせる」工法からきています。建物の部品をいくつも組み合わせて形を作るから、とても自由度が高いのも面白いところです。こんな発想ひとつで建て方が変わるのは工夫の楽しさを感じますよね!