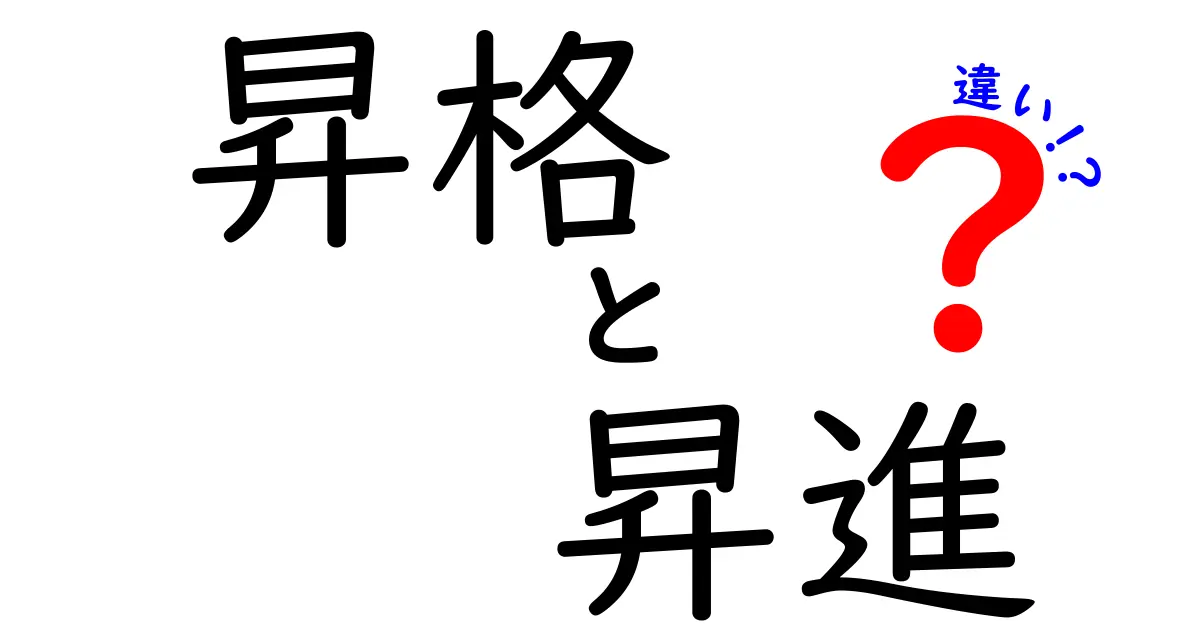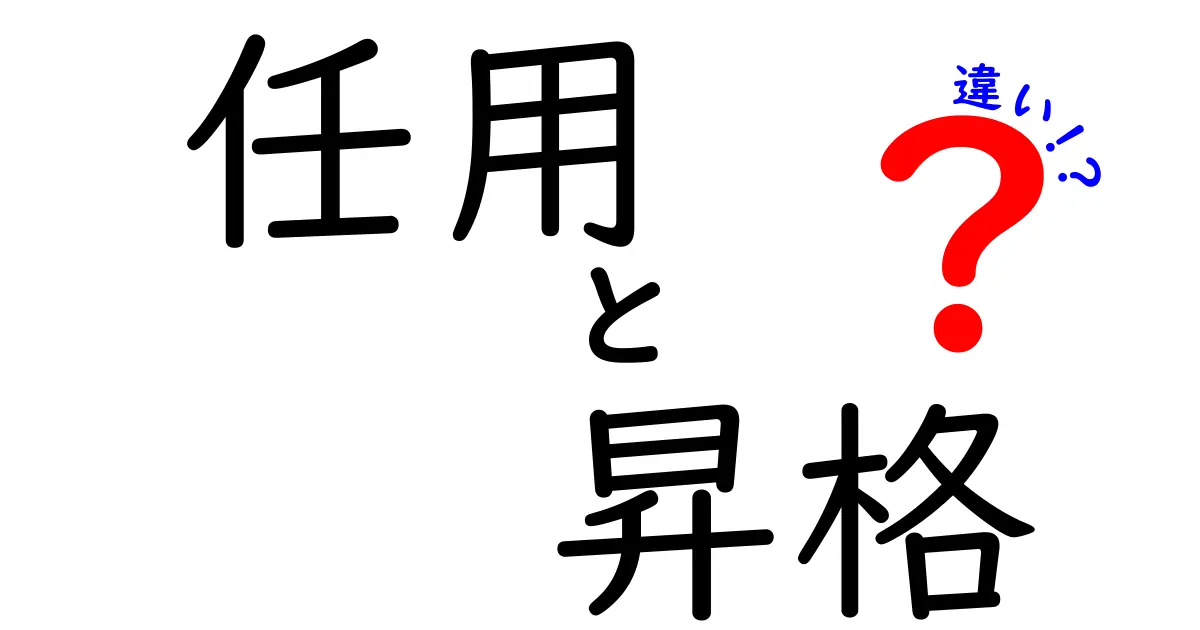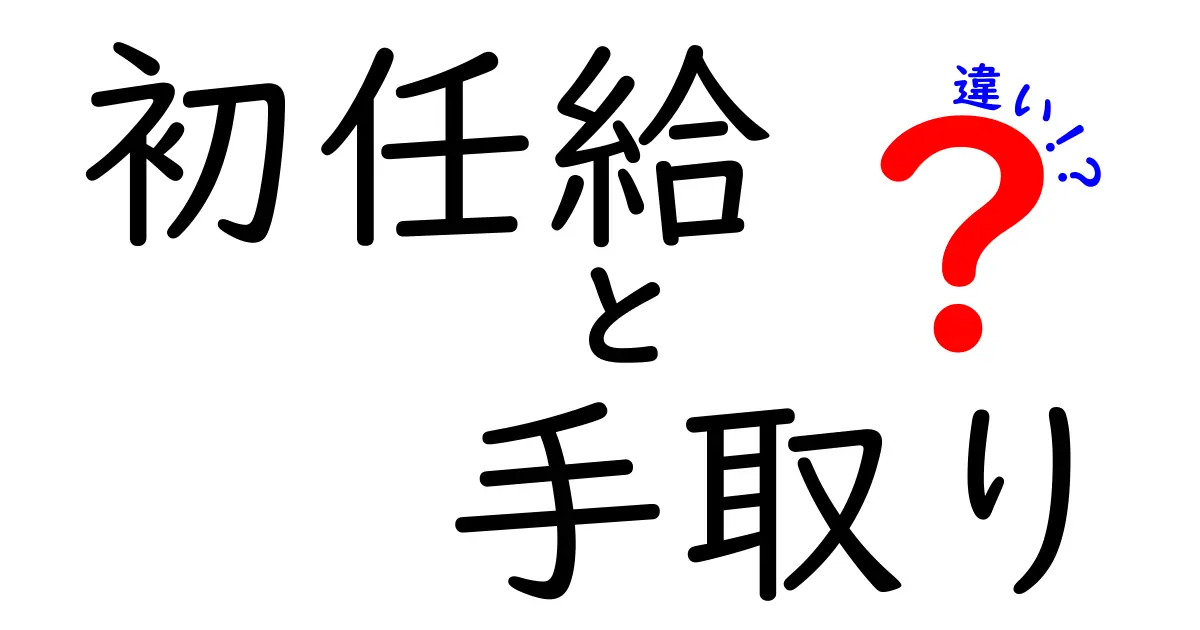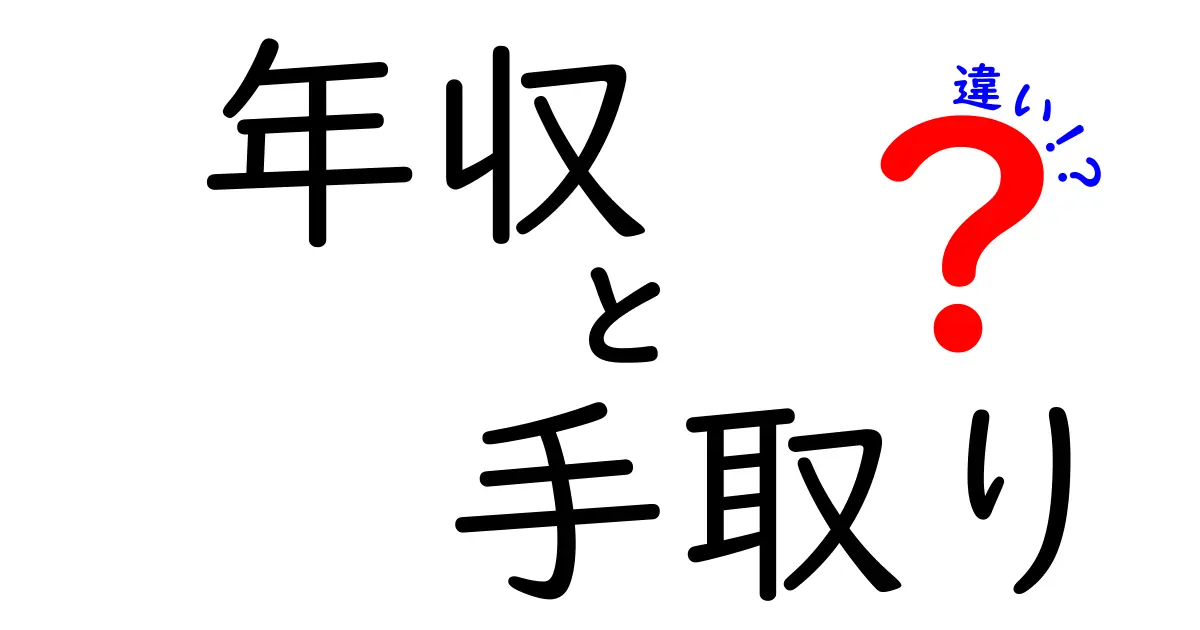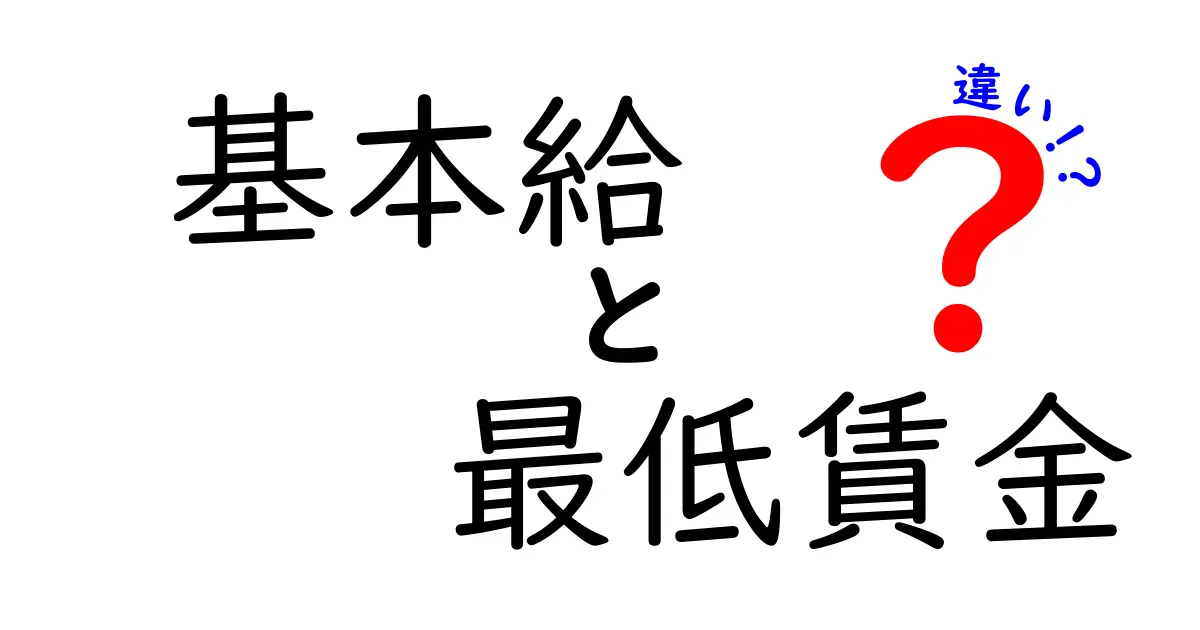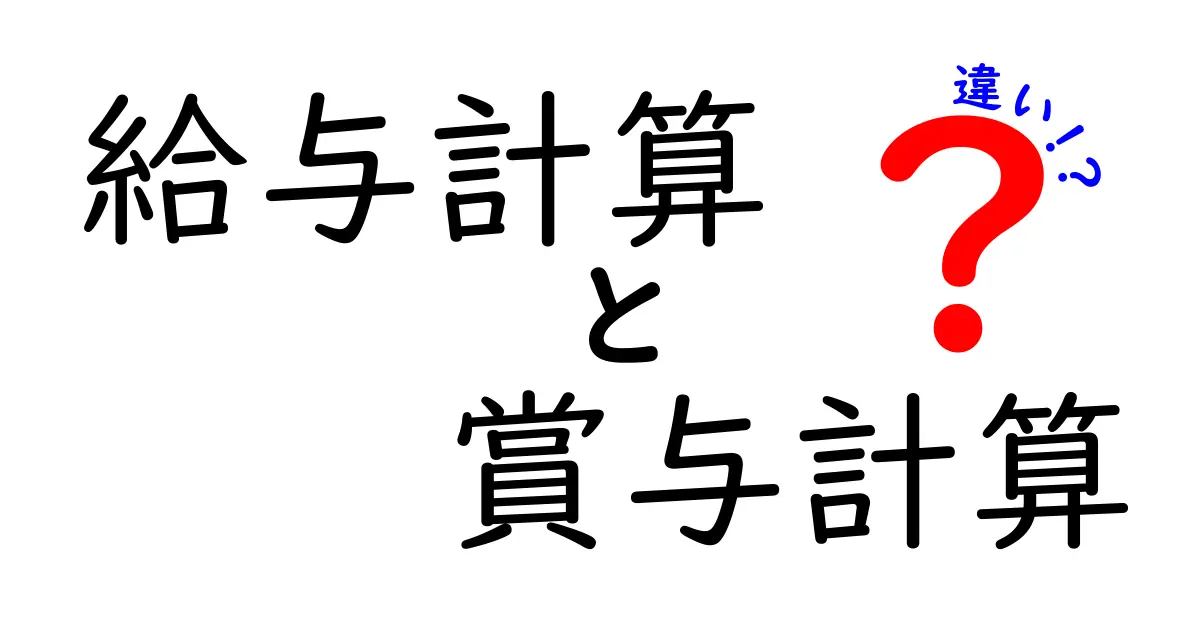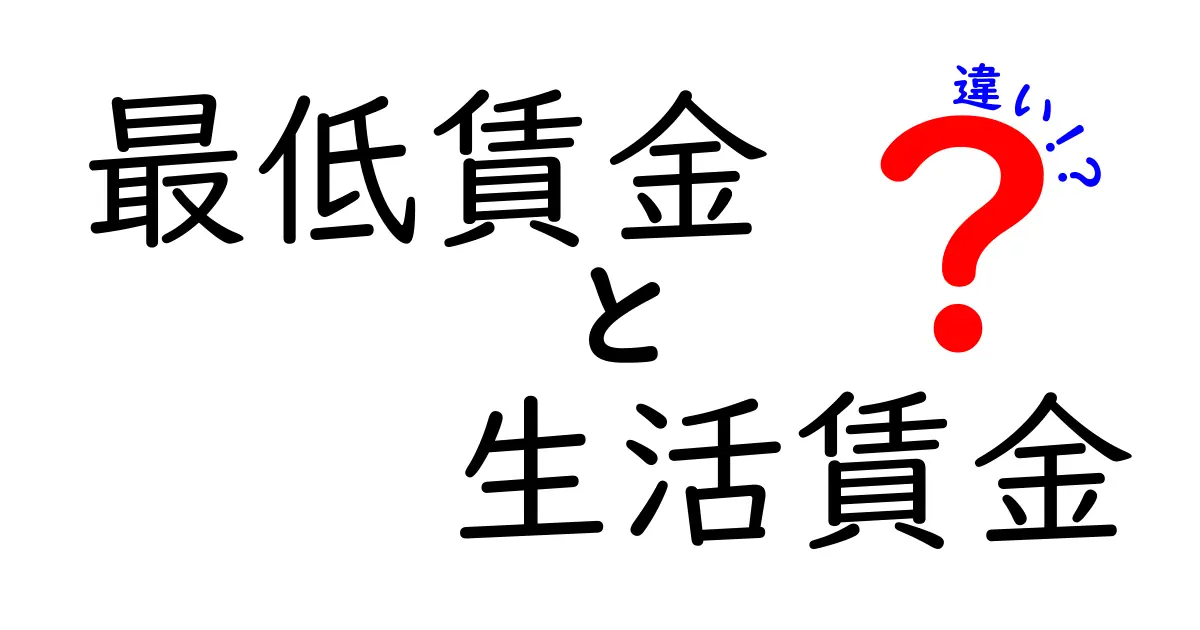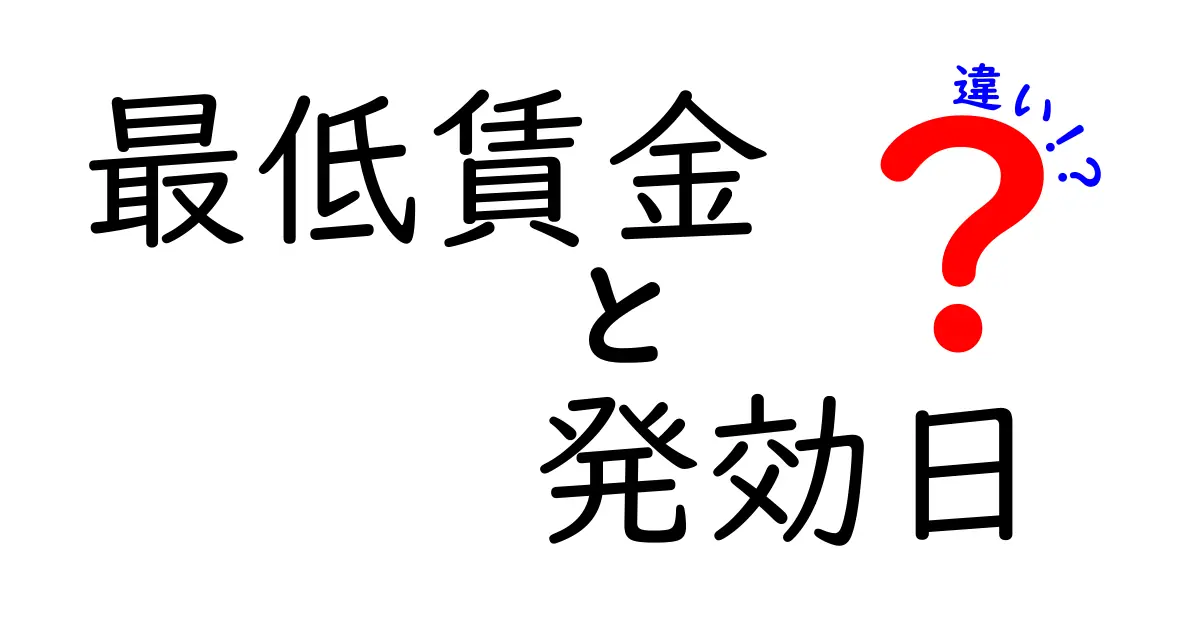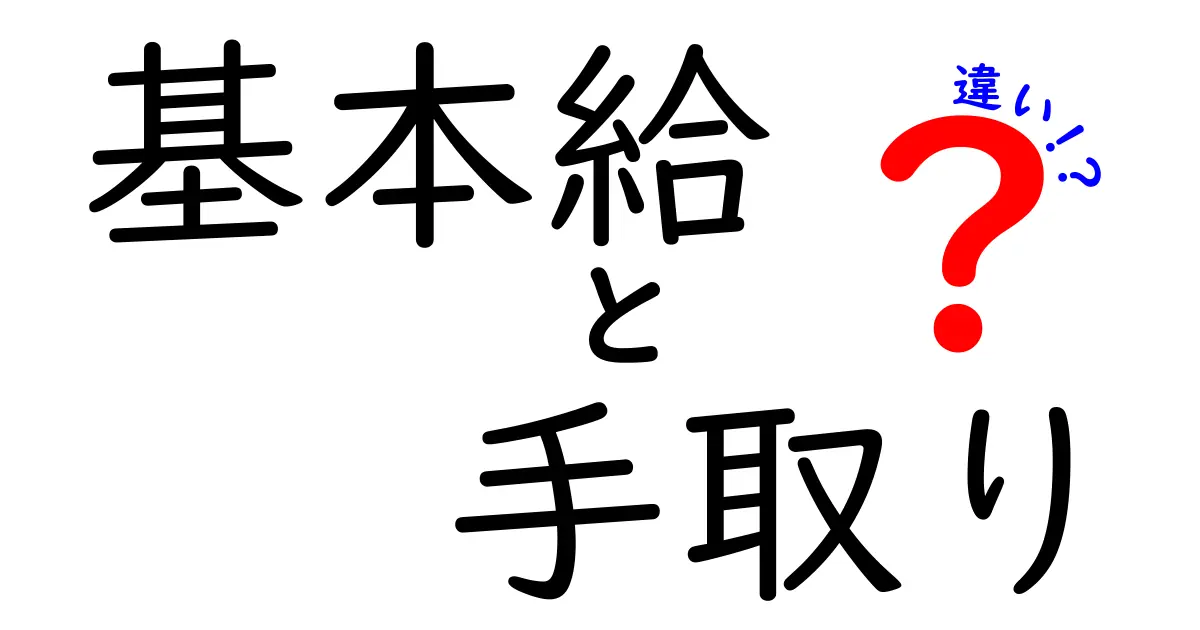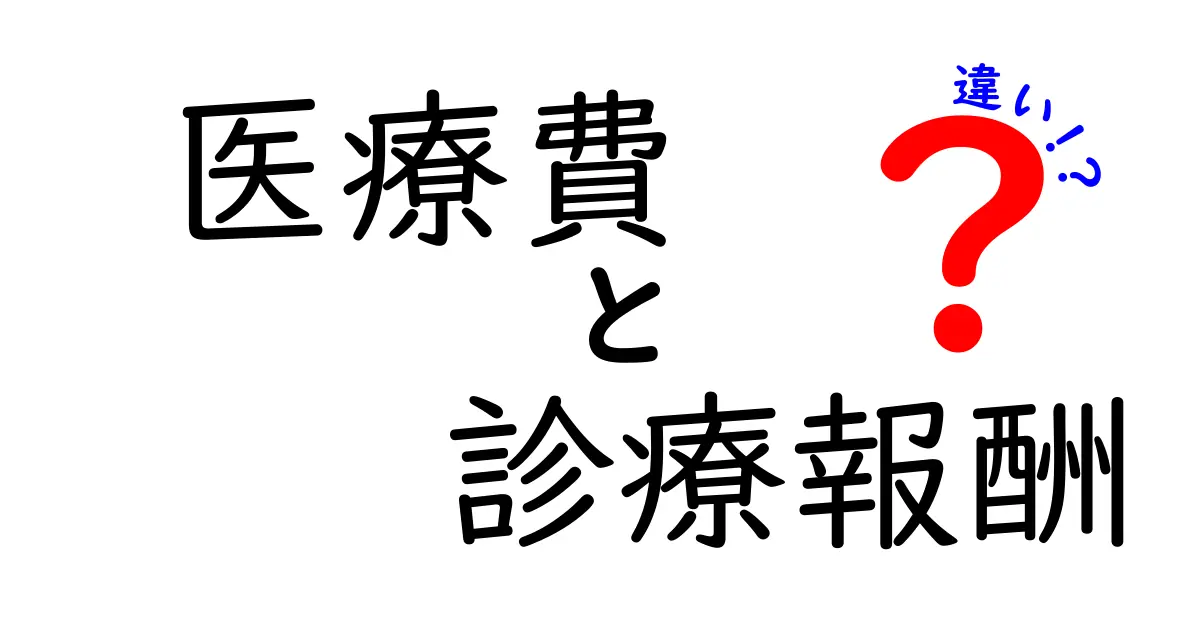
医療費と診療報酬の基本的な違いとは?
私たちが病院で診察や治療を受けるときに支払うお金があります。これが医療費です。一方で、診療報酬は、医療機関が国や保険者からもらう報酬のことをいいます。いわば、
患者さんが支払う料金と、医療機関が保険制度の中で得る収入を表しています。
これは似ているように見えますが全く別の概念です。その違いを理解することは健康保険や医療制度を正しく理解するのに役立ちます。
医療費は患者が実際に病院で支払う費用を指し、診療報酬は医療機関に対する公的な支払いの仕組みです。
例えば、病院で診察を受けて3000円払ったとします。この3000円が医療費です。そのうち3割が患者の負担で、残りは健康保険や国が負担しています。
医療機関はその保険負担分と患者負担分を合わせて、診療報酬として受け取っているのです。
医療費と診療報酬、それぞれの役割と仕組み
医療費は患者にとって身近なもので、「実際に自分が払うお金」と認識できます。
健康保険に加入している場合は、多くの医療費が保険から支払われるため、患者の自己負担は軽減されます。負担割合は一般に2〜3割ですが、年齢や条件により変わります。
一方、診療報酬は医療機関が提供した医療サービスに対して、「国が決めた料金体系」に基づいて支払われます。
この料金体系は「診療報酬点数表」と呼ばれ、年に一回見直されています。
医療機関はこの点数に応じて報酬を受けるため、診療内容が細かく点数で管理されているのです。
この制度により、医療機関の経営も安定し、患者は適正な治療を受けられる仕組みが成り立っています。
医療費と診療報酬の違いを表にまとめると?
| ポイント | 医療費 | 診療報酬 |
|---|---|---|
| 支払う主体 | 患者 | 健康保険組合や国(保険者) |
| もらう主体 | なし(患者が支払う) | 医療機関 |
| 内容 | 診療や治療にかかる費用 | 医療サービスに対する支払い |
| 料金の決まり方 | 診療報酬を基に算出される | 国が定める診療報酬点数表で決定 |
| 患者負担割合 | 自己負担部分(例:3割) | なし |
このように、医療費は患者側の目線での支払いのこと、
診療報酬は医療サービス提供者に対する国家的な支払い制度を指すものと覚えてください。
なぜ医療費と診療報酬の違いを知っておくことが大切?
医療費と診療報酬の仕組みを理解することは、医療制度の問題点や医療費の増加の背景を知るうえでも重要です。
日本の医療制度は多くの人が健康保険に加入し、医療費負担を軽減していますが、その支払いの根拠は診療報酬にあります。
医療機関が適正な診療報酬を受けるためには、国が設定した点数表に則りサービスを提供しなければなりません。
ここが適切でないと過不足が生じ、結果的に医療費の増減につながります。
また、患者として自分が支払う医療費にどんな費用が含まれているかを知ることで、無駄な検査や過剰診療を避ける手助けにもなります。
さらに高齢化が進む中で医療費総額は増加傾向にありますが、診療報酬の見直しが医療費削減に大きく関わっています。
つまり、両者の違いを知ることは医療の適正利用や制度改革について考える第一歩と言えるのです。
診療報酬の話になると、“点数表”がとても重要なんです。実は、医療機関がもらう診療報酬は、細かく決まった「診療報酬点数表」によって計算されています。この点数表は毎年見直されていて、例えば診察や検査、手術などのサービスにはそれぞれ点数が割り当てられています。点数が高ければその分だけ診療報酬が多くなる仕組みです。だからこの点数表を知っていると、病院がなぜこの値段なのか、ちょっとだけ理解できるようになるかもしれませんね。中学生でも、医療の裏側の仕組みが見える面白い話ですよ!
前の記事: « 医療費と社会保障費の違いとは?分かりやすく徹底解説!